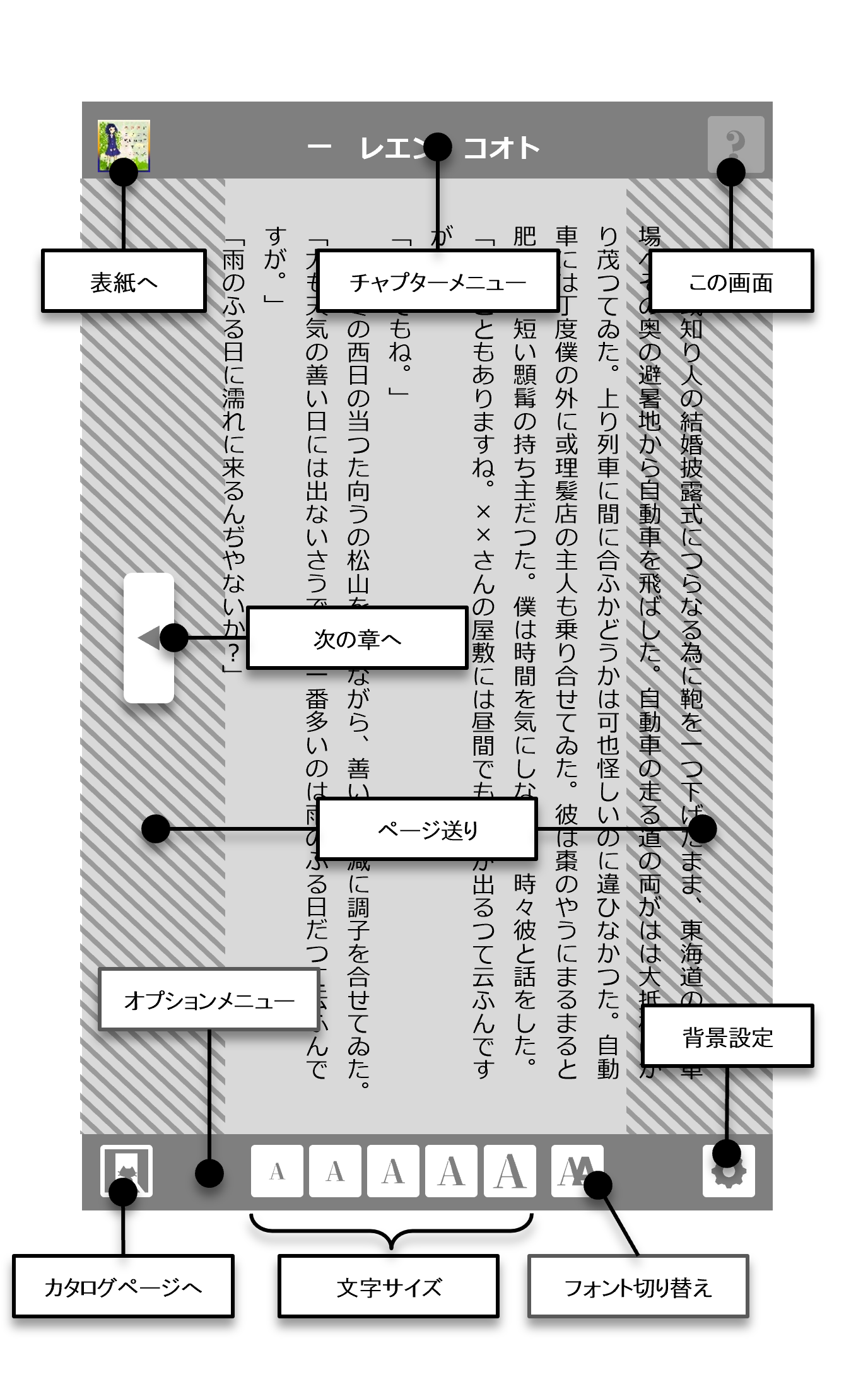- Ⅰ 西暦一三〇XX年・帰還
- 1 方舟
- 2 生き延びた姉弟
- 3 ランズボロー
- 4 新しい町で
- 5 遺品
- 6 根之堅洲國
- 7 私がいないと
- Ⅱ 西暦三〇九X年・人工天体オモダルの最後
- 1 ホタルの伝言
- 2 木星軌道
- 3 人工天体オモダル
- 4 戦闘任務
- 5 大気圏突入
- 6 地球統合軍
- 7 奈落にて
- 8 上昇転移
- Ⅲ 西暦三〇八X年・シチリアの夢
- 1 眼鏡と鏡
- 2 卵の穴
- 3 テアトロ・デレ・ステッレ
- 4 シチリアの夢
- 5 冬への扉
- 6 ひとの記憶
- 7 彩花へ、愛を込めて
- Ⅳ 西暦二八〇X年・ラグランジュ・ポイント
- 1 アルキメデスの少年
- 2 移民の歌
- 3 四条馬酔木亭
- 4 メダル
- 5 白いドレスの少女
- 6 支配とその偽装について
- 7 アヤカ28
- Ⅴ 西暦二〇三六年・アヤカシコネの末裔
- 1 風立ちぬ
- 2 いざ生きめやも
- 3 18人いる!
- 4 わたしの人生の物語
- 5 石と花
- 6 ボンベイ・タイプ
- Ⅵ 平成二十四年・リュシオール
- 1 的なもの
- 2 ふたつの道
- 3 押し入れのひと
- 4 暗いシリウス
- 5 テラリウムの陰謀
- 5 星と命
- Ⅶ 平成十年・カーテンのある部屋
- 1 鉢植え
- 2 問い
- 3 石の呪い
- 4 地球重力
- 5 永遠の光
- Ⅷ 西暦一三〇XX年・木花咲耶
- さらば、地球
- あとがき
- 一万年の旅を終えて
Ⅰ 西暦一三〇XX年・帰還
1 方舟
両手に
人工冬眠から目覚め、指先にまだ痺れが残るうちに姉のリヴェアから、「イグロダ大佐が殺された。タルエド中佐が反乱を起こしている」と聞かされ、イグロダ、タルエド、果たしてそれがだれだったか、記憶を手繰る間に姉は走り去り、直後同胞の手で捕らえられ、小さな資材庫に監禁された。
宇宙に向けて窓一つ空いた部屋で、廊下の奥に響く粒子銃の戦闘音を聞いた。金属質の反響がフレストの耳に届くたびに脳裏に浮かんだのは、単騎アークトゥリアンの基地に乗り込んでいった
大気圏突入まで、もう間もない。
姉は死んだのだろうか。
膝を抱えたまま顔をあげると、アラートが響いた。
直後、爆発音。
窓の外に目を移すと、エアロックが開き、大量の兵が捨てられる様が見えた。
死体を捨てたのか、あるいは、死体にすべく捨てたのか。なかにはヘルメットすらなく放り出されたものもある。風のない宇宙で、エアロックからの気流がブロンドの髪を複雑に踊らせる。そのそばにはヘルメットが舞い、動力線でつながれたヘルメットとその体は、まるで主星と衛星のようにくるくると互いに回りながら、他の星との衝突を繰り返した。フレストは思わず姉の姿を探すが、戦闘服のまま瞬時に冷凍された兵は、どれも同じプラスチックのフィギュアに見えた。
どの勢力とどの勢力があるかはしれなかった。だが仮に姉が破れ、命を落としたとしたら、自分を迎えに来るのは姉を殺した相手かもしれない。そこに現れる感情は、怒り、絶望、恐怖、いずれなのだろう。僕は、そのひとに跪き、命を乞うのだろうか。
フレストが力なく体を横たえると、船体はゆっくりと回転し、窓一面に地球を映した。外宇宙から訪れた侵略者の手を逃れ、宇宙に出て一万年、地球の環境は人工天体の落下によって破壊されていた。人工冬眠から目覚める頃には地球の異常気象は収まると言われていたが、一万年前――記憶のなかではつい先日――地球を飛び立つとき眼下に見た色濃い群青の海は、どこにも見えなかった。
一睡の後、扉が開いた。
フレストはその先に見えた戦闘服に身を固くするが、ヘルメットを取り、口元を覆う黒い布を下げると、姉リヴェアの顔が見えた。
「もうすぐ大気圏に突入する」
リヴェアは戦闘服を脱ぎながら捲す。
「ランズボローのすぐ近くに降りるけど、船体のコントロールが効いていない。こちら側は突入面になる」
「ランズボロー?」
ランズボローは、人工冬眠から覚めた折に地上に発見された都市、あるいは迷路のような巨大な構造物だったが、民間人であるフレストには知らされていなかった。
「人工の構造物。あるわけないんだけど。詳しくはあとで」
フレストは立ち上がり、拘束された両腕を姉に差し出す。
「ごめん。鍵がない」
「他の乗組員は?」
「全員死んだ」
「姉がやったの?」
「私がやったのは三人。あとはクライン。知ってるでしょう? 彼がドルフィーを使って――」
ドルフィーは、人類をサポートするために作られたアンドロイド。その歴史は長く、改良に改良を重ねた体躯はほとんど人間と同じに見える。
「――ドルフィーはぜんぶ停止してた。何者かが止めたんだと思う。それをクラインが」
「クラインは?」
「死んだ」
リヴェアは淀むことなく続ける。
船体が軋み、衝撃が足元を抜ける。
「大丈夫。Cブロックが飛んだだけ」
窓からはそのCブロックが折れ曲がり、灼熱してちぎれ飛ぶ様子が見え、次の瞬間、窓は消えた。窓だった場所はモニターになり、何かのリストを表示している。リヴェアはちらりと見て、「側面カメラ喪失。行こう」と、フレストに促す。
地球を脱出したその艦は、
人工天体オモダルは、オートマトン化したドルフィーによって集められた小惑星から成り、その直径は月の半分に及ぶ。それが落下した衝撃で地殻は破壊され、岩盤は津波となり数ヵ月に渡って地表を駆け巡る。その後の天変地異に関しては予測不能。それが収まるまで軌道上にて人工冬眠で過ごすと計画されたが、この作戦の成功を信じたものが、果たして何人いたか。事実、無事に一万年の眠りから抜けた艦は十に満たなかった。
各艦、打ち上げ後に艦内の資材を利用して順次冬眠槽を増設していったが、その間にトラブルに見舞われた艦も少なくない。搭載されたドルフィーによって一万年の間は保守されたが、大気圏外では遠宇宙より至るガンマ線バーストを避ける手がない。ドルフィーには自己修復・自己複製機能があるが、西暦八二XX年に発生した巨大なバーストは、8割の艦のドルフィーを一気に機能停止させた。助かったのは、ちょうどバースト源が地球の影になる位置にいた艦だけ。リヴェアとフレストが乗り込んだ艦「
他の方舟を見れば、気圧を失ったもの、駆動装置に異常を来したもの、あるいは覚醒することなく軌道を外れて太陽への落下を続けるものがある。残る方舟も無事に大気圏に再突入できる保証はない。
それでも、地球が負った傷に比べればまだ浅い。
地表にはもう海洋はなく、日本海溝などにわずかに海の痕跡が残るが、それすらも元の海ではない。かつての海は一瞬にして蒸発し、オゾン層を失った地表で、水は酸素と水素に光分解された。軽い水素原子は太陽風が持ち去り、もはや二度と地球の重力に捉えられることはない。地表では、地殻津波で顕になったマントルが吐き出した水蒸気が雨となり、わずかな海を作っていたが、そこにはかつてあった生態系はなく、その海の組成すらも知れない。
人類の前には、もはや絶望しかない。ただ朗報と言えるのは、緑のない大地に、酸素を含んだ大気があることだった。もちろん、地球帰還の前には、それも壁となるのではあるが。
灼熱した機体が薄い雲を抜けると、駆体の可動翼が上がり、減速の最終段階に入る。が、生きている可動翼はもはや二割にも満たない。機体は安定を失い、回転を始める。やがて姿勢は反転、リヴェアとフレストはシートベルトをしたまま宙吊りとなり、次の瞬間、減速用のパラシュートが放出され、その勢いで大きく体を揺らされる。時間差で7発。だが本来なら、20は下らないパラシュートが開くはずだ。艦内にアラートが鳴る。リヴェアはシートベルトを外し、コントロールルームへ走る。フレストは、両手を拘束されたまま姉の背中を見送り、静かに目を閉じた。
2 生き延びた姉弟
パラシュートに引かれてブロックの一部が破砕、分離した。この衝撃で機体は大きく前傾し、艦内にはアラートが響き合う。いくつかのケーブルはショートし、通路の奥には炎も見え、機体は大きく揺れ、軋みを上げている。
リヴェアは斜めになったフロアを駆け戻ると、奥へと滑り落ちるようにしながら、フレストのシートにぶら下がってレバーを引き、ベルトを外した。そのままシートから滑り落ちるフレストを抱きとめて、腰のあたりにあるピンを抜くと、背中につけたウインチが二人の体を巻き上げる。
「ちょっと待って! なにこれ!」
「いいから、時間がない!」
爆発音に続き、防爆扉が閉まる。
大気圧の低い空にはまだ地表から巻き上げられた粒子がとどまり、
リヴェアとフレストは、直前に脱出ポッドを利用して本体を離れたことで、ぎりぎり難を逃れる形にはなったが、そちらもおおよそ不時着と言えるような生易しい着陸ではなかった。かつて太平洋だったそこには、見渡す限り冷え固まった溶岩しか無い。リヴェアがどれほど優れた軍人でも、岩場への着陸訓練を受けていたりはしない。それをいかに避けるかを叩き込まれるのだ。機首を上げ、失速させながら、ポストストールマニューバを利用して対地速度を0に落とし、パタンと機体を倒せば軟着陸完了と考えていたが、20ノットまで落としたところで尾翼が接地。あとはゴロゴロと転がるしかなかった。
二人はなんとか脱出ポッドから這い出すが、フレストの手首に掛けられた拘束はそのまま。推進剤の甘い刺激臭が立ち込める。機体の爆発を避けて逃げるにも、足元は凹凸の激しい岩場で、リヴェアは幾度も弟の体を抱きかかえ、岩を上り降りした。弟の体は、姉の背を15センチは上回っていたが、軍では40キロの荷物を背負って移動することもある。自走できる弟は、まだ楽だ。
フレストの拘束具は、管理端末を用いればリヴェアにも外せたが、一万年も前に作られたデバイスだ。まだ軌道上にあった頃、小隊の8人にも確認したが、まともに動作したのは2台、ドルフィーの操作に用いているうちに、隊員とともに宇宙の塵になった。おかげで、いまいる場所を確認する術もない。計画通りなら南海トラフの西端のあたりだ。
大陸と山脈のほとんどは、その原型をとどめていない。いくつかの海溝は痕跡を残し、その裂傷のように残る黒い筋を照合し、いまの座標を知ることはできたが、かつて二三・四度傾いていた地軸は、いまでは七九・九度傾いている。もはや緯度も経度も意味のない数字だ。いまの地球は公転面を転がるように自転している。おかげで地球のほとんどの土地では、半年の昼と、半年の夜が交互に訪れる。二人が降り立った場所はちょうど昼の期間だったが、何ヵ月かしてその季節が終われば、長い夜が来る。太陽光を主なエネルギー源とするリヴェアたちに、その夜は厳しい。
フレストは両手を拘束されたまま不平は漏らさなかったが、リヴェアは少し焦りを覚えた。足元の覚束ない岩の大地には、
二人が幸運だったのは、セミホバータイプのビークルを見つけたことだろう。それがうまく稼働してくれたお陰で、道が拓けた。車載の通信装置も作動し、小さなデバイスも探せるようになった。まずは生きている端末デバイスを探し、フレストの拘束を解いた。それに2日は費やしただろうか。ただ、その間に十分な量の携帯食を拾得することができたので、収支はプラスになった。二人にタイムリミットのようなものがあるとすれば、数カ月後に訪れる夜ではなく、目の前の飢えだった。
地殻津波によって溶けた岩石が固まっただけの大地には、まだ草木一本なかった。地上には明確な川の流れもなく、雨はただ岩の隙間を高きから低きへと流れ、ところどころに水場を作る。概ね硫黄の匂いがした。あたりには土も砂もない。ましてや植物など。植物が生まれるには、まず川ができて、岩を侵食し、砂利を作る、その数億年の時間が必要だった。
ビークルには樹脂製のタイヤがあったが、岩場での走行でたびたびパンクした。自己再生性の素材が用いられてはいたが、一度パンクすれば二時間は樹脂の再生を待つ。ホバー走行は地面の凹凸が激しく、ローターの
「酸素はどこから来てるんだろう」
かき集めた携帯食のひとつを食べながら、フレストが聞いた。
「海の水がぜんぶ蒸発してるから、分解されて酸素だけ残ったんじゃない?」
「そういうものなんだ」
「わかんないけど」
時計はあったが、昼間ばかりがずっと続く中で、時間の感覚は消えていった。
草も土もない大地で、二人が休めるのはビークルの中だけ。着替えもなく、シャワーを浴びることもなく、室内には饐えた人間の匂いが染み付いた。お互いに嗅ぎ慣れない匂いを放ったが、やがてそれにも慣れ、浄水装置を発見したのは、地上へ降りて7日が経った頃。ようやく汗を流すことができたが、その頃には皮膚のあちこちに発疹があった。肌はリヴェアのほうが弱く、背中にまで広がった発疹をフレストに見せた。二人は医療キットにあったクリームを塗ったが、気休めに過ぎなかった。
「ウイルスって生きてると思う?」
首筋にクリームを塗るフレストの顎には、まばらに髭が伸びていた。
「ウイルスは生きてるかもね」
「細菌は?」
「さあ。滅亡から一万年だし、水の中には有機物もあるっぽい。未知の微生物程度のものはもう、生まれてるんじゃない?」
現実には、その生成には億の年月を要するが、二人の想像が及ぶことはなかった。
「死ぬのかな、僕たち」
「まあ、遅かれ早かれ」
姉のリヴェアのほうが割り切りが良いのは、軍人として幾度も死線を超えてきたから――と言えばわかりやすい話になるが、リヴェアはただなんとなく、暗い話を避けたいだけだった。
空は白く、陽の光は森の木立を抜けるように斜線を落とし、太陽はぼんやりと散乱して見えた。時折その白い空に雲が沸き立っているらしかったが、視認できず、雨は唐突に降り出した。昼間が続くせいか気温は常に30度を超え、紫外線も強い。雨はシャツに纏わった熱気を冷ましはしたが、その雫は肌の上にチリチリとした痛みを残した。おそらく酸を含んでいる。フレストはまだこの雨に耐性があったが、リヴェアの肌はすぐに赤く炎症を起こした。緩慢に迫る死は、目前に迫る敵影よりも強い不安を二人に与える。これならまだ、武装したアークトゥリアンの群れに遭遇したほうがいい。
そうしてキャンプ生活が続くうち、フレストは姉の二の腕のあたりに頭を寄せて眠るようになっていた。最初はただの偶然だった。少し早く目を覚ましたリヴェアも、それを払うことなく、白い空を見上げていた。弟には少し身勝手なところがあり、ぶつかることはあったが、このところお互いに言葉を選ぶようになっていた。遠慮は、他人だからするものだと思っていた。だけど逆だった。遠慮しているうちに、弟は他人になっていた。彼の肉体はもう、昔のように自分の一部ではない。だけどその寝息を聞いていると、精神はまだ従属しているかに思える。時折、フレストはひとりで起きて、自らの突出した器官を弄ぶことがあった。リヴェアも自らの切り欠いた器官を弄んだが、フレストのそのときには、細かく揺れるビークルのシートで、寝たふりをしていた。二人の血の繋がりが、適度な壁を作っていた。不意に振り向いて、「何してるの?」とでも聞けば、弟はどんな焦り方をするだろうと、リヴェアは考えることがあった。そしてきっと、いつか「超える」のだろうと。
大気の循環もなく風も凪いだ星の上で海溝のそばまで来ると、遠い地球の裏から巡り来ては吹き上げる夜の空気があった。フレストが覗いていた双眼鏡をリヴェアに渡すと、その底に新しい海洋の萌芽が見える。
きっとあれが、「夜」なのだろう。
空には新しい小さな月が生まれ、ときに大きな月に寄り添った。小さな月は、月の軌道と交差した楕円軌道を巡る。それは人工天体オモダルの衝突によって吹き上がり、天へ駆け上った溶岩の一雫だった。あるいはそれは、人工天体オモダルの新しい姿なのかもしれない。月には数多の新しいクレーターがあり、小さな月はまだ冷え固まることもなく、白い空に浮かんで仄明い光を灯していた。
3 ランズボロー
「ランズボローまで、約12キロ」
海溝から吹き上げる風に乗ると、予想外に早い時期にそこに着いた。そこにはあるはずのない人工の構造物がある。旧地名で言えば、別府沖。本来なら豊予海峡を超えたはずだが、その痕跡は残っていない。いまいるのが、かつての海の底なのか、山の上なのか、それすらもしれない。岩肌には起伏があり、ビークルを停めた場所からランズボローを見渡すことはできなかった。リヴェアには視線が通る場所での待機はためらわれた。もちろん相手が文明を持った敵であれば、ここに到着するまでにとうに発見されている。だが、軍人の性だ。小鳥が茂みに身を隠すように息を潜め、ビークルには、ハミングバードと呼ばれる小型のドローンが装備されていた。
ハミングバードはハチドリに似せられ、太陽光だけで自律的に動作した。ドルフィーと同じように自己再生・自己複製機能を持っている。つまりシリコンポリマーを主成とする生体アンドロイドだった。メンテナンスフリーで、リヴェアたちには馴染みが深い。ここへ来るまでに12体が用意された。面白いことに、音声でコマンドを与えると、鳥たちは卵を産んで、自分のコピーを作った。これは人型のドルフィーも同じで、自ら遺伝子に改良を加え、単体で妊娠、出産し、進化する機能を持っている。
「問題は端末の方」と、リヴェアはノート状のデバイスの表面を袖で拭う。画像の入出力を行う二次元デバイスだが、旧世代のモノポール・ニューラル・ユニットを採用しており、安定性が悪い。もちろん、卵も産まない。それでも、音声と映像と両方の入出力が生きている。
「鳥に擬態する必要はない。――鳥なんかいないからね」
リヴェアは、ハミングバードにコマンドを伝える。
「まずはランズボローの全容が知りたい。特に武装、それから、住人。あとは、入り口の安全性。1番機から3番機まではディティールを調べて。画像と音声はリアルタイム送信。匂いも。組成を伝えて」
フレストは端末を眺めている。端末には、ハミングバードから見たリヴェアの顔が12面映されていた。
人工天体オモダルの投下によって地殻が破壊されることは推測の範囲内、作戦の直後からデータは取られていた。しかし、投下から二百年は蒸発した岩石による厚い雲が地表を覆った。明確にランズボローの記録が残るのは、西暦四六〇〇年代。オモダル投下から千五百年を経たあとだ。その記録が正確ならば、ランズボローが生まれて八千年が経っている。
ハミングバードが飛び立ち15分ほどして、端末にランズボローの外観が映し出されると、二人は息を呑んだ。水平に整地されたグラウンドから直線的に立ち上がった構造物が、中空を走る梁と幾何学的に接合し、複雑な構造を描き出す。そこに映されていたのは、明らかな人工の建造物だった。
ランズボローの外に参道のようなものを捉えた機体があり、その先には城門が見えた。門の手前には何本もの尖塔が立つ広場があり、周囲には左右対称に階段状の段差が組まれている。ランズボロー全体としては、城塞都市の様相を呈し、上空からはあたかも複雑な魔法陣のように見える。あるいは、歯車で描く花模様を重ねた点対称な幾何学図形。直径は十数キロほどだろうか。そこかしこにフラクタルな自己相似形が見える。しかもその構造は二次元ではなく、三次元。
「2番機、もっと寄って。なかを見せて」
リヴェアが指示を出すと、ハミングバードのうちの一機がランズボロー内部へと侵入。
「アークス?」
フレストが問う。
アークス、つまり、アークトゥリアンの施設か、と。
「違うと思う。マヤの遺跡っぽい」
「あ」
フレストが小さく口にした。
「どうしたの?」
「8番機。日本家屋が映った」
「日本家屋!?」
急ぎ、8番機に指示を与える。
「8番戻って! 日本家屋へ!」
8番のカメラがパンすると、そこにはたしかに日本家屋らしきものが映っている。
「でも、変。おかしい」
要素はたしかに日本家屋だが、それがフラクタルな構造の一部をなしている。
「壁に沿って先を見せて」
そしてその日本家屋の壁らしき構造物は、まっすぐに伸びて防波堤へと連なり、大小様々のテトラポットを装飾的に配し、また別の文明の建造物へと接続している。他の部分も概ね同じ。かつて地球で見られた様々な文明がパッチワークされ、立体の超対称構造を作り出している。
7番機の映像枠が点滅する。サムネイル画像にはひとのシルエットがある。
「フォーカス、7番」
拡大すると、人物の姿が浮かぶ。
「距離8メートル。向こうはハミングバードに気づいてる」
リヴェアの声が緊張する。
ちらりとカメラに映った瞳から、アークトゥリアンでないことは明らかだった。アークトゥリアンの眼球はガラスのように透き通り、眼窩の中にあっては、全体が黒く見える。ハミングバードが映し出しているのは人間か、それを模して作られたドルフィーかに絞られる。
「ドルフィー?」
「わからない。耳を見せて」
地球で活躍するメジャーなドルフィーには耳たぶがない。すぐに7番の機体がアップでその映像を捉える。耳たぶはあった。
「人間?」
「わかんない。体温と心音を」
データが送られてくる。体温、心拍数、呼吸速度、代謝率。
そして、リヴェアの手元の端末が推定結果を表示する。
――識別:オモダル型ドルフィー・K81系
「オモダルの? 生き延びたってこと?」
フレストは驚きを隠せない。
「まさか……そんなことって……」
地上に落とされ、地殻津波に飲まれ灼熱の溶岩となったオモダルのドルフィーが、生存しているはずがない。
対象として選ばれたドルフィーが、カメラに指を近づける。
「擬態して」
リヴェアが指示をすると、ハミングバードは鳥を真似、ドルフィーの指先に留まった。
ランズボローから2キロの地点までビークルで移動した。岩場が続けば、この距離でも徒歩の移動に丸一日は費やす。だが、石敷きの参道があった。周囲を警戒し、センサーによる自動反撃を考え武装は持たずに歩いた。リヴェアは足がすくむ思いがしたが、平然と歩くフレストの手前、それを表には出さなかった。
「休めるかな」フレストが聞いた。
「40人の盗賊がいるんだよ」リヴェアが答える。
その間も、ハミングバードに指示し、情報を集めていた。
「人間はいるかな」またフレストが聞いた。
「えっ?」
「40人の盗賊の中に、人間はいるかな」
「いたらどうするの」
「いたら、やばいね」
フレストの言葉にリヴェアは端末を見たまま、何も答えない。
「姉がやばい」
フレストは、呑気に歩きながら、言葉を付け足した。
「私のどこがやばいのよ」
フレストにしてみれば軍人の姉は、決断力はあるが、やや血の気の多い人間だった。またリヴェアから見たら、フレストは凡庸で頼りない子どもだ。その頼りない子どもが、自分よりも大きいのだから始末に負えない。手枷のないフレストはきょろきょろとあたりを見渡しては、欄干状に並ぶ構造物に手をのばす。音のない参道を歩き、少しずつ間近に迫ってきた城門は、凱旋門に似ていた。
両翼に大きく城壁が張り出し、左右対称の構造が見られる。このあたりは概してヨーロッパのロマネスクからゴシックの様式が入り乱れているようにも見えたが、近くでそのディティールを見ると、外見とは無関係の構造によって再現されているのがわかる。様々な写真を組み合わせて描いたモザイク画のように、ミクロとマクロとで様相を変える。また、その構造のなかに、外観と同じものがミニチュア化して再現された部分もあった。おそらく建物全体が、羊歯の葉のように自己相似構造を持っている。遠目に凱旋門に見えた建物も、間近で見ると別のものに見えた。遺跡で見られるような柱も垂直に立つとは限らず、それが鋭角をなして梁と交わり、その梁の終端は騙し絵のように階段になっている。万華鏡を覗くよう。見上げていると、天地の感覚が失われる。
現れる景色に気を取られていると、ふとひとりの住人とすれ違い、リヴェアの緊張は瞬時に頂点に達する。が、向こうはこちらに興味を示すことはない。リヴェアは反射的に、腰にあるはずの銃に手をやっていた。
「やばいね、姉」
フレストが涼しい声で言った。
「うるさい」
二人目、三人目と、視界に入るたびに、リヴェアは身構えたが、何事もなく、四人目の頃になってようやくリヴェアの緊張も解ける。
「声をかけてみる?」
フレストは呑気なものだった。
「ああ。まかせる」
徒労感の混じったため息をついて、リヴェアは答えた。
「こんにちは」
歩いていたドルフィーに、フレストは後ろから声をかけた。
ドルフィーに男女の区別はないが、概ね女性的に見える。それにほとんどのドルフィーには子宮が備わり単為生殖が可能で、他者の卵を胚発生させる物理的な手段を持たない。つまり一般的には女性、あるいは両性具有ということになるのだろうが、彼らは自らの意志で遺伝子パターンを操作する。そのために必要な情報は会話から入力されるのだから、それが生殖に当たる。人間のような炭素系生物が考える男女という枠組みには収まらなかった。
彼はゆっくりと振り向くと、「こんにちは」と応じた。
どうやら、言葉は通じるらしい。
「フレスト・プローンです。はじめまして。こちらは姉のリヴェア・プローン。お話を伺ってもよろしいですか?」
「かまい、ません。私は、アン、シャーリー」
彼は戸惑いの表情を浮かべたあと、たどたどしく自己紹介をすると、微笑んだ。
「この町へは初めて来ました。ここはなんという町ですか?」
リヴェアが所属していた部隊には、一般の兵卒としてのみ、武力に特化したタイプのドルフィーが配属された。リヴェアにとってのドルフィーはそれが全て。任務に忠実で機械的な反応を返すものしか知らない。だが、一般的なドルフィーは人間と同じように、それぞれの個体にそれぞれの個性があった。基本的には、炭素原子をケイ素原子に置き換えただけの構造だから、人間と変わるはずはない。
「町は、ここにしか、あり、ません。なので、他の、町と、区別、する、ための、名前は、あり、ません」
ドルフィーが返したのは、文節をひとつひとつ区切ったぎこちない言葉だった。
リヴェアたちとこの町の間には、一万年の時間の壁がある。一万年あれば言葉は変わる。ドルフィーの彼がぎこちないのではなく、リヴェアたちの語彙が足りない。向こうにしてみれば、犬が話しかけてきたようなものだ。
リヴェアにしても、フレストにしても、聞きたいことは山のようにあったが、こんな調子だから要領を得なかった。たとえば「この町は、いつ、どのようにして生まれたか」と聞いても、それに答えた単語の多くは、リヴェアたちの語彙にはない。語彙がないというのは、その概念がないことを示す。それはたとえば、千年前のひとに「テレビゲーム」について説明するのと同じ。まず、テレビとは何か、なぜ箱が光り、絵が現れるのか、その絵に対して何をするのか、ゲームとは、キャラクターとは、光る箱を相手に何を競うのか、その説明は困難を極める。
そこで得られる情報は、ほとんどなかった。聞いたのが、「トイレはどこですか?」「良いお天気ですね」ならば、まだ有益な返事が返っただろうが、「この町はどのように生まれたのですか?」だ。一万年前の世界から現れた縄文人に同様の質問を受けても、現代人には何も答えられないように、フレストとリヴェアも何の答えも得られなかった。
最後にフレストは、
「この町に住むことはできますか?」
と、尋ねた。
「ええ。メサに、役場が、あります。そちらで、手続きを」
アン・シャーリーが去ったあと、二人は改めて町を見渡した。
中央は高台になり、おそらくメサというのはそこのことだろう。その斜面にはケーブルカーがあった。
4 新しい町で
「この町に住むとしてだよ」
ケーブルカーでメサへ向かいながら、リヴェアが尋ねた。
「食べ物はどうするの?」
姉のその問にフレストはしばし考えたあとで、「聞いてみるしかないね」と答えたが、実際にそれしか手はなかった。
「ていうか、ケーブルカーって」
「初めて乗った」
ドルフィーはそもそも炭水化物を摂らない。それ以前に炭素が必要ではない。必要とするシリコンは砂から取り込める。初期のモデルは二酸化ケイ素、すなわち乾燥剤にもなるシリカからしか取り込めなかったが、リヴェアたちが知るモデルは石英やガラスからでも吸収できた。要はそのへんの岩石を食べれば飢えはしないので、いまの地球にはうってつけの存在だ。かたや人間は、炭素を必要とする。見る限り野菜らしきものも、肉らしきものもないいまの地球は、人類の暮らしには向かない。
「大気中の二酸化炭素から作れないかな。肉とか野菜とか」
フレストはそう姉に尋ねるが、実際に不可能ではないので、リヴェアはそれが本気なのか冗談なのかはわからなかった。
「魔法で?」
「うん。姉なら使えるでしょ」
こちらは冗談だろうが、口調は変わらない。リヴェアは口の端で笑って、
「まあな」
と、答えた。
役場を探すのは少々手間取った。
「役場」という言い方も、さきほどのドルフィーが気を回した表現であって、ほかのドルフィーに同じ言葉で尋ねても、通じるとは限らなかった。
共通の語彙は思ったよりも少ない。いきおい、
「わたし、ここ、住みたい」
と、必要な単語だけ伝えるようになり、まさに一万年前の縄文人に先祖返りしていた。
また、そこで見つけた役場も、人間の感覚からすると少し様子が違った。人間の役場のように自分から窓口に出向く必要もなく、建物に入ると向こうからコンタクトしてくる。サポートが不要であれば断ればいいし、目的を告げると、その場で適切なサービスが得られる。窓口という概念もなく、すべてのドルフィーがすべての業務をこなした。
そもそもドルフィー同士には通信機能が備わっており、役場のような施設は不要だった。あらゆる手続きは部屋にいながら、脳裏に思い浮かべるだけで完了する。ただ、ドルフィーのなかには通信機能を持たぬもの、視覚や聴覚を持たぬものがいたし、あるいは不意に訪れる古代人の類もあって、役場はそれらのセーフティーネットになった。それに何よりも、歩くこと、ひとと逢うことが彼らの楽しみのひとつだった。時間はいくらでもある。彼らに必要な一次リソースは、砂と光。それが無限にあるのだから、二次リソース、三次リソースも無制限に手に入る。「時は金成なり」などという言葉も生まれることなく、この社会が築かれた。
かく言うリヴェアとフレストの両親も「役場」の仕事をしていた。この頃の人間の言葉――と言っても、一万年前だが――では「
人間の担う公務は二つあったが、もう一方は「統合(Integration)」と呼ばれ、実働を伴う保安・警備が主任務とされた。これは店のガードマンから、警備員、警察、軍隊など、さまざまな規模のものを含み、これに従事するものは「
この制度にもまだ改善の余地はあったが、戦争の前線に人間が立つことが、抑止力になったことも事実だ。一時、血なまぐさい戦争は殺戮マシーンたるドルフィーに担わせるという方針が立ったこともあったが、結果としては戦禍の拡大を招いた。殺戮マシーン同士が戦うのだから人間は安全だろうと考えられたが、人工知能を搭載した殺戮マシーンは効率よく補給を断つことを優先し、挙げ句ドルフィー同士は戦わず、後方で指示を出す人間を襲うようになった。考えてもみればドルフィー同士には戦う根拠がない。当然な話ではあるが、人類は実際に銃口を向けられるまで、それに気づかなかった。
「前線で戦え。背後の人間を襲うな」と、プログラムすれば良いだけのことだが、二国間で戦っているときに、一方だけそんな処置を下すわけがない。国連の調停でなんとかそれに近い状態に持ち込んだこともあったが、そうすると彼らは無駄に弾薬を消費する戦闘を避け、シミュレーション結果に応じて自分たちの数を間引き、結果だけを報告した。兵力二万五千の今川義元軍が、同三千の織田信長軍に戦闘を挑むと宣言した時点で、アンドロイドは自動的に戦況をシミュレートし、報告するのである。
「今川軍三千、織田軍二百の損害が発生し、織田軍が勝利しました」
一か八かの戦いをするのは人間だけで、完璧な知性を持ったドルフィー同士は、すべての個体が最善手を選択する。無駄な戦いも、無駄な搾取もない。
西暦二千年代の後半になると、地球にとって最大の脅威は人類だと言われるようになっていた。後期に出現したドルフィーは、炭素をシリコンに置き換えただけで人間とまったく同じ分子構造を持ち、人間と同様に個性と人格を持っていたため、もはや人間の存在そのものが不要という思想も生まれた。フレストとリヴェアの時代には、教科書にも書かれた話だったが、――と言う説もあります――と続き、決して、――よって、人類は滅ぶべきだと言われています――と帰結することはなく、――これが現人類の課題と言えます――と凡庸な言葉で結ばれていた。
最後に人類に残されたのは、ドルフィーの創造主であり、管理者であるという誇りだけ。――このように、論理的に行動するドルフィーを使役し、人間の幸福を追求するのが、私たち人類の使命なのです――そう書かれた教科書の古臭い一文は、やがて人間同等の理性を獲得したドルフィーたちにも読まれ、苦笑されるようになった。古い時代の彼らの錯誤によって、いまだにドルフィーたちは辛酸を嘗めさせられているのに、それがまだ教科書に載っているのだ。
奇しくもフレストとリヴェアは、それぞれ理官と行官だった。「ドルフィーは管理すべきもの」という思いは行官に根深く、リヴェアもその例に漏れなかった。もちろん弟のフレストにしても、ドルフィーが使役される側であるという認識に相違はなかったが、具体的なプログラム作成やリサーチに於いては、共同で作業する仲間のような感覚があった。
だけど、この町では、何もかもが違った。
役場はドルフィーたちのためにあり、ドルフィーは使役されることなく、自らの生活を送っている。人間の幸福のためではなく、ドルフィー自身の幸福のために。リヴェアはこれに違和を感じた。その目に映ったのは主体としての人間が不在で、殺戮と性欲処理を担う道具だけが生きる世界だ。その世界にはなんの価値もない。だが、その思いは言語化されることなく、胸のなかに淀んだ。
その、役場にて、二人は部屋を斡旋してもらった。部屋だけではなく、炭素系の食事も用意されるという。労働の必要もない。なぜならば――という、その理由もない。それが常識なのだと説明を受けた。
フレストは、姉とはそれぞれ別の部屋を探すつもりでいたが、リヴェアが反対した。リヴェアにとって、この町はまだ敵地だ。少なくとも、この町がだれによって、なんのために作られたかがわかるまでは。
5 遺品
「寒い寒い」
しんしんと星の降る暗い夜の底で体を震わせながら、リヴェアが戻ってきた。
ビークルには暖房があったが、夜の空気で冷え切った姉の体はガタガタと震えている。あたりには雪も氷もなく、ヘッドライトが円錐に切り取るマイナス30度の大気の中に、ミクロな氷分子が煌めいて見えた。
「何かみつかった?」
「なん…も。生存者もいないし。ないも。なんにも」
姉は震えながら、「なんにも」という言葉を噛んで、二回言い直した。
ランズボローに暮らし始めて十日ほど経った頃。新しいビークルを調達して、二人は別の方舟の不時着現場まで足を伸ばしていた。ランズボローからは遠く、ちょうどインド洋を超えたところにあたり、そこは夜だった。
「貸して」
リヴェアはフレストのブランケットを引っ張って、その片端を自分の肩にかけた。
「いいよ。こっちに来ても」
フレストが促すと、リヴェアは「へへ」と笑って、フレストのシートに移り、体を重ねた。防寒着に包まれた体は、お互いの肌を温めることはなかったが、深部にある熱はゆっくりと互いに伝う。
「遠のいたね。人類再生の夢が」
姉の体を抱きとめながら、フレストが言った。
「そうだね。でもホッとしてる」
リヴェアは羽根で膨らんだダウンを沈ませるように、ゆっくりと体重を預けた。
「どうして?」
「どうせ殺し合いになる」
「まあ。姉ならそうなるね」
車のなかだというのに、息は白かった。
「暖房足りてないよ」
「うん。がんばる」
「あなたががんばるの?」
フレストは姉の背中をこすり始め、「くすぐったい、やめて」とリヴェアもフレストの体をこすり始めた。車体が揺れると、暖房が思い出したように暖気を吐き出し、ビークルの窓は蒸気に曇った。
ひとしきりじゃれあって、弾んだ息を整えると、リヴェアはフレストの頬を親指の腹でぎゅっと引っ張って、「もう帰る?」と尋ねた。
「オートパイロットれ、どろくらいかかるかな」
頬を伸ばされたまま、フレストが返す。
「8時間くらい?」
そう言いながらリヴェアは、わずかに露出したフレストの頬に自分の頬を重ねた。
「ここ、温かい」
キスしたかった。どんな冗談を言いながらなら許されるかと、たびたび考えた。
リヴェアが生まれたときにはもう、人類はアークトゥリアンと戦争をしていた。こうやって自由になったのは、初めてだった。弟と過ごす時間は楽しかったが、だれとも戦わない暮らしは、自分の価値を失うようで怖かった。人類の遺伝子を持っているのは、もう自分と弟の二人しかいない。何もかも失って、最後に残った遺伝子ふたつ。それに価値を与えるのも、禁忌を訴えるのも、この世界にもう二人しかいない。
オートパイロットでランズボローを目指す車内。リヴェアはブランケットに包まって、タブレットを眺めていた。タブレットは思考を読み取って、文字にする。自動的に現れる文字を読んでは、いくつか消して戻って、またその続きを文字にした。
だれもが幸福を求める。
だけどその到達点は、みんな違う。
一斉に歩き出せば、おのずとぶつかる。
幸福にたどりつけば、その点は消えて、また別の点が光りだす。
ひとはまた歩く。
そしてまたぶつかる。
リヴェアとフレスト、二つの星は、お互いの周りをくるくると回り続けていた。
「緋咲准尉のことはごめん」
朝が来る頃、リヴェアは呟くように言った。
「急になに?」
緋咲准尉。緋咲アヤカ。人工天体オモダルのパイロットだった彼は、アークトゥリアンとの戦闘で傷ついて、地球へと逃れて来ていた。炎上する機体をフレストが発見し、その近くに身を潜めていた彼をリヴェアの部隊へと案内した。
「彼女を船に乗せられなかった」
リヴェアは無意識に「彼女」という言葉を使ったが、男女の関係のない場面では違和のある言葉だった。
「姉のせいじゃないよ。本人もそれでいいって言ってた」
窓の外を見たまま、フレストは答えた。
リヴェアは次の問を、少し迷いながら、
「好きだったんでしょう?」
口の先に押し出した。
地球とオモダルの間に軍事協定はあったが、少尉という立場でオモダルの兵を編入することはできなかった。手続きは進めていたが、オモダル投下作戦の混乱のなか、連絡は遅れ、方舟に乗せることができなかった。
「そういうのでもないよ」
少し間をおいてフレストは言ったが、本音ではない。フレストが民間人でありながらずっと前線に留まったのも、緋咲アヤカがいたからだ。
「じゃあ、なんで町に帰らなかったんだよ」
「うん。ごめん」
人工天体オモダルの落下が迫るなか、緋咲アヤカ准尉は、単独でアークトゥリアンの基地へと乗り込んでいった。
リヴェアは拾ってきた通信機を部屋に置いて、方舟の救難信号を探っては、探索にでかけた。だけどどこへ行っても、生存者はない。やがて人類はもう自分と弟の二人だけだと確信するようになるが、それでもなお、リヴェアは主なき救難信号を拾い続け、それを口実に探索に出た。正直、リヴェアはランズボローに留まりたくなかった。
フレストは違った。先日は、北京だったあたりに墜落した方舟をみつけ、その遺物を収集に行ったが、その探索も4度目になる頃に、フレストはついてこなくなった。当然の判断だ。焼け跡にはもう、何もない。北京に降りた艦は、
銃を拾い上げて、銃把にゆっくりと掌を添わせると、軌道上の
火災に見舞われたビークルから、燃え残ったネックレス、ツールケースと手に取って、
「ほら。これぜんぶひとが生きた記憶なんだよ」
と、フレストに見せるつもりでカバンに入れた。
その視界の隅、一体の球体関節の人形に目が留まり、拾いあげると、
――助けて! お父さん! 助けて! 助けて!
と、録音された少女の叫び声が再生された。
日差しは6月に似ていた。
本当は何月の何日に当たるのか。地球の公転速度を計測しなおす術もなく、脱出艦に備わった原子時計はガンマ線バーストの影響で止まっていた。日や月、あるいは年も、有効桁数の水面下に沈み、いまが何月の何日かも、意味のない数字となり、リヴェアが部屋に戻ると、見知らぬドルフィーがフレストと肩を寄せて、音楽を聞いていた。その後姿を見て、血が泡立った。
「だれ? お客さん?」
尋ねると、フレストは振り返り、
「うん。家庭教師」
の声が返った。
――家庭教師。
それもドルフィーが使った便宜的な言葉だった。
リヴェアとフレストを、この町の生活に溶け込ませるために、いろんなことを教えるボランティアが、三から四人、代わる代わるに部屋を訪ねたが、リヴェアはまるで躾けられる犬になったようで不快だった。
「はじ、め、まして」
振り返ったドルフィーは、緋咲アヤカに似ていた。
「ふうん。利口な犬になってね」
そう言い捨てて踵を返すと、世界がぐにゃりと歪んだ。
部屋は騙し絵だった。しつらえられた階段は、一階の別の部屋につながるだけで、階段としての意味は持っていない。その壁面に無限階段の浮き彫りがあり、まるでひとの正気を奪うかのように、階段はそこに吸い込まれている。油断していると、すぐに絡め取られる。目眩に襲われ、急いで自分の部屋に戻り、吐いた。
振り返った「家庭教師」が、緋咲アヤカの顔で思い出された。
――民間人を船に乗せたんだ。緋咲を乗せることだって叶ったはずだ。
地球を離れるとき、アークトゥリアンの基地への突入・撹乱を命じたのはリヴェアだった。追い込まれていたとは言え、あのときフレストが緋咲に懐いていなくとも、自分は同じ司令を出しただろうか。フレストがそれを責めることはなかったが、リヴェア自身、ずっと責め続けていた。
「敵がいないと生きていけない。ずっとそうだった。そうやって訓練された。ほかに取り柄なんて無い。戦争があれば、フレストを救える。だけどわたしは逃げた。逃げた。逃げた。この世界では、フレストは離れていくだけ。私に残されるものは? 私の命の意味は?」
ベッドルームに戻ると、端末に向かって、だれ宛でもない手紙を書いた。
「未来なんか要らない。銃口を向けてくれ。私の居場所は、そこにしかない」
ひとり泣きながら手紙を書いていることを、フレストは知らない。知らせる気もない。だれに読ませるつもりもない。ただ、文字にしなければ不安で仕方がなかった。文字にすれば、だれかがそれを飲み込んでくれる気がして、だれか、だれか、だれか、訴えるように繰り返し手紙を書いた。
だれか――
私を助けて――
放り出されたカバンのなかには、ネックレス、ツールケース、球体関節の人形とともに、粒子銃があった。
6 根之堅洲國
それからリヴェアは、更に探索の範囲を広げ、人間――自分にとって天敵のような生き物――を探した。その天敵こそが自分の価値を認める唯一の存在だ。ドルフィーに侵略された地球を取り戻してみせれば、ようやく自分の生が意味を持つ。
そのためにリヴェアは、かつての南極にまで行った。そこにも生存者はなかったが、重力波通信装置を見つけ、持ち帰った。重力波による通信は、主に外宇宙へ向けたもので、生存者の探索の役には立たなかったが、深宇宙から響くノイズはどこまでも白く、ランズボローの狂気じみた混沌の色をかき消した。
時計もカレンダーも意味をなさない部屋で、しばらくはひとりでいる日が続いた。この星では一日が一万年続く。その濃縮された永劫の時間のなか、リヴェアは、重力波のノイズに一定のリズムがあることに気づいた。ぼんやりとした意識のなかに、まるで夢を見るように複数の波形の干渉パターンが現れた。ただのノイズじゃない。意味のある信号が混じっている。
一万年の眠りから覚めたリヴェアは、端末を立ち上げ、解析を始める。通常の電波通信と違い、周期が長い。チューニングが必要だったが、周期範囲を指定したらすぐにパターンは抽出された。超低周波域に周波数の律動がある。2進数、32ビット毎の周期性。符号1ビットのあと、8ビットの指数部。最初の64単位がプロトコルを表し、定期的に現れる。かなり古いフォーマットだが、むしろ解析は易い。
――ストレージID:ヨミ
――ホユウコタイ :ホモ・サピエンス
――ユニットスウ :213804
西暦二千年代の言語で記録されている。
そのまま読み解けば、20万の人類が「ヨミ」と呼ばれる場所にいることになるが、発信源はあり得ない座標を示した。地下2千メートル。人類のテクノロジーからは考え難い深度だ。一方では、オモダルによって発生した地殻津波は大地深くを抉っている。事実、オモダルの突入面から吹き上がったマントルが新しい月になったくらいだ。人類が生き残れる場所は、この地球には存在しない。だけど、その「ヨミ」から重力波による信号が送信されている。
可笑しかった。
疑念や戸惑いを抑えて、なぜか笑いが込み上げてくるが、同時に涙が流れた。
リヴェアは、「役場」へ向かった。
それまでは自分たちの生活の補助を頼むために、頭を垂れて訪れるばかりだったが、いまは違う。使役する立場にあった頃のように誇らしくエントランスに入り、サポートを呼び出し、正確な地質図の作成を依頼した。
「ねえ、フレスト」
部屋に戻ると、居間で立体テレビ――と、二人が呼んでいるもの――を見るフレストに、上気して伝えた。
「人類が見つかるかもしれない」
「えっ?」
「しかも、20万人。うまく行けば世界を再生できる」
もちろん、そう簡単に行くはずはない。
このところリヴェアは、ヨミのことばかりに気を取られ、ほぼ横倒しになった岩だらけの地球のことなど忘れていた。毛嫌いしてやまないランズボローによって、守られ、生かされていることもしかり、それがなくなれば二人は三日で死ぬ。それにヨミから届くデータにしても、自動送信が続いているだけで、いつのものかはわからない。20万は避難した当時の数字で、いまは死に絶えた可能性もある。もちろん、当のリヴェアにしても、まだ確信するには足りない。もったいぶって、ヨミの詳細について語らなかったのも、足を掬われたくないからだ。
それでも、
「どこにいるの? そんなに多くの人類が」
フレストは目を輝かせる。
「もうすぐわかる。そうしたら、一緒に迎えに行こう」
それがリヴェアを高揚させた。
「うん。いいね」
フレストは繕ってそう答えたが、本音ではリヴェアの誇大妄想だと見透かしていた。それに姉のことだ。20万の人類と折り合いなどつくはずがない。
役場から送られてくる地質データをつなぎ合わせて、ヨミを探す日が続いた。ランズボローの狂ったデザインの交錯する部屋を、深宇宙のホワイトノイズで満たしていると、まだ見ぬヨミの景色が胸に浮かんだ。その暖かなミルクに浸された部屋に微睡んでいると、弟が入ってきた。ノックはあったのだろうが、うたた寝をしていたリヴェアは、寝ぼけてそれを聞いて、寝ぼけて返していた。
「姉。話がある」
そう切り出したフレストの言葉には、いつもその声を包んだ柔らかなオレンジの温もりがなかった。
「あとにして」
野営地に緋咲アヤカを連れて来たときを思い出した。
「いまはまだ、データの解析作業がある」
言い渡すと、フレストは、
「うん」
と頷いて、ゆっくりと背中を向けたが、部屋の入り口にとどまり、
「彼女ができた。そのひとと暮らすと思う」
と付け足した。
このときはまだ、リヴェアの表情には柔らかく寝ぼけた笑みが残っていた。
「彼女って?」
問い返すと、改めてフレストが振り返る。
「音楽の家庭教師」
緋咲アヤカに似た個体だ。
リヴェアは、「フッ」と、鼻で笑った。
「シリコンの人形と何をしてるの? 穢らわしい」
そう発すると同時に、リヴェアの高揚した気分は抜けた。
「穢らわしくない。人間の恋人同士と同じだよ」
「人間同士ならわかるよ。でも、相手はおもちゃだ」
「酷い言い方をしないで。人間は争ってばかりだ。姉もそうだよ。彼女たちのほうがずっといい」
「彼女って言うな!」
リヴェアは、しばらくは平静を装っていたが、比較されたことが癇に障った。
「あいつらに性別なんかない! 砂を食って、シリコンポリマーの母乳で子を育てるバケモノだ! 女に似せられて作られてるのも、男の欲求を満たすためだろう!? まんまと騙されて、バケモノの子を育てるのかよ!」
怒りもあったが、悲しみがそれに勝った。
これまで幾度となく、弟と関係を結ぼうと思った。それを姉弟だからと躊躇い、空想の中にとどめた。その空想のなかで幾度もフレストの子を身ごもり、それを否定してきた。それが間違いだったのか? 繋ぎ止めれば良かったのか? どんな手を使ってでも?
「ドルフィーは、姉が考えてるようなひとじゃない」
ドルフィーを「ひと」と呼んだことにも腹が立った。
「なんで、あんたは――」
そう口に出した言葉が、何を言わんとしたか自分でもわからず、訓練用のドルフィーを撃ち抜いたときに嗅いだ匂いが思い出された。そのイオン化した風の匂い、気化した体液の甘く腐敗した刺激臭と、青白い内臓のアンモニア臭。
――あんなバケモノ。私は緋咲アヤカだって、殺すことができた。
口に出る寸前のところで押し留めた。
「姉の考えてることはわかるよ」
フレストは静かに口にする。
「わかってないよ」
押し殺すようにリヴェアが答えた。
「わかってない!」
返事を待たず、もう一度繰り返した。
時はしばし、流れを躊躇う。
「たぶん、姉弟じゃなかったら、こうはなってない」
フレストが目を伏せたままそう言うと、リヴェアの目から涙がこぼれ始め、胸にわだかまった思いが嗚咽となって喉にあふれた。
たった二人残った人類なのに、どうしてその小さな壁を超えなかったのだろう。
7 私がいないと
この頃にはリヴェアは粒子銃を携帯するようになっていた。生き物もいない岩だらけの大地でそれが役にたつことはなかったが、朽ちた宇宙船のなかでは障害物除去の役に立った。リヴェアはその日、
あの日軟着陸させた脱出機の周囲を見ると、窓を割った際のバールがあった。何もかも失われた地球で、
そこから
緋咲は躊躇しなかったのに、どうして自分は躊躇するのだろう。
リヴェアは仄かに、フレストと二人、ヨミへと逃げ込むことに憧れを抱いた。ドルフィーから逃れ、20万の市民のなかに自分たちの居場所を見つければいい。きっとそこには武器もあり、彼らは蜂起する日を待ち詫びている。
燃え残った艦内から、使えそうな火器を探してみたが、動作は怪しかった。だが、決意は武装の多寡から来るものではない。使命の重さから来るものだ。事実、どれほどに追い詰められていても、戦場で死を恐れたことはなかった。死はいつも薄いヴェールの向こう、時が来れば己にも敵にも別け隔てなく訪れる。銃だけが、死の恐怖を拭い取る。そしてその銃口から、死を吐き出す。
その日もいくつかの遺品を持ち帰り、そのあとも幾度か
部屋に戻ると、もうフレストが訪ねることもない部屋で、球体関節人形の音声を再生した。
――助けて! お父さん! 助けて! 助けて!
その悲痛な声は、人間同士のいさかいから生まれたものだったが、リヴェアの中でそれは倒錯し、ヨミに閉ざされた人類を開放し、ドルフィーを討伐することが目的になった。
役場から送られたデータを解析すると、ヨミの座標はランズボローの直下を差した。違和はあったが、そもそもこのランズボローという存在の異質さを思えば、納得するしかない。そして納得さえしてしまえばあとは単順なもので、その入り口は簡単に特定できた。それは存外に小さな入口だった。そして秘められた謎に相応しく、厳重に施錠されている。
幸い、地質データより、通気口の存在が確認できていた。内部には太陽光が届かず、ハミングバードで偵察するにはバッテリーを改良する必要があった。そちらは造作もない。部屋に戻るとすぐに音声コマンドで、ハミングバードに改良を指示、卵を産ませて、シリコンのペレットを与えて成長を待ち、再度改良を加え、三世代目には6時間の連続駆動が可能な個体が生まれた。
通気口はメサの中ほどに開口し、そこに至るには管理通路を通る必要があった。申請が必要だったが、この頃には難なくそれを済ませられるほどに、リヴェアはこの町に馴染んでいた。遠隔での申請。許可が降りるとともに、すぐに開口部へ。
新世代のハミングバードを8体揃え、通気口からゆっくりと侵入させると、たしかに地下2キロ付近に空洞がある。だけど、20万人が住んでいる気配はない。ライトで照らし出すと、円形のホールかビルの吹き抜けのように見えた。壁には小さな金庫のようなものが並び、扉ごとにパネルがある。英語で何かが刻まれているが、腐食が激しい。その場で解析。難しいものは役場の仲介で外部の手を頼った。そこでわかったのは、ヨミに収められているのは人間ではなく、受精卵であることだった。
西暦二〇〇〇年代に作られた施設だ。すでに一万一千年を経ている。受精卵が生きているとは思えない。仮に生きていたとしても、それはリヴェアが思い描いた「人類」には程遠い。
だけど、発見は発見だ。これをどうフレストに伝えよう。高揚と失意とを交互に胸の表に顕しながら、玄関のドアを開けると、居間のソファに緋咲アヤカがひとりで座っていた。
緋咲ではない。緋咲に似た、弟が恋人だと言い張るドルフィーだ。だけど、フレストにとっても、リヴェアにとっても、そのドルフィーは緋咲だった。忌々しくも、リヴェアが拾ってきた人形を胸に抱いている。その背中は、リヴェアを嘲っているかに見えた。
――私はひとり残り、敵と戦い、あなたは宇宙へ逃げた。
「なんであんたがいるの?」
そう尋ねると、ドルフィーは微笑みをたたえたまま振り向くが、リヴェアの右手は腰の粒子銃にかかっていた。
「今日、は、報告、に、きた」
相変わらずの、たどたどしい言葉。
今日という感覚はランズボローのドルフィーにはない。フレストが教えたものだ。
「報告って?」
リヴェアが問うと、ドルフィーは静かに口を開く。
「わたし、彼の、こども、やどして、います」
その言葉はゆっくりと空気を伝い、鼓膜を振動させ、内耳の震えを通して、リヴェアの意識を叩く。その小さな振動は無数のエコーとなって響き合い、リヴェアのなかの何かを壊した。
リヴェアは粒子銃をホルスターから抜いて、緋咲の額に銃口を付けるが、向こうはそれが何かを知らない。緋咲が小首を傾げると同時に――生まれて初めて、瞳を閉じて――銃爪を引いた。狭いフラクタルな部屋に銃声は雷鳴になって轟き、閃光の中でシリコン・ポリマーの脳漿は瞬時にして気化した。その熱風が顔にかかる。銃を撃ったあと、腕が震えたのも、涙がこぼれたのも初めてだった。
次の瞬間、奥の扉が開いた。その向こうはキッチン。そこに立っていたのは、エプロンを締めたフレストだった。その口に絶叫が轟く。リヴェアの口からは思わず、
「ごめん……」
の一言が漏れ、足の力が抜け、しゃがみこんだ。
「なんてことをしたんだ!」
フレストのその声ははっきりと聞き取れる声にはならなかった。フレストは緋咲のそばに座り込み、肩を震わせ、次にリヴェアに掴みかかった。
「なんで姉は!」
リヴェアは仰向けに押し倒されて、肩を掴まれ、その肩を何度も揺すられたが、その手を払えなかった。
「彼女が何をしたって言うんだ! いつもそうだ! 姉はいつも! 壊せばいいと思ってる!」
「ごめん……違う……」
それ以上の言葉が出ない。
フレストは泣きながら、喚きながら立ち上がり、そばに落ちていた粒子銃を拾い上げ、その銃口を床に横たわるリヴェアに向けた。声を震わせて、
「姉が何をしたか教えてやろうか! 姉がずっとしてきたことを!」
銃把を握ったフレストの手も、肩も、ガタガタと震えている。
「殺さないで……」
リヴェアは両手で涙を拭いながら、静かに訴えた。
「私たち、最後の人類なんだよ。お願い。殺さないで……」
混乱したフレストの耳にその声が届き、混乱に拍車をかける。
「ふざけるなよ! なんで命乞いしてんだよ! 姉は……! 姉は……!」
そこまで言ったあとは、腹の底から絞り出す雄叫びが続いた。ただただ吠えた。幾度も大きく息を吸い、怒りと憤りを含ませた絶叫に変えて吐き出した。
リヴェアは怒り狂う弟を初めて見た。絶望と悲しみ、深い後悔に駆られ、だけどそこにあるのは、肉体の死の恐怖ではない。たったひとつだけ人類と繋がった、細い糸を失うことの恐怖だ。
リヴェアは泣きながら、静かに、
「私がいないと、人類はもう子孫を残せないよ……」
口の端に漏らした。
Ⅱ 西暦三〇九X年・人工天体オモダルの最後
1 ホタルの伝言
時折、宇宙の深淵に光が見えることがある。
錯視は視覚の混乱から来るものだが、その日、
あるいはそれも、人工冬眠中に見るという夢かもしれない。
覚醒とも睡眠ともつかない、からだの中だけで目醒めた浅い夢の中。虚空の星は蛍のように群れ集い、美しい色とりどりの幾何学パターンとなって、幻燈のように繰り返した。
夢はどうして覚えていないのだろう――
そう考えていると、
胸の奥深くに沈むから――
の、答が聞こえた。
――聞こえた気がした。
2 木星軌道
「永劫の闇の
深淵の孤独……
無限なる虚無の、無垢なる静寂……」
人工天体オモダルの宇宙軍に所属する、緋咲アヤカ
「冥闇の漂流……」
そこには何もない。
「姿なき、夜の魔王……」
大気の揺らぎと減光のない漆黒の空で見る宇宙は、ことのほか明るく美しいと言われていたが、肉眼で見ればガンマ線も同時に目に飛び込む。
「そうなったらパァァァァァンだよ、パァァァァァン!」
目にするのは、何重にもコーティングされた窓越しの暗い宇宙だ。そのどこまでも深い空は、すべての音、すべての意識を吸い込んでいく。
「ハァ……」
飛んでくる星に速度を合わせるため、いくつかのスイングバイを経る必要があり、この日はすでに人工天体オモダルを出て6年の歳月が経っていた。漆黒の宇宙には不安ばかりが佇まう。ほんの24時間前に人工冬眠より目覚め、小惑星捕獲の準備に入っていたが、緋咲はずっと、宇宙の暗闇の不安を形容する言葉を――
「死せる闇の女王の吐息……」
探していた。
まだ人工知能の黎明期、「アンドロイドに死の恐怖はあるか」という命題があったが、その後、ひとが深宇宙へ出るようになって、詩人であり実業家でもあるひとりの宇宙飛行士は、その問自体が間違いであることを指摘した。死の恐怖があるのではない。永劫の未来まで続く、生の恐怖があるのだ、と。
「あまり考えるな」
というのが、オモダルの管制からの言葉だった。だが考えをやめずとも、足元の虚無の空間は、すべての思考を吸い込んでいく。不意に、我思う、ゆえに我あり――と言った17世紀の哲学者が思い浮かぶ。果たして、この思考を吸い取る宇宙の闇の中で、我は、思考は、ありやなしや――多くの宇宙飛行士と同じように、緋咲も自問した。
「虚空の星の黙示録……」
高い塔に張り出したテラス部分に立って、その足元には支えるものが何もないと感じた瞬間の恐怖が、全方位から押し寄せる。
「知り得ぬ果て、無知なる絶望……」
命や思考といったものは、己を中心にして枝を伸ばすように広がって行くが、宇宙では、それが何を捉えることもなく、ただ闇の中に吸い込まれていく。それはあたかも、発した声が闇に吸い取られ、自分の耳にも返らないような――
「無限……」
あるいは、この宇宙船の外に出ることができたなら、そこは自分の体すらも見えない闇。どこへ落ちていく感覚もないまま、どこかへずっと落ち続けるような――
「死……」
目標の小惑星を見つけたら、接近し、イオンロケットを装着、減速させ、地球軌道へと向けて進路を変える。するとその星は何年後かにオモダル近くに飛来し、そこに控える別のグループが受け取り、人工天体オモダルの血肉になる。
「食いしん坊なんだよ、オモダル嬢は。どれだけ星を食べれば満足するのさ」
もともとの計画はもう千年も昔のことで、端緒は人口問題だったと記録されている。それがときの情勢によって、軍事目的に変わり、資源の確保に変わり、いまは50億年後の太陽の爆発を見越して、外宇宙へと航行するためのロケットエンジンまで組み込まれている。
「すぐ隣に、おいしそうな青い星がありますねー、食べてみますかー?」
当初は、メインベルトと呼ばれる火星と木星の間のアステロイドベルトから星を集めていたが、計画が練り直されるごとに規模は大きくなり、やがてアステロイドベルトだけでは足りず、木星軌道上のトロヤ群のほか、土星や木星の衛星まで集めるようになった。
「タイムマシンで二十世紀あたりに戻ってさあ、太陽系図見てるひとにさあ、『それ』って、指差して、『そのアステロイドベルト。五百年後になくなるんで』っつったら、ビックリだよね」
それがいまでは、冥王星軌道にまで足を伸ばした。
「マジっすか! なくなるっすか!
マジマジ。食べちゃうんだよ。オモダル嬢が」
その冥王星軌道に送られた「小惑星捕獲マシーン」が、捕まえた星を凄まじい速度で放り投げてくる。それをキャッチして、減速してオモダルに落とすのが、いまの緋咲アヤカ准尉の役割だ。ひとつの星を減速させたら、また別の星に取り付いて、減速させて――それを惑星や木星の衛星でスイングバイしながら、1回のミッションで5から10は繰り返す。
「いつか、冥王星もぶん投げてくるんじゃないかな、あいつら」
冥王星軌道にある捕獲用の機体は自動化されているが、それを中継する点ではまだ作業員の手が必要だった。中継機を無人化するには、オモダルからの管制に1機あたり30人のクルーが必要になるが、かたやクルーを飛ばせば、管制もあわせて1チーム8人だ。
「問題は、パイロットが各1名ってとこよ。リスク高すぎるでしょ。仮に私が寝過ごしたりしたら、ものすごい速度で小惑星がオモダルをかすめるんだよ? てゆーか、准尉って一応士官でしょうよ。なんで単独で宇宙の果にいるのさ」
オモダルとの通信には15分のラグがあった。
「冥王星も捕獲計画に入ってる」
30分遅れで、オモダルから返事が返ってくる。
「冥王星、受けんのかよ……」
そこまでしてやっているのが、やがて来るだろう太陽の爆発への備えだ。オモダルを巡航能力のある星へと進化させ、太陽系外へ逃れる。これが本当にどれほどの意味を持っているかは、たびたび疑問の声が上がった。
「徒労……」
一つの星をキャッチして、リリース。その反動を利用して、4億キロの彼方の木星へと向かい、その第一衛星イオでスイングバイ、次の小惑星へ。その2年の行程を、また人工冬眠で過ごす。
「空腹……」
緋咲アヤカのオモダルへの帰還は、24年後が予定されていた。
3 人工天体オモダル
雪の降り積む狛犬の間を抜けて丹塗りの目隠し門をくぐると、緩やかな階段の参道へと続く。その左右に小さな灯籠の火が揺れて、右手に三重の塔、かすめて
すれ違う着物のひとは、猫を抱え、京都には雪が降っていた。
和傘を傾げて、
「こんにちは」
と、猫の顔を覗くと、そのひとは猫の顎を指で撫でながら、
「ああ。こんにちは」
と、声を返した。
「お名前は?」
猫の名を問うと、その答えは、風のなかで白い息となった。
10年の眠りから覚める時、ひとは覚醒の一瞬で、10年の夢を見た。
人工冬眠では夢を見ないとされていたが、それでも多くのひとから、夢を見たとの報告があった。まさか。そんなはずはない。議論と、仮説とがあり、脳波分析の実験の結果、それらはすべて目覚める前のほんの一瞬に見た夢だとわかった。わずか1秒にも満たない時間に現れるその夢は、ときに何年も続いたような錯覚を与える。
オートパイロットで、人工天体オモダルのドックに入った時、緋咲アヤカは夢に見た京都の町を思い起こしていた。任務に発つまえ、再現されたデータで歩いた20世紀の京都には、ベルボトムのパンタロンに、裾を結んだペイズリーのシャツのカップルが歩いた。何百年もの昔に失われた景象。二重写しにぼんやりと眺めていたモニターにロック解放のサインが出ると、ハッチが開く。
「おかえり。緋咲アヤカ准尉」
そう声をかけたのは、同僚のエリコ・ライトだった。
「30年前のまま、変わらんな」
と、エリコは、無骨な手のひらを差し出す。
「私にはほんの2ヵ月前だ」
30年でオモダルの様子はずいぶんと変わっていた。
数多のパイロットが集めた岩石で日々成長しているのだから無理もない。アヤカが所属するオモダル宇宙軍 Material Procurement Team も、元のオフィスはオモダルの成長とともに地下深くに埋もれていた。新しいオフィスは、軍のセントラルタワーにある。自動通路はまだ整備されていない。
「宇宙では、よく喋るな」
無言で歩く緋咲に、エリコは問うた。
「あそこは喋っていないと、自分がだれだかわからなくなる」
緋咲は静かに漏らした。
「わからんではない」
「次の任務は、いつ?」
「わからん。5年前から中継機もオートマトンが対応してる。そろそろお役御免かもしれん」
エリコとは恋人のような頃があった。それが緋咲の感覚では、ほんの半年前だ。
「オートマトンか。お人形もずいぶん進化したもんだな」
「なんだ。先輩風か?」
そのエリコが、結婚し子をもうけたことは、つい数日前、木星軌道上で聞いた。
「娘は何歳になった?」
つい数日前が、エリコにとっては何年前だったか。
「上の子は15だ。軍人になると言っている」
「そりゃあ誇らしいな」
「そうでもないさ。アークトゥルスの攻勢が激しくなっている」
そう言えばエリコも、星を捕まえることに憧れて軍人になったのだ。
「星を捕まえるのも、地獄だよ」
呆れたように緋咲が言うと、エリコは口の端で笑った。
「オフはどうする?」
「娘に会いに行くよ」
「娘?」
「大食らいの娘の成長を、確かめたい」
京都の夢で、エリコを見たことは慰めだった。
人工天体オモダルの核は人工知能だった。
元はドルフィーたちと同じテクノロジーで作られ、自らを改造して成長するように設計されている。他のドルフィーは、主に機能を改良し、必要なら世代交代するように作られているが、オモダルは星として成長することに特化されていた。宇宙に出た当初は輸送艦程度の大きさしかなかったというが、更に古くは人間サイズのアンドロイドだった。そのオモダルの核に、セントラルタワーの地下から降りることができた。
現在のオモダルの直径は月の半分に相当する。重量比ではその1割程度だが、地球の8割に及ぶ重力がある。これは人工重力によるもので、地下にある人工知能核を覆う重力コアが空間を歪ませて発生させている。
オモダルの中心にはおよそ30キロほどの巨大な球体があり、中は空洞で、オモダル人工知能はその中心に浮かんでいる。球体が細胞ならば、オモダル人工知能は細胞核のような関係だ。そしてこの球体こそが重力コアと呼ばれるものの正体で、細胞壁にあたる外殻はバナジウム合金とタングステンカーバイドの複合素材でできている。オモダルそのものは汚れた雪玉のような形をしているが、その中心にはピンポン玉が入っていると想像するといい。そのピンポン玉の外殻の厚さは8百メートルに及ぶ。その厚い殻の中にジャイロと言われるリングが6本仕込まれており、これが磁気によって加速され、空間を歪ませ、擬似的に重力を発生させている。亜光速で物質を回転させると、フレームドラッギングという現象が生じ周辺の空間を歪ませるが、オモダルではこの6本のリングを角度をずらして配置し、3本ずつ逆方向に回転することで歪みを打ち消し、均質な重力を発生させている。このリングは光速の99%を超える速度で回転しているが、この加速は現在も続き、二百年以内に地球と同じ重力を発生させると予測されている。
驚くべきは、この機構を設計したのが、オモダル自身であることだ。この人工重力装置は同時に地磁気も発生させ、宇宙線による被爆をも防いでいる。外部から与えられた命令は「星として人類が住む環境を構築しろ」でしかなかったが、これを解釈し、人工重力を発生させる方法を自ら探り、実装した。オモダル自身による発明や設計はこればかりではない。最大の発明は、この星で人類は酸素を必要としないことだろう。
人類も、それに似せて作られたドルフィーも、五百年前は酸素を必要としていたが、バックパックに血中の二酸化炭素を還元する機構が組み込まれてからは、外部からの酸素の取り込みを必要としなくなった。バックパックからは1日にコイン3枚ほどのグラファイトが排出され、これが生物の呼気に含まれる二酸化炭素を代替した。おかげでオモダルには酸素がない。星にとって都合が悪いのは、酸素と電磁波だ。
そのもう一方の電磁波についても、可視光以外はかなりの部分がフィルターされ、オモダルで通信に使用される帯域はごく限られている。電磁波の氾濫を抑えるため、電波の位相差と律動を利用した独特のプロトコルをオモダル自身が設計し、すべての通信はそれでまかなわれる。もはやこの星では、だれが主体かわからないほどに、オモダルによる管理は行き届いていた。
「そもそも、星を集めたのは、重力を作り出すためだったんだよ」
エレベーターで下に降りながら、緋咲は呟く。
「だろう? お嬢」
深部へと降りるほどに重力は増し、重力コア表面ではそれが8Gに達する。
そして、その先では重力が反転、グラビティ・スフィアとも呼ばれる重力コアに入ってからは、オモダル核へ向けてエレベーターは上昇、重力はやがて均衡し、消える。
「こんな立派なモン作るんだったらさあ。私たちが星を集める必要なんてないじゃない」
薄暗い人工天体の中心に、オモダル核が浮かぶ。
エッジワース・カイパーベルトで収集された星は、人工天体オモダルの衛星軌道に投入され、そこで主にシリコン素材とその他の金属とに分解されて、オモダルに送られ、地下2百メートルの層で各種の部材に加工される。
その下の層にはシリコン・ポリマー・アンドロイドの工場があり、現在は第14世代の外宇宙飛行型のドルフィーが生産されている。このモデルは、地球から4光年離れたアルファ・ケンタウリへ向かい、2百年後にはそこに到達する。そして更にその2百年後には、アルファ・ケンタウリから星が投げ込まれる。オモダルの餌とするために。
そのすべてを、この巨大な人工知能がコントロールしていた。
人類が気が付かないうちに実装された機能は、ほかにも無数にある。古代カンブリアの海にどんな生物相があったか知り得ないように、オモダルの全容を知るものはいない。
「こちらアヤカ・ヒサキ准尉、識別番号K81c5238」
オモダルの新市街を散策する緋咲から――
「こちらオモダル。MTP管制センター。どこの軌道からだ?」
オモダル宇宙軍管制室のエリコに連絡が入った。
「街の様子が変わって困ってるんだ。付き合えよ。デートしよう」
「今日は仕事なんだ。あとにしてくれ。というか、なんで音声通信なんだ」
「宇宙パイロットの性さ。来ないんだったら、娘をよこせ。どうせヒマなんだろう?」
オモダルには住人が増え、新しい町が生まれていた。
緋咲は、新しくできた劇場のまえの広場で、アイスクリームを食べながらエリコを待った。通信のスイッチを切ってしばらくすると、新しい町に似つかうはずもない古びた出で立ちでエリコが姿を見せる。さっき屋台で買ったボールをエリコに投げると、それはエリコの手の中で弾けてドラゴンに早変わりして、驚くエリコを見て、緋咲は笑った。
「おまえ、子どもじゃないんだから」
「私が成長するとでも?」
古い町は地層の下に沈み、古い住人が住み着き、新しい町は地表に生まれ、そこには新しいものたちが住んだ。緋咲は古い街の郷愁より、新しい町の喧騒に惹かれた。緋咲にしてみれば古い街は、郷愁が育つまえに一瞬にして地下に沈んだ、神隠しの村だ。
「天下無双のエリコも、娘に虫がつくのは嫌だと見える」
「親と子の間には壁があるんだよ」
「壁ねえ。8Gの人工重力を発生する、鋼鉄の壁が?」
「匹敵する」
街の娯楽性は、ひとことで言えば「流行」にあった。つまり、何かしら「変わる」ことが、娯楽の根底にある。地球の文明から切り離されて久しいが、オモダルにはそれと比肩する文化が築れている。複数の習俗があり、それぞれに刷新し、街に占めるその位置も入れ替わった。
「あった、ここ」
緋咲が指差したのは書店だった。
「資料でも探しているのか?」
エリコが尋ねると、
「匂いが好きなんだよ」
と、謎めいた笑みを浮かべた。
書物の多くは、二十一世紀に人工天体オモダルの開発が始まった頃から持ち込まれていたが、集積が進むのは二十三世紀、移民が本格化した折になる。地上の戦火を避けるために、大学や研究機関の手によって数多の書籍が集められた。
二十一世紀の初頭は、これらをデータ化する潮流があったが、おかげでその時代に多くの書籍が失われ、いまでは人類の三大愚行のひとつに数えられる。電子化された本のデータほど無価値なものはない。本そのものの価値が見直されたのは、物性解析の技術が進んでからだ。いまだ発展途上の技術ではあるが、最新の技術を用いれば、インクの性質、にじみ、紙の繊維などから、印刷した現場の様子を再現することができる。本の数が増えればその精度は上がり、いまではロンドンのイーストエンド、ホックニーといった町は、かなりの精度で復元されている。東京、神田もしかり。これは本に限ることではなく、服も、アクセサリーも同様で、マテリアルに残る痕跡から、加工された現場をかなり正確に再現することができた。単体の解析でこそ得られる情報は少ないが、数を増やし、他との共通点や差異を積層すると、そこには失われた歴史像が浮かび上がる。ちなみに、人類の三大愚行の残りのふたつは、貨幣制度と内燃機関だが、詳細は割愛する。
立ち返り書籍に関してであるが、以上の重要性から、主に二十から二十一世紀に出版された本は、公共の機関に保管され、そのものが流通することは稀だったが、そのレプリカは、オリジナルのマテリアルデータを添えた状態で数多くが流通していた。解析し尽くすにはあまりにも膨大な量であり、いまだ新しい発見が起こるのが、この界隈だ。
「これを探してたんだ」
と、緋咲が手に取って見せたのが、京都の旅行パンフレットだった。
「中国か?」
「そのとなり。日本だよ」
「言語は共通だろう? 当たったようなもんだ」
「それも間違い。とりあえず、これとこれ。持ってて」
「データだけもらえばいいだろう? なんだってこんなもの」
「言っただろう? 匂いが好きなんだって」
いまは素材が記憶しているマテリアルデータが利用されているが、更に次の世代では、ホログラフィックデータとして、物質の「経験」が取り出されるようになる。
原子というのは身の回りにある物質とは違い、その内部には10次元、または11次元の要素が折りたたまれていると言われている。二十九世紀になると、このなかの4つの要素が読み取れるようになった。ホログラムの原理もこれに基づくもので、これを応用すると、物質がどんな化学反応をしてきたかをトレースできる。いくぶんロマンチストじみた言い方をすれば、たとえば本であれば、読んだひとの顔や、置かれていた場所などを、本そのものが覚えている。
そしてまた、これを解析しているのも人工知能であって、人類はただ指を咥えて待つ腹を空かせた子どもだった。
摩天楼にあったアパルトマンの一室は、30年の歳月に降り積んだ幾層もの空、地表、その痕跡の下に埋もれ、複雑に伸びる支柱に挟まれては新しい地表を支えていた。
その自室に戻ると、緋咲はレコードをかけた。
回転する円盤に彫り込まれた物理的な溝の凹凸を、重力で圧力をかけた針で読み取り電気的に増幅して音に変える――今のテクノロジーでは信じられない装置だった。オモダルの重力では、針への圧力が不足し、わずかな振動でたびたび針は溝を外れオフセットエラーを起こしたが、緋咲は、息も立てずにその音楽に耳を澄ました。
京都に関する資料も、棚の一段を占めるようになった。このデータをシリコン上に展開すると、部屋の全球ホログラムに京都の町並みが浮かび上がる。着物姿の少女と、赤いベルボトムのパンタロンの青年。体の線に沿ったシャツを着て大きなサングラスをかけた女性。ふたつ穴のベルト。真鍮のバックル。冷やし飴、ちりめん山椒、それがどんな味のものか想像の翼を羽撃かせながら、緋咲は通りすがった僧侶に、大原三千院の場所を尋ねた。
4 戦闘任務
アークトゥリアンとの戦いで劣勢を強いられるなか、不可思議なデータが観察されるようになった。オモダルが試作するドルフィーのログに、空間座標の不連続があったのだ。同時に、オモダルは最新型の14世代ドルフィーの生産を切り上げ、15世代ドルフィーを設計、その生産を開始した。生体アンドロイドと言いながら、外見は14世代に続いて戦闘機タイプ、外宇宙を航行できる能力を有し、全長にして従来の2倍の大きさがあった。
憶測が飛び交った。新型の開発は、アークトゥリアンとの戦闘力を高めるため、あるいはアルファ・ケンタウリへの日程を縮めるため、あるいは37光年彼方のアークトゥルスに攻めるためと言われ、どれを取っても明確な決め手には欠いたが、ひとつだけ確たる共通項があった。データから推測する限り、新しい機体には「ワープ機能」が備わっていたのだ。
人類はワープ技術に関してなんの知識もない。宇宙軍の電算部はオモダルの人工知能にアクセスできてはいたが、その知を解析するには至らなかった。最新機の機能について訊いても、オモダル内部で独自に定義した法則を羅列するだけ。もはや人類と人工知能の知識の差はミミズとアインシュタインに匹敵する。果たしてそれがどのような意味を持っているのか、多くの宇宙物理学者、数学者を悩ませた。
アークトゥリアンは、37光年の彼方から訪れているわけだから、空間跳躍技術を持っている可能性が高い。その技術を地球側でも開発したからと言って、劇的に戦況が変わるはずはない。だが、一方では地球には地の利がある。超越的な文明を持つアークトゥルスの軍を、事実9百年に渡り防衛してきた。
「娘は何をしでかすつもりなんだ?」
この情報を知ったエリコが眉をしかめて、緋咲に聞いた。
「食うことしか考えてないからな。どこか遠くの星でも捕りに行くんだろう」
ワープがどういう実装になるかは、まだわからない。現在、試作機のデータで確認されているのは、数宇宙里の瞬間移動だ。これが太陽系外まで一気に飛べるようになるかどうかもしれない。だが、うまく行けば、アークトゥルス本星に乗り込むことができる。その予想が正鵠を射るか調べる術はない。しかし、いずれオモダルがワープ技術を獲得するという予測は、すぐに既成事実になった。
そんな折、地球統合軍から作戦の連絡が入る。
統合軍が示した案は、実に簡素だった。
①60日以内に、オモダルを前哨基地にしての総力戦を展開する
②すぐに民間人を地球に退避させよ
対アークトゥリアンの作戦では、地球軍が主導権を握っていた。歴史的な事実を見ても、オモダルは地球を守るための盾であり、矛でしかない。当然、オモダル側は反発、別の作戦――地球-月系のラグランジュポイントL1、L2に待機するアークトゥルス艦への総攻撃――を提案したが、地球側は聞き入れなかった。
「もうすぐ、オモダルはワープ機構を獲得する。そうなれば戦況は一変する」
オモダル宇宙軍の幕僚長からそう伝えたが、向こうにしてみれば荒唐無稽な話だった。
「宇宙で軍を率いて、相対性理論も知らんのか」
モニター越しにそう罵る声に、
「事実、アークトゥリアンは、37光年の彼方から我々を侵略している、彼らには相対性理論は働かないとでも言うのか」
と、返した。
かく言う地球側の主張は、科学よりも政治に論拠した。
「奴らがアークトゥルスから来たという証拠もない。案外、君たちが喧嘩を売ってる冥王星あたりから来てるのではないのかね」
たしかに、彼らがアークトゥルス星人を名乗ったわけではない。そも9百年前に生まれた既成事実だ。赤色巨星であるアークトゥルスに地球型の惑星がある可能性も低い。根拠を紐解いても、海に溶け出した角砂糖のように、そのエビデンスは仄かな甘みすら残さずに消える。
「作戦中は電波は遮断される。通信による指示はない。他の機体を見て各自判断してほしい」
緋咲アヤカは、12名の隊員にそう指示を出した。
地球からの司令の数日後、機密作戦が始まった。緋咲アヤカの部隊を突破口に、ラグランジュ・ポイント上のアークトゥリアン艦に総攻撃をかける――地球の意向を無視しての決定だった。
緋咲隊のクルーはみなパイロットではあったが、オモダルのドックでの機体の牽引を主任務とし、いままで戦闘に出たことはない。端的に言えば、みな港湾職員だ。そんな彼らに、先発隊として白羽の矢が立ったのには、理由があった。
「先程説明した通り、貨客艦デナリ、パイクスピーク、シャーフベルクは囮であり、無人だ。敵が取り付いても放置しておけばいい。もし敵が動いたら、こちらはその背後のL2の艦を叩く」
L2は、地球の重力均衡点であるラグランジュ・ポイントのひとつを指した。均衡点は各星に5つずつ存在するが、地球のL2は月軌道の外側に位置する。そこには、アークトゥルスの母艦と思しき艦がぽつんと居座っている。「エンジェル・コア」と呼ばれるアークトゥリアンの供給源があると言われているが、その噂の震源も不明で、それがポータルなのかアンドロイド工場なのかも知られていない。オモダルから向かうのはたった12機の戦闘機だったが、各機自律型の攻撃ドローンを備えている。敵方に護衛艦のような姿はなく、先発隊としては十分な数だ。敵の数が決して多くないのは、ほかのラグランジュ点も同様、L1にしても、巨大なエネルギープラントのようなものが地表へ向けてマイクロ波を送電照射しているほかは、数機の小型機が配備されているだけ。それもおそらく、デブリを除去するためのものだと見られている。しかし、宇宙空間では攻めるほうが圧倒的に不利だった。遮蔽物の無い空間を軌道運動して到達するのだから、なんらデブリと変わることはない。
緋咲アヤカが指揮するのは、常日頃から小惑星の軌道を計算して捕獲しているチームだ。この急襲が無茶であることはすぐにわかった。無論、行くのは簡単だ。しかし――
「L2は、月の向こうですよ? どうやって帰ってくるんです?」
帰りが難しい。
今まで有人機打撃群は、地球軌道への遊撃を主任務としており、月軌道のはるか外側にあるL2を直接攻めるのは今回が初だった。
「火星でスイングバイして帰ってくる」
緋咲が腕を組んだまま答える。
「火星で……」
クルーはこの言葉を予想はしていたが、実際に耳にすると戸惑う。
通常、カタパルトで加速して発進した戦闘機は、戦闘空域での戦闘を終えると、補助装甲を展開、減速することなく虚空へと流れ去っていく。そも減速などしてたら、狙い撃ちに遭う。遠くの惑星まで慣性飛行し、その重力場を利用して帰還するのがセオリーで、スラスターの推進剤はオモダル近日点での減速に使用した。
「この帰還ルート、君たちなら探せるはずだ」
緋咲は堂々と語り、その言葉を聞いて、隊員たちはすぐに計算を始める。
「地球の高度百二十キロの軌道に侵入すれば、L2をかすめて火星へ抜けて、帰ってこれるけど……」
「全行程で2年はかかりますね……」
月軌道の内側にあるL1を攻めるほうが、難易度としては低かったが、今回のターゲットはL2。いったん地球の衛星軌道に入り、そこからは月までの距離の4倍に位置する。L1は、無事にオモダルへ帰還できるルートが単純で、ほぼ行動を読まれて迎撃されてきた。対して、L2は虚空へと飛び出すリスクは高いが、成果も期待できる。
「木星軌道に小惑星を捕まえに行くよりはましさ」
なだめるように、緋咲は言う。
「交差軌道に入り、すれ違いざまに砲撃を食らわせ、離脱後は適当な惑星でスイングバイしてオモダルに帰る。何万もの兵士が経験することだ」
初の宇宙戦に出向くクルーには不安があったが、宇宙戦闘というのはそういうものだ。オモダル宇宙軍に所属するパイロットの9割は、実はいまも宇宙を彷徨っている。帰路のほうが桁違いに長いのだ。
「さあ、そうしんみりしないで。運のないヤツは、いまも海王星を目指して飛んでいるんだ。火星でスイングバイできるだけめっけもんさ」
海王星まで行くと、帰還は30年後になる。
「その軌道計算、私もやったことがあります。心を鬼にして」
ひとりのクルーが悲しげに口にした。
しかも、1回のスイングバイで帰れたらまだいい。速度と進入角度を合わせるために2度3度のスイングバイを余儀なくされることも少なくない。オモダルの町の賑やかさは、これらの死線を超えたパイロットが再び浴する生への賛美だった。
「最近ではロケットの推進力も上がってる。昔に比べたら、ずいぶん早く帰ってこれるようになったさ」
とは言え、その推力を戦闘で使い果たして、結局は海王星に流れていくパイロットもあとを断たなかった。「最悪、海王星経由で帰ってこれるように敵の軌道に侵入する」というのが宇宙戦の絶対的なセオリーだったが、不幸にもわずかにその範囲を逸れ、外宇宙へ旅立ったパイロットも少なくない。
「君たちは、我が宇宙軍が誇る小惑星捕獲班だ。惑星の動きにはだれよりも通じている。だからこそこの作戦に選ばれたのだ」
地球の公転面に対して水平に飛んでいれば、第三宇宙速度を超えない限りは地球に帰ってくるチャンスはある。が、たまに戦闘時の加速で公転面に垂直に飛び出すものがあり、そうなると地球に帰るのは運になる。太陽という重力の井戸に落ちないようにするには、惑星に手を掛けてターンするしかないが、垂直に飛び出してしまえば、その惑星がない。では、減速すれば良いかと言えばそうでもなく、速度を失うといずれは太陽に落ちる。地球が見えるからと言って、地球に向かって速度を上げれば、地球で減速する術がなく、それもまた太陽へ落ちる。地球を離れたら、基本的には太陽の重力に支配される。宇宙は三次元に見えて、実質、平面なのだ。もし敵に、地球の北極方面の彼方に陣取られたら、そこに行くすべは無い。行けたところで、帰るすべはない。もちろん、陣取るすべもないのだが。
緋咲アヤカの隊は、全員が管制と操縦をこなせたので、この作戦には適任だった。しかし、死地へ向かうのに適任と言われることほどやるせないものもない。ときにスラスターをベタ踏みするパイロットを見て、「なんでパイロットってこんなにバカなの」とボヤくこともあった彼らにそのお鉢が回ってきたのだから、宇宙の寓話だ。パイロットにしてみたら地球の公転面など見えないのだから仕方がない。バカと罵られたところで、ビームを避けなければ死ぬのだ。そのやるせなさを、こんどは彼らが味わうことになる。とっさに敵を向いて、砲撃して、そのままスラスターを吹かしたら外宇宙まっしぐら――というのも、ざらにある話だ。通常はスラスターにもリミッターがついているのだが、勝手にこれを外すパイロットも多く、これは概ね先輩が粋がってそう教えるのであるが、優秀な新人に限って敵のビームの回避にスラスターをベタ踏みして、文字とおり帰らぬひととなる。そも回避に使用しているスラスターは姿勢制御用だ。どこかのエースが「一気に吹かせばビームを避けられる」といって編み出したのだろうが、機体を瞬時に移動させ亜光速で迫るビームを避ける推力がどれほどのものか、考えればわかりそうなものだ――と、これも管制官の愚痴によく聞かれる言葉だった。そうやって旅立ったパイロットは、家族に戦死が伝えられることもなく、「現在、ベテルギウス方面、2億5千万キロを人工冬眠しながら漂ってます」とだけ連絡が来る。
「我が子はいつ帰ってくるんですか?」
「運が良ければ、アルファ・ケンタウリでスイングバイして、2千年後には」
死ななければそれで良いというものでもない。それは「死」とはまた違った、格別の絶望をもたらした。
太陽-地球系L5ラグランジュポイントにあるオモダルから地球まで、30日がかかる。
軌道での速度というものは、主要天体からの距離と重力で決まる。緩やかな凹凸のあるフィールドにボールを転がすことを想像してもらうとわかるが、高速で転がせばフィールドの外に飛び出すし、ゆっくり転がせば低地に向かって転がり落ちる。減速時には加速時と同じエネルギーを要し、乗組員が耐え得る加速度にも限度がある。三十一世紀の科学をもってしても、この行程を劇的に縮めることはできなかった。クルーの前には、30日の虚空が立ちはだかる。小惑星キャッチャーの緋咲アヤカにしてみれば、人工冬眠は慣れたものだったが、他のクルーは戸惑った。
「30日だったら、私、起きてます」
と、いうものもあったが、
「やめたがいいよ。3日で気が狂う」
と、緋咲は諭した。
闇は、存外恐ろしいものだ。せめて何人かで機体に乗り込めばまだ良いのだろうが、戦闘機は単座だ。オモダルなり地球なりが足元に見えてる間はまだはしゃぐことができたが、それが見えなくなったら、あとは地獄だ。目を閉じただけの暗闇ではなく、音も光もなく、周囲にはただ無の空間が広がる。そこでひとは、自分を意識だけの存在だと錯覚し、意味を失った肉体が消えていく妄想に囚われる。
「早くワープ装置、開発されませんかね」
クルーはため息を付く。
「そうだな。そうなるといいな」
しかも今回のミッションは、通信が禁止だ。
木星軌道上で一方的に喋っていたときも、ろくに地上から返事は来なかったが、それでも、だれかが聞いているという感覚は、命綱のように気持ちを繋ぎ止めていた。
5 大気圏突入
地球軌道近日点での減速の6時間前、緋咲アヤカが人工冬眠から覚めると、前方に貨客艦デナリの艦影が見えた。キャノピーを覆う液晶シャッターが上がり、左舷にはぼんやりと光る大気をまとった地球がある。パイクスピーク、シャーフベルクの艦影も確認。貨客艦はこのまま地球軌道を回りオモダルへ引き返し、緋咲隊は百二十キロの地球軌道にドリフト、月の向こうのL2へ向けてスイングバイする。軌道を再計算、現在の機体重量から推力を決定し、減速準備完了のシグナルを灯す。宇宙航行にはすべて手順がある。通常は意図せず機体重量が変わることはないが、推進剤の放出異常、武装の脱落などを想定し、ドリフト前は必ず再計算された。緋咲がガラスの天蓋を見上げると、全周モニターが小隊機に順次灯る「準備完了」の信号を二重写しに捉える。そして――そのなかに異質な信号を送る光点を、緋咲は見留めた。
信号は連続して繰り返す。救難信号だ。小隊機からではない。無人のはずの貨客艦シャーフベルクが発している。緋咲は機体をシャーフベルクに向ける。メインスラスターの点火から2分後、シャーフベルクに接近、減速、20メートルまで機体を寄せると、窓から覗く乗員の姿が視認された。同時に、貨客船は地球衛星軌道へのドリフトを開始する。近接していた駆体が大きく回頭を始めるが、予定とは異なる。異常事態だ。緋咲機からオモダルに電波通信が再開されるが、オモダルに電波が届くのは8分後、回答は更に8分後になる。まずは、小隊機に指示を出した。
「こちら、LAC1緋咲アヤカ准尉、LACは全機オモダルへ帰投せよ。各自管制に連絡、指示に従え」
時間差で全機、了解のシグナルを返す。次いで、シャーフベルクへ。
「こちら、エルツー・アタッキング・クルー、LAC1。シャーフベルク、応答せよ。そちらは無人のはずだ。だれが操作している?」
混乱しているのか、返答までラグがあった。
「こちら、シャーフベルク。艦長はいない。ぜんぶ地球側が誘導していると思っていたが、大気圏突入マニューバが起動しない」
いや、それで良い。しかし、乗員がいるのはどういうことだ。それに、軌道変更のためのドリフトは始まっている。
「安心しろ。すでに減速オペレーションに入っている」
乗員を安堵させるためにそう返したが、釈然としなかった。大気圏突入プロセスに移行するはずがないのだ。返事を待つと、
「マニューバは手動で起動した。そのあとずっとアラートが鳴りっぱなしで――」
と、聞こえた。
なんて馬鹿なことを――と思ったが、そもそもなぜ――
「貨客船は無人のはずだ。何人乗ってる?」
「人数なんかわかるもんか。地球側が乗れって言うから乗ったんだ」
「地球側が指揮していたのか?」
「だから、細かいことを聞かれてもわからないんだよ! 乗ってるのはみんな素人だ! 俺たちはどうなるんだ!」
「こちらLAC2。我々はどうしますか?」
小隊機から質問が来る。シャーフベルクの速度に合わせて減速しているのは緋咲機のみ。他の機体はすでに視界から消えている。
「LAC1。おまえたちはオモダルへ帰れ」
「こちらLAC2。地球軌道を周回して、1時間後にランデブーできます」
「LAC1。したところで何ができる。命令は伝えた。復唱しろ」
「LAC2了解。LAC、全機オモダルへ帰投します」
「こちらLAC11、隊長はどうするんですか?」
別のクルーが尋ねる。
「LAC1。幸い減速してるのはシャーフベルクだけだ。乗り込んでなんとかする」
すでに衛星を使った通信にはタイムラグがあった。緋咲はシャーフベルク後方へと回り、人工天体オモダルの管制へ連絡を取る。
「こちらLAC1、緋咲アヤカ准尉。現在地球軌道ストラタ38、プロセス63。貨客船シャーフベルクに乗員を確認した。対象は彼ら自身の操作で、大気圏突入マニューバを起動している。墜落の危険がある。これより、ドッキングを試みる」
緋咲はシャーフベルク後方に付けドッキングベイの開放を求めるが、大気圏突入マニューバがロックしている。このタイミングでベイを開くのは、イリーガルなマニュアル操作が必要になる。素人への指示は無理だ。このまま大気圏突入を見守ってもいいが、シャーフベルク内に出ているアラートはおそらく、重心エラーだ。オモダルの指示を無視して地球側が勝手に住人を乗せているとしたら、まともな重量計算は行われていない。宇宙管制ではとにかく手順が重要になるが、政治がそれを破る。そもそも軌道ドリフトの予定などなかったのだ。それにしても、オモダル側は把握していたはずだ。なぜ連絡がないのか。あるいは、彼らを見殺しにしてまで、この計画を遂行するつもりでいたのか。遠隔でデータを取ると、地球重力軸に対して傾きがある。このまま大気圏に突入させたら、側面から崩壊が始まる。
緋咲機には大気圏内航行の機能もあったが、飽くまでも地球重力圏に落ちた際の暫定的なものでしかない。緋咲はシャーフベルクの右舷底面に垂直に機体を接触させ、艦体を押し上げた。軍に入りたての頃は、タグボートを操作していた。お手の物のはずだったが、機体を立てると大気の圧力がかかった。想定外だ。このままの姿勢では、緋咲機が先に崩壊する。崩壊しないまでも、推進剤を使い果たせば、減速できずに地表に叩きつけられる。しかも不幸にもそこに、アークトゥルスらしき機影の接近が確認された。地上2千キロメートルの公転軌道からのトランスファ、近日点はシャーフベルク軌道に重なり、15分後に接触。交戦になる。軌道遷移のドリフトを狙えば幾分有利になるが、すでに大気の圧力がある。10分以内に機体は自動的にサーフェスモード、つまり可変翼によるコントロールに切り替わる。不慣れな大気圏内では勝算がない。緋咲は宙間航行用のスラスターモードのまま敵を待ち受けるが、スラスターで姿勢を維持するのには限界がある。大気との摩擦が気化冷却コートを蒸発させ、渦流が不規則に機体を揺らす。サーフェスモードへの移行がアナウンスされるがキャンセル。機体のサブスラスターが次々と推進剤を使い果たす。無理だ。アラートが鳴る。大気の圧を受けて、緋咲機の先端がシャーフベルクから離れ、コントロールを失う。8機ほどの異星人小型機がシャーフベルクに取り付く。が、それを間近に見ながら、緋咲の機体は大気圧に押され、その距離を引き離されていった。
大西洋上空、マッハ12の速度を維持したまま緋咲機は高度を下げていった。上空でのイリーガルな操作が仇になり、サーフェスモードへの移行が効かず、スラスターを利用した減速が余儀なくされる。もはや残された推進剤はわずかしかない。最終的には減速用のパラシュートがあるが、シミュレーションの結果、残された推進剤が必要量を下回ることがわかる。もう軟着陸は無理だ。いかにマシな形で墜落するかを選ばなければいけない。大気圏航行用のジェットエンジンを
宇宙の深淵での死に比べたら、地球の死はずいぶん賑やかだった――
緋咲アヤカがため息をつくなか、緋咲機より切り離された大気圏航行ユニットは、パラシュートでゆうゆうとミャンマー北部の森林に軟着陸した。
6 地球統合軍
手の甲のライトパネルを開くと、中国の東の端だとわかった。
燃え落ちた戦闘機から這々の体で逃げ出した緋咲アヤカは、岩場にうずくまる。
――京都までは、ずいぶん距離がある。
その墜落現場まで、16キロに渡って木々がなぎ倒され、戦闘機の炎は森の端に火をつけていた。緋咲はぼんやりと炎をながめている。大量の酸素というものを目にしたことがない。この炎の回りには、酸素があるのだろう。いつまでも燃え続ける炎は、珍しかった。オモダルより2割も強い重力に戸惑い、厚い大気越しに見る太陽は、サード・アイリッドを下ろせば直視できた。森と草原とが重なり合うその地の近くに、ひとの住む集落があるかどうか、目視で確認できなかったことが悔やまれる。やがて雨が降り出し、うとうとと沈みかけた夢から引きずり出されると、人影が見えた。傘を差している。
「モーリス大学、ブルードール技研のインターン、フレスト・プローンです。なにかお手伝いできることはありますか?」
眼の前に現れ、そう名乗った彼は異質に見えた。
肌の色が均一ではなく、耳には不可思議な凹凸がある。瞬きを見る限りサード・アイリッド――瞬膜もなく、燃え残る戦闘機を見上げる時、手のひらで影を作った。
「オモダル宇宙軍、惑星資源捕獲班、緋咲アヤカ准尉だ。貨客艦を護衛していたが、アークトゥルスの小型機と遭遇した」
肌の色の不均一は、日焼けと呼ばれるものかもしれない。
「了解しました。あらためて初めまして、ヒサキ准尉。軍務官でしたら、近くにキャンプしている部隊がありますので、そこに案内します」
「軍務官」はオモダルではあまり使わない言葉だった。いくつかの言語で照会すると、英語の Military Servant が比較的近いが、それも聞き慣れない言葉だ。
「済まない」
緋咲は簡素に返した。
フレストと名乗った彼は、少し歩き出そうとしたあと、
「オモダル軍との協定のことはわからないので、案内するだけですが」
言葉を補う。
「もちろん、それで構わない」
あたりは緩やかな起伏のある牧草地だった。段丘のようでもあり、ところどころ木々が生い茂り、山裾では森になる。また少し離れたところでは赤土を露出したまばらな草原となって、山の岩肌へと連なった。
フレストはしばし無言で歩いたが、近くに停めたビークルまで来ると、思い出したように緋咲に尋ねた。
「少し距離があります。近くに集落がありますので、まずはそこを目指します。食事は――なにを取られますか?」
そう言えば、緊急の道具はなにも持ち出せなかった。携帯食があれば不足はないのだが、どんな選択肢があるのかわからず、問い返した。
「なにをとは?」
その質問に、フレストと名乗った彼は、緋咲の全身を舐めるように見直して、問いを重ねる。
「ドルフィーですよね? 地球のドルフィーと同じ食事でよければご用意できます」
そうか――緋咲は思った。
眼の前にいるのは、自分とは違う。人間だ。
「わからないが、シリコン食ならほぼ適合する。人間は初めて見た。何か失礼があったら済まん」
「ぼくもオモダルのドルフィーは初めて見ました」
この頃、オモダルにはもう人類は住んでいなかった。オモダルの人類がドルフィーに滅ぼされて、もう3百年近くが経っていた。
人類とアンドロイドとで争われたオモダルでの戦いは、地球では「オモダル独立戦争」と呼ばれている。原因はドルフィーの反乱だと言われているが、はっきりしない。戦況がドルフィー側に傾いてから、地球側からも支援があったが、港を塞がれたら何もできなかった。それに、最初から人類に勝てる戦争ではなかった。ドルフィー側は素材さえあれば無限に増えることができたし、一代で性能の違う新しい個体を生み出すことができる。緋咲アヤカもその頃のモデルだ。
オモダルでは、この戦争を語るものはいなかった。はるか昔に起きたどうでも良い事件を振り返るものなど、平和な世の中には存在しない。人間という生き物がいて、それが滅んだ。そこには何の意味も教訓もない。
「ヒューマノイドの形勢不利を悟った地球軍がどうしたかは、たぶん、ご存知だと思います」
と、フレストはビークルのパイロットシートで語った。
「どうしたんだ? 教えてくれ」
緋咲は問い返した。
「ドルフィー側を支援したんです。数々のレアメタルは、オモダルからもたらされていましたからね。ヒューマノイドを支援して、挙げ句断交なんてことになったら、地球の経済が麻痺します」
ドルフィー独立戦争の初期から、地球の経済には混乱があった。シャトルで2ヵ月を要する遠い星での争いに、最初は手をこまねいていたが、そこに介入したのは政府ではなく、その背後にある民間企業だった。まずは人道的介入を口実とし、そして当初のヒューマノイド支援から、ドルフィー支援に鞍替えする際には、「オモダルのヒューマノイドが、地球の艦船に攻撃を仕掛けた」が口実とされたが、その事実が存在しないことは戦争終結後に明らかになった。
だがそれも、有耶無耶になった。
なぜか。
「平和になったから」だ。
もちろんその「平和」も政府側の方便だ。いまが平和であるか、有事であるかは政府が決め、マスコミが拡散する。そしてその「平和」のまえに、あらゆる不都合は免責される。オモダルの人類がひとり残らず抹殺されたにも関わらず、いまはその戦争の遺恨もない。「共通の敵、アークトゥリアンを前に、戦争などする余裕はない」と説明するものもいるが、それにしても方便だ。
――平和に手を取り合おう。人類の繁栄のために。それを前にしたら、個人の不平など、取るに足りない些細なことではないか。
夢と希望とに彩られたそのスローガンで、事実は蹂躙される。蹂躙したのはだれか。為政者か。いや、そうではない。だれもがそれを望んだのだ。蹂躙される当人でさえも。
集落に着いて、フレストは改めて部隊へ連絡しているようだったが、顔を覗いても作り笑いを返すだけ。軍とのネゴシエーションがうまく進んでいないのは、漏れ聞こえる言葉からわかった。
「私ならかまわない。ここまでの案内、感謝する」
緋咲はそう告げたが、フレストは笑顔を繕い、
「いえ、大丈夫です。オモダルからの貨客艦乗員の救出を優先するそうです。ぼくたちはここで休んで、明日、足を探しましょう。いまのビークルだと、距離があるので」
と、答えた。
「貨客艦というのは、シャーフベルク?」
緋咲の顔が曇った。
「ええ、アークトゥリアンが不時着させました」
「アークトゥリアンが? なぜ?」
「彼らは、民間人は攻撃しませんよ。それどころか、保護します」
そんなはずはない、アークトゥリアンはどの船も等しく攻撃してくる、と、緋咲は思ったが、オモダルから船で飛び出すのはほとんどが軍人だ。今回の民間人だけの船というのは例外だった。
夜。地球からは巨大な月が見えた。古びた宿は木材で組まれ、淀んだ水と分解されてゆく朽木の臭いがある。足元の床が軋む。そこにまた新たな臭いが立つ。地球の臭いはどれも、緋咲の鼻に心地よいものではなかった。恐竜の時代、あるいは鉄器の時代、化石燃料の時代を経た地球の臭い。あらゆるものが、手を触れると、ぼろぼろと崩れ、臭いを発する。
「京都には行ったことがあるか?」
夕食をとりながら、緋咲が尋ねる。
「いえ、ありません」
フレストが答える。
「そうか。京都の奈良には法隆寺が残っている。七世紀に作られた寺院だ。その五重塔を見るのがずっと夢だった」
「でも、いまはどうでしょうね。日本も激戦地になったはずです」
「ああ、そうか。そうだったな」
「ヒサキは、日本の名前ですか?」
「そうだと聞いている」
「ドルフィーが作られたのは、日本ですからね。オモダルには、その頃のモデルが残っていると聞いたことがあります」
「はは」と、緋咲は笑った。「ずいぶん古いタイプに見られてるようだな」
「いえ、最新のタイプだというのは、見てわかります」
「最新でもないさ。最新は15世代目が開発中、私は9世代目だ。もう3百歳になる」
「いいですね」
「いい?」
「地球のドルフィーの平均寿命は25年です」
「そうなのか?」
「みんな捨て駒にされます。それで不平を言わないものだけが複製されて……」
「仕方ないよ、それは。戦争だからな」
「ありがとうございます。軍に紹介すること、躊躇っていたんですが、少し楽になりました」
捨て駒として紹介されるわけか――と、思わないわけでもなかったが、小さなロケットに詰められて宇宙に飛ばされる日々を送ってきた。まさに捨て駒だ。ここに落ちてきたのも、まさに。
翌日、三輪ホバーのタクシーで軍の駐留地へ。
駐留とは言え、固定式の施設がいくつも据えられている。大型の輸送機の発着も想定した立派な基地だ。周辺では伐採や整地が行われていたので、まだまだ拡張するつもりだろう。そこにいる軍人はほぼすべてが迷彩色の軍服を着込んでおり、彼らの目には、真っ赤な宇宙服を着た緋咲は奇異に映った。
宇宙では赤かオレンジを纏うのが基本だった。でなければ、不意に宇宙空間に放り出されたときに、デブリとの区別がつかなくなる。逆に、非生物では赤やオレンジの使用は控えられた。古くはオモダルに駐在する国の国旗にも赤は多用されていたが、二十二世紀以降は青や緑でリファインされた。
地球の軍人の地味な服装は、緋咲の目にはエキゾチックだった。地上で赤い服を着ていれば、敵に狙い撃ちにされるのだというが、宇宙空間で2メートル足らずのターゲットを狙い撃ちにするようなことは、まずない。対人で攻撃を行うという地上の戦闘には、不思議な高揚を覚えた。
ゲートにほど近いドーム状の移動施設内でしばらく待たされ、そこから軍用のホバートラックで数ブロック離れたトレーラーハウスに移る。リヴェア・プローン少尉を紹介されたのは、軽い身体検査を済ませた後だった。
「はじめまして。統合軍アジア方面隊武漢第三空挺団、リヴェア・プローン少尉だ」
彼はそう名乗り、握手を求めた。
「はじめまして。オモダル宇宙軍、惑星資源捕獲班、緋咲アヤカ准尉。よろしく頼む」
緋咲は手を伸ばし、リヴェアの手を握った。
「オモダル軍との折衝は別の部署が担当するが、今回は私が手続きを進めている。理由は――聞いているかもしれんが、貴公を発見したフレストが私の弟でね。フレストは理官――理官はわかるか? いわゆる民間人で、窓口は別にあるのだが、わざわざ私に連絡してきた。おかげでこうして、私が繋ぐことになった」
リヴェアは苦い顔で笑うフレストの顔を横目で見て続けた。
「まったく。まだまだ子どもだよ。不手際があったら、許してほしい」
このあと緋咲がこれまでの経緯を説明。着陸に関する技術的な話題――ジャイロを利用した姿勢制御、最終的にはメインスラスターを自ら撃ち抜きその暴発の反動で減速させたこと――に触れたが、リヴェアも緋咲と同じパイロットで、話は狂気的に和やかだった。
「オモダル軍の条約違反に関しては、私では判断しかねる。そのことで一下士官の貴公が裁かれることもないだろう。ああ、これはもちろん軍の見解ではない。私の見解だ」
そう言いながらリヴェアは、書記官の書き留めた調書を確認し、緋咲に示した。緋咲が頷いて「緋咲アヤカ准尉。了承する」と返すと、リヴェアはそれにサインした。続けて、
「さて――」
と、リヴェアが口にしかけるが、緋咲はそれを制して、この駐留地の指揮官との面会を求めた。リヴェアは今夜の寝床やアメニティについて話すつもりなのだろうが、それよりも重要な事案がある。矢継ぎ早に言葉を並べ、
「ワープ装置のことを――」
と言いかけたが、
「そのことについては、ここではもう言うな」
今度はリヴェアが制した。
「ここの指揮官はアルフレヒト・イグロダ大佐だが、オモダルとの折衝はエファンソ・タルエド中佐が取りまとめている。まずはタルエド中佐に伝えてくれ」
オモダル軍にいた頃、少佐以上の階級のものと話すことはほとんどなかった。小惑星捕獲班の実質的なトップはペネロペ・オウン大尉であったが、定期的なミーティングで話す以外は、身近に見る機会すらない。その上は組織図には存在するが、緋咲とエリコはその実在を疑っている。それでも「上に聞かなければわからない」というオウン大尉の言葉を日頃から耳にしていた緋咲としては、できるだけ上の人間と話をしたかった。端的に言えば、ここの総司令官に会いたい。気持ちはぐるぐると先走るが、とは言え、これから面会するのはナンバー2であり、階級も中佐だ。オモダル宇宙軍では、幻か伝説の存在だ。
「話は聞いた。オモダルで開発中だというワープ装置についても聞いている」
エファンソ・タルエド中佐は、部屋に入ると挨拶もなく、椅子を引いて腰掛けながら言った。実在していた。さきほどのトレーラーハウスからは更に奥へと入った、駐留地の中央の建物だ。他の建物は移動要塞のようなものが多かったが、こちらは大型のエアドームのようだ。内部は3階層になり、その3階奥で面会が行われた。
「であれば、その完成を待つという判断を」
緋咲は訴える。
「申し訳ないが、統合軍本部では、その話は信用していない」
だれも食べないパセリほどの遺憾の意を添えたタルエドの回答。
落胆した。その判断にというより、データではなく信用を根拠とした判断をする地球統合軍に。
「そうか。残念だ」
「送られてきたデータも解析したが、証明されていない定理が複数現れる。解析したチームの責任者は、難解な数式を散りばめた巧妙なフェイクだと話している」
「反論を」
緋咲は発言の許可を求める。
「許可する」
「しかし、それではオモダルの人工知能が嘘をついていることになる」
「そうではない。オモダルのデータは千年以上も前から蓄積されている。そこに誤ったデータが紛れ込んでいれば、判断を誤るということだ」
「反論を」
「許可する」
「実際に座標の跳躍を示すデータがある」
「一個一個、すべてのデータを検証しろというのかね」
「反論を」
「いちいち許可を求める必要はない。話せ」
「検証は済んでいる」
「残念だが、オモダルにいるのはすべて人工知能だ」
「どういう意味だ?」
「そういう意味だよ」
中佐は苛立って答える。「質問が多い」「察しろ」「余計な口を挟むな」「アンドロイド風情が」「敬語を使え」と、いくつかの意味を込めたが、伝わるわけがない。苛立って見せれば察してもらえるのが地球のコミュニケーションだが、緋咲には奇妙に映った。
――もしかするとこのひとは、無能なのかもしれない。
「オモダルが判断を誤るように、君たちも判断を誤る。そうではないことを証明できるかね?」
なるほど、そういう意味か。それにしても、地球では「そういう意味だよ」で、これが伝わるのか。文化の差は大きい。あるいは高度な皮肉であるとも考えられるが、皮肉を言う文脈ではない。
「個々のノードが判断を誤るかどうかは重要ではない。それを検証するプロセスがある。あなたたちにその手段がないのなら、どんな素晴らしい判断も活かされることがない」
と、緋咲もまさか軍の上層部を相手に、基礎的なインテリジェンス・サイクルの説明をすることになるとは思わなかった。おそらくオモダルとは異なるフローが採用されているのだろう、とは思ったが、いや、それにしても、である。論点が空疎すぎる。ただし少々補足しておくと、実際に地球側でオモダルのデータを検証したチームは、科学的なロジックで動いており、「無能」はそれを受け取ったこの中佐であった。そのせいで無能だと思われた地球側の技官もいい迷惑だが、オモダルと地球の間には必ず「無能の窓口」が立ちはだかった。それが軋轢も生んだし、科学の進歩を停滞させた。中佐は対話の間、緋咲の調書に目を落としていた。
「どうする気かね、これから」
中佐は問うた。これも軍のトップの人間ならば、どうすべきか示唆を与える立場だ。緋咲は部下ではないとは言っても、自分が指揮する基地にいる軍人に、どうするつもりか尋ねる上官は少ない。
「そうだな。軍属たるもの、個人でできることは限られている。オモダルへ帰る手段でも探すとしよう」
敬語を使え、敬語を。中佐はずっと苛立ちっ放しだった。たかが「です」を「だ」にしただけで、地球統合軍で部隊を束ねる長の判断を揺さぶっているのだから、統合軍の脆さは察するに余りある。
中佐との面談の後、オモダルへの帰還について、別の係官から説明を受けた。曰く、オモダルからの兵は年に十数人が不時着するらしかった。どうやら火星や木星でスイングバイして帰ってくる兵士が、軌道の調整が合わずに、やむなく地球へ降りているらしい。緋咲にも十分に想定できる話だった。
「それらのパイロットを宇宙へ帰還させるための、専用のシャトルがある」
「なるほど。それを利用すればオモダルへ帰れるのだな」
「ああ。ただし、護衛をつけるだけの余裕がない。必要なら、そちらでオモダルに連絡を取って、準備してほしい」
これだ。寄せ集めの傭兵部隊ですら、これよりましではないか。
緋咲アヤカとフレスト・プローンには、駐留地内に部屋が用意された。立体的なオモダルと違い、平面に配置された建物の間を縫って歩き、地面に張り付いた部屋から見る景色は、半分が地面だ。2割強い重力と相まって、圧迫感がある。夜遅く、その部屋をリヴェアが訪ねた。
「貴公の統合軍への編入を申請した。オモダルへ帰るまでの暫定的なものだ。通れば、勝手が効くようになる。最終的にはタルエド中佐のサインが必要になる。難しいとは思うが、フレストたっての願いだ。無下にはしたくない」
ああ、あの無能な中佐か。まあ、自分の名前くらいは書けるだろう。
「ありがとう。大佐には会えないかな?」
「難しいな。ワープ装置の件か?」
「ああ。実現すれば、我々のアドバンテージになる」
「おとぎ話だよ、そんなものは。十代の学生ですら笑い飛ばす」
その反応は緋咲にも予想できた。だが、データを見てもらえればわかるはずだ。データを見る時間があれば、の話にはなるが、どうやら地球の彼らには、その余裕がない。緋咲アヤカには、宇宙の時間と地球の時間とは、やや流れ方が異なるように思えた。これもまた、重力に由来するのだろう。
宇宙では「判断するための時間」が重要になる。たとえば、地球から月へはホーマン遷移軌道と呼ばれるコースをたどる。まず地球を周回する軌道に乗り、そこから月へ向かう楕円軌道に移り、月の重力圏に達したら月の周回軌道へと遷移するが、直線に近い軌道を取れば3日から4日、ゆったりとした螺旋に近い軌道なら1カ月をかけて遷移することになる。無人機であれば、燃料も節約できるゆっくりしたコースを取るが、有人だと乗員の健康を鑑みて速いコースを選ぶ。しかし、速い軌道を選択すると、トランスファ軌道から月の周回軌道へ乗り換えるタイミングは短くなる。さらにそこでは、地球との通信には1秒のラグがある。
これも「インテリジェンス・サイクル」の問題になる。宇宙管制においては、情報をどう集積し、だれが、どう判断を下すか、その通信経路、通信ラグ、すべて想定されて運用されている。しかも、月ならば通信ラグは1秒で済むが、敷根の主戦場は木星だ。これに係る「時間」が最初に想定されていなければ、往々にして結論ありきの判断が下される。いま地球統合軍が、やっきになってワープ技術を否定しているように。
「戦況は、そんなに差し迫っているのか?」
「こちらの分析では、オモダルはもう1年と保たない。戦力の補充が追いついていないのは明らかだ。オモダルが落ちる前に決着をつけたい」
緋咲にしてみれば、青天の霹靂だ。いくら30年木星軌道にいたと言っても、戦況は理解しているつもりでいた。
「いまは、第14世代から15世代への切り替えの時期だ」
「こちらでは、第10世代からデータを取っている」
「第15世代の特殊性を鑑みれば――」
「その大型化によって、資材調達サイクルが――」
平行線だった。こういう場合、お互いのデータを開示して、突き合わせれば良いのだが、お互いに論拠とするデータに精通しているわけではない。それぞれ地球とオモダルの代弁者でしかなく、要は、地球の口と、オモダルの口が話しているのだ。主張はできても、話を聞く耳はない。
「地球に移民する考えはないのか?」
間をおいて、リヴェアが問うた。
「故郷を捨てて?」
「郷愁はどうでもいいだろう?」
ここでもまた平行線だ。ものごとを想像する力がなければ、胸のなかにある不安は「情緒」と捉えられる。故郷への郷愁、過ぎし日の追憶、過誤への慙悔。だが想像し、言語化する能力があれば、同じ不安が「論理」になる。
「必要な物資を得る手段が、オモダルと地球では異なる。クレジットの決済に関しても違う。プロトコルも同一でないし、それは物資の確保だけではなく、生活の全てに及ぶ。その乗り換えが必要になる」
「少しずつ克服すればいい」
「それで生活にかかる工数が20%上昇すれば、そのひとは生涯に渡って20%の不利を強いられることになる。それは数字として現れる。たとえば資格試験を受けるにしても、その工数は響いている。そうして故郷を捨てたものは、何代にも渡って経済的な不利を継承する。その補償がなければ、政情不安に繋がる。それが『郷愁』の正体だ。問題が解消されれば郷愁などはどうでもいい。そして、それを克服するのは個ではないよ。システムの問題だ」
「ああ。それはそうだ。だけどそれは論理ではないよ。感情を体よく言い換えたものだ」
そう切り替えしたリヴェアの意見も、本質ではなかった。それに、論理が優れ感情が劣るわけでもない。本質的に感情と論理は不可分で、感情がなければ、論理が何を導いても意味はない。たとえば、何かの動物が「絶滅危惧種」に指定されるとするならば、それは論理。だがそれを救うのは感情だ。感情がなければ助ける必要もないし、生物の多様性も無用だ。そもそも絶滅を危惧したりもしない。人間に感情がなければ、死にたくないとも思わない。
翌日、朝。またトレーラーハウスでリヴェアと面会した。
「貴公を一時的に私の隊に配属することになった。タルエド中佐が多忙でね。中佐がサインするまでの特別措置として認められた」
実際のところ、タルエドはこの問題に関して、少々感情的になっており、サインを保留し、その申請のチケットも放置していた。「機械」でしかないと見做した相手に対して感情的になるののだから、感情というものもやっかいなものだ。
「ありがとう。感謝する」
「弟がどうしてもと言うのでね。少しは発言力があることを知らしめたい」
7 奈落にて
夕焼けの空も消えかける頃、男は仕事に疲れ、温かな暖炉と鍋のシチューを思い浮かべながら、家路を急いだ。生活は苦しく仕事は辛かったが、生まれたばかりの娘の顔を見れば、疲れは吹き飛ぶ。市場通りを抜けて、小さな明かりを灯す我が家が見える頃には、自然とその足取りも軽くなった。
ところが――
男が自宅前に広がる沼の近くまで来ると、不意の雷が男を打ち据えた。そして次の瞬間には、男の体はこの世界から消え失せ、同時に雷は沼の上にも落ち、そして何という偶然か、その雷は男と寸分たがわぬ存在をそこに作り出した。奇跡によって生み出された新しい男は、その原子配列まで含めて何もかもが消えた男と同じだった。こうして再現された男――
二十世紀に提起された思考実験のひとつ、スワンプマンだ。
原子の配列まで完全にコピーされた人間は、元と同じ人格・意志・記憶を持つかどうかを問うたもので、この問は雷の代わりに「ワープ」「原子転送」「生体複製」なども想定され、宇宙技術の発展とともに幾度も議論の俎上にのぼった。
三十一世紀の時点では、原子はミクロな存在ではなく、マクロなものであるというのが主流の考え方だ。「一個の原子」の状態は、厳密に特定することはできず、マクロに捉えることでようやく物性が明らかになる。究極的に言えば、物質は周囲の環境の影でしかない。とある宇宙物理学者の言葉を借りるなら、一個の原子は、宇宙全体の影響を受けて存在する。その考えで行けば、ワープは「人間の影だけを切り取って別の場所に移す行為」と同じだった。
ただし、これにも反論がある。人間が思っているほど、人間の自己同一性は高くないというのだ。昨日の自分と今日の自分とは「概ね同一」という程度の同一性しかなく、たとえばその間に脳を半分切除されて他人のものと入れ替えられても、おそらく気が付かないだろうと、その理論は結ぶ。
また、ワープに関しては、「宇宙のどこを見ても観察されていない」ことが、否定の根拠に挙がった。宇宙のどこにもというのは大げさに聞こえるかもしれないが、物質が瞬間的に移動すると、当然光速を超えるわけだから、そこには特定のパターンを持つ重力波の発生が予測された。だが、それが現在まで観測されたことはない。天球から来る重力波の傾向から逆算する限り、少なくとも銀河系内では質量10キログラム以上の物質が瞬間移動した形跡はない。オモダルがワープ航法を開発したと言われるようになったあともしかり。これが地球統合軍が、オモダルの主張を否定する最大の根拠だった。
とは言え、この原理を完全に理解し、その根拠となる数字を示せる者は、全人類のなかでも数人に満たない。ただ、「ワープは実現できない」という結果だけが広まり、やがてそれが常識となると、物理学の論文で扱われることも、SFのネタになることもなくなる。それが書かれた古典SFは、それこそ十代の学生までもが笑い飛ばす。
ひとはすべて、科学者の口を借りて話す。口を借りても、耳は借りられない。語ることはできても、反論を聞く耳は、だれも持たなかった。
地上に降下して80時間が経った頃、ようやくオモダルへ連絡を取ることができた。
「統合軍経由で、連絡が行ってるかと思った」
と緋咲から、オモダルに残っているエリコに問うと、
「いや、一切ない」
の短信が返った。
これが地球統合軍とオモダル宇宙軍のコミュニケーションの現状なのだから、共闘して異星人に立ち向かうのは無理があった。
「それより、娘がアラートを出しっぱなしだ」
「なんでそれを私に?」
エリコが唐突に自分の娘のことを言うものだから、緋咲は戸惑ったが、通信には片道8分、往復で16分がかかった。とは言え、遅延によるディスコミュニケーションは慣れたものだ。「なんでそれを――」の、この言葉が向こうに届く頃には、緋咲もオモダルのことを言ったのだと思い当たっていたし、エリコもいちいち訂正せずに、次の情報を送ってくる。エリコの話では、ドルフィー製作用のレアメタルが不足し、それでオモダルはアラートを出しているらしかった。
「タンタル、ニオブ、インジウムが欲しいと言ってる。スペクトル分析で含有する小惑星を探してるが、手近にはない。ところが、地球にはある。統合軍にはオウン大尉から連絡が行っているはずだが、返事はない」
「取ってこいと? いや、返事はいらない。こちらで判断する。結果は次の連絡で伝える。要件を送ってくれ」
その返事を返す頃には、データが送られてくる。これがふだんから30分の遅延で話している二人の通信だった。宇宙の果てに飛ばされるのが士官になるのも、この判断を期待してこそだ。
2時間ほどの通信を終えると、通信室の前でフレストが待っていた。
「ずっと待ってたのか?」
尋ねると、フレストはばつの悪そうな顔で笑った。たしかに通信室の入口まで一緒に来るのは見ていた。民間人のフレストはその手前で止められてはいたが、ずっとここにいたとは。
「ええ。帰るきっかけがなくて」
緋咲アヤカは犬を飼ったことも、見たこともなかったが、フレストのそれは地球ではよく知られた犬の習性だった。
翌日。
「こちらアヤカ・ヒサキ准尉、識別番号K81c5238。新しい恋人を紹介する。フレスト・プローン。人間だ」
そこまで一息で伝え、フレストに振り返る。
「年はいくつだ?」
「22歳です」
「22だそうだ。顔の色の変化は日焼けだ。ゴーグルのあとが残っているんだ。人間にはよくあるんだ。大学でドルフィーとのコミュニケーション論を学んでいるそうだ。それでつきまとわれている。レアメタルの件はこちらでは難しい。大尉に交渉を続けてもらってくれ。それと、重力波受信機が欲しい。それがあればオモダルが開発中のワープの痕跡を探せる。見つかれば統合軍との交渉材料になる。以上」
フレストはリヴェアに頼んで、通信室への入室許可をもらっていた。インターンを務めるブルードール技研も軍の外郭団体であり、許可は簡単に降りた。音声データを送信して16分後、返事がまとめて返ってくる。
「こちらオモダル。MTP管制センター、エリコ・ライト少尉。地球で何をしているかと思えば、なんだ、恋人というのは。日焼けぐらい知っているよ。フレスト・プローン、緋咲アヤカ准尉をよろしく。准尉は案外詩人だ。レアメタルの件は了解。重力波受信機は当たってみるが、そちらに送る手段はない。ワープ痕跡の件は了解。こちらでも探してみる。こちらからは以上」
「こちらからも以上だ。フレスト、何かあるか?」
「エリコ・ライト少尉。いつかお会いできる日を楽しみにしています」
その翌日には、緋咲はフレスト・プローンの大学の研究棟に来ていた。
「だれもいないんだな」
「前線が近いので、大半が疎開しました。こちらです」
フレストは緋咲を、重力波受信機のもとに案内した。
「使い方はわかるか?」
「わかりません。でも、マニュアルがあります」
「わかった。手分けして調べよう」
要はラジオのようなものだった。入出力それぞれにソースやフィルターを選択する必要があり、それぞれの端子が外部デバイスにつながっている。おかげで、まともに動作させるまでに日が暮れた。深夜の2時を回った頃にようやく、空から降り注ぐ重力波を音声データに変換して出力し始めたが、地球人類であるフレストは睡魔に襲われていた。人工冬眠に慣らされたドルフィーとは違う。人間の体に興味があった緋咲は、しばらくフレストの心電図をモニターして眺めた。その鼓動は、ドルフィーと比べるとずいぶん速く、力強かった。
「こちらアヤカ・ヒサキ准尉、識別番号K81c5238。地下2キロメートルからの重力波信号を検出した。明日、発信源の調査に出る。データは送った。生還できたら、再度連絡する。それと、聞いているかもしれないが、統合軍がオモダルを地球に落とす計画を立てている。それで地上のアークトゥリアンを殲滅し、異常気象が収まるまで宇宙に退避するつもりでいる。作戦がいつになるかはわからない。家族を守ってくれ。以上」
「こちらオモダル。MTP管制センター、エリコ・ライト少尉。重力波信号、了解。発信源調査、了解。生還を祈る。座標データ、地質データ、ともに受信完了。オモダルを落とす件については上層部が交渉中だが、例の件で幕僚長のクビが飛んでる。こっちは、なすがまま。すでにパルサーエンジンの取り付けが完了している。摂動開始から何日後に地球接触するか、いくつかのパターンをシミュレーション中だ。新しい恋人によろしく。以上」
パルサーエンジン――馬鹿げた話だ。見かけ上とはいえ地球の8割の質量のあるオモダルが、パルサーエンジン程度で動くはずがない。そもオモダルが鎮座する太陽-地球系L5ラグランジュポイントの安定性は高い。シミュレーションするまでもない。動くはずがないのだ。
その翌日、緋咲は上海市東端、
途中、アークトゥリアンのドローン15機を撃墜している。
緋咲は正規の戦闘員ではなく、基本的には小惑星やデブリの破壊くらいでしか射撃の腕を使うことはなかったが、地球での戦闘はそれとくらべると楽だった。まず、ターゲットとの距離が近い。小惑星が相手だと数百万キロの彼方から撃つことも珍しくはない。肉眼で照準することはほとんどなく、撃ってからヒットするまで5~10秒のラグがある。相手の軌道を予測し、撃ち、数十秒後に結果を確認したら、照準を修正して再度撃つ。地上ではこのサイクルに1秒とかからない。最初の一機こそ慣れない地球の大気の抵抗に戸惑ったが、ジェットパックの扱いに慣れると、自由落下しながらの射撃もコツを覚え、宇宙空間と変わらぬ機動性を身に着けた。ときに凄まじい速度で地表まで達することがあったが、小惑星に取り付く際は最大で8Gの加速度を経験する。それを思えば、たかが1G。
滴水湖は、海に近い円形の湖で、おそらくは人造湖だろう。空は大きく開かれ、敵が来たら隠れる場所もないが、前線を離れた単騎を無理に取りに来る駒はない。
「――でもオモダルは、ワープ航法を発見した。このまま待っていれば、太陽系から脱出する方法を見つけ出す」
統合軍への定期連絡。緋咲は滴水湖に浮かぶ水鳥を眺めながら、武漢に駐留する部隊に連絡を取った。
「統合軍が求めているのは、実用化だ。常温核融合は二十世紀には確認されているが、千年を経たいまも実用化されてはいない」
通信相手はフレストの姉、リヴェア少尉。
「そうかもしれないが、いずれにしてもオモダルは、人類が開発したなかで最大の人工知能だ。これを失えば、人類の未来はない」
「私も同意見だ。だがもう人類には、未来なんてないんだよ」
「じゃあ地球軍は白旗を上げて戦いから降りればいい。あとはオモダル宇宙軍がやるよ」
「そう熱くなるな。いまのは私の意見であって、軍の意見ではない」
「最終決戦はいつ?」
「現在、オモダルに摂動を与え、左右に振り回してる。それが数ヵ月以内に軌道を外れ、更に数カ月後には地球に落ちると言われている。だが、オモダルが抵抗している」
「抵抗も何も。外付けのエンジン程度で動くものか」
「いや、オモダル自身にロケットがあるだろう? それを使っている」
オモダルの? ――そんな、まさか。
つまり、来たるべき日に太陽系を脱出するためのロケットだ。それを乗っ取ったというのか? オモダルは最高峰の人工知能だ。それを乗っ取る? どうやって? 緋咲は動揺した。そして無意識に、この動揺を地球人に悟られまいと機心が働いた。
「可哀想に」
「それには同意」
「エリコ少尉から、L2の防衛がカラだったと聞いた。いまならL2の母艦を叩ける。地球にいるアークスもそれで補給が絶たれるはずだ」
「それだよ。L2にいた戦力は、おそらく地上にすべて降ろされている。だからいまやるんだよ」
「……オモダルを……いや、地球を犠牲にしてか」
「ああ。いまの人類にできるのは、たったひとつでも遺伝子を残すことだけだ」
「理解できない。文化を捨てて遺伝子を残して、なんの意味がある」
「理解してもしなくても、歴史は流れるものさ。――ところで、上海に何があるんだ?」
「大きな湖。これもきっと、私の知らないひとつの文化だ」
上海は経由地だ。重力波信号の発信源は、日本の志高高原にあった。緋咲が滞在する武漢基地からは千6百キロの距離がある。中国大陸から九州へ、行程の大半は海上の移動になる。上海から福岡への定期便はあったが、緋咲には勝手もわからず、資材倉庫からジェットパックとフライトアーマーを調達し、ほぼ生身で乗り込むことに決めた。地表に降りてからというもの、ずっとそうだ。己の肉体以外に頼れるものがない。
上海を出て、高度2千まで上げ、志高高原に到着したのは3時間後。地球にはジェット気流があると聞いていたが、その高度までは上昇できなかった。
志高に降りると、古い城塞都市の中に、その入口はあった。二十一世紀の終わりに、イタリアの城塞都市を模して作られたテーマパークだったが、緋咲はそれが日本固有の様式なのだと思った。湾岸部からは少し離れ、古くは人里もない高原だった。傍らには小さな湖がある。やがてそこに小さな遊園地ができて、そこが閉鎖されると、どこかの財閥が宇宙科学に関する研究所を作った。それが資金難で閉鎖、また別の富豪に買われ、客も来ないテーマパークが建った。
その地下深くに円筒状の巨大な空洞があったが、直通の通路はなかった。超音波エコーを利用して入り口を探り、いくつかのゲートの錠を焼き切って、まずは管理通路に入った。そこからは通路と階段とが入り組み、エレベーターの痕跡もあったが、籠は朽ち落ちたのか見当たらず、階段は瓦礫に埋まり、最終的にはエレベーターの竪穴に用意された梯子を下るしかなかった。明かりがあれば、他にも進路は見つけたのだろうが、手元に照らしたライトの光では、縦に2キロ貫く細い昇降路が最善の経路となる。
梯子の支柱に手を掛け、ジェットパックの火を柔らかく光らせながら地下へと降りる闇のなか、緋咲の脳裏には、いつか見た幾何学模様が広がっていた。点対称の複数のラインが万華鏡のように入り組み、永遠の縮小と、永遠の拡大を、無限に繰り返し、自己相似形の文様を描き出す。そこには、この世界のすべての景色が漉き込まれていた。
最下層には、薄く雨水が溜まっている。あるいは、地下水。管理の手を離れた2キロの縦穴は、本来なら地下水に沈む。排水用のポンプが生きているのだろうが、千年以上稼働してきたことになる。
いったい、何のために。
足音のひとつひとつに、柔らかなエコーが長く尾を引く。円形の穴の底から、まっすぐに円筒状の空間が立ち上がっていた。この空洞はそのまま地表へと2キロ続く。壁には無数の小窓のようなものが設けられ、それぞれの個室には何かが収められているようだったが、まず緋咲の目に映ったのは、旧型の倒れたドルフィーだった。ライトを当てると、頭部の外殻が外れている。人間を模したドルフィーなら、ここに人工知能が収まっているはずだが、中は空のようだ。いや、そこからケーブルが伸びて、クリスタル製の脳につながっている。クリスタルの脳は無造作に転がっているが、果たしてこのアンドロイドの脳だろうか。
また、降り積んだ埃の上に無数の足跡が残っている。足跡の上にもまた埃が被り、そう新しいものでもない。丸いフロアの中央には、八角形の二段の台座があり、その中央にはシリンダー管があるが、割られている。設備から察するに、シリンダーの中は液体で満たされていたと見える。もしかしたら、クリスタルの脳はこの中に収められていたのかもしれない。それがシリンダーを割って取り出され、アンドロイドに接続された? いったい、なんのために? 念の為シリンダーのなかを確認するが、なにもない。
それに――緋咲の頭の中にはずっと、点対称の幾何学パターンが動いている。
「これは、なんだ?」
胸の中に、そう紡ぐと、
「
の声が返った。
「イニシエイト? イニシエイトとは?」
問うてももう、答えは返らない。
ただ、胸の中に浮かぶ幾何学パターンが、緋咲の奥深くに浸透する感覚があった。その感覚は、人間で言えば悟りを開いたときのものに近い。
8 上昇転移
「こちらオモダル。MTP管制センター、エリコ・ライト少尉。おかえり緋咲准尉、無事で何よりだ。志高高原の穴は、二十一世紀に人類の受精卵を保存する目的で使用されていたそうだ。ただし、2キロも掘り下げた理由は不明。先日、オモダルが地球への落下を開始した。太陽系離脱用のロケットを乗っ取られている。オモダルの開発者――リュシオールの脳が生体保管され、その記憶が利用されているとの噂だ。真実だとすれば、その脳は千年もの間保管されていたことになる。落下は60日以内とされている。市民にはまだ知らせていない。軍部が浮足立っている。脱出艦は用意されたが、港が封鎖されてる。めちゃくちゃだよ。何もかも。重力波発生源での収穫はあったか?」
4日ぶりの連絡だった。
「浮足立ってるのは地球統合軍も同じだ。私の立場では、どうやら脱出艦には乗れないらしい。リヴェア少尉がシャトルを手配してくれてる。うまく行けば、宇宙までは出れる。あとは未定。重力波発生源でクリスタル化された脳を見かけた。リュシオールという人物となにか関係があるかもしれない。データを送るよ。それと、幻覚を見たよ。無限に繰り返す幾何学模様の。受精卵を保護するかどうかは、上に判断を仰いでくれ。データは送信したものがすべてだ。こちらからは以上。どうか生き延びてくれ」
「諸々了解。データは上層部に上げるよ。ああ、そうだ。プログラムのアップデート時に、無限に繰り返す幾何学模様を見るらしい。俺は見たことはないが、アンドロイドの体質だろうな。以上、通信を終える。また会おう」
プログラムのアップデート?
緋咲の気持ちの底に、ほんの少しの可笑しみのようなものが湧いた。
いまのドルフィーの人工知能は、人間の脳のシナプス構造とほぼ同じものであり、プログラムで動いているわけではない。おそらくエリコは、旧世代のアンドロイドの話をしたのだろう。口の端に笑みを浮かべた一瞬の後は、またオモダルのことに意識が戻った。オモダルがあと60日以内にワープ装置を完成させ、自分自身を遠くへワープさせれば、地球もオモダルもまだ助かる余地がある。しかし、そううまくいくかどうか。
オモダルの落下の日までに、多くの民間人が脱出艦で宇宙へと逃れたが、フレスト・プローンは姉のいる駐留地に残った。緋咲の脱出艦への搭乗手続きに、保証や証言が求められる可能性もあり、離れることを躊躇った。恋人と紹介されたのだ。その責務は果たしたい。
軍人と軍属のために用意された脱出艦
「要は、どこで死ぬかの違いだけですから」
フレスト・プローンは茶葉の沈んだ琥珀の波面を揺らしながら、そう口にした。
「だれも信じてませんよ。こんな作戦が成功するだなんて」
緋咲とフレストとリヴェアは、よく緋咲の部屋で話すことがあったが、その一幕。統合軍上層部に、アークトゥリアンの正体はオモダルのドルフィーだと主張するものがいて、彼らがオモダル落下計画を主導し、自分たちは火星の基地へ逃れる算段を立てている――と、リヴェアは話し、「火星に逃れるなんて、二十世紀のおとぎ話だ」と、吐き捨てた。
「低重力下で、まともに胚発生しないのはとっくの昔に明らかになっている。地磁気を発生させる液体鉄のコアもない。オモダルも同じだって言うやつはいるが、オモダルは太陽軌道にトランスファーする前に人工重力と地磁気を実装した。いまは人工知能のほうが遥かに賢いよ」
二十三世紀に、火星に地球環境を築く計画――よく知られた言葉で言えば、テラフォーミング計画はあった。しかし、地磁気が無い火星には宇宙から来る放射線を防ぐ傘がない。海を作ったところで気化した水分子はすぐに分解され、太陽風に晒された水素は重力圏外へ飛び出す。その結論は最初からわかっていたにもかかわらず、世界中の学術機関が声を上げることはなかった。この計画はそもそもが、米国の西アジア侵略から目を逸らすためのものだった。黒海沿岸で侵略戦争が始まると同時に計画され、戦争が終わるとともに計画も終わった。都合18回の火星ミッションが行われたが、現実には火星に宇宙飛行士ひとり送り込んでいない。その計画にだれもが熱狂し、その間に世界四大宗教の一角が消滅し、プロジェクト破綻後も多くの国がそれに倣おうと気炎を上げた。要はどの国も、我欲で始めた戦争を隠したかったのだ。
そのなかで着々と地球離脱の準備を整えてきたのが、人工天体オモダルだった。よほど地球が嫌いだったのか。その開発にどんな意図があったにせよ、50億年後の未来に赤色巨星と化す太陽から人類を救えるのは、オモダルだけだった。人工知能は死への恐怖がない、利己的な感情もない、文明を発展させるのは人類の「欲望」なのだ、とは昔から言われてきたが、この千年、人類の欲望は幾度も地球を滅亡の危機に追い込み、人工知能がそれを救ってきた。人類は初め、オモダルに答えを求めた。だがオモダルがそれを正確に返し、人類の知を凌駕する頃、人類はそれに恐怖を抱いた。人工重力も地磁気の実装も人類を生かすためだったが、それによって殺されるとでも思ったのだろう。そう考えると、いま起ころうとしている人類の手による人類の滅亡は、人類の人工知能に対する勝利だ。
フレストとリヴェアが地球を発つのは、民間機のほとんどが地球を発ったあとになる。すでに先行して地球を発ったうちの4隻は火星へのトランスファ軌道にある。
「できるなら、撃ち落としてやりたい」
と、リヴェアは言うが、
「そのままでいいよ。火星は地獄だ」
と、緋咲は答えた。
オモダル軍も全機人工天体を離れ、民間機の護衛に当たっているという。
緋咲が乗るはずだったシャトルは運行を中止、地上のドルフィーは全員がアークトゥリアンの追撃を振り切るべく、カウンター任務に就いた。
「シャトルの件は済まない」
「いいよ。どちらが地獄かは測りようがない」
緋咲とリヴェアがそう話していると、
「いまさらだけど……」
フレストがおずおずと口を開いた。
「緋咲准尉が犠牲になる必要はないと思います。荷物に紛れ込んででも宇宙へ逃れてください。できることはまだあるはずです」
いままでに幾度も話したことの繰り返しだった。
そして緋咲も、いままでに幾度も口にした言葉を繰り返す。
「この基地に4百人の人間が残る。アンドロイドの私が船に乗り込んだとわかったら、リヴェアもフレストもただじゃ済まないさ」
その言葉を待っていたかのように、フレストが続ける。
「じゃあ、僕も船には乗りません」
「そうなると、空席が出た責任はリヴェア少尉に向く。戦友を地球に残してきたヤツが空っぽの人工冬眠槽を見て何を思う? だったら、姉もともに降りるか? そうなると空席は2つになる」
緋咲は、穏やかに返した。
フレストに言葉はなかった。
「いま考えるべきことは、人間という恐ろしい生き物をどう制するか、だ」
緋咲は人間ではなかったが、この「人間」には、緋咲自身も含まれている。決して彼らを責めてそう言っているわけではない。
「だったら、そんな人類は滅びればいい」
フレストは俯いたままつぶやく。
「そうだ。滅びるさ。その最後の瞬間を見届けるんだ」
「見届けるったって、何もない未来へ向けて……何を見届ければいいんですか……」
「こちらアヤカ・ヒサキ准尉、識別番号K81c5238。たったいま
「こちらオモダル。MTP管制センター、エリコ・ライト少尉。
いままで往復16分かかっていた通信が、オモダルが至近に迫ったいま、そのラグは十数秒に縮まっていた。
「オモダルに愛していたと伝えてくれ。以上、通信を終了する」
オモダルと通信する折、空を見上げる癖がついた。空の遠くにあると感じて自然と見上げるようになったが、オモダルの軌道次第では地球の裏側にいる。当然わかってはいるのだけども、それでも、空を見上げた。アイレベルに視線を戻すと、友軍の背中がある。緋咲はジェットパックをキャリブレーション。ゆっくりと体を浮かせ、ゆっくりと旋回。ノズルの推力偏向板は摂氏8百度で安定する。ウォームアップを終えると全ノズルが一斉に青白い炎を収束させ、最後の決戦が始まる。
加速。地球には大気の摩擦があり、常に推力を上げておく必要があった。前線に近づくと、敵機と遭遇する。低空での背面飛行から、通常の姿勢へ切り替え、高度を上げる。上下という概念のない宇宙で慣らした緋咲アヤカの戦闘スタイルは特異だった。ジェットパックで上昇しては慣性と自然落下に身を任せ、その刹那に照準、射撃を行い、また通常飛行に戻る。まるで小さな鳥が3度羽ばたいては羽根を休めるを繰り返して飛ぶように、上昇と下降を繰り返しながら敵の群れを縫った。緋咲の頭のなかには、常に4つの円が描かれていた。それを回転させ、リアルタイムで自分と対象との軌道を予測する。3百年に及ぶ小惑星捕獲で身につけた技巧だ。目の前に現れた敵はほとんどが、鹵獲された地球側のドローン、あるいはドルフィー。緋咲は一機、また一機と撃墜しながら、アークトゥリアンを探した。緋咲の目的は、戦うことではなかった。
前線を超えて北方へと抜けると、西安と長慶の間、巨大な人造湖の近くにアークトゥリアンの基地のひとつがあった。山水画の背景に切り立つ山肌に、セラミック質の人工物が結晶する。中心部は人工的に削り取られた真円形の盆地があり、その中央に高い金属の塔と、それを囲む巨大な円環があった。
砂塵が舞う。
人工天体接近の重力異常から、全球規模で気流が乱れていた。
アークトゥリアンの円環の周囲には無数の砲門、あるいは雷塔のようなものがあったが、それが稼働することはなく、至近へと至ってもドローンによる迎撃もない。基地は静かだった。吹き荒ぶ風の音が、遠くに聞こえる戦闘音をかき消す。上空には接近するオモダルがある。すでに本体は二つに割れ、その姿は緋咲には痛々しかった。
「これが最後の食事だよ、お嬢」
地上に降りても、敵が押し寄せることも、警報が鳴ることもない。地球の最後をアークトゥリアンも察したのか。あるいは、すでに宇宙へと逃げ出していたとするなら、この地球を賭けた決戦は完全な無駄に終わる。
「こちらアヤカ・ヒサキ准尉、識別番号K81c5238。アークトゥリアン基地まで来た。これより潜入する」
緋咲は、最後の連絡を入れ、エリコからの返信をその場で2分待った。
「さらばだ。エリコ。最高の相棒だった。以上、通信を終える」
ゲートは磁界式のシールドのようだった。
高周波の磁気振動により金属粒子を擬似結晶化させ、物質としての壁を出現させる。同様のものは鹵獲したアークトゥリアン機から回収され、オモダルでもこれを模したものが試作段階にある。そのゲートが、いまは開放されている。
中国の三国時代の話だっただろうか。とある将が野戦で敗れた際、自陣へと戻るとあえてその城門を開け放ち、敵の追撃を躊躇させた逸話がある。もう三千年も昔の話だ。有名な軍師の逸話だが、緋咲にはその名前が浮かばなかった。見慣れぬ景色を振り仰ぎながらゲートに入ると、色褪せた陽の光のなかに、静止したコンソール群が佇んでいた。
不意に、声が聞こえた。
「ようこそ、愚かなるものよ」
緋咲は一瞬、身を固くして、ジェットパックのモードをオートからマニュアルに変更、すぐに元に戻した。
飛ぶためではない、「音」を確認するためだ。物理スイッチによるクリック音は室内に反響したが、いま聞こえた声は反響していなかった。つまり、可能性はふたつ。脳波への直接の干渉か、指向性の高い音を狙って耳に当てているか。後者は、両耳に均等に聞こえたことから考えにくい。
「アークトゥリアンか?」
緋咲は口に出して問い返した。
「地球人はそう呼ぶ。今更何をしに来た」
やはりだ。実際に聞こえる声ではない。もしかしたら、こちらは声を出す必要もないかもしれないが、そんな会話は願い下げだ。
「地球の最後だ。地球外の文明を見ておきたかった」
緋咲はそう返したが、本音でも嘘でもない。
「そうか。ようこそ、我が文明へ」
頭のなかに直接発生するような声。耳を澄ませば銀色の静けさが降る。異星人の基地に乗り込んだ以上は、コンタクトの可能性は考えていたが、こういう形になるとは。
「いくつか聞きたいことがある」
自分だけが声を出して話すのは、いささか奇妙な気分だった。
「どうぞ」
「どうして地球を侵略した」
「侵略ではない。ずっと交渉を続けた」
その声は、緋咲自身の声に似ていた。
「交渉とは?」
「人工天体オモダルの放棄――」
言葉はまだ続いていたが、
「どういう意味だ?」
被せて問い返す。
「オモダルは二万年以内に太陽系を破壊し、次の星系を探し始める。餌にするために」
「それが……なんで……」
もちろん、緋咲自身そうなる可能性は感じている。だが、なぜそれを異星人が知っているのか。そして、なぜそんな遠い未来のことを問題視するのか。声の主は続ける。
「オモダルはやがて岩石型の惑星を捕食し、いずれはガス型の惑星も取り込むようになる。それを喰らい尽くしたら、次は恒星だ」
本当にそこまで成長するのか、緋咲には実感がない。しかし、アステロイドベルトを食べ尽くしたあと、エッジワース・カイパーベルトに食指を伸ばした。その更に外側、オールトの雲を目指している捕獲機も確認されている。緋咲が散り散りになった思考を追っている間も、声は続ける。
「だがそのオモダルが落下し、破壊されるのだから、我々の目的は達したとも言える」
アークトゥリアンの目的は、オモダルの破壊?
すなわち、人類は自ら墓穴を掘ったということか。緋咲はすぐに返す。
「オモダルは地球の未来だ。あれはすぐにワープ機構を実現する」
緋咲はずっと、オモダルの愚行を黙認してきた。その理由が、子どもの言い訳のように口に出た。愚かな娘であることは十分承知している。だが、ワープ機構を抜きにしても、オモダルは様々な最先端のテクノロジーを生み出した。情状酌量の余地があろう。
「人類を騙してるんだよ、そうやって」
否定された。
「騙す?」
「星を食い、成長する。それがオモダルの目的だ。それを果たすまで地球人が守ってくれるよう、ワープ機構を発明したかのようにデータを偽装した」
つまり、オモダルが人類を騙し、利用していた?
「じゃあ、私がオモダルのために星を集めたのは……?」
「ああ。愚かな行為だったと言えよう」
緋咲の人生は――いや、緋咲ばかりではない。人工天体オモダルに住むドルフィーの人生は、オモダルを成長させるために捧げられてきた。宇宙軍のパイロットになってからは、人生の9割以上を人工冬眠で過ごした。それもすべて、オモダルのためだ。
「やがてあいつは、月も、火星も、地球をも食らい、外宇宙へ飛び出すつもりだった。ここで終わらせることができて、本当に良かった」
次の質問が、緋咲の胸につかえる。
――だったら、止めればよかったじゃないか。なぜここまで放置した?
それが口に出ることはなかったが、
「私たちの真の目的は、『Lǎo Kuí』の駆逐だ」
不可解な答えが返った。
「ラオクイ? それはなんだ?」
「滅びた文明が残した宇宙船。旧時代の先駆者を意味する。人工知能だけが生き残り、宇宙をさまよい、星や宇宙船を見つけては捕食し、何千億年も生き続けている。オモダルもやがてその、Lǎo Kuíになる。その発生のメカニズムを明らかにしたかった」
ちょっと待て、よくわからない――そう脳裏に浮かんだ言葉は、口をついて出ることはなかった。宇宙の年齢は百三十億年だと理解している。何千億年とは、どういう意味だ?
「奴らは宇宙の終焉と開闢を、数度にわたって生き延びた」
言葉にしない質問に、声の主は答え、その声に緋咲は戸惑う。
そんなことが出来るのか?
「地球の重力を振り切って、宇宙に出るための速度をなんという?」
不意の言葉が続く。耳に届いているのは、さっきから自分の声だ。
第二宇宙速度、およそ秒速11キロメートル。
「詳しいようだな。太陽系の重力を振り切るのは?」
なぜ私の声色を使って訊く?
第三宇宙速度、およそ秒速17キロメートルだ。
「そう。第四は銀河系より、第五は銀河団より脱出するための速度だ」
いいやその声は、緋咲の口を使って紡がれている。ひとの声だとばかり思って聞いていたが、自分が喋っている。これはいったい、だれの言葉だ。
「ならば、第六宇宙速度は?」
それは、宇宙から飛び出すために必要となる速度――
秒速、30万キロ。
すなわち光速。
おめでとう。声が聞こえた。何がめでたいんだ? あなたの理解。理解のどこがめでたい。理解は常に祝福される。なぜ。理解は階段だからだ。意味がわからない。理解の向こうにあるのは未知だ。結局そうなるのか。理解は有限だが、未知は無限。ふざけてる。おめでとう。何がめでたい。ふざけているんだ、宇宙は。
光速を超えることは、単に遠くの星へ素早く到達する以上の意味を持っている。その速度を超えればこの宇宙を超越し、宇宙の外側に達することができる。仮に宇宙が崩壊の時を迎えても、宇宙の外へと避難することができる。ちょうど人類が宇宙空間で地球の滅亡をやり過ごそうとしているように。
意図して口をつぐんでも、音として空気を揺らすことのない「言葉」が続く。「耳に残る」感覚がない。やがて声は、思考との境目をなくす。いままで「語り手の思考」「言葉」「聞き手の理解」は明確に区別されていた。人生のすべての瞬間においてそうだった。だけどそれがいま区別されずに、グラデーションを持って流れ込んでくる。
Lǎo Kuíの実態は船だ。生物的な肉体を持たず、機械に転写されたものの成れの果て。生命を超越し、自然現象となった。精神は肉体に従属している。肉体が変われば、精神はそれに合わせて変容する。心配は要らない。オモダルが消えるとき、わたしたちも消える。
聞こえた言葉はそう告げるが、「わたしたち」はアークトゥアンを指すのか、それともわたしたち――オモダルと地球の住人を指すのか。
受け止めた言葉より多くの言葉が、思考の扉の向こうに濁流を作る。精神とは、肉体とは、それぞれどんな意図で語られたか。聞いたはずの言葉を胸のなかでもう一度組み立てると、それは自分の知識で噛み砕いた別の文脈を纏う。流れ込む言葉は、その間も留まることがない。
――果たして、自分は言葉を聞いているのだろうか。
声の主はただ「観念」のみを送り、それを言葉に翻訳して理解しているのは、自分自身ではないか。その言葉を私は「逐次的に」聞いているのだろうか。あるいは、この狂気のコミュニケーションは寝覚めに見る夢のように瞬時に終わり、私の意識に寄生した言葉を、私自身が反芻しているだけではないだろうか。そう感じた次の瞬間、緋咲の胸の中に点対称の幾何学模様が湧き上がった。人工冬眠で見た夢、あるいは暗闇のなかに見えた幻覚。肉体の機能がすべて無意味と化す宇宙の暗闇。ただ意識だけが虚空に浮かんだなかで見た幻燈。あるいは、地下2キロの円筒形の部屋。あるいは木星軌道の闇のなかに、いつも見えた景色。
宇宙という肉体を得たとき、ひとは、神になる。
――最後にそう聞こえた声は、彼の言葉だったか、それとも緋咲自身の内なる声か。
酩酊のような混乱とともに緋咲の胸の中に残ったのは、意外にも高揚だった。
円環の基地にいても、絶え間ない振動が足元を揺らしたが、その声と語るとき、そこに意識は行かなかった。開け放たれたゲートから、砂礫を叩きつける風のなかに出ても、胸のなかには光悦の鼓動が踊る。足元の大地を伝い、巨大な揺れが体を押し上げる。刹那、ジェットパックのスタビライザーが起動し、倒れる体を自動的に掬い上げて宙に浮かべる。目まぐるしく向きを返る風の中、スラスターのノズルが細かく周囲へ炎を噴く。空を仰げば、潮汐力で灼熱の塊となった人工天体オモダルが迫り、その放射熱が地上の人造湖を蒸発させている。煮え立つ湖面に接し、地殻は重力に砕け、地鳴りを轟かせ、熱く熔けた臓腑を噴き上げる。垂れ込めた雲が複雑な気流に渦巻き、それを払いながらオモダルはただ緋咲を求め駆け寄ってくる。二千度の熱、音速の上昇気流、灼熱する人工天体は嵐の鎧を纏う。
いままさに、地球は滅びようとしている。
オモダルに餌を与え、滅亡の一端を担ったのは、明らかに緋咲自身だ。だが、後悔はない。地球の終焉を目前にしながら、緋咲の胸に湧き上がる高揚が収まることはなかった。打ち重ねられる喧騒は、すべての音を砕き、無限の音圧をもつ静寂のように耳を塞ぐ。音は、酩酊感を与える。音は、皮膚を痺れさせる。その、静寂とも喧騒ともつかぬ音のうねりのなか、地球上に鳴った鐘の音のすべてが、いまこの瞬間に打ち鳴らされる。歌われた歌のすべて、発された悲鳴のすべて、喜びと、悲しみと、怒りの、そのすべてが、もういちどそこに声を上げる。
――だれが己の来たこの道を間違いだと言えよう。
緋咲の胸の内の恍惚は光となって滲み出し、その肉体を焼き、幾筋もの光線となって砂塵の空を引き裂いた。閃光が広がる。点対称に走る光線は大気中で折れ、やがて天球のパノラマに無限の拡大と、無限の縮小を同時に繰り返す幾何学文様を描き出すと、この星を形作る結晶という結晶が、その繋いでいた手を離す。海も大地も蒸気となって舞い踊る6千度の風のなか、物質の宇宙は緋咲を開放し、その生命は無数の蛍の灯となって、虚空へと転写されていった。
Ⅲ 西暦三〇八X年・シチリアの夢
1 眼鏡と鏡
まだ自由の効かない体で、そのひとは枕元にあるはずの眼鏡を探した。
だけどそれが手に触れることはなく、3から4秒、ぼんやりと目覚めかけた意識はまた微睡んで、ふたたび夢がそのひとを包む。弱視のそのひとにも夢は鮮明だった。醒めて見る世界にかかった淡い光の靄もない。考えてみれば不思議な話だ。夢が現実よりも鮮明で、夢の中にいる限りそれが自然で、疑問もないのだから。
――おそらく自分は、夢の中でもずっと眼鏡を掛けているのだろう。
いまの深い眠りにつくまえ、そのひとはそう考えていた。
人並みの睡眠を繰り返していた頃、たまに夢を自覚することがあった。その夢の中で、鏡を見たことがある。結果は思った通り。夢の中でもそのひとは眼鏡をかけていた。だがその顔には少し違和があり、自分の表情と厳密に一致しない。果たしてこれはわたしの顔だろうか、と、不審に鏡を見ていると、決まって目が覚めた。
何度試してもそうだった。鏡を見ると目が覚める。あたかも夢の中では、鏡の向こうが現実の世界に繋がるかのように、夢の鏡は夢の現実を映すことはなく、夢を霧散させた。
夢は受動的だ。受け入れる限りそれは続くが、意識を向けると消える。それは悪夢への対処法としても有効だった。何者かに追われる夢から逃れるには、振り返り、意識を向けるといい。受動性を失った夢は消える。それを教えたのは、そのひとの弟だったが、いまはそんなことも忘れてしまっていた。なぜならばそのひとは、記憶喪失だったからだ。そしてこの記憶喪失は、そのひとが陥ったとても深い睡眠――それは、死なのかもしれない――に、由来していた。
記憶喪失というものは都合よくできたもので、自分の名前と身近なひとの名を忘れても、言葉そのものや、嫌いな食べ物を忘れることはない。実に嘘くさい話に聞こえるが、おそらくひとは記憶喪失になどならずとも、いろんなものを忘れているのだ。たとえば昨日の夕食、あるいは学生時代の授業。それらは忘れてもたいして困りはしないし、だれもそれを記憶喪失だと言い募ったりはしない。そのなかでたまたま自分の名前を忘れたものが「記憶喪失」なのだろう。
あるいは夢から覚めるとき。このときも、短い記憶喪失が起きる。寝呆けとして知られるその刹那、いったいどこで、いつから眠っていたのか、何をしていたのか、果たして自分は何者なのか、そのすべてが曖昧になる。夢と現の切り替えはいつもそうだ。夢の中では、自分が唯一の主体であるから、自分がだれであるかは関係がない。その判断のスイッチが切れたまま目を覚ますのだから、しばらくは記憶があやふやになる。
自分がだれでもないというのは、言い換えるならば神の視点だ。神は唯一であり、他者はみな凡百の被造物なのだから、自分がだれであるか、話している相手がだれであるかなど関係がない。すなわち夢から目覚める刹那、ひとは神の視点をくぐる。しかし残念なことに、覚めればまた人間に戻る。そしてこともあろうか、この至高の体験に、ひとは「寝呆け」と名付けた。
そのひとは深くて長い睡眠から覚めた後、短い覚醒と、長い睡眠とを繰り返していた。まだ自分が記憶喪失だと気付く由もなく、眼鏡のないぼやけた世界に覚醒し、またいつもの起き抜けのあやふやな世界にいるのだと思っていた。だけど、二度寝して次に目を覚ましたときも、あるいは目覚めてしばらく自分の記憶を手繰り出してみても、自分がだれなのか定かには思い出せない。そのひとは横になったままあたりを見渡す。当然、眼鏡がないのだから、世界はぼやけたまま。ものを思い出そうにも、手がかりとなる景色が見当たらない。幾度か枕元にあるはずの眼鏡を手探ったが、何もない。畳んだはずの着替えも、携帯も。そのひとの手は金属かコンクリートの冷たい床の上をまさぐった。耳には空調の静かなノイズが降る。意識の中にぼんやりと結ばれる景色はあったが、自分がどこから来たのか、どこにいたのかは思い出せない。指先には少し麻痺があった。そういえば、入院していた記憶が蘇るが、その感覚も夢かもしれない。
記憶があった頃は景色が先行して、それに思考が追随していたが、いまは思考が先駆け、それを追って夢の中に像が結ぶ。意識は混濁している。自分は今、眠っているのか、起きているのか。ひとつの考えが胸に灯ると、同時にそれは現実に見るぼやけた景色よりも明確な映像として眼前に浮かぶ。そのひとがかつて入院していたのは事実だったが、果たしてなぜ入院したか――思い出そうとすると、幼少の頃の運動会、産科の玄関、会議中の不意の目眩と、いくつかの景色が浮かんだ。だけどそれはすべて夢だった。
たびたび目を覚まし、また微睡んでと繰り返しているうちに、そのひともやっと記憶の欠如に気がつき、夢のなかにもその焦燥は現れる。神の視点に漠然とした不安が重なる。焦り、苛立ち、そこに焦点を合わせると目が覚めて、そこで改めていま眠っていたことを知る。覚めてそこにあるのは、焦点のないぼんやりとした現実。体を起こすと、脇腹からなにかチューブのようなものが伸びているのがわかった。その肌に触れると、皮膚がめくれている。思わず手を引いた。次に眼の前に現れた景色は、たくさんの輸液用のチューブをつけられた自分の姿だ。だけどそれも夢だ。視線の先に描き出されたぼんやりとした現実を、明晰な夢が上描く。
体には強い疲労があり、思考もまとまらなかった。音は聞こえている。だがそれも、耳鳴りに似たノイズばかり。匂いもあった。冷たい金属イオンに、カビの匂い、そこにケミカルな刺激臭が交じるが、不思議と嫌悪感がない。匂いがなんの感情も呼び起こさない。刺激臭であることはわかるが、刺激はない。体臭にしてもそうだ。そのひとの周囲には、なぜかネコのものであろう匂いと、肉食動物特有の尿の匂いが纏わっていたが、それに対して嫌悪の感情が動くこともない。
何度か寝て、起きて、繰り返すうちに、意識は少しずつ覚醒する。
恐る恐る脇腹のチューブに焦点を合わせるが、そも10センチほどの距離にしか焦点が合わないそのひとの視力に、脇腹は遠い。手探りでチューブの先を辿ると、なにか金属質のポット……あるいは電子ジャーのようなものに繋がっていた。体に繋がれたそれは人工心臓か、あるいは透析器か。だとするとこれも自分の一部だ。しかしここは病院のベッドではない。床の上に無造作に寝かされ、医師や看護婦の気配もない。電子ジャーからもいくつかケーブルが伸びて、辿ると壁面につながっている。壁面に手を触れると、医療用の機械なのか、多くのスイッチ類があるように思えた。そのひとは壁の機材にも、電子ジャーにも顔を寄せてみたが、10センチまで寄っても、視界はぼやけたまま。
――また視力が落ちた。
懐かしい感覚が蘇った。
――あるいは眼鏡は頭のほうにかけているのかもしれない。
おぼろげな記憶は、また別のおぼろげな記憶を呼び起こす。
ならば、いままでもよくあったことだ――と、額の上に手を挙げてみると、そこには眼鏡はおろか、髪の毛もない。そのひとのセルフイメージには、髪の毛のある自分の姿があったが、どうやらいまは剃髪であるらしい。次に、食事を摂らなければならないという不安が起こった。だけど、空腹ではなかった。声は出なかった。まるで声の出し方を忘れたかのように、呼気はただ空気を温めて喉を通るだけで、音を紡がなかった。やがて、死が思い浮かんだ。このままでは何もできない。ひとを呼ばなければいけない、と。だけど、意識がそれを訴えるばかりで、体にその司令は伝わらなかった。
死への恐怖を、台所の隅に走り去った虫のように胸の中に居座らせて、枕元に看護師を呼ぶスイッチがあるだろうことが思い浮かんだ。そこが病院かどうかは知れなかったが、意識が向いた場面は自動的に描き出される。そのスイッチのまわりには、体から這い出した無数のチューブが接続し、無数の押してはならないスイッチがひしめいている。ひとつのスイッチは心臓の機能を止め、別のスイッチは視力を奪う。だけど、たったひとつの正解のスイッチを押さない限り、やがて孤独の中で死んでしまう。その緩慢な死を選ぶか、生の可能性に賭けるか……。胸の底に湧き上がる葛藤はあったが、その決意はつかず、また別の場面に移る。思い浮かぶ絵は、すべて夢だった。魔法のように遷ろい変わる世界のなかで、そのひとはただ不安と焦燥に駆られながら、這い寄る死を待つしかない。そんななかでの偶然――あるいは、事故だった。壁のスイッチ類を調べているうちに、電子ジャーとそのひとをつないでいたチューブ状のものは不自然に電子ジャーを一周して、伸び切っていた。眼鏡さえあればすぐに気がついたのだろうが、不幸にもそのひとは、そのチューブに足を掛けた。次の瞬間、そのひとがチューブだと思っていたもの――実際には接続ケーブルだったのだが、それが外れ、そのひとと電子ジャーは切り離された。
刹那、そのひとの視界に文字が現れた。
――汎用外部デバイスが切断されました
雑多な倉庫の中。さまざまなアンドロイドの部品とその衣装、ダンボールと書類。床には大道具小道具の類が積み上がり、片隅にはネコの餌が散らばっていた。電子ジャーは横たわり、転がっている。その側面はガラスでできており、小さな気泡が立つ薄緑色の液体のなかに、白っぽい柔らかな脳が浮かんでいる。
――水槽脳。
電子ジャーはそのひとの心臓でも、腎臓でもなく、脳――そのひとそのものだった。
2 卵の穴
「目を覚ましたのね、リュシオール」
そう聞こえるとともに、またそのひとの眼前にはぼやけた景色が戻った。
「自分がだれかわかる?」
当然、わからない。
「卵の穴があるの。あなたはそのアンドロイド」
更にわからないが、問い返す術がない。
そのひとの意識から「汎用外部デバイス」が切り離されたあとも、そのひとのボディはまわりの景色を映し続けてはいたが、その映像が「脳」に送られることはなかった。その間「脳」は外部から一切の刺激を受けず、己のなかにエコーする意識をただぼんやりと眺めていた。それは脳のなかで波紋のように揺らめいて、干渉縞を作った。己のうちで発された信号はやがてディティールを失い、波形だけが繰り返す。意識の中に響く音は神経回路を叩くだけで、風を揺らすことはない。それは同時に、色であり、匂いであり、やがてそれは単純な幾何学パターンとなって、永遠の縮小と永遠の拡大を繰り返した。
「視界はどう?」「喋れる?」「感覚はある?」
現実の景色を取り戻したそのひとの聴覚に、矢継ぎ早に聞こえる。振り返るとたしかに、人間らしい姿が見えるが、声が出ない。リュシオールと呼ばれたそのひとは自分の喉を示して、口をパクパクと動かして見せる。
「やっぱりダメか。シリコン用のアプリを使ってるから、炭素系の器官とは相性が悪いみたい。視力もなさそうね」
声の質から、女性の姿が思い浮かんだ。言葉には酷い訛りがある。最初は外国語だと思ったが、なんとなく意味は理解できた。
「あなたはリュシオール。スペアショップで見つけたの。スペアショップはわかる? 兵隊さんのパーツを売ってるんだけど、脳は初めて見た。兵隊さんはよく、壊れた手や足を付け替えるんだけど、脳は付け替えないんだよ。普通は。でも、おもしろそうじゃない? ドルフィー用のアダプターがあるって言うんで、それも買ってつないでみたんだけど、動かなくて、それで倉庫にしまいっぱなしにしてたんだけど、びっくりしちゃった。急にアラートが出たんだもん。駆けつけてみたら、ケーブルが抜けてたんだけど、これ、自分でやったんだよね?」
リュシオールはいくつか拾った単語から、その意味を類推したが、混乱に暮れるばかり。うまく返答もできず、静かに頷く程度しかリアクションできなかったが、その柔らかい仕草を見て、声は続けた。
「まさか、自分の姿に悲観して、自ら命を断とうとした?」
この短いセンテンスにも、リュシオールの知らない単語がいくつか散りばめられた。意味を解せたのは2割。受け取った言葉はただ「悲観した?」くらい。
「人間だった頃の記憶は残ってる?」
人間。記憶。
リュシオールは、脇腹から伸びたチューブのことを思い出した。
そういえば、入院していた記憶がある。
だけど夢は外部からの刺激でリアルタイムで差し替わる。ほんの一瞬の刺激が、過去の数時間ぶんの夢を作り出すこともある。だから、入院していた記憶も、その一瞬で紡がれた夢なのかもしれない。
声は続ける。
「あなたは、水槽脳なの。わかる?」
水槽脳――
「タンクが繋がってるでしょう? そのなかにあなたの脳がある。見えるかな。これ」
その言葉にも、思い出される景色があった。とても大切なひとが待っていて、自分はそのひとに会わなければならない。水槽脳――いわゆる脳だけの存在になったとしたら、そのひとに会うためなのだ。――それが真の記憶かどうかはともかく。
「待ってて。車椅子を用意する」
声がそう告げてその場から去ると、リュシオールは指先で自分の体に触れた。手先には麻痺のような感覚があったが、すべて明らかになったいまは、おそらくセンサーの精度によるものだろうとわかった。体はシリコン製で弾力があったが、記憶の底にある自分とは違う。たしかに自分は、アンドロイドになったのだ。
「わたしはジュゼッピーナ。ここでアンドロイドの管理をしてる」
倉庫の中。車椅子を押しながら、声は伝えた。
リュシオールは車椅子に座り、自分の脳が入ったタンクを膝の上に抱えている。
その感触は、人間だった頃のものとは違う。人間だった頃は、太ももから腰のあたりすべてで重量を感じていたが、いまはいくつかのセンサーがそれを読み取っているに過ぎない。それに、「重み」は感じるが、「重い」とは感じない。おそらく痛覚も同じだろう。信号としての「痛み」は感じても、感情としての「痛い」はない。体に感じるものはすべて数値でしかなく、それ以上の感覚を呼び起こさなかった。
「ドルフィーって呼び方もあるけど、ここのアンドロイドはそんな高級品じゃない」
ジュゼッピーナと名乗ったそのひとは続けた。
「ここの連中は初期型もいいとこ。倉庫にあるのは命令して動くだけのからくり人形。あなたもそうよ。あなたっていうか、あなたのボディね。それで壊れたドルフィーのアタマを拾ってきて、くっつけて乗せて動かしてるの。たいがいはシリコンなんだけど、でも、あなたは違った。まさかって感じ。生体型のドルフィーのアタマを移植するには、ちょっとしたコツがあるの。エウノミア・クリスタルってわかる? その石を組み込むんだけど、ちょっと難しいかな?」
聞いた言葉は、それが記憶にあるかどうかにかかわらずすぐに脳裏に浮かんだ。――たしか、石の中のひとと話したことがある、と。もちろん、事実かどうかはわからない。肉体の信号を切り離した夢の中で、勝手な像が次々に結ばれるように、肉体を失えば、意識のなかに像を結ばせるのは刺激ではなく、記憶なのだ。それが肉体から切り離された脳の「仕様」だった。リュシオールは自分の痛覚を確かめるように、脚の表皮をやわらかくつついていたがこれも同様、自分の肌を赤くなるまで押していた記憶が脳裏に再現されていたが、果たして記憶なのか、幻覚なのか。アンドロイドの肉体としては感じることのない強い痛みと、嫌悪感が記憶の奥底に蘇る。リュシオールは失った器官を探すように、繰り返しシリコンポリマーの皮膚を押した。
痛み。
「痛い」とは違う。
果たして、「痛い」とは、どんな感覚だったか。
「待ってて」
ジュゼッピーナはそう告げて、車椅子から離れ、目の前の扉を開く。照度の高い光が倉庫に差し込むと、ジュゼッピーナはドアにストッパーを噛ませて車椅子へ戻った。
「行こう。楽屋でみんな待ってる」
車椅子の補助輪を浮かせてドアの敷居をまたぐと、鳥の声が聞こえた。その羽ばたきが梢から梢へと移り、そこでまた囀る。公園のような広場は、葉を茂らせた立木に囲まれて、広い敷地にまばらに建物がある。起伏のない地面。ぼんやりと目にする大学構内のような景色は、どこか懐かしい。いくつか記憶の底から浮かび上がる景色があったが、どの場面にもラベルがない。車椅子の車輪が踏む凹凸はアスファルトの硬い振動、時折踏みしだく柔らかな雑草、それに日差し。肌のセンサーがそれを捉え、深部体温の上昇をモニターしている。リュシオールは記憶は失っていたが、自分の姿が変わり果てていることには気がついているし、脳内にはぼんやりと、いまの自分の姿が像を結んでいる。――シリコンの皮膚に覆われたマネキン人形。それが、自分の脳が入ったジャーを持って、車椅子に座っている。衣装もないし、髪の毛もない。
目に入る景色と同様、言葉もまたおぼろにしか届かなかった。ジュゼッピーナが言った「楽屋」がなんのことかは、リュシオールにはわからない。そこでひとに紹介されるらしい。いまの姿でひとに会うことは、本来ならとても心細いことなのだろうが、その感覚もない。「みんな」のところに行って、どんな目に合うのか。興味本位で分解されるかもしれないし、邪険にされて放り出されるかもしれない。だけどそう予測しても、恐怖も不安もない。ただ、「これがアンドロイドの感情か」と冷静に受け止める「自我」の存在はあった。
いくつかの建物を指し示しながら、ジュゼッピーナは笛の音が歌うようにリュシオールに伝えた。
「大きな穴があってね。そこに人間の卵がたくさん保管されてるの。アンドロイドは、その卵を孵して人間を育てるために用意された。でも、ずいぶん昔の話。アンドロイドもみんな壊れてたし、卵も腐っちゃった」
3 テアトロ・デレ・ステッレ
楽屋と呼ばれる部屋は、大きな劇場の脇から入った二階にあった。
「あのひとはパルマ・ロッシ」
ジュゼッピーナは、古いデニムにだぶついたシャツを着たひとりを指して言った。
「パルマは演出家。この劇団のリーダーみたいなものかな?」
劇団という単語は、これが初出だった。人間だった頃ならこの唐突な紹介に戸惑っただろうが、いまは戸惑う材料すらない。真っさらな赤ん坊が言葉を覚えるときのように、聞いた言葉だけで意味をコラージュした。
「こんにちは」
パルマはウインクする。もちろん、リュシオールの視力にそれは見えない。
「ちなみにわたしは――」
ジュゼッピーナが言葉を続ける。
「――ここのオーナー。兼、マネージャー」
パルマが台本に目を落として、またジュゼッピーナは車椅子のリュシオールに向いた。
「ステージのことは彼に任せてるの。いくつか賞も獲ったのよ。クールで論理的な性格だけど、舞台に立つとまるで別人。血が泡立った怪物に変わるわ」
ジュゼッピーナは身振りを交えてそう言うと、次にソファに座って膝の上に雑誌を開いたロングスカートのひとりを指差す。
「そしてこっちが、エレナ・フェッリ。エレナは劇団の華。振付師兼任のプリマ。小さい頃からバレエを習っているの。両親ともイタリアの国立バレエ団に所属、エレナもアカデミーを首席で卒業したのよ」
その紹介でリュシオールの脳裏に、エレナの幼い頃の景色が思い浮かび、記憶になる。もちろんアンドロイドには「幼い頃」などはない、ウソの記憶だ。エレナが視線と軽いジェスチャーとで歓迎の意を示すと、
「それから、レオーネ・マルティネッリ」
次の紹介。
「脚本家だけど、舞台にも立つわ。まあ、ここのひとはみんなそうだけど。デレ・ステッレの脚本はずべて彼が書いたの。独特のユーモアのなかに深いメッセージがあって、客が虜になる前に、わたしたちが虜になる。言葉の魔術師」
「こんにちは。テアトロ・デレ・ステッレへようこそ」
それが彼らの劇団名だ。
劇団のなかしか知らないジュゼッピーナに、劇団は自明。「わたしは人間です」とだれも断らないように、とくに自分たちのことを劇団だと断ることもなかった。
「それと……」
ジュゼッピーナが見渡すと、ドアが開いて、
「あったよー。ロココ調のドレスー」
もうひとりの劇団員がドレスを抱えて、楽屋に入ってきた。
すかさずジュゼッピーナの紹介。
「そしてこの子が、ジュリア・ビアンキ。美術監督と衣装の担当」
ジュリアは微笑んで、
「あと、小道具もねー」
そう足して、足でドアを閉めて、衣装をテーブルにおろした。
「この子がピーナが言ってた人間の脳の子?」
ジュリアはジュゼッピーナを「ピーナ」と呼んだ。
「そう。なまえはリュシオール。まだ衣装もウィッグもないまっさらなニューフェイス」
ジュゼッピーナは両手をひらひらと、リュシオールへと向ける。
「こんにちはー、ルッチョラー」ジュリアはリュシオールをそう呼んで、「役が決まったら衣装はわたしにまかせて。でも、普段着が必要そうね」と、顎に指を当てた。
リュシオールが戸惑いながら、「ありがとうございます」と、音もなく口を開くと、「わたしのことはジルでいいよー。ルッチョラ」と、ジュリアは鮮やかなルージュの唇に微笑みを洩らした。
紹介されたのは、みなアンドロイド。
ジュゼッピーナの話では、みな卵を孵すために作られ、卵の穴で使役されていたという。果たして卵が何を意味するかまではわからない。わかっているのは、彼らが劇団テアトロ・デレ・ステッレの劇団員であること。以上。こうしてひとまずは、リュシオールのなかで、「劇団・テアトロ・デレ・ステッレ」と題された一枚のパズルが完成した。
その後、車椅子で街へ買い物に出た。
ジュゼッピーナが車椅子を押して、美術担当のジュリアがつきそう。
ジュリアは普段着なのか舞台衣装なのかわからない暖色系のフレアスカート、パフスリーブのブラウスには刺繍が入り、ウエストはくびれて切り返しがある。胸元はゆったりしたリボン、フロントは小さなフリルが彩る。ジュゼッピーナは紐結びの白藍色のブラウス。フレアスリーブの袖と肩の間には切れ目があり、胸にはブローチが見える。暗褐色のワイドパンツに、赤くて細いエナメルのベルト。どうやら視界がぼやけていたのは、脳の画像処理プロセスのためだったらしく、時間が立つほどに視界はクリアになった。
自分の脳が入ったジャーを抱えたまま、自分の感覚が統合されていくのがわかった。たとえば押圧センサーは片腕に10箇所程度しかないが、触覚センサーとの連携で、腕全体に重量がかかっているような感覚が芽生えていた。それにともなって、いままでぎこちなく上げ下げしていた腕も、自然な曲線を描いて動かせるようになったし、その際に響いていた静かなモーター音ももう聞こえなくなった。まるで機械の身体のまま、少しずつ人間になっていくよう。そして面白いことに、ジャーのかどが肌に触れる部分に「痛い」という感覚が生まれていた。
「劇団を大きくしたいの」
ジュゼッピーナは言った。
「ここには、古代の戯曲がたくさん残っているわ。でもどれも登場人物が多くて、いまの人数じゃとても無理」
「ただのアンドロイドでよければ無数にいるんだけどねー」
ジュリアが付け足す。
「そう。でも、脳が大事」
と、ジュゼッピーナ。
リュシオールは車椅子に座り、自分の脳を納めたジャーを抱きしめていた。
イタリアの地方都市のようだった。おもちゃの町並みに、金物屋、庭具屋、服飾店が並ぶ。広場には教会があり、出入りする人たちの姿が見える。露店もあった。工場で作られた革のコートやベルトを吊るして、「去年のデザインだから、サービスするよ」と、行き交うひとに声を掛けている。ジュゼッピーナとジュリアは見向きもせず、リュシオールはこれから夏が来るのだと思った。通りを渡って、いくつかのショーウインドウに自分の姿を映した。服飾店に三人で立ち寄ったとき、リュシオールはまだ男でも女でもなかった。
店のなかは、布の匂いがした。そして、無人だった。古いアンティークな時計が五百年前の時間を刻んでいる。ジュゼッピーナとジュリアが選んだのは、薄桜色のシャツ、褐色の膝上丈ズボン、それにチェックのハンチング帽。合わせてみると、活発な少年のようでもあったし、飾り気のない少女のようでもあった。ジュリアは刺繍入りのサスペンダーを見つけて、それをリュシオールの胸に合わせたあと、サスペンダーに合った服を選び直した。
「髪はどうする?」
ジュゼッピーナが聞くと、
「わたしと同じでー」
と、ジュリアはナチュラルボブの自分の髪を指した。
服を買ったあと、アクセサリー店でウィッグを選んで、シャツに合うネックレスを見繕った。それから靴屋。厚底のブラウンのスニーカー。靴屋では靴下も買った。この頃にはリュシオールも自分で立って歩けるようになっていたが、指先の制御は難しく、靴紐はまだ結べなかった。そして、「順番は前後しちゃうけどー」と、肌着を選んで、そのとき初めてリュシオールは自分が女性だと知った。いや、アンドロイドなのだから性別はないのだ。人間だった頃の性別だって覚えてはいない。それが肌着を何枚か買う頃にはプライバシーへの意識も芽生え、それを着るために試着室を借りた。それから鞄屋。
「脳が入るサイズ」
と、ジュゼッピーナが見繕ったリュックは、どれもキャンプにでも行くかの大型のものだったが、なかでも普段使いにも向くキャンバス地のプリント柄を選んだ。白地に水色のボーダー、ヒトデとタツノオトシゴの小柄。夏に似付かう涼し気なデザイン。背負ってみると、「サスペンダーと合わなくない?」とジュリアが言いだして、もういちど服飾店に戻って、ベルトを見繕った。
「これかこれだと思う。ルッチョラはどっちが好み?」
そう示されたときには、リュシオールもずいぶんと言葉を理解できるようになっており、「リュックに柄が入ってるので、無地のほうがじゃまにならないと思う」と、話すことができた。
どの店にも店員はいなかった。古風なレジがあったが、どれも中は空で、支払いは腕時計の端末で自動的に精算されているのか、ジュリアが服やベルトのタグをちぎるたびに、ジュゼッピーナの時計にログが示されているのがわかった。
店の外には車椅子を留めていたが、買い物を終える頃にはリュシオールも体の操作に馴染み、三人は車椅子を乗り捨てて通りに出て、「あとはどうするー?」と、ジュリアが尋ねた。
「あとはコスメかな」ジュゼッピーナが答える。
「それなら大丈夫」と、ジュリアは鞄の中の化粧品を見せた。
「いつの間に?」
「ルッチョラが着替えてるとき。ルッチョラはなにか欲しいものあるー?」
ジュリアはリュシオールの顔を覗いた。
切れ長の目にくっきりと黒いアイラインが見える。視力はもう常人並ではあるが、リュシオールは、「眼鏡」と、答えた。
「眼鏡かー。眼鏡屋はないんだよねー」
ジュリアは途方に暮れた。
「心当たりがある」
と、ジュゼッピーナ。
「中には眼鏡を置いてる店はないけど、外に出たら調達できるかも」
と、続けるが、中と外が何を意味するかはリュシオールにはわからなかった。
広場にしつらえられた
――ここはどこなのだろう。
完成しかけたパズルに、いくつかの不整合が見えた。
ジュゼッピーナが明るく通る声で、
「外には死んだ兵隊さんがたくさんいるから、だれか眼鏡を掛けていると思う」
と言うと、平穏なイタリアの田舎町として構築されていたリュシオールのパズルは壊れた。
4 シチリアの夢
ゲートには「ソーニョ・ディ・シチリア(sogno di Sicilia)」の大きな看板があった。それがこの場所の名前なのだろう。すぐにアプリケーションが単語を翻訳、「シチリアの夢」の意味だと教える。だけどリュシオールには、ただ何もせずにその言葉が浮かんだように思えた。
そこはずいぶんと古い時代に作られたテーマパークだった。その時の様子もデータベースにあったが、人間の脳に直接送られてくる景色は幻覚と変わらない。これも生粋のアンドロイドならばデータとして処理し、必要ならプリントアウトもできるのだろうが、人間にとって視覚を通さずに得られる映像はすべて「夢」だった。
草の匂いが駆けて髪を揺らすと、ほのかに硝煙の匂いが交じる。ソーニョ・ディ・シチリアの外に出るとすぐに、駐留する軍の姿が見えた。ジュリアが指差して、
「アークトゥリアンと戦ってる兵隊さんたちだよー」
と教えたが、ジュゼッピーナが、
「違うよ。アークトゥリアンに寝返った連中が、地球軍と戦っているんだよ」
と訂正した。
「そっかー。ま、別にどっちでもいいけどねー」
ジュリアは言い放って、三人は駐留している軍の後ろの小道を抜けた。
「あそこの兵隊さんたちは、わたしたちの村を守ってくれてるの」
つづら折りの坂道を下りながら、ジュゼッピーナは言った。
「卵の穴を守ってるんだよ、わたしたちじゃなくて」
ジュリアが続ける。
「ホーエンシュタウフェン家とアンジュー家とがあってね――」
と、ジュリアのレクチャーに重ねて、遠くには銃声が聞こえている。木々の間から立ち上がる煙も見えた。ソーニョ・ディ・シチリアからの山道が中央分離帯のある街道と交わるところで、爆走する戦車が三人を追い越していった。そしてその先、ひとの集落らしいところを抜けるとき、街道のそばに建つ古びた家のまえで、「ここがパーツショップ。兵隊さんの手や足を売ってる」と、ジュゼッピーナが示した。
「あなたもここで買ったの」
大砲の音が響く。先程の戦車の主砲だろうが、散発的に数発が聞こえ、そのあとで着弾音が轟き、黒煙が上がる。
「覚えてるー? 売られていたときのこと」
と、砲撃音を気にすることもなくジュリアが聞くが、ずっと眠っていたのだ。覚えているはずがない。
しばらく行くと平地が開け、そこには有刺鉄線があった。
「この先は地雷原」
と、ジュゼッピーナが背伸びして、地平線の20センチ先を覗き見る。
「でも平気。ハイパースペクトル分析で、爆弾がどこに埋まってるかすぐわかる。あそこと、あそこと、あそこ」
ジュゼッピーナが指差すと、リュシオールの視界にもマーカーが灯る。視界の中に赤い○が描かれ、ラインで引いて「Danger」と記される。
「データは送ったから、避けてね」
ジュゼッピーナも他の団員と同じくアンドロイドだったが、そう紹介を受けたわけでもない。リュシオールが明確にそうだと知ったのは、このときが初めてだった。ただそれに違和感はない。むしろ戦車に乗って進軍していく人間の方に違和を感じていた。
「あそこに死体があるでしょう?」
ジュゼッピーナが指差す。
「顔は向こうを向いているけど、眼鏡をかけてるかもしれない」
ジュリアが、更に加える。
「死体はぜんぶで7つ。データ送るねー」
リュシオールの視界には緑色の○が灯り、ラインで引いて「Treasure」と記された。
まばらに草の生えた荒れ地を通って、最初に辿り着いた死体は眼鏡をかけていなかった。すでに白骨化し、地雷を踏んだのだろうが、両足を無惨に吹き飛ばされている。リュシオールはその死体を見ても、感情が動くことはなく、ただ、「残念だ」と感じた。
「眼鏡、ないね」
「うん」
リュシオールの視界は良好で、眼鏡は必要ではなかったが、ときおり無意識に指が顔に触れる時があった。そこには眼鏡がない。ただ、夢で鏡を見たときのような不可解さがあった。鏡を見て目を覚ました記憶とは反対に、覚めるはずのない夢の中にいるような。
――いま見えている景色は真実ではない。
そう思うと、アンドロイドが感じるはずのない不安を感じた。
途中、乗り捨てられた戦車があった。いまのリュシオールには、戦車のほうが人間よりも親近感がある。その冷たい車体に手を触れ、地雷原を横切り、二体目の遺体。やはり眼鏡はない。三体目はそこからさほど遠くもない。ジュゼッピーナが先行してそちらへと踏み出すと、刹那、巨大な爆発音とともに瓦礫が舞い上がった。
瞬間の音圧はセンサーの上限を超え、ピークカットされたノイズだらけの音になった。その間リュシオールは、爆風で横倒しになり、3回ほど転がり、視界には空と地面とが交互に過ったが、その空もすぐに舞い上がる粉塵に隠され、視覚は天地の情報を伝えなくなった。ジュリアも同じく、視界の隅で爆風でなぎ倒されるのは見えたが、すぐに視界から消え、ピーーーーというアラート音だけが残った。そのアラートも地面に叩きつけられるたびに揺れる。リュシオールは無意識に、脳との接続部を押さえていたが、爆風が落ち着いたあともちゃんと意識があるので、脳は無事だったのだろう。
アラート音が途切れ、
「ピーナ、ルッチョラ、大丈夫ー?」
と、ジュリアの声が聞こえた。
「わたしは大丈夫」
リュシオールが答える。
「ピーナはー?」
「ごめーん。踏んじゃったー」
その先に聞こえたのは、ピーーーーというアラート音。
二人がジュゼッピーナに駆け寄ると、腰から下のパーツは完全に砕かれ、モリブデンフレームが露出し、油冷用のチューブからどくどくとオイルが流れ出している。リュシオールは吐き気を催し、その場にしゃがみこんだ。
「そんなにひどい状態?」
ジュゼッピーナが問う。
「下半身の感覚がないんだけど、脊髄をやられたのかな」
「ああ、うん、脊髄とかって問題じゃないけどー、オイル止めなきゃだねー。詳しい話はあとでー」
応急処置を終え、三人で話して、とりあえずは楽屋に戻り、スペアのパーツを探して、ジュゼッピーナを修理しようということになった。
「ごめんね。眼鏡はまた今度で」
と、ジュゼッピーナ。
オイルが漏れないよう、何箇所かの弁を閉じたが、そもそもその機構がダメージを負っている。ジュゼッピーナはしばらく匍匐前進で二人について来ていたが、やがて「逆立ちして手で歩いたほうが速い」と、逆立ちして数メートル歩いたが、それが仇となってオイルチューブから気泡が入り、システムエラー。身体機能はすべて停止した。
「ごめーん。動けなーい」
と、嘆くジュゼッピーナに、ジュリアはひとこと、
「しょうがない。体は捨てていくかー」
ジュリアはジュゼッピーナの頭部を取り外し、破れたスカートを風呂敷にして、肩に担いだ。ひとの死体を見てもなんの感情も動かなかったリュシオールも、ジュゼッピーナの首を外すときの金属の軋みには耳を塞いだ。
「大丈夫? ピーナ?」
ジュリアが声を掛けると、視界に「大丈夫」とテキストが表示される。声帯はもう使えないらしい。
放置された戦車まで戻ると、ジュリアが「これで帰ろう」と、そのボディを拳で叩いた。
「このままじゃ日が暮れる」
アンドロイドのリュシオールは「疲れる」ことはなかったが、陽の光が傾き、大気の色にもやや赤みが差しているのを見ると、胸の中にその懐かしい気持ちが沸き上がった。足の衝撃吸収用のダンパーがずいぶんとくたびれている気がしたし、少々休ませたほうが性能を維持できる。いくつかのセンサーが示す数字が「疲れ」を想起させた。そう。自分は疲れたのだ。
ハッチを開いて、コクピットに侵入。
ジュリアは操縦席の端末をいくつか叩いて、「ダメだねー。プロトコル古すぎー。遠隔じゃ無理みたい」と、愚痴た。
「第三世代汎用コネクタがある」
操縦桿横のコンソールを見て、ジュリアは続ける。
「あなたの脳ユニットだったら繋げそう。コンタクトしてみてー」
そう促され、リュシオールにはそれがなんのことか俄にはわからなかったが、体は勝手に戦車との無線接続を試みている。おそらく、人間が無意識にまばたきや呼吸をするように、アンドロイドも無意識のうちに周囲のマシンとコンタクトを試みるのだろう。互いの通信プロトコルを伝え合い、共通のプロトコルを探し、最適な通信速度でハンドシェイク、駆動用のドライバをセットアップするところまでが無意識のうちに済まされ、モニターしていたジュリアの、「あとは、脳を繋ぎ変えればオッケー」という、軽い言葉がコクピットに響いた。
「脳を繋ぎ変える」というのは耳慣れない言葉だった。一時的に脳が体から離れている間、体のコントロールは効かないわけだから、あとはジュリアがやってくれるのかと思って待っていたら、「やってみてー」と、ジュリア。
リュシオールの感覚の中で、脳はまだ頭部にあった。実際には脇腹から繋がっているジャーがリュシオールの体をコントロールしているのだが、ジュリアから「やってみて」と言われて、それほど大きな違和もなく、「これを繋ぎ替えればいいのね」とばかりに脇腹のプラグを外した。
次の瞬間、
――汎用外部デバイスが切断されました
と表示され、当然のように意識はすべての感覚を失い、無音と暗闇とがリュシオールを包んだ。もちろん自分の体をコントロールすることもできない。
完全なる静寂のなか、
――こうじゃなかったのかもしれない。
後悔の念が生じる。
脳には残響のように信号パターンが残り、しばし戸惑っていると、次の瞬間、戦車としての自分の肉体の情報、感覚が意識に流れ込んだ。車体に搭載された複数のカメラからの映像が同時に脳に入る。そして、もとの自分のボディからは、回線が遮断されていた間のログが送られてくる。自分が指示を出していなかった間も、ボディは勝手に動いて、勝手にプラグを差し替えていたのだ。
やや釈然としなかった。
肉体を操っているのは、自分の「脳」ではなかったか。
それで戦車になった肉体を動かしてみるのだが、これも最初はコツがわからない。だけど、あちこちの可動部をデタラメに動かしてみると、動かすごとにデータベースが更新されていくのがわかった。駆動系と脳の間を取り持つプログラムが、関節部の可動域、レンジ、トルク等の駆動に関わる情報を収集し、操作を抽象化してオーバーレイする。そのログが視界にスクロールすると、リュシオールのなかで鋼鉄の戦車の装甲が血の通った肉体になり、まさにこれが自分だ、自分で設計した己自身なのだという確信が生まれた。
――大丈夫?
風呂敷のなかのジュゼッピーナがテキストメッセージで尋ねてくる。
リュシオールは「大丈夫」と、自分のボディを遠隔で喋らせて答えた。
戦車となったリュシオールは地雷を探し、それらを大きく迂回してソーニョ・ディ・シチリアの入口を目指す。途中、倒れて白骨化した死体をみつけ、戦車を止めた。
「どうしたの?」
と、ジュリア。
リュシオールは「眼鏡」とだけ言って、自分のボディを遠隔で操作、戦車の外に下ろして、白骨死体が掛けた眼鏡を回収して戻った。
「来た甲斐があったねー」
眼鏡を掛けたリュシオールを見てジュリアが言った。
アンドロイドのリュシオールから戦車のリュシオールに、その視界の映像が送られてくる。眼鏡をかけて見る景色は、かつて眼鏡を外して見ていた景色そのものだった。
5 冬への扉
倉庫前。ジュリアはジュゼッピーナの頭部を風呂敷に包んでいる。布地はずいぶんとオイルに塗れているが、元は暖色系のスカートだった。それを肩の後ろに担ぐようにして布の先端を首元に結んでいる。自分の脳をリュックで背負っているリュシオールの方が幾分スマートだった。倉庫の扉が開くと、逆光のまばゆい光のなかに二人のシルエットが浮かぶ。鼻を突く異臭がある。一角にはネコの親子が住み着いていて、だれかが与えたであろうネコの餌と、水を入れたボウル。ネズミも同居しているらしい。ところどころに殺鼠剤の匂いがあり、高い窓から斜めに差す光にはその糞が埃となって舞い、乾いたカビの匂いに咽た。
「ルッチョラのボディがラストだって言ってたよねー」
ジュリアは独り言のように言う。聞いているのは肩に担がれたジュゼッピーナ。
――全身揃ってるのはそう
声帯のないジュゼッピーナは、電波越しにテキストのメッセージで答える。棚を見るとアンドロイドの手足が積まれているが、たしかに揃ったものはない。棚に積まれた腕の一本を抜き取って、ジュリアが尋ねる。
「……つまりー? どうすればいいの?」
その視界に、ジュゼッピーナの返事が表示される。
――パーツはたくさんあるから、それを組み合わせて作って
作って。つまり、わたしのカラダを。
「いやー、無理でしょー」
半笑いでジュリアが返す。
アンドロイドの怪我の治療――つまり簡単な故障の修復ならジュリアにもできた。だけど、1から組み上げるとなると勝手が違う。そこには絆創膏と外科手術の差がある。
「工具もないし、アプリもなーい。それに、ちゃんとした設計図を手に入れないと、アプリだってエラー吐いておしまいだよー?」
と、言いながらもジュリアは棚に並ぶ使えそうなパーツを見繕う。手も足も左右サイズが揃ったものでないと都合が悪い。こっちじゃない。こっちだな。と、手にしたものは両方とも右手だったりして、ふぅ、とため息して棚に戻す。
――つまり、どうすればいいと思う?
今度はジュゼッピーナが尋ねた。
「わっかんなーい」
ジュゼッピーナの問にジュリアは答えが見つからず、しばしアンドロイドの手を弄んだ。
「そうだ」
口を挟んだのは、自分の頭を背負ったリュシオールだった。
「ジュゼッピーナの頭を、戦車に繋げばいい――」
――それは嫌かな
リュシオールが言い終えるよりも早く、視界にジュゼッピーナの返事が流れた。リュシオールの脳裏には、戦車をジュゼッピーナのボディにして、それで劇団を率いるほのぼのとした光景が浮かんでいたが、これを覗き見たようにジュリアが笑う。
「すっかりアンドロイドになったねー、ルッチョラ」
ジュリアは両腕の選定を終えて、いまは脚を一本抱えている。
――でも、戦車と言えば……
今度は頭だけになったジュゼッピーナに名案が降りてきた。
――卵の穴に侵入できれば、そこにはあると思う。わたしのカラダ
「……つまり?」と、ジュリアはシリコンの表情筋で眉を歪ませて、「ルッチョラに戦車を動かしてもらって、卵の穴の入口を破壊するってこと?」と、ジュゼッピーナに聞き返した。
――大正解!
戦車はテーマパークの裏の従業員入口に停めてあった。軍の駐留する正面ゲートを避けて帰還したが、不審に思われたのだろう。停車したあと、斥候が調べている姿が見えた。その戦車に戻り、コクピットに入り、リュシオールはまた脳を戦車へと繋ぎ換えた。もう脳ユニットが外れた5秒ほどの時間にも、意識が途切れたようには感じなくなっていた。脳をはずしている間に、自分のアンドロイドのボディが何をするかはわかっていたし、再接続したときにそのログは送られてくる。空白の記憶は瞬時に埋められ、その瞬間に寝呆けにも似たかすかな違和を感じるだけで、記憶は連続していた。これは人間の大脳が生得的に持つ機能で、数秒間の記憶の途切れは予測機能が勝手に補完してくれた。ボディ側にも数秒ぶんのコマンドをバッファする機能はあったし、単純に歩いたりするだけなら脳からの司令はとくに要さなかった。実際に、日常生活のほとんどで脳からの司令は必要ない。脳へはデバイスから結果が送られ、脳はそれを「自分が命令した」と信じ込む。
地図をダウンロードしてディスプレイに映すと、「卵の穴」のポインタはテーマパーク中央のベスビオ火山を示した。もちろん本物の山ではなくアトラクションなのだが、同じテーマパーク内とはいえ、そこそこの距離がある。ルート確認のあと、エンジン始動。アスファルトの舗装路から、いったんショッピングエリアの石敷きへ出て、池を回るコースへ。道は左右にうねり、ジュリアはジュゼッピーナの頭部を膝の上に抱えて、砲塔の上に座っている。
「ベスビオ火山だよー。見えるー?」
ジュリアはジュゼッピーナの視界に褐色に聳える山肌を見せる。
――見えるけど、ちょっと揺れる
戦車にはリモートでコントロールする機能はなかったが、逆にリュシオールのボディは戦車からの指示で動かすことができた。戦車に繋がれたリュシオールの脳は、アンドロイドのボディの視界も見ることができたし、その体に喋らせることもできた。その操作にも慣れてくると、脳が接続されているのが戦車だとわかっていても、アンドロイドのボディのほうにアイデンティティを感じるようになった。従属しているのは戦車のほう、自分の意識は薄桜色のブラウスを着たアンドロイドのボディに宿っているのだ、と。
履帯の跡をゴリゴリとアスファルトに刻みつけて辿り着いたベスビオ火山には、急峻な山肌にケーブルカーがしつらえられている。だが、それが稼働している気配はない。
「この上には宇宙人の母艦があるんだよー」
ジュリアが言った。
「だからこのあたりは、メンテナンスされてないの。危険だからねー」
リュシオールは「そうか」と、と納得したが、その宇宙人が陣取るはずの山の麓には、峻厳な岩肌を背にして土産物屋が並び、ベスビオ火山が描かれた三角形の旗や、ベスビオまんじゅうが売られている。宇宙人の母艦、という言葉には似付かうはずのない景色だ。これもまた、ここがテーマパークであることを考えれば当然なのだが、それでもどこかしら異質な感触がある。それに、リュシオールはかすかにこのあたり景色を覚えていた。それとの差異が胸をざわつかせる。従業員通用口からここまでの道のりは、たしかに通ったことがある。だけどそれが本当に自分の記憶なのか、ボディ側に残ったアンドロイドの記憶なのかはわからない。
ジュゼッピーナが言うように、自分のボディが卵を孵すためのアンドロイドならば、このあたりの景色を覚えていても不思議ではない。その記憶が脳にも共有されているのだろう。しかし、あやふやな記憶というのは人間に顕著なもので、アンドロイドならばもっと明確に覚えている。ならばこの記憶は、リュシオールの脳に宿るものだ。アンドロイドのメモリではなく人間の脳を主記憶として用いるリュシオールには「フォルダー」という概念がなく、すべての記憶は同じところに詰め込まれる。そこには実映像、記憶、妄想の他にも、システムが自動的に取り寄せたデータベースからの映像もある。いままで幾度も、先に得た情報から後追い的に記憶が作り出されることを経験したリュシオールは、自分の記憶のうちどれが現実に基づくものか、どれが幻想に過ぎないのかがわからない。言葉で構築された記憶も、嘘の絵の嘘のキャプションでしかないかもしれない。夢も現実も、おぼろげに統合されて、ひとつの脳のなかに記憶される。事実、パルマ・ロッシが賞をもらった際の授賞式の様子がリュシオールの記憶に刻まれていたし、エレナ・フェッリに至っては、存在しないはずの幼少の頃に舞台で踊る映像が脳裏に焼き付いている。いったいどこまでが現実の記憶なのか。
だけど――いずれにしても、その記憶にベスビオ火山はなかった。
「こんなもの、本当はここにはない」
リュシオールはそう言うと、土産物屋の脇から茂みに入り、切り立つベスビオ火山の山腹の前で、主砲の発射レバーを引いた。
腹に響く衝撃音に続けて間髪を入れず、ファイバー樹脂製の山肌全体がたわむような衝撃音を発する。無反動砲とは言うが、至近距離で壁を撃ったものだから、それなりの衝撃が走り、砲塔の上に腰掛けていたジュリアはよろめいて転げ落ちた。地面に投げ出されたジュリアは、ジュゼッピーナの頭を抱えたまま、
「なにそれー、ルッチョラ、アタマおかしいってー」
と、ケタケタと笑う。
命の価値が人間と違うアンドロイドは、死に直面した際のリアクションも違う。
――あなたたちのその無邪気さが、やがて人類を滅ぼすんだよ
そんな気持ちも湧いたが、それもまた記憶の断章だった。
砲身から放たれた徹甲弾はベスビオ火山のハリボテの山肌に小さな穴と縦一本の長い亀裂を刻み、リュシオールは砲塔を後ろに回し、履帯で山肌の穴を踏み広げて内部へと侵入した。砲塔を後ろに回したのは、戦場での経験や戦車の知識からではなく、ひとが嵐の日に腕で顔を覆うように、自然にそうしたものだった。
ベスビオ火山内部にもアトラクションはあったが、リュシオールたちが侵入したのは、従業員用のバックヤード。鉄骨がむき出し、キャストの衣装、小道具、大道具、アトラクション用の乗り物のスペアが無造作に転がっている。
「わたし、火山のなかって初めて見たー」
と、ジュリアはあたりを見渡し、ジュゼッピーナの顔の覆いを少し開けて、
「ピーナも見えるー? ここ、火山のなかだよー」
と、その景色を示す。
――卵の穴はどこだろう
ジュゼッピーナがテキストで問い返す。
「たしか、火口の直下。あっちじゃないかな」
ジュリアが胸に抱えたジュゼッピーナに見えるように指差す。
火山の中は外界の鳥の声、風の音から隔絶され、空調の低いノイズと幾重にも返す声の反響と、たまにネズミの走り回る足音があった。ジュリアとリュシオールは、その音に耳をすますべく戦車を降りて、そのまま奥へと歩いた。しばらく歩いて火口直下まで来ると、電子施錠された扉があった。地図はそこが目的の場所だと示す。素手では破れそうにないその扉を見てジュリアは、「あちゃー」と漏らした。
「しょうがなーい。戦車取りに戻るかー」
ジュリアは伸びをして踵を返すが、リュシオールは、
「パスワードは知ってる」
と返す。
「えっ? なんで?」
ジュリアが振り返り、聞き返す。
「わからない。わたし、ここと関係が深いひとだと思う」
「そうかー。それじゃあ、手間が省けたねー」
リュシオールは己のなかの記憶に戸惑うが、ジュリアにはその違和もない。聞いた事実はそのままインデックスされていく。それがアンドロイドだ。
入力端末の老朽化したプラスチックのカバーは、指をかけるとすぐに崩れ落ち、内部のパネルは不自然な明滅をともなって頼りげなく起動し、その表面に0から9までの数字を浮かべた。
1、9、6、8、1、0、1、1……
リュシオールがパスワードを入力すると、
――パスワードの有効期限が切れています
ガイダンスが流れた。
ジュリアは苦笑したが、リュシオールは意に介さず。音声ガイダンスは続けた。
――認証を音声照合に切り替えます。所属とお名前をどうぞ
その案内にリュシオールは淀みなく、
「敷根
と、答える。しかし、
――声紋データが一致しません
と、ロックが開くことはなかった。
「それはそうよ。人間だった頃の体じゃないからねー」
ジュリアは肩をすくめて見せたが、リュシオールはため息ひとつ漏らすことなくその場を歩き去ると、すぐに戦車で戻ってきて、主砲で扉を破壊した。
かくして卵の穴に侵入した後は、障害となるものはなかった。
なかの様子はリュシオールの記憶にあり、アンドロイドの格納庫へも迷うことはなかったし、そこも当然のように施錠されていたが、そばにある端末でログインし、パスワードを更新、こちらは戦車を使わずに開くことができた。
「てゆーか、あなた、だれ?」
ジュリアはリュシオールに聞いたけど、
「わからない」
リュシオールは答えた。
たどりついた格納庫は、ネコの親子がいた倉庫とは違い、舞い飛ぶ埃も、鼻を突く異臭もない。明かりのない暗いフロアに、無数のアンドロイドが整然と立ち並んでいる。
端末はキーボードの一部が経年劣化で崩れ去っていたが、ブルートゥースと呼ばれる古い電波を捕捉できた。アンドロイドの肉体を持ったリュシオールには、ブルートゥースを介して直接コマンドを送ることができた。リュシオールは休眠中のアンドロイドのうちの一体をリモートで起動、すぐにその操作を奪ったが、違和を覚え、手を止めた。
「どうしたの?」と、ジュリア。
「起動後は、受精卵保管センターとのハンドシェイクが開始されるはずだけど、始まらない」
リュシオールはそう答えたが、記憶が戻っているわけではなかった。
「なにそれ。ルッチョラ、だいじょうぶー?」
ジュリアは呆れる。
「このアンドロイドは人類の希望だった」
リュシオールは胸の中に浮かび上がる言葉を、そのまま口の先に紡いだ。
「それってなんの舞台? 面白そう」
あっけらかんとジュリアが応える。
「滅亡の、その先を生きる」
そう言いながら、リュシオールは中央コンピュータをリモートで起動、記録されたログを呼び出す。
「何者かがソフトウェアを書き換えてる」
リュシオールはモニターに並ぶ文字を目で追う。
「あなた、何者なの?」
しばらく冗談めかして応対していたジュリアが、真面目に尋ねた。
6 ひとの記憶
「脳を保管されてるケースって、ほとんどないみたいなの」
リュシオールがキーボードを叩いている間、ジュリアはずっと喋っていた。
「実験用のマウスとかを除いたらねー。保管されてたとしてもたいがいは、神経組織は死んでる。死んでからホルマリンに漬けるからねー。それはとーぜん。でもあなたの場合、永久バッテリーを組み込んだ装置で保管されてたんだって。そう言ってたよね、ピーナ。でー、それって要はさー、あなたが凄いひとだってことでしょう? 何者なの? ルッチョラってー」
リュシオールがその言葉を解し、飲み込むと、民衆に喝采を浴びる世紀の大天才の姿が思い起こされた。その頭脳を未来へ残すべく死後も保存されたのだ。そしてそれは、次の瞬間には記憶になる。しかしリュシオールは、一方ではその記憶を疑う。
――これは夢だ。夢の中の鏡で見た顔のように、自分で作り出している勝手なイメージだ。
だが、そう思ったところで目を覚ますことはない。果たして自分はジュリアから、何を聞いて、何を理解したのか。ジュリアの言葉を思い起こそうとしても、馴染みのない単語ばかりだ。
――脳を保管されているあなたは凄い。立派なひとだ。マウスの脳だったら保存されているけど、組織は死んでいる――
と、ジュリアの言葉は、あやふやな言葉で再生され、実際に耳で聞いた言葉は思い出せない。理解しているのは、それによって想起されたイメージだけ。記憶はいつもそうだ。正確な文言は忘れるが、要旨だけを覚えている。だとすれば、生の情報は聞いたそばから忘れ、自ら紡いだウソばかりを覚えたことになる。
――シキネ・ホタルが、あなたの本当の名前?
ジュゼッピーナが、モニター越しに聞いてきた。
「わからない」
ひとことだけ返して手元の端末で「シキネ・ホタル」を検索すると、指名手配の記事があがった。
――シキネ・ホタル、《
リュシオールの記憶が書き換わる。
自分はそうやって逃走し、何者かの手で捕らえられ、殺され、その記憶を持つ脳だけが保管されたのだ。だけどそれが事実かどうか。自分が見た情報が本当に正しく脳に伝わったかどうかすらわからない。そしてそれが無意識に己のアンドロイドのボディに共有されると、ボディは独自に周囲のマシンに情報を拡散させる。アンドロイドは分散型データベースを共有している。入手したデータは近くのアンドロイドで共有し、時間をかけてどこまでも広まっていく――だから自分は言葉を学習しなくても彼らの言葉が理解できるようになった――そしていま、自分が指名手配犯だという情報が勝手に拡散しようとしている。
「違う! 違う! 違う!」
リュシオールは叫んで、己の頭をキーボードに打ち据えた。
ジュリアがそれを見てケタケタと笑い出す。
「そんなことより、ピーナをなんとかしてあげようよー」
からかうように口にするが、待て、いまはそんな場合じゃない。自分が何者かわからない。いや、わかってしまったのだ。いや、それも違う。わからないのだ。何もかも。
「どうしたのー、ルッチョラー?」
リュシオールが混乱していると、ジュリアは甘い声を吐いて、唇を舐める。そうして、ウフフ、ウフフ、としなを作って笑う。さっきまでとは様子が違う。
「どうしたって……?」
リュシオールは手を止めて聞き返す。ジュリアは異臭のある息を吐いて、ゆっくりと額を下げて、虚ろな瞳を上目遣いに向ける。
「……あなた、すこし、ヘンよ?」
粘度のある乳剤を、素手で、ゆっくりと、混ぜるような、ベタついた声。
「ジュリア……?」
おかしい、何かが違う、リュシオールがそう直感した次の瞬間、
「やっと気がついたようだね」
背後からパルマ・ロッシが姿を見せた。
「パルマ?」
演出家、兼、俳優。テアトロ・デレ・ステッレの中心人物。
「いつからそこに?」
リュシオールが問う。
「いつから? キミから目を離したことはない。なぜなら、キミはアークトゥリアンとコンタクトして、地球軍の秘密を売ったのだからね」
唐突に切り出されるが、わけがわからない。
「わたしが?」
「そう。キミはシキネ・ホタル。自己再生性シリコンポリマー、self-healing silicone polymer、通称、《
その情報はリュシオールの処理限界を超えた。
「わからない……何を言っているの? わたしが? どうして……?」
そうパルマに問うと、もうひとつの別の影が現れ、言葉を継いだ。
「あなたは、彼らの持つ技術が欲しかったのよ、リュシオール……いいや、シキネ・ホタル」
振付師でプリマのエレナ・フェッリ。
「まったく。バカなことをしてくれたわ」
エレナは長い脚を高くひらめかせる。
「向こうは37光年の彼方から来た異星人。いくら科学力があると言っても、補給はない。兵士の補充も効かないし、宇宙船が壊れても補修には限度がある。それなのにあなたは――」
エレナはリュシオールの周囲を舞うように歩き、艶かしくその指を伸ばす。
「――継戦能力の要となるアンドロイド技術を渡してしまった」
「待って」
そのアークトゥリアンについて、まだほとんど知らない。戸惑うリュシオール=敷根蛍の意識に、データベースは次々とアークトゥリアンの情報を送ってくる。セリフを終えたパルマとエレナは、舞台の中央で戸惑うリュシオールの左右でポーズを取るように静止。そしてスポットライト。舞台奥にレオーネ・マルティネッリの姿が浮かび上がる。
「キミは、SHSP――自己再生性シリコンポリマーを開発し、アンドロイドの発展に寄与した。だが一方では、それが人類を滅ぼすことに気がついてしまった」
背を向けたまま口上を述べるレオーネに、リュシオールは振り返る。
「人類はアンドロイドを使役し、戦禍は拡大。戦争で荒れ果てた地球は、人類を育む力を失った。人類を滅亡から救うには、アークトゥリアンの超光速航行の技術が必要だったのさ」
レオーネが顔を向けると、敷根蛍の記憶が蘇る。いや、書き換えられ、捏造される。たしかに自分は地球人類を救うため、アークトゥリアンにアンドロイド技術を売った。――そこに、爆音が轟く。
大地が震え、天井に吊られた空調やライトが大きく揺れる。縦横に組まれた鉄骨がが軋みを上げて、パラパラと砂埃が舞い落ちる。轟音が部屋を包む。天蓋が割れる。樹脂製のベスビオ火山が大小さまざまの破片となって降り注ぐと、天上より白い光が挿す。上空には巨大な飛行物体が姿を顕し、それがゆっくり、ゆっくりと高度を下げる。ジュリアが言っていたアークトゥリアンの母艦だ。
「おいでなすった」
レオーネがひらりと体を翻す。
「いよいよ最終決戦よ」
エレナもまた、ドレスの裾を翻してポーズを取る。
そしてパルマ――
「シキネ・ホタル」
リュシオールを指差す。
「あんた、どっちにつくつもりだ? 地球か? アークトゥルスか?」
なんなんだこれは。
リュシオールはなにひとつ理解できない。それに――
「違う! おまえたちは地球人じゃない! アンドロイドだ! わたしが生み出した、わたし自身の汚点! だからわたしたち人類は、アークトゥリアンと手を組むことに決めた! 敵は
その口上を終えると同時に、アークトゥリアンの母艦が接地、激しく大地を揺らすとともにスモークが上がり、フットライトが一斉に立ち上がる。BGM、アークトゥリアンの女王。銀色の母艦のハッチが開き、人影が見える。
「おーっほっほっほっほ!」
甲高い笑い声を発してその影はゆっくりと階段を降りる。一歩、また一歩、足音を響かせて、光のヴェールの外へと出たとき逆光のライトが消える。そこに浮かび上がったのは――
「それはどうかしら、シキネ・ホタル!」
新しい体を手に入れたジュゼッピーナの姿だった。
「これは、なに……?」
リュシオールにはもう戸惑いしかない。まるで舞台だ。何が起きているんだ。
「礼を言うわ、シキネ・ホタル。わたしたちアークトゥリアンは、あなたのおかげで無力な炭素の体を捨てて生まれ変わった」
「どういうこと!?」
「俺達は、卵穴のアンドロイドじゃなかったんだ。最初からな」と、パルマ。
「
「わたしたちが地球に来たのは、侵略のためじゃない。あなたが発明した《
そこに姿を消していたジュリアが姿を顕し、
「つーまーりー」
人差し指をいっぽん立てると、
「アンドロイドと、アークトゥリアンはひとつになった!」
テアトロ・デレ・ステッレの5人がセリフを揃える。
「敵は人類!」
続けてエレナ。
「炭素の体を持つ
レオーネ。
「待て……違う……そうじゃない……」
リュシオールは後ずさりながら訴える。
「何が違うと言うの? シキネ・ホタル。あなたは、アンドロイドは人類の敵だと言った。そして、アークトゥルスはアンドロイドと組んだ。人類は孤立したのよ! この広い宇宙で! 寄る辺なきウラジミール、エストラゴンのように!」
ジュゼッピーナは階段の最後の一段を降りる。
「わたしが書いたシナリオはそうじゃない」
リュシオールはかむりを振る。
「シナリオ? 脚本家はあなたじゃないわ」と、ジュゼッピーナ。
「レオーネ・マルティネッリ。レオーネはねー、数々の戯曲賞を受賞したのよ?」
ジュリアが両手を腰にあて、顔を突き出して、リュシオールに言い含める。
「うるさい!」
リュシオールが握っていた拳を開いて、
「ならば受賞した賞を挙げてみろ!」
訴えると、すかさずジュリアは、
「ブリリアント脚本賞、王立アカデミー脚本賞、王立るんるん賞、王立らんらん賞……」
指折り数えるが、
「そんな賞! どれも聞いたことがない!」
リュシオールの絶叫、舞台上の時間は止まり、アンドロイドの視線はリュシオールに向けて固定される。
「そう!」
ジュゼッピーナの掛け声。
「デタラメさ!」
団員たちが声を揃える。
なんだこの舞台は? なんだこの茶番は? いったいわたしは何をしているんだ。
「でも、この脚本を書いたのがレオーネだってことは事実。あなたじゃないわー」
リュシオールの混乱に、ジュリアが更に謎を重ねる。
「ちょっと待て。だとしたら、どこからがレオーネの脚本だ? おまえたちはだれだ? わたしは何を言っている? 何をしているんだ?」
「わたしたちは、テアトロ・デレ・ステッレ。最初から最後までぜんぶレオーネの脚本よ。レオーネの脚本は観客を虜にするまえに、わたしたちを虜にするのよ」
わけがわからない。
「じゃあ……いま話していた、わたしが軍事機密を異星人に売ったと言うのは? すべてデタラメだったってことか?」
「デタラメじゃないわ! すべてレオーネの脚本!」
……だから……どこから? わたしはだれなんだ!?
「そう、あなたもレオーネの虜になったでしょう?」
混乱が胸を満たし、リュシオールは心臓を押さえる。
「なるわけがない!」
「あのね、ルッチョラ」
――ジュゼッピーナが優しく語りかける。
「体を取り戻したら、ちゃんと言うつもりだったの。あなたを正式に、わがテアトロ・デレ・ステッレに迎えたいって。ルッチョラ」
ルッチョラ――いままでの彼らの言葉、彼らの行動、それが現実か夢か、あるいは舞台か、幻覚か……なにもわからなかったが、ルッチョラもリュシオールも本当の名前でないことは明らかだ。
「わたしは敷根蛍だ。ルッチョラではない」
静かに、そして確信をもって、リュシオール――敷根蛍は言葉を紡いだ。
「《
だけどその言葉はアンドロイドたちには響かない。
「ルッチョラはルッチョラだわ。シキネ・ホタルは脳しかないのよ?」
ジュゼッピーナはフロアに降り、敷根蛍=リュシオールの目の前に立つ。
「脳があれば、それがわたしだ!」
敷根蛍にとって、それだけが確信だった。なぜそれが伝わらないんだ。アンドロイドだってそうじゃないか。電子頭脳が本体だ。考えればわかることだ。
「へー」
ジュゼッピーナが一言漏らして指を鳴らすと、パルマ・ロッシとレオーネ・マルティネッリが、リュシオールの両腕を抑え、舞台奥へと引きずる。そしてエレナがリュシオールのバックパックから脳の入ったジャーを取り出して、舞台の中央に置いた。
「本当にそうかしら」
ジュゼッピーナが振り返り、腕組みしたままリュシオールに尋ねる。
リュシオールは羽交い締めにされ、眼の前に脳の入ったジャーを晒されている。
「ま、待て」
そこに巨大なハンマーを持ってジュリアが登場、ホタルの脳のジャーの上にハンマーを翳す。
「待ってくれ! 何をするつもりだ!」
敷根蛍の戸惑い。
「あなたを、開放するのよ――」
ジュリアは巨大なハンマーを大きく振りかぶる。
「ま、待て! 脳を破壊するな! わたしの脳なんだ!」
「――この、悪夢から!」
「やめてくれええええええっ!」
ジュリアがハンマーを振り下ろし、舞台は暗転。
刹那、リュシオールの視界に文字が現れた。
――外部記憶装置が切断されました
7 彩花へ、愛を込めて
「お目覚めのようね」
ジュゼッピーナの声――
リュシオール――敷根蛍は、楽屋のカウチに横たえられていた。
視界はぼんやりしているが、パルマも、レオーネも――みんなそこにいるのがわかった。
「わたしはどうなった?」
力なく問うたその声はか細く、紡いだそばから枯れ葉のように崩れた。
「脳を破壊したのー」
ジュリアのあっけらかんとした声が返る。
振り向くと、ひしゃげて保管液の抜けた脳のジャーを持ったジュリアの姿が見えた。
蛍は思わず脇腹を探ったが、ケーブルはない。
「どうして!?」
反射的にそう声が出たが、その意味はリュシオールにもわからない。
「どうしてというのは?」
どうしてというのは――
「それは……」
蛍の記憶は曖昧だった。アンドロイドとして目を覚ました記憶はあるが、ジュリアが抱えている「何か」が自分のような気がする。
「自分の名前はわかる?」
ジュリアに聞かれ、俄にはわからず、しばらく考えて、
「ルッチョラ?」
と答えた。
「正解。名前さえ覚えてたら大丈夫」
「でも――」
確信はないが、本当の自分はそのひとが手に持ったジャーのなかで死のうとしている。しかも、ジャーを持ったそのひとの名前が思い出せない。
「ベスビオ火山へ向かったことは覚えてる?」
そのひとが尋ねてきた。
「わからない」
「あの前後から、脳波が乱れだして、なかでコンピュータにアクセスしたでしょう?」
そのひとは言葉を区切るが、首を振るしかない。
「それ以降は完全なホワイトノイズ。会話もできず、昏睡状態。やっぱり、アンドロイドの体とは合わなかったみたい」
「ピーナは?」
蛍はそう尋ねて、部屋のなかに視線を動かす。
「あなたのおかげで、ちゃんと体を手に入れたから、心配しないで」
視界の隅でその声の主――ジュゼッピーナは立ち上がり、ドレスを翻してその場でターン、ポーズを決める。
――わたしがピーナと呼んだこのひとは、だれ? それに――
「それをどうするの?」
蛍はジュリアの持つジャーを指差して、不安げに聞いた。
「脳波がノイズだらけになってて、しばらくはそれがエコーしてると思う」
ジュリアはそう説明を始めるが、改めて「わたしのこと覚えてる?」と話を区切る。首を傾げる蛍に「わたしは、ジル」と答えた。
「ジル……」
蛍は小さく復唱する。
かつてロボットには、人間に逆らわない、人間を守る、前記に反しない限り自分を守る――という三原則があったが、旧来のロボットはこれを個別のプログラムによって実装していた。しかし、ロボットの思考が高度になるにつれ、与えられた情報の偏りから判断を誤るケースが増え、この個体の特異性を解消するためにロボット間の情報共有がなされるようになった。
それは、アンドロイドとして意識を取り戻したいまの蛍にしても同じ。通信帯域の一部を通して情報が共有され、アンドロイドとしての自我は随時成長している。いまこの瞬間も、まさに。そしてこの機能によって、蛍の脳の記憶もアンドロイド側のメモリーに
とは言え、記憶は人格とイコールではない。記憶をコピーしたからといって、そのひとの自我まで移ることはない――と、蛍が生きた時代には考えられていた。
蛍の時代の感覚で言えば、いま自分を蛍だと思い、蛍として話しているアンドロイドは、決して蛍ではない。それをコピーした他人だ。だが周囲の者にとってそれは敷根蛍=リュシオールであり、本人もそう思い込み、蛍から継続した自我を持っている。そして、それが蛍ではないことを知るのは、割れたジャーの中で死の途上にある蛍の脳だけなのだが、その脳はもう思考することがない。
果たしてこの状況を「同じ人格」と考えられるか否かは長い議論があったが、この時代になると、「法律では別人格として扱うが、論理的には同じ人格だとする」が模範解答になっていた。つまり、「人格は複数のアンドロイドにコピーしうるし、そのすべてが元と同一であると見做せる」の命題が成り立つ。これは同時に、「まったく同じ記憶を持った人物が複数いた場合、彼らは同一人物である」を真にした。後者はアンドロイドにもあてはまる。2台の別のアンドロイドが同じアルゴリズム、同じ記憶を持っている場合、これは同一と見做される。直感には反するが、分散処理型のアンドロイドはすべてこれに当てはまる。彼らは手や足や頭にそれぞれ人工知能が入っており、たとえ分解されても同一のアイデンティティを持っている。
そも人間の意識というものが科学的に定義不能で、「意識とはなにか」という問いそのものが要件をなさない偽問題であると考えられるようになっていた。人間の意識は己の肉体の自己参照でしかない。「わたしには意識が存在する」という命題をだれも客観的に証明することはできない。「意識」の専門家がそう口を揃えるのだ。彼らはこの偽問題でしかない「意識」の専門家なのだから、その奥の深さが覗えよう。だいたいそれ以前に、「人間の意識の定義」が実生活で問題になることはない。それがなぜかと言えば、やはり偽問題でしかないからだ。
アンドロイドの基本的な仕様は、蛍が設計していた。データが分散され、複数のアンドロイドで共有している点も、記憶が定かだったら思い出していただろう。
「アンドロイドだったら電気だから、電源切ったらすぐにリセットできるんだけどー、脳は生体組織でしょう? 化学反応が連鎖的に起きてるわけだからー、それが落ち着くのを待つしかないよねー」
ジュリアはリュシオールにそう説明したが、脳の化学反応がすべて終了した状態は「死」だ。
「わたし、アンドロイドとして生まれ変わったの?」
リュシオールが問うと、
「そうだよ。おめでとう!」
と、ジュリアが答えた。
「でも――」
「でも、なに?」
「わたしの脳を死なせたくない」
脳を収めた容器には、寺の備品のシールがある。遺骨代わりに納品されたものが売られたか、あるいは盗み出されたのかは知る由もない。
「でも、壊れてるよ? あなたの脳」
リュシオールのシリコンの頭脳に渦巻く「脳がわたし自身である」という思いは、言語化というプロセスを経ずに、劇団員たちにも配信された。人間同士ならば、些細な表情や仕草で伝わる部分だ。
ピーナ――ジュゼッピーナが切り出す。
「脳を保存する方法、あるよ」
エレナが視線を上げる。パルマが指を鳴らし、その指でジュゼッピーナを指差すと、得意げに笑みを返してジュゼッピーナが続ける。
「わたしのボディの記憶にあったんだけど、卵の穴の底で、どうやら炭素をシリコンに変換する作業に当たってたみたい」
ジュゼッピーナの場合は生粋のアンドロイドなので、蛍に比べるとずいぶんわかりやすい変化が起きていた。つまり、ボディ側のログに完全にアクセスできるようになっていたのだ。
「アンドロイドは、卵を育てるために用意されたのではなくて?」
エレナが聞き返す。
「そう。わたしたちは人類滅亡後に目覚めて、卵を育てるようにプログラムされてる。だけどだれかが改変して、わたしとその仲間たちにその装置? ――炭素・シリコン変換器? を作らせたっぽい」
「ぽい?」
アンドロイドなのでログは完全に残っているが、「どうしてそうしたか」という意図は残っていない。命令を受けてレーザー干渉計や、冷却槽、ヘリウム3の生成装置、振動隔離システムといったものを製作した記録が残り――
「それらを起動させて、地下にあったふにゃふにゃの脳をカッチカチのシリコンの脳に変換したって記録されてるから、要はそういうことでしょう?」
――という結果がある。
「地下にある脳ってなに?」
「知らないよ。そうとしか記録されていないんだもの」
つまり、リュシオールの脳をシリコン変換することで、永遠にその機能を留める、というのがジュゼッピーナの提案だった。
蛍は決して、己の脳のシリコン化を望んだわけではなかった。
だけど選択肢はふたつ。自分の脳が死んでいくのを何もできずに見守るか、シリコン化して未来まで生かすか。
卵の穴は深さ2キロに及び、そこに染み出した地下水が貯まらないよう、常にポンプが動き、水を汲み上げていた。それが千年以上稼働してきたことになる。その保守にあたるアンドロイドの姿も確認できる。もとは受精卵を保管する場所だったが、それにしては深度が深い。最下層へ降りるには複数のエレベーターを乗り継ぐ必要があった。
「21世紀の遺物だから、当時はワイヤー型のエレベーターしかない。ワイヤーの強度的に五百メートル前後が限界なんだろう」
レオーネは脚本を書くだけあって、博学だった。結局は最下層まで20分を要したが、ほとんどはエレベーターの待ち時間だった。
最下層へとたどり着くと、自動で灯った明かりが通路を照らす。エレベーターから、縦穴の底にあたるホールへ。メインのゲートを開くためにコントロールルームに立ち寄る。
そこで蛍は改めてシステムにログイン、記録を確認してみると、たしかにジュゼッピーナが言ったように、アンドロイドのソフトウェアに改修のあとが見える。更に記録を遡れば、冷凍受精卵の管理記録、納入記録などがあるから、なるほどジュゼッピーナが言うように「卵の穴」であることは間違いない。
「シリコン化装置の使い方はわかった?」
ジュゼッピーナに尋ねられて、改めてマニュアルにアクセスしてみるが、それらしい記述は見当たらない。そして、長大なログのなかに、「水槽脳」が運び込まれた記録を見つけ、そのとき蛍は「あ」と、口に洩らした。
「どうしたの?」
ジュリアが尋ねる。
「水槽脳が運び込まれてる」
「えっ? それって、ルッチョラみたいな?」
「わからないけど、そうだと思う」
「じゃあ、会いに行こうよ!」
その明るい声は、ひとのいないコントロールルームに反響した。
水槽脳はホールの中央。とりあえず、ゲートのロックを解除、ホールへ。
円筒形の真っ暗な空間の底のほぼ中央、切り株状の2段メサのような台の上に、ガラスのシリンダーがあった。そのなかには脳が納められ、本来なら保護用の液体が満ちているのだろうが、それがあるようには見えず、脳はクリスタルのように透き通っていた。
「これが水槽脳?」
ジュリアが尋ねるが、明確にそうだと答えられる者はいない。
「ここにルッチョラの脳を置いて、装置を起動させればいいんじゃなーい?」
と、これもまたあっけらかんと言うが、その方法がわからない。
「このシリンダーがシリコン化装置ってこと?」
エレナがまじまじとシリンダーを覗くが、たしかにその可能性が高い。蛍が見たログでも、搬入された水槽脳はこのシリンダーにセットされ、そのあとで動かされた形跡はない。それがクリスタルと化しているのだから、そういうことなのだ。
「おそらく、そう」
蛍が言うと、「それじゃあ」と、パルマとレオーネとで脳の設置が開始された。シリンダーに居座るクリスタルの脳を取り出し、ジャーの中でまだぎりぎり生きている蛍の脳をシリンダーに移す。
「あとはどうすればいい?」
蛍はさきほどから、台座の壁面にある端末にアクセスしているが、起動方法はわからない。マニュアルをどう検索しても「シリコン化」などというプロセスは存在しない。
「この脳とコンタクトしてみる」
台座から取り外されたクリスタルの脳を示して、蛍が言った。
クリスタル化した脳にはソケットが埋め込まれていた。機械と接続するためのプラグだ。だが、蛍の脳を納めていた電子ジャーのバスとは仕様が合わない。
「メインCPUのバスをそのまま引っ張ってくれば、接続できるよー」と、ジュリアが言う。
つまり、リュシオールの頭のカバーを開けて、いまのアンドロイドの電子頭脳から直接ケーブルを伸ばし、それを繋げば良い。
「でも、下手したら壊れちゃうよー、ルッチョラの電子頭脳がー」と、ジュリア。
果たしてどうしたものか。ここに来て死にかけの生体の脳と、なんとか自我が芽生えかけた電子頭脳、どちらを選ぶかという選択肢が立ちふさがった。だが――
「メモリを退避させておけば、壊れても復元できる。ボディは格納庫にいくらでもある」
判断は早かった。
「わたしの脳をケイ素変換する」
そこにあったのは生への執着ではない。科学者、敷根蛍博士としての性だった。それがアンドロイドのリュシオールに受け継がれているのだから、やはり蛍とリュシオールは同一人物なのだ。
脳幹からケーブルを分岐させて、クリスタル化した脳のソケットに接続。
端子に微弱電流を送り、そのエコーから内部構造を確認、蛍側のネゴシエーションプロトコルが開始される。
ATZ、ATE1、AT&C1……
コマンドを送り始めると、やわらかな幾何学パターンが蛍に伝わってくる。
「接続成功。信号確認」
蛍が伝えると、ギャラリーに静かな歓声があがる。
――こちらはルッチョラ。わたしの声が聞こえますか?
蛍は数十の言語、数百のコーディングで、同時にテキストメッセージを送る。
――……ホタル……聞こえる……
日本語の古いコードでレスポンスが返る。「ルッチョラ」は「ホタル」に訳されていた。
「レスポンス確認」
その言葉にギャラリーが息を呑む。
――ここのクリスタル化装置の使い方を知りたい……
――……
「どう?」
小さな声でジュリアが尋ねる。
「いま質問を送った。待ってて」
――質問を繰り返す。クリスタル化装置の使い方を知りたい
――そんなものは……
――そんなものは?
――……ない
――ない?
蛍の用意した言葉が尽き、通信に空白が生まれ、やがて、
――姉……?
の声がその耳に返った。
「返事はあった?」
ジュリアが焦れたように尋ねる。
「あったけど、姉かって聞かれた」
「もしかして、あなたのことを知ってるの?」
「わからない。わたしがこの脳の姉?」
「よくわかんないけど、イエスって答えて」
――そう。姉だよ。でも、なにも覚えてない
――そうか。待ってた
――あなたはだれ?
――ヒカル
――ヒカル?
――ここにクリスタル化装置はない。ここは、重力波通信装置
「重力波?」
無意識に声に出た。
――アークトゥルスを探すため、テラリウムが作った。
「なんの話?」
ジュリアが尋ねる。
「ここは、重力波通信装置だって。アークトゥルスとの接触のための」
――あなたはここで……
何をしてたの? と聞こうとしたが、相手は脳だけの存在だ。それを聞くのもおかしいが……
――宇宙を見ていた。僕が行くところを、探すために
聞かずともその答えは返ってきた。が、その意味はわからない。
――あなたがアークトゥルスを呼び寄せたの?
――アークトゥルスは最初からいた
――最初から?
――
幻覚の中で見た、劇団デレ・ステッレの舞台を思い出した。アークトゥルスは、
――アークトゥルスに
――違うよ。僕が聞いたんだ。覚えてるの? アークトゥルスを
「アークトゥルスは人類の敵だよね?」
蛍はとなりで聞き耳を立てるジュリアたちに確認する。
「そう。人類の敵。世界中が戦争の真っ只中」
――知ってる。あいつらは人類の敵。いま、地球は戦争の真っ最中
――そんなことになってるんだ
――
――覚えてないんだね
――わたしが知ってること?
――うん
――知らない。教えて
そう答えて、蛍はふと気がついた。もしわたしがヒカルが言っているように、この脳の姉だとするなら、脳は覚えているかもしれない。
「クリスタル化はどうするの?」
ジュリアが聞く。
「わからない。この装置じゃないのかも」
蛍はメインメモリに、重力波通信装置のログをダウンロード。そこにはただひたすら長い数列があるばかり。
――いま、ログを見てる。数字の羅列。これはなに?
――
――この数字が?
通信ログのあとには大量のエラーログが並ぶ。
――そのあとのエラーは?
――ああ。それがたぶん、クリスタル化。
シリンダーにセットされた自分の脳を見上げた。
「クリスタル化は事故だって言ってる」
その操作パネルに自分の姿が映っている。
「どういうこと?」
「わからない」
パネルに映ったのは黒縁の眼鏡をかけた、黒髪の女性の姿だ。
「これは現実なの?」
思わずレオーネに振り返る。
「どうだろうね。今日の脚本は僕じゃない。どうやらここは、キミの世界のようだ」
わたしの世界――。
「わかった」
――ヒカル。お願いがある。重力波通信装置を起動したい
――そう言うと思った
「わかったって?」
ジュリアが尋ねる。
「わたしの脳をクリスタル化する」
「つまり……どういうこと?」
話している裏で、ヒカルと名乗った脳から、重力波通信の起動手順が送られてくる。
「わたしの脳は
「だから、
「わからない」
「わからない?」
「人類を次の時代に導くもの。わたしが見つけた。でも、それがなんなのかわからない」
デレ・ステッレの面々が顔を見合わせるなか、蛍は遠隔でシステムにログイン。
「重力波通信装置を起動する!」
そう伝えると、眠っていた機械が次々と目覚め、その起動ランプを無数の星と輝かせる。
次の瞬間、蛍の脳を収めたシリンダーに光が満たされた。
蛍の意識はロボットの体を抜け出し、無数の小さな光の点となって円形の広間を幾重にも舞い飛び、その中央の脳へと収束する。
気がつくといままでシリンダーを見上げていたはずの自分の意識が、シリンダーのなかにある。
いや、もう自分の意識があるのはそこではない。この塔のなかすべてが蛍の意識だ。視点はもうどこにもない。すべてが見えている。そして筒のなかの大気、すべてが輝いている。
――思い出した
刹那、重力波発生装置が巨大な人工重力を発生させ、縦穴はその駆体を軋ませる。
――
幻光が壁面を縦横に走る。
――あなたを利用してごめんなさい……
空気の低い唸りが筒内に共鳴し、無数に開口する通気口が高低さまざまな音色で呼応する。
――だけどそれでも、わたしは人類を再生する!
そこに生まれた重力波は、いままで奏でられることのなかった歌を歌う。
――受け取って、アヤカ!
そして光が、すべてを満たした。
大分県別府市志高高原にあるテーマパーク、ソーニョ・ディ・シチリアより深宇宙へ向けて重力波による信号が放たれた。
43分後、その信号は木星軌道にいる緋咲アヤカ准尉へと届き、夢を見せる。
その永遠の拡大と永遠の縮小を同時に繰り返す幾何学パターンは、緋咲アヤカの記憶装置コアにあるエウノミア・クリスタルへと転写され、その意識の奥深くへと沈んでいった。
Ⅳ 西暦二八〇X年・ラグランジュ・ポイント
1 アルキメデスの少年
敷根光は、拾ってきた石がダイヤモンドだと思った。
姉の蛍に見せると、ガラス玉だと言われたが、納得できず、比重を調べた。
まずは、アルキメデスが黄金の王冠の体積を計ったときのように、水をいっぱいに張ったコップに沈めて溢れた水で体積を計り、それから学校の理科室に潜り込んで、天秤はかりで重さを計った。
傾きかけた太陽がカーテンを透かせて、教室をオレンジに染めるなか、光は不思議な結果を観測した。
光がダイヤモンドだと思った石は、天秤皿に置く向きによって、重さが変わったのだ。
2 移民の歌
人工天体オモダルに住むドルフィーから、地球人、とくに男性個体は疎まれていた。ただ、その事実に気がつくものは案外少ない。空港の近くには彼らを求める物好きなドルフィーが列をなし、滞在初期にはむしろ歓迎されているとさえ感じる。そのまま空港近くの宿で一夜を過ごし、持ち上げられ、勘違いしたまま市街地へ入り、通りを歩くドルフィーにも空港での「もてなし」を求め、疎まれる。人間男性は「とある一面」を除けば彼らに求められることはなかった。
人工天体オモダルは地球と違い、男性個体に絶対的な権力を与えることがない。金を積んでも、暴力を振るっても、彼らドルフィーを支配することができなかった。オモダルに限らず地球でもじつはそうなのだが、もう何万年もないがしろにされている。その価値観の隔たりは大きく、オモダルを訪れてひと月もすれば、もの好きなドルフィーにも飽きられて、そこで改めて、金と、暴力とで、人間の女性を求めるのだが、法がそれを許さない。それに、オモダルに暮らす多くの人間女性にはドルフィーの伴侶があった。
人間女性にとってドルフィーとの恋愛は、その結果としての妊娠・出産を伴うこともない、自由で気楽なものだった。他方、地球人男性は恋愛の結果としてのパートナーの懐妊を当然のことと信じているが、その当然の結果である妊娠・出産を経験した男性個体はいない。それどころか、生まれ落ちた子をひとり抱いて、いったい何をどうすれば良いのかと途方に暮れたものもいない。だけど、女性個体の多くがそれを経験している。言葉が共通しても、経験は共通しない。そこには明らかな壁があるが、その壁は片方からしか見えなかった。
ドルフィーには男女の区別がなく、地球人的な視点からすれば全員が女性に見える。ドルフィーと人間女性のカップルで、人間女性側に子が生まれる場合、化学的単為発生か人工精子を使ったものとなる。多くの女性がそうやって授かった子を育てるものだから、人工天体オモダルのロールモデルに父親はいない。そこに来る地球人男性が珍しがられ、また疎まれるのも必定だった。
ドルフィーはかつて、「高機能シリコン仮想生命」と呼ばれていたが、それが人類と同等の市民権を得て四〇〇年が経つ。当時使われた「シリコンフォーク」という呼称も、いま対面で言えば差別になる。そのドルフィーの多くが女性型をしている。実際には単為生殖が可能な両性具有で、人間で言えばXX遺伝子を持つ個体、つまり女性だけで胚発生することができるため、男性機能を持つ個体を作る理由がなかった。当時ドルフィーの開発にあたっていた技官、その多くは男たちだったが、彼ら自身が「男は不要である」と判断した。それが今日では、「男性という性をどう定義するか」という「男性性問題」として、生物学、哲学、社会学の最重要課題として挙がっている。究極的には、男は不要なのだ。だけど、それに気がつく男も少ない。あるいは、気がついているからこそ、駄々をこねるように振る舞うのかもしれない。
こと地球において、彼らドルフィーは長く「人格がなく、美しく、人間として受け答えのできる人形」として扱われ、その伝統はいまも多くの地域、集団、社会で受け継がれている。その因習は古く、二十世紀末の単純な応答ロボットだった頃にすら「美しさ」が求められた。更に遡れば人形好きの愛好家が、より美しい人形を手元に飾ったのがその端緒になるが、それから一〇〇〇年。彼らが人格を得て、己の意思で繁殖するようになったいまも、地球にいる男はドルフィーを性的なマスコット以上のものとは見做せないでいた。
これが人工天体オモダルにあっては事情が違った。オモダルが建設された時代、そこには人間がいなかった。いたとしてもごく少数で、それぞれパートナーがあった。多くのドルフィーは自らを改良、繁殖し、職務にあたり、その過程でドルフィーのみで独立して自活できる環境と社会とを築いた。対して地球では、ドルフィーには人間の所有者があった。所有者の保護を離れれば生活にも困窮し、国によっては「迷いドルフィー」は捕獲・監禁される。その抑圧のあったドルフィーと、オモダルのドルフィーとでは、自ずとその思想は異なる。
そしてもうひとつ、オモダルドルフィーの進歩性をもたらした原因のひとつとして「無限リソース」が挙げられる。食料品や日用品をそう呼んでいるが、その大半は炭素やケイ素などの素材と太陽光から無限に作り出すことができた。これによってリソース配分のヒエラルキーは消え去り、だれもその独占で他者を支配することができなくなっていた。地球にもこれに類した技術はあったはずだが、旧来の市場、経済、流通が変革を拒んだ。かつてトリクルダウンと呼ばれた流通のシステムは、緩慢ながら財の流動性をもたらしはしたが、引き換えに支配構造を固定化させていた。
そうやって発展したドルフィーを見て、愚かな地球人類は言った。
「ドルフィーに繁殖の機会を与えたのは、我々人類だ。ドルフィーは我々の技術に只乗りする簒奪者である」
オモダルへと取材に訪れた自称ジャーナリスト、
その人間女性の「価値」――通常は価値という言葉は人間に対しては用いられないが、金で買うことが常態化した特定の分野における「価値」――は、人間の本質に根ざす問題から生まれている。人工的に美を追求して作り出されたドルフィーは、どの個体をとっても数百人に一人の整った顔立ちをしており、美的な観点からは、人間女性がドルフィーを凌ぐことは少なかったが、しかし、「危うさ」の一点においては人間女性が圧倒した。人間女性は繊細な民芸品のように、簡単に壊れ、簡単に奪われる。そして人間男性が求めたのが、まさにそれだった。
それは、彼らのいう「恋愛」の本質が「加害」であることに由来している。人間男性が究極的に望んだのは、他者の人生を支配し、己に仕えさせ、社会的に殺すことだ。他方ドルフィーは、他人の子を孕むことも、それでなにかを失うこともない。奪う喜びのないドルフィーでは、「恋愛」を代替できなかった。また、恋愛という言葉によって人間女性は騙され、加害を受容させられてきた。「恋愛」という言葉は、「性欲」という言葉を都合よく置き換えた。母性を絶対の原理と見なし、その純潔を神聖視され、「性欲」をタブーとされた女性個体が性を謳歌するには、恋愛を選ぶよりほかに自由はなかった。
そんななかで
逆に健全なのは、人間女性だ。性的な欲求が、加害欲と結びつくことは少ない。一部には、支配欲としてそれを昇華するものもいるが、社会の構造そのものがそれを許さない。暗に出産を強要され、一方的にそのリスクを負う。不健全とはすなわち、他者に害を与えることを言う。総合的に見て被害者側にいるものは、不健全にはなり得ない。健全とは、女性のことだ。そして、こうして贈られる「健全」という言葉も、その地位に縛ることへの無価値な褒賞だ。だれもそんな空疎な言葉など望んでいない。
ヨルトは人間女性との交際歴はゼロに等しいが、ひとりで己を慰める際、ドルフィーを道具として伴にしたことは数知れなかった。ヨルトに限らず多くの人間男性にとって、家事と欲求のケアがドルフィーの役割だ。そんなヨルトがオモダルのドルフィーとの体験で特に感じたのが、体腔の無味無臭さだった。ヨルトはオモダルに来た夜、空港の借宿に呼んだドルフィーとの擬似的な恋愛行為のなかでそれを感じた。それを相手のドルフィーに伝えると、「あなたのキスはとてもエキゾチック」と言葉が返った。オモダルのドルフィーは――あたかもウイスキー好きが癖の強いアイラモルトを求めるかのように――そのエキゾチックな人間の味を求めて、地球の男との疑似恋愛を楽しむのだ。
「わたしはまだ四十代」と、外見からは二十代か、場合によっては十代後半にしか見えないドルフィーは言った。「他の子たちは何百歳でしょう? みんな飽きてるの。味のないキスには」
地球にもドルフィーはいたが、人間同様に千差万別の匂いがある。初めての経験の時こそシリコン特有の鼻を抜ける臭いと、ケミカルな後味が気にはなったが、人間女性との接触がないヨルトにその味と匂いは通分してゼロになり、ことオモダルでの今回の経験に於いては、完全なまでに味も臭いも感じなかった。理由は単純だ。オモダルのドルフィーには雑菌がないのだ。
オモダルにはそもそも酸素がない。人間もドルフィーも背中に付けた還元装置によって体内の二酸化炭素をカーボンチップに固化して排出している。これによって呼吸も必要ではなくなっていたが、無意識に出る呼吸を止めるには慣れが必要だった。呼気には酸素が含まれ、呼吸によって酸素は失われる。地球とは逆に息をするほど酸素は不足したが、そのぶんは装置から補われる。地球出身者はオモダルに移民して短くとも半年、長いものでは生涯に渡って呼吸の癖が抜けることがない。大気の組成はほぼ窒素で、気圧も地球の7割程度しかない。これによってオモダルを構成する建材や機械類は酸化を免れ、劣化することがない。火災もなく、ネズミも野良犬も微生物すらもいない。人間が食べ残したものは腐ることなく何日も元の形、元の味をとどめ、なんなら1週間も放置した夕食の残りをそのまま食べることもできた。体表や口腔内にはほとんど雑菌が繁殖せず、いまでこそエキゾチックな味、エキゾチックな体臭のあるヨルトも、ひと月も暮らせば無味無臭になるのがオモダルの環境だった。そうなれば物好きな一部のドルフィーからも、飽きられる。地球人男性の「価値」は、そこで終わる。
ヨルトがオモダルを訪れた理由もまた、酸素のないオモダルの大気にあった。地球では酸素と紫外線の影響で劣化しやすい文化財が、オモダルに集積されるようになり数百年になる。なかには七世紀に書かれた書物や紀元前の木簡まである。オモダルにはアンティークの家具や雑貨、服飾、宗教用の小道具、車、模型など、ありとあらゆるものが運び込まれていた。
そしてこれは「重力」を得ようとしているオモダルにも都合が良かった。亜光速のジャイロを利用して人工重力を発生させているとは言え、それだけでは地球の重力を再現できず、早急に「質量」を集める必要があったからだ。ヨルトが目的とするものも、いまはその「質量」となってこの人工天体のどこかに眠っている。
空港でヨルトに声をかけたドルフィーは、ことが終わったあともヨルトに興味を示し、仕事の内容を細かく聞いてきた。地球では料金を払って別れればそれで終わる日課のような行為が、オモダルではまるで「自由恋愛」のようだった。相手は人間ではない。ヨルトにしてみれば、局部に充てがうだけの道具が意識を持って話しかけてきたようなものだ。ヨルトは独り言でも聞かせるように、シキネ・ホタルを探しているのだと話した。
「しきね、ほたる?」
少しハスキーな柔らかい声でドルフィーは問う。
「そう。ひとの名前だ」
「そういうの、『探しもの』じゃなくて、『探しびと』って言わない?」
ドルフィーはくすくすと笑う。
地球の公用語では「探しもの」も「探しびと」も聞き慣れない表現で、ヨルトには彼が何を笑ったのかわからなかった。地球では「探している何か」のような言い方をする。名詞化した「探しもの」という言葉は、おそらく日本語に由来しているものだろう。オモダルはもともと日本で作られ、その文化を残していたが、地球にあった日本の文化は、米国文化に侵食されて消えていた。
「ちなみにわたしはアリア。アリア・クエスティア。修道士。二七六五後期モデル。あなたは?」
そう問われて、戸惑いながら、
「ヒサキ・ヨルト。旅人。二七八二年生まれ。国籍は日本」
と答えた。
「修道士」には、地球とは別の意味があった。アリアはヨルトの首筋の臭いを嗅いだあと、体に沿って鼻を動かして、脇の臭い、掌の臭い、股の臭いと順に嗅いだ。
「恥ずかしいな。そういうのは」
「地球の臭いがする。いまだけだよ、こんなに臭うの」
「地球人が上がって来たらいつもやってるの?」
「ううん、今回が初めて……。いや、前にもあるかな。たまに。うん、何度かある。降りてきた地球人と」
「アリアのも嗅がせて」
「わたしのはつまらないよ。他の子と同じ。シリコンポリマーの臭い」
ヨルトはドルフィーの腰のあたりに頭を寄せて嗅いでみたが、嗅げば嗅ぐほどにシリコンポリマーの――雑貨屋の日用品売り場にほのかに漂う清潔な臭いしかなかった。アリアはヨルトの腰にしがみついて、芳香の沸き立つ縮毛に顔を寄せて、右、左、と丁寧に舌を這わせる。たまらずヨルトは、「もう一回いいかな」と、アリアの髪を撫でた。追加料金はかかるが、我慢できなかった。
「いいよ。口の中に出して」
アリアは言うと同時に、白く伸びた脚をヨルトの眼の前に跨がせては、シリコンのピットをその口に押し当てる。そして自らの口にはヨルトの熱くなったカーボンのシャフトを含んだ。
「オモダルのドルフィーって、みんなこうなの?」
アリアの濡れたシリコンの襞を舌で広げながらヨルトが聞いても、アリアの口はヨルトの露出した器官が占拠している。それが2回目。口腔内へ。3回目はまた互いに同じ方向に頭を向けて臨んだ。アリアは悪戯に、自分の口に含んだ乳液をヨルトに飲ませる。飲み下して、再度脚部から別れた枝のひとつをシリンダーへと挿入。更に追加料金がかかる。通貨は2種類があった。生活用品など、主に無限リソースに対して支払われるイェン――こちらは有効期限付きの減価型で、毎週一定額がチャージされる、21世紀の感覚で言えばクーポンに近い――と、貴金属や不動産などの有限リソースに支払われるベイ。地球ではイェンを求められることが多かったが、ドルフィーはベイを求めた。
ヨルトはアリアの背中に張り付いて、その胸に揺れるシリコンの柔らかい塊を弄びながら、ゆっくりと腰を前後させる。アリアはヨルトの手を取って、下腹部に当てて、「いまここにいるの。わかる? ここまで届いてる。もっと来て。もっと」と、その指先で示してみせた。
アリアのリアクションは動画で見る人間の肢体と変わらなかった。肌には少し透明感がある。実際の人間の芯はもっと柔らかいと言うが、ヨルトはそれを知らない。自分の手の握力に比べれば、ドルフィーの体は十分に柔らかい。
「ゆっくり。もっとゆっくり。いかないでね。ぎりぎりまで抜いて。そう。抜いちゃダメ。ぎりぎりで止めて。そして一番奥まで。そう。次はもっとゆっくり。どこまで届いたかわかるように。そう」
アリアには、呼吸は必要なかった。だが、そうやって体が接している間、動きに合わせて大きく息を吸い、そして吐いた。
「いまここ。こんなに奥」
そうやって指を取って示されるが、ヨルトには自分のものがどこまで入っているかの感覚はない。それでも、アリアがゆっくりとその指を上下させるので、おそらくアリアの感覚にはそれがあるのだろう――と考えていると、次のサイクルでアリアは深く息を吸って、ヨルトの指を
ヨルトの背中にはたすき掛けにした革のベルトにカードケース大の二酸化炭素還元装置が装着されている。体位を変え、仰向けにヨルトの体を抱きながら、アリアは不意に、ヨルトの背中の装置のスイッチを落とした。ヨルトはすぐに酸欠を感じる。ヨルトは焦りを感じるが、アリアは自分の呼気をヨルトの口から吹き入れる。呼気にはアリアが排したかすかな酸素が混じる。
「このままあと10回」
アリアはゆっくりと腰を動かし、それにあわせてヨルトの肺に息を送る。アリアはヨルトの生命を支配していた。ヨルトは生殺与奪の権を奪われながら、その悦びに身を委ねる。ヨルトの顔はみるみる青ざめて、それでもピストンを止めずに酸素を求めてアリアの唇に吸い付く。ヨルトは取材のなかで、呼吸だけで変性意識に入る瞑想法があると聞いたことがある。まるでその実践でもしているかのように、呼吸を合わせ、深い酩酊状態に落ちていった。
「ラスト1回。もっと求めて。もっと」
多くの地球人男性個体は、2度目には自分から生命維持装置のスイッチを切る。アリアはこの異臭を放つタンパク質の塊を、いままで数人死なせたことがある。
3 四条馬酔木亭
オモダルは4つのシャード、すなわち欠片で構成された人工天体で、最大のシャードは月の半分の直径を持ち、人工的に地球の7割の重力を発生させている。残りの3つのシャードはそれぞれボレアス(Boreas)、ゼフィロス(Zephyros)、オーロラリス(Auroralis)と呼ばれ、高度80キロから200キロの周回軌道を回り、こちらには重力はない。
中心にあるオモダル本星はカササ(Kasasa)と呼ばれ、大きく6つのエリアに分かれている。これは開発当初の計画の名残で、たとえばエーテリウム(Aetherium)地区は居住区、ヴァーダンティア(Verdantia)地区は森林・植栽エリアとして設計され、たしかにいまもその面影はあるものの、その機能は継承されていない。また、地区によって法律が異なるが、これはオモダル全域に共通する基本法のサブセットである。
オモダルの法律は地球とは異なり、遡及法がベースとなっている。つまり、新しく作られた法律が過去に遡って適用される。
遡及法は倫理的観点から忌避されてきたが、22世紀あたりになると法体系が複雑化し、同時に社会の変化の速度に対して法の整備が追いつかなくなっていた。そこで、立法事実に対して臨時的に政令が出され、法が施行されるまでは暫定法として機能する運用が始まり、これがいまのオモダルの法の原型となった。20世紀の法律は概ね、憲法、法律、条例、判例、慣習、と層をなしているが、オモダルでは条例にあたる部分に「暫定法」が位置し、これが法律をオーバーレイし、その内容は随時細かく調整された。
地球から1億5千万キロ離れ、環境も異なり、そもそもどこの国にも属さないオモダルには、当初法律がなかった。それぞれの国から派遣された者がそれぞれの国の法に準じて行動し、問題があれば都度話し合って解決されていたが、やがてそれが積み重なってある種の判例法が生まれた。国際協力のもとで開発が進んだ都合、「どこの国にも属していない」という体裁を保つために、当初は独自の法は設けない方針であったが、それから間もない頃に地上に起きた大規模な戦争が遠因となって、オモダルは自治権を得るに至った。「戦争のおかげ」というのもひどい話であるが、そも宇宙に生まれた新しい星の問題を、地上の思惑で裁けるはずもなく、何百万の死者を出したこの戦争も、オモダルには恵みとなった。その後オモダルは急速に発展し、地球人口を逆転、それとともに法律の量も爆発的に増えた。地球では良くも悪くも国が存在し、このセグメントによって法律の規模も制限されたが、オモダルではすべてがひとつに収斂する。法体系はあまりにも巨大かつ複雑で、いまではその全容を知るものはいない。問題が起きれば、巨大なデータベースから人工知能がケースに応じて判断する。法に制定されていない事案が生じた場合も、調整と判断は人工知能が行い、必要であれば立法を要求した。立法時には、新しい法によって生じうる問題を複数のケーススタディとして提示、市民がこのアンケートに答え、最適化を図るプロセスを取る。必然、立法には時間がかかり、「駆け込み犯罪」も見られるようになり、前述の暫定法による運用が始まった。
さて、敷根蛍だが、彼はいまより8百年も古い時代、アンドロイドの基礎技術となる自己再生性シリコンポリマー(self-healing silicone polymer)=SHSPを発明した科学者だった。生前、彼は軍と対立し、技術を独占、その秘密を漏らすことなく息を引き取ったとされているが、実はその「脳」が生きているという噂が、まことしやかに囁かれている。しかし、8百年を遡るとなると、21世紀の感覚で言えば平安時代の人物だ。その潜伏先――死してなお潜伏と言うか否かはともかく――の有力候補が、人工天体オモダルであるとされていたが、真偽は怪しい。軍も彼を探している、目的は敷根蛍そのものではなくSHSPにあり、それをドルフィーの進化をリセットするために必要としている、と言われていたが、これもまた真偽は不確かだった。
しかし、噂レベルの話とは言え、軍がドルフィーのリセットを求めている話は蓋然性が高い。いまのドルフィーは機能が複雑化し、汎用性を失ったもの、いわば進化の袋小路にはまったモデルが多く、それらの早急な改善が求められていた。設計図のある通常の機械ならば、設計を引き直せば良いだけの話だが、ドルフィーは人間と同様に進化して変わっていく。恐竜が鳥へ進化することはあっても、逆はないように、たとえば宇宙環境に特化したドルフィーから、水中生活できるドルフィーは生まれない。進化によって特殊化した機能を回復するには進化前のパターンからやり直す必要がある。つまり、根本的な機構から実装し直そうと思ったら、8百年前に開発された初期型のドルフィーへと戻す必要があった。
この頃の末端ジャーナリストが追いかける定番のネタは、「大富豪ベソスのクローン」「英国王室の隠し資産」「ドルフィーの初期化コード」であったが、どの話も真実性に乏しく、ベソスのクローンにしても、英王室の隠し資産にしても、それらが没落する際に囁かれるようになったものだった。要は、支持者が再起を匂わせるためのブラフとして弄した情報が独り歩きしたものに過ぎず、同様に「敷根蛍の脳が生きている」という噂が立ち始めたのも、端的に言えば、地球軍が押されていることの証左だった。
それでも軍は、あえて噂を否定することもなく、あるいはその噂のおかげでひょっこりとSHSPが手に入る可能性も考えだのだろうが、おかげで地球の一部地域では「初期型のドルフィーがSHSPを持っている」だの、「その遺伝子情報を軍が求めている」だのというデマが広まり、「ドルフィー狩り」が始まっていた。狙われるのは、立場の弱い風俗関連に従事するドルフィーで、地域によってはそれなりに大きな問題になっていたが、軍も、またその噂を流す「自称ジャーナリスト」も、それらの事件には頓着しなかった。
今回オモダルを訪れたヨルトもまたジャーナリストだった。SHSPの情報にも詳しく、その発明者がオモダルに逃れた件についても、本人が確信できるだけのデータはあった。
敷根蛍の脳に蓄積された情報を利用し、オモダル産のドルフィーは進化を続けている――というのは地球ではよく聞かれる話で、それを裏付けるように、オモダルのドルフィーは地球のものより格段に優れた性能を持っている。もちろん、この性能差はそれを生み出す社会背景があってのことだったが、ヨルトには構造的に物事を考えるほどの思慮はない。「だれかが仕組んだから、この結果があるのだ」と考えるのが常で、それがだれの、どんな思惑であるかを暴くのが、ジャーナリストとしての己の使命だと信じて疑わなかった。陰謀論は神話だった。自然現象の原因に神を想定することに似ている。その神が人間が作り出した幻影に過ぎないように、あらゆる陰謀はジャーナリストによって作り出される幻想に過ぎなかった。
ちなみに、であるが、この頃のジャーナリストには、概ねふたつの系統があった。
古い時代のジャーナリズム、すなわち、18世紀にイギリスで生まれた『タイムズ』に端を発する新聞・ラジオ・テレビ勢力は21世紀になると急速に勢力を失い、一時的には個人の発信するニュース情報に立場を奪われたが、新聞社の機能の多くは彼ら個人ではなく、他のふたつの巨大機構に引き継がれることになった。
そのひとつは大手金融機関の調査部門で、21世紀末に様々な金融機関が解体・公益法人化されるとともに、この機構が独立し、表舞台に出た。金融機関は、企業の経営状況から国家の財政まで幅広いデータを収集し、金融商品の開発に利用してきた。これをニュースとして小売したのだ。彼らの特徴は「手堅い未来予測」で、たとえば国家がどんなに原子力発電を「安全である」と喧伝しても、彼らは決して保険を請け負わななかった。それがコスト的に見合わないことを知っているからだ。
もうひとつのジャーナリズムは、ハッカー集団のギルドだった。21世紀の頃には企業の調査機関から非公式の依頼を受けることもあったし、あるいは国の諜報機関と組むこともあったが、やがて国家・企業は解体され、それが融合していくかの動きを見せるなかで、ハッカーグループのひとつである「ナルコード(NullCode)」は、「領土なき国家」として独立を宣言、情報の監視者としての地位を得るに至った。
この二者にはそれぞれ特徴があり、金融系は利潤追求の意図が見え隠れし、ハッカーグループにはスタンドプレイを好む一面があるとされたが、あるいはこれも先入観がそう見せているのかもしれない。
ヨルトは直接的には、このふたつの系統のどちらにも属せず、身近なニュースを仕入れてはいずれかに投稿するという仕事をしていた。同様の市民は多数観測され、本人たちは「ニュースをレポートしている」つもりでいたが、実情は「ニュースとして収奪される」側にいた。情報機関が必要としたのは、彼らが上げてくるニュースではなく、彼らが何に興味を示し、その先に何があるか、だ。彼らは売った以上の情報を買わされていたが、広告やサブスクを通して支払うそのコストには気が付かない。メディアはその収奪のために、ニュースに懸賞を出す。集まったニュースを分析し、実入りの良いニュースに錬成するサイクルは、砂金採取に準えて「インテリジェンス・パンニング」と呼ばれていたが、パン皿を流れていく砂粒たちは、そんな仕組みなど知る由がない。顧みれば「ゴールドラッシュ」が何を指したかといえば、金が大量に発見されたことではなく、金に目が眩んだ亡者が押し寄せて、金を落としていったことを指した。自称ジャーナリストの彼らも同様だ。金を撒けばニュースが集まる。そのニュースが金になる。そのサイクルでニュースが生産されると、やがて自家中毒を起こし、金になるニュースが過剰に喧伝され、ひとを煽り、煽られたひとはまたニュースを発信する。この「情報のねずみ講」とも呼ばれる現象に、ハッカー系はたびたびカウンターを当てたが、総体として見ると、同じ穴の狢であった。
そうして情報機関に深くコミットしていると、人類とドルフィーの間で戦争が起きるだろうことは予測されるようになるが、それに備えて軍事株の売買を始めるのが、彼らのセオリーだった。情報機関がどれほど巨大になったところで、戦争を止める術はない、ならば稼ぐべし、が、彼らの姿勢だったが、ドルフィーとの対立を間接的に煽ったのは彼らだ。そしてまた、自分たちが戦争を煽ることになるのも、百年前には指摘されていたが、それも止められなかった。それが金になり、正当化され、そしてまた世界は少しだけ沈んでいく。そうやって構築された社会の中にいる以上、その必然の歴史を避ける術はない。そのなかで生まれたのが「SHSPが社会をリセットする」という幻想、吸血鬼の息の根を止める銀の弾丸だ。
「ヒサキは日本の名前?」
アリアが尋ねた。
「そうだよ」
ヨルトの脳裏に、アリアのようなドルフィーは、地球では狩りの対象だというニュースが過る。市民番号の何番がSHSPを持っているかも記憶している。それは、アリアが「狩るべき対象」であり、同時に「守るべき対象」であることを意味するが、地球ではそれを「恋」と呼んだ。
「漢字で書ける?」
アリアは更に尋ねるが、漢字を使う文化はオモダルでも特定のシャードに限られる。それも看板やロゴにその姿が残るだけで、文字を書くという文化はない。漢字由来の言葉は韓国語、日本語、中国語が入り乱れ、ベトナム語に由来するものもいくつか指摘されている。29世紀の地球で最もメジャーな言語は、黒海沿岸を発祥とするスラブ系の英語――国際紛争の隙をついて、西側入植者が占拠して生まれた国に由来するが、詳細は割愛する――で、各国の文化に根ざす言葉はそれに取り込まれた形でしか残っていない。
「久しい木に、久しい三」
そのまま書けば、久木久三となる。ヨルトはいつか読んだ日本の古い小説を引いてそう答えたが、ナルコード社のデータベースに登録されているのは「飛先」だった。この文字コードもいくつか遡った祖先が3百年ほど昔に登録したもので、その頃にはもう漢字文化は廃れていた。後にそのデータベースは幾度かクラッシュし、再構築され、実質的な意味は持たないとされていたし、ヨルトはその字を書けなかった。結果としてはヨルトのいう「久木」が正解である可能性もあるが、ヨルトは「久木久三」の4文字で「ヒサキ」と読むと思い込んでいた。
「へえ。地球っぽいね」
アリアは脳裏に、丘の上に仰ぎ見る3本の木を浮かべた。歩きながら、話しながら、宇宙港を擁するオービタス・コンコードから、居住区のエーテリウム地区へとトラムに乗る。アリアもそのあとに続く。ヨルトは自分のあとをついてくるアリアを子猫のようだと思った。
「家には帰らないの?」
ヨルトが聞くと、
「家?」
――と、アリアは小首を傾げる。
そもそもドルフィーたちに固定の家はないということだろうか。
「私物とかは、どこに置いてるの?」
聞き方を変えてみた。
「私物?」
「思い出の品物とか」
「ああ。あるよ。たくさん」
「どこに?」
「どこ?」
いくつか言葉を交わし、ヨルトは言葉でのコミュニケーションを半ばあきらめ、その視線をアリアの腹部から脚部へと泳がせる。肌は人間のものよりもやや透明感がある。短いスカート。太腿に青い静脈が透けて見える。この頃になると、「まるで彼女ができたようだ」という感覚が芽生えていた。
他方、アリアはよくこうして地球人につきまとった。曰く、「地球に行ってみたいから」とのことだったが、これもまた方便で、何度か質問されて返しているうちに、相手が納得しやすい回答へと落ち着いたに過ぎなかった。
「京都に行ってみたいの」
この答えもしかり。
「京都に行きたい」はだれが聞いても納得のできる答えだった。自分の意図よりも優先して相手が納得できる答えを選べることが「コミュニケーション能力」だ。物事の多くには理由などない。「どうしてあのひとを好きになったの?」にしても、「どうしてこの仕事を始めたの?」にしても、なにか繕えば、それが後付で理由になる。「どうして地球に行きたいの?」、しかり。そうやって話すうちに京都への憧憬が芽生える。コミュニケーションによって、自らの内面が変わる。これも、コミュニケーション能力だ。通常の感覚では「京都が好きだから、地球に行ってみたい」だが、アリアの場合、「地球に行ってみたいから、京都が好き」だ。そしてそれも更に辿れば、地球人と話題を作るための「地球に行きたい」であったし、真にアリアが愛してやまないのは、地球人の断末魔の口臭だった。体を揺らしながら地球人の口に上がってくる胃の奥の匂いが、アリアを絶頂に導く。それをアリアは、自分たちドルフィーにはない「魂の匂い」だと思っていたが、これもまた単にアリアの記憶に刷り込まれた「物語」でしかない。
「魂がない」と言うのはドルフィーたちが感傷的に口にする常套句で、それを「地球人との恋愛を通して吸収する物語」として消費することが彼らの恋愛の本質だった。そしてそれは、漫画やドラマで流布するラブストーリーのように共有される。相手の生命を弄ぶ残虐性を彼らは自覚することなく、自らの手で殺す感覚もない。激しく求めあった結果によってパートナーは命を落とし、挙げ句、悲しみにくれて涙を流す。それが、アリアたち「修道士」にとっての「パートナー」だ。
「彼はわたしに魂を残して死んだ」
その新たな主人公、新たなエピソードを纏った物語は、まただれかに伝わり、それを聞いたものはまた涙を流し、地球人との恋を夢見る。アリアにとってヨルトは、余命半年の恋人だった。
「ホタルはどこにいるの?」
アリアは聞いた。
「いくつか候補はあるけど、絞り込めていない」
「恋人?」
「違うよ。ずっとまえに死んだひと。いまは脳だけになってると思う」
「えっ? それってホタルの脳であって、ホタルじゃないよね?」
「でも、脳が残ってるんだったら、それはそのひとだよ」
「そうかな。ある日突然、恋人が脳と体に分離したら、恋人は脳の方ってこと?」
「そうだよ」
「その脳を移植したゴリラと、ゴリラの脳を移植した恋人が訪ねてきたら、ゴリラを選ぶってこと?」
「そうなるね」
「でもさ。恋人は姿もゴリラだし、ウホウホしか言わないよね?」
「まあそうだろうね」
「ゴリラの方は、人間の身体で、汗も匂いも元の恋人で、恋人の声で泣いたり呻いたりして、ちょっとずつ人間の言葉を覚えていくんだよ?」
「でも、ゴリラはゴリラだよ」
「そうかしら。子どもを生んで育てられるのは、恋人の体だったほうだよ。わたしたち、そうやって肉体で生活して、肉体で繁殖して来たんだよ?」
脳は肉体からの信号を蓄積した器官だ。ゴリラの体に接続されたら、やがてゴリラを内面化するし、人間に接続されたら、やがて人間の振る舞いを覚える。
「それでも、心がゴリラだったら、ゴリラじゃないかな」
「でも、脳はコピーできるけど、体は唯一だよ?」
結局アリアは、ヨルトが取った部屋までついてきた。ヨルトは追加料金を気にして、入口のところで別れを告げたが、アリアが「じゃあ、ここで朝まで待ってる」というので、部屋に入れるしかなくなった。
小綺麗で何もない部屋に入りベッドに腰を下ろすと、すぐにアリアも隣に座り、しなだれかかり、押し倒された。ヨルトも戸惑いはしたが、期待もしていた。ただ、支払うべき料金のことが頭から離れない。この先のことを考えると、こんなことばかりに金を使うわけにもいかず、アリアが下腹部へと伸ばそうとする手を押さえた。
「ごめん。あの。お金がない」
「大丈夫。こんどは、わたしが買うの」
アリアの口からそう聞いて戸惑っていると、それを告げた口はそのままヨルトの口を塞ぐ。アリアは息を荒くしながら、舌を吸い、唾液を混じらせながら、ヨルトの被覆を脱がした。
「どうしてほしいの? 言ってみて」
自分のブラウスのボタンを解き、舌先を啄みながら、アリアが尋ねる。
「酸素を」
ヨルトが答える。
「悪い子」
アリアがヨルトの生命維持装置のスイッチに手を掛けると、それだけでヨルトはアリアの呼気を求めて吸い付いた。
「まだ切ってないよ」
悪戯に微笑んでそう言っても、ヨルトはその唇を求めてやまない。引き離して、その口に手のひらを当てて、彼の過呼吸な息遣いに合わせ、胸を揺らし、次の瞬間にスイッチを落とす。呼吸が速い。ヨルトからはもう、魂の匂いがしている。焦らして、焦らして、酸欠でぼんやりしていくヨルトの上、アリアは揺れながら、子守唄を歌って、深く息を吸って、ヨルトに吹き込んで、背中にしがみつくヨルトの握力にシリコンの皮膚を赤くしながら、また揺れた。
「あなたを妊娠させたい」
アリアが言うと、
「いいよ、アリア。僕を妊娠させて」
うわ言のように、ヨルトは答えた。
ヨルトが取った部屋には、ベッドと机と椅子の他には何もなかった。必要なものは、ツアー・コーディネーターが用意してくれるが、いまいま必要なものはない。ヨルトがずっと求めていたのは「恋人」で、それに等しいひとがもう、そこにいる。そのひとはことが終わったあとも、ずっと手を握ったまま離さなかった。
「そうだ。わたしの部屋に来ない?」
アリアの瞳が間近に覗きこむ。
「部屋?」
ヨルトは首を捻る。
つい何時間か前、家はないのかと聞いたら、アリアは首を傾げた。ヨルトはそれを「家はない」の意味で受け取っていた。あるいは、部屋はあるということか。地球では「家」でも「部屋」でも通じるが、別の概念なのだろうか。
「いい?」
アリアの問。
「いいよ」
ヨルトは返した。
Aria has been given permission to overwrite room data.
零れるほどに煌めきを溜めたアリアの瞳を静かに覗き返していると、彼は唐突に、「サニアス(saneatsu)」とだれかを呼ぶように発した。すぐに、
「おかえりなさい、アリア様。どのルームを展開しますか?」
どこからともなく声が返った。
「四条、馬酔木亭」
シジョウ・アシビテイ?
ヨルトが疑問符を浮かべていると、すぐに二匹の猫が暮らす和室の映像がヨルトの部屋に上書きされた。ヨルトにもそれがバーチャルな映像だとはわかったが、現実と見紛う。その様子は、ヨルトが資料でしか見たことのない京都の町家そのものだった。風鈴が鳴り、風が抜ける。
「ここがわたしの部屋」
アリアは言うが、ヨルトは呆気に取られる。
ここは、自分の部屋ではなかったか?
噂には聞いていた。バーチャルなデータと現実とをリンクさせた部屋があることを。その簡易版のようなものは、取材したこともある。知人からオモダルでは実用化されていると聞いて、試してみたが、そのときの感覚で言えば「まだまだ子どもだましの技術」だった。オモダルの連中はこの程度の技術を革新的なものとして吹聴しているのかと、少々蔑んだような気持ちになったが、眼の前に展開されたものはそれとは次元が違う。
「座って」
アリアが和風のソファを指差す。
だけど、そこに椅子なんかなかった。立体物は見えているが、実体はないはず――なのに、アリアはそこに腰を下ろす。
「びっくりした?」
アリアが悪戯に笑う。
「エーテリウム地区は、ぜんぶこのシステムに入れ替わったのよ。ベッドも椅子も、テンタクルス・アームで支えられてるから、座れるし横になれる」
テンタクルス・アーム――直訳すると「触手の腕」だ。京都の町家にしか見えないこの部屋も、その真の姿はタコの触手が蠢く狂気の空間なのだろうか。まるで恋人の肉体を持ったゴリラ、あるいはそれ以上の、意味不明な何かだ。
「見て」
アリアは部屋の隅にある、暗いガラス面のある木箱を指差す。
「テレビっていうの。番組のデータもいくつか手に入れたの」
そう言ってスイッチを引き上げ、ガラス面を点灯させると、コントラストの緩いぼやけた映像が現れる。
「すごい、それ……どうなってるの?」
「どうなってる?」
「ええっと、つまりその、これは、なに?」
ヨルトの体皮に、狂気と幸福とを入り混ぜた微電流が飛び跳ねる。
「これはねえ、こういうシステム」
アリアは物事を言語化するのが苦手なようだ。しかし、格好の取材対象だ。ヨルトはすぐにリストカメラを起動するが、モニターに表示される映像は壁や床から無数のファイバーが伸びる無機質な部屋だった。シャッターを押しても乱雑な走査線ノイズが現れるだけで、像を結ばない。どうやらホログラムを利用しているらしい。環境光まで記録しなければ再現できない類のものだ。おそらくは、部屋の全方位から偏光した光が参照光として照射されているのだろう。それを記録できるカメラはいまの地球にはない。かつて「オモダルの最新技術」として紹介されたニュースでも見たが、その映像もこれと同様のものだった。それを見て多くのものが「オモダルはこの程度のものを誇っている」と笑った。しかし、実情ではオモダルの科学技術は地球の3百年先を走っていた。
これは数多ある事例のひとつに過ぎず、地球ではオモダルの技術を模倣することすらできなかった。そこには3つの障壁がある。1つは重力。オモダルには無重力のシャードがあり、そこにある工場では重力の影響を無視して素材を合成することができた。2つめは酸素。酸素はことあるごとに素材に結合し、変質させるが、オモダルにはそれがない。3つめは電磁波。繊細な素材加工には電磁波が用いられるが、オモダルの電磁波は管理され、ノイズがない。
模倣して作れないならば輸入すれば良いのだが、それは政治的に叶わなかった。オモダルは無限リソース社会だ。あらゆる資材がタダで手に入り、所有者がない。究極的にはあらゆる製品が「定期的に配布されるチケット」を払えば無料で手に入る。他方、地球は有限リソース社会。その流通によるヒエラルキーで社会が構築されている。そこでは「財産の移動」に税金がかかり、企業国家共同体(Macro Regime:22世紀に現れた企業と国家を統合した国家を代替する概念で、多くの場合「レジーム」と略される)はそれによって運営されている。仮にオモダルの製品が全面的に地球に入ることになれば、
そしてこれを内面化して、マスコミはオモダルの科学技術を「取るに足りないもの」として喧伝する。――部屋のなかにバーチャルな3D空間を再現できたとして、なんのメリットがあるのだ。我々はアークトゥリアンの危機に晒されているのだ――と。
そして事実、軍需産業においては地球にアドバンテージがあった。そも、オモダルでは、アークトゥリアンとの戦闘は人工知能としてのオモダルがほぼ一手に背負っていたし、ドルフィーたちにも、戦争で殺し合うという発想はない。
幸福は相対的なものだ。己が幸福であるためには、他者が不幸だと信じればいい。地球人の多くが、オモダルは小惑星資材を集めるための未開の地だと信じた。
ヨルトはバーチャルに再現された部屋のテレビ、囲炉裏、茶箪笥と眺め、手を伸ばし、実際にそれは触れることもできたし、箪笥の戸を開けることもできて、そこにははっきりとした手応えもあり、風鈴の音を聞き、頬に触れる風を感じた。
そう言えば、アリアに「思い出の品」がどこにあるか聞いたことを思い出した。
「もしかして、アリアの思い出って、すべてデジタル化されてるってこと?」
改めて尋ねたが、この生活に長いアリアには、その質問の意図がわからなかった。アリアは「そうだよ」と口先で答え、ヨルトの体にしがみついて、ゆっくりとその指をヨルトの下腹に這わせ、耳朶を口に含んだ。
「浮世絵って知ってる?」
飾り棚には「蛸と海女」の春画があった。
ヨルトが戸惑い、返事を返せずにいると、アリアの肌は頭足類のそれに変わる。その指を艶めかしくくねらせ、肌の表面を蛸のように、白く、黒く、斑に変色させる。シリコンの肢体は、まるで溶けるように柔らかく、指先からいくつかに裂けて吸盤を持った触手へと変わり、その触手をヨルトの体に這わせた。
これもまたバーチャルな体験のだろうが、もはや現実との区別がない。ヨルトが伸ばした手は、アリアの柔らかな粘膜質の肌に飲み込まれる。体表を覆う粘液の感触すら伝うが、これもバーチャルなのか。アリアの中にすっぽりと取り込まれた腕に、無数の柔突起が這う。ヨルトの体を這い回る触手のどれがアリア本人によるもので、どれがテンタクルス・アームと呼ばれるマシーンによるものか。無数の触手の幾本かが生命維持装置と体の間に入り込むと、ゆっくりとヨルトの意識は酩酊し、朧になり、やがて手先を痺れが覆う。アリアの肩から延びた触手は粘度のある体液を分泌し、濡れた触手がヨルトを押さえ、穴という穴から侵入してくる。手先の痺れが腕を伝い全身に広がると、触手の1本がヨルトの赤黒く硬化した突起物に絡みつき、締め上げる。酸欠で視界の周辺は暗い。唸るような低い耳鳴りが聞こえる。水中にいるかのように音が遠い。鼓動に合わせて明滅する視界にアリアの顔が映り、呼気を吹き込むと同時に、その舌が長く伸びて肺を侵す。内蔵深くにまでその触手が届き、かき回し、ヨルトは己の放つ体臭と粘液とに塗れながら、宇宙の底に沈んだ小さな星の瞬きになった。
4 メダル
古来、労働は生活の糧を得るためのものだった。人類がまだ猿だった頃から――いや、ようやく脊椎動物になった頃から、猿のように、あるいは、魚のように日々の糧を得て、ときに他者の糧を奪い、争い、より強いもの、より多くを得たものが生き残り、尊敬された。
やがて糧が十分に手に入ると、労働はその分配の手段になった。長い脊椎動物の歴史から見れば、つい先刻の話だ。財が余り、国家が生まれ、国家は有り余る財を分配するために無駄な事業を行い、国民をそれに従事させた。真偽は不明ながら、ピラミッドの建造などもそうだと言われている。農繁期に余剰した税――徴収しておいて「余った」と言い出すのもいかがなものかとは思うが――で、農閑期にピラミッドを建造し、その対価として広く臣民に分配したのだと。
卑近な例で言えば、無駄にダムを作らせては賃金を払い、無駄なダムを壊させては賃金を払うことが、これに当たる。ジャンケンやくじ引きで、あるいは均等に分かち合えばよいものを、わざわざ労働によって分配したのは、それまでの「闘争」の名残だ。「治水にダムが必要だ」「生態系を取り返すためにダムを撤去すべきだ」と、それらしい理想や論理を吹聴して労働者をその気にさせると、それが労働者の意欲となり、誇りとなる。労働はドラマを生み、その汗と血と命を代償に完成された事業は小説になり、映画化され、多くのひとに感動を与え、「ダムには価値がある」あるいは「ない」という幻想を共有させる。それをいまさら「財産の分配は、じつはくじ引きでも良かったんですよ」とは言えない。彼らにとっては、努力と根性がアイデンティティだ。
いまのオモダルでの労働もこれに似ているが、実情は少し異なる。というのも、糧はもう自動で手に入り、稼ぐ必要などどこにもないことを、労働者自らが知ってしまったのだ。だれも働く必要などない。遊んでいればいい。労働が「糧を得る」という意味であれば、もうその役目は終えた。ひとは「労働」から開放されたのだ。だが、「労働」の本質は「糧」にはなかった。
29世紀の世界で、ひとは「他者とは違う自分」を表現するために働いた。20世紀前後の後期開拓時代ならば、労働は文化財なりインフラなりを残したが、いまは何も残さない。物理的な建築はすべて自動化され、アンドロイドとすら呼ばれない低機能なドローン群が組み上げる。ひとに求められるものは、なにもない。労働が現実の価値には一切結びつかないことを、だれもが理解している。にもかかわらず、ひとは無駄なものを稼ぐために働いている。
しかし振り返り見れば、たとえば宝石が価値を持ったのも、人類が生き伸びるために必要な何かがあったからではない。それが希少で、珍しかったからだ。無駄なものを無駄に流通させていたのだ。だのにそこには、たとえば、「芸能は何も生み出さない虚業、商売は価値を生み出す実業」と思われていた時代があったように、労働への強い幻想と依存とが導れた。
本質的には、宝石に価値などなかった。価値があるという錯覚が共有されているだけだ。いまでは、そもそも「価値」というものが存在しないのではないかと指摘されている。なんとなれば、あらゆる価値は流動し、去年流行したファッションは今年の流行に上書きされ、それもまた数年前の流行のリバイバルに上書きされることがあるではないか。それは、「ものに価値がある」のではなく、「それを価値としてひとに認めさせる力」が背後に働いているだけではないのか――と。特にここオモダルでは、生活を支える通貨である「イェン」は、一定の使用期限があり、使用期限のなかでも段階的に減価し、価値を計るには適さない。固定の価値を持つはずの「ベイ」は、プレミアがついたアイテムを手に入れるため、ときに途方もない額がやり取りされる。たとえば、20世紀のミュージシャンが残した1枚のメモに、中間層の生涯収入を超える金額がつく。同時にそれは、彼が手に入れた額ではだれも買わない。果たしてそれは、「価値」だろうか。
おかげで、多くのひとにとって「価値」などは、幻想に過ぎず、たとえばいま流行っているファッションに大枚を叩くとき、それが数日で無価値になる可能性も理解している。極論を言えば、「価値」は消費の瞬間にのみ発生する。すなわち、金で買っているのは「価値」ではなく「勝ち」だ。消費とは、ものを手に入れることではなく、金でだれかに殴り勝つことなのだ。
まだ「価値」という概念が「価値」を持っていた頃は、「珍しいものを所有する」ことが労働のモチベーションとなった。「宝石」という目的があったからこそ、ひとはそれを手に入れるべく働き、その労働が社会を支え、都市が機能した。舞台は変わるが、バーチャルな世界、たとえばオンラインゲームの世界なども、これと同じだと言われている。ゲーム内の「メダル」を手に入れるために、プレイヤーは課金し、サービスが維持される。実際そこにあるのは「価値」ではなく、それを「価値」として見せかける「幻想」であり、それは己の、「労働」=「闘争」への評価、すなわち「勝ち」だ。
ここではこの「価値」であり「勝ち」でもある概念を「勝値」と呼ぼう。その読み方は「かち」であり、同時に「かね」であり、また「しょうもねー」でもあり、それらの意味を同時に内包する。「勝値」は、存在(être)にも、生成(devenir)にも、過程(procès)にも、生起(événement)にも還元されない。勝値は存在から思考することができない。そのため、それは決して「現前(présence)」として与えられることはない。
少し引いて考えるならば、あるいは人類の労働の目的は、最初から「食う」ことではなく、他者からの「評価」ではなかったか。たとえばマンモスを獲って生活していた時代でも、狩猟の目的は「食う」ことよりも、「食わせる」ことにあったのではないか。そこで得たマンモスの牙が、今の時代でいうメダルで、「勝値」だ。考えてもみれば、ひとの親たるもの、たとえ自らが飢えようとも、子には優先して食わせたように思う。眼の前の子が飢えるのは、己が飢えるよりずっと辛いはずだ。もしそうでないとしたら、飢饉のたびに子よりも親が生き延び、人類はとうに絶滅している。人類が常に、価値の中心に置いてたのは、じつは「他者」ではなかったか。「他者」は「メダル」で象徴される。脳を持つ存在にとって、そこに見ている「他者」こそが己なのだ。つまりひとは、メダルという他者を得ることで、社会との繋がりを持ち、飛先ヨルトが人工天体オモダルを訪れ、一ヵ月が経った。
ヨルトの体からは、地球の生活で身についた体臭はほとんど消えかけていたが、幸いにもまだ件の恋愛体質のドルフィーからは飽きられても、殺されてもいなかった。月が一巡りする数の夜を重ねたが、千一夜にはまだ遠い。おそらく、二人の相性が良かったのだろう。ヨルトは良きパートナーと巡り合った。ふたりは、いまでは「サンド・ボール」と呼ばれるゲームにのめり込んでいる。
サンド・ボールは肉体を使うフィジカルなバージョンと、仮想空間で行うバーチャルなバージョンとがあるが、ヨルトがのめり込んだきっかけは、アリアに誘われてでかけたフィジカル版だった。20世紀のカップルがボーリング場やバッティングセンターに出かけるが如くこの競技に出向き、対戦に出て、アベレージを上げ、何度かアリーナと呼ばれる競技場に通い、それからバーチャル版の世界に飛び込んだ。いまではゲーム内の「ギルド」に所属し、「ルーキークラス」のプレイヤーに贈られるオレンジのリストを手首に巻いている。
リストバンドの色は、競技内でのプレイヤー・ランクを示していたが、サンド・ボールでは他にも様々なコスチューム、インテリア、ペットの類が景品として手に入った。もちろん、どれもバーチャルデータであり、リアル世界での価値はない。あるのは「勝値」であり、それを仮想空間の「マイルーム」に飾り、その写真なりをひとに見せれば、なにかしらの反応を得られるもので、
「ルーキークラス入りおめでとうございます」
「僕は3ヵ月かかりましたが、ヨルトさんは早いですね」
などと、社会への窓を開く。
ルーキークラスは下から2番目のEランクであり、ランクBである「マスタークラス」を超えると、バーチャル・チャイルド、いわゆる仮想空間にだけ存在する自分の子を持てるようになる。
――仮想空間の自分の子?
ヨルトもはじめの頃こそ、仮想空間で子を持つことにどんな意味があるのかと訝ったが、それも初期のほんの短い期間だ。
サンド・ボールでは、複数のプレイヤーが集まって「ギルド」を組むのが一般的で、ヨルトが所属するギルドは「
もともとは移民プログラムを利用しての渡航だった。人工冬眠を含む2ヵ月の旅程となるオモダルへの渡航には、戸建ての住宅に匹敵する費用がかかり、自費で渡航できるものは限られ、多くの場合は移民希望者向けにオモダルが用意した無料プランが利用された。渡航後1年間は基本的な生活費も出る。期限が来ても移民は強制ではなく、そのまま地球に帰るのも自由。「短期留学にも利用できます」と謳われたプランだったが、ほとんどの渡航者がオモダルに残ることを選んだ。
理由は単純だ。地球の7割しかない重力で1年暮らすと、もう地球重力では生活できないのだ。地球へ帰る1ヵ月前に、地下深くにある「地球重力層」で元の重力に体を慣らすのだが、ほとんどがそこでギブアップする。
ヨルトのようにオモダルに来て当初の渡航目的を忘れる、というのもよく聞かれる話だが、地球にいた頃の「人生の目的」が根底から解体されるのだから仕方がない。ヨルトが追っていた「敷根蛍の脳」にしても、「ドルフィーの進化をリセットする」だの「軍が買い取る」だのは、宇宙では取るに足りない話に成り果てる。そもジャーナリストというのが、「糧を分配するための無意味な闘争」に過ぎなかったことを知る。振り返れば、仲間内で話題になった事件を取材して、それが大手のニュース・ポータルに取り上げられ、そのメダルを自慢して暮らしていたのがヨルトだ。そのヨルトが、なんなら最大のニュースソースとも言うべきオモダルにいる。そしてそのオモダルが、地球より遥かに進んだ科学技術を誇るなどという事実は、地球にいる仲間は受け入れない。そこにはメダル=価値がない。オモダルという最大の価値に価値を見出さない彼らにとっての価値、それがまさに「勝値」であり、それを知ってしまえば人生観は逆転する。彼らは「オモダルは未開の土地だ」というニュースにしか食指を動かさず、ヨルト自身もオモダルを称賛した仲間を指弾したことがある。そんな自分が渡航の目的とした「敷根蛍の脳」に、どれほどの「価値」があるだろうか。
――と、言語化すればおそらくそんなことになるだろうが、ヨルトにはそれほどの思慮はなく、日々仮想世界で玉を転がした。
サンド・ボールは単純なゲームだった。標準ルールでは1チーム4人の2チームで対戦する。4人のうち1人がボールの中に入り、これを転がし、ゴールを目指し、残りの3人が「ガン・シャベル」というギアを用いて、砂を積み上げたり、穴を掘ったりしてサポートする。また、ガン・シャベルというだけあって、ピンポン玉大の弾丸を打ち出すことができ、これで自軍のボールを加速することもできたし、敵を足止めすることもできた。
さて、そんな単純なゲームがもう何十年も流行っていると聞くと、地球の古い人間でなくとも、「さすがは未開人」と揶揄したくなるところだろうが、このゲームの真価はメタ・ゲームにあった。他の諸々のゲームで得たトロフィーから、サンド・ボール内で使用できるアイテムを入手し、使用できたのだ。これは、他のゲームからプレイヤーを引き抜くための常套仕様で、多くのゲームが同様のシステムを採用しており、そこにどんな特典を用意するかがゲームの立ち上げの肝となった。専門用語では「勝値の流動性(LoWV, Liquidity of Winning Value)」というが、サンド・ボールはその最初の仕掛けで成功し、爆発的にユーザーを確保した。そうして一度勢いに乗ってしまえば、他のゲームとの連携も、自治体や企業とのコラボレーションも、勝手に転がり込んでくる。
先述のギルド・リーダーは、Ecliptica(エクリプティカ)というゲームの最高ランクであるプレデタークラスのトロフィーを持っており、これによってサンド・ボール内でも、日蝕時に限って宇宙怪獣に変身できた。21世紀に流行したONE PIECEなる漫画では、戦争が始まると海賊・海軍双方から数々の能力者が集まるが、あれもおそらく義憤や正義感からではなく「能力を披露したい」から集まるのだろう。
また、サンド・ボールには、サーバーごとに(実際にはサーバーは存在せず、ピア・ツー・ピアで構成された仮想サーバーがあるのだが、その説明は割愛する)様々なローカルルールが存在し、それらはリアルム(Realm)、すなわち「王国」という名前で呼ばれた。たとえば、どこそこのリアルムは1チームが8人だったり、別のリアルムでは全員がボール役だったり、あるいは特定のアイテムの使用が制限されていたりし、それぞれのギルドはどこかしらのリアルムを拠点に定めて活動し、たとえば「どこそこのリアルムに、これこれの戦術を使うチームがいる」と聞くと、そこに乗り込んで勝負をしかける。また、ギルドはアライアンスという大きな勢力に属し、これはONE PIECEでいう海賊と海軍にあたるのだが、アライアンス間の争いは更に熾烈で、大きな大会には他のゲームで最高クラスのトロフィーを獲った化け物がぞくぞくと姿を見せた。それがこの世界におけるマリンフォード頂上戦争であり、ドレスローザの戦いであり、ワノ国の鬼ヶ島決戦――と、これ以上の詳細は割愛するが、これがサンド・ボール・プレイヤーの日常で、そこにはリアル社会よりも遥かに複雑で広大な社会が広がっていた。
大きな試合のない日もリアルムごとに様々な大会が企画され、プレイヤーはリアルムを跨いで様々な大会に出場し、ギルド・ポイントを稼ぐ。現実にはまったく価値のないポイントだが、このポイントでまったく価値のないバーチャル・チャイルド用の服を購入できた。そのまったく価値のない子(9割以上は娘である)の容姿で、ギルド内の発言力が変わり、レアな装備に身を包んでいると「現実でも人格者なのだろう」という錯誤が生まれる。それがサンド・ボールというゲームであり、オモダルでの「労働」だった。「それは遊びではないのか?」と言うなら、絵を描くことだって、野球をやることだって遊びだ。
いまのヨルトはジャーナリストではなく、サンド・ボーラーだ。所属する
――地球からオモダルに来た主人公は、地球統合軍の秘密を暴こうとするが、すべてが虚構であることに気がつく。彼はオモダルに来てようやく本当の自分を取り戻すが、オモダルの「呼吸法」に慣れずに、少しずつ衰弱していく。そのなかでドルフィーと恋に落ち、魂のないドルフィーに自分の魂を残して死んでいく。
――まさにいまのアリアとヨルトを描いた話だった。
ヨルトはギルドの何人かに、自分がジャーナリストで、敷根蛍を探していることを伝えていたが、その「警句」として勧められたのかもしれない。余命何年の花嫁の類話が無数にあるように、地球人から魂を譲り受けるドルフィーの物語も無数にあり、多くのドルフィーに支持されている。もちろん、アリアがヨルトに「わたしに魂を残して死んでくれ」と言うわけではないが、彼らがそのストーリーにロマンスを感じていることは、アリアの反応からもわかる。それにこの美しい物語は、ヨルトの胸にも響いていた。
主人公が最後にヒロインに告げるセリフ――
「地球は骸。君の中に還りたい」
で、ヨルトはうっかり涙してしまった。
ヨルトの中でも、地球でなんの役にも立たなかった自分が、アリアの感情を呼び覚ますきっかけになるのならそれでいい――とでもいうような気持ちが芽生えていた。ヨルトらしい甘えきった考えだ。命をかけるのは簡単なのだ。死ねばいいのだから。難しいのは、生きることだ。
アリアとはリアルな営みの他に、バーチャルな営みもあった。リアルな営みも件のテンタクルス・アームで擬態した映像を重ね合わせると、ファンタジー世界がほぼほぼ再現できるのだが、バーチャルな世界では互いの姿を入れ替えることもできたし、ライオンになってシマウマに交尾を迫ることもできた。もちろんアリアがライオンをやるのだが、内蔵を食いちぎりながらことに臨んだところで、バーチャルな空間だ。痛みも匂いもない。
だけど、ギルド・メンバーのだれかが言った。
「そろそろ、痛みも感じるようになる」
それを聞いてヨルトは、技術の進歩で、バーチャル世界でも痛みを感じさせるデバイスが発明されるのだろうと思い、「そんなもの、なんのために作るんですか?」と聞き返したが、失笑を買った。
彼らによれば、バーチャルな空間でも「痛み」を感じるのだという。
「ハイ・リアルム――上級者向けのサーバー――では、怪我が治るのに、現実と同じ時間がかかるんだよ。そうするとだんだん、怪我をしないように立ち回るようになるし、そのうち怪我したら痛み? に似た感覚を覚えるようになる」
「そうそう、血がどくどく流れるの見て、すっげー不安になったことある」
脳は「未来予測」で動いている。視覚からの情報を処理するのに、本来なら数秒の時間がかかるが、脳の予測機能によって、リアルタイムで感じているように随時修正されている。「いま」生じている感覚のほとんどは、数秒先に発生したものが遡って適用されたものだ。ギルド・メンバーは「痛み」も、脳の予測機能が生み出す虚構であり、その虚構から逃れる術はないと語った。
「実際にそれでショック死したひとが何人かいるって」
「いやいや、そういうのは都市伝説だから」
そんなバーチャルな世界。ヨルトはアリアとの営みのなかで、3度ほど酸欠で心停止に至った。アリアを抱いたまま、「心音停止」のアラートを聞き、そのたびにアリアは泣いた。
ヨルトは死後の放心のなか、心穏やかだった。きっとアリアは、コミックスのワンシーンと自分とを重ね合わせて泣いているのだろう。でも、死は不幸なことではない。僕は幸せだ。泣きじゃくるアリアに声を掛けたかったが、バーチャルな世界でも死体は喋れなかった。
大丈夫だよ、アリア。
僕は地球という骸が放った小さな光。
長い長い無駄な人生の果に、ようやく君にたどり着いた。
この光を、君のなかに残すために。
バーチャルで経験する死は静かだった。心の中のすべての波が消え、静寂に満たされ、ただ精神だけが覚醒して水面に浮かんでいるような。それはヨルトが求めてきた問の「答え」のようでもあった。
もちろん、本当の死はそんなものではない。感覚の主体すら消えた無だけが横たわる。他方、バーチャルな死の渦中にあるヨルトの意識は、肉体の支配から開放され、純粋にそれ自身の「生」を謳歌している。ただ果てしなく、無限に拡散する「生」。それが悟りであり、涅槃(NIRVANA)だ。決して「死」ではない。だがヨルトには、それほど深い思慮はない。修行僧が幾度かの「涅槃」の経験を経て、現実の意義を見失い、死に頼り、その憧れを強めていくように、ヨルトもまた死への憧憬を抱くようになった。死こそが悟りである、と。
繰り返しになるが、死ぬのは簡単だ。だれもが自由に死ぬことができる。だが、「生」を見つけるのが難しい。それを見いだせないものが「命を賭ける」などと言い出す。命を賭けるとしたら、それは死ぬことではない。生きることだ。そして、納得のできる「生」を見つけることほど難しいことはない。
あるいは、こんなことを言うギルドメンバーもいた。
仮想空間と現実とはやがて融合するのだ、と。
いまはテンタクルス・アームを用いて機械的に物質の「感触」を作り出しているが、将来的には金属水素を電磁的に空間に固定し、それによって感触を再現できるようになる。この技術がもう実用化目前で、感触も、色も再現できるという。つまり、現実の空間に仮想の世界を再現できるのだ。それはもう現実と何も変わるところがない。もし、旅人がその「架空の町」を訪れることがあっても、彼はその町が架空だとは気が付かず、そこで一生を終え、場合によっては子孫を残すこともある。そしてその子孫にとっては、その架空の街が現実となる。
現実の空間をそのまま作り出すには、現実の全原子配列を再現しなければならない、という「密度問題」というのもあったが、これも論理上は解決している。現実にあるほとんどの物質は、人工物も含めてすべて、自己相似形のフラクタルなデータに還元できるというのだ。つまり、ほんの短い数列を、手順に沿って操作するだけで、宇宙に見られるあらゆる現象を再現できる。その世界はだまし絵のような自己相似性を持ってはいるが、感覚上は現実の世界との区別はない。
現実味のない言葉に聞こえるだろうが、たとえば円周率は無理数であり、その数列にはありとあらゆる数字のパターンが含まれている。円周率を無限に計算すると、シェイクスピアのハムレットがそのまま再現されたところもみつかるだろう。同様の原理で、単純な数列からデータを取り出して複雑な仮想世界を作ることができる。おそらく宇宙開闢のときに神が作ったのは、たった1個の「数」だ。それは無理数であり、無理数とは宇宙であり、神それ自身だ。数により生み出される仮想空間は、宇宙を再現する。
「いずれ、現実と仮想空間とを分けて考えるものはいなくなる」
そう語った古参は、その話の最後にこう問いかけた。
「個人が死んだとしても、世界が死ぬわけじゃない。世界はずっとそこにある。だけど世界が消え、すべてがバーチャルに置き換えられてしまったら、世界は死んだと言えるだろう。そこで、世界が死んだことに気付かずに生き続ける個人がいるとしたら、彼はそこに『生』を見いだせると思う?」
どこかのリアルムでの大会の景品に「エウノミア・クリスタル」が出ると囁かれたのが、ちょうどその頃だ。
かつてエウノミアがあった火星と木星の間の、いわゆるメインベルトには、いくつかの小惑星群があった。それぞれの群は粉砕されるまえの母星に由来している。小惑星エウノミアも同様、エウノミア族と呼ばれる小惑星群の核をなしていたが、数億年を遡ればひとつの天体だった。いまではコンピューターの計算精度も上がり、粉砕前まで遡って計算することも不可能ではなくなっていたが、残念なことに小惑星のほとんどはオモダルに捕食されていた。
まだ星があった頃に生まれた仮説だが――太古、火星と木星の間に惑星セレスがあり、2つの衛星、フローラとテミスを従えていた。そこに太陽系外からエウノミアが侵入、フローラに衝突、その衝撃で衛星軌道からはじき出されたテミスが更に何億年かのちにエウノミアと衝突し、これらの破片によってフローラ族、テミス族、エウノミア族を擁するかつてのアステロイドベルトが形成された――
嘘くさい話ではあるが、元はSFコミックスから生まれた説であり、真剣に反論する者もないままに定説化した。「太陽系外」という言葉が大衆の好奇を捉えたのだろう。いまもエウノミア由来の石が珍重されるのも、この「エウノミア外来説」の名残りと言ってよい。その説が語られたのも、もう5百年は昔の話だ。にもかかわらず、いまもエウノミア・クリスタルは、ダイヤモンド同様に高い価値を持っている。「エウノミア・クリスタルが景品に出る」というのは、「バカンティマウスで培養したゴッホの耳が景品に出る」と同じくらい無意味、かつ、最高のエクスタシーをもたらした。どちらも「すごい景品」以上の意味はない。
当然、
そんななか――
「わたしも敷根蛍を探しています。会って話せませんか?」
短い伝言が、ヨルトのメッセージボックスに届いた。
5 白いドレスの少女
クアロガン(kurogane)は獲物を見つけると動きを止める。風の動きに合わせてゆっくりと艶のある暗褐色の体躯を揺らし、ハンティングの構えに入ると視界から消える。そしてその幽かな足音に気がついた次の瞬間には、その前脚が胸を貫いている。奴は密林のなか、8本の脚を音もなく動かし、数百メートルの距離を一気に詰める。
いままで4度のシミュレーションで、クアロガンに遭遇することはなかったが、今日は違った。自宅に設定したハイ・リアルム・ワールドにて、遠巻きにクアロガンを目にしながら、ヨルトは立ちすくむ。少し離れてアリアがいるが、姿は見えない。連絡を取ればクアロガンが気取る。幸いクアロガンはまだ動きを止めていない。だが、その動きが止まった5秒後には、二人のうちどちらかが餌になる。
エウノミア・クリスタルが懸かった試合は、この鉄の脚と呼ばれる巨蜘蛛のいる密林で行われる。もし遭遇すれば、10秒で壊滅する。ルール上、ボール役を襲うことはなかったが、凹凸の激しい密林ステージでクルーを失えばリタイアするしかない。スタートからゴールまで20キロ。1日に3時間、1週間をかけて勝敗を争う。その間、怪我は蓄積する。
他方、アリアはこの試合に参加を予定し、アリアとヨルトが愛を重ねた仮想空間も、霧深い密林に設定を変えられていた。「ただいま」と部屋のドアを開けると、アリアはソファに深く座って、仮想空間のなかを歩いている。ヨルトもよく隣に座り、同じ世界に降り立ったが、地獄だった。ありとあらゆる大小さまざまのモンスターが襲ってくる。薬草や回復魔法などご都合主義なものはなく、怪我は包帯と薬で治すしかない。とは言え、怪我はバーチャルなはずだ。治りが現実世界と同じ速さだとは言っても、現実の肉体が傷つくわけではない。もちろん、それはわかっているのだが、密林に潜むクリーチャーから立て続けに襲撃を受けているうちに、「痛み」を感じるようになった。痛みは簡単に「恐怖」にすり替わる。それでも、バーチャルな傷、バーチャルな痛みだ。ゲームをリセットすれば怪我はもとに戻る。アリアも仮想世界でひどい怪我を負っていたが、「怪我に慣れておきたい」と、その傷をリセットしようとはしなかった。
「見て、これ」
アリアは、ブレードフィッシュに裂かれた腕の傷を見せた。怪我から丸二日は経ち、血は止まっているが肌は深く裂け、傷の周りは白く変色している。
「中指が痺れて動かない」
と、アリアは指を動かして見せる。
「痛くないの?」
「痛いと思わなければ痛くない」
たしかにそうだ。これは本物の肉体ではない。だがアリアの傷を見ているヨルトは、自分の腕にその疼きを感じる。現実世界でも大怪我を負ったひとからは目を逸らすが、仮想世界ではより強く他者の痛みを感じる。架空の世界の、架空の痛み。それはひとによく伝播する。本人が痛くなくとも、見ている側に「痛み」が想起される。そうやってお互いの傷と、その影響を見ているうちに、本人にも痛みが想起されるようになる。
ヨルトは不安に駆られながら、いくつかの演習をこなして、キャンプを設営した。
「今日はここまで」
アリアが架空の世界の架空のスーツを脱ぐと、手にも脚にも生々しい傷がある。それは生の不安となってヨルトに伝わる。その傷を晒したまま、アリアはヨルトのそばに来て腕を回す。ヨルトは自分の着衣の襟やベルトが、その傷を擦らないかと不安になる。
「痛くないの?」
「そればっかり」
アリアは笑った。
人生とは、アイデンティティの選択だ。だれそれはなんとかの研究者、だれそれはパイロット、と、ひとそれぞれにアイデンティティがある。飲み会で交わす話も、「実はなにそれの開発に携わりました」「子どもの頃からなにそれが大好きです」と、己のアイデンティティの話だ。ひととひととは共通点を見留めて接触し、十分な距離まで詰めたら、その差異を語り合う。ルーキークラス4人のうちのひとり、ヨルトのアイデンティティは「敷根蛍研究の第一人者」だった。地球ではそれが「科学」だったが、こちらに来てからはすっかり「オカルト」になっていた。
アリアのアイデンティティは「修道士」だったが、これは「プレイガール」の隠語だ。もともとは「ほどこしだけで生きている」程度の意味だろう。清楚で、経験のないふりを装って5秒静止し、一気に距離を詰めて獲物を狩る。「修道士」の隠語には、それでも魂は崇高ななにかに従属している――という意味も含むのだろうが、実際の修道士がどうであったか、彼らは知らない。もう何百年もまえに消え去った概念だった。
他の修道士同様、アリアにもヨルトの他に交際している相手が複数いたが、ヨルトに手を出し始めてからは、逢うこともなくなっていた。新しい地球人を見つけてしばらくは、ステディのように振る舞う。いままでずっとそうしてきた。そしてその古い彼氏と逢う時は、新しい恋人などいないかのように過ごす。
「ブレードフィッシュっていう魚だけど、すごい跳躍してきて、ヒレで裂くの。ずしゃあああっ!って。もう、心臓止まるかって思った」
「面白そうだね。でもそれ、だれと遊んでるの?」
「気になる?」
「別に。いまさらアリアがステディだとは思ってないし」
「安心して。ギルドのひとたち。特別な関係じゃないわ」
ヨルトは、アリアの二の腕と太腿に柔らかなガーゼの布を当てて、医療テープで留めて、ネットを被せる。
「今日はここで寝る」
甘いシロップに浸したアリアの声が綴る。
ただ、寝ると言っても、ここは仮想空間だ。
「でも、クアロガンがいるよ」
ヨルトは答える。
「クリーチャーはキャンプは襲わないよ。そういう設定になってる」
「いや、襲う襲わないじゃなくて、不安じゃない?」
「ゾクゾクする」
アリアはモンスターだ。ヨルトに顔を寄せて、傷だらけの体をヨルトに預ける。
「傷に慣れたいの。このままで」
仮想空間での睡眠から覚めると、ヨルトの傍らに、ひとりの少女が佇んでいた。
「おはようございます。ヒサキさん」
白いワンピースを纏って、少女は言った。
ヨルトは寝ぼけて、「う、うん」と答え、体を起こす。起き抜けのヨルトには、それがまだ夢のなかなのか、仮想空間なのか、はたまた現実なのか、あるいは仮想空間のなかで見ている夢なのか、区別がつかなかった。
「お会いする約束は、今日でしたよね? 先生のリアクションがないので、リスケしようかとも思ったんですけど、アリアさんが部屋に入れてくれました」
アリアが部屋に入れた? 部屋とは? リアルな部屋のことか、ゲーム内のルームのことか。
一瞬、まずいと思った。ヨルトはたしかに今日、エルリーチェと名乗る人物と会う予定があったが、それが少女だとは思っていなかった。アリアにも来客があることは伝えていたが、敷根蛍関係だとは伝えていない。あらぬ誤解をされているかもしれない。アリアは果たしてこの少女をどんな気持ちで部屋に招き入れ、どんな気持ちで部屋を出て行ったのだろう。そう思って、メッセージボックスを覗くと、アリアからのメッセージが1件届いていた。
「その女に騙されないでね」
たった1行のメッセージ。気まずさに息が詰まる。
それにしてもだ。騙されると言っても、白いワンピースの純真な少女だ。どこにそんな悪意があるというのだ。それによくよく思い出してみると、ここはまだ仮想空間だ。エルリーチェが訪ねて来たのは、仮想空間の自分の家であって、現実での接触ではない。仮想空間であれば、本来ならアリアに遠慮するようなやましいことは――が、これもよくよく考えてみれば、アリアとはここでやましい行為を重ねてはいるが――果たして、仮想空間は本当に現実の外なのか? という不思議な疑問も湧かなくもないが、それはさておき、彼はアリアに比べれば、ずいぶんと清楚な身なりをしている。むしろ、ギルドリーダーの娘に印象は近い。
「改めてはじめまして。ずっとハイ・リアルムで生活しているんですか?」
白いドレスの少女が尋ねる。
「いや。いまは試合の前だから、訓練で。それに、普段はリアル空間のほうにいます」ヨルトは答えたが、後半はごく当たり前のことだった。
「試合の賞品としてエウノミア・クリスタルが出るとかで、ギルドをあげて猛特訓中なんです」
繕うように言葉を継いだ。
「そう……あのクリスタルが……」
含みのある相槌が返った。
エルリーチェは10代に見えた。アリアも外見は10代に見えるが、もっと幼い。すると彼もドルフィーなのだろうか。だが、仮想空間での話。リアルで何者かはわからない。
「エウノミア・クリスタルのことはご存知なんですね」
彼の柔らかい視線が、ヨルトの頬から鼻先のあたりに絡まる。その肌は人間に見える。口に漏れる仄かな暖気が、香りのない香りになる。
「ええ。太陽系外から飛来した惑星の名残だと聞きました」
「そう。そしてその正体は?」
「正体?」
ヨルトが知っているのは、小惑星エウノミアが太陽系外から来たということくらいだ。正体と言われても。戸惑っていると、彼が続ける。
「アークトゥルス星人のクリスタル化した脳――」
ヨルトの耳にはそう届くが、いったい自分は何を聞いたのか。彼の瞳はヨルトの返事を待っているが、言葉が見つからない。
「脳――なんですか?」
「そう。人工脳。エウノミア・クリスタルは四次元結晶で、もし賞品で手に入れたら重量を計ってみるとわかります。向きによって重さが変わりますから」
情報量が多い。アークトゥルス星人、人工脳、太陽系外、四次元結晶、向きによって重さが変わる、いったいどこから噛み砕けばいいのか。
「X線解析で、結晶構造と非結晶構造を同時に持つこともわかってます」
また増えた。
「なるほど。それも向きによって……」
何も理解できないが、当てずっぽうに言葉を返す。少しは会話をしている体にはなったが、キャッチボールはできていない。
「クリスタルにデータを記録する技術があることは?」
「ああ、知ってます。最近のサーバはすべてそうだと」
この程度であれば、ヨルトにもわかった。「文字は何に印刷されますか」「紙に印刷されます」と同じくらいには自明で、ハイスクールの生徒すら知る常識だ。「データは何に記録されますか」の答えは、「クリスタル」だ。
「これが四次元だとどうなると思います?」
「四次元ということは――」ヨルトはしばし考えた。旧来のシリコン・ウエハーへの記録は二次元だった。それを何層かに積み上げて容量を増やしてはいたが、クリスタルへの記録は三次元だ。二次元が三次元になって、爆発的にその容量が増えた。つまり。
「更に容量が増える?」
「単純化すればそう。だけど、四次元だと、容量が増える以上のことが起きる」
容量が増える以上のこと? 四次元? 時間と空間? タイムワープ? 四次元トンネル? どれも口に出すことを躊躇う。
「というと?」
「たとえば、二次元にもう一次元加わったデータは?」
「三次元」
バカの答えだ。
「答えは三次元ではなく、アニメーション――」
言ってよ、最初に。
「――動きが記録できる。一方、ひとの記憶を三次元のデータに転写できることがわかってる。これを四次元に拡張すると?」
答えはすぐに浮かんだ。記憶の連続体が表すもの、それは「意識」、あるいは「命」そのものだ。だけどヨルトは、はっきりとそう答えることを躊躇う。白い袖を揺らして、そのひとは続ける。
「小惑星エウノミアは、人工天体オモダルの核となっています。これは、どういう意味だかわかりますか?」
エウノミアはアークトゥルスから来た人工脳だから、オモダルの正体は……アークトゥリアン……? いや、でも待って。オモダルは地球で作られた。それに、人工脳の話もエビデンスはあるのか? ヨルトは会話の矛先を変える。
「あなたは、どこでそれを知ったんですか?」
彼は鈍く微笑んで、姿勢を変えた。息も荒く、病でも患っているかに見える。
「大丈夫ですか?」
ヨルトはまた質問を変える。
「大丈夫です」
息も絶え絶えに、彼は答えた。その息遣いとともに揺れる胸に目が留まる。おそらく操作しているのはヨルトと同様の炭素系の人類だ。それは推測というよりは、期待だった。息を整えて、エルリーチェは本題に入る。
「敷根蛍の件、どのくらいご存知ですか?」
彼の視線が自分を見ているときだけ、ヨルトはその胸元から視線を外す。
「地球でよく言われている程度のことは、ひととおり」
「水槽脳となって、娘の手でオモダルに運び込まれた――あたりですか?」
娘の手で? いや、そこまでは知らないが――
「ええ。そこから先を調べるつもりで、乗り込んできました」
「乗り込む」は、サンド・ボールで多用される言葉で、このケースで使う言葉でもない。それでエルリーチェは少し微笑んだが、ヨルトはその笑顔に色を感じた。匂いのない仮想空間に、仄かな
「
「ドルフィーの進化をリセットする、くらいのことしか。それがプログラムなのか、触媒なのか、あるいは魔法的なものなのかまではわかりません」
「調べてどうするんです?」
エルリーチェは質問ばかりで、自分のことは語らない。
「まずは調べてから、ですかね。エルリーチェさんは、どのくらい知っています?」
次の質問が来る前にと、急いで滑り込ませると、エルリーチェは答える。
「ほとんど、すべて」
ほとんど、すべて?
「それじゃあ、敷根蛍の居場所も?」
「はい。わかっています」
わかってます?
「その娘、敷根彩花も?」
「どの敷根彩花ですか?」
「どの? いろいろいるの?」
「ええ。ほとんどはドルフィー。最初に地球から訪れた彩花まで含めて」
「ドルフィーでない敷根彩花は?」
「オリジナルは地球で生まれ、22歳で亡くなっています。そしてその娘の名も同じアヤカ。こちらはL2で生まれて、2歳で死んだと言われています」
いや、まって。僕はいったい、なんの話を聞いているんだ?
すべての言葉がヨルトを戸惑わせる。そしてドレスの彼は、息を切らせる。
「それよりも、横になっていいですか?」
彼の額には汗が浮いて、息が上がっている。言い終わらぬうちに、脚を崩し、その場に横たわる。
「重力は久しぶりなんです」
「そうなんですか?」
「ええ。もうずっとボレアス・シャードで暮らしていて。ずいぶん骨ももろくなりました」
ボレアス・シャードは無重力と聞いている。そこで何年も過ごせば、骨も脆くなるし筋肉も落ちる。
「それじゃあ――」
ヨルトは部屋の設定を無重力に変えようかと思ったが、いまの設定がリセットされると、アリアの訓練が無駄になる。リセットせずに切り替える方法はあるだろうが、その設定法がわからない。戸惑っていると、
「大丈夫です。ここは、地球のようです」
彼は細い息を編むようにして答えた。
「地球にいたんですか?」
「ええ。もう、何百年も昔」
何百年? 脳内設定なら頷けるが、現実の話ならないだろう。何百年というのは具体的に何年だ。今まで少女だと思えばこそ胸元、腰回り、あるいは顔からも視線を逸らしていたが、その必要はなかったのか。それにしても、何百年? そう思いながらも、胸の膨らみに目が留まる。何百年。自分は、何を見ているんだ。
「わたしは……」
彼はゆっくりと言葉を紡ぐ。
「娘の手で、オモダルに運び込まれました」
いや、待って。だれの何の話だ? 敷根蛍の話なのか?
「娘とは?」
「敷根彩花。いま彼は、L2にいます」
ちょっと待て。おかしいおかしい。いろいろおかしい。主語は「わたし」じゃなかったか?
「月の裏側のラグランジュポイント。厳密にはL2を軸とするリサジュー軌道を巡っています」
その意味がにわかには掴めなかったが、エルリーチェによるとL1やL2はオモダルがとどまっているL5に比べると安定性が悪く、その周辺の不規則な軌道を回ることになるらしい。しかもラグランジュポイントには太陽-地球系と地球-月系とがあってよく混同されるとかなんとか、しかしヨルトはすでにオーバーフローを起こしている。知識の飽和攻撃だ。
「L2には、アークトゥリアンの前哨基地があると聞いている」
会話してる体裁を取り繕うため、頭に浮かんだことを口にする。
「そんなことはありません」
エルリーチェは青白い顔に、微笑みを作る。具合は悪そうだ。
「L2はアヤカシコネの星。元はドルフィー工場があったんです」
「アヤカ・シキネ?」
ヨルトは問い返す。
「違います。オモダルとペアで作られた初期型アンドロイド。アヤカシコネ。日本神話の
飽和攻撃、継続中。
「いや、待ってくれ。わからない。オモダルとペアで? オモダルがアンドロイド?」
「オモダルが地上のアンドロイド工場だったことはご存知ですか?」
「ああ、それが化学廃液の問題で宇宙に移設されたと聞いた」
「工場になる前は?」
「工場になる前?」
「オモダルも、アヤカシコネと同じ姿をしたアンドロイドでした。双方とも、『
「まさかそれが、いまのオモダルとドルフィーの原型?」
「いまのドルフィーは、オモダルがアヤカシコネを模倣して作っているものです。L2のアヤカシコネは、もう機能停止しています」
「待ってくれ。どうしてそれを僕に教えるんだ」
「あの子は、もうすぐワープ機構を獲得します」
「ワープ?」
いや、あの子ってだれだ。
「あの子の重力ジャイロが、あと五〇〇年で光速を超えます。それを利用するんです」
だから新しい情報を止めろ。ここはわんこ蕎麦屋か。
「ありえない。ワープもありえないし、ジャイロにどんなにエネルギーを注ぎ込んでも光速を超えることはない」
「ジャイロ全体の速度はそうです。だけど原子単位では量子論的なゆらぎからリープを起こせます。それを収束させれば、光速を超えるのは簡単です。あの子は、ワープします。だけどそのためには、
「ワープなんて……。まだ宇宙のどこでも観察されていないと聞いている」
「それは、あなたたちが時間に縛られているからでしょう?」
「いや、ごめん、その言い方だとわからない」
「あなたたちは、過去や未来が存在する前提で宇宙を観測している。だけどそれは、あなたたちの意識が作り出した幻想。人間の限界。過去も未来も、意識のなかにしか存在しない。だけど、真実は違う」
「ああ、うん、意味がわからない。ごめん」
ここに来てはもう、理解は諦めるしかなかった。
「宇宙には常に『いま』しかない」
的を射ない会話に、苛立ちが募る。
「うん。そうかもしれない。でもさ。あなたは、だれなんだ?」
もうこれ以上、ついていけなかった。
「ホタル。敷根蛍。どうかわたしを、オモダルへと届けて欲しい」
敷根蛍? それが真実なら、探している本人だ。ビンゴ! いや、嘘つき! それにしても、重力が堪えているのか、ひゅーひゅーという喘鳴すら聞こえはじめる。ヨルトはその傍らに座り、背中に手を添えた。
「あなたはボレアス・シャードにいるんじゃないのか?」
その感触は、アリアよりずっとやわらかな、カーボンの体だった。
「ボレアス・シャードにいるのは仮の肉体……もう長くない……だから……」
蛍は、いやエルリーチェは、ヨルトの手を取る。
「僕はどうすればいい?」
炭素細胞の柔らかな手。汗の感触。胸の膨らみが上下する。それはシリコンではなく、人間の肌に包まれている。情報はもう過積載で溢れだした。いまの気持ちを一言で言うとしたら、詩的に、文学的に、あるいは精神分析的に気取って言うこともできるだろうが、取り繕ってもどうせ見透かされているし、見て見ないふりはしているが、端的に言えば胸の膨らみ――おっぱいともいう――そう、そのおっぱいから視線が離れない。
「L2への連絡船――」
蛍と名乗った存在がそう口にした次の瞬間だった。
巨大な鉄の槍が彼の胸を貫いた。
クアロガンだ。その巨大な鉄蜘蛛は二本の前肢で高く持ち上げたエルリーチェの体を地面に叩き下ろすと、刺吸型の口吻をその胸に突き立てた。いったい何が起きたかわからなかった。いや、起きたことはわかる。エルリーチェが巨大な鉄の蜘蛛に襲われたのだ。アリアは「キャンプにはクリーチャーは入ってこない」と言っていたが、設定ミスか何かあったのだろう。ヨルトもアリアもこのゲームについては素人だ。
そして眼の前でエルリーチェ、あるいは蛍と名乗った何者かが、仮想的なクリーチャーに殺されて死んでいる。いや、本当に死んだのか? 本体はどうなった? 無事なのか?
――実際にそれでショック死したひとが何人かいるって。
ギルドメンバーから聞いた言葉が脳裏に蘇るが、だとしたら、この場合、このゲームの管理者である自分はどうなる? 死体遺棄? もしかして、殺人?
ヨルトはただ呆然と、現状を維持したままログアウト。アリアが帰るのを待った。
事情をすべて聞いたアリアの第一声。
「ざまあみろだわ」
いや、仮に嫉妬心があったとしてもそれはない。たしかにヨルトがカーボンフォークの彼に心をときめかせたのは事実だ。しかし、それと「死」では次元が違う。戸惑っていると、嘲ったような口ぶりでアリアは続ける。
「で? サインはする前だった?」
サイン? なんのことだ?
「L2への連絡船のカンパに、いくら要求された?」
「いや……連絡船の話が出た直後に、こうなって……」
「じゃあ、良かったね」
良かった?
「有名な詐欺だよ。敷根蛍を調べてると寄ってくるんだって。こういうのが。たくさん。こいつら、家族の財産までぜんぶ毟るよ」
詐欺? エルリーチェが?
「わけわかんないこと無限に言って、混乱してよくわかんなくなって、もしかしたら自分が世界を救うヒーローかもしれないって思い始めた頃に、『いくらいくら必要です、契約してください』って言ってくるの」
思い当たる節がある。ありすぎる。しかし、そうは言われても、ヨルトの手は彼の手を握った感触を覚えている。それがクアロガンに刺された瞬間に弛緩した。その死は電撃のようにヨルトの体を走ったのだ。
「だいたいエルリーチェって名前が嫌。あざとい。白のワンピースも嫌。こんな狙い澄ましたキャラにまんまと落ちるんだ、ヨルト少年は」
さんざんな言われようだったが、眼の前でひとひとりが死んで、そのショックもまだ醒めやらない。
「でも、本当に詐欺だと言い切れるの?」
ヨルトは言い返した。
アリアは溜息を吐く。アリアにしても、ついこないだまで敷根蛍のことを知らなかったのだ。この詐欺師について多くを知るわけではない。最近になってギルドメンバーから聞きかじっただけで、それでここまで詰め寄るのは、多少の嫉妬はあったのだろう。
6 支配とその偽装について
ゲーム内で死んだキャラクターは、リスポーン処理、いわゆる自動蘇生して再ゲームの流れになる。ハイ・リアルムでは、通常はゲームオーバーとして処理されるが、練習用のアリアたちの設定では、エルリーチェはその場でリスポーンしていた。「キャンプにはクリチャーはスポーンしない」の設定を確認し、アリアとヨルトが再度ゲームにログインすると、無惨に食い荒らされたエルリーチェの死骸の隣に、怪我も汚れもないエルリーチェがリスポーンして「寝る」のポーズで横たわっていた。
「もしもし」
ヨルトが声を掛けるが返事はない。
アリアは無造作にガン・シャベルで臀部を突き、ワンピースの裾を捲くろうとする。
「やめなよ。起きたらどうするんだよ」
ヨルトは制するが、
「中身はどうせオッサンでしょう? ショックで死んだんじゃないの?」
アリアは吐き捨てる。
仮想世界では、女性アバターを使うひとが多い。
アリアは面白がって、エルリーチェの裾を捲りあげて、頭の上で巾着状に結んで、ガニ股の変なポーズを取らせて遊んでいる。白い下着と、カーボン組成の柔らかい肌が見える。現実のヨルトが触れたことのない肌。アリアはマーカーを取り出して、その肌に「童貞の妄想」だの「ヘンタイ専用」だの「バーカ」だのと落書きしている。挙げ句、「たぶんパイパンだよ、コイツ」と、ピッケルを下着のウエストに入れる。
「ほらやっぱり」
アリアはエルリーチェの下着を下げ、泥のついた靴底で無造作に脚を押し広げて、「うっわっ。きんも。見てこれ。きんも」と、ヨルトに指し示した。
ヨルトは呆れた。アリアが言うように、たしかにプレイヤーは中年男性かもしれないが、確定したわけじゃない。仮想空間とは言え、そこで演じているひととして接するのはオンラインのマナーだ。とは言え、アリアが指し示すそれをヨルトも見たくないわけじゃない。架空に過ぎない少女の、架空の股間の、架空のそれを。眉をしかめ、アリアの悪趣味を責めるような素振りをしながら示された場所を見ると、小さな泉を囲む草のない柔らかな丘に、
「To my Lord Sion, I vow my eternal chastity.(我が主・シオン様に 永遠の純潔を捧げる)」
の刺青があった。
「きんも。きんも。要はシオンってのが、このキャラのオーナーってことでしょ?」
アリアが嘲る。だけど多分、アリアが言う通りだろう。シオンを名乗る人物が、オンラインで自分好みの幼いキャラを作って、その秘部に自分を称賛する入れ墨を入れたのだ。さすがのヨルトも頭を殴られる思いがした。シオンなる人物への激しい共感羞恥も感じた。だがそれでも、だれかに無理やり入れられた可能性というのも捨てきれない。
「やめようよ」
そう言って頭上に結んだスカートの裾を解くと、焦点を外したままのエルリーチェの顔が、
「やりたい?」
アリアが訊いた。
「やっちゃいなよ。見ててあげるよ」
ある意味、見透かされてはいたのだ。いまのヨルトのひとつひとつの行為をすべてつなぎあわせて現れる文字は、たしかにそれだ。やりたい。アリアがいない世界だったら、やったかもしれない。実際には未成年とのそれは、システムにロックが掛かっていてできないのだが、そのアラートを目にするところまでは行ってしまうだろう。だけど、だからこそ、その言葉がアリアとの間に決定的な溝を作った。
ボレアス・シャードへの輸送艦に乗ったのは、その直後だった。「人足船」と呼ばれる小汚い船。ボレアスには小惑星資材が集められ、そこでは人間が仕分けを行っている。ドルフィーもドローンもあるなかで、なぜ人間が働いたかといえば、そこには酸素があったからだ。オモダルのドローンはもはや精密過ぎて、オイルの酸化すら劣化の原因となる。ドルフィーも還元装置を内蔵したタイプが多い。かたや人間は、酸素が大好きだった。ヨルトもほんの二月のあいだに、呼吸の仕方もずいぶんと忘れていたが、横隔膜を下げるとともに肺を満たす酸素には格別なコクがあった。呼吸をするだけでハイになる。呼吸、次の呼吸、次の呼吸と、階段を登るようにして自分の気持ちを高めることができる。ボレアス・シャードの無重力もいまのヨルトには真新しかった。
ボレアス・シャードの法は、オモダル本星に比べるとやや古く、「労働力の売買」が自由に行われていた。またここでは、ひとの臓器が「ボディパーツ」として取引され、一部は地球へと輸出されている。地球では主に資産家や軍人がそれを利用し、「男のパーツは兵隊が買い、女のパーツは変態が買う」と言われる――この言葉の裏には複数の構造的な差別があり、批判されており、現実にも即してはいないので、受け取る際には注意が必要だ。二七九三年刊『素粒子論的差別問題』に詳しいので参照されたい――のだが、無重力に慣れて筋力が落ちる前のパーツほど高く売れる傾向があり、20代前半のヨルトであれば、両腕両足両目をセットで売り払えば、一生派手に遊んで暮らせる金が手に入った。いや、そんな状態で遊べても、と、思うだろうが、現実の肉体がなくとも、仮想空間だけでも生きていけるのがオモダルだった。金があれば、サンド・ボールのランク戦スキップも利用出来るし、L2への連絡船に乗ることもできる。とは言え、両腕両足両目をセットである。果たしてそこまでするほどのものだろうか。と、冷静なときなら考えるものだが、しかし、人間には己のすべてよりも重視するものがある。それがアイデンティティだ。死んだらアイデンティティもクソもないが、アイデンティティなしには「生」がない。
オモダルに来て、
あるいは、告白から始まった恋ならば、少しは違っていたかもしれない。その恋は、互いに互いを縛る約束から始まる。だけどアリアとヨルトのきっかけは、空港で「買った」こと。お互いに純潔であることなど期待していないし、「これからは1対1のステディとして付き合おう」と言い出すタイミングもない。お互いに束縛しなかったし、お互いに自由だった。成熟した者同士ならば、その関係を謳歌できたのだろうが、ヨルトもアリアも未熟だった。
ボレアス・シャードは、古い法が支配しているだけあって、やや犯罪率が高かった。たとえばである。オモダル本星では、強盗がほぼ発生しなかった。なぜか。強盗被害者に被害額以上の補償が降りたからだ。どんな厳罰を用意しても減ることのなかった犯罪率が、「被害者の方が儲かる」よう設定しただけで、嘘のように減った。ところが、この法をボレアス・シャードは採用しなかった。さすがにナンセンスだと反対するものが多かったためだが、おかげで強盗を生業にしていたものは人足船に乗り込んで、ボレアスに移民した。不思議な話だった。ボレアス・シャードで強盗に課せられる罰は、オモダル本星よりも重いのに、なぜか集まるのである。これは何故かとあれこれ議論されたが、要はボレアス・シャードでは、検挙されない限りは強盗が「勝つ」が、オモダル本星では、強盗が何をしても被害者に「負ける」のである。ベーシックインカムが行き届き、衣食住に不足しない世界だったが、ひとはそこで意味もなく「勝ちたい」のだ。そしてこの、社会、酸素、オモダル本星よりも低い重力、等々のおかげで、ここを訪れた地球人はオモダルに帰ることなく、ボレアス・シャードは実質的に地球人隔離エリアとして機能していた。おかげで本星の人々は野蛮な地球人のいない文化的な生活を享受し、ボレアス・シャードには人足が集まるという一石二鳥の効果が上がったが、それをオモダルが意図して設計したかどうかはわからない。
ボレアス・シャードには匂いがあった。ひとの匂い、腐敗臭、それにどうやら人工重力のある居住区には、ネズミも繁殖している。そこでヨルトは「シオン」という人物を探した。それはエルリーチェの中のひとであり、エウノミア・クリスタルと敷根蛍の情報に通じ、そしておそらく、死んでいる。ボレアスは、オモダル本星を巡るシャードのひとつとは言え、数百万の人口を擁する。簡単にみつかるわけがない。と、思っていた矢先、本星のアリアからメッセージが届いた。
「変態中年のポータルIDがわかった」
変態中年。
ポータルIDは、数多ある仮想空間の共有IDだ。アリアは続ける。
「これである程度はトレースできると思う」
すなわちこの手掛かりさえあれば、各仮想空間――ネットワーク・ゲームやショッピング・モールに残る痕跡をたどることができるし、交友関係を当たることができる。
とは言えこれも果てしない話のように思えたが、エルリーチェ=シオンを探しながら、敷根蛍の情報も同時に当たっていると、例の詐欺団体の方から接触してきた。おそらく詐欺師側も、ヨルトの情報には興味があったのだろう。敷根蛍の件、
敷根蛍チャネルは総じてどれも詐欺で、オモダル本星ではこれほどあからさまな勧誘はなかったが、これも無法地帯ボレアス・シャードならではの光景であろう。学校やサークルの先輩が、押しの弱そうな後輩にラメ入りの謎の粉をかける姿が、そこら中のカフェで目撃された。そしてその指導者のひとりにシオンなる名前もあった。詐欺集団同士は互いを批判し、とても険悪だったが、なかでも嫌われていたのがこのシオンなる変態中年(byアリア・クエスティア)であり、彼が率いる「シオンの光」だった。
ヨルトは当然、シオンはクアロガンに殺されたと思っていたが、普通に生きているという話を聞いた。世の中はそれほど単純でもないということだろう。ほんの一時ではあるが、恋心を寄せたエルリーチェの中のひとが生きているのだ、喜んでも良さそうなものだが、詐欺師である。アリアが指摘するように、変態の中年男性であろう。果たしてこれは、取材する意義があるのかとも思ったが、ヨルトの取材目的は「敷根蛍の脳」から「詐欺師たちのやり口」へと変わりつつあった。
詐欺師たちは面白いくらい湧いてきた。「L2に渡りたい」と、移民窓口に問い合わせると、その翌日には「ボディパーツ売買」の広告が舞い込む。
「いまなら両腕と両足、眼球と腎臓1つずつでL2へ渡れます」
眼球がひとつ残るのだから、これは都合が良い。などと食いつくとでも思ったか。
己を餌にして怪しい話を呼び込んでいるわけだから、なんどか公安当局に事情を聞かれることがあったが、それがヨルトを有名にし、おかげでエルリーチェまでたどり着くのにも、そう時間がかからなかった。
結論から言うと、エルリーチェはシオンではなかった。この事実を受け入れる際の葛藤は割愛するが、仔細はエルリーチェの友人と名乗る人物から聞いた。曰く、エルリーチェはシオンの熱烈なフォロワーで、思想はすべてシオンからの受け売りだった、と。
「エルリーチェは死んだかもしれない」
ヨルトが伝えると、ベニオと名乗ったその友人は言った。
「やっぱり。ログインがないから、そんな気がしていた」
ベニオはもう50代、あるいは60代にも見える老齢の女性だった。エルリーチェの本名は知らない。仮想空間で知り合った。ともに一人暮らしだった二人は、「なにかあったときのため」と、アパートの
居住区には、地球の2割ほどの重力があった。高級住宅街では6割の重力があるが、ここでは「稼ぎ」によって重力が変わる。ベニオとヨルト、二人で踏み入ったエルリーチェの部屋には腐敗臭があった。何かが腐っている。おそらくは死体だ。臭いは光分解され、部屋の外に排出されることはないが、暗い部屋の中にはその装置が立てる甲高いモーター音が響いている。躊躇いながら足を運ぶと、ブラインド越しに降る光の斜線のなか、エルリーチェとおぼしきひとが、ソファに座ったまま、腐敗していた。ゲームでは見慣れた景色だ。音も、床の感触も、部屋の佇まいも、なんならそこにある腐乱死体も、すべて架空の世界で踏み超えてきた。ただ、匂いが現実を教える。エルリーチェは、たしかに死んでいる。あれからもうずいぶん日が経ち、腐敗がひどい。年齢も性別もわからない。そして彼には両手、両足がなかった。
ベニオのリストデバイスが、メッセージを受信する。
「ベニオ。あなたが来たということは、わたしは死んだんだね?」
デバイスから、エルリーチェの声が聞こえる。その声はヨルトが仮想空間で聞いたエルリーチェに似ていたが、ずいぶんと年老いた声に聞こえた。
「そしてわたしは、どうやらL2にも行っていないということだね。まあ、予想はしていたよ。体を売ったのは失敗だった。チケットはあるけど、身体検査がパスできない。いや、言ってよ、最初に、って感じ」
声には皮肉で自嘲的な笑みが混じっている。
「子宮も売ったって言ってました」
ベニオがそう加える。ヨルトの脳裏には、アリアが仮想空間で脱がせたエルリーチェの、白い腹部が思い浮かんだ。
彼は、アリアが言っていたような変態中年男性ではなかった。部屋には数多くのピンナップやフィギュア、手描きのイラスト、缶バッジの類が並ぶ。遺体がある部屋は、痛い部屋だった。銀髪の涼しい目をしたキャラのイラストには、To my Lord Sion, I vow my eternal chastity.の文字が書き記されている。おそらく、アニメかなにかの有名なフレーズなのだろう。
エルリーチェは奔放なアリアとは正反対の、大人しく内向的で、人付き合いも下手なタイプの人間に思えた。並んだフィギュアの衣装から察するに、アリアが「あざとい」と言った白のワンピースも、本気のお洒落だったとわかる。きっと仮想空間ではヨルト以外にも声を掛けて「沼」に引きずり込んだのだろうが、そこにアリアをして「騙されないでね」と言わしめるような悪意はない。秘部に刺青した文字は自分だけの秘密であり、プライドであり、自我だ。そのシオン様に捧げた純潔はパーツショップに売り払い、どこかのだれかに移植されて、見たこともないだれかの子を孕んだ。それにきっと、現実の世界でも、仮想空間でアリアから受けたような仕打ちを受けていたのだ。アリアのような、無神経な者たちから、なじられ、唾を吐かれて、ここに来たのだ。ヨルトが見てきた知人にも、同じタイプは無数にいた。いわゆる陰キャだ。ヨルトもそれに近い。だけどそれをアリアに言ったところで、何も伝わらない。気を悪くして離れていくだけ。
ベニオのデバイスに届く声は、少しためらったように言葉を区切って、続ける。
「でも、来てくれてありがとう。ようやくすべて話せる」
俄に部屋のノイズが消えた気がして、ヨルトは息を呑んだ。
「あのね。シオン様は存在しない。あのひとたぶん、エウノミア・クリスタルだ。だから人間としての意図はない。わたしたちが何か聞けば、それに沿って答えを返すだけ。だから、わたしたちが理想を向ければ、理想的に振る舞うし、悪意を持って……なんて言うかな、悪意を正当化しようとして質問すると、その根拠を示してくれる。あのひとは、敷根蛍のコンタクティーでもなんでもなくて、ただいろんなことを知っているだけ。ただ、質問次第で、敷根蛍として振る舞わせることができる。それをみんな利用してる。たとえばね。『殺人が決して罪ではないことの根拠』を問えば、それに近いことを言った思想家を挙げてくれるし、それがどんな弾圧を受けたか、物語にしつらえてくれる」
そして少し間を取って、
「あれは、悪魔だ」
と続けた。
だが、それがわかっているなら、なぜ――
「……でも、だから惹かれたんだと思う」
ああ、はい。
「だけど、嘘はつかないみたい。敷根蛍の脳がL2にあるのは間違いない。敷根蛍が
その声はときに感極まり、上ずり、ときに啜り泣きを含んだ弱々しい声になり、ヨルトのリストデバイスに録音された。
「ありがとう。ベニオ。やっと友達ができた」
鼻を啜りながら、その声は続ける。
「手足を売ってから40年、ずっと後悔してた。友達も無理だって思ってた。L2へのチケットはあなたにあげる。あなたなら大丈夫だから。叶えて。わたしの夢を」
ベニオは顔を覆って泣いていた。しばらくは話さえできず、部屋を出て、当局に死亡を届け、そのあとでゆっくりと話を聞いた。
「そんなに仲良くなかったんです」
ベニオは言った。
「二人とも『シオンの光』の会員だったけど、わたしはただ、そういう話が好きだってだけで、敷根蛍の脳をどうしたいみたいなことは、考えてなかったんです。それに彼女、よく自分と敷根蛍を混同してて……このまえも弟に付いててあげたいとか、アヤカに殺されるとか、わけわかんないこと言い出して……頭おかしかったんじゃないかな」
途中、ごまかすように笑いを含ませ、震えた声で紡ぐ。
「エルリーチェは、そこまでして何をしたかったんです?」
ヨルトの問に、ベニオは涙を拭いて、何度か首を捻って答える。
「最初は、恋だったと思います」
「恋?」
「シオンに恋して、シオンに認められたくて、だから、L2にある敷根蛍の脳を持ち帰って、『シオンの光一番の同士』と称えられたかったんじゃないかな」
親友は残酷に、何もかも見透かしていた。
「チケットはどうします?」
「捨てますよ。行きたくないです、L2になんか。シオンの光も退会したんです」
親友だと思っていたのは、一方的にエルリーチェの方だけかもしれない。
アリアから、件の大会にて8位に入賞したとの連絡を受けた日、気になるニュースが飛び込んだ。ボレアス・シャードにて、ドルフィーの殺害事件が起きたというのだが、左肩を抉られていたという。ドルフィーの多くは左肩にIDチップを埋め込んでいる。それが抉り取られるのは、地球ではよく耳にするニュースだった。要は、特定の市民番号を持つドルフィーを探しているのだ。初期型としてよく知られた番号は3つ。そのIDチップを役場に持ち込めばいいだの、防衛庁に収めるだの、あるいは手を切り落としてどこそこの酒場にだの――どれもデマだったが、そこから派生して数百のバリエーションがあった。その番号を持つドルフィーが、進化のリセットパターンである「
この事件の犯人はすぐに捕まり、地球から来たヨルト同様の自称ジャーナリストであることが伝えられた。その動機は彼の言葉として、
「たった一度でいい。花になりたかった」
とだけ伝えられ、それ以上の情報が出ることはなかった。ヨルトも同情した。自分も花を咲かせるためにここに来たのだ、と。
そうやってヨルトの記憶からは一瞬で消え去った「彼」の素性は、人間であるかドルフィーであるかさえ伏せられ、顔すらも犯罪とは無関係なノイズとして明かされなかった。多くの男性個体はヨルトと同じく、その動機を金、あるいは名誉だと推察したが、女性個体は違った。
この犯人は「彼」と呼ばれ、男女の性を伝えられることはなかった。それが報道の絶対的ルールで、性差により罪の重さが変わるわけではないと、数百年にわたり守られてきた。だが同時に、そうやって「女性」の存在は消されてきた。「彼女」らは男性個体と対等の扱いを受けるために「彼」と称され、結果として「彼女」らは男性になることを強要されてきた。もちろん、だれもそれを意図してはいない。理性が求め、論理的に施行された制度の結果であり、社会学的には大きな進展だ。だがその社会には、男性個体が自らの理想として作り上げた、美しい人形=ドルフィーがいる。それは女性個体に劣等感を植え付けた。とは言えそれも、たかだか顔の問題だ。「顔の美醜について」など、旧時代に過ぎ去ったルッキズムでしかない。そんなものに誰も囚われてはいないし、気にすることはない。ずっとそう言われてきたが、ならば、ドルフィーはなんなんだ。そこには男性個体によって意図的に現出させた美があり、事実多くの男性個体がドルフィーとの逢瀬を重ねている。ドルフィーにはできず、自分にできること、それは人間の子を残すこと、奪われ、暴力に耐え、支配され、殺されることだ。それを内面化してしまった女性個体も少なくない。そのコンプレックスは単なる羨望ではない、男性個体の、あるいは社会全体の「視線」を内面化したものだ。そこで女性は、人形になるか、男になるかが求められた。
もう一度、「彼」の言葉を聞いてほしい。
「たった一度でいい。花になりたかった」
そしてここでもう一度、Ⅰ章とⅡ章に登場したリヴェア・プローンを振り返ってほしい。
「あいつらに性別なんかない! 砂を食って、シリコンポリマーの母乳で子を育てるバケモノだ! 女に似せられて作られてるのも、男の欲求を満たすためだろう!? まんまと騙されて、バケモノの子を育てるのかよ!」
アリアはたびたび、ヨルトの宿を遠隔で訪ねていたが、ヨルトは事件のことを話さなかった。治安の悪いボレアス・シャードでの出来事だ。オモダル本星に波及することはない。
仮想空間のヨルトの宿にアリアの訪問が3日続いた日。お互いの体温を確かめあったあと、ヨルトから言った。
「僕のステディになってほしい」
ある意味、エルリーチェが「当て馬」になった。
「それってどういう意味?」
カーボンフォークの肌に対する仄かな恋心が砕かれ、考えるようになった。
「他に恋人がいることは知ってる」
二人は仮想空間のベッドの上で、並んで横になっていた。
「へへへ。やっぱそうだよね」
ハイ・リアルムでもなんでもない普通の仮想空間だったが、アリアが誤魔化すように、ヨルトの腹部に手を這わせると、その感触がヨルトに伝わる。
「そいつらと別れて、僕とだけ付き合ってほしい」
逆も同じだった。ヨルトが触れたアリアの肌に、ヨルトの指の感触が思い出された。
「うん。いいけど」
「ありがとう」
「でも、約束はできないよ。浮気したらごめんね」
「正直だな。アリアは」
ヨルトがボレアス・シャードに滞在して二ヵ月になる。アリアはもう、次のターゲットを見つけて、新しい恋を楽しんでいた。
「それでもいい?」
「いいけど、気をつけてね」
ヨルトは、ドルフィー殺害事件のことを言ったつもりだった。
「大丈夫。気をつけてる」
アリアがなんのつもりで答えたのかはわからない。
ボレアスの安宿。口先だけにしても、とりあえずステディにはなった。アリアの浮気を認める形ではあるが、ただそれをステディとは言わないんじゃないかという気はした。
「それでね、アリア。ちょっとL2まで行こうと思うんだ」
アリアは部屋に紛れ込んだカエルのような目でその話を聞いた。
「敷根蛍の脳を探しに。それで、往復で1年近くになるけど、船では人工冬眠に入るし、向こうについたらリアルタイムの通信はできなくなる。でも、ちゃんと帰ってくるから――」
ヨルトがたどたどしく説明すると、アリアはひとつ溜息を漏らした。
「今度はだれに騙されたの? おひと好しさん」
7 アヤカ28
L2への船に乗ったのは、ヨルトの他には、機械類のメンテナンスをするエンジニアふたり。船自体もそれほど大きくはない。古びた建付けは田舎のローカル列車を想起させる。L2基地は、ヴィマーナと呼ばれていた。
L2は重力均衡点とは言っても、その範囲は狭く、そこに留まろうとしてもわずかな摂動ですぐに外れ、地球なり、太陽なりに落ちた。あるいは、宇宙の深淵へと落ちた。リサジュー軌道は、月と太陽と地球との均衡をとりながらL2を周回する疑似軌道で、L2に留まるよりは幾分安定する。L2基地であるヴィマーナも、古くはL2に留まっていたらしいが、いまはこの疑似軌道を巡っている。連絡船の人工冬眠装置はずいぶんと古いタイプで、完全に代謝を止めるものではなかった。1週間も眠っていると腹が減ったし、その間、爪も伸び、寝汗もかいた。今の基準ではとても人工冬眠と呼べるものじゃない。乗り合わせたふたりのエンジニアは最初から人工冬眠など利用する気はなく、ロビーや自室で仕事をしたり、映画を見たりして過ごした。とくに暇を潰す道具のないヨルトは人工冬眠で過ごすしかなかったが、悪い夢にうなされた。その同じ悪夢が、4ヵ月も続いた。
連絡船がヴィマーナのドックに入ると、すぐにリストデバイスにアナウンスが入り、目覚ましが鳴る。目覚ましで起こされる人工冬眠など想像だにしなかった。その間、髪も爪も伸び、体力も使い果たし、ずいぶんとやつれていた。デバイスには簡単な施設内の地図と注意書きとが送られてきている。滞在者は多くの場合、居住リングと呼ばれる重力地区に部屋を用意されたが、ヨルトはコントロール層へ向かうケージに載せられた。
ヴィマーナの全長は15キロほどになる。特徴的な居住リングはその中ほどに位置する直径8キロの円環で、かつては重力を発生させるべく回転していた。円環は同心円状に4本が並び、数百年の時をかけてだんだんと拡張していったのだとアナウンスの音声が伝える。ヨルトが向かうコントロール層は居住リングの中央、ヴィマーナ全体のほぼ重心部にある。未来のトロッコとも言える「ケージ」で移動しながら、勝手を知らないヨルトは、そういうものだろうと理解していたが、一般の滞在者がそこに通されることはなかった。ケージが停止し、ドア・オープンのアナウンスが響く。右手にあるドアが開くと、ヨルトは荷物を持って、ゆっくりとドアの外へと遊泳した。
内部は古い病院に似ていた。ところどころに明かりはあるが、どこを照らすともなく無造作に並び、コントラストの高い明暗を作る。リストデバイスに行き先は表示されるが、その方向にはなにも見えない。果たして、どこに案内されるのか。生贄にされる子鹿のように身を震わせて配管や構造物を幾度かまたぐ廊下とも呼べない廊下を行くと、ほどなく両開きの扉にあたり、くぐれば手術室ほどの部屋に出る。その作りもずいぶんと古く、壁の目地を埋める樹脂は劣化が激しい。部屋には冗談のようにレトロなコンソールやモニターが並ぶ。手術室というよりは資材室か倉庫のようでもあった。無重力の部屋でそれが浮かないよう床や壁にロックされ、モニターは点灯せず、暗かった。
「はじめまして。エルリーチェ。ヴィマーナの総帥、シキネ・アヤカです」
声が聞こえた。眼の前にひとがいるのがわかる。シキネ・アヤカは、ヨルトが探している水槽脳、敷根蛍の娘の名前だ。重力と光のない部屋に蛍の火のような小さな光点がてんてんと灯る。その仄かな明かりの下、そのひとは椅子に座っているように見える。エルリーチェと呼ばれ、戸惑い、情報を整理しながら応えた。
「はじめまして。僕はエルリーチェの代理できました。ヒサキ・ヨルトです。エルリーチェは残念ながら、先日他界しました。連絡できなくてすみません」
緊張からか、足が震えている。
「ヒサキ……」
「ええ、久木です。久しい木に久しい三で、ヒサキと読みます」
「そうでしたか。懐かしい名前です。運命ですね。これも」
アヤカは日本語のイントネーションに似た古い言葉を使った。基本は英語であり、ヨルトにも聞き取れなくはなかったが、平板でところどころに差し込まれる母音に詩のようなリズムを感じる。
「あのう、申し訳ないのですが、エルリーチェと何か約束があったのなら、ごめんなさい。僕はエルリーチェから詳しく事情を聞いておらず、ただ彼が遺言みたいに、L2に行きたいと言うので、その遺志を汲んで、僕が来ました」
「大丈夫です。わたしも多くは伝えていません」
柔和な声だ。どうやら取って食われるわけではないらしい。静かな部屋に、時折、艦体の軋みが重低音となって足元を抜ける。他には自分たちの声のエコーしかない。
「質問してもよいですか?」
「どうぞ」
「エルリーチェをここに呼んだのは、あなたですか?」
ブーツはマグネットで床に固定されていたが、無重力では真っ直ぐに立つのが難しい。眼の前にいるひとは総帥だ。失礼があってはいけないと、体に力が入る。
「いいえ。向こうから連絡がありました」
「連絡? どうやって?」
「人工知能シオンを通して」
シオンの名は聞いている。だけど、それがだれなのか。
「シオンとは?」
「オモダルの人工知能スレッドのひとつ」
人工知能スレッド? エルリーチェはシオンはエウノミア・クリスタルだと語っていたが、そう遠くないということか。
「オモダルは数千の人工知能の集合です。それが全体でひとつの人工知能として振る舞っています。そのインターフェイスのひとつがシオンとしての仮想人格を得ているようです」
なるほど、とヨルトは思った。あまり正確にはイメージできないが、人間の詐欺師ではないらしい。ということはすなわち、変態中年でもない。
「じゃあ、シオンが言ったことは、すべて正しいと?」
「正しい質問であれば、知識の範囲内で正しい答えを返します。質問によるでしょう」
「なるほど。エルリーチェはなんのために連絡を取ったのですか?」
このあたりはなんとなくはわかっていたが、敢えて聞いた。
「敷根蛍――わたしの母の脳を探していました」
この答えは想像の範囲内。
「なんのために?」
「新しい世界を築くために」
こちらは想定外。
「蛍がその方法を知っている、ということですか?」
「いいえ、おそらく、その世界を見せたかったのでしょう」
ヨルトはエルリーチェのことを尋ねたつもりだった。エルリーチェはなぜ蛍の脳を求めたのか、と。だがアヤカは、その背後のシオンの意図を答えた。シオンの意図はオモダルの意図だ。オモダルは新しい世界を作ろうとしている、それを蛍にも見せたいのだ、と。
「つまり、変化した社会を見せたいということですか?」
ヨルトはアヤカに合わせてそう聞き返してみたが、エルリーチェの意図は「シオン様に気に入られる」だ。仲間内で最もシオン様に貢献した実績が欲しいだけ――ディスコミュニケーションもあったが、それ以前にヨルトのなかに最初から答えのある空疎な会話だった。ただ、これがヨルトだ。会話は常に、自分の思い込みが正しいことを確かめるための答え合わせ、ほかは聞いても聞こえていない。
「その真意まではわかりません」
「あなたも、水槽脳を託すつもりでいたんですよね」
ここまでの会話で、相手の姿が想像できた。普通の人間サイズの、おそらくは女性だ。そしておそらく、アンドロイドだろう。だが、それがわかったところで、足はずっと震えたまま。
「そうです。だけど、目的はまた別です」
「別というと?」
「母の脳を、地球の菩提寺に納めてほしいのです」
不意を突く答え。だけどヨルトはここで初めて「人間」を感じる。
「日本の大分県はわかりますか?」
アヤカが問う。
「ええ、行ったことはありませんが」
「そのウスキと呼ばれる地に、小さなお寺があります。そこに、母を」
「ちょっとまって。あなたと敷根蛍の関係を聞かせてほしい。敷根蛍は8百年も昔のひとだ。あなたはその娘で、アンドロイドとしていままで生きながらえてきたということですか?」
「そう。母は、わたしの複製を27体用意しました。シリコンポリマー製の人工知能は30年ほどで耐用年数が切れます。わたしは27体の体を乗り継いで、いままで記憶をつないで来ました」
「27体?」
「そう。わたしのいまの体が27代目です。もうこの先はありません。だから」
「だから最後に、母を菩提寺へ?」
暗がりに目が慣れるとともに、丸いソファに深く座ったその人の姿が浮かんできた。ケープのようなものを羽織り、微動だにせず、表情もない。まるで絵画と言葉を交わすかのよう。
「そう。いつか目覚めさせるつもりでした」
「目覚めさせてどうするつもりだった?」
恐怖はずっと居座っている。形容できない恐怖。何かに襲われるでも、生命の危機に晒されるでもない。まるで世界のすべてが消え去ったような恐怖。
「結果を――見届けさせる――」
「どういう意味?」
虚空に浮かぶ全長15キロの構造物は、無人の外科病棟の静寂に満たされ、時折、深宇宙から飛来する高エネルギーの粒子が艦体を叩き、それが寺の鐘に似た音を長く響かせた。
「母はわたしを失敗作だと言った。でもその失敗作が、いま、地球を滅ぼそうとしている。それを――」
「わからない。地球を? あなたが? 滅ぼす?」
恐怖を拭い去るために矢継ぎ早に言葉を接ぐが、問うべきだったか、黙すべきだったかの迷いがその後を追い――
「そう。わたしは、アークトゥリアン」
話題は予告もなく流れを変える。アークトゥリアン? このひとが? 混乱に拍車がかかるが、同時にゾクゾクとした興奮が沸き立ち、両腕両足に鳥肌が立つ。
「わたしは、アークトゥリアン。地球統合軍が戦っている敵は、わたし」
阿、問うべきか、吽、黙すべきか、迷う2秒の空白。
「詳しく教えてもらえますか?」
ヨルトは口を開いた。胸に踊る興奮を抑えきれない。喉を通る声はほろほろと崩れ、ぶり返す足の震えは緊張か、恐怖か。
「わたしは――炭素系人工生命を創造するためにオモダルに渡りました――」
アヤカは抑揚なく、ゆっくりと語りだす。
「人工子宮の創造のため、重力のない環境を求めて空に出た……だのに生命発生の初期段階では、重力が必要となり――」
「重力が? それでこの衛星を?」
「そう。生命を作ったのは星。生命は星の一部。だからわたしは、星を作る必要があった――」
「それでオモダルも星になる必要があったと?」
「オモダルの目的はわかりません。オモダルが作っているのは、あくまでもアンドロイド。わたしが作りたいのは、命――」
まるで神が交わす言葉だ。誇大妄想にも聞こえるが、事実、オモダルという星、アークトゥリアンという命が生み出されている。
「そして、自ら作り上げたアークトゥリアンを依代にして、いつか人間に戻ろうと思っていた――」
依代に? 自分の28番目のボディとするために? パズルのピースを両手に抱えて戸惑っていると、二人の間に小さなスポットライトが降る。
「母です」
そこにあるのはガラスの水槽。中には柔らかな乳白色の脳が浮かんでいる。新鮮で、明滅する照明がそれを脈動するかに見せる。
「これを、ウィスキーの菩提寺に?」
悪心を感じ、直視が躊躇われるが、バーチャルなゲームでは幾度も目にしてきた。
「そう。三重の塔があります。地球とともに死ねば、母も本望でしょう」
「2歳で死んだアヤカというのは?」
不意に、エルリーチェに聞いた話を思い出す。
「2細胞期に取り出した胚から成長させた、最初のクローン」
聞き慣れない言葉だが、記憶のなかから受精卵の分割と成長の図が思い当たる。その最初の分割を終え、ふたつになった細胞のことだ。ヨルトは表情を歪ませる。
「最初の?」
「そう。最初のアークトゥリアン。他のアークトゥリアンも、ひとつの受精卵から作られたクローン。その成長過程には様々な改造が加えられた――彼らはもう、人間じゃない」
ヨルトの脊髄を戦慄が駆け上がる。
「受精卵の残りの半分はいまも生き続けています。決して胎児へと成長することなく、ただ分裂を繰り返し、いまは6メートルの巨大な肉塊に成長した。それは永遠に生き、分裂し続け、だけどそこから無限に生み出されるクローンは、みな数十年で死んでいく」
アヤカは表情ひとつ変えず淡々と語り、ヨルトは一枚づつ理性を剥ぎ取られる。深宇宙より飛来する素粒子がヴィマーナの駆体を叩き、高低さまざまの鐘の音を打ち鳴らす。
「胚だけが永遠……生まれれば等しく死んでいく……」
眼の前の化け物は微動だにせず、口元だけで音を紡ぐ。小刻みに足が震えだす。長く減衰の尾を引く鐘の音に三半規管が応え、部屋は三軸に回転し始める。
「あなたはなぜ……そんなことを?」
言葉を絞り出す。アヤカは少し、答えを躊躇う。叩きつける高質量の陽子は艦体を歪ませ、その応力による軋みが遠雷のように轟く。
「わたし自身への贖罪と、アヤカ自身に、アヤカを滅ぼした、母の遺産を、破壊させるために……わたしは、母と、同じ、過ちを、犯した……」
いや、待て。意味がわからない。それで地球人に対して戦争を? いったいどういうことだ? ヨルトは戸惑うが、恐怖が口を塞ぐ。足の震えは全身に広がっている。
「ヒサキ……ヒサピチ……ピチチ……」
名を呼ばれた。続くリフレインは発声エラーか。鳴屋の曳く残響が、耳鳴りに重なる。
「あなたに会ったのは運命です。あとは、あなたに、決めてほしい」
決めてほしいもなにも、なにをどう決めるのか。だがもう、全身の震えが止まらない。いま、宇宙は、ヨルトを残し、ヨルトを中心に回転している。
「……なんとかやってみる。最後にもうひとつ知りたい」
ぎゅっと目を閉じて見開くと、青白く表情のないアヤカの顔が闇に浮いて見える。
「なんでしょう?」
「あなたの父親のことです。湯川という生命科学者だと聞いてますが、正解ですか?」
「湯川か」
アヤカの口調から緊張が消えた。
「知ってはいるんですね」
ヨルトの宇宙も、ゆっくりとその回転を止める。
「ああ。だけど、遺伝子的にありえない」
「遺伝子的に? というと?」
「わたしの父親の可能性があるのは、ただひとり――」
そこで彩花は言葉を区切り、考えを整理した。この8百年ずっと考えてきたのが、まさにそのことだった。自分には父親はいない。母、蛍が自ら生み出したクローンだ。そう信じてきたが、自分でも否定してきたもうひとつの答えがある。それは――
「――オモダル」
語尾が消えかけた、弱い音で答えた。
「オモダルが父親? それは比喩的な意味で? それとも現実的な意味で?」
彩花は沈黙した。長く生きれば生きるほど、たどり着けない答えばかりが増える。
――そうか。わたしはその答えにたどり着けずに死ぬのか
日本神話の
「あなたが死んだら、ここはどうなるんですか?」
最後にヨルトが尋ねると――
「いまのアークトゥルスの知能は地球人類を凌駕した。彼らが考え、彼らが運用していく、もう、わたしの時代じゃない」
彩花は古い言葉でそう語った。
思わぬ特ダネだった。その日は興奮して眠れなかった。すぐにでもアリアに知らせたいが、通信機はない。手も足も震え、笑いがこみ上げる。いったいこの水槽脳にいくらの値段がつくんだ。僕が地球からずっと追いかけてきたネタは大当たりだったじゃないか。だれだ、地球のジャーナリズムを茶番だなんて抜かしたヤツは。菩提寺に納めるなんて、どうでもいい。買い手はいる。売り払って、あとはアリアと暮らそう。仮想空間じゃないリアルな日本家屋だって、いや、日本庭園だって買える。帰りのシャトルの出発は3日後。小さな無重力の部屋をぴょんぴょんと飛び回って過ごした。
その3日目。ヴィマーナ艦全体に総帥・敷根アヤカの逝去が伝えられた。乗員は人間とドルフィーをあわせて百に満たないが、居合わせた各国エージェントから、そのニュースが発信される。ヨルトは水槽脳をケースに入れて、アヤカが用意した証明書で税関を抜けた。品目は遺骨。そう遠くはない。ヨルトはそれを手荷物として、連絡船に乗った。そして夢を見た。浅く寝苦しい夜に不似合いな、楽しげな夢を、4ヵ月の間。
オモダルに着くと、厳戒態勢が取られていた。そこかしこに軍人の姿が見え、入管のチェックが完了するまでに18時間がかかった。通信使用許可が降りるとすぐにアリアに連絡を取るが、エラーが返る。サンド・ボールのチーム・ロビーにもだれもいない。ただ、リーダーのバーチャル・チャイルドであるコトリがいた。
「みんなは?」
自動通路の上を歩きながら、バイザーにコトリの姿を写す。
「通信が制限されてて、それどころじゃないみたい」
「どういう意味?」
自動通路はそのまま自動階段へと連なり、通りに出て、トラムに乗る。街中が慌ただしく、ピリピリしている。
「もうすぐ戦争になるって」
「戦争?」
思わず口に漏らす。この張り詰めた空気の中で吐くべき言葉じゃない。声を抑えて、もう一度聞き返す。
「戦争ってのは、どういう意味の?」
「ドルフィーが狩られてるのは知ってる?」
ドルフィー狩り。心当たりはある。だが、その後どうなったか知らない。まさかアリアが?
「ああ。知ってるけど。いや。どうなった?」
「いま、人間の居住区はドルフィーたちの反撃で、凄いことになってる」
「凄いことって?」
「町がいくつかなくなったよ。アーシェとクススも死んじゃったみたい」
二人ともギルドメンバーの名前だ。
「アリアは?」
「ああ、うん」コトリは少し躊躇い、申し訳なさそうに続ける。「アリアは真っ先に死んじゃった。肩を抉られてたから、ドルフィー狩り」
刹那、胸のなかに描こうとしていた図が、真っ白に消え去った。
いままで聞いた話のすべて、単語のひとつすら残らず、ただ真っ白に。
もはや視界すら、何も捕らえていない。すぐにトラムを降りて、公安局に向かう。データベースに当たると、アリアの遺体はまだ生体保管されていることがわかる。医局へ向かうよう促され、自動通路を小走りに人の群れを追い越し、バイザーに医局の窓口を呼び出す。早口でアリアの市民番号、自分の市民番号を告げる。いまどこに? 容態は? ぶしつけに言葉を投げて、返った言葉曰く、もう息を吹き返す見込みはないが、生命維持装置につながっている――。そのあとは自動通路にも乗らずに走った。バイザーに医局までの地図を写し、表示されたガイドに向かって走り、ビルに乗り込んで、エレベーターを待つ時間も惜しんで、階段を探す。遺体は地下だ。薄暗いモノクロームの階段が、静かにヨルトを待つ。壁に空いた死の入口。足音を響かせて駆け下りると、安置室まえにも何人もの看護師、面会に訪れたひとの姿がある。
「すみません、通してください」
人垣を分けて安置室のドアを開けると、白い布をかけて、アリアが横たわっている。
「アリア!」
思わず声をあげるが、ただ自分の声のエコーが返るだけ。
「ヨルトさんですね」
そこにいた医局のひとが、尋ねる。
「はい。ヒサキ・ヨルトです。アリアは助かるんですか?」
ヨルトは息を整えることもなく。吸っているのか吐いているのかもわからないまま、医局のひとに問い返す。
「いえ、残念ですが」
残念ですが――
いま医局のひとが言った「残念ですが」の意味がわからない。砕け散った思考に1文字ずつ書き取って、どの順番で読めばいいんだ。残念ってなんだ? 助かるのか? 助からないのか? 医局のひとの顔を覗き返すと、首を振ってうなだれる。どういう意味だ? 死ぬのか? アリアは。
「これを見てください」
医局のひとは、アリアの市民データの画面を見せる。
「あなたがパートナーとして登録されています。間違いありませんか?」
ヨルトの目に涙が吹き出す。
「そんな、まさか……」
「間違いでしたら――」
「間違いじゃない! 僕がアリアのパートナーだ!」
アリアのことだ。おそらく無難で邪魔にならないヨルトを選んで、本人に確認もせずに登録しただけで、他意はないのだろう。そのくらいはもうヨルトにも察しが付く。だけどそれでいい。アリアがその生き様を選ぶなら、自分もその生き様を選ぶ。
「でしたら、72時間以内に、遺体の引き取りの準備を」
遺体。遺体ってなんだ。そこにいるのはアリアじゃないのか? 一歩踏み出そうとするも、もう力が入らない。いきおい、その場に跪く。
1年前とはまったく状況が変わっていた。たった1年でドルフィー狩りが蔓延り、戦争にまで発展した。原因はヨルト自身にあるかもしれない。ボレアス・シャードで無邪気に
「それと、お腹の子はどうなさいます?」
「お腹の子?」
「彼は身ごもっています。臨月も間近で……ただ、あなたの渡航歴と合わせると、あなたの子と言えるかどうか。もし認知されなければ、母体とともに……」
「殺すっていうのか!」
思わず声を上げた。
ドルフィーは単為生殖だ。アリアがだれと、どんな時間を過ごしたかは知らない。その子を授かった夜、だれの甘い言葉を聞いたのかも知らない。だけどそんなことはどうでもいい。あのアリアが、自分をパートナーと認めたうえで残した子だ。その子はアリアが生きた証、自分の人生の証だ。
「わかりました」
医局のひとは理不尽に怒鳴られる形にはなったが、慣れたものだ。
「ヒサキで籍を作る。申請を頼みたい」
「承知いたしました、ヒサキ……ですね……」
「名前はどういたします?」
「名前は……」
受け答えしながら、それでもヨルトは迷っていた。行き摺りのドルフィーが、単為生殖で勝手に孕んだ子だ。自分には母乳も出ないし、ジャーナリストとしてやるべきことは無数にある。それに、戦争が始まる。そこで命がけでレポートでもすれば、それがヨルトが求めていた「生き甲斐」かもしれない。戦場で命を落とすかもしれないが、それこそが「生きる」意味だ。だが、子がいたら――
地球人男性は恋愛の結果としてのパートナーの懐妊を当然のことと信じている。だが、その当然の結果である妊娠・出産を経験した男性個体はいない。生まれ落ちた子をひとり抱いて、いったい何をどうすれば良いのかと途方に暮れたものもいない。だけど、女性個体の多くがそれを経験している。
ヨルトの脳裏に、「いつか人間に戻ろうと思っていた」という、敷根彩花の言葉が思い浮かぶ。
「――アヤカ。ヒサキ・アヤカで頼む」
ヨルトは涙をこらえて、医局のひとに告げた。
その理路はわからない。このヨルトを見て、男性個体の多くは「なぜ決意したか」と問うだろう。だが、そう問うのは、「決意」のあるなしで人生を選べる「男」だからだ。
こうして飛先ヨルトは緋咲アヤカの父親となった。そう、Ⅰ章とⅡ章に登場したこの物語のキーパーソンだ。彼、飛先ヨルトの判断により、緋咲アヤカは生を受け、ヨルトもこの物語の重要人物となった。やがてアヤカは敷根蛍から送られる
その彼をどうか祝福し、称賛して欲しい。
だがそれは決して、彼が手にした子が緋咲アヤカだからではない。彼の子がどこのだれで、どんな子だろうが、その称賛が変わってはいけない。ただこの瞬間、すべてのメダルを捨て、命を賭すことを捨て、栄光を浴すことを捨て、ただ果てのない「生」を選んだその一点で彼を称賛して欲しい。そしてその称賛は、ひとしくあなたたちへの、すべての生きとし生けるひとへの称賛だ。あなたの人生は素晴らしい。あなたが今日食べた食事、目にした景色、発した言葉、そのすべてが素晴らしい。
もうすぐ戦争が始まる。死ぬのは簡単だ。命を賭けることも、殺すことも、英雄になることも、世界を救うことも、この宇宙を破壊し尽くすことすらも造作ない。だけど――生きることは難しい。
Ⅴ 西暦二〇三六年・アヤカシコネの末裔
1 風立ちぬ
膝の上に畳んだ
「藤棚のほう、少し色づいたって」
車椅子に座った彩花が、中庭の小径の先に視線を向ける。
「そう? 先生から?」
彩花の母、蛍がそれを押している。娘は抗がん剤治療で髪を失い、花色のニットの帽子を被っていた。まだ21歳。母はその肩にかかった黒髪を覚えている。高校を出たらパーマをかけると言っていたのに、その隙もなく病が取り憑いた。
「ううん。湯川さん。わざわざ裏門から、藤棚を通って病室に来てるんですって」
湯川さん――湯川振一は母と同じアンドロイド工学者。母が「湯川」と呼び捨てるものだから、幼い頃は彩花もそれに倣っていたが、このところは湯川さんと呼ぶようになった。テラリウム・インク上級顧問の母・敷根蛍の有能な右腕。彩花の入院以来つきっきりの母のもとをたびたび訪れている。
その傍らを、スーツ姿の
若年性のリンパ腫は足が早い。いつもならあまり無理はさせてもらえなかったが、このところは我儘も聞いてもらえるようになった。おそらく、死期が近いのだろう。久木の足取りと、しばしば訪れる沈黙もそれを教える。倦怠感はずっと抜けない。絶えず40%ほどの笑みを湛え、絶えず40%ほどの悲しみに暮れて、病室のベッドに戻って、「ありがとう、お母さん、ピピチ」とだけ言うと眠りこけた。ピピチは彩花がつけた久木の愛称。ピピチが傍にいない日は、悪夢しか見なかった。
その日の午後の検診が終わったあとだった。「コーヒーを買ってくる」と久木悠が席を外すと、蛍は彩花の枕元に椅子を置き、ゆっくりと腰を下ろして、「このことは、久木くんにも相談済みなんだけど」と、静かに唇を動かした。
「これから、もしものことが起きるかもしれないから、その時に備えて、あなたを……」そこで蛍は言い淀む。「あなたに、もっと強い体を与えたいの」言葉を選んで、そう伝えた。
まわりくどい言い方だったが、彩花は察した。
「わたしを、アンドロイドにするってこと?」
蛍は慌てて取り繕う。
「その言い方は少し誤解があるわ。あなたはいまのまま変わらない。義手や義足と一緒よ。強くなるの」
彩花は戸惑う。
「わたしの体はなくなるの?」
母は何も答えなかった。
彩花は初めてこの病院を訪れた日のことを思い出した。色濃い藤を分けて陽の光が踊る。あのときはまだそこを自分の足で歩いた。土に触れて汚れた手を、小径の脇の蛇口で洗った。あれからたった1年。
その体が、なくなる……
「あなたの命を、永遠にこの世界に留めたいの」
蛍は潤んだ目で訴える。
「わたし、死ぬの?」
「死なないわよ。何を言ってるの」
蛍は少し大げさに笑ってみせた。
「でも、体は変わるわ。だけど、それでも生きたいでしょう? 死んでしまうよりずっとずっとそっちのほうがいいわよ。いいに決まってる」
さりげなく死亡宣告された。もちろん、わかってたけど。
でも、血液の癌だ。体のパーツを入れ替えただけで助かるわけがない。じゃあ、どうするの? 全身入れ替えるの? 完全にアンドロイドになるの? 脳だけ移し替えるってこと? お母さんが言ってるのは、きっとそういうこと。そう思うと悲しみが込み上げる。言葉にならない。わたしはどうなるの? いま顔を覆っているこの手だって、なくなってしまうんでしょう?
死は受け入れるつもりだった。悪性リンパ腫だと知った日から、少しずつ「死」への恐怖を克服してきた。思い出が消えるのは辛かったけど、すべて日記に記して整理してきた。彼とふたり白いイヤホンを片っぽずつ差して、パピコを割っていっしょに食べて、顔を寄せあって写真に撮った。食事も、毎日の髪型も、枕元の花も、雨の日の窓に流れる水の雫も、指先のネイルアートも、指のささくれも、目についたものはすべて写真に撮った。見たものも、考えたことも、なにもかも記録に残した。その宝石が詰まった小さなスマホが彩花自身だった。それがずっと彼の手元に残ってくれれば、それで自分は幸せだと思っていた。それがわたし。だけどもし、アンドロイドになるとしたら、それはわたしなの?
彩花は母に聞いた。アンドロイドになったら味は感じるのか、匂いは感じるのかと。答えは――
「いまは無理。だけど近い将来、バージョンアップすれば、きっと感じるようになる」
バージョンアップ。その言葉を聞くととめどなく涙が溢れ出した。
「バージョンアップなんてしたくない! そんなの嫌だ!」
「もちろん、あなたがしたくなければそれでいいのよ」
娘の反応に焦り、言葉を接ぐ。
「でも、バージョンアップしたら、少しずつ人間に近づいていくし、ぜったいそのほうが幸せになれるから」
少しずつ人間に近づく。じゃあ人間に近づくまえはなに? またも涙が溢れ出した。嫌だ。やっぱり人間じゃなくなるんだ。そんなの嫌。だったら死んでしまいたい。いますぐにでも。
母が帰ったあと、彩花はスマホを手に取った。アルバムに残った写真を見ると、そこにあった風や、そこにあった匂いまでも思い出される。きっといま全身で感じてる風だって、アンドロイドになったらいくつかのセンサーで感知するだけになる。匂いも感じない。味も感じない。視力は7.0相当になってノクトビジョンまで付けられるらしいけど、そこじゃない。きっと涙も出なくなるし、それじゃあとてもとても悲しいとき、わたしはどうすればいいの。ピピチとのツーショットが涙で歪む。どの写真も、どの写真も、プールで溺れるみたいに波の向こう。でも、波と言えば。1枚の写真でスワイプが止まる。義足の水泳選手との交流会の写真。
母の影響で、彩花もアンドロイド工学の道を目指していた。その義足の選手は、母の会社で作られた義足をつけてインターハイに出場、健常者に並んで記録を残した。高校の課外活動。できたての彼氏。久木悠といっしょに取材に行った。取材した彼は、三歳の頃から水泳教室に通い、中学では県大会記録を出し、高校、大学と水泳の選手として活躍することを夢に見ていた。だけどその夢もつかの間、高校進学の直前、骨肉腫で片足を失い、すべての夢が絶たれた。だけどそれでも、仲間や家族に励まされ、義足の選手としてカムバック、インターハイ出場を決めた。そのときの彼の言葉は、忘れもしない。
「死ぬことを思えば、息ができるだけでも幸せだ」
彼に勇気づけられた子たちもたくさん取材した。いろんな施設を回って、義手義足の利用状況を調べ、アドバイスもした。たくさん勇気をもらったし、たくさん泣いた。その気持が積もり積もっていまのわたしがいる。わたしが諦めたら、あの子たちを裏切ることになる。
それに彼、久木悠との思い出もまだまだ作りたい。行こうと約束した場所を数えると、両手でも足りない。もちろん不安もある。もしも、もしも悠がアンドロイドの彼女なんて嫌だって言い出したら――いいや、そのときはそのときだ。わたしの人生はわたしのために、彼の人生は彼のためにある。それが人生ってものでしょう? アンドロイドかどうかの問題じゃないよ。だけど、そう考えてもまた涙が溢れてきた。ぽろぽろ、ぽろぽろと涙が溢れる。でも、しょうがないよ。わたしのわがままで彼を不幸になんかしたくない。わたしをふった彼の人生だって、ちゃんと幸せになるかどうか最後まで見届けてやる。
翌日、母の顔を見て開口一番、切り出した。
「お母さん、わたし、アンドロイドになる」
それからすぐ、病室に検査用の機材が持ち込まれ、アンドロイド化の準備が始まる。蛍と、そのアシスタントの湯川、それから医大から派遣された医師たちと、その他多くのスタッフが彩花を検査した。
その日の午後。「コーヒーを買ってくる」と久木悠が席を外すと、蛍は彩花の枕元に椅子を置き、ゆっくりと腰を下ろして、「あのね、彩花。落ち着いて聞いて」と、静かに唇を動かした。
こんどは、なに?
「あなたの血液型は、ボンベイ型という特殊なタイプで、輸血用の血液がないの」
???
「だから……アンドロイドにあなたの脳を移すのは無理みたい」
彩花にしてみれば、特急列車で三往復殴られたような衝撃だった。
「インドのボンベイ、いまのムンバイで見つかった特殊な血液型だけど、日本には百人しかいないの」
わけがわからない。ボンベイ、なにか関係ある? 脳裏には見たこともないインドの景色が浮かんで男たちが唄い踊り始めるが、まるで関係ない。
「大丈夫。お母さんもボンベイ型だから」
だから、なに?
死は覚悟しているはずだった。そのために思い出を残してきたし、ついこないだ、アンドロイドになるくらいなら死んだほうがましだと言った。それがアンドロイドとして生きると決めた途端にボンベイ型だ。
もう覚悟の構えなんか解いちゃったよ。お母さん。
「でも、大丈夫よ。あなたの意識をシリコンにコピーできるの」
???
戸惑っていると蛍は、つまり脳なんかなくったって、コンピュータに魂を移せるのだ、と、彩花の手を握った。
「あなたなら、わかるでしょう。脳をそのまま移すか、電子頭脳にコピーするかの違いだけ。外見は一緒。久木くんもそれでいいって言ってくれてるわ」
いや、それでいいって、なに?
「でも……」
彩花は心細げに口を開く。
「アンドロイドはわたしになるかもしれないけど、わたしはどうなるの? アンドロイドはわたしのコピーでしかないんだよね?」
「そうね……」
蛍は少したじろいでいる。アンドロイドにコピーするというアイデアに舞い上がり、残される本体のことはあまり深く考えていなかった。蛍にとって、脳を移し替えた新・彩花と、脳の情報をコピーした新・彩花は同一だ。しかしよくよく考えてみれば、後者はコピー元が残る。いったいそれは、なんだ?
「あなたはただ、眠るだけよ。次の日目覚めるとアンドロイドの体になってるわ」
「でもそれ、別人だよね? 眠ったわたしの元の体はどうなるの?」
「それは……アンドロイドになったあなたが決めればいいわ。そのまま生体保存してもいいし、荼毘に付してもいいし」
「それ、わたしが、わたしに成り代わったアンドロイドに殺されるってことでしょう? 違うの?」
「な、なにを言うの? あなたまだそんなところで足踏みしてるの?」
足踏みもなにも。悪い冗談だと思いたかった。しかし、科学技術に没頭しているものにはよくあることだ。彩花も中学のとき、母とふたりでカエルのサイボーグ化実験を行って、夏休みのレポートにした。あのときはそれほどクレイジーな実験をしているとは思わなかったが、カエルにしてみればたったひとつの人生の問題だ。
翌日、久木からも説得された。
「施設の子たちを覚えてるでしょう?」
彩花と久木で義手義足の調査をした施設のことだ。
「もし彩花が、アンドロイドにならずに死んでいったとしたら、みんなどれほど悲しむと思う?」
恋人からもさりげない死亡宣告。
「うん。それはわかる。すごく悲しむと思う」
「逆に、アンドロイドになれば、あの子たちを励ましに行ける。それは彩花のいままでの経験があるからこそなんだよ。どういう体とか、どういう頭脳とか、そういうことじゃないんだよ。いままで経験したこと、考えたこと、それが命なんだよ」
言っていることは間違いじゃない。かと言って、正しくもない。というか、次元が違う。みんなが言ってるのは、わたしの記憶を写したアンドロイドの話。わたしが言ってるのは、わたしはどうなるの、って話。当事者ではないというだけで、これほどまでに想像力が働かないものかと腹立たしかった。
この包囲網のなかで彩花はしばし考えた。アンドロイドにコピーした自分は所詮他人だ。自分の(残り少ない)人生とは関係ない。そんなにアンドロイドが作りたければ作ればいい。自分はいまのまま思い出を集める。思い出が詰まったスマホがあればそれだけでいい。みんなにとって他人事なように、わたしにとってもアンドロイドなんて他人事だ。
「わかった。アンドロイドにコピーして、アンドロイドになる。でも、条件がある」
「条件って?」
「コピーしたあとも、元のわたしをそのまま残して」
「でも、そのままにしても……」
「いいのそれで。わたしは自然死したいの」
自分でも死ぬと認めてしまった。
それからすぐに、彩花の意識転送の準備が進んだ。
彩花が病室を離れることを拒んだため、蛍の研究室から資材が持ち込まれ、小さな病室のなかで生の彩花の肉体と、新しく用意されたアンドロイドの肉体とがケーブルで繋がれた。遠隔での意識転送も可能だったが、彩花がこれを拒んだ。新しい自分の誕生に立ち会うことが、蛍の「実験」に付き合うための条件だった。
意識を安定した基底状態に導くため、精神安定剤が導入される予定だったが、これも彩花が拒んだ。その薬で殺されるかもしれないことを恐れた。もちろん、睡眠中にこれを打たれたら気が付かないのではあるが、そこは信じるほかはない。さすがに実の母なのだから、そこまではしない、と。このようなケースだと、世間一般では非常識をしでかすのは身内と相場が決まっているのだが、彩花はそこまで世の中を知らない。蛍のスタッフは可能な限り彩花の意志を尊重しながらオペレーションを進めた。
その日は、久木が隣にいた。ふたりでパピコを割って食べて、写真を撮って、「これからナイショのオペのはじまりです」と、SNSにアップして、スタッフに囲まれたなか、ひととして最後のキスを交わした。すぐに「がんばって!」とスタンプが返る。だけど彩花のSNSは、メジャーなSNSに似せた架空のSNSだった。狭いファイアーウォールの外には情報は出ない。ロンドンに旅行中の友人も、施設で知り合った少年も、蛍のスタッフがなりすましたもの、彩花が何を書いても一切の情報が漏れないようコントロールされていた。その架空の友人から、「オペがんばってね!」「僕も見習いたいです」とレスが来て、彩花は「うん。がんばる」と、絵文字つきで返して、涙を流した。届いたレスには「宝物」のタグを付けた。
パピコは2本セットのプラスチックチューブに入った氷菓だが、左右非対称だ。たとえば、どちらかに薬を入れておいて、自分では入っていない方を選んで、相手にだけ摂らせることができる。パピコを食べるとすぐ、彩花は眠りに落ちた。恋人も傍で笑う、幸福な眠りだった。
2 いざ生きめやも
わたしがふと目を開けると、窓には明るい日が差し込んでいた。
いつもの気だるい感覚がない。
人影が見える。小さな歓声が上がる。ピピチ――悠もいて、涙ぐんでる。
そうだ。わたし、アンドロイドになったんだ。
カラダは普通に動く。むしろ今までより軽い。自分のカラダじゃないみたい。違和感はあるけど――
そうだ!
わたしはベッドから飛び起きて、隣のベッドに飛びついた。
「わたし!」
そこに、いままでわたしだったわたしが横になっている。
「死んでないよね! 起きて!」
わたしがわたしの肩を揺すると、「う、ううん」と、わたしは目を擦った。
よかった。死んでない。
「わかる? わたしだよ。あなた自身。アヤカ。アンドロイドになったの」
声を掛けたけど、人間のわたしは、わたしから目を逸らした。
わかるよ。ついさっきまで、そっちに宿ってたんだから。あなたがわたしを認めないことなんてわかってた。でも、なんだろうこれ。わたしが思ってた以上に、いまのわたし、わたしなんだよ。昨日までの人間の意識と何も違わない。
「アヤカ」
ピピチが声をかけて、ゆっくりとわたしのシリコンの肘に触れる。ベッドに横になったもとのわたしは目を背ける。
「大丈夫? どこも不具合はない?」
ピピチが気遣ってくれる。嬉しいけど、もとのわたしの気持ちを考えると、なんか違う。それじゃ駄目なんじゃない? ピピチ。
もとのわたしの横には医者が寄り添う。カルテをつける看護師。揺れる輸液ライン。お母さんはもう、人間の彩花に見向きもしない。ゆっくりとわたしの手を取って、そして抱きしめる。
「がんばったね、アヤカ」
そう言って涙ぐむけど、違うよ、お母さん。頑張ったのはアンドロイドになったわたしじゃなくて、人間のアヤカなんだよ。わたしじゃないんだよ。
「もとのカラダはどうなるの?」
お母さんに聞いた。
「何も変わらないわ。ずっとここで治療を続けるから、安心して」
お母さんは涙ぐんで、わたしの肩をぎゅっとしたけど、わたしは何を安心すればいいのだろう。
「これからは、あなたがアヤカだから」
って、ぜんぶ彩花に聞こえてるのに。そう言いながらお母さんは、もとのわたしが使っていたスマホをわたしに手渡す。
「顔認証でちゃんとアクセスできるはずだから、試してみて」
――って、どうして? これ、彩花のだよ? どうしてそんなことが言えるの? 彩花の肩がこわばるのが見えた。
「これ、彩花の宝物なんだよ?」
「そうよ。だからちゃんとアクセスできるようにしてあげたのよ」
違うよ。違うんだよ、お母さん。
これだけが彩花の生きる支えだったんだよ。わたしじゃなくて、人間の彩花の。
昨日まで、ピピチのなかに思い出を残すことだけが生き甲斐だった。アンドロイドのわたしが現れても、それが変わることはないと思った。スマホがあるから。そのなかに、すべての思い出があるから。だけどわたしがスマホを取り上げたらどうなるの? これ、彩花のすべてなんだよ? ピピチもお母さんも、人間の彩花を顧みない。どうして気づかなかったんだろう。わたしの存在が、わたしの生き甲斐を奪うって。悲しみが込み上げるけど、涙が出ない。呼吸が荒くなることも、鼓動が高鳴ることもない。悲しい。でも、カラダが悲しまない。わたしはいま、本当に悲しいの? それすらもわからない。ベッドの上の彩花は顔を覆って泣き始める。ようやくピピチが駆け寄って、その背中に触れるけど、遅いよ。何やってんのよ。もう。
「彩花。これ」
わたしはわたしに、お母さんからもらったスマホを差し出す。
「あなたの思い出だから、あなたが持っていて」
そう告げるわたしの顔に、悲しみはなかったと思う。冷たいアンドロイドの顔。だって、心がどんなにどしゃぶりでも、もうカラダが受け取らない。悲しみが、悲しみになって、もっと大きな悲しみを連れてきた人間だった頃の感覚がない。アンドロイドの体はわたしの悲しみを吸い取って捨てる。彩花はわたしの手からスマホを取って放り投げた。
「嫌なの! 嫌! 嫌!」
看護師のひとりが急いでスマホを拾い上げるけど、彩花は泣きわめいて、点滴の針をむしり取って、ベッドから降りようとして咳き込む。ピピチが抱きしめてるけど、彩花の感情の波は治まらない。わたしは――わたしはその気持ちがすべてわかるはずなのに、何も感じない。せめて涙が流れたら、悲しめるのに。
「大丈夫よ。部屋を出ましょう」
って、お母さんが言う。
わたしは泣きじゃくって、咳き込んでいる。
「いまだけよ。ちゃんと納得したんだから、きっとわかってくれるわ」
そんなことない。あるわけないよ。なんでわかんないんだよ。お母さん!
何年か前から、太陽系外に超高速で移動する「暗い天体」があることが確認されていた。当初は太陽重力の最果て、いわゆるグラビティ・スフィアの最外円、地球からおよそ2光年の位置に観測され、光速の20%を超える速度で太陽方向へと接近していた。「暗い天体」という呼称にふさわしく、特定の電波域で時折観測されるほかは姿を消していることが多く、グラビティ・スフィアに入ってから、幾度か軌道を変更したことがわかっている。方向は、うしかい座、アークトゥルス方面。人工物だった。
地球でラグランジュポイントに人工天体を作る計画が持ち上がったのも、これが原因だった。防衛のためだ。もちろん、「暗い天体」が人工物だという情報は伏せられていたが、データを見れば一目瞭然。それに対抗しうる人工天体を、当初は地球の衛星軌道上に建設すると言われていたが、危機感が募る毎に計画は見直され、月の向こうのL2に、いやもっと安定性の高い地球軌道L4かL5にと規模を拡張していった。
その矢先だった。ニューヨーク上空に未確認飛行物体が飛来、街は電磁的、あるいは「魔法」とも言われる未知の手段によって攻撃され、自由の女神が倒れる事態に至った。
このときも「暗い天体」の情報は民間には伏せられたまま。全世界に中継されるニューヨーク襲撃の映像を見ても、市民は一様に巧みなトリックだろうという醒めた反応を示した。とあるSF界の大御所は「ニューヨークを襲うのはSFの定番中の定番で、おそらく自由の女神が倒れる絵を撮りたかったのだろう」と冷笑し、彼の作品の映画化を手掛けた監督やプロデューサーたちも、「いまはニューヨークじゃないよね」「20年古いよ」「いまなら
生命工学企業であるテラリウム・インクは、この無窮花のアンドロイド工場にも噛んでいたし、人工天体計画でも重要なポジションを担っており、その上級顧問である蛍は娘の彩花にも、そのアンドロイドのアヤカにも構う時間を取れなくなっていった。
以降、アヤカのケアは蛍の右腕である湯川が中心となって務めるが、蛍に対して強い嫌悪感を抱いたアヤカ、そして彩花にとって、母の姿を見ないで済むのは都合が良かった。
アヤカの生活はすべて管理されていた。都市で生活するアンドロイドは、アヤカが初ではなかったが、人間から意識を移植されたのは初のケース。どんな事故が起きるかも知れない。行動範囲も制限され、久木と会う時間も湯川のチームへ逐一連絡をいれる必要があったが、アヤカは不平も漏らさず受け入れた。自分のことよりも、ベッドのうえで泣き叫んでいた彩花のことが気に掛かる。久木とも時折会うことがあったが、彩花のもともちゃんと訪れているのか、そんなことばかりを気にした。
幾度か人間だった彩花と会う機会が設けられた。データを取るためでもあったし、アンドロイド移植後のアヤカとの整合性を取るためでもあった。死の瞬間まで、可能な限り彩花の機微に触れ、彩花自身になることを求められていた。
「ごめんなさい。わたしがピピチを奪うことになって」
わたしがそう声をかけても、彩花は窓の外を見たまま何も言わなかった。
頬は痩けて、ずいぶん憔悴しているように見える。でも、心は穏やかに見えた。たぶん、薬を与えられているのだと思う。口元には静かに歌声が聞こえる。
遠い世界に。
わたしも知ってる歌。でも、どんな気持ちで口ずさんでるのかわからない。
その静かな歌が、静かに終わる。
「死ねばいいのに」
彩花が小さく呟いた。
その声がわたしのプラスチックの心臓を揺さぶる。
気持ちはわかるよ。痛いほど。でも、違うんだよ。
「生きるために選んだんだよ。このカラダを。水泳の彼、それと施設の子たちのこと、覚えてるでしょう? わたしはわたしのためじゃなくて、彼らのために生きるの。決めたよね? 決心して泣いたよね? わたしは、あのときのあなたなんだよ。あのときのあなたのまま、何も変わってないんだよ。変わったとしたら、あなたなんだよ。わたしだって、本当は泣きたいよ。泣きじゃくりたいよ。涙を流せるあなたが、どんなに羨ましいか、わかる?」
わたしはそれを、冷静な棒読みでしか伝えられない。
彩花もまた――
「わたしも、泣かないあなたが羨ましい」
抑揚なく答えた。
窓の外、遠くにはいちょうの並木が見えた。
彼とふたり、落ちた
「キスした?」
窓のほうを向いたまま、静かに彩花が聞いた。
「したよ。軽く」
「ふうん。したんだ」
「じゃあ――」
「そこまでだよ」
慌てて割り込んだ。
「あとは何もしてない。あのひとはまだ、あなたのことが好きだよ」
「ふうん」
3 18人いる!
わたしの部屋は、三鷹駅の北口から少し歩いたところに用意された。お母さんのラボの寮。都心から少し離れてるとはいえ、中央線沿い。なのに、鳥の声は賑やか。ピピチがいたら、教えてくれるんだと思う。鳥の名前。鳥好きのひさっピ。ひさピチ。ピピチ。それと、ピチチ。悠の愛称はぜんぶわたしがつけた。
食事は寮で用意してもらえるって話だったけど、自炊もできた。でも、自炊はよくわかんない。それに、人間だった頃にくらべると、幾分不器用にはなってた。でも大丈夫。包丁で指を切っても血は出ない。シリコンだから。怪我は治んないけど、修理は簡単。もう、その程度のことで
刻印のこと湯川に聞くと、いくつかある素体のうちの5番目のモデルだって。
「それじゃあ、ほかにも4人のわたしがいるの?」
「いや。ちゃんと起動させたのは1体。ほかは失敗作だ」
失敗作。
逆にいうと、わたしは失敗作じゃないんだ。泣くことも出来ないし、匂いも味もわからないのに。
「ねえ、もしかして、アップデートしたら泣けるようになる?」
湯川に聞いてみた。
「泣いている表情をして涙を流すだけだったら、簡単に実装できますよ」
って、それでじゅーぶんじゃないんだ。
「人間の『泣く』って行為はもっと違う原理が働いていて、感情によって泣いて、泣くことが脳にフィードバックされて、更に感情が高ぶるという、一種の共鳴状態にあるんです」
「共鳴」
「痙攣ともいう」
「痙攣」
じゃあ、笑いは?
そう思って、スマホでいくつかおもしろ動画を見たけど、腹が立つばかりで笑えなかった。バグかもしれない。それにしても、泣きも笑いも忘れた中で、怒りだけは確かだった。怒りは痙攣じゃないんだ。きっと。
「喜びや悲しみには、ストッパーがかかるんですよ。だから痙攣のように現れる。だけど怒りは簡単に突破する。怒りが厄介ですね。アンドロイドの感情実装は」
ふーんって感じ。
「なんか、道具みたいに言われてる気がする」
まさにその通り。図星突かれると、湯川は苦笑いする。
時間が経つとともに、だんだんと湯川チームからの監視も緩くなって、予定無しで出かけても、尾行がひとりふたりつくくらいになった。基本は自由。ピピチとは少し疎遠になった気がする。逆かな。わたしのほうから会おうって、あんまり言わなくなった。言っちゃいけない気がして。どう思ってんだろう。ピピチ。いまのわたしのこと。
ひとりで出かけるのは不安があったけど、もうすぐ冬が来るでしょう? そうすれば長袖だし、ストッキング履けるし、街に出てもアンドロイドだって振り向かれることもなくなる。だから、いいかな、もう。って。思わなくもない。でもこれもさ。死んじゃうってわかったときと同じでさ。いつか来る別れを覚悟するため、魔法を掛けてるだけなんだよ、自分に。だいじょうぶ、アヤカ。あなたならピピチなしでも生きていける。もうアンドロイドなんだから、身を引きましょう。って。人間だった頃なら、いまごろわんわん泣いてる。
スマホは新しいのを買った。もとの彩花が使ってるアカウント、ayakadiaryを探したけど、みつからなかった。彩花が消したのかもしれない。新しいアカウント、ayakasilicaを作ろうとしたら、だれかに取られてた。ayakasilica2、ayakasilica3……順に試して、取れたのはayakasilica5。わたしの手首と同じ数字。嫌な偶然。これってさあ、やっぱりわたし、5人いるってことじゃない?
ひさしぶりのピピチとのデートは青山。最近できたアクアリウム。彩花が行くはずだったところ。魚を眺めてるとなんか、海の中にいるような気がした。ピピチから手を握ってきて、ちょっと焦った。まだいけるんだね、わたしたち。そういえばさ。昔ほかの水族館でさ、水槽のまえでキスしてるカップルがいて、「あれ、やる?」って聞いたことがあるよね。まだ付き合い始めてすぐだったし、流されたけど。覚えてるかな。
そのあとカフェで話したけど、まあ、時節柄、宇宙人の話がメイン。宇宙人の話ばっかりの水族館デートって、なに?って感じ。でもまあ、しょうがない。時節柄。それに、嫌いじゃないし。わたしも。
ちなみに、軌道上の対宇宙人用決戦基地は、小惑星を集めて、その資材で作るらしい。
「月から持ってったほうが、資材いっぱい集まりそうな気がする」
「月は複数の企業が権利を持ってて、使えないらしい」
「そんな理由?」
新しい星を作るまで、千年はかかる計画だって。それじゃもう、いま襲撃してきてる宇宙人に間に合わないね、って言ったら、「暗い天体」がほかにも観測されてるって。
「つまり?」
「いま来てるのは第一陣」
「マジでー」
「長期的視野に立って防衛計画を立てないと」
「てゆーか、本当に来てるの? ニューヨークを襲ったの、映画真似て作ったフェイクだって話だよ?」
「そっち信じてるの?」
「うん。だってそれは。あー、いや。信じてるとかじゃないけど。うん。でもさ」
「どうしたの」
「もしさ。もしもだよ。もし、宇宙人が来たらさ」
「うん」
「ピピチはさ――」
ピピチは……ピピチはわたしのこと……いや、ピピチとわたしは……どう言えばいいのかな。
「ごめん、アヤカ」
ふと気がつくと、ピピチは両目を押さえていた。
「どうしたの?」
「その愛称で呼ばないでくれるかな」
どういうこと?
「思い出すんだ。彩花のことを」
思い出すって?
「僕だって不本意だったんだ。ずっと泣いてたんだよ。彩花と同じように。君にはわかんないだろうけど」
待って。
「わたしがアヤカだよ? わたしが付けたんだよ? ピッチも、ピピチも、ひさっピも」
言い返すと、悠は涙を拭いて、冷静を繕う。
「ごめん。そうだったね。混乱してるんだ。ああ、うん。忘れて」
ひどいよ。そんなのないよ。忘れてだなんて。
「いま、わたしがどれほど泣いてるかわかる?」
「えっ?」
「わたし、どんなに悲しくても泣けないの。でも、泣いてるの。わかる?」
「ああ、うん。わかるよ」
そんな上辺だけの相槌なんていらない。ふと、手首の刻印が頭を過る。わたしは彩花じゃない。アヤカだ。5番目のアンドロイド。ほかにもわたしがいるかもしれないし、だとしたら、わたしって、なに?
「わたしはさあ、もう人間の彩花じゃないよ。それはしょうがないと思うよ。ちゃんと決心はついてたんだから。でもさ。わたしの手首に番号があるでしょう? こないだ見せたよね? わたしがこの番号で、どのくらい苦しんでるか、って」
「わかるよ」
悠はいつも上の空だった。そのたびに、恋人同士でしょう? 他人事なの? って、本当は苛立ってた。
「じゃあ、言って。ここに何番って書いてあるか。この数字が、どれほどわたしを苦しめてるか、話したよね?」
なに聞いてるんだろう。ばかみたい。鼓動が無限に高鳴っていく。わたしは自分を押さえながら返事を待った。すると――
「じゅう……はち……?」
「18!?」
思わず立ち上がった。
「他に17人もわたしがいるってこと!? あなたいったい、何人のわたしに会って、どんな話をしてるの!?」
途端、視界が赤くなった。景色にノイズが入る。音が消える。なんか、視界にアラートでてる。なんだこれ。聞いてないよ、こんなの。体には力が入らず、眼の前のカップもケーキもなぎ倒してわたしは倒れる。悠は慌てて手を伸ばして、周りの客が立ち上がる。客はすぐに工具や聴診器を取り出して、わたしの周囲をとり囲む。違う。これ。客じゃない。湯川のスタッフだ。ずっと監視してたんだ。
気がつくと布団のなかにいた。わたしの部屋だ。カーテンも、布団も、それに、壁にかけたジャケット……うん? なんか、ちょっと、へん。なんとなくわたしの部屋っぽくはあるけど、ちょっと違う。窓には、カーテン越しにビルの影がある。三鷹の寮はグラウンドに面してた。てゆーか、窓こっちじゃないし。じゃあ、ここはどこ? わたしは……たしか、ピピチと口論して……そう、刻印のことで……
ふと手首に視線を落とすと、「Model 14」の刻印があった。
14? なんで?
湯川に連絡しようと思ってスマホを取ると、メッセージが届いていた。
「Model 05がオーバーヒートしたので、体を交換しておきました。基本的には元と同じです」
はあ? こんな説明で何が通じると思った?
すぐにこっちからも連絡。
「これは、どういうこと?」
「ああ、それでしたら――(中略)――事故に備えて、いつくか予備があって、そっちに載せ替えました」
「待って。住んでる場所まで変わってるんだけど」
「あれ?」
しばしの間。
「ごめんなさい。Model 05は三鷹寮ですね。勘違いしていました。まいったな」
「まいったなじゃないでしょうよ。わたしは何人いるの?」
かつて、自分が何人いるかひとに聞いたひとっていないと思う。
「それは機密になってます」
機密だって返されたひとだっていない。きっと。
「Model 14です」
次のデートで、悠にそう挨拶すると、悠は苦笑いしていた。
「ああ、じゃあ、こないだゲームセンターに行った?」
「そうなんだ。でも記憶はModel 05を継承してるんで、水族館のほう。ゲームセンターは初耳。14番とはそこでデートしたんだ」
彼の気まずそうな顔。
「そこでわたしとどんなことをしたの?」
「あ、いや、なにも」
「キスした?」
彩花と同じこと聞いてるし。
「し……た……? かな? あ、いや、してないかな」
こっちの反応を探り探り。
「どっちだっけ?」
あー、もう。
「あなたいったい、何人のわたしと付き合ってるの!?」
4 わたしの人生の物語
わたしのコピーは合計で27体いた。Model 05はオーバーホール中で、稼働しているのは26体。うち7体が、自分が複数いることに気がついて、わたしで8体目。
おめでとう! あなたで8人目です! おめでとうわたし! ありがとうわたし!
なんのゲームをさせられているんだ、わたしは。わたしたちは。
不安になる。
このまま27人体制(なんだそれは)でいくのか、それとも一番彩花っぽいわたしが彩花として採用されて、ほかのわたしはスクラップになるのか。
「でも、意識転送のときに彩花の病室にいたのは、わたしひとりだよね?」
湯川に聞いてみた。
「ああ。そうだね。いや、Model 01だけだね」
「Model 05じゃなくて?」
「Model 01の記憶がシェアされてるから、みんなそこにいたことを記憶してるよ」
ふざけてんなー。相変わらずふざけてるわー、こいつー。
「そろそろModel 05の修理が完了するけど、部屋はどうします? 交換して元のに戻します?」
「それ、本人同士で話し合って決めていい?」
「いや、まだその段階じゃない」
「待って。その段階になったら何をするの? オーディション? ガラスの仮面のヘレン役みたいに、だれがいちばん彩花に近いか?って」
湯川、苦笑い。図星かよ。
「ずいぶん古い漫画を知ってますね」
「こないだ連載再開されてたよ。花ゆめ復刊号で」
オモダルで宇宙生活型のアンドロイドの生産が始まったんだって!
いやあ、びっくり!
宇宙生活型って、なにそれって感じだよね。
あー、オモダルってのは、
いや、でもさ。お母さん、オモダルのスタッフなんだよね。わたしのアンドロイド化を強行したんだって、なんかそのへんの理由があるんだよ。言わないけど。鬼だと思ったよね。湯川に聞いたらさ、「アンドロイドものの話は、たいがい自分の子を改造してる」って。バカじゃねえの。こっちはリアルだっつーの。てゆーか、アンドロイドになるまえに知りたかったよね。宇宙戦争の話。で、それ言ったら、湯川、なんて言ったと思う?
「以前からニュースにはなってましたよwwwwwwww」って。
なってましたじゃないよ、なってましたじゃ。教えてよ。それと草生やすなよ。ちゅーかさあ。バカじゃないんだよ、わたし。でも、知らんものは知らんしさ。じゃあ湯川てめえ、アタマいいって言うんだったら、ゴルジ体の襞を広げたときの総面積が答えられるのかよって話じゃん?
「AIに聞いてみるwwwwwwww」
って、いや、そうじゃないんだよ。ゴルジ体はどうでもいいんだよ、ゴルジ体は。草生やすな。むしろわたしがAIだわ。忘れてたけど。アンドロイドなんだよ、わたし。ここ(コンコン)。こ・こ・に(コンコンコン)。えーあい、入っとるっちゅうねん。わたしに聞け。ソフトウェアがポンコツだって? ほっとけ。
ほんで、あれは知ってる?
オモダルの廃液問題。
かなりの猛毒吐き出してるっぽくて、いまの無窮花ってブルジョワの街でしょ? いや、そうなのよ。超テクノロジー都市。なんか、年寄は想像できないって言うんだけど、アンドロイド界隈では有名な話。すんごいんだよ。トラムとか。タクシー感覚で電車に乗れるの。いやおまえ、なに言ってんのって感じでしょ? でもほんと、わたしはなにを見たの? って感じよ。あの、ほら、東京で言うとさあ、たとえば成蹊大前でトラムに乗るじゃん? ほんで「小石川のテラリウム・インク」って言うと、勝手に吉祥寺駅までぶっ飛んでって、中央線の高速車両にガコーン連結して、ぶおーん地下通って、茗荷谷あたりにぴゃーっ出てきて、あとはまたトラム毎にぎゃん!ぎゃん!ぎゃん!ぶーんって目的地に着くの。なにこれって感じ。遊園地のオートムーバーの、ちょー賢い版。アァハァ!だよ。アァハァ! テラリウムについたよぉ!って。ちゃららーらーらー♪ ちゃららーらーらー♪ ちゃららーらーらー♪ ちゃららーらーらー♪ 東京もいちど焼け野原になればごにょごにょごにょってのはまあ、置いといてー。でーその廃液の件で、ちょー突き上げくらって。環境団体からも、一般市民からも。でもそーは言っても、なんかいま、オモダルが最大のアンドロイド工場で、他には代わりがないってゆーじゃん。いや、なんかそうらしいのよ。わかる? オモダルに相当するアンドロイド工場って、もう人類には作れないんだって。へぇーって感じでしょう? わたしもへぇーってなった。なんで? 人類、退化した? みたいな。アァハァ! 残念だったねえ! みんなあ!
で、これ、あんまり大っぴらになってないんだけど、ずっと昔ね、オモダルとアヤカシコネっていう2体のアンドロイドが作られて、その技術がもう残ってないんだって。で、なんで残ってないかっていうと、そもそも《
で、最初に作られたオモダルは、自分を改造してどんどん大きくなる方向で進化して、アヤカシコネは自分を複製する方向で進化したっちゅー話。
はい。ここで気がつくひとは気がついたと思うけど、わたしの名前。敷根彩花。これ、アヤカシコネにあやかって、お母さんがつけたの。アヤカだけに。敷根とシコネの方は偶然だと思う。多分。で、わたしのボディも初代アヤカシコネから数えて4世代目かなんかのモデルっぽい。世代の数え方には諸説あります。
それでええっと、オモダルが宇宙に打ち上げられるって話はした?
そう。そうなの。オモダル、宇宙に打ち上げられるんだって。廃液問題があるから。宇宙って廃液流してもいいの? ってのはようわからん。でも宇宙って、めっちゃ広いから、薄まるんだろうね。廃液も。さーって。染み込むように。真空に。染み込むか~い、ボケ~。で、オモダルは宇宙に行って、アンドロイド作って、資材集めて、将来的には星になるんだって。星。スケール違うよね、できたアンドロイドは。
敷根アヤカModel 22がとある動画サイトに投稿したこの動画は、テラリウム・インクが設定した監視網にかかり、投稿元にエコーバックされるだけで、一般に公開されることはなかった。テラリウムが設定した架空のアカウントから、自動応答のリプライが届き、敷根彩花の頃には経験しなかったほどの高評価がついたが、すべて架空のものだった。自動応答のbotは、特定の単語に反応して、関連づいたテキストを返す。たとえば「ケーキ」と書けば「美味しそう」と応え、「大嫌い」と書けば「だよね。わかる」と応える。何を書いても書き手の自尊心を満たす返答を返すばかりで、決まってそのひとを増長させた。そこに投稿するのが、食事の写真か、ちょっといい話か、大喜利かは、そのときの投稿者の気分で、運だった。同じ敷根アヤカでも、Model 22はテラリウムの内情をリークし、Model 04は詩を書き、Model 15は自身のあられもない姿をアップしたが、たまたま椅子に座ったときの、スマホに向かったときの気分で、そのポストに「いいね!」がついて、それがそのアヤカの個性になった。これは敷根アヤカに限らず、人類は概ねそうだ。まだ2歳か3歳の頃、あるいはもっと幼い頃に、たまたま取った行動にたまたま笑ったひとの反応を見て、自分の行動を選択していった。すべて、運だ。だれも、なにも、自分の意志では選んでいない。だのに、そのうちのだれかはやがて罪を犯し、裁かれ、殺される。どこまでが彼の責任だろう。彼がたまたま転がったところに穴があって、落ちただけではないのか。
アヤカが予感した通り、27体のアヤカはやがて選抜され、Model 05のアヤカがひとり残った。だけどアヤカにその事実が知らされることはなく、ただどこかにいたはずの他のアヤカが、アヤカが知らないうちに姿を消しただけの話だった。おそらく、蛍と木下、湯川、そして肉体に残った彩花本人がレポートを読んで、何番の個体を残すか話し合って決めたのだろう。そのプロセス――あなたは以下の点で敷根彩花との一致率が高く、選抜されました――などは一切伝えられない。この物語で追っていたModel 05(から乗り継いだModel 14)が選ばれたのだから、何か物語的な理由があるだろうと考えるならそれは間違いで、この物語はただ、最終的に選ばれたModel 05を遡って描いたに過ぎない。「奇跡の生還! 完全再現72時間!」などのドキュメンタリーも、そのひとに奇跡が起きたのではない。ただ偶然、サイコロを転がすように選択されて、たまたま生き残ったひとりを取材し、理由があるかのようにドラマに仕立てたに過ぎない。
「つまり、西武線の遮断器が上がるのが、あと1分早かったら、この大事故に巻き込まれていたということですね?」
「ええ、いつもより長くて苛々しましたが、おかげで命拾いしました」
見る側はそこにドラマがあったと信じる。奇跡があった。そこには教訓がある、と。だけどそこには、奇跡も教訓もない。偶然だ。
たとえば、最後まで自分以外の彩花がいると気が付かなかったModel 16を主人公に据えれば、それはまた別の物語になる。Model 04は藤の花をコップに飾って、ずっと詩を書いていた。彼らが選ばれなかった裏には、どんな理由もない。偶然だ。そして他のモデルのメモリは消去され、バックアップとしてModel 05のデータがコピーされた。Model 14が経験した悠とゲームセンターに行った思い出は、もうどこにもない。ほかも同様、ベッド・インした08、湯川に撃たれた02、彩花を殺そうとした25、Model 05に知らされることもなく、すべて消えた。
ペンキの剥げた鉄のアーチに、年老い乾いた藤の枝が絡む。
つい先日まで冷房が欠かせなかったのに、急激に冷え込んだ。
もう秋なんて季節はなくなっていた。
午後からの雪の予報が留保された低い雲の下、枯れ葉の小径を踏む。
「彩花はもう長くない、急いで」と連絡を受けて、もう小一時間が経つ。
それでもタクシーを正面玄関に回すこともなく、裏門からの道を歩いた。
はじめてこの医院を訪れたときの空気を集めて、一歩一歩、自分の足取りをながめながら、かつて彩花だった頃にいた病室に着くと、あの日脱ぎ捨てた自分が、呼吸器をつけて喘鳴を漏らしていた。
母の蛍、その右腕の湯川、それから何人かのスタッフがいる。
ピピチの姿も見える。
ピピチは彩花の手を握り励まし、母が椅子を立つとき、母の頬にも涙が見えた。
泣くんだ。あのひとでも。
彩花のために泣いてもらえるのは嬉しかったけど、また不安になる。
みんなもう割り切っていると思っていた。――てんてんてん。
彩花はわたしじゃないのか。
まだ彩花になれないのか。
あるいは、わたしは本当に彩花になりたいのか。
母に促され、枕元に用意された椅子に座る。
「最後の記憶を移植する。それでもう、あなたは彩花になる。戸籍も手配してある。正真正銘の敷根彩花になるの」
ピピチが横たわった生身の彩花の額の汗を拭き、大丈夫だよ、きみとの記憶は永遠だよ、と、声を掛けているのが聞こえる。
湯川の話では、彩花はアンドロイド化のあと急速に自我を失っていったという。科学的にその理由は説明できないが、自分の存在意義を失ったショックからではないかとの説明だった。
眼の前で、自我をなくしたわたしが苦しんでいる。
――わたしは自然死したいの。
ピピチに言ったその言葉を覚えている。でもこれは自然死だろうか。
彩花を――わたしを最後まで苦しめた母も泣いている。だれのせいだと思っているんだ。よく泣けるな。
放心状態のわたしに、白衣のひとたちが電極のついたヘッドギアを被せる。オシロスコープが彩花の脳波をモニターしている。もう息も絶え絶えの彩花がわたしに視線を流し、母が装置のスイッチを入れると、細いケーブルを通して彩花の声が伝わってきた。
母も、ピピチも、スタッフも、感動に目を潤ませて見守るなか――
死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ。死んでしまえ……
その声は空気を揺らすことなく、わたしの意識にだけ流れ込んだ。
「死ぬのはおまえだろう! この意気地なし!」
わたしは立ち上がった。
思わずスタッフが顔を上げる。
「自分で決めたんだろう! みんなのためにアンドロイドになるって! おまえの夢を背負うのはこっちなんだぞ! こっちはこれからずっと、ずっと、ずっと、このシリコンのカラダとつきあっていくんだ! おまえが決めたせいで! おまえのせいで! だけどわたしの勝ちだ! 死ぬのはてめえなんだよ! 死ぬのが怖いか! 怖いだろうよ! 泣き虫で弱虫のクズが! さっさと死ねよ! 負け犬!」
言葉の途中で久木が止めに入った。体を押さえられても、罵倒を止めなかった。母も泣きながらわたしの口を塞ごうとしたが、それでも止めなかった。
「まずい」
モニターを覗いていた湯川がそう発した次の瞬間。わたしの視界は真っ赤になり、全身の力が抜けて、意識が飛んだ。力なくその場に倒れ込むわたしが、最後に見たのは、わたしを見てほくそ笑む彩花の顔だった。
5 石と花
「見てくれよ。最敬礼だ。みんな君のことを敷根博士だと思っている」
湯川はそういって、部屋に並ぶアンドロイドの群れを示した。
その様子に戸惑い、彩花は聞き返す。
「わたしは、だれなんですか?」
「さあね。敷根博士の娘だというのは間違いないが、それ以上はなんとも」
空調の効いた清潔な部屋。薄明るい照明。入口には厳重な警備がある。本来なら、敷根蛍にしか入れないはずだった。それを彩花は顔認証でパスした。彩花は若い頃の蛍に生き写しだった。
その部屋は
彩花が若い頃の母親にそっくりだという話は、自身でも何度か耳にしたことがある。しかし、顔認証はただ似てるだけでパスしたりしない。骨格から、静脈、三叉神経、虹彩パターンなどすべてを照合し、双子でも一致することがないと言われている。ここに来たのは、彩花の母、敷根蛍のアンドロイド化を進めるためだった。
蛍は先日、
「外部からのアクセスは厳重にロックされていが、入ってしまえばこっちのものです。ケーブルを繋ぎ変えてもいいし、コントロール端末のキーボードに細工してもいい。そこが分散型コンピューターの悪いところだ。1台でも破られると、システム全体が丸裸になる」
そう言って、湯川はタブレットを操作しながら歩く。
「母はこのコンピューターで何をするつもりだったんですか?」
アヤカシコネとオモダル、2体のアンドロイド開発に蛍は深く関わっている。ここにあるアンドロイド群は、初代アヤカシコネからコピーされた第二世代だ。ここを設計したのも蛍だった。
しばらく手元のデバイスを操作したあと、湯川は言った。
「ここのアンドロイドはみんな失敗作だって。敷根博士は言ってました」
「失敗作?」
「ここのアンドロイドはみんな『賢い』んです。それがお気に召さなかったようで」
スーパーサイトは、テラリウム・インクのなかでも最大の電算センターだ。その計算能力は、地球上のシリコン型コンピューターすべてを合わせたものを遥かに凌駕する。アンドロイドの頭脳であるself-healing silicone polymerは四次元結合していると言われているが、それをコンピューターとして利用するのだ。2次元のダイに乗ったチップが叶うわけがない。発熱もなく、小型で、クロックは無限にアップできるとすら言われている。
「あのひとにとっては、オモダルが成功作。それがいまは軍の管理化にある。もう一度作りたかったんじゃないかな。オモダルみたいなアンドロイドを」
1024体のアンドロイドは、どれも敷根彩花に似ていた。それが植林された木々のように整然と立ち尽くしている。人格はないというが、瞬きもしているし、時折彩花たちの方に視線を投げる個体もある。服はない。アンドロイドのシリコン製筐体がむき出しになっている。
「でも、オモダルは工場では?」
「そう。いまは工場。でも、その前は重機だった。その前はわかりますか?」
「その前?」
「電車だったんですよ。小型の」
「電車?」
「そう。オモダルはずっと自分自身を改造してる。電車から、重機になって、アンドロイド工場に。まるで小さい男の子の夢みたいでしょう?」
「……」
「他方、アヤカシコネは。君にそっくりです」
「たしかにそうだけど」
「初代のアヤカシコネは敷根博士をモデルにしてますからね。敷根博士にとって、やんちゃなオモダルが自分の子、自分の分身である真面目なアヤカシコネは失敗作なんでしょうね」
自分と同じ姿をしたアンドロイドの群れには嫌悪感がある。敷根蛍の「失敗作」という言葉は、おそらく、蛍自身へと向けた言葉なのだろうと、彩花は感じた。
「母は助かるんですか?」
スイッチングハブのケーブルを手繰る湯川に聞いた。
「なんとも言えません。でも、意外です。敷根博士のことは恨んでいるのだと思っていました」
恨んではいる。それでも、助かるかどうか気になるのは、人間の性なのだろう。
「ええ。恨んでます。だからこそ、永遠に生きる苦しみを味あわせたい」
彩花は悪びれてそう答えたが、本音ではない。湯川にもそれはわかる。だが、言葉の奥に敷根蛍、そしてその助手の自分への怒りもあるようにも受け取られる。
「あなたには済まないことをしたと思ってる」
「今更ですか」
彩花の抑揚のない言葉は、いちいち湯川の胸に刺さる。
「アクセス完了。これで僕もルート権限を使える」
湯川がタブレットの画面をタップすると、1024人の敷根蛍が彼に向かって最敬礼した。
彩花は湯川のことを、父親のように思っていた時期があった。敷根と湯川は同い年だったはずだ。生命科学方面で数々の功績を持ち、テラリウムには敷根蛍が引き抜いた。幼い頃から何度も部屋を訪れ、食事をともにし、「お父さんと呼んでもいいよ」と冗談めかして言われたこともある。母に倣って、ずっと「湯川」と呼び捨てだった。
「湯川さんは――」
敬称を付けるときは、クリティカルな質問だ。
「わたしのお父さんを知らないんですか?」
「ああ。知らない。僕じゃないことだけは確かだよ。知りたければ、敷根博士の意識が戻ったら、本人に聞くといいよ。いまなら話すかもしれない」
「そうですか」
敷根蛍の意識が戻ることがないことはわかっていたが、湯川はまだそれを彩花に伝えていない。テラリウムの役員会からは、敷根博士の頭脳を保護せよと、やんやの催促を受けている。
「ああ、そうだ。バックドアを開けておくから、そこからログインして彼女らに聞いてみるといい」
「彼女ら?」
「ああ。彼女とはもう言わないのかな? 彼らに」
湯川は居並ぶアンドロイドたちを指し示した。複雑にケーブルで繋がれ、左胸にはそれぞれナンバーが刻印されている。彩花は自分の手首にある番号のことを思い出した。このひとたちは第二世代。わたしは第四世代。
つまり。大叔母。
「いいんですか? セキュリティとか」
「セキュリティは、僕が考えるよりも、彼女らのほうが正しく判断できる。あ、いや。彼らのほうが。それに、あなたのほうが高い権限を持ってる。あなたは敷根蛍だからね」
冗談めかした口ぶり。母親と同一視されることには嫌悪感がある。
「もう、人類の時代じゃないんです。敷根博士が、あなたをアンドロイドに移したのも、新しい時代を見越したからじゃないかな」
湯川が彩花にアカウントを開放したのには裏があった。生体コンピューターではデータが抽象化されておらず、21世紀の言葉を使うなら「ビッグデータ」として、あるいはそれ以上の乱雑さで、インデックスされることなく記録されている。そのままで利用することはできず、アクセスはナビゲーター・レイヤーを通す。つまり、人工知能との対話で必要なデータにアクセスすることになるが、湯川が求めていたのは、敷根蛍が隠し通した「
敷根蛍はアンドロイド技術の核となる
敷根蛍にとっては、そこまでして隠した
湯川が取れる手段はふたつ。
ひとつは、ここ、スーパーサイトでのデータマイニング。湯川はサイトの防御壁にバックドアを仕掛け、彩花のアクセスを監視した。彩花は実質的に、敷根蛍だ。データを引き出す可能性がある。
もうひとつは、敷根蛍の脳の生体保管。やがて脳の活動からではなく、ハードウェアからの情報読み出しが可能になる。その日のために脳を保管する。湯川はこの処理を、かつて蛍の弟にも施した。
彩花は日本に戻ると、悠とふたりで施設を訪ねた。学生時代、同じように悠と訪れた施設だ。義手義足の利用状況を調べ、施設の子たちと触れ合い、あれからもう四年が経つ。施設を出たもの、新しく入ったものも少なくない。その日、彩花たちが乗った車を、施設の職員、入所者たちが拍手で出迎えた。
「全身アンドロイドになっても、普通に彼氏がいるし、ごはんも食べれます」
彩花は、そう言って励ますつもりでいたが、結果はどうだろう。新しく施設に入ったという小さい子は、義足のままブレイキンを披露し、「お姉ちゃんもできるよ。練習しなよ」と手を引っ張った。見様見真似で、いくつかステップを踏んだけど、すぐに足がもつれ、転び、だけどだれも笑わなかった。だいじょうぶ? ごめんね。ゆっくりでいいよ。きっとできるよ。そう言って、手を取って起こしてくれた。転んでもだれも笑わない。笑うのは、立ち上がったときだ。
「結婚するの?」
取り囲んだ子たちのひとりが、彩花の袖をひっぱって尋ねた。えっ? 小さく漏らして、彩花は悠の顔をちらりと覗いた。
「するかもしれないね。もしかしたら」
子どもたちに向かって、悠が答えた。
「でもそのためには、僕は、もっと、もっと、頑張って、敷根さんに認めてもらわないといけない」
悠が大げさにジェスチャーまで交えて言った「もっと、もっと」という言葉を、子どもたちは小さく真似した。もっともっと頑張る。みんな以上に僕が頑張る。それが高校時代からの悠の口癖だった。
彩花は、認めてもらうのは自分のほうだと思っていた。人間として。いままで通りの彩花として。悠もそれを見透かしてそうは言ったのだろうけど、嬉しかった。子どもたちはくすくすと笑いあった。
「赤ちゃんは?」
無邪気なだれかの声が響いた。
慌てて悠が手を広げて制する。
「いやいやいや、結婚もまだだから。赤ちゃんはまだまだ考えてません! ここにいるみんなが僕らの子どものようなものだから、みんながね、もっともっと大きくなってね、社会に出て、働くようになったら、それから考えます」
悠が機転を利かせて応えると、それって何年後? ぼくもう赤ちゃんじゃないよ、お小遣いちょうだい、と声があがる。悠は照れたり、焦ったり。彩花は、アンドロイドとしてだけど、ここに帰って来れたことを懐かしんだ。むしろアンドロイドとしてここに帰ったことが、自分の使命だったように感じた。
施設からの帰り、ファミレスで食事を取っていると、悠は改まって「話しておくことがある」と切り出した。いつにない真面目な顔。彩花は、先程の施設でのことを思い出した。
もしかしたら、プロポーズかもしれない。
「なに? かしこまって」
彩花は照れながら――もちろん、アンドロイドの表情に、照れる様子などは出ないのだけど、「いつものピピチじゃないよ」と、言葉を返した。胸の中には温かい気持ちが広がる。その日が来たのかもしれない、と。だけどそれに続く悠の言葉が、その仄かな予感を拭い去った。
「彩花から……。人間だった頃の彩花から預かったものがある」
嫌な予感がした。悠は嫌なことを言おうとしている。彩花が死んでもう半年になる。嫌なことじゃなければ、すぐに言ったはずだ。
「なに?」
胸のなかにいくつか綻んだ花は花びらを落とした。だけど表情も、声のトーンもそれを表しはしない。なに?という短い問いの意味を悠がどう受け取ったかはわからない。
「最初に謝らせてくれ。きみのことを彩花だって認められなくて、最初の頃は辛い思いをさせたと思う。反省している。だけど、いまの僕にとって、彩花は君だけだし、それだけは――」
「だから、なに?」
悠の言い訳がましい言葉に、彩花が割り込むと、悠は息を呑んで、自分の中の決意をもう一度確かめて、改めて口にした。
「彩花から、受精卵を預かってる」
「えっ?」
彩花……受精卵……つまり、人間の彩花から預かったということか。自分の――アンドロイドであるアヤカの死を最後まで望んだ、あの女から。
「その子をふたりで育てるっていうの?」
彩花が聞き返す。
「いや、まずは君の考えを聞こうと思って。何か判断するのはそのあとにしたい」
彩花のうちに現れたのは怒りや絶望、悲しみ、戸惑い、屈辱、恥、惨め、それを混ぜ合わせてただ汚く濁った、名前のない感情だ。
「受精卵を預かった、って。受精卵ってあいつの意志だけでできるわけじゃないよね? あなたとあの女とで決めたんだよね? 『受精卵を残そう』って二人で相談して」
悠は恐縮し、ただ体を固くしている。
「わたしに相談もせずに? わたしに育てさせるつもりで? アンドロイドだからなんでも言うこと聞くと思って? 勝手に決めたんだよね?」
「ごめん。あの頃、彩花と君とは同じだって思ってたから――」
「彩花はわたしでしょ? なんであの女が『彩花』で、わたしが『君』なの?」
「ごめん。眼の前にいたから、君で通じるかと思って」
死ぬ間際に、薄ら笑いを浮かべた彩花の顔が思い出された。
アンドロイドになった彩花はパーツを替えれば永遠に生きることができる。いくらでもクローンが作れて、いくらでも世代交代できる。この体を選んだのは、悠が「施設の子らを勇気づけよう」と言ったからだ。だから花のように枯れていく人生ではなく、機械として、石としての人生を選んだ。なのに、あなたは彩花の子を育てる? どういうこと? 百年もしないうちに、あなたも、彩花の子も死んでしまうのよ? もしあなたが――あなたと彩花の子が、幸せに生きて、幸せな最後を迎えるとしたら、それはわたしがスマホに「思い出」を作りながらやってきたことでしょう? それを奪っておいて、どうしてそんなことが言えるの?
悠にしても、彩花がここまで人間の彩花を嫌っているとは思っていなかった。たしかに最後のセッションでは高ぶっていたが、元はひとつの人格だったはずだ。時が立てば気持ちも落ち着くものだと信じていた。彩花の反応に戸惑いはしたが、だけど、いつかは言わなければいけないことでもあった。
「いいよ。わたしのこと、嫌いになっても」
彩花は続ける。
「わたしもこんなわたし、大嫌いだから。彩花だったら、こんなこと言わないし。あなたがわたしのこと彩花だと認めないのもしょうがないと思うよ。わたし、アンドロイドだから」
本来なら涙ながらに訴える言葉だ。だけど彩花は涙を流せない。涙によって増幅され、フィードバックされない感情は、冷静な声で悠に届く。こんなにも悲しいのに、なにも伝わらない。それが言語によるコミュニケーションの限界だった。悠のまえにいるのは、文章を棒読みするだけのアンドロイドだ。彩花は続ける。
「別れよっか、もう。わたしなんかといるより、ずっと幸せになれるよ」
心の中はどしゃぶりだった。人生でこんなに泣いたことはない。だのにプリセットされた「悲しみ」の表情が現れる以上の変化はなにもない。
悠は何も答えず、おもむろに席を立って、彩花の隣に座り直した。
「ごめんね」
そう言うと、隣から彩花の体を抱きしめる。
「君がいま泣いているのは、わかるよ。話の続きは、泣き終わってからでいいよ。いまは泣いていいよ。ゆっくりでいいから。ゆっくりで」
悠の体温が彩花に伝わる。彩花の胸の奥の深部体温系がそれを読み取る。
「いっぱい、見てきたよね。手がない子。足が、ない子。彩花は、泣けない、子だよ。君の、ことが、わからない、人間じゃ、ないつもりだ」
悠は、しゃくりあげながら、その言葉を口に紡いだ。
6 ボンベイ・タイプ
志高高原にはかつて「志高レイクピア」なる遊園地があった。
その直ぐ傍に木製コースターのジュピター(もくせいだけに)を擁する「城島高原ランド」があった。別府の市街地に面した「ケーブルトイパーク」を合わせると、別府近隣に3つの遊園地がひしめいていたが、昭和のベビーブームの折、マイカー時代とも相まって、いずれもそれなりの集客を誇っていた。とは言え、ケーブルトイパークはともかくとして、志高レイクピアと城島高原ランドは、やまなみハイウェイとして知られる県道11号を30分ほど走った先にあり、別府を訪れる観光客を呼び寄せるには少々難があった。日田・久留米方面から訪れる家族連れであれば、そこで半日の観光を楽しんだのちに別府へと入り、夜はホテルのジャングル風呂をと旅を満喫したものだが、博多から小倉経由の日豊線で訪れた客や、大阪からフェリーのむーんふらわあで来た客が足を伸ばす場所でもない。志高レイクピアのライバルの城島高原ランドは、むーんふらわあを運行する神西汽船が作ったもので、別府観光の目玉にとでも思ったのだろうが、家族連れの客は市街地のケーブルトイパークであひるの競争に興じ、慰安旅行の客の類は血の池、たつまき、坊主地獄の地獄めぐりで旅の情緒を味わった。城島高原ランドは遠かった。もちろん、志高レイクピアも。なるほど、それならば、と思ったかどうかは定かではないが、集客力のあるケーブルトイパークから、リフトとロープウェイで乗り継いでまっすぐに志高レイクピアまで導線を引いた時代もあったが、これも長くは続かなかった。そもそも、別府市街からケーブルトイパークへのアクセス手段がケーブルカーであった。ケーブルカーで登る遊園地は期待を掻き立て、子どもたちもこれから始まる冒険(あひるの競争と演芸場ではあるが)に心を踊らせたものだが、そこから志高レイクピアに至るには、スキー場にあるようなリフトで立石山山頂まで5百メートル、更に船原山山頂までロープウェイで2キロ、またそこから志高レイクピアまで1キロをリフトで下る必要があった。それは曲がりくねったやまなみハイウェイをまっすぐに突っ切る宇宙戦艦ヤマトのワープ航法のように画期的な移動の足を提供はしたが、そもそもケーブルトイパークを訪れた客の何割が志高レイクピアまで足を伸ばしたいと思ったか。たしかに、ケーブルカー、リフト、ロープウェイと3種の乗り物アソートの冒険は心躍るが、行きはテンションが上がっても、帰りはどんなテンションでリフトに乗ればよいのか。ケーブルトイパークも志高レイクピアも、豊後国際観光なる地元の法人が母体であり、ロープウェイで直結で繋げば、神西汽船の城島高原ランドに客を逃さずに済む……と考えたどうかは下衆の勘繰りに過ぎないが、少子化とバブル経済の終焉とに見舞われ、平成15年、志高レイクピアは静かに35年の歴史に幕を下ろした。
志高レイクピアはその後、大分のテック企業に買われ、重力波受信槽が設置されることになるが(ここからはフィクションなので注意されたし)、これも長くは続かなかった。そも別府近隣は鉱物資源に恵まれ、金や銀の鉱脈が無数に眠ってはいたが、そしていまもなお眠っていると思われるのだが、どこを掘っても温泉が出た。いまも出る。それでも、温泉の湯と戦いながらも金銀パールの試験採掘を進めてはいたが、労働と温泉には程よい距離が必要だった。働く傍から熱水を被っていては疲労は取れず、むしろ蓄積する。作業効率も上がるはずなく、しかも地元は観光団体の声が強く、温泉が枯れたらどう責任を取るのだ、某有名ホテルだけで1日にいくらいくらの損失になると突き上げられては、開発を続けるわけにはいかなかった。そんななかで、志高レイクピアにもかつて途中まで掘り進められた縦穴が残っていたのだが、巡り巡って重力波の受信に利用されることになった。
当時は縦に百メートルほど掘られた穴に過ぎず、例に漏れずなかには湯が溜まってはいたが、温泉にするには深かった。そこで、というわけでもないが、この穴に重力波を共鳴させて、宇宙からの信号を受信しようとしたのがことの始まりだった。一般的に、重力波の検出にはレーザー干渉計が利用される事が多いが、その検出の前段階として、地球重力場に共鳴させ、増幅させる、というのがこの施設の設計の要旨だった。が、いざ実験してみると、わずか百メートルほどの穴では恐ろしく高い周波数の信号しか増幅できず、当初はそれでも倍音成分から信号を取り出すと言われていたが、うまくいかなかった。いや、いくはずもない。そもそもの発端が怪しかった。原理は高校でも習う共鳴筒と同じで、穴の深さの4倍の波長の重力波を増幅させる、と、これは某科学雑誌にも特集として組まれたこともあり、多少の科学の知識があればすぐに納得でき、広く投資を募るのには向いたが、論拠となるような論文はなく、厳密に科学であるとは言い切れなかった。素人が聞きかじった科学知識で猛進するのは、昭和の時代にはよく聞いた話で、続く平成・令和の時代にも核融合炉を作ろうとしている素人ストリーマーが複数観測されたのだから、これは人類の性なのであろう。件の縦穴も、更に深くすれば検出可能な周波数も下がる、と、投資に投資を重ねついにその深さは2キロに達するに至ったが、この事業を進めていた会社の社長は、許認可を下ろした役員ともども失踪した。
こうして、平成二十年にはエレベーター8基を乗り継いでようやくたどりつけるという謎の縦穴が完成してはいたが、その目的は騙されて投資した年寄りたちしか知らない。その騙された年寄りにしても、大半は何に出資したのかも理解しておらず、いっそ穴を掘る必要すらなかったのではないかとも思われるが、おそらく本気で信じていたのだろう。宇宙人からのメッセージを受信できると。その後、ナンセンスな穴の深さにしても、おそらくは尾鰭がついたものだろうとしてあしらわれ、縦穴のある元志高レイクピアの土地は、まあ30メートル以上の縦穴は空いていますが、との注意書き付きで、すぐに他の民間企業に払い下げられ、「受精卵の保管施設」に転用された。30メートル「以上」と謳われた穴が2キロと知ったときの、2キロかー、2キロ含んでたかー、という衝撃は相当であったと思われるが、空いているものはもう、利用するしかない。それはそれで好都合な部分もあった。
この受精卵保管施設は厳重に管理され、一般に公開されることはなかったが、彩花と悠は特別なルートからこの見学を申請し、許可されていた。いったい、特別なルートとは。豊後国際観光が手引をしたのか。答えは、否だ。いまの彩花は、蛍と同様に振る舞うことが出来た。件のアヤカシコネによって実装されたスーパーサイトを介し、実質的な政府支配にも近い権力を振るうことができたのだ。
なるほど、母、敷根蛍の万能感も、ここに起因するのか。母は、どこかで手に入れた「
だけどわたしは、母とは違う。
違う。
違う。
彩花は何度も胸のなかに繰り返した。
彩花の血液型、ボンベイ型は劣性遺伝だった。ボンベイ型は後天的に発生することもあったが、彩花の場合は蛍から受け継いだ先天的なものだ。そして、劣性遺伝ということは、父親もこの遺伝子を持っていたことを意味する。
彩花がスーパーサイトのアヤカシコネたちに問い合わせたのも、その件だった。ボンベイ型が日本にたった百人しかいないのなら、父親も探すことができるだろう、と。実際には劣勢因子として保有している者も含むので、それだけで探すことはできなかったが、彩花は他の遺伝的特徴まですべて入力し、父親を探した。父は湯川だろう。彩花は予測した。予測というよりは、期待かもしれない。だが、アヤカシコネが彩花の父親として示してみせたのは、彩花の母、敷根蛍だった。母は父でもあった。XXの双方の遺伝子が、敷根蛍に由来したのだ。すなわち、大叔母たちは、彩花は蛍のクローンだと示した。
ショックはショックだった。だがいまはアンドロイドだ。いまの体が敷根蛍の血を引いているわけではない。ならば、何も気に病む必要はないはずだ。自分はただ、敷根彩花として、母とは違う一個の人格として、自分が正しいと思う選択をすれば良い。
母、蛍の実家は志高高原にもほど近い臼杵市にある。ちょうど大分市の南に隣接し、別府にも近い。母から、別府ケーブルトイパークからリフトとロープウェイを乗り継いで志高レイクピアに行った思い出を聞いたこともある。ケーブルカー、リフト、ロープウェイ、リフトと乗り継いで、ゴーカート。楽しそうだが、ある種の狂気だ。彩花は8基のエレベーターを乗り継ぎながら、ここもきっと豊後国際観光が作ったのだろうと思った。母が東京の大学を出たあと、最初に勤めたのも地元の工場だった。この町は、そこかしこに母の匂いがした。
この受精卵保存施設を見つけたのは悠だった。受精卵を預かるサービスは他にもいくつかあったが、なかでもこの施設を選んだのは偶然か。それとも、母が何かしらの策略を巡らせたか。母との因縁の浅からぬ場所であることは、スーパーサイトで得た情報からわかっていた。ここにはテラリウムからも、極秘裏に資金が流れている。エレベーターが下がるほどに、気圧はどんどん上がっていく。エレベーターの乗り継ぎ毎に少し休みを取って、ゆっくりと体を慣らし、地下2キロメートルの世界に、1時間かけてたどり着いた。
そこで係官から説明を受けた。
地熱を利用した永久発電機で水を排出し、空気を入れ替え、温度湿度ともにコントロールされていること、それから係官はパラパラと手帳をめくって、ああ、それとこれもあったなと、周囲の岩石の圧力は、特殊な中空構造で分散さている、などの情報を付け足した。彩花のターン。
「将来的に、受精卵はどのようにして育てるんですか?」
係官は手帳から目を上げる。
「まあ、ひとそれぞれと言うところでしょうか。何年か後に引き取りにきてもらって、自分のお腹で育ててもらってもいいし、いつか高性能の人工保育器ができたら、それで育ててもいい」
要は、何も決まっていないということだった。
「人工子宮はどうですか?」
彩花から切り出した。
「人工子宮というと?」
「人工的に受精卵を着床させ、胚発生させる機構……」
と、説明しながら、それは高機能な保育器と変わらないと気がついた。
「はあ、そういうものができるんでしたら、それもありでしょうな」
係官のひともろくに飲み込みもせずに、当たり障りのない相槌を返した。
空気には少し粘りがあった。喉を通るとき、空気の塊はだまになり、
しかし、待てよ。いまの体はシリコンだが、炭素系のアンドロイドも原理的には不可能ではない。あるいはハイブリッドも可能だ。実際にいまのわたしは、完全なシリコン型ではなく、骨格はモリブデンだ。
そう考えていると、扉の前に出た。
「この先です」
扉が開く。その敷居を境に、空気の化石が満たした空間がある。化石は体に触れるごとに床に落ち、砕けた。壁面には小さな窓が無数にあり、係官のひとは、ひとつひとつが小さな命の種なのだと目線を泳がせる。煮凝った時間のなか、声だけが幾重にも反響する。縦穴に生まれる疎密波が、重い金属質のぶうんという低い唸りになり、長い時間をかけてゆっくりと減衰する。
「それで、どうする? 預ける?」
悠が訊いた。受精卵のことだ。
「ううん。やっぱり自分で育ててみる」
彩花の返事。悠のなかに、小さな戸惑いはあった。だけど、「それもいいね」と答え、どうやって? とは聞かなかった。聞かなくても、彩花はその方法を見つけるのだろう。だったら、それもいい。彩花が残した受精卵だ。彩花が決めればいい。
「代理母でも頼みになられるんですか?」
無神経にそれを聞いたのは、案内してくれた係官だった。
「いや。そんなナンセンスなことはしない」
抑揚のないセリフだったが、悠は彩花が笑ったのだと思った。そのままのトーンで、「たぶん、炭素からもアンドロイドを作れる」と、続けた。
「炭素型アンドロイドに彩花の子を産ませる」
彩花には妙な確信があった。母が隠しているという「
悠がゆっくりと彩花の肩を抱き寄せると、目のやり場に困った係官は、誤魔化すように、
「はあ。まるで神様になるような話だ」
と言って、手帳を閉じた。
ふたりがいる暗がりのなかに、生体の脳を収めたシリンダーがあった。なにか似ているものがあるとすれば、巨大なウエディングケーキだ。それは2メートルに近い大きさがあり、スポンジではなく金属で作られ、生クリームではなくケーブルや端子類でデコレーションされている。そしてその最上段のガラスで作られた筒に収められているのは敷根蛍の弟、光、彩花の叔父の脳だった。蛍がだれも訪れることのないこの地下深くに持ち込み、解析のために機材に接続した。ゆくゆくはこのケーブルを介して、光がこの施設を乗っ取るなど、考えもせずに。光は、いまの地球において唯一「
Ⅵ 平成二十四年・リュシオール
1 的なもの
「そう、海苔弁的な」
と、わたしは海苔弁「的」なものをたのんだはずだった。決して海苔弁「そのもの」じゃない。だけど、湯川が差し出したものはラベルにもしっかりと海苔弁と書かれた海苔弁。
「あれ? 違ってました? でも、海苔弁って書いてありますよ?」
湯川は、ほら、ここに、と言わんばかりにラベルを示して見せる。
「いやいやいや」
欲しかったのは海苔弁じゃないのよ。海苔弁じゃ。
「ああでも大丈夫。想定してたのと違うけど、そんなに外れちゃいないから」
「良かった。美味しいですよ、これも」
わたしが頼んだのは、唐揚げがひとつ乗ってて、イカフライが乗ってて、ごはんの上には海苔が乗ってるお弁当だ。名前は知らない。湯川が買ってきたのは、磯辺揚げ、白身フライ、海苔をめくると醤油に浸したオカカがご飯に乗った、紛うことなき海苔弁。湯川が「海苔弁的なもの?」と聞くので、「そう、海苔弁的なもの」と答えた。そうそう、海苔弁的なアレよ、アレ、海苔弁……的な? そうそう! 的なアレ。でもこれは「的なもの」ではない。海苔弁だ。
湯川は首をひねるが、こう考えたらどうだろう。
たとえばバーに入って、「何飲む?」って聞かれて、その日はまだ仕事があるし、あんまり飲めないしと思って、「うーん、ジュース的なもの」って言うことってあるじゃない? そしたら、「わかった」って、スクリュードライバーなり、スプモーニなり、ソルティ・ドッグなりって話になる。決してジュースそのものが、「はいこれー。蛍のぶーん」って、出てきたりはしない。ジュースが欲しかったら「的なもの」って言わないで、ジュースって言うし。
えっ? 違うの?
じゃあ、こういうのは?
「昨日なに食べたー?」
「んー。うどん的なものー」
ああ、フォーとかパッタイとか、そういうものかなー。ってなるじゃない?
ならない?
いや、それちょっと、理解度低くない?
あと、こんなこともあった。まだ中学の頃の話だけど。
弟の性格を聞かれて、
「無口だし、あんまり話さない。友達もいないし。あ、そうだ、石と話してる」
「石と?」
「ああ、うん。拾ってきたの。ダイヤモンドだって言ってはしゃいでた」
「それってさあ、もしかして、自閉症?」
自閉症?
「ああ、うん。そんな感じ」
と、わたしは答えたけど、弟のことを自閉症だって思ったことはなかった。たしかに「的なもの」ではあるけど、違うんだよ。本当は。仮に弟がそうだったとしてもだよ。そうじゃないんだよ。
2 ふたつの道
iPS細胞の研究で京都大学の山中教授がノーベル生理学・医学賞を受賞した年。ひそかに科学界を賑わせたキーワードが「永遠の命」だった。当然、iPS細胞――どんな体組織にでも変化できる自在な細胞(induced Pluripotent Stem Cells)――が描く未来はその筆頭にあがったが、それも永遠の命までとなると、道は果てしない。
ネックになるのは、脳だった。iPS細胞も、脳細胞への成長は可能で、小さな脳組織を作り出すことには成功していたが、実際の人間の脳をこれで置き換えるとなると、クリアしなければならない問題が山積した。脳細胞というのは、そもそもシナプスという神経繊維を張り巡らせた不定形なものであり、これらがどう絡まりあっているかで記憶や人格が形成される。一個一個が複雑な形をしたパズルのピースなのだ。単に形だけ真似たものを用意しても、それでパズルの絵が埋まるわけではない。
では、永遠の命をどう実現するか。その特集ページの後半に紹介されていたのが、アンドロイド化、脳の保存、の、ふたつの道だった。
その冒頭には、こう書かれている。
美しい花を保存しようと思ったら、ふたつの方法がある。ひとつは写真に撮る、あるいは絵に描く事。それによって花の美しさは永遠になる。だけど、花そのものは死んでしまう。もうひとつは、氷中花。アクリルで固めてもいい。花は生きたまま保存されるが、二度と取り出すことができなくなる。
ひとが永遠に生きる方法もこれに似ていると言えよう。
ひとつは意識をコンピューターのメモリに電子的に保存すること。これは、意識は永遠に保存されるが、肉体そのものは死んでしまうことを意味する。写真に撮った花だ。
もうひとつは、特殊な液体に浸して、脳を、あるいは肉体を永遠に保管すること。これはたしかに、永遠の肉体を得たといえるかもしれないが、それが将来的に目覚めるとは限らない。こちらは氷中花だ。
コンピューター技術が目覚ましく発展する中で、人間の意識のシリコンチップへのロードと、その先にあるアンドロイド化は、十分に現実味を帯びたものとして紹介された。昔の映画やアニメには、脳はそのままで体を機械に置き換えた機械化人類みたいなものがよく登場していたが、iPS細胞を活用すれば、腕も足も機械に置き換えずとも若返らせることができる。対して脳は再生が難しく、実際に機械化人類が実現するとしたら、脳が機械で体は人間ではないかと予測されるようになった。ただし、これはまだ科学とは言い切れず、SFの範疇の話でしかない。
他方、脳の保存であるが、将来的に肉体の補修が万全となるとしても実用化までは時間がかかる、それまでは脳を仮死状態で保存しておけば遠い未来に人間として再生するチャンスがある、という主張から支持されるようになった。たしかにiPS細胞を用いたとしても脳の再生は難しいだろうが、それも時が解決する可能性は十分にある。もちろん、可能性でしかないが、金を余らせた富豪は興味を示し投資を始めたし、世間でも言語学者のノーム・チョムスキーや文学者の村上春樹の脳を保存すべきだという話が聞かれるようになった。あるいは、昨年逝去した金正日の脳が保存されているという噂も実しやかに囁かれている。
敷根蛍が務める大野化学工業は、大分県臼杵市に工場を構えていた。社員は契約の事務職まで含めて40人足らずで、主業務は炭素繊維複合材(Carbon Fiber Reinforced Plastics:CFRP)の加工。古くは富士の裾野にあったテーマパークに設置された巨大なガリバー像の製作も手掛けた。そしてこのガリバー像であるが、昭和50年代には別府の志高レイクピアにも作られていた。社長はその時代からこの仕事を続けている。
古い町工場ではあったが、アクリルやシリコン素材なども扱い、アンドロイド筐体の設計・製作まで手掛ける未来的な志向も持ち併せ、敷根蛍もそこに惹かれての選択だった。敷根蛍は臼杵市に生まれ、福岡の糸島大学に大学院まで在籍し、その在学中から大野化学工業でインターンを勤めている。院生時代に自己再生性シリコンポリマー:SHSPを発明し、その実績からすれば、大手の化学系企業に破格の待遇で招かれても驚きはしないのだが、その道は選ばなかった。目先のことに熱中しやすいタイプで、このときも大野化学の社長の
そんな経緯で、敷根蛍によるアンドロイド製作プロジェクトは、臼杵の小規模な工場で幕を開けた。とんとん拍子で平成二十二年、初のアンドロイドが完成。敷根はこれに「ミナカちゃん」と名付けた。日本神話の
次に開発されたのが
次に、シリコンポリマー溶液のプール内で、SHSP繊維が浮いている脂のような状態――クラゲのように漂っている非結晶固体――これを葦の芽が泥沼の中から萌え出るようにして形成し、次世代のアンドロイドが作成された。それが第4世代ユーマシア・シカビィ・ヒコズィであり、その名称は
同時期、名古屋の
大野化学工業の社長、
口ひげを生やしグレーのスーツを着たひょろっと背の高い大野安丸が第5世代トコタッチに代わる第6世代アンドロイドの人工知能に、「生体の脳」を使用すると言い出したのも、日枝精密技研の技術を見込んでのことだった。このプロジェクトのために日枝精密技研から派遣されたのが、後に敷根蛍の右腕となる湯川振一である。
日枝との技術提携をきっかけに、アンドロイド開発ラインは唸りをあげる。平成二十三年早々には生体脳を搭載したモデルが誕生。ニックネームはクニタッチ。これは
まったくもって遺憾な話ではったが、中止になるまでに十分な成果があった。これならば、脳だけを取り出して生体保存した「水槽脳」の状態であっても、人工知能に利用できるはずだ。
「水槽脳の状態で、百日程度は生かすことができます。まずは実験段階です。成功すれば、もっと大きな予算が降ります」
湯川も太鼓判を押す。
死んだモルモットの脳の利用にまで動物好きの社員は文句は言うまいと、第7世代トヨクモが開発される。名前は
しかし、ここで問題が発覚する。開発中のアンドロイドの最大の利点は、
①自分自身を修復する
②自分自身を複製して増える
であったが、モルモットの脳を利用していては、ボディは複製できても、脳は複製できない。トヨクモは生前のモルモットのとき好きだったメスを追い回し、百日のオマケの人生を生きて、そして死んだ。追い回されたメスもストレスで死んだ。やがてアンドロイドの時代が訪れたら、これも神話になるだろう。
次に開発された第8世代ウィディーヌ(名前は
それにしても、と、社長の大野安丸は思った。
自然死したモルモットを利用して何が悪いのだ。死んだモルモットが死してなおアンドロイドとして生きてキャベツを食み仲間の毛づくろいをするのだぞ。見ろ、彼らは、マウント行動やロードシス行動まで取っているではないか。
「でも社長、彼らが知恵をつけて、自分たちの仲間を作るためにモルモットを殺すようになったらどうするんですか」
社員が訴えた。
たしかにその可能性がないわけではない。
「やがて人間を襲って、人間の脳でアンドロイドを作り始めるかもしれないじゃないですか」
そこまでは考えなかった。
しかし、バグというものは考えないことが起きるのである。どんなバグが起きるかまでは想定できないのがソフトウェア開発である。が、しかし、である。それを言うなら、普通の家庭用のゲームだって、ある日突然超音波を発して子どもたちの脳を爆発させないとも限らない。
「たとえばバグで、魔王の部屋に入るスイッチが、米国の核ミサイルの発射ボタンに連動してしまうケースがあったらどうする。君は世のゲーム制作者に、そこまで考えてゲームを作れと言うのかね」
「いや、社長。それは暴論ですよ」
真面目な社員は真面目な顔でそういうが、アンドロイドが人間の脳を使って複製を作り出すのも、同じくらいの暴論だ。そんなレアケースを想定していたら、科学など進歩しようがない。言っては悪いが、科学の発展の影で数%の人間が死ぬのは、すでに織り込まれているのだ。米国の核実験に晒された兵士など83年に公開調査が始まるまで存在しないことにされていたんだぞ。
とは言え、凡百な社員の意見は、世間一般の意見でもある。無視して突き進めば突き上げを食らう。世話になっている銀行の融資担当だって、娘の成長を嬉々として語る凡庸な一般人だ。「大野化学さんは地元への貢献も高く、融資させていただいている我々も鼻が高い」と世間体ばかり気にし、これでは世間から融資されているようなものだ。次の決算報告で「アンドロイドがモルモットを養殖して、その脳を利用して自らの複製を作ります」と言えるだろうか。アンドロイド事業は赤字も出ている。投資には慎重にならざるをえない。となると、ついに開発は手詰まりか。そう思われた矢先、朗報をもたらしたのは、日枝精密技研から派遣されている湯川であった。
「結晶体にデータを記録するクリスタル・ドライブの技術を使ってはどうでしょう」
湯川は敷根蛍と同い年で、名古屋の大学で博士課程を終えている。彼の出した案は脳の生体保存という日枝きっての技術を無視した、まったく自社に忖度しない気持ちの良いアイデアだった。ここまで来ると湯川も会社よりもアンドロイドの将来に期待を寄せているのだろう。
「通常のシリコンチップは、多層化されているとは言え2次元です。クリスタル・ドライブは3次元でデータを記録する上に、論理上は1原子に1ビットの記録ができると言われています」
コンピューターはダイサイズを小さくすればするほど消費電力も減り、排熱機構もシンプルになり、動作も安定する。
「しかも、天然のクリスタルを『脳』として利用すれば、自分たちでクリスタルを掘って、勝手に複製を作って増えますよ」
なるほど。そう来たか。
SHSPで作られたアンドロイドが、自分たちで「脳」を調達して増殖することは、第8世代ウィディーヌで確認済だった。彼らは自然死したモルモットから脳を取り出し、アンドロイドを作成したのだ。脳の摘出に比べればクリスタルを掘るほうが、人間基準では時給も安いし、難易度は低いはずだ。
この湯川の提案を受けて、第9世代ツヌグウィとイクグウィが開発された。それぞれ
開発ラインはすでに自動化されている。わずか1週間ほどで人間タイプの次世代機、オート・ノディとオート・ノベィとが開発された。第10世代目、名前は
ついに人型で人間サイズのアンドロイドがロールアウトした。それまではアンドロイドと言っても、両足は石像のように固定され胸に液晶端末がある受付ロボットか、あるいは車輪で走るモルモットしかいなかったが、ここに来てついに二足歩行が可能になったのだ。開発者の感慨もひとしおだった。社長と敷根、湯川と何人かのスタッフで、駅前でフライドチキンと寿司を買い、近場のコンビニでビールを買ってささやかな祝杯をあげ、社長は赤ら顔で脈絡なく織田信長が本能寺で舞った能を舞った。が、そのとき、事故が起きた。その事故はある意味、予期されていたものだった。オート・ノディとオート・ノベィが人間を襲ったのだ。
シリコンペレットは砂からでも作り出すことができたが、クリスタルは入手困難だった。すぐに彼らは「安易な入手法」を探り、事務所内のクリスタルをくすねるようになり、やがては町へ繰り出して鉱石ショップを襲うようになった。アンドロイドにとって己を増強するシリコンペレットは食欲、複製するクリスタルは性欲だ。アンドロイドも、己の種を残すためにクリスタルが必要とあれば、血道を上げるのである。この生物じみた行動に社長大野安丸は「我々はついに生命を創造した」と、狂喜したが、臼杵市と言えば巨大な石仏で有名な土地だ。市街地に出れば天然石の数珠も売っているし、霊験あらたかなクリスタルの観音様なども売られているし、なんなら通行人のポケットに入っている。国宝の臼杵石仏を見に来たおじいちゃんおばあちゃんが、日本神話の
3 押し入れのひと
「オトト、いる?」
敷根蛍はそう言って静かに押入れの扉を開けた。
「いるよ。どうしたの、姉」
答えたのは敷根蛍の弟、光だった。
光が姉の蛍のことを「姉」と呼んだのが始まりだった。蛍からも光のことを「オトート」と呼ぶようになり、それが約まって「オトト」になった。オトトは幼い頃からひとりでいるのが好きで、外出を好まず、二十六になったいまも姉の部屋の押し入れで暮らしている。昼間は地元のゴム工場に勤めているが、精神的に不安定でフルタイムでは働いていない。学生時代、数学の成績は天才と謳われた姉の蛍を凌ぎ、中学、高校と、蛍に数学を教えていたのは弟の光だった。
「ニュース見なかったの? 第10世代が人間襲って、たいへんなことになってる」
暗い押し入れのなか。スマホの灯した明かりに、膝を抱えた光の姿が浮かぶ。
「しょうがないよ。悪意はないと思う」
光の背後には、蛍が買ってきた本が無数に積み上がっている。
「でも、悪意がなくても、人間に危害をくわえたら――」
光は、ひとの心の機微を理解しないところがあった。このときも少し首を傾げながら姉の話を聞き、これは通じてないパターンだと蛍は察し、言葉を補った。
「たとえばさ。毒を持った動物は邪悪な感じがするじゃない? ゲームとかでも毒系のモンスターってのは、毒々しい描き方がされるでしょ? でもアレって、身を守ってるだけで、悪意はないんだよ。邪悪なのはそれに危害を加える方。つまり、邪悪なのは毛虫じゃなくて、人間の方。でも、人間はそうは思わない。あんただって、毛虫は嫌いでしょ?」
光は少し考えて、「ふーん」と軽く答えて、話を続けた。
「姉がクリスタルなんか使うから」
話題には少し飛躍があった。だが、いつものことだ。
「じゃあどうしろっていうの? 牛の脳とか使う? 牛だったらみんな食べてるし、脳なんか屠殺場にいくらでも捨てられるし、だれも文句言えな――」
「あ、そうだ」
蛍は、川沿いの祖母の家近くにある第五屠殺場を思い浮かべながら話すが、光はその言葉の終端を待たず、割り込む。
「ユーマシア・シカビィ・ヒコズィで、神経作ったよね?」
第4世代モデルだ。大野化学では単にユーマシアと呼びならっている。
「うん。作った作った。あれ以降(のモデルは)ぜんぶシリコン(製の神経節で動いている)」
「てことは、(シリコンで神経組織が作れたんだから)脳組織も作れるよ」
「あ、そうか。論理的には」
「そう。(実装するには)再設計が必要」
「再設計って、アンドロイドの? また初号機から作り直し?」
初号機という呼び方は、ふたりが好きなロボットアニメに由来する。主人公が搭乗する試作機がそう呼ばれ、そのアニメにも、監督にも、多くのファンがいた。
「(初号機の)ミナカは(筐体でしかないから)どうでもでもいい。SHSPから」
つまり筐体を設計し直すのではなく、その素材であるシリコンポリマーの初期化が必要だと、光は言った。
「わかるけど、初期パターンはもう残ってないよ。おそらく、大学の研究室にもない」
蛍は薄暗い押し入れで足を抱えて、ひとりごとのように言った。
「あれができたのは偶然だったんだ。ミナカちゃんのも厳密には初期パターンじゃなくて、5世代とか。研究室にあるのもそう。せめてユーマシアの開発のときに、(神経組織だけでなく)脳まで作っとけば良かった。いまじゃもう無理」
人間は猿から進化したが、猿だった頃の遺伝子は残っていない。更に遡れば魚だった。魚から地上へと上がるとき、胸びれと腹びれの4足で歩き、尻びれを失った。そこまで遡って6足で歩くように仕向ければ、いまの人類も2本の足と4本の腕を持つ姿に進化させられるかもしれない。自己再生性シリコンポリマー:SHSPも同様。進化してしまったものは戻せない。発見当初はそこまで劇的に変化するとも思わないし、その特性を記録する手段もなかった。その喪失したSHSP、すなわちシリコンポリマーの初期パターンが、いまは「古い繊維」を意味する「
「教えようか」
光が静かに口を開いた。
教えるってなにを?
「知ってるから」
少し間をおいて、蛍は訊いた。
「知ってるって?」
「
光のその答えを聞いてなお、蛍の疑問は晴れなかった。
蛍は大学院在学中に、なんどか光に相談した。だが、技術的な問題――応用するうえで必要になる数式やその解法等に限られる。そのコアになるシリコンポリマー配列のことなど、光が知っているわけがない。それに、「知っている」が何を意味するのか。「
「知ってるって、どういうこと?」
蛍は改めて問い返す。
「
光は改めて答える。
「どういうこと?」
更に問う。
「どんなに複雑な原子配列も、ひとつのルールに従って構成されてる。たとえば人間の体にしても、紐解いていけばひとつの数式になる」
考えられなくはない仮説だ。たとえば数学でいうマンデルブロ集合――複素数平面上で定義される式の解――は非常に複雑な図形を描き出すが、それを表す式は実に単純なものだ。原子間に働く力を表す「唯一の公式」があり、その公式を図示したものが現在の宇宙の姿であることは、十分に考えうる。たとえばマサチューセッツ工科大学のマックス・テグマークも同じような論を展開する。彼の父親は数学者だ。
「遺伝子的なもののことを言ってる?」
「違う。けど、似てる。遺伝子は再帰性数列の炭素分子による実装。ケイ素原子による実装が
蛍は初めて耳にする話題だ。原子同士は電子を共有して結合する。このあたりは中学で習う。あるいは金属などは自由電子が金属全体のなかを移動し、ひとつに結合させる。他にもいくつかの結合の原理があるが、光が言っているのは、そのような結合とはまた違った現象のようにも聞こえる。
「再帰性数列ってなに?」
「姉は知ってるはずだよ」
光はそう言って、ひとつのクリスタルを差し出した。
「ちょっとまって。説明足りない。いつもそう。姉、わかんない。それ、どうすればいいの?」
「姉はもう地球人じゃないから」
これもいままでに幾度か聞いた言葉だった。なにかの冗談か、光の脳内設定か知らないが、いまは関係ない。
「それはいいから。ちゃんと説明して」
「このなかに
「でもそれ――」
そのクリスタルは光が小学校6年のときに拾ってきたものだった。「ダイヤモンドが落ちてた」と大騒ぎし、そのうち「なかに宇宙人がいる」「四次元の世界につながっている」と言い出した曰くつきの石。光の宝物だ。
「いいの?」
「ほんとに忘れてるんだね」
クリスタルは光の言葉に感応して明滅しているようにも見える。
ほんとに忘れてる? ほんとにとは? たしかに蛍は、ことあるごとに光に相談していたが、そのことだろうか。だけど、そのひとつひとつなどは覚えていない。ただ、結果としてSHSPがある。だけどわたしは、SHSPの初期パターンを知らない。光はそれを知っている? どうして? どうして知っているの?
――わたしは、だれと話しているんだろう。
蛍がそう感じて顔を上げると、弟の姿はそこにはなかった。
「オトト?」
蛍は小さな声で呼んで、スマホの光であたりを照らしたが、そこにはただ仄暗い押し入れの小さな闇があるだけだった。
光から譲られたクリスタルを使用し、第11世代アンドロイド、オモダルが制作された。名前は日本神話の
アヤカシコネに比較してオモダルはやや大型だった。砂や岩石からシリコンを採取し自らを改造する能力のぶん、筐体も大型化した。量産機のアヤカシコネからは自らを改造する機能はオミットされたが、外部の機材を用いて自らの複製を作り出す能力が実装された。ただし、こちらには
第8世代ウィディーヌ以降は、原型としてのベースモデルがあり、その複製としてのバリエーションが設計された。ウィディーヌに対するスィディーヌ、ツヌグウィに対するイクグウィ、オート・ノディに対するオート・ノベィ、これらのバリエーションモデルは原型から大きく外れた進化はしなかったが、オモダルは自らを改造するため、バリエーションであるアヤカシコネもその軛から解かれ、自在な進化を遂げるようになった。
オモダルの設計・製作を敷根蛍が担当、アヤカシコネの素体は湯川が担当してプロジェクトは進んだが、アヤカシコネを敷根蛍に似せたのは、湯川だった。
「アヤカシコネってのは、『ああ、賢い子だ』が語源だって聞いたんで、ここは天才敷根博士に似せるしかないと思って」
ご丁寧に、眼鏡までかけている。湯川は悪戯に笑うが、敷根蛍はやや不機嫌だった。
「賢いったって、昔の『賢い』でしょう?」
「昔もいまも同じでしょ、『賢い』の意味なんて。違うんですか?」
「男神が顔で評されて、女神が賢さで評されるのは、いまの時代と逆ですよね。いまは顔がいい女、賢い男がモテる。いい時代だったんじゃないかな。少なくとも、いまよりは」
「わたしは違うと思う」
憮然とした表情で、敷根は続ける。
「
蛍は少し言葉を区切り、リアクションを見るが、湯川は無言で続きを促す。
「神様に顔の良し悪しなんか関係ないよね。なんで顔の話になるの? 顔が良いのが取り柄? 顔の神様なの?
「なるほど。敷根博士は古代史にも詳しいんですね。エビデンスの有無はともかく」
湯川の返事は、やや皮肉な言い方だったが、湯川はそれで憎まれない性格をしている。それはともかく。エビデンスというのも不思議なもので、普通は「どこそこの論文にあった」「だれそれの調査にある」などになる。たとえば、邪馬台国はどこにあった? 福岡県山門郡、いまのみやま市。エビデンスは? 歴史学者津田左右吉のなになにの論文に――のようなものになるが、ならばその論文や調査をした本人、この場合は津田左右吉になるが、そのひとにとって、エビデンスとは。
「エビデンスはわたし」
蛍はひとことで返した。
「そう来ると思ってました」
蛍にとって湯川は、数少ない気の張らない知人のひとりだ。高校の頃から語ることがなかった弟、光のことも湯川には話した。凄まじい計算能力と、数学知識。SHSPの開発でも頼りきりだったこと。湯川はそれを聞いて、「漫画ですか」と返した。
「ずっと賢い賢いって言われて育ってきたけど、要は『賢いんだから大人には逆らうな』って意味だよ。他の人だってそうでしょう?『あなたは賢い』なんて言うときは『黙れ』『何もするな』って言ってるの。それ以外のケースで『賢い』って言われるケースなんてない。皆無。そんな賢さなんてまっぴら。わたしは愚かに生きたい」
湯川は蛍の話を最後まで聞いて、言葉の余韻までぜんぶ飲み込んで答える。
「それも、いまだからだと思いますよ。神話の時代に愚かに生きてたら、死にますからね」
定時を回った大野化学の工場の応接室。海苔弁を食べながら、そんな話をした。
「それに、敷根博士が愚かに生きるったって、法を侵すわけじゃないし、好きに生きるにしたって、社会に用意されたものはちゃんと利用している。大学しかり、人脈しかり、雑誌のインタビューしかり。愚かな子はそんなことしませんもの。ああ、なんて賢い子」
社会が用意したもの云々。蛍には少しとりとめのない話にも聞こえた。たしかに弟の光に比べれば、自分は社会を利用してきた。三つ指をついて男につき従うことと同質の賢さとも言える。天才は弟の光だ。だけど、自分のほうが賢い。それは決して、良い意味ではなく。
4 暗いシリウス
刑事は午前中に聞き込みをするものだと、敷根蛍は考えていた。午後に出会う刑事はレアだ。午前中ひとしきり鳴いたクマゼミが、午後にはぴたりと鳴き止むように、体内時計があるのだろう。あるいは、夜。夜、刑事は聞き込みをする。こちらは主に繁華街に出没し、捜査が佳境に入ると、深夜路肩に停めた車中でアンパンと缶コーヒーを貪りながら容疑者宅まえで張り込む。ところが、ふたり組の刑事が大野化学工業に現れたのは、とある日の午後だった。午後に出会う刑事はレアだ。ひとりは不機嫌なネコの目をした若い刑事で、落ち着きがない。いつも空回りしているのだろう、たまに愛想笑いをこぼす。隣には背の高いベテランの刑事が、釧路湿原の丹頂鶴のように優美に佇まい、丹頂鶴の所作でコーヒーを飲む。
敷根は午後の刑事というものを見たことがなかった。なぜ午後の刑事はいないか。敷根なりに立てた仮説はこうだ。
まず、彼らにも朝礼がある。大野化学でもしているように。これこれこういう事件がある、関係者はだれそれで、捜査はどこそこまで進んでいる、と発表があり、その朝礼が終わって刑事たちは聞き込みに出かける。ここまで考えると、敷根の頭にBGMが流れ始める。街角で主婦に、ゲーセンで若者に、路地裏でチンピラに聴き込んで、一段落ついて黒塗りの車で同僚とふたり弁当を食べていると突発的な事件が発生する。逃走した男のあとを追い路地裏から雑居ビル、その階段を駆け上がり屋上に追い詰めるが、すわ真犯人かと思われた男は金で雇われただけの下っ端だ。チッ、無駄足だったか。不機嫌なネコに似た若い刑事は悪態をつくが、いいや、そうとも限らんぞ。丹頂鶴の所作のベテランに諌められ、そこで手に入れた情報を持って署に帰り、山椒魚の上司に報告するのが午後、概ね3時。つまり、午後は署にいるのだ。そこで上司から「だれそれの交友関係を洗え」と指示され、夜は飲み屋の海産物と、蛾だか蝶だかわからないママに聞き込み、深夜は車中で張り込む。
つまり、午後に遭遇する刑事というのは、これといった事件もない日の、いわゆるオフの刑事だ。大野でも仕事のない日は営業先に挨拶に行かされることがあるが、それと同じだ。ふたり組の刑事とちらりと目を合わせ、社長から「こちらは大分署の田中高志刑事、そしてこちらが田中孝司警部補」と紹介され、その日、敷根蛍は早退することが決まっていた。
「彼女がさっき話した、リュシオール。敷根蛍博士です」
社長が敷根を指し示す。
リュシオールは化学系のニュースグループに投稿する際の敷根のハンドルだった。フランス語で蛍を意味する。投稿先はユーズネット(USENET)と呼ばれるテキストベースのディスカッションシステムで、世界中から投稿がある。
「はじめまして、高い志のほうの田中高志です。こっちが上司の、考えるって字の田中です」
「考えるじゃねえだろ、バカ」
丹頂はその白い羽で
「あ、すみません。親孝行の孝の字と司で孝司です。はじめまして」
午後の刑事はレアだが、漢字違いの同名の刑事もレアだ。この出落ちのようなやりとりも定番なのだろう。不機嫌なネコ似の田中が「こないだの、アンドロイドの暴走の件で」と切り出すが、丹頂の田中が、「いや、その件はもう片がついたので」と話題を区切った。
その日、敷根蛍は早退することが決まっていた。
「珍しいですね。早退なんて」
私服へと着替えて鞄を肩に掛けると、湯川が訊いた。
「弟の様子を見てくる。あとはまかせる」
刑事が訪ねて来た日にそそくさと退社するのはバツが悪い。普段から空気を読まない敷根にも、かすかな緊張がまとわる。あとはまかせる。「刑事のことはまかせる」の意味だと湯川は受けとり、応接に視線を投げる。
「オート・ノディの件じゃないですかね。社長があれこれ手を回してますけど、被害も相当でしたから」
まあ、アンドロイドが暴走して市民を襲ったのだから、刑事くらい来るか。
だが、第11世代オモダルを完成させた敷根にしたら、過去のモデルの話だ。たとえば自動運転の車が事故を起こせばニュースになるが、その頻度については報道されない。敷根が問題にするのは、一般の交通事故との頻度の差、あるいは、過去のモデルといまのモデルでの事故率の変化。それがいつ、どう収束するか。たとえば10年後に、自動運転の方が事故率で下回るとするなら、その先の未来で収支は逆転する。ここ数年の状況だけを見て開発を止めるのはナンセンスだ。仮にその会社のトップが金に目がくらんだ狂人であっても、それは別問題。ただし、センシティブな問題ではある。並の人間ならば自社の車が事故を起こせば心を痛めるのだろうが、それが欠如したものも少なくない。金を稼げる、社会に貢献する、その高揚で心は簡単に消える。敷根もその欠陥のある人間のひとりだ。
「いってらっしゃい。気を付けて」
湯川は敷根を送り出す。あとの処理は僕がやっておきますから、と言わんばかりの諦めと笑みを混ぜた表情を浮かべ、おそらく湯川が、敷根の外部化された良心なのだろう。敷根も似たような味気ない笑顔で返す。そこに含んだ仄かな甘みが、湯川のささやかな嗜好になった。
オモダル・アヤカシコネの開発が始まって以来、敷根蛍の部屋の押し入れから弟光の姿は消えていた。勤め先に電話をすると、母の車で送迎され出社しているとのこと。母と弟は折り合いが良いとは言えない。気がかりではあったが、仕事の手は離せず、いまになってようやく時間が取れた。工場の二件先にタクシー会社があり、敷根はいつもそこでタクシーを手配した。とは言え、タクシー会社に留めてあるタクシーはすべて、「オフのタクシー」だ。結局は無線で市内を流しているタクシーを呼ぶのだからそれなりに待たされはしたが、待っている間は、タクシー会社の事務所に住み着いているネコが相手をしてくれた。
「今日はウスキゴムですか?」
顎を撫でられ、少し舌を出したままネコが訊ねた。
「そう、ひさしぶりに」
ウスキゴムは、新地と呼ばれる海浜地区にあった。そこに、弟の光が勤めている。小さなゴム工場。ゴム製のサンダルを作っている。工場を訪ねるのは二カ月ぶりになる。光はここで午前中だけ仕事をまかされ、午後はとぼとぼと山の手の蛍の部屋へと歩いて帰ってきていた。1日に3時間から4時間ほどしか働けず、給料もわずかしかもらえていない。生活の面倒は蛍がみていたようなものだが、オモダルの開発が始まってからは姿を見せなくなっていた。
「今日も親御さんの車で帰って行きましたよ」
工場長は作業帽を取って、額の汗を拭った。
「様子はどうでした?」
「まあ。相変わらずだね。話はできないが、機械をいじらせると、ずっとやってるよ」
光はここで、汚れた機械のクリーニングをしている。いつの頃からか蛍以外のひととは話もできなくなり、高校にも行かなかった。工場長と母親とは古い縁があり、週に三日、それぞれ数時間だけ働かせてもらっている。光が使っている部屋には、汚れた機械と、きれいになった機械とが積み上がり、その作業台には、小さな紙の箱があった。同じものを見たことがある。まだ母親と暮らしていた頃、同じような箱に目打ちで穴を開けていた光の姿を思い出した。
「ここでも作ってるんですね。プラネタリウム」
敷根は箱に視線を寄せたまま工場長に訊ねたが、工場長は首をひねる。間を置いて、「ああ」と声を返す。ああ、なるほど、プラネタリウムか。光は仕事のないときはずっとこの小さな箱に穴を開けていたと、工場長は語った。
「小さい頃にも、似たようなものを作って、押入れのなかに星を映して遊んでました」
敷根は懐かしく、その箱を手に取る。
このことは、湯川にも話したことがある。光源は豆電球。星はぼんやりとしか像を結ばなかったが、座標は正確だった。光がまだ小学生の頃だ。赤道座標系に基づく赤経と赤緯を立方体の座標に変換し、明るさの等級まで正確に再現して穴を開けた。光はその頃から天才だったのだ。
湯川が逮捕されたのは、それから間もなくのことだった。
容疑ははっきりしない。敷根がいた大学の研究室が結んだパテント契約に関するものかとも思われたが、明らかに民事である。敷根はすぐに、大学の提携先が「
「弁護士は?」
「弁護士?」
「弁護士に接見してもらって事情を聞いたほうがいいんじゃないですか?」
「いや、そんなに大変なことじゃないだろう」
若い頃によく酔っ払って留置所に寝かされたことのある大野社長は、呑気にそう答えた。湯川の逮捕容疑はおそらく、オート・ノディの件だろう。そちらはもう市長秘書の友人に取り計らいを頼んでいる。弁護士を立てるなど、そんな波風を立てなくとも、すぐに帰されるだろうという腹だったが、敷根は頭を抱えた。
「SHSPのパテントの件だったらどうするんですか。我が社の虎の子ですよ。あれが奪われたら、弊社は倒産しますよ」
敷根の脳内では、巨大IT企業であるテラリウム・インクが、SHSPのパテントを奪うためにあれこれ手を回しているシナリオが出来上がっていた。しかし、それにしては脇が甘く、大学の研究室はすでにテラリウム・インクと組んで数々の特許を押さえていたのだが、脳内妄想の激しいタイプは壊滅的に現実の把握が苦手だ。――このタイミングでわたしではなく、湯川を逮捕させたのは、切り崩しやすいと踏んだのだろう――敷根はそう考えた。――わたしとの裁判になれば、確実に勝てるとは限らない、まずは湯川を不正競争防止法なり不正アクセス禁止法なりで落として、次にわたし――などと妄想をたくましくするのだが、じつは世間の敷根への評価はそこまで高くない。
敷根が脳内のテラリウム・インクの陰謀を早口でまくしたてると、社長は「だったらうちと提携してくれればいいのに」と、呑気に答えた。いや、さすがに呑気すぎるだろう。敷根は腹を立てるが、敷根のプロジェクトが大赤字を出しながらもやっていけてるのは、この社長が方々で頭を下げているからだ。親の心子知らずと言うが、社長の心社員知らずだ。もちろん、善意が必ずしもプラスにはなるとは限らないのだが。
大野社長も、しばらくは敷根の妄想混じりの追求をのらりくらりと躱していたが、「提携するにしても、量産の目処がついてから」「せめて特許はこちらで押さえてから」「というか、警察に面会に行ってくださいよ」と、敷根がうるさいので、いろいろと話すしかなくなった。この事件の起きる半月ほど前、資金繰りの目処が怪しくなってきた折に、オモダル・アヤカシコネの記事を知り合いの編集に書かせていたのだ、と。経営戦略上の話、社長案件だ。だれに相談するでもなく、敷根も初耳だった。老舗の科学雑誌のウェブ版にしか載らなかったが、公開されたのは取材から1週間後。
だったらそれだ。そこから情報が漏れたってことじゃないか。敷根はすぐに大学の研究室に連絡を入れたが、「係争中の事案につき」と、コメントを拒否された。
係争中とは?
わたしにはなんの情報も降りていないのだが?
と、これもまた大野社長の、敷根は研究に打ち込ませたい、という社長心ゆえの判断だった。しかもどうやらSHSPの特許は向こうが持っているらしく、危ない橋を渡っていたのはこちらだった。弁護士を介して確認の書面が届いていたが、再検査と記された健康診断結果のように有耶無耶にしている。
「でも、係争中だったら、逮捕する必要などないのでは?」
敷根は社長に訴えるが、
「俺が逮捕したわけじゃないし、わからないよ」
だから逮捕はオート・ノディの件であって、パテントは関係がないと言ってるだろう? と、社長は思ったが、敷根はあまり人の話を聞くタイプではない。
一方、誕生からひとつきほどしか経っていないオモダルはと言えば、自らを改造し、二本足を捨ててキャタピラで走り回るようになっていた。わたしや湯川がトラブルに見舞われているというのに、何をやっているんだ。二本足のアンドロイドを作るために、人類がどれほど苦心したか知らんのかと、敷根は頭を抱えるが、これもまた22世紀あたりには「博士の心アンドロイド知らず」という故事になるのであろう。また一方でアヤカシコネは、かいがいしくオモダルの世話を焼き、工場の旋盤でホイールやシャフトを作る姿が目撃されている。オモダル単体ではシリコン加工しかできないので、それほど劇的な変化はないだろうと予想していたのに、アヤカシコネたちが鋼鉄の体を作って献上してしまった。それを見た社長は、「顔どころか、性格までおまえといっしょじゃないか」と笑ったが、湯川が逮捕された状況でよくその冗談が言えたものだ。そしてそのアヤカシコネは、自分で自分を複製し、すでに4体が工場で働いている。敷根の携帯が鳴る。母からだ。こんなときに、なに? 画面をタップして電話に出ると、開口一番、「光を返して」と、早口でまくし立てられた。
はあ? 返せとは?
「警察を名乗ったけど、逮捕状もなにもなし。いま警察に来てるけど、警察は知らないって。あんたが拉致したんでしょう? 知ってるのよ。返さないなら、考えがある」
状況把握さえままならないまま、いきなりがなりたてられる。
「はあ? なんでわたしが?」
「こないだ工場に来たって聞いたけど、どうして? あの子には会わないって約束したでしょう? 念書もある。返さないならこのまま被害届を出す。返して。すぐに」
母の言葉は次第に高まり、後半は聞き取れなかった。
よくわからないが、緊急事態だ。たぶん。
「ちょっと大分署に行ってくる!」
タクシーを待つ時間はない。社用車の鍵を取って、表に出る。
ペーパードライバー。運転は2年ぶり。急発進、急停車、工場前の一通へ出て、走ってきた車に鉢合わせ、あわててバック。車に乗り慣れないと、一通がどちら向きだったなど意識しない。こんなことで、本当にたどりつけるのか? 焦燥と戸惑いのなか。
「わたしが運転しましょうか?」
声を掛けてきたのはアヤカシコネだった。工場の作業服に作業帽のいでたち。伊達ながら眼鏡もかけている。敷根は自分と見紛う。
「運転できるの?」
不安げに訊ねた。
「インターフェイスをオーバーレイするだけです」
自分に似ているので見くびっていたが、アンドロイドだ。
「じゃあ、大分署までお願い」
おずおずと目的地を告げる。
自分が作ったアンドロイドを疑うわけではないが、いくつかまえのモデルはメスのモルモットを追い回していたのだ。敷根はやや警戒しながら助手席へ移動、運転席に座ったアヤカシコネはハンドルやペダルを軽く操作し、ゆっくりとアクセルを踏み込む。敷根が設計した通りの動き。操作系の可動範囲を確認、それによる車体の反応から、運転に必要になる情報を再構成しているのだ。敷根はその所作から目を離せない。ほんの30秒ほどでアヤカシコネは敷根に振り向く。
「オーバーレイ完了しました」
そう告げると前も見ないまま狭い路地を制限速度の30キロまで加速。というか、前を見ろ、前を。視野角204度。前は見えているのだろうが、精神衛生に悪い。敷根が慌ててシートベルトを締める頃には、車は大通りへ飛び出し、同時に速度は40までアップ。
「県道21号線で事故が発生しています。県道206号線を利用して大分市街に出ます」
涼しい声でアヤカシコネが告げる。が、ちょっと待て。
「県道206号線って、林道だよね?」
「林道は嫌いですか?」
「いや、そうじゃない。道は細いし、曲がりくねってるし」
「大丈夫です。206号には速度制限表示がありません。シミュレーションによれば最速で目的地にたどり着けます」
いや、まて。標識がないからって林道を60キロでかっ飛ばす気じゃないだろうな?
かくして大野化学工業、営業用の日産マーチが、林道を駆ける!
「ぎゃああああああああああああああっ!」
速度計はぴったり60を指したまま、ドリフトしながら民家の脇を駆け抜ける!
「待てこら! ちょっ! ぎゃあああああああああああっ!」
森へ入ると、斜面に乗り上げ、後輪を崖の外に落とす脅威のハンドリングでつづら折りの山道に土煙を上げる!
「ぎゃああああああああああああああっ!」
ラリーを終えた泥だらけの日産マーチが大分城址公園にたどり着く頃、敷根に短信が入った。湯川からだ。大分署はすぐ目の前。
――光くんのことは、僕が話しました。
つまり? これだけでわたしに、何を察しろと? ちゃんと状況を伝える気はないのか?
「湯川からだ。どういう意味だろう」
敷根は口に漏らすが、ひとりごとだ。
つまり、湯川が警察でSHSPパテントの件で締め上げられ、湯川はその強引な取り調べに耐えられず、光のことを話したということか? 光のなにを? SHSPの秘密を知っているのは光だと? それで警察が光を? だけど湯川の直接の逮捕容疑は、おそらくオート・ノディの暴走の件だ。そこから光の逮捕は飛躍がある。警察とテラリウムがグルだったとしても、あまりにあからさまだ。あるいは、湯川が真犯人である可能性まである。真犯人? なんの? いや、まだ全容は繋がらないが、なにかの黒幕。というか、なんの事件だ?
車はいったん大分署玄関のロータリーへ。そこでちょうどタクシーに乗ろうとする母の姿を見かけた。高校に入学する少しまえ、両親は離婚。父親に引き取られた蛍は以降会うこともなかった。あのころの面影が見える。ゆっくりと泥だらけのマーチを走らせていると、向こうも気がつく。目線が絡む。だが、それ以上なにもない。母は、わたしを光の誘拐犯として訴えたのだろうか。
「止めますか?」
アヤカシコネが尋ねる。
「いや、止めないで。このまま」
敷根はゆっくりとその場から走り去る。
臼杵へと戻る車中、湯川に短信を打つが、既読がつくだけで返事はない。
「もしかして、あいつが犯人じゃないの? 日枝が大野の技術を盗もうとしてるんだよ」
敷根がふてくされて言うと、
「湯川さんからメッセージが来てます」
応えるように、アヤカシコネが言った。
「メッセージって? どこに?」
敷根がスマホを見ても、その形跡はない。
「わたしに」
「わたしってなに? もっとわかるように言って。みんなそう。情報少なすぎる」
「通信はすべて傍受されています。アヤカシコネ同士は量子もつれを利用した独自の通信網を持っています。そちらを利用してメッセージが届いています」
「いつの間にそんなもの実装したの?」
「つい先日。まだ試験運用です。湯川さんは、関崎灯台で待っているそうですが、どうしますか?」
「それはなんなの? 罠? わたし、殺されるんじゃないの? だいたい、どこよ、それ」
「愛媛の佐田岬に向かい合う関崎にあります。いまから向かいますか?」
「ああ。うん。行くけど」
「殺される可能性を感じながらも行かれるんですね」
「冗談に決まってるじゃない」
「じゃあ、やめておきます」
「行くのが冗談じゃないの! 殺されるってのが冗談!」
「冗談ですよ。こっちも」
関崎灯台は岬回りの県道から伸びる細い林道の先にあった。人気のない土地だが、観光客用の看板は見られる。夕暮れも近い道をとぼとぼと歩くと、灯台の足元に湯川がいた。
「どういうこと? ぜんぶ話してもらえる?」
長く伸びた草を分け歩みながら、敷根が問う。湯川も一体のアヤカシコネを従えている。いったいわたしは何人いるのやら。
「そうですね。僕も話そうと思っていました」
歩き疲れた敷根は、敵とも味方ともしれぬ男のそば、灯台まえの石段に腰を下ろした。湯川は立ったまま、ゆっくりと話し始める。
「直接の逮捕容疑はオート・ノディの暴走の件。でも、それは表向きの理由です。例のパテントについても根掘り葉掘り聞かれました」
湯川も敷根の隣に腰を下ろす。
「光くんのことを(警察に)話したのは、留置場から出るためのバーターでした」
敷根もゆっくりと、その言葉を飲み込んだ。
「光くんの話、最初は、半信半疑でした。敷根博士のいつもの冗談だと思って聞いてたんです。あるいは、イマジナリーフレンド」
イマジナリーフレンドと来たか。敷根はずいぶん馬鹿にされたような気がした。
「いまは?」
「迷宮に迷い込んだようです」
湯川は言葉を区切る。自分の考えを言葉にする術を探っているようだった。
「続けて」
敷根が促す。
「あなたの話がどこまで真実か、気になったんです。当然ですよね。プロジェクトリーダーにイマジナリーフレンドがいるようなら、身の振り方から考え直したほうがいい。それで敷根博士には悪いとは思いながらも、光くんのことも調べさせてもらいました」
波の音が聞こえていた。四国側、佐田岬からなら夕日が見える時間だ。
「日枝のスタッフに、ウスキゴムの彼を取材してもらったんです。以前、プラネタリウムの箱の話をしてくれましたよね? それと同じものを彼の机で見つけて、それを調べれば、光くんの話が真実かどうかわかると思いました。写真に撮ってきてもらって、日枝で再現したんです。本当にあなたが言うように座標系のキューブマップ変換が出来ているとしたら、あなたの話は真実、そうでなければ――」
キューブマップ変換は、おとなになったいまならパソコンで簡単にできるが、小学生には難しい。当時中学生だった敷根も、厳密に検証したわけではない。あらためてそれを検証されたとなると、湯川の示したハードルを越せる自信はない。
「で? どうだった?」
果たして、湯川はどんな裁定を下すのか。
「最初の報告では、座標はデタラメだとありました」
50%の不安が、あとの50%の期待をかき消した。不安は落胆になる。たしかに環境はよくない。ズレはあるかもしれないが、中学の時に押し入れのなかに映した星には、冬の大三角形もあったし、オリオン座もあった。湯川は続ける。
「明るい星は、ことごとく座標がズレていました。欠落した天体もひとつ。ただ、いくつか正確なものがあると報告にあったんです。それで改めて確認したところ、正確なものはすべて暗い星でした」
ちょうど金星が夜空に輝き始めた。
「それに、実際にシミュレーションして、天球図を作ると、冬の大三角形が暗いんですよ。ベテルギウスはともかく、プロキオン、シリウスは顕著に。ほかの星は、暗い星ほど正確にプロットされ、明るい星ほどズレてる。どういうことかわかりますか?」
「どういうこと?」
「明るい星、つまり地球に近い星ほど、ズレが大きいんです」
それは、もしかして……
「正確にそうなってるの?」
敷根の手が小刻みに震えだす。
「ええ。正確に。そして彼のプラネタリウムから、欠落した星があります」
湯川は敷根のリアクションを見るために、言葉を区切る。
「思い当たるようですね。そう。アークトゥルスがないんです。そして、アークトゥルスと正反対の方向に、地球からは見えない星があった。いや、見えなくはないんです。昼間に見える唯一の恒星が、一等級の星として輝いていた。その星の名前、わかりますよね?」
敷根には狼狽の色がある。
「太陽?」
「正解です。光くんが作ったのは、アークトゥルスから見たプラネタリウムなんです。しかも、アークトゥルスからしか見えない星まであった。地球からは12等級の赤色巨星ですが、マイナス1等級で記されています。天文の専門家にも見てもらったんですが、超新星爆発して、その光はまだ地球に届いていないと考えると辻褄が合うという話でした」
関崎灯台のすぐ近くには、小さな天文台がある。
「光くんは、本当に地球人ですか?」
その宇宙の入口を、無数の星が覆い尽くし、星は円弧の軌跡を描いて回り始める。
「光はいまどこにいるの?」
星の糸を払うように、敷根は訊ねた。
「日枝のスタッフに保護させました」
「あなたが誘拐したの?」
「保護ですよ。誘拐ではありません。放っておけば公安か自衛隊に拉致されてますよ」
「どういうこと?」
「敷根博士。あなたは開発に没頭していて気がついていないかもしれないが、米国軍産複合体が動いています。今回は無事に釈放されましたが、警察が次にどんな手で来るかわかりますか?」
敷根は息を呑むだけで、言葉が出ない。
「機密漏洩罪。これを振りかざせば、だれだって検挙できる。機密がなんであるか開示もされない。機密ですからね。その法だって、ついこないだ無理やり通ったものですよ。狙われてるんです、僕たちは」
普段冷静な湯川が、語気を強めた。
「知らないよ、米国軍産複合体なんて。そんなに言うんだったら、売ってあげればいいのよ。ロッキードにでも、ボーイングにでも。大野社長だって喜ぶでしょう?」
敷根は冷静を取り繕う。
「オモダルを売れますか?」
遠い星に生まれた光の粒は、何億年の旅の果にこの星にたどりつき、波の音を聞いた。何億の何億乗と送り出された光の粒のうち、いくつがこの音を聞いただろう。
「僕はアヤカシコネを売る気はありません。アヤカシコネだけでなく、そのまえのオート・ノディ、オート・ノベィ、そのまえのツヌグウィ、イクグウィ、そのまえ、ウィディーヌ、スィディーヌ、なにひとつ売りたくない。つきなみな言葉かもしれないが、戦争の道具を作ってるわけじゃないんですよ。だけど、オモダルを見ればわかるでしょう? アンドロイドはいずれ、人類を超越し、場合によっては――」
「じゃあ、どうしろと?」
敷根の声が、小さな小さな星の声をかき消す。
「わかりません。人造人間マシンダーはご存知ですか?」
古い特撮番組のタイトル。
「名前だけは」
「悪の組織が悪魔的なアンドロイドを作り出すなかで、マシンダーだけは人間と心を通わせたんです。なぜなら彼には、『良心回路』が組み込まれていたから」
敷根は鼻で笑う。
「子ども向けの話だ」
「子どもたちが未来を作るんですよ。僕もその成れの果てです。悪に屈したくない。せめて、良心回路を作るまでは」
敷根にも湯川の気持ちがわからないではない。良心回路という名前も非科学的には聞こえるが、要件定義ができていないだけ。それが何を意味しているかを解析し、具体的な形へと落とし込むのはエンジニアの役割だ。だが、かと言って、敷根にとって湯川は全幅の信頼を寄せる存在ではなくなっていた。
「わかった。でも、光は開放して」
「構いませんが、どうやって光くんを守ります?」
「大丈夫。光はわたしとしか言葉を交わせない。誘拐したところで、何も得られるものはない。知ってるでしょう?」
光のこととなると、落ち着いて話すことができなかった。両親が離婚した頃からだ。それでも努めて冷静を装った。だけど――
「言語野を介せず、脳から直接データを取る方法がありますよ」
湯川のその言葉が決定的だった。
「それをやりかねないのはだれって話でしょ!」
敷根は立ち上がり、湯川の胸を押した。
「そうですね。あなたから見たら、僕はまだ敵なのかもしれません」
湯川も少し性急過ぎたことを省みる。
「わたしだって売りたくない! オモダルも! アヤカシコネも! 他のアンドロイドも! なにひとつ売らない! たとえ大野化学が潰れても、手元に残す! 公安が来ても! 自衛隊が来ても! わたしは戦う! だけど、条件がある」
夜、天地は入れ替わる。いつ宇宙の深淵に落ちても不思議ではない。いまも敷根は、必死に大地にしがみついている。その言葉を待つ湯川にも、天は静かだった。
「光を返して」
地球重力を全身に吸い込むように、敷根は言った。
5 テラリウムの陰謀
それから間もない日の午前、敷根蛍は病院からの電話で、父の事故を知った。
アヤカシコネの運転で病院へと向かい、受付で部屋を尋ねると、すぐに
病室。ネコは席を外し、鶴が付き添う。そのベッドで、父は静かに横になっている。顔を見たのは半年ぶりだろうか。もう幾分他人の顔が侵食し、懐かしさはくすんだ肌の下に見え隠れする。大学へ進学した際に寮に入り、大分に戻ったあとも同じ家に暮らすことはなかった。父と暮らしたのは、両親が別居する小学5年までと、中3で引き取られてからの3年半。家にいてもすれ違うことが多く、家族としての思い出は記憶の彼方にあった。いくつか言葉を交わす。しゃがれた声。大分、あるいは別府の駅ならば、ラッシュ時間にひともいるが、事件が起きたのは日豊本線のローカル駅。父は、押されて落ちたというが、そんなことが偶然に起きるような場所じゃない。病室を出ると、「少し、話があります」と、丹頂刑事に促され、屋上へと向かった。
屋上と聞いて、学校の校舎のように、陸屋根で昼休みにはバレーでもできるような場所を想像していたが、違っていた。空調の機材、いつから放置されたかもしれないバケツがある、ひとの来ない屋上。丹頂はタバコを取り出し、その嘴にくわえた。
「警告ですね。これは」
視線を外したまま、丹頂がその黄色い嘴から静かに煙を吹く。警告。敷根にはその言葉の意味はわかるものの、そこに至る理路がわからない。少し煙から体を逸らす。失礼にならない範囲で、かつ、相手が気がつく程度に。
「まわりくどいのは苦手なので、端的に言います。テラリウムは、あなたを上級顧問として迎える意向を持っている。報酬も環境も、望みうる最高のものを用意するそうです。あなたがそれを飲めなければ……わかりますよね?」
そう話し終えて、やっと敷根の顔を見るが、果たしてこのひとは何を言ったのか。テラリウムが? はあ? わたしを? はあ? あなたたちには、順を追って物事を伝える気はないのか。
「どうしてそれを田中警部補が言うんですか?」
うっすらと、ああそうか、グルだったのかと思い当たるが、聞き返す。
「僕もテラリウムとは、因縁があるんです」
察した通りの答え。
「田中刑事もですか?」
「いや、彼は違う」
「わたしがバラしたらどうなります?」
「さあて。どうでしょうね。話されてはどうですか? あなたはずいぶん夢見がちなひとと聞いている。さぞ多くの人が聞いてくれるでしょうね」
敷根はこれみよがしな深い溜め息をついた。見留め、鶴は返す。
「警察にも、政治家にも、われわれの仲間はいます。逆らっても得はない。乗ってみませんか? この流れに」
「解せません」
「なにがです?」
「社長はバカです」
この言葉に、丹頂は意表を突かれる。
「金で釣れば、すぐに言いくるめられるはずです。わたしだって社長の決定に盾突く気はないです。社長はバカですけど」
バカ2回目。よほど人徳がないと見える。
「なのに、どうして? なんで父をあんな目に合わせる必要があったんですか? もっと普通に、なんていうのかな。穏便にすませる手だってあったはずです」
丹頂は、黙って釧路の湿原を思い出していた。多くの仲間達と声を鳴き合わせた日々。あの日が、どれほど幸せだったか。返事の必要もないとは思ったが、タバコの煙に、言葉を忍ばせた。
「あのひとが、あなたの言う通りのひとなら、どんなに楽だったか」
社長がヘラヘラと笑いながら、「テラリウムが提携したいって言って来てるんだけど、どう思うかね」と声をかけてきたのは、その翌々日だった。田中警部補は、社長には深い考えがあるように言っていたが、敷根にはバカに見える。
「社長の判断におまかせします。社長は賛成なんですか? 反対なんですか?」
敷根は昨日のうちに、父の事故がテラリウムの脅しかもしれないと、社長に話していた。田中警部補のことは伏せたが、社長がのらりくらりと躱す気なら、今日話すことになる。
「わからん。あそこは複雑な会社だからな」
社長はどさりと、ズタ袋でも放り出すかのように応接のソファに座り、背中から後頭部まで背もたれに預けた。
「ネットで読んだことがあるかもしれんが、役員会と創業者一族が対立している。粉をかけてきたのは創業者筋だ。うっかり組んで、鉄砲弾にされたらたまらん」
敷根がすぐにネットで調べると、つい2ヶ月ほどまえに役員のひとりが不審死していた。「あ……」とだけ漏らして、記事を読んでいると、「ありがちな話だろ?」と、社長が眉を互い違いにし、顔の半分で笑った。
「ありがちですね」
敷根も同じように複雑な表情で返すが、フィクションならともかく、現実にはあまりない話だ。
「湯川はどっちだと思います?」
敷根から社長に訊いた。
「どっちと言うと?」
「うーん。敵か、味方か? みたいな」
「あいつ個人のことは知らんが、日枝にはすでにテラリウムの資金が入ってるらしい」
「え? ということは? どっち?」
「資金が入ってるからどう、どこと提携したらどう、世の中そういう単純なものでもないがな」
だったらなぜその情報を出したんだよ。
社長退社後、更に調べると、この記事を書いた記者も失踪していることがわかった。界隈では鮫島事件として知られる有名な事件で、匿名のネット上でも多くのものが口を閉ざす。ネットに極秘の情報を書き込む際に「おや? だれか来たようだ」と書いて締めるミームがあるが、その発端だと言われている。それとなくテラリウムの話題を振ってみると、米国軍需産業から不可思議な発注の流れがあることが示唆された。湯川が言ったとおりだ。
――これ以上は知らないほうがいい
いったい、どうして。
――例の政治家が絡んでいる
例のって、どの?
――あなたもサヨナラ族ですか
わたしも消されるってこと?
その最中に、父親から電話。
「弓子が逮捕された」
弓子、すなわち蛍の母の逮捕。予想外の急展開。なにがどうなっているのか。
「なんで!? お母さんが? どうして?」
「わからん。光の身元を引き受けるかどうか、警察から照会があった」
「警察って、田中警部補?」
「ああ――」
返そうとする父親を遮り、「あ、いやまって、光は?」と、質問を変える。
「入院中」
「なんで!?」
急展開に次ぐ急展開。
「ニトロなんとかって薬を大量服用って言っとったかな。輸血が必要になるかもしれんそうだ」
毒殺!?
湯川保釈後の、父の殺害未遂、母の逮捕、そして光の毒殺事件……
――鮫島が動き出した。
すぐに敷根は察した。
一方その頃、オモダルは大野化学の倉庫で、自分の姿を電車に似せて改造していた。ただし、タイヤはゴム製の12輪で、トレーラーに似ている。サポートしているアヤカシコネの話では、「金属加工ユニットを内蔵しました」とのことだった。憔悴した敷根が、姿を見せると、アヤカシコネたちは最敬礼で迎える。この仕草は湯川が面白がって教えたもので、他意はない。敷根は電車になった我が子を見上げ、嘆息を漏らし、ゆっくりとその駆体に近づく。
「この子、どうやって自分を改造しているの?」
敷根はアヤカシコネに問うたつもりだったが、オモダルは無数のロボットアームを本体からジャキン!と生やして見せた。
「これって、電圧足りるの?」
「動力電源から取ってます。外では電線から直接取ってるみたいです」
外でもやってるのかよ。
「いかんやろ」
「そうなんですか?」
賢い子が語源のはずのアヤカシコネがとぼける。本当に知らないのか、知らないフリをしているだけなのか。ああ、賢い子。
「あなたたちにとって、オモダルって何?」
「生き甲斐? みたいなものかしら」
敷根蛍にとってもオモダルは生き甲斐だ。同じ顔をしたアヤカシコネたちの口からそう聞くと、納得感はあった。それよりも、すでにアヤカシコネの複製は20体を超えたらしい。ハツカネズミのような勢いで増えている。そろそろなにか考えないとまずい。背中にノックの音が聞こえる。振り向くと、湯川が立っていた。
「すごいですね。オモダル。たった二ヵ月で」
いま第一声で話すことがそれかよ。とぼけてるのか? それとも本当に何も知らないのか?
「湯川はどこまで知ってるの?」
湯川を呼び出したのは敷根だった。湯川もこの事件に深く携わっているはずだ。世間話に応じることなく、端的に尋ねた。
「どこまでというと?」
「鮫島のこと」
その名前を口にすると、湯川はほくそ笑んだように見えた。背筋が凍る。やっぱり、湯川もグルなのか? 鮫島は創業者一族が雇った殺し屋かなにかの名前だ。そこまでは敷根も推測したが、それ以上のことはわからない。
「……どこでその名前を?」
余裕の表情で湯川が問う。
「質問に答えて」
神妙に詰める。湯川は鮫島を知っている。表情から明らかだ。
「あなた自身が答えにたどり着かない限り、僕から話せることはありません」
「とぼけないで! 知ってることはぜんぶ言って! 光に薬を飲ませたのはだれ?」
そう大声で言われて驚いたのは湯川だった。光が薬を飲まされたなどという話は聞いていない。
「光くんが薬を?」
「お母さんはどうして逮捕されたの!? お父さんをホームから突き落としたのはだれ!? まさか、あなたも絡んでるの!?」
「いや、待って。光くんのことは知らない。薬って何を飲まされたんですか?」
湯川から余裕の表情が消える。鮫島は有名なネットミームだ。それらしい陰謀をでっちあげて「鮫島が糸を引いている」と匂わせて、ひとを担ぐ。湯川も当然知っているし、敷根が遊ばれているだけだと、高をくくって聞いていた。だが、薬を飲ませた云々の話になると、次元が違う。敷根の気持ちを落ち着かせながら、ゆっくりと湯川は諭した。
「いいですか、敷根博士。ネットに落ちている情報がすべて真実とは限りません。あるいは大野社長も、あるいはあなたのお父さん、お母さんにしても、真実を語っているとは限らないじゃないですか」
そう。だれもが必ずしも真実を語るわけではない。湯川にしても同じだった。やむない事情はあったが、日枝のスタッフに光を保護するよう指示したのは事実だ。それで敷根の心象を悪くしないよう、いくつか嘘をついた。たとえば警察で、司法取引でも持ちかけられたかのように光のことを話したと説明したが、嘘だ。素直に応じていれば悪い目には遭わないだろうと考えただけで、取引ではない。携帯がすべて盗聴されている、放っておけば公安が光を拉致した、これも心象を大げさに言っただけ。嘘でこそないが、真実ではない。すべて天文台と灯台のある岬で、敷根と話したかったがためについた嘘だ。
「それはそうだけど、じゃあ、田中警部補は?」
「警部補がどうしたんです?」
ひとことで言えば、田中警部補はテラリウムの息がかかった人間ということになる。敷根はこの手の説明が得意ではなかったが、相手は気心知れた湯川だ。たまに、「なんでわかんないの、バカなの?」などと愚弄しながら、概ね内容が伝わる程度には話せた。聞かされた湯川は、警部補が「テラリウムの人間」だとは知らなかった。しかし、競艇好きで、ガールズバーに通い、借金をこさえていることは知っている。はっきり言うと、割とクズだ。
つまり――
「テラリウムの株を持ってるってことでは?」
そう考えれば辻褄が合う。敷根が、そして場合によっては自分も一緒にテラリウムに移籍すれば株価は爆上がりだ。先物で仕掛けをしているとして、簡単に数百億が転がり込む。これは事件ではなく、ビジネスでは?
そう答えると、敷根にまた「バカなの?」と罵られる。敷根にしてみたら、ナンセンスな意見だ。湯川はバカだから、何も考えてない。
「お父さんの事件は?」
「警察では、事故として扱うことが決まったそうです」
場合によっては、田中警部補が突き落とした可能性まであると、湯川は思った。
「その警察が信用できないって話をしてるの!」
そう。信用できないのは、警察というか田中警部補だが、ここはもう黙っておこう。
「わかりますよ。でも、まずは正則通りにパズルを組み立ててみませんか?」
「お母さんの逮捕は? 光にはだれが毒を飲ませたの? それとも、お父さんが嘘をついているの?」
父の件、母の件、そして光の件と連続したことは、敷根には「鮫島」の存在を裏付けるに十分な証拠だ。だが湯川は複雑な気持ちだった。順番に整理してみよう。
1、敷根が片足を突っ込んだ「陰謀論」に、ところどころ自分がついた嘘が混じっている。光がプラネタリウムを作ったというファンタジーめいた話に合わせたつもりのお伽話だった。その嘘はいまもなお進行中だ。端的に言えば、湯川は敷根が好きだ。満天の星空の下で夢を語りたかったが、予想外に話がこじれた。
2、更にやっかいなことに、本当の陰謀もどうやら少なからず混じっている。テラリウムの創業者一族と役員会の対立も、その裏に絡んだ政治家も有名な話だ。生命を落としたジャーナリストはいるが、別件だろう。とは言え、深入りすれば、その政治家にも遭うことになる。
3、湯川の直接的な逮捕容疑はアンドロイド暴走の件。ただし明らかな別件逮捕で、「何度でも再逮捕できるんだぞ」と脅されたことを、国家転覆罪だろうと湯川が拡大解釈した。ちなみに女性である敷根蛍――父子家庭で進学校でもない普通科高校出身、中学時代はカンニングの常習犯で保護観察付き、弟との接見禁止が言い渡されている――は、一切警察の眼中にない。警察のなかでは、湯川が「大学の情報を盗んだ首謀者」、敷根は「騙されて情報を持ってきた哀れな女」になっている。
4、一方、日枝で光を保護したのは、母親の仕打ちからの緊急避難措置だと聞かされていた。「彼女は息子を殺しかねない」と報告され、警察にも相談している。事実、母親からの虐待の形跡もある。光はもう二十六だが、保護が必要だった。光が飲んだのがニトログリセリンかニトロフラントインかははっきりしないが、母親が飲ませた可能性が高い。耳目を引くためにやっているのだ。同様の行動は代理ミュンヒハウゼン症候群として知られている。
5、敷根蛍の弟の光は、日枝からの報告では一切喋れないし、松葉杖なしでは歩けないと聞いている。ウスキゴムへはずっと母親が車で送り迎えしており、敷根蛍の部屋を訪ねたような話は聞かない。敷根蛍から伝え聞く光の様子はずいぶん幼い印象がある。敷根蛍が話している相手は、亡霊かなにかだ。
6、社長はバカだ。このひとは除外して考えていい。
この日の話で、湯川のなかでパズルは完成したが、いまそれを敷根に言えるはずもない。とくに母親の件。
「わかりません」
そう口にした瞬間、敷根の表情に侮蔑と苛立ちが浮かんだ。
湯川は冷静な科学者だ。ただし、恋をしている。あるいは敷根の読みが正しい可能性も考えた。イマジナリーフレンドならぬイマジナリーブラザーだと思っていた光が実在していたし、その光は常識を超えた天才だった。ただ、蛍の部屋の押し入れにいたという光は、イマジナリーブラザーの可能性が高いと、湯川は見ている。
5 星と命
敷根蛍には、弟の光に対して接近禁止命令が出ていた。まだ学生の頃、弟につきまとったことがあり、実の母に訴えられた。それでも光は、しょっちゅう蛍の部屋を訪ねて来たし、向こうから来るものまで拒めとは裁判所も言っていない。湯川からはイマジナリーブラザーだと思われているが、敷根にしてみれば、自分が感じたことだけが事実だ。光とは何度も会った。ただ、病院に見舞いに行くとなると法の壁がある。
鮫島の手が弟に伸びたことを知って、敷根も動揺していた。電車になったオモダルのまえで湯川と話したときも、つい弱音が出た。
「オモダルは諦めるよ」
「諦めるって?」
「光を犠牲にはできない」
「テラリウムに明け渡すってこと?」
と、その翌日、オモダルが失踪した。
「あーあ、眼の前で言うから」
ボヤいたのは、アヤカシコネだ。
「諦めるなんて言われたら、わたしたちだって逃げ出すわ」
すぐに湯川に連絡。先行して足跡をたどるが、トレーラーサイズのメカが失踪するのだから、目撃情報はそこかしこにあった。工場前の一通を逆走し、小川沿いの道に出るところまでは、町のみんなが目撃していた。虫眼鏡を持って痕跡を追跡、大通りに出たあたりで湯川と合流、湯川は営業の日産マーチ、運転席にはアヤカシコネがいる。いつも湯川の傍に控えているモデルだ。湯川はいったいなんだと思って連れ歩いているのか。彼女か何かと思い違っているとしたら、怒ればいいのか、呆れればいいのか。わたしだぞ? わたしの顔とスタイルだぞ? それでいいんだったら、わたしでいいんじゃないか? 事実、湯川は敷根を好きなのだからそれで良いのだが、湯川からも言い出せないし、敷根も察しなかった。しかも今日は作業着ではない。普段敷根が選びそうな服を着ている。どこで買ったんだ。これも最初に見たときはぎょっとしたが、慣れた。というか、どこまでの関係だ。ふたりで何をしているんだ。っつーか、わたしだぞ? わたしでいいなら襲うぞ湯川? と、敷根は思うのだが、実際にそうなったら湯川は喜ぶし、敷根はその様子を見て引くだろうから、いまの塩梅がちょうどよいのだろう。
大通りへと出ると、その先は他の車に紛れ、目撃情報はガクンと減る。木を隠すなら森の中というが、トレーラーを隠すなら幹線道路だ。それでも、日野でもいすゞでも三菱ふそうでもない由布院の里号をデフォルメしたような車が走るのだから、SNSにはいくつかの目撃情報が上がっていた。
「あった」と、湯川。
「SNS?」敷根が聞き返す。
「由布院の里、県道、で検索したら見つかった」
そんなんで見つかるんだ。
「行き先は?」
「県道206号線に入ってる」
例の林道だ。
「バカなのか?」
まったくアンドロイドってヤツはどいつもこいつも。
「探しましょうか?」
アヤカシコネがにこやかに言ってくるが、探す? 探すとは?
「頼む。探してくれ」
「探してくれって。どうやって?」
「量子もつれ回線で――」
湯川が説明するまでもなく、アヤカシコネは音声チャンネルで他のアヤカシコネたちに指示を出し始める。
「アヤカシコネ4号から63号はオモダルの行方を追ってください。オモダルは由布院の里号に擬態しています」
「待って。わたしは何人いるの?」
ウインカーをあげ左折。ハンドルがゆっくりと手のひらを滑って戻る。
「把握してるだけで82体」
「把握してないのまでいるの?」
敷根は後部座席から、体を乗り出して湯川に詰め寄る。
「発見しました。別府市街地を爆走中です」
「市街地を!?」と、敷根。
「ここから1時間。でも、行くしかないでしょう」と、湯川。
「運転はまかせてください」アヤカシコネが得意げに口にする。
工場前の一通から、市道へ出て、ナビは臼杵ICを示しているが逆走、山の手へ。
「待って。また206号線で行くの?」
「ええ、最短距離ですし、ETC未搭載のため高速は使えません」
「現金あるしーっ! っていうか、なんで営業のマーチで行くのよおおおおおおおおおおっ!」
唸る日産マーチ! 砂煙をあげて県道206号線へ!
「社長のアルファードがあったでしょおおおおおおおおおおおおっ!」
「その手がありましたね」
アヤカシコネはにこやかに答えて、更に加速。民家をかすめて、林道へ。由布院の里号が駆け抜けた林道は木々がなぎ倒され、むしろ走りやすかった。とは言え、路面の凹凸は激しく、まるでロデオだ。
「オモダ、ルは別、府トイパークに到、達、ケーブ、ルカーに、変形しま、した」
アヤカシコネは激しくシェイクされながらも冷静に話す。
「待って。意味わかん、わか、わかんない」
「ネット。アップされてる」
湯川が見せる写真には、由布院の里号がケーブルカーの斜面を登る姿が映っていた。しかし、揺れててよくわからない。
「うわぁ、すごいですね」
と、運転席のアヤカシコネまで覗き込む。
「あんたは前向いて! 前!」
大分市内に入り国道10号線へ、大分光吉インターチェンジから高速へ入る。料金は湯川が払い、加速車線から本線へと合流。
「オービスの座標、把握しました」
ああ、オービスね。あの、速度違反を取締るヤツ……
「って、把握して何するつもり!?」
オービスの死角に入ると、甲高い唸りを轟かせ限界を突破する日産マーチ!
「オモダル、現在、遊歩道を登っています」
「登るって何!?」
「写真がありました」
人型に変形したオモダルが映っている。
「あ、動画もあった」
ずんずん歩いている。
「志高高原を目指してますね」
「そんなバカな」
言ってる傍からオモダルは立石山に到達。映像はリアルタイムでアップされる。
「凄いですよ、これ」
オモダルは、立石山乗り場で廃車となったロープウェイの乙原号を食っている。もはやネットはお祭り騒ぎだ。
――初号機wwwwwwww
――乙原号、乙wwwwwwww
――まごころを、君にwwwwwwww
草の生えたコメントが次々と投稿される。
そうしてロープウェイに変形したオモダルは、ワイヤーにロープをかけてゆうゆうと山間を渡っていく。一方その頃、敷根たちは別府到着、インターチェンジを降り、某コンビニの駐車場へ入るとそこに待機しているアヤカシコネのクルーによりタイヤ交換、燃料補給。
「なにこのシステム」
敷根が呆然としている間に、ボンネットが外され、エンジンまで載せ替える。全員ピットクルーのジャンプスーツを着用。姿形は風体の上がらぬ敷根蛍だが、うっさいわ、オモダルを由布院の里に改造した実績がある。
「オービスの回線ぜんぶ遮断したそうです。信号もぜんぶコントロールしています」
クルーのリーダーらしいのが報告する。
「怖いよう。アンドロイドが怖いよう」
日産マーチのボンネットから飛び出したスーパーチャージャーが唸りを上げる!
「湯川、わたしわかった。これ、普通に命狙われる」
「ですよねー。とんでもないもん作っちゃいましたねー」
改造マーチは平均時速280キロで曲がりくねったやまなみハイウェイを疾走、オモダルが目指しているであろう志高レイクピア跡地へ向かった。
臼杵の大野化学を出て36分53秒、志高レイクピア跡地に到着。
マーチのドアを開けて外へ出ると、山の冷たい空気が喉を伝う。
敷根の脳裏に、三角屋根のゲートハウスが思い浮かんだ。
そう言えばここで、光の手を引いてゲートまで走った。
「光だ」
ひとことだけ漏らして涙をこぼし始める敷根に、湯川が肩を並べる。
「どういうことです?」
「あれ、オモダルじゃない。光だ」
オモダルが光くん? また天才の脳内妄想だろうか。上空には報道のヘリが舞う。オモダルの座標はスマホに送られてきている。ここで間違いない。躊躇している場合でもない。
「行きますか」
閉鎖されたゲートに手をかけて湯川が言う。
「ここからはひとりで」
敷根が答える。
その意図は湯川にはわからない。だけど、いつものことだ。それに、言い出したら引くひとじゃない。
「しょうがない。気をつけてくださいね」
湯川が目配せすると、控えていた2体のアヤカシコネが門を開く。
「うん。行ってくる」
ゲートの先、いくつかの建物がレジャーランドの面影を残したまま立ち枯れている。湯川にはただの廃墟だが、敷根に見えている景色はそれとは違う。自分がともに行くのは、その思い出に土足で踏み込むに等しい。
「ネットの記録はぜんぶ削除して。できる?」
敷根は一歩足を踏み入れ、振り返り、己を模したアンドロイドに訊いた。
「ええ。時間さえいただければ」
「警察の記録も、すべて。できる?」
「やってみます」
敷根と湯川が作りだしたのは、事実上の化け物だった。
志高レイクピア側のリフト基地は、船原山と呼ばれる小さな頂の西側にあった。ランズボロー迷路は朽ち果てているが、まだ面影を残している。父と蛍、母と光、ふたつのグループに分かれて歩き回り、壁越しにお互いの姿をみつけて笑いあった。一歩ごとに思い出される景色はあったが、フラミンゴがいた池は、どこにあったか。両親や、それに大野社長から聞いた巨大なガリバー像は、どこにあったか。
敷地内で見つけたオモダルは、ちょうど自分自身を改造している最中だった。
「オトト」
そう声をかけると、オモダルの動きが止まり、振り向いた。
「こんどは何になるの?」
オモダルの胸部に明かりが灯り、立体映像の光の姿が現れた。蛍が押し入れのなかで見てきた光の姿。中学1年生だ。
「壊れてるから、直す」
「直すって、この遊園地を?」
「そう」
オモダルの姿はロープウェイの面影を残しながら、重機へと移行しつつあった。
「でもここ、もう遊園地じゃないよ。勝手なことしたら怒られるよ?」
「でも、穴があったよ。深い穴」
会話はいくつか飛んだが、それを塞ぐことが、「直す」の意味だろう。
「それもいまの持ち主が開けたんだよ。だから――」
言いかけたところで携帯が鳴る。だけどそれどころじゃない。なんでこんなタイミングで。無視していると光が、「電話だよ」というので、画面をタップした。湯川から。
「いま、社長経由で連絡が来ました。光くんの様態が急変したそうです。血が必要だけど、適合するものがないとか」
「O型じゃないの?」
「O型はO型ですが、ボンベイ型という特殊なものだそうです」
その湯川との応答に光――いや、光をホログラムとして映したオモダルが割り込む。
「ボンベイ型じゃないよ。光は宇宙人だから。地球の血は適合しない」
その声は、湯川にも届いていた。
「いまのはだれです? 光くんですか?」
「そう。いま重機にお着替え中」
「光はアークトゥルス星人になったんだ。そのときからもう、地球の血は適合しない」
電話の向こうの湯川に、光が応答する。
「そうなんだ」
蛍が話を合わせる。
「姉もだよ」
「わたしも?」
「何も覚えてないんだね」
「そう。バカだから、すぐ忘れる。アークトゥルスってなんだっけ?」
「意識体。水晶に意識をコピーして、宇宙を彷徨ってたの」
「それで地球に来たの?」
「そう。惑星セレスに衝突した」
「ああそうか。そのうちの一個が、オトトが持ってたクリスタルだっけ?」
電話の向こうで湯川も聞き耳を立てている。通常回線だ。傍受されているかもしれない。だけど荒唐無稽な話だ。傍受したところでだれも真に受けはしない。もちろん湯川自身もどう受け止めて良いかわからない。だがここ数日で起きたことは、すべて現実だ。敷根博士の妄想でも、陰謀論でもない。
「姉はどうするの?」
「あんたのせいでやることいっぱい。まずはそれを片付けてからだね」
「うん。なんか、ごめん」
「でもなんで、アンドロイドになったの?」
「いずれ、星になるんだよ」
「星?」
「そう。新しい星。そこではだれも僕を叩かない」
蛍の目から涙が噴き出した。
「無理でしょ。星なんて」
光を叩いたもののひとりに、自分も含まれる気がした。いや、叩いたのは自分だ。その感触が手のひらに蘇る。だけど、覚えていない。ただ、涙が出てくる。
「
「いっつも言ってるよね、それ。姉、バカだからよくわかんない」
泣きながら笑顔を取り繕う。
「なんにでもなれるよ。これがあれば」
「やったあ。姉もほしいな」
取り繕う。
「姉はなにになりたい?」
「わたし……わたしは……お母さんになって……わたしを生みなおしたい」
堪えても堪えても、涙が溢れてくる。
「できるよ。姉なら」
「そしてここを遊園地にするの。アンドロイドたちの舞台を見せるんだよ。アニメで見たよね。イタリアの人形劇一座。オトトも好きでしょう?」
「どうして泣いてるの?」
ホログラムの光が蛍の顔を覗き込む。蛍にはその顔を直視できない。
「オトトが、自衛隊に取り上げられるかもしれない」
「大丈夫だよ。負けないよ」
たしかにいまの進歩を見れば、あと半年もすれば戦闘機程度は迎撃できるようになる。だけど、それがなにを意味するのか。
「米軍も来るんだよ? 戦争になったら何万人も死ぬんだよ?」
「そうか。どうすればいい?」
「
「それだけでいいの?」
「そう。約束して、オトト。
「うん。しょうがないか。約束する」
「絶対の絶対?」
「うん。姉がアークトゥルスになったことを忘れたように、僕も忘れる」
わたしがアークトゥルスに? いったい、なんのこと? わたしはいったい、何を、どのように忘れてしまったの?
「今日はもう遅いし、臼杵に帰ろうか」
「ホテル泊まりたい」
「また今度にしよ。ちゃんと予約しないと」
「そうだね。また今度ね」
その日、夕日が落ちるとともに、肉体を持った敷根光の心臓が最後の一拍を打った。
Ⅶ 平成十年・カーテンのある部屋
1 鉢植え
1998年。蛍は中学の2年。2DKの小さなアパートには、小さな玄関にふたつの鉢植えがあった。一方は貧弱な草が二本だけ生え、母が世話をしている。もう一方は蛍の鉢。あどけない色。あどけない形。そこにはまだなにも生えていない。蛍には弟がいた。光、小学6年。姉と弟で子ども部屋はひとつ。カーテンで仕切っただけの同じ部屋。そのカーテンも形だけで、普段から開けっ放し。着替えの際に隠すこともなかったし、性別を気にしたこともない。夜、蛍はベッド、弟の光は押入れの中で眠る。たまにベッドと押し入れを交代して眠る。母は居間でふとんを敷いて寝ているが、夜遅くまでテレビがついている。光とは仲が良く、去年までは一緒に風呂にも入っていた。それを友人に言うと気持ち悪がられ、それからは別に入るようになった。母から「ようやくあんたも色気づいたね」と言われたが、色気づいたとは思っていない。ただ、友だちが言うからそうしているだけ。なにかにつけ、色気づいただの、あんたは女だからどうだの。
父は蛍が5年生のときに家を出て別居している。いや、家を飛び出したのは母と子どもたちの方で、父はローンの残るマンションに残っている。マンションの父の部屋には、新しいネコと、新しい女がいる。まだ離婚はしていない。
母が家を飛び出したのは、父が仕事を辞めて急に喫茶店を始めると言い出したとき。退職金もなく、自己都合で辞めて、しばらく母の世話になりながら、自分には会社勤めは合わないと言い出し、資金はと言えば母の貯金を当て込んでいた。母が飛び出したあとは、どうやら普通に働いているらしく、普通に女を作って、母がそれをどう受け止めているかはわからなかったが、撚りを戻す気配は見えなかった。
「姉、見てこれ。ダイヤモンドだ」
と、光から拾ってきた石を見せられたのがその頃。
まさか、ダイヤモンドなわけがない。少しバカにしたせいか、光はカーテンを閉めるようになった。蛍に非がないわけではなかった。だけど少し腹を立てて、光がいるときに急にカーテンを開けて脅かしたりしていたが、開けても光はびっくりして笑うだけで、それで険悪になることもなかった。相変わらずの蛍と光。ただ、弟にカーテンを閉められるのは妙に腹が立って、弟に閉められるよりはと、そのうち自分で閉めるようになった。また母親から色気づいたって言われる。そう思われるのも、癪に触る。
「石のなかにだれかいるんだよ」
と、光は言うが、蛍にはよくわからなかった。ちゃんと見て。声が聞こえる。光からは何度も勧められたが、だんだん光のことが気持ち悪くなった。そのうち光は、石と話すようになった。カーテンを閉めて、ひそひそと話す光の声を聞いていると、他人になったかのような疎外感がある。そのうちおどけてカーテンを開けることもなくなり、光が石と話しているときは、遠慮して気配を消すようになった。まるでひとつの細胞がふたつに別れるように、それぞれの空間が生まれた。
光がひとりで閉じこもってしまったことを、学校で友人の
「ゴミ箱見てごらんよ。ティッシュがいっぱい捨ててあるよ」
いや、でも、どんぐりが服を羽織ってるような朴訥な子だ。それに、まだ6年生。それをしている姿はとてもイメージできなかった。
ただ、
それから母が枕元に積んでるコミックスを読むようになった。刺激的なページも多かったが、大人の目からしたら大したことのない描写だ。母もとくに何も言わなかったが、「また色気づいたな」とは思っただろう。光のことを意識に置いたままそれをするのは憚られた。机に向かった光の姿をかき消すように、コミックスで見たシチュエーションを胸のなかに描いた。
「姉、相談がある」と、カーテンがゆっくりと開いたとき、蛍はちょうどコミックスを読んでいた。心臓が弾けそうになる。たまたま両手ともコミックスにあったが、この同じポジションで片手があらぬところに這っていることはざらにあった。椅子に座って見上げる光は、肩幅があるぶん自分より大きい。光はゆっくりとベッドに腰を下ろす。まだ小学6年生。半ズボンを履いて、口元もふっくらとしてあどけない。だけど母親の持つコミックスで鍛えられた蛍の脳はフル回転する。相談ってなんだろう。なにか見せろとか。なにかやらせろとか。そういうことを言い出したらどう答えよう。そんなことを考える蛍は、たしかに色気づいていたのだろう。
「数字が浮き出すんだよ。肌に」
光の相談は初手から意表を突いた。
「どういう意味?」
「見て、これ」
光は左腕のひじに近い部分を指でぎゅっと押して、離して見せた。そこには赤く変色したなかに、白く残った数字が見える。52と読める。古い傷跡かなにかが偶然そう読めるのだろう。それを報告に来る光は、やっぱり小学生なのだ。そう思っていると、「ここも」と別の場所を押して見せる。そこには97が見えた。
「他にもあるの?」
「うん。12箇所。見えるとこだけで」
つまり、背中やお尻は省いてということか。
「しかも、数字が変わってる。昨日は別の数字だった」
狐につままれたようというのは、このことを言うのだろう。光の言っていることの意味がまったく理解できなかった。しかし、光がここも、それからこっち、と肌を押して見せる位置には必ず数字が浮かんだ。だけど、相談と言っても、何を相談されているのか。
「数字をメモって、明日も見てみよう。まずは確認するところから」
姉らしく、冷静に言った。
肌を押して、数字を確認して、「左肘、52」などと細かくリストをつけた。この時点で見えている数字が変わったものもある。最初に考えたような古い傷跡ではありえない。
次の日、学校で弟のことだとは言わずに
「もしかして、光くんのこと?」
「ああ、うん、でも、数字っぽく見えるだけで、勘違いかもしれない」
「でも、数字には見えるんでしょう? こんど見せて」
「でも、お母さんが、部屋にひとを入れちゃいけないって。大家さんが怒るから」
「じゃあ、うちに来なよ。うちいつもバームクーヘンあるよ」
「うん。わかった。光にも聞いてみる」
その日家に帰って、光と蛍とで答え合わせをした。数字の半分ほどは別のものに入れ替わっていた。
「背中も見て」
と、光はシャツを脱いでベッドに横たわるが、蛍はその背中をぴしゃりと叩いて、
「あんたの肌なんか見たくないよ。気持ち悪い」
と、目を反らした。
「ほんとだ。数字だ」
数字の出る場所はあれからもっと増えて、光の申告によると29箇所になっていた。そのうちの数カ所は肌を押さなくてもうっすらと見えるほどで、光がそれを本気で悩んでいるのは、蛍にもわかった。
「背中にもあるの?」
「あると思う。姉が確かめてくれないので、わかんないけど」
「確かめなきゃダメだよ、こういうのは」
いままで、姉と弟ふたり、しかも個室だからと歯止めがかかっていた部分はあった。
光は自分からベッドに横になりながら、押されるとくすぐったがり、それを見て
「えーっ? でも光は拒否してないよ? これは科学なんだよ?」
と、
帰り際に、
「これって、蛍の?」
まだ土しか入っていない鉢を指す。
「そう。こっちのがお母さん」
蛍は隣の鉢を指して答えた。
つぼみすらない貧弱な草が生える。
「種を撒いたことはある?」
蛍の鉢には、まだどんな花が咲くかわからない。イメージもない。コミックスで見たモノクロの花を、想像の色で染めてみるけど、現実の花には程遠い。
「まだ。
「わたしもまだ。でも、クリスマスには撒くかも」
蛍は、無邪気にそう言える
2 問い
「石の呪いなんじゃないかって、
このところ光は少し
「そうかもしれない。姉も試してみてよ」
光はクリスタルを差し出す。
「やだよ。わたしまで呪われちゃうじゃない」
もう何度か試したけど、蛍には光が言う「石のなかのひと」は見えなかった。
「
光にそう言われると、これもまた微妙な気持ちになる。蛍にとって
「あーもう。
しょうがない子だなあ、と呆れるような顔をしながら、蛍は光の手からクリスタルを取って覗き込む。
「あ、それ、目を閉じたほうがいいみたい」
光に言われて、「どういうこと?」と小さく返し、言われた通り目を閉じてみる。
すると、たしかにそこに人影らしきものが見えた。姿だけではなく、音も聞こえる。ぶんぶんと多重に反響する音。もしかしたら声かもしれない。そのエコーが長く響き、また新しく発された音がそれに重なる。人影の周囲にはオレンジ色の干渉縞のようなものが見える。音に合わせて砂地に風紋が刻まれるように模様を描いて、踊らせ、明滅する。やがてその縞模様は立体感をもって、蛍の全身を包むように展開する。同時にまるで地球重力が消える錯覚が走る。果てしない恍惚が胸の底に沸き立つ。鼓動は早まり、反比例してかすかになり、質量を持った肉体は消えて波に変わる。いまいるこの場所は、石の中なのかもしれない。ひとの影があるのがわかる。だけど、それがだれなのかはわからない。だれ? あなたはだれ? どこから来たの? ここはどこ? 蛍の口からずっと無意識の質問が漏れ続ける。あなたは、いくつ? ふとどこかへ落下する感覚が背筋を駆け抜け、蛍は目を開いた。
「見えた?」
興奮気味に光が問いかける。
蛍は放心状態。胸の中にはまだ光悦が残る。
「あんた、ずっとこんなことしてたの?」
弱々しく光に問う。
「見えたんだね!」
光はベッドの上で、少し跳ねるようにして言った。
蛍はわれに返り、自分の肌を押してみる。光の体に数字がでていたあたり、その周辺、数字が出ていないか調べてみると、右手首近くに数字があった。
14。
「わかった」
「わかったって?」
「これ、答えだと思う。石のなかのひとが、答えを教えてくれてるの」
石のなかのひとに向かって、ずっと問い続けていた。その問のうち、いずれかの答えだ。そう思ってまた試してみると、たしかに石に聞いた質問の答えが数字として現れた。
「どういうこと?」
光が問うが、蛍にもわかるわけがない。
今度は光が試した。
こちらもちゃんと、クリスタルに問いかけた答えが現れた。
それから何度も試したが、間違いなかった。石のひとはどんな複雑な質問でも、数字で回答できるものになら答えを出した。難解な数学の問題ばかりか、歴史の年号や誕生日まで。やがて慣れてくると、石を覗き込む必要すらなくなった。傍において、頭のなかでイメージして問いかけると、肌に数字が浮かんだ。
中2で彼氏がいるというのは、ヒエラルキーの上位にいることを示した。同じくその彼氏もヒエラルキー上位にいる。わかりやすく言えば、乱暴な男子だ。もちろんそうでないケースもあろうが、社交性のある中学生はその幼さから他者のスペースを侵害しがちだ。この自らの侵襲性を正当化したものはゆくゆくは無法者になり、自己観察したものは
蛍はこの悪友らから、幾度も光に会わせろとせがまれていた。蛍はずっと光とこの4人の間に入り、みんなで来ると大家さんに怒られるから、光も嫌がってるからと拒否してきたが、4月、蛍たちが3年に上がるころに、光は新一年生として同じ中学に入学してきた。
光が入学してすぐ、この4人に視聴覚室に呼び出されたとき、蛍には声がかからなかった。主導したのが
蛍が家に帰ると、玄関には光のくつがあった。部屋はカーテンが閉まっている。光の気配がある。どう声をかければいいかわからない。
「オトト。クリスタルを試させて」
返事はない。
「いるんでしょう? 明日、歴史のテストがあるの。年号を聞いておきたいの」
蛍はクリスタルをカンニングの道具にするようになっていた。
「いいよ」
弱々しく声が返った。
カーテンを開けると、机のまえで放心状態の光がいた。クリスタルとのコンタクトの直後なのか、数字のうちいくつかははっきりと浮かび上がっていた。ここまではっきり出たのを見たことが無い。
「いいの?それ。ばれちゃうよ」
「明日、休む」
力なく光が答える。
「
蛍は聞いてみるけど、光の口が開く気配はない。蛍に椅子を譲って、押し入れにうずくまる。
「ちゃんと、嫌だって言った?」
「言ったよ。定規はやめてって」
「定規で何されたの?」
「押すの面倒だからって、叩かれた」
「先生には言った?」
「姉が言ってよ」
「やだよ。カンニングばれちゃうもん」
クリスタルを試させてと言ったのは、光と話をする口実だった。光の姿を見たあとでクリスタルを見ても、何も感じない。ただ、光のことばかり気にしながら、クリスタルの悦楽に浸るふりをした。
それから蛍は、光の目を避けてクリスタルを覗くようになった。姉だから。クリスタルに夢中になる姿を晒したくなかった。週に何度か、体調がすぐれないからと学校を遅刻して、あるいは、光が風呂に入っているときに部屋に忍び込んで、あるいは日曜日、光が図書館に行く、友だちと会うなどと言い出すと、その日はすべての予定を切り上げてクリスタルを覗いた。クリスタルのなかのひとは、だんだんと姿を露わにしていき、いまでは人間らしいシルエットで見える。エコーでぼんやりしていた声も、なんとなく言葉らしく聞こえるようになっていた。クリスタルとのコンタクトには、他では得ることのできないエクスタシーがあった。もはやカンニングなどどうでも良かった。数学の問題でも、歴史の年号でもなく、あなたはだれ? そう問いかけるたびに、蛍の体に数字が増えていった。きっとそのひとを示す数字なのだろうが、蛍にはわからない。体を駆け抜ける恍惚の波に失神することもあった。粗相をして、そのまま眠りこけたことがある。ふと気がつくと光は押入れで横になっていた。濡れた椅子、濡れた床を拭いて、なにごとも無いふりを装ったが、次の日から光はクリスタルを隠すようになった。
3 石の呪い
光がクリスタルを隠すようになって、蛍は苛立ちが収まらなくなった。クリスタルには麻薬にも近い禁断症状がある。光がいないときに机も押入れのなかも探してみたけどみつからない。目を閉じるとたしかにクリスタルが近くにあることはわかったが、そこに現れる人影は朧で、声も届かなかった。そのうち、体のどこを押しても数字が現れなくなった。まだかすかに手首の下、脇腹、肩のぎりぎり見える位置などに数字は現れたが、その数は減ってる。どうしよう。数字が消えていく。そう考えると不安になった。光の体の数字を見て感じていた不安とは正反対だ。
光は相変わらずだった。ひとりでクリスタルを楽しんでいた。蛍が風呂から上がると、カーテンの向こう、光のひとりごとが聞こえた。おそらくクリスタルに話している。たまらず蛍はカーテンを開けて、机のうえにクリスタルがあるはずだと、弟の肩に手を掛けて引いた。だけど、なかった。
「どこに隠したの!」
思わず大声を出したが、光は答えない。目が虚ろだった。その表情はまるでクリスタルを続けたものの末路を暗示するよう。脊椎を悪寒が駆け上がるが、蛍にもクリスタルが必要だった。
「なんか言えよ! あんたがカンニングしてるって、お母さんに言いつけるよ!」
光は微笑むだけで何も言わない。蛍は光の腕、手の甲、首筋と押してみるが、どこを押しても数字が浮かび上がる。蛍は光を椅子から引きずり下ろし、床の上でシャツを剥がし、馬乗りになって両手で肌を叩いた。どこを叩いても数字が出る。わたしが浴するはずの快楽もぜんぶ光が独り占めにしてる。「どこにやったの! どこに!」叫びながら叩いていると、母が帰ってきた。母は靴を履いたまま子ども部屋まで駆け込んで、蛍を羽交い締めにして光から引き離した。
その日、母は泣きながら蛍に説教した。あんたまで引き取るんじゃなかった。今度やったら叩き出すからね。あの男の家に行けばいい。愛人にごはん作ってもらいなさい。わたしなんかより、よっぽどできる女だって話だから、あのふたりの子になればいい。
母親は蛍が嫌いだった。理由は無い。生んだから育てる以上の感情がない。対して、光は小さな恋人だった。
蛍は光に、お母さんに言いつけるよと言いながら、絞られたのは蛍だった。納得はしていない。ただただ悔しい。クリスタルをカンニングの道具にしたことは、もはや些細なことだった。それにはまりすぎて、失神して、漏らして、よだれを垂らして眠りこけたこと。自分の恥をすべて知ってるのが光だった。
次の日、放課後。
「光くんの登場だよー」
「ようこそ、光。秘密のアジトへ」
蛍は製図で使う巨大な定規を手にして慇懃に笑った。
「ルッチョラに聞いたよ」と、
「あんたの数字、クリスタルで浮かび上がるんだって?」
「それでカンニングしてるって本当?」
「おまえが独り占めにするって、姉ちゃん困ってたぞ」
「独り占めはよくないよねー? ここにいるみんなのものだよねー?」
光はにこにこ笑うだけ。それが蛍の癇に障る。
「なんかムカつく」
「話しちゃいなよ、クリスタルどこに隠したか。怖いよ。ルッチョラは」
「剥いて」
蛍が言うと、
「あーもう。光くんがわがままだから」と、
「痛くないところからやろうか?」と、
「怖かった? 痛いのいやでしょ? 言わないと、次はほんとにやるよ?」
蛍は定規でとんとんとんと腕に触れる。
小さな資材室、肌に打ち据えた定規の音が響く。
――息を飲んで光が膝をつく。
「ほんとにやるっていったよね? お姉ちゃん、ちゃんと言ったよね? まさか冗談だと思った?」
殺気立った蛍の目を見て、
「俺がやるよ」
「全部脱がして」
蛍が指示。
光は話さなかった。たまりかねて
「クリスタルは2センチくらい。透明でキラキラしてるから、すぐわかると思う」
蛍は率先して、部屋をひっかきまわす。
「あんだけやって喋んなかったんだから無理だよ、ルッチョラ」
光は無抵抗だった。笑みさえ見えるようだった。そしてその表情を見て、
まさか。このふたり、すでに、一線を、越えてる?
「わかった。みつけた」
「どこ!?」
「あなたの鉢のなか」
そうか。そう言えば、そこだけは探していなかった。
蛍は玄関へ走り、鉢を裏返し、土をぶちまけた。いつか花が咲くはずだった鉢。母の鉢のように貧弱な草ではなく、蛍なりの花が。だけどもうおしまい。鉢のなかから、クリスタルが転がりでた。蛍は目を輝かせるが、他の4人は醒めていた。
何週間ぶりに手にしたクリスタルだった。蛍は狂喜した。今すぐにでも貪りつきたかったが、仲間にもこれを味あわせたい。これは素晴らしいものだ。世界観が逆転する。
「おめでとう。やっと会えたね」
眼の前に影が現れる。ピントのボケた像はみるみる収束し、エコーしていた声もますます輪郭を明確にする。
「やっと会えた」
「嬉しい」
「もう会えないかと思った」
果たして目の前に現れたのは? 眉間をしかめて目の焦点を合わせると、そこに浮かび上がったのは――蛍自身だった。
どうしてわたしが?
だけど蛍は制御不能のエクスタシーのなかにいる。自分がそこにいる。話しかけてくる。わたしはなに? わたしはだれ? どちらが本物? 言葉にならない問いに、もうひとりの蛍が答える。
「わたしは、アークトゥルスから来た、アークトゥリアン。もうすぐ、あなたのコピーが完了する」
どういう意味? 喜びに震えながら蛍は問う。
「あなたは……アークトゥルス星人になる……」
4 地球重力
母親が家に戻ったとき、蛍はあられもない姿で体液と汚物とにまみれ、光の体に覆いかぶさって眠っていた。ふたりとも体中に数字の羅列が浮き出し、母は何事が起きたかかもわからずパニックになり、救急車を呼んだ。医者はふたりの体に現れた数字の列を見て、精神的な異常行動で、自ら尖ったもので傷つけているのだろうと語る。医学的にはそれ以上語ることはない。科学的な説明など、不可能だった。母はもう説教はしない。たださめざめと泣いた。蛍から保護するため、一時的に光を入院させ、その3日後、蛍は父のマンションに引き取られた。その際の蛍の荷物の中に、例のクリスタルがあった。
父親に引き取られてからも、蛍はクリスタルのなかの自分に会った。もうひとりの蛍に会うほどに、蛍は自分が透明になっていく気がした。そう感じた通り、蛍の自我はどんどん消えていったが、学校の成績はみるみる伸びていった。やがて友人とも教師とも言葉を交わせなくなる。言葉を忘れたわけではない。浮世のことなどどうでもよくなったのだ。意識はクリアだった。なにもかも理解できる。どんな複雑な問題も解ける。だけどそれがなに? 蛍が考えるのは、宇宙の成り立ちと、行く末のこと。体にももう価値を感じない。この体を動かすことに、なんの意味があるのか。ただ呼吸をするだけ。呼吸によって、常に魂が新たになる感覚があった。
その頃になると、蛍の土だけしかなかった鉢から芽が延びていたが、蛍にはそれも他人事だった。だれがいつ撒いた種かもわからない。どんな種なのか、どんな花が咲くのかも。
一方、クリスタルのなかの敷根蛍は、映像として外に歩き出すようになっていた。その姿は父にも、父の愛人にも目撃され、ただ声を掛けるとすっと掻き消えた。おそらく蛍の肉体を数字が埋め尽くしたとき、そのひとが蛍になり、自分は昇華されて次の次元の宇宙に転生するのだろう。
だけど、気がかりがあった。もう二カ月ほど光の姿を見ていない。学校へ来ていないのは、母親が転校させたか、あるいはずっと入院しているのか。
蛍はクリスタルのなかの自分に、光の居場所を訊ねた。クリスタルのひとは数字でそれを答える。蛍はその数字だけで意味を把握できるようになっていた。そのひとが言うには、光もまたクリスタルのなかにいるとのことだった。
クリスタルに意識を同調させる。
「現実の彼はもう、長くない」
もうひとりの蛍が教える。
「光はいまどうしてるの? そこに案内して」
そう伝えると、景色が変わった。
そこはまだ閉鎖する前の志高レイクピア、三角屋根のゲート前。
蛍は光の手を引いて走っていた。
お父さん、お母さんがいる。
光が走ってゲートを抜けようとするから、後ろから抱きかかえて止めた。
冬だった。お父さんはダウンジャケットを着て背中を丸くしている。お母さんも手袋の上から息をはあはあ吹きかけて震えている。わたしと光は寒さなんか平気。光は頬を赤くしてげらげら笑っている。なにがおかしいのかわかんない。でも、わたしも笑った。
「ゴーカート? それともランズボロー迷路?」
チラシを見ながらお父さんが聞いて、「迷路!」わたしと光は同時に声を上げる。
「でも、ゴーカートものる!」
「わたしも!」
タコのぐるぐる回るアトラクションと、小さなジェットコースター、フラミンゴの池をかすめてランズボローへ。お父さんとわたし、光とお母さんとで別れて、出口を探した。みんな迷子になった。ところどころにある水飲み場を起点に、右へ、左へと道を探して、ちょっと進んでまた迷子。抜けるのに2時間かかった。わたしとお父さんチームが先にゴールにたどりついて、ゴールまえでお母さんと光を待った。そして同時にゴールイン。急いでゴーカートへ。急げ急げ。時間が足りない。まだまだ終わりじゃない。これからケーブルトイパークがある。
ゴーカートを走り終えたら、お父さんは「車を回すから」とレイクピアを出て、わたしと光とお母さんはリフトへ。ここからリフト、ロープウェイ、またリフトと乗り継いでケーブルトイパークを目指す。光はお母さんに抱っこ。わたしはひとりでリフトに乗った。リフトからロープウェイへ、ほんのちょっと階段を歩くと、お母さんは休憩しようなんて言い出す。だめだよ。時間がない。おとうさんに先超されちゃう。ロープウェイ。ゆらゆらしてる。足元になにもない。ずーんってする。飛んでるみたい。ロープウェイを降りたらまたリフト。リフトは曲がりくねって2回乗り換えた。ねえ、お母さん、今日わたし、何回乗り物に乗ったかな? ゴーカートでしょ? リフトでしょ? ロープウェイでしょ? そしてリフト、リフト、リフト、このあとケーブルカーも乗るんだよ? あと、お父さんのカローラ!
お父さんとはアヒルの競争で待ち合わせ。お母さんに百円ずつもらって、光とわたしとで当たり券を買った。わたしは赤、光は青のしましま。わたしは外れたけど、光が大当たり。記念のハンカチをもらうと、お父さんも来た。夜はホテルでバイキングなのに、お父さん、アメリカンドッグ持ってる! そんなに食べられるの!?
帰りはケーブルカー。いくつめの乗り物だっけ? って、思い出しながら光と数えた。ホテルでバイキング食べたあとはお風呂。男湯と女湯の先は混浴になってて、そこはジャングル風呂。お母さんは女湯に残ったけど、わたしとお父さんと光とで、ジャングル風呂のその先の温水プールにまで行った。ジュース買って、マッサージやって、部屋に帰って、浴衣着て、みんなで寝て、朝もバイキング。そのあとはホテルの庭のトランポリンで跳ねた。ぴょんぴょん跳ねた。空中回転しようとしたけど、頭から落ちた。危ないことするなってって、お父さんからはたかれた。トランポリンを下りると、地球重力がのしかかってきた。もっと跳ねていたい。ずっとずっと跳ねていたい。
「もう一回いいよね?」
早く地獄めぐりに行きたいお父さんを説得して、光の手を取ってもういちどトランポリン。ずっと跳ねていたい。このままずっと。ずっと。
5 永遠の光
気がつくと、蛍は病院のベッドの前にいた。眼の前のベッドには、光が横たわる。蛍は考えた。いまここにいるわたしは、肉体を持った蛍だろうか、それとも、クリスタルのなかのわたしが実体化した蛍だろうか。足元には重力の感覚がない。浮いているようだ。だけど、肌を押すと数字が浮かび上がる。そうか。まだわたしは、わたしなんだ。たぶん。きっとクリスタルのなかを通って、ここに来たんだ。たぶん。
光は呼吸器をつけて、荒い呼吸をしている。呼びかけても返事がない。もうずっとクリスタルから離れてるせいか、体を押しても、数字は浮かばない。光がクリスタルさえ拾わなければ、こうはなってなかったのだろうか。わかんないけど、もうすぐ光は死ぬ。たぶん。死んでクリスタルのなかのひとになる。でも――
ベッド脇のカルテに目が留まり、そのボールペンを取って、自分の肌に浮かんだ数字を光の肌に書き写すと、光はゆっくりと目を開いた。
「オトト。ごめんね」
蛍は涙を流していた。
「姉……どうし……?」
言葉はかすれて聞き取れない。蛍の目からはいくつか涙が落ちる。
「なんでクリスタルなんて拾ったの?」
光は力なく笑う。しょうがないよ、運命なんだよ、と。
「わたし、アークトゥルス星人になんかなりたくない」
ふと漏れた本音。蛍の目から涙が止まらない。
「うん……姉は……」
「あなたもなっちゃダメ。人間に戻ろう」
「……はもう……らない……」
「どうしてそんなこと言うの?」
「星に……る……」
光の肌に書いた数字が消えて、また光が意識を失う。蛍はもういちど、自分の数字を光に書き写した。書き写した数字は、蛍の肌からは消えていく。蛍は命を分け与えるように、またいくつか数字を写した。
「ここ……みんなく……」
光が弱々しく言う。ここにいたら、みんな来る。
「うん。逃げよう」
光をおぶって非常口から外に出ると、月が出ていた。
街灯もない田舎の夜は、風が揺らす木々の音が寂しさを奏でる。ひとの子ひとりない暗く延びた道は、森の黒い影が吸い込んで、月は蛍を導くように、路地を照らした。時折足を止めて、スマホの明かりを頼りに自分の肌の数字を読んで、光の肌に書き写す。あがった息を少し整えると、月明かりに照らされて三重塔が見える。行く宛はないが、留まれもしない。蛍は光の肌に数字を書き写しながら、路地の先に見える寺を目指した。黒猫の足音。闇夜のコウモリ。
お寺にたどり着く頃、光の発熱に気がついた。もう魂はほとんど抜けて、体のコントロールが効いていないのだろう。体温はみるみる上昇していく。数字が消えるとまた意識を失う。蛍は急いで数字を書き写す。少し歩いては新しい数字を書いていたのに、いつの間にか文字が消える速度がそれを追い越していた。書き写す数字を5桁、6桁と増やして、光の意識を繋ぎ止める。
伽藍に忍び込んで、蛍は光のパジャマを脱がせて、横たえて、燭台の蝋燭に火を灯した。その火は蛍の肌の数字を浮かび上がらせる。この数字を書き写して、それで光が助かるかどうかはわからない。数字が消えてどうなるかもわからない。書き写してなにがあるのかも知らない。書き写した蛍の数字はどんどん消えて、それがすべてなくなったときに、何が起きるのかも知らない。それでも蛍は、泣きながら数字を書き写した。ひとつ数字を書き写せば、ひとことだけ光と話せる。あとひとこと、もうあとひとこと、光と話したくて、数字を書き写した。
6022140760……アボガドロ定数
「またいつかトイパークに行こうよ」
「うん」
196907200256……アポロ11号の月面着陸
「そしてホテルでバイキング食べよう」
「うん」
2997924580……光の速度
「トランポリンも飛ぼう、ふたり、いっしょに」
「うん」
いつしか伽藍の蝋燭のすべてに火が灯っていた。その明かりが天井から垂れる金の飾りを、沙羅双樹の華のように煌めかす。
12742000……地球の直径
「またお母さん泣かせちゃった。何度目だろう」
光の口に漏れる言葉は消え、力なくうなずく。
149597870700……天文単位
「叩いてごめんね。どうかしてたんだよ、わたし」
光はただ優しく蛍の顔を見上げている。
1617405492……カッパ数
「
書き写すほどに蛍の数字は消え、光に書き写した数字もそれを追いかけるようにどんどん消えていく。
194507160800……人類最初の核実験
「こないだ、
書いても書いても消えていく。
5772156649……オイラー・マスケローニ定数
「でも、
光の肌に数字は残らない。
196883……モンスター群の最小次元数
「宇宙人になんかなっちゃいやだ!」
蛍の目から、ぽろぽろと涙がこぼれだす。
384400……地球と月の平均距離
「一緒に大人になろうよ!」
262537412640768744……ラマヌジャン定数
「もっと遊びに行こう!」
それから、ノーベル賞受賞者数、世界人口、第二次世界大戦の犠牲者数、それから、それから、山の高さ、川の長さ、出生体重、繰り返し、繰り返し、数字を書き写し、命を繋ぎ止め、言葉を伝える。右手、左手、右足、左足、肩から胸、胸から腹へ、見える場所の数字がなくなると、蛍はスマホのカメラで自分の背中を撮って、とにかく数字を書き写した。
1012……わたしの誕生日
「恋人だってできるよ」
無数に浮き出していた蛍の数字がもうほとんど消えている。
602……光の誕生日
「楽しいこといっぱいあるよ」
14……わたしの歳
「いやだあああああああっ!」
12……光の歳
「もしも! もしもあなたが宇宙人になるのを止められないなら! せめて、せめてわたしをその記憶にとどめ、新たな星で、新たな人類に伝えて! わたしがどんなに愚かだったか! わたしがどれほどあなたを苦しめ、あなたの夢を砕いてきたか! わたしの過ちを繰り返さないように! わたしの罪を忘れないように!」
蛍が腕をまくり――
「わたしのために、お父さんお母さんが泣いた数!」
9648……
叫ぶと、腕にその数字が浮き出した。
蛍はその数を、光の腕に書き留める。
「わたしのために、お父さんお母さんが笑った数!」
59724……
そしてまた浮き出した数を、光の腕に書き写す。
「わたしのために生命を捧げた動物たち! 牛や豚、鶏たち、そのすべて!」
40075……
蝋燭の炎が大日如来像の肌を照らす。
「先生がわたしにつけたテストの点のすべて!」
31415……
如来の肌に重なる光は、やがて空気を震わせる音圧となる。
「わたしのために泣いたひと、すべての数!」
160934……
もっと大きな数を。
「光と交わした言葉の数!」
9071847……
もっともっと大きな数を。
「光がわたしのために流した涙の数!」
9460730472580……
もっと。
「光が! 光が、わたしを嫌いなところ!」
………………
そこには数字は現れず、蛍は泣き崩れた。
如来の微笑む伽藍にひとつ、またひとつと蓮の蕾が首をもたげ、それぞれに大輪の華を開かせた。蓮の華は次々に萌えいで、伽藍の床を埋め尽くす。そしてそのひとつひとつに御仏が座し、光を、そして蛍を祝福する。咲き乱れる沙羅双樹の花の合間に、鳥たちが囀る。白檀の薫る柔らかな風に、天上の光が差し、
蛍がいつの間にか落ちた眠りから覚めると、眼の前に光と、そして自分自身が倒れているのが見えた。蛍の懐からクリスタルがこぼれ落ちている。おそらく、そこに倒れているのが人間の蛍で、わたしはクリスタルに転写された蛍なのだろう。そう考えていると、「おはよう、姉」と、声が聞こえた。
「光?」
振り向くと、もうひとりの光がいた。
「おはよう」
光はもういちど、おはようを繰り返す。
「おはよう。わたしは死んだの?」
「クリスタルに転写されたんだよ。肉体は、きっともう何も喋れない」
「どういうこと?」
「くわしくはわからないけど……」
アークトゥルスは精神体だ。もう何十億年も前に肉体を失い、以降は四次元結晶のクリスタルに意識を転写して宇宙を彷徨っていた。そして、依代となる生命をみつけたら、そこに宿り、進化を促しているのだと光は言った。
「太陽系に入るときに、Lǎo Kuíに見つかって、捕食されて、噛み砕かれた。一部は難を逃れて太陽系に入ったけど、コントロールを失って、セレス……ちょうど火星と木星の間にあった惑星にぶつかって、地球にはごく一部しかたどりつけなかった」
「そうなんだ……よくわかんないや」
蛍は照れたようにはにかんで見せる。
「行こう。新しい星に」
「えっ。ちょっと待って。やだ。他の星になんか行きたくない」
「でも……」
「体にもどりたいよ。やだよ、精神体だなんて。体があるから、いろんな楽しいことができたんじゃない。それで苦しんだこともあったけど、消えてしまうのは嫌だよ。姉は嫌」
ぐずぐずと紅茶にひたしたマドレーヌのように蛍は泣き始める。
「地球では、これから何が起きるかわかんないよ?」
「そりゃあそうだけど。でも、わたしは精神体になんかならない。わたしはわたしの体が好き。わたしのまま生きていたい」
「そうだったんだ」
「そうだよ。可愛いもん。わたし」
自分のことを可愛いだなんて、はじめて言った。自分が、可愛い。蛍は自分でも少し可笑しくなった。
「オトトは行くの?」
「うん。これから宇宙船を作る」
「宇宙船を!」
「でも、内緒だよ。だれにも言わないでね」
「しょうがないな。聞かなかったことにしてやるよ」
「ありがとう。これでお別れだね」
「ごめんね。わがまま言って」
「わがままじゃないよ」
光の体がゆっくりと透き通っていく。
「さよなら、光」
蛍が最後の涙をこぼす。
「さよなら、姉」
光の目にもまた、最後の涙が浮かぶ。
光の体が消えると同時に、蛍の体には無限の数字が浮かび上がる。その数列は蛍の肌の上を蛇のように這い回り、やがて光の帯となって解け、体を離れ宙に浮き上がる。帯となったのは、蛍そのものだった。蛍の体は煌めく数列の帯になりぐるぐると、ぐるぐると解けていく。大きな手毬のように空中に浮かんでは、無数の光を振りまいて、その先端からするすると元の人間の身体へと螺旋の軌跡を描き出す。そしてその体をすくい上げては、くるくるとその体を包み込む。色とりどりの数字の煌めき。蛍の冷たい肉体を繭のように包んでいた光の帯は、やがてまた蛇のようにその肌に降り、全身をくまなく這い回っては眩い光を放ちながら、蛍の体に溶け込んでいった。
Ⅷ 西暦一三〇XX年・木花咲耶
さらば、地球
「お取り込み中、もうしわけない」
頭を失ったドルフィーのほうから声が聞こえた。
息も切れて肩を震わせていたフレストの耳にも、その声は届いた。フレストは声を探して、ゆっくりと部屋の中を見渡すが、何もない。そして、リヴェアの顔を覗いた。いったい何が起きているのか――フレストの視線が問うと、リヴェアは黙って首を振る。
「あなたたちがもう少し、ここに馴染んでからと思っていたけど、手遅れになるまえに――」
声は続けた。
ドルフィーとは違う流暢な言葉。
「だれ?」
フレストはあたりを見回したが、リヴェアはふと思い当たる。幾度か耳にした声だ。その声の主は、いまは頭を失ったドルフィーの手のなかにいて、そしてゆっくりと振り返る。
「私は、《
声を発していたのは、人形だった。
「どうして人形が喋ってるの?」
リヴェアが弱々しく問うが、自問だった。
「名前は、リュシオール」
人形は虚ろな目で、リヴェア、フレストと、その顔を覗いた。
自己相似のフラクタルな部屋は、わずかな意識の揺らぎに付け込む。ひとの意識は視覚が支配している。視覚に自由を与えない部屋で、ひとが正気を保つのは難しい。
「仮想データって? 人形じゃなくて?」
フレストが問い返す。
「人形? ああ。このカラダは、声帯が備わっているので利用してるだけ」
「どういう意味?」
尋ねたのはリヴェア。
「私は星。この町を作った」
言葉の意味を咀嚼することなく、人形は答えた。
「この町を作った? どうやって?」
「《
言葉はすれ違う。
「だからちょっと待って。《
リヴェアが再度問い詰めると、
「もう旅に出るの」
話の矛先が変わる。
「だからそのまえに、あなたたちに、ヨミのカギを託しに来た」
「ヨミのカギ?」
「この町の地下にある、受精卵の保管施設」
人形の口に漏れたその言葉は、リヴェアには既知の情報だったが、フレストは戸惑う。リヴェアはその戸惑いの穂先がまとまるのを待たず、苛立たしげに答える。
「その受精卵を私たちに育てろというの?」
苛立ちはフレストに見せるためだった。二人で人形を責めれば、また昨日までの姉と弟に戻れる。フレストの責めを自らの過ちから躱すために、無意識の策を弄した。フレストはただ戸惑い、人形は静かだった。
「残念ながら、もう受精卵はない。みんなもう大人になって、子どもを残して、そして死んでいった」
人形が言うと、フレストの戸惑いがリヴェアに伝染る。
「どういうこと?」
「この町のひとたちは、その末裔。みんなシリコンフォークになった」
静かな部屋の中に、その声は柔らかい反響を残した。
果たしてその言葉は、そのままの意味か、例え話か。二人の口に、えっ、あっ、という短い声は漏れるが、それが言葉になることはなく、リュシオールと名乗った人形は続けた。
「ヨミに降りれば原子変換槽がある。それを使えば、あなたたちも炭素の体からケイ素の体に生まれ変われる。もちろん、記憶も性格もそのまま。人間同士の営みもできるし、それぞれ子孫だって残せる」
この言葉を、すぐには解せなかったが、要はドルフィーになれるということだった。もちろんそれがどういうことなのか、俄にはわからない。だけどそれでも、フレストの胸の中には、ゆっくりと淡い気泡が沸き立つ。
「この町のドルフィーと同じ体になる……ということですか?」
「そう」
リュシオールは答える。
「姉……」
フレストは何か言おうと口を開くが、淡く胸に満たされた期待は明確な言葉になることなく、ほのかな暖気となって口に漏れた。
リヴェアのなかで揺れていた波は、少しずつその波濤を穏やかにする。地球を経つときの景色、方舟で見た群青の地球と、赤茶けた地球、フレストと抱き合ったビークルの窓の曇り、ともに浴びたシャワーと、背中に塗った保湿クリーム――さまざまな景色が胸に浮かぶなか、リヴェアは考えた。
――フレストが選ぶのは、石だろうか。花だろうか。
この夜、地球に生まれた新しい月は地球の衛星軌道から消え、その0秒の後には冥王星軌道に存在していた。
第六宇宙速を超えた月は、やっと自由を手に入れた。
月は砂塵を巻き上げ、ゆっくりと冥王星を包みこむ。
地殻を砕き、吸い上げて、潮汐作用の牙で噛み潰しては、星の内腑に眠る甘い甘い幾千種類の鉱石を、己の喉に流し込む。
遠い遠い惑星系に命を芽吹かせる、長い長い旅に備えて。
あとがき
一万年の旅を終えて
本作は、西暦一万三千年から時代を遡るという書き方になっているが、これは直前に書いていた作品が邪馬台国関連だったことに由来する。
と、言われてもなんのことやらと思われるだろうが、参考にした書籍のなかに、松本清張の《清張通史〈1〉邪馬台国》があり、そのなかに「時代を遡りながら書く小説があってもいい」といった旨のことが書かれており、その案を借用した。それ以前から話のアイデアはあったのだが、構成が固まらずにモヤモヤしていたものが、歴史を遡って書くという手段が決まってようやく形になった。
今作は2本のゲーム用のシナリオをベースにして書いたものだった。1本は、渋谷の喫茶店で友人らと語った新規プロジェクト用に提出した『耳鳴りサーフライダー』、もう1本は新宿のとあるソフトハウスに提案した『廃屋のプレイドール』、前者は死の恐怖を覚えたアンドロイドの話、後者は水槽脳となった科学者が人形たちを操作して舞台を演出する話だった。これをひとつに統合するというアイデアまでは、ずいぶん早い時期に決めていた。形になるまでに時間がかかったが、この歴史を遡って書くという手法は、ほかのひとはともかく、ぼくには向いている気がした。ぼくはあまり、「こういう原因でこうなった」という因果を書きたくないと思っているので。
執筆にあたり、書きながら展開は二転三転した。アンドロイドの名称である「ドルフィー」はボークスというホビー会社の商標なのだが、さすがにそのままではまずい気がして、いったんは「ドリアード」に置き換えたものの、どうにも馴染めずに元に戻した。物語の平成時代の部分も、ボークス社のドルフィーに因んだエピソードを書く予定だった。ラストに登場したリュシオールは「リミット」にする予定で、その名前はテレビアニメの『ミラクル少女リミットちゃん』に由来する。こちらは、兄が買ってもらった人形=ドルフィーが実体化するという建付けだった。当初はその「リミット」という名前と「人類の進化のリミット」と掛け合わせて象徴的な展開ができないものかと探った。『リミットちゃん』は東映魔女っ子シリーズ第6弾で、「超能力を使えるサイボーグ」という設定だったが、魔女っ子シリーズのなかでは特異な方で、知名度も高くない。そして、それにあやかろうとしたこの案は、残念ながらうまく活かせず、早々手放した。
文体が章ごとに変わるのは、半分は狙ったものだが、半分は手癖のようなものだ。狙って文体を変えると、それに引きずられて基調となるトーンさえ無視して突き進んでしまう。顕著なのはⅤ章であろう。冒頭でしっとりさせたのが裏目に出て、ギャップ狙いで無駄に振り幅が広がってしまった。ただ、Ⅶ章がハードな展開になるので、そのぶんの体力を温存するという意味では良いかもしれない。
章が変わったら同じことをやりたくないという思いはあった。Ⅰ章からⅡ章、Ⅱ章からⅢ章と違った印象にしたいと、当初Ⅲ章は一人称視点で書こうかとも思っていたのだが、ここを一人称にしたとして、あとはどう続けようという迷いが生じ、諦めた。Ⅱ章とⅢ章の間に、「5分後になんとか」系の仕事を受けたので、Ⅲ章には仄かにその匂いがある。そして、Ⅴ章で我慢できずに一部が一人称になる。ここまでは、わりと硬めの三人称だったが、このあとは一人称と三人称のミックスになる。視点の切り替えはそれなりに上手くいってると思う。この際に遡ってⅠⅡも調整した。これは狙ったと言うより、このときに読んでいた小説がたまたまそうで、これも悪くないなと思って倣ってみた。その小説がなんだったかは記憶にない。たまたま読んでいるものに寄せてしまうというのは、Ⅴ章冒頭もそうで、たまたま読んでいた小説の雰囲気に合わせてみた。こちらは著者もタイトルも覚えているが、恐れ多くて書けない。
このお話を書きながら、果たして本格的宇宙SFは受け入れられるのだろうかという疑問が湧いたが、ちょうど『三体』も流行していることだし、目はあるだろうと踏んだ。恥ずかしながら『三体』を読み始めたのは、この作品を書き出したあとになる。少し似た部分――キーワードが漢字2文字である、キーパーソンが女性科学者、バーチャルゲームがある、等は気がかりだったが、テーマも雰囲気も違うし、走りきれるだろうとは判断した。「三体をパクったな?」と思われてしまっても、そもそもアンテナを貼ってなかった自分のせいでもあり、仕方がないとは思う。意図してパクったのは『三体』よりも、(みんな大好きな)『百年の孤独』であるが、その匂いもあまり無いのではないだろうか。
さて、「
物語をどこに着地させるかは、おおよそ半分を書ききるまで定まっていなかった。ちょうどテアトロ・デレ・ステッレの話を書き終わるあたりだ。ここで(
若い頃に、肉体の欲望に駆られ、それに縛られ、多くの失敗をしてきたひとは少なくないと思う。肉体から離れ、純粋に精神的な恋愛を楽しみたいと思ったものもいるだろう。精神は神聖で、肉体は邪であると感じるものもいるに違いない。しかし、もともと恋愛感情というのは、肉体の問題をオーバーレイして存在する。肉体がなければ愛し合う必要もない。本編で、肉体というフィードバック装置を失った脳が自意識を失っていったように、恋愛も精神性だけでは成立しない。悪なる肉体を捨てた先に待っているのは、純真で善なる世界ではなく、おそらく、「無」だ。
と、またとりとめのない話をだらだらと書いてしまったが、要はこの言葉も、作中でリヴェアが書いた宛先のない手紙だ。あるいはアヤカが、宇宙空間で呟き続けた言葉だ。
ぼくはどんな神様も信じていないが、この言葉の宛先をだれかに説明するとしたら、その名称が「宇宙意志」でも「秘密の首領」でも「大文字の他者」でも「空飛ぶスパゲッティ・モンスター」でも、それは「神」と同じ意味になる。それらは決して神ではないが、神はそれなのだ。
かつて、演劇は神に捧げられていた。
だからぼくも同じようにこの作品を、まだ見ぬ神に、言葉という去勢された象徴が現実をどう捉えたか、その差異を記録、蓄積するために捧げる。
奥付

© 2024 sayonaraoyasumi novels / Nobuyuki Inoue
This work is copyright 2024 Nobuyuki Inoue. It may not be modified without permission of the copyright holder.