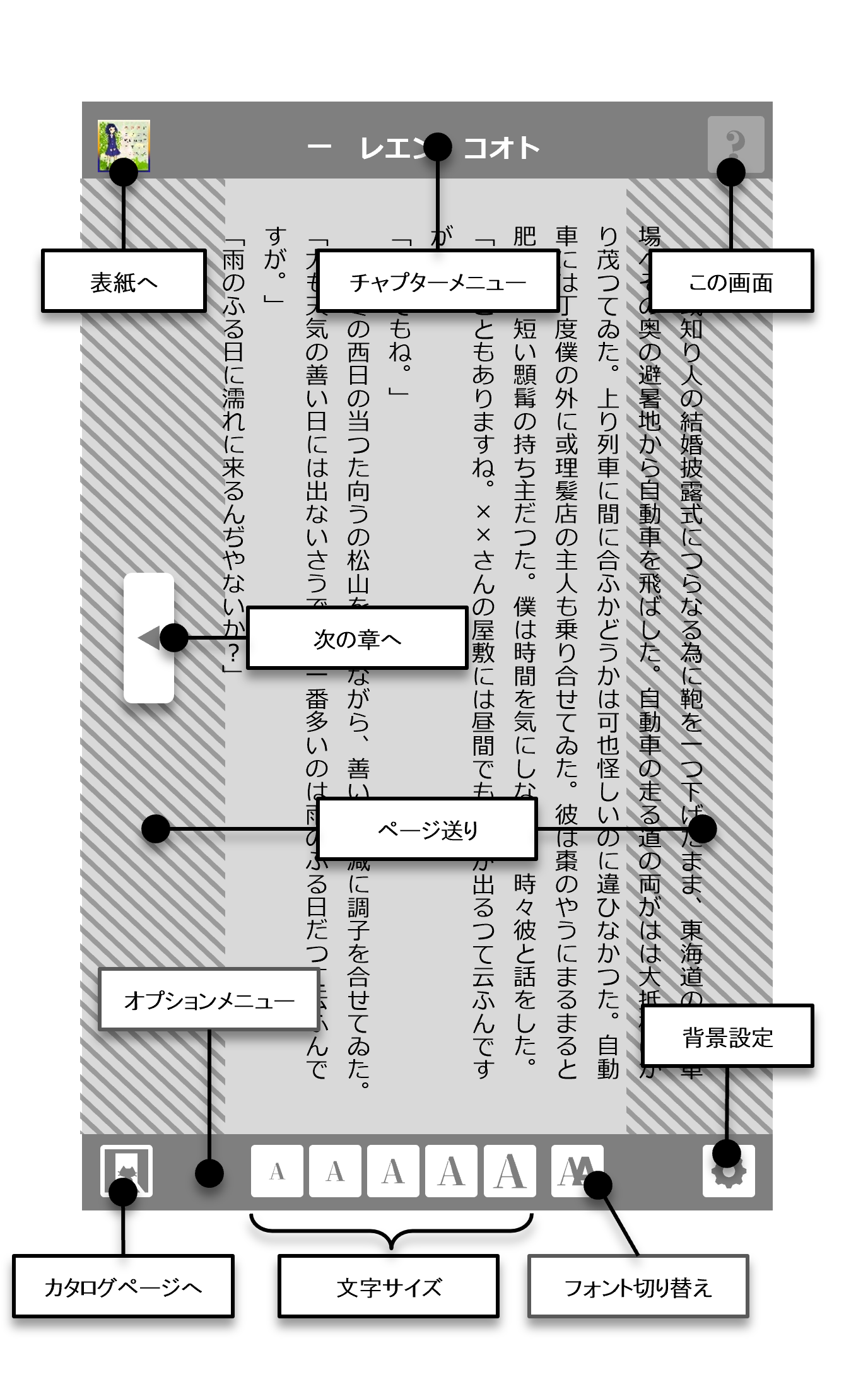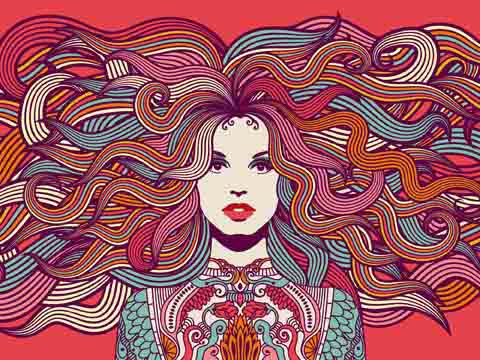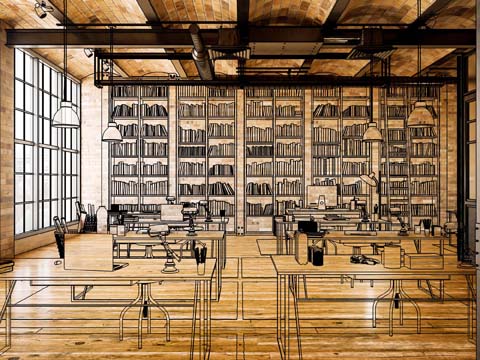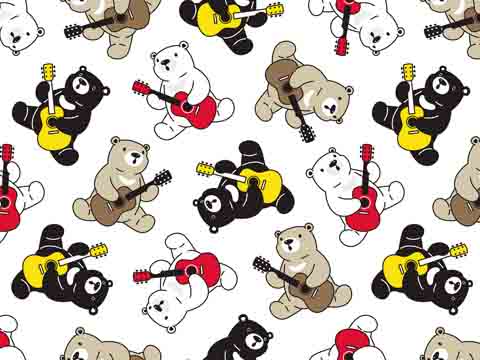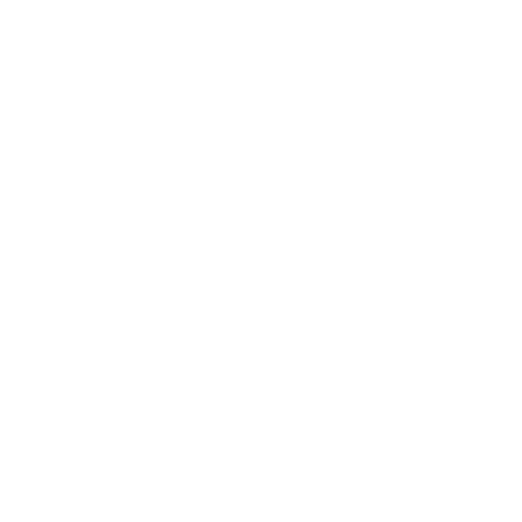
- プロローグ
- 第一部 苅田の実家
- 第二部 大阪での暮らし
- 第三部 栄華之夢
- 第四部 絆
- あとがき
プロローグ
イントロダクション
この物語は、わたし、
とまあ、わたしの話は置いといて、さきほど出てきたなむりんですよ。改めて紹介いたしますと、このひとは、名村英敏というわたしの師匠です。実在します。ここ、大事なところなのでもういちど書きますね。実在します。リアルに存在するひとです。そこそこの歳……もうおっさんというか、お爺さんですね。でもなんか本人がなむりんでいいって言うので、なむりんになっちゃってますけど、タツノコプロってみなさん知ってますか? 古いアニメスタジオなんですけど、そう、『科学忍者隊ガッチャマン』とか、『タイムボカン』とか作ってた。そこでアニメーターをやってたひとです。それからフリーになって、『名探偵コナン』、『ルパン三世』といったテレビシリーズの作監とか演出とかやってたというので、わたしからしたら大先輩、本当なら雲の上のひとですね。いま……2032年4月の時点ではもう引退して、実家近くのヤクザに子飼いにされてるらしいです。それもまあ、わたしのためにそうなってしまったってのもあり……って、そんな話もまあ、さておいて、わたしが言いたいのは、このお話がその、なむりんのお話の続きだということです。だから物語にはなむりん――名村英敏師匠も出てくるし、更にその師匠のまりりん、青木真理子師匠も登場します。ちなみに、まりりんという愛称は彼女の自称ですけど、あのひとなむりんより4つか5つ上だったと思います。いまはもう白髪のお婆ちゃんですけど、20代の頃のまりりんはわたしに似てたって、なむりんが言ってました。要はわたしも原田知世ってひとの若い頃に似ているということらしいです。原田知世っていうのは、古い時代の俳優さんですね。アマゾンプライムで見て、遠くはないかなとは思いましたが、まーなんてゆーか、近くもない感じ。あんなに細くはないし。で、まりりんも実在します。
ちなみになむりんのお話は、昔の知り合いが勝手に本にまとめたらしく、『アニメーターの老後』というタイトルでキンドルで売られています。書いたのはタツノコプロ時代の後輩で、一条一ってなまえでその物語にも登場しますけど、なんでおまえは本名じゃねえんだよって笑いながらピキピキしてました。あろうことか表紙も描いてくれと頼まれたらしいけど、断ったって、まあ、そりゃそうでしょう、と。
まあそっち――『アニメーターの老後』は、なむりんのお話なので、地味で、苦労ばかりで、古めかしくて、それでいて業界歴は長いもんだからだらだら長いというパッとしない物語なんですが、で、そのお話の終盤、わたし、神崎弓との出会い! さて! このひきこもりの原石をどう磨き上げるか! みたいなところで終わっていまして、わたしがこれから語るお話はその続きです。まあ、原石っていうか、石ころみたいなぞんざいな登場でしたね。ここだけの話、すごいお荷物扱いされてるのは、薄々感じてました。
というね。なむりん的には、この物語のタイトルは『続・アニメーターの老後』なんでしょうけど、いやいや。ちょっとまってよ、って話ですよ。もういいよ、昭和の話は。わたしの話をしようよ、わたしの。
だってなむりん、自分のこと語るの下手でしょう?
師匠のこと最高の物語にできるの、わたししかいないんだから、ここはわたしにまかせてよって、運命の導き的なあれで、わたしの出番が来たって感じです。
なんだ、続き物の後半かよ、なんて思わないでくださいね。物語なんて、すべてほかの物語の続き。そしてまたほかの物語につながっていくものなんです。
たしかなことはひとつ。
バトンはいま、わたしの手にある、ってこと。
序
順番として、どこから切り出そうか迷ったんですが、まず話しておきたいと思ったのは、わたし、神崎弓が東京武蔵野市のとあるアニメスタジオの面接を受けたときのことです。
そこはなむりん師匠の先輩たちが中心になって立ち上げた、設立からもう何十年も経つ老舗です。母体となった国分寺のスタジオのなかでも群を抜いた人たちが作った、なむりん師匠もここの仕事を請け負うときは覚悟が必要だったというエリート中のエリートが集うスタジオ。あのころはわたしがそこに入るのが、わたしとなむりん師匠の共通の目的になっていました。
まあ、それまではいろいろとあっち行ったりこっち行ったりはしてるんですけど、目的が定まってからは一直線でしたね。自分でも上達したって実感はあるし、なむりん師匠も「ゆみりんだったら間違いない」とは言ってくれてたんですけど、でも、師匠がひーひー言ってたスタジオですよ? わたしなんかがほんとに? みたいな感じで、ちょー緊張して門を叩きました。門を叩いたっていうか、呼び鈴鳴らしました。ぴんぽーん、ユミだよー、伝説作りにきたよーって。応接室に通されて、そこで映画の予告編2本分くらい待たされて、ようやく面接官のふたりが現れました。初対面で名前はわかりませんでしたが、あとで杉山さんと福田さんの凸凹コンビだと知りました。このふたりがどっちもお茶目で愛らしいことは入社後にわかったんですが、このときはもう、神々のまえですっ転んだ迷える子羊みたいに超絶緊張していましたね。
挨拶して、自己紹介して、3ターン目に杉山さんから例のお決まりの「多くのスタジオの中から当社を選ばれた理由はなんですか?」の質問が出て、もう、例のやつキターって感じですよ。そのとなりで福田さんはペラ数枚の応募書類を眺めて、こんだけかよって、不満そうに口を尖らせてましたけど、これはなむりん師匠の作戦で、応募には5枚しか作品を入れてなかったためです。わたしは、杉山さんからの定番の問に答えました。
「わたしに絵を教えてくれた先生の憧れのスタジオでした。最初からここを受けるのを目指して猛特訓しました」
と、何度も練習してきたセリフです。ところが。
「猛特訓(笑い)」
と、その言葉に受けたのか、杉山さんが笑いながら復唱しました。
わたしは「ほほう、その先生というのは?」と聞き返されるのを期待していたんですけど、猛特訓のほうを拾われてしまって、これは痛恨の作戦ミス。それでも用意した回答を読み上げるしかないと――
「わたしの師匠は国分寺のアニメ技術研究所の出身で、名村英敏さんっていうんですけど、ご存知ですか?」
やや強引に持っていってしまったんですけど、だってしょーがないっしょ。緊張してたんですもん。
「わかんない。聞いたことはあるかもしれない」
と、杉山さんは首をひねり、後ろを通りかかった別の人――西田さんですけど――に、
「なあ、名村って人知ってる?」と尋ね、わたしの方を向いて「アニメーターだよね?」と確認。「そうです。研究所時代は動画のはずです」と返すと、西田さんは少し頭のなかから記憶をたぐりだして、「ああー」と口にしました。なんかこう、人差し指で空中のボタンをピンポンピンポン押しながら、「いたいた、いた気がする、そういえば」と、ピンポンピンポンピンポンピンポン。研究所時代の師匠は、芳しい成績ではなかったというし、そのころの話はあんまり聞きたくなかったんですが、そもそも覚えてるひとがいないという想定外の展開でもう、苦笑するしかないっていうか。でもなんか、このへんで緊張がすーっと抜けていきましたね。
わたしが、「名探偵コナンやルパン三世の演出もしていたみたいです」と言うとやっと、「演出の名村さん!」と、福田さんのほうが思い出してくれました。アニメ業界って系列で分かれてて、コネで知り合いを頼ることも多くて、交わらないひととは本当に交わらないからねー、みたいなことを笑いながら話して、そのどうでもいい談笑が途切れるあたりでおもむろに、「で?」って杉山さん。話題を戻してきました。
「で?」
わたしはスケッチブックを1冊、机の上に置いてたんですけど、それを指さされて、「そちらのスケッチブックは……」って。
もう、きたーっ! って感じです。
緊張は瞬時にピークに達しました。
「これは、師匠がこれだけで勝負しろって言うんで、今回はこれだけ持ってきました」
本当は見せたい絵はいろいろあったんです。でも師匠に言うと、「そういうのは PIXIV の URL 貼って見せたらそれでいい」というので、本当にもう、その1冊だけの勝負でした。
「おお。師匠、厳しいねぇ」
いや、ほんと、マジで。
「でも師匠のお墨付きの自信作なんだ」
ほんっと、マジで緊張しました。心臓飛び出るかってくらい。結果はまあ、あのときのわたしあっての、いまのわたしというか。予想を超えた反応を頂いて、わたしのなかでは超絶照れくさい伝説として全わたしに語り継がれているんですけど、まあ、あの緊張を乗り越えたわたしはもう無敵ですよ。
そこで開いたスケッチブックのことについてはおいおい。最後にばばーん! みたいな感じで公開するとして、突然ですがここで、お知らせがあります。
なんとこの夏、わたしの総作監した映画が公開されるのです。
じゃじゃーん。すごい。すごいですねぇ、わたし。
で、その試写会には3人を招待するつもりです。
今日これからお話するのが、その3人になります。
ひとりはもちろん、なむりん師匠。
もうひとりはなむりん師匠の先生でもあり、わたしもいろいろとお世話になったまりりん師匠――青木真理子先生。
そしてあとひとりは、アリア。
何者だアリア!
どっから出たアリア!
……って言われそうですけど、わたしの姉です。
まあ。いろいろ迷惑かけたんで。
ねえ、アリア。
ようやくデュエットはひとりだちできたよ。
心配ばっかりかけてごめんね。
第一部 苅田の実家
第1章 アリア
姉とは5つ離れてたせいか、そんなに喧嘩することもなかったし、仲のいい姉妹だったと思います。だから、姉が中学進学のお祝いに任天堂のゲーム機を買ってもらったときも、自分に買ってもらったみたいに嬉しかったですし、あれ、だれからだったか忘れたけど、たぶん祖父からだったと思います。進学祝いのはずなのにリビングのテレビに繋いであって、父も自分でゲームを買ってきて遊んでたし、家族のゲーム機みたいな感じになっていました。太鼓の達人とか、ピクミンとか、マリオカートとか。あと、ボーリングと、テニスもやっていた気がします。当然、わたしがいちばん下手でしたけど、わたしがいちばんムキになっていました。いまもそうですね。わたしがいちばんムキになるタイプ。
で、わたしと姉がいちばんはまったゲームが出たのが、その年の夏? ドラゴンクエスト
接続にお金がかかるゲームでしたけど、毎日2時間だけ「キッズタイム」っていう無料で遊べる時間があって、そのときに1時間ずつ交代で遊んでました。そのときの姉のキャラ名がアリア。わたしがデュエット。姉がいない時はキッズタイムを独り占めできましたが、あのころはあんまりひとりでゲームを遊びたいとも思っていませんでした。
で、そのアリア。意味も知らないまま付けたらしいのですが、わたしのキャラも作ろうという段になって初めて意味を調べて、オペラのソロのパートのことだってわかりました。それにちなんでわたしのキャラはデュエットになったわけですど、アリアはウェディっていう海の民の戦士。わたしは森っていうか、和風の国に住んでるエルフの魔法使いでした。
でもあのころたしか7歳? あるいは8歳くらいだったと思います。町の外に出るとモンスターがいて怖かったので、だんだんデュエットで遊ぶことはなくなっていきました。姉のアリアを後ろで見てるのが好きで、クラスメイトとチャットしながらボスを倒しに行ったときも、わたしは隣ではしゃいで見ているだけでした。姉も、その友だちもみんな強くて、憧れていました。「ユミも戦ってみなよ」と、よくコントローラーを握らされて、「まずはレベルを上げよう」などと言って町の外に出されたりもしましたが、たびたび死んじゃって――最初に死んだとき、泣いちゃいましたもん。
姉からは「死んでも教会で生き返れるから」と言われましたが、「死ぬ」って言われるのが、すんごい怖くて。夜寝るときもずっとそれが頭から離れませんでした。
でも、RPGってなりきって遊ぶものだから、それが正しいのだと思います。「教会で生き返れるから」とか言って死の恐怖を感じなくなったら、それはもうリアルな体験ではないのではないでしょうか。
という臆病なわたしでしたが、ドラクエXでは、七夕とかバレンタインとかに合わせて、町の中だけで遊ぶイベントが催されることがあって、そのときはわたしもコントローラーを争いました。で、そのころになると、アリアにはアストルティア――ドラゴンクエストのなかの世界――に彼氏みたいなひとがいたみたいです。それでだんだんコントローラーを渡してくれなくなってっいったんですけど、その彼氏みたいなひと、クラスメイトだったんだと思います。男子か女子かは知らないけど、アリアと同じ海の民で、男キャラで、同じ戦士でした。あのころのわたしからしたら大人の世界です。中間考査がどうのこうのって話してるのも、すごく意味深に聞こえて、ドキドキしました。小学校2年生の終わりころです。中学生にもなったら男子とキスくらいするのかと思ってました。そういうの、漫画で覚えるんですよね。遠い将来のこと、ってのはわかるんですが、わたしにとって5つ上の姉はもう、遠い将来にいましたから。
それで、「ちゅうかんこうさってなに?」って聞いたら、「うるさい」って。
うわーって思いましたね。その言葉になんかすごい聞いちゃいけない秘密があるのかーって。でもいまにして思えば、成績が悪かったんだと思います。まあ、ゲームばっかりやってましたから、それはそうですよね。
わたしも学校で、だれかドラクエXやってる子いないかなと思って探したんですけど、それがたぶん、池田、後述、が絡んでくるようになったきっかけだと思います。あいつはわたしが楽しそうにゲームの話をするのが気に入らなかったんじゃないでしょうか。わたしがヒューザってキャラがかっこいいって言うと、「ヒューザのまねしまーす」とか言って、よぼよぼのジジィが戦うような仕草をしてみせました。まあ、いまでも絶対殺すリストの筆頭ですよ、池田。そういうの、気にしなきゃいいのでしょうけど、なんか妙に腹が立って、つい言い返してました。だって。なんかムカつくし。
「じゃあどこがおもしろいのかちゃんと説明しろよ」
「ネルゲルっていう、すごい強い敵が出てきて――」
「はーい、ネルゲルのマネしまーす。ようきたのう勇者よ、うぇふぇふぇふぇふぇ」
って、気にするしないじゃなくて、ほんと、腹が立ちました。池田。もう、ほんとクソ。死ねよ。家族ともども3回死ね。
絵を描くようになったのもこのころですね。最初に描いたのはご存知、スライムです。次はドラキーだったと思います、キメラやナスビナーラも描けました。人型のキャラに関しては、自分のキャラ、エルフのデュエットを見ながら描いたのを覚えています。キッズタイムは2時間で、そのうちの半分、わたしの持ち時間をいっぱい使って、テレビに映した自分のキャラの絵を描きました。
ひきこもり時代、なむりん師匠に会ったころは何も見ないで描くのが「ホンモノ」だって思いこんでましたけど、こうやって追っていくと、わたしも模写からはいってはいたんですね。
ネットでトレパク疑惑みたいなことをよく言われてるじゃないですか。トレースして描くのはパクリだ、みたいな。それで一時期は、意地でもなにも見ないで描くってのが信条だったんですけど、なむりん師匠から「まずはトレースして覚えろ」って言われて、そこからですよね。わたしの画力が伸びたって言えるのは。あのとき、トレースしろって言われて、もしかしたら匙を投げられたのかもしれないと思って、まりりん師匠にも相談したんです。そうしたらまりりん師匠の意見も同じでした。まずはトレースしろ、って。いや、もう、意外でした。トレースそんなに大事か! 最初に聞いておけばよかった! って。
で、わたしが絵を描いてると、やっぱり池田がちょっかい出してくるんです。わたしのスライム見て、うんこスライムだって笑って、ほかの男子もそれ聞いてみんなでうんこスライムって囃す。何度か泣いたけど、泣くのも悔しくて、隠れて泣いてました。
屁こき虫って言われたのも、あのころですね。池田はわたしのこと臭い臭いって言うけど、自分じゃわかんなかったし、「わたしじゃない」って言い返してました。最初はだれかがオナラをしたのをわたしのせいにされてるんだと思ってましたし、体臭のことを言ってるって気がついてからは、長めにお風呂に入って、しっかり洗うように気をつけて、だから臭いのはわたしじゃないって言い返してました。
このころの記憶は、どれが先でどれが後だったか、いまいち混沌としているんですけど、いずれにしてもアリアとデュエットの冒険は、そう長続きはしなくて、姉の高校受験が始まるころにはコントローラーを握ることもほとんどなくなっていました。姉が中3だから、わたしが小学4年生のころですね。まだひきこもるまえ。わたしも学校でKARAとかきゃりーぱみゅぱみゅとか歌う子でした。
中学に入ると、いちばん仲が良かった子と別のクラスになって、ほとんどひとと話さなくなりました。こういうとき、友だちが少ないと不利ですよね。というか、友だちが多い子って、どこに行っても友だちちゃんと作るんです。わたしは別に友だちなんてどうでもいいとは思ってたけど、でも、敵じゃないって思えるひとは欲しいと思ってました。
ふつうのひとからしたら、敵だなんて大げさだって思うかもしれませんが、そういう子とわたしの見てきた世界は違うんだと思います。そんな子は可愛くて、身なりもきれいで、喋りだってスマートなんです。誰からもいじめられず、ちやほやされて、環境が変わってもすぐ友だちができる。わたしからしたら、それだけでもう選ばれし者たちですよ。教室で絵を描いてて、男子が覗いてきても隠す必要なんてないんでしょう?
みんながみんなお互いのこと知らない同士なら、まだ良かったと思うんですけど、そうじゃないじゃないですか。仲良く語りあってるひとはいて、自分もその輪に入んなきゃいけないようなプレッシャーとか、入ってもどうせ馴染めないんだよなっていう諦めとかいろいろで、あと、池田と仲がいいやつとは話したくなかったし。まあ、中学では池田は隣のクラスだったんで、まだましだったかな。
入学式のあと、席につくと、まえの席の尾花さんが話しかけてきました。彼女はとてもいい子で、人付き合いの垣根も低くて話しやすかったんですけど、でもちょっと苦手でした。会話するときのインターフェイスが大きいっていうか、画面いっぱいの巨大なカーソルでぐりぐりされてる感が、わたしにはちょっと。お話の内容はべつになんともないんですけど、まずはお通し、出身校を聞いて、「じゃあ、だれとかさんといっしょだ」「◯◯って子が転校して来なかった?」みたいな話をして、話題は過去から現代へ、「わたしは卓球部に入るつもりだけど、神崎さんはどんなことが好き?」って聞いてきて、わたしはそのころマリオカートってゲームにはまってましたから、ゲームって答えちゃったんですけど、それがあとあとちょっと面倒なことにはなったかなと思います。まあ、面倒ってほどでもないんですけど、あんまり家に友だちを招いたりすることもなかったから、「じゃあ遊びにいってもいい?」って聞かれてちょっと戸惑いました。出会って最初の会話ですよ? このカーソルの巨大さ、わかります? 1クリックのダメージ。
マリオカートの面白さを熱弁しちゃったから、まあ、流れとしては当然そうなるんでしょうけど、うちに帰って母に週末に友だちが遊びに来るって言ったら、それを口実に居間の掃除をさせられるし、当日は尾花さんだけでなく、ほかにもふたり連れてきて、しかも自分の部屋で遊べるならともかく、ゲーム機は居間でしょう? 普段父が座ってる席に尾花さんが座って、その後ろを中野さんがコップ持ったまま立ってまたいでるときの、なんとも言えない不安感。言葉にできないけど、なんか不安。その間、姉は自室に籠もりっきり。父は朝からとっとと追い出してたから良かったんですけど、わたしたちが居間でマリオカートをやってる間、母はわたしの部屋でネットを見てるって言うから、それもまた不安。そのときつくずく思いました。ゲームは小学生までだ、って。中学生になってゲーム――とくに居間のゲーム機なんか独占したら邪魔でしょうがないです。――とは言え、わたしと姉のドラゴンクエストはその年の11月までは続くんですけどね。
学校ではそれから、ゲームの話はあんまりしなくなりました。とくにドラゴンクエストのこと。またバカにされたりしたら嫌だったので、語らないようにしてたし、まわりからたまにドラゴンクエスト・シアトリズム(ドラゴンクエストのキャラを使ったリズムゲームです)がどうのって言葉が聞こえても食いつかないようにしていました。それに、ちょうど任天堂の新型のゲーム機の発売直後で、旧型のゲーム機(しかも新型のWiiUでもなくて、ただのWii)で遊んでるのが少しコンプレックスだったのも事実です。姉も高3で受験生だったし、夏にリリース予定の拡張パックをクリアしたらドラクエももう辞めるって言っていました。まあ、次のバージョンからはもう旧型のWiiでは遊べないって噂を聞いていたので、引き際だったんだと思います。中学に入って、新しい生活が始まるというのに、なにかひとつの時代の終わりのような気がしていたのは、ひとえにこのせいなのだと思います。
ひきこもりの原因ってひとそれぞれだといいますけど、わたしの場合はこうやってだんだんと現実が意味を失ってったからなんじゃないかと思います。ゲームの世界から帰ってこれなかったわけではないと思うんです。わたしのドラクエXのプレイ時間なんて可愛いもんでしたし、姉の後ろで見てた時間のほうがはるかに長かったわけですから。
で、その姉は、人生でいちばん大事な夏を、ナドラガ神との戦いに費やして溶かしていました。
「マリーヌが何だというのだぁぁぁっざっぱーーーーん!」
「うっせーわ! さっさと死ねーっ!」
という戦いを何度見たかわかりません。まさにドラクエ三昧の夏でした。姉は、受験する大学も決まって、塾にも通っていたんですが、勝負の夏、キッズタイムの2時間だけはジャージのまま居間に降りてきてドラクエをやっていました。わたしもその時間が楽しみで、外で遊んでいても、部屋にいても、その時間だけは居間に飛んで帰っていました。
とは言え、キッズタイムの1日2時間でしょう? そんなのは受験勉強の息抜きとして、必要な時間じゃない? などと思われるかもしれませんが、甘いです。姉は生粋のバカです。
キッズタイムのみでナドラガ神を倒すのには綿密な計画が必要でした。「パッシブ」と言われるスキルを取得しないといけないし、能力を強化するための「宝珠」も集めなければいけません。姉はスマホで調べた情報をびっしりメモして、キッズタイムが始まったら速攻で「元気玉」をもらい、酒場で仲間を厳選し、オススメの狩り場へと走ってはレベル上げに勤しみ、メモを参考にしながら宝珠を取るためにひたすら狩りを続けていました。そのときの姉のメモを見る限り、わたしには姉が受験勉強をしているなどとても信じられませんでした。
クラスに絵が得意そうな男子がいることにも気が付きました。
ハギが絵を描いているのは、仲の良い子が覗き込んではちやほやしていたのですぐにわかりました。女子同士でも絵を描いて見せあってる子たちはいたけど、男子よりは少なかったように思います。目立ったことをするとすぐに男子がからかいに来るし、あまり大っぴらにはしたくなかったってゆーか、ノートに描く絵っていうのは大好きなキャラなので、それをいじられたくもないし、警戒心がありました。そのときにちゃんと抗弁できるか、できないかが男女の差なのではないでしょうか。究極的には暴力という手段を持つ男子に対して、女子は遠慮せざるを得ない立場にいたと思います。ハギは漫画かアニメのキャラを描いているのかと思ったら、クラスメイトの似顔絵をよく描いていて、それがまたよく本人の特徴を捉えていて、たしかにこれはちやほやされるわと思ったものです。アニメや漫画の絵が得意な子はほかにもいたのですが、そのなかでもハギは特別で、中1のわたしの目から見たら、なかにプロの絵描きが入ってるかのようでした。わたしが美術部に入ったのは、おそらくハギの影響だと思います。
美術部ってのも、正直良くわからなくて、躊躇はしました。小学校のころ美術の成績が良かったかというと、決してそうではないんです。絵ってやっぱりちょっと高尚なところがあって、真面目に形を取って、しっかりと仕上げられるひとが市展とか県展とかでも選ばれるし、わたしには遠い世界だと思っていました。写生でもわたし、空ばっかり描いてましたから。校内で好きなもの描けって言われると、いかに空を広く取れるかを基本にして場所を選んでました。中庭から校舎を見ると、なんだかよくわからない煙突みたいなとこがあって、そこだと半分以上は空を描けて、もうここしかないみたいな感じで。で、美術部っていうのは、そうじゃないひとがいくところ。渡り廊下のまっすぐな柱がパースつけて並んでるようなところで、柱とその向こうの校舎の窓ガラスを丁寧に塗り分けるのが美術部。構造物が画面に入ると、4本柱があるはずなのに、なぜか3本しか入らないとか、右と左とで柱の太さが違うとか、めんどくさいことばっかり想像してしまうんですけど、それを考えないひとがいるのが不思議でした。美術部はまぁ、乗り越えるんでしょうけど、逆にすべてなぎ倒していくひともいて、そっちはまたそっちで――いや、どちらかと言えばそっちのほうが更に不思議でしたね。その究極は松田さんですよ。「わたし、グラジオラスが好きだからここでいい」とか言って座ったとこ、目の前が自転車置き場なんですよ。「ここだと自転車も入るけど、いいの?」って聞くと、「自転車も好き」って、いや、好き嫌いは聞いてねぇ、自転車の大群描くの地獄だぞ、みたいな。で、結局松田さんは、グラジオラス以外は、ぐちゃぐちゃっとした線のかたまりに色をつけただけのもの描いてたけど、いいのかそれ? って感じ。黒いぐちゃっとした意味不明の背景の前のグラジオラス。いいのか? それで。
松田さんはナチュラルで、あんまりまわりのことを考えない子でした。それでも許されるタイプ。男子にも人気がある子でした。授業がはじまるまえ、「オナラしたひとがいる」って大騒ぎし始めたことがあって、あれもね、わたしが言ったら「くせーのはおまえじゃねぇのか」で終わってたと思います。でもあの子が言うと、まわりも釣られて、「ほんとだ、くせぇ!」「この列かこの列が怪しい」って騒ぎ出して、もちろんわたしがしたわけじゃなかったんですけど、そのへんの臭いを嗅いで回ってる男子もいて、なんかもう、はぁ? って感じ。臭い臭い言いながらわざわざ嗅ぐってどういうこと? で、そいつ、ひとりひとり近くまで来て臭いを嗅ぎ始めて、わたしの目の前に来たとき、反射的に突き飛ばしてしまいました。いま思い返しても、わたしなにも悪くないと思うんだけど、すごく怒られましたね。先生にも、親にも。「向こうは臭いを嗅いでただけでしょう? 突き飛ばしたら暴力だから、あなたが一方的に悪いに決まってるじゃない」って。いまだに1ミリも理解できていません。
クラスで自分の絵を見せたいとは思ってなかったけど、ハギが美術部だって聞いて、わたしも美術部に入っちゃえば、いつかハギにだけは絵を見せられるかなと思って、入部届を出しました。まあ、実際には美術部はあんまり肌に合わなかったってのが正直なところで、ハギもサボりがちだったし、わたしはただ放課後の居場所がないと思ってそこに逃げ込んでただけで、いつまでも仕上がらない石膏デッサンをずーっといじってた記憶しかありませんけどね。
第2章 ひきこもりの始まり
何度かひきこもりになった理由を聞かれたことがるんです。そのたびに答えてたのは、「ドラクエXのWiiでのサービスが終了したから」でした。中1の夏が終わると、姉はちゃんと受験生になって、それからもしばらくは、デュエットにもできそうなクエストをやってみたりしてたんですけど、秋に新バージョンが始まるともうWiiでは遊べなくなって、明けて春、わたしは中2、姉は短大生になると決定的に何かが変わってしまって、学校に行ってもつまらなくて、やることがなくなってしまっていました。あの、びっしりとメモした紙を見ながらドラクエを遊んでた姉が、毎朝化粧をしていました。大学に入ったら祖父が任天堂の最新型のゲーム機、「スイッチ」を買ってくれるかと期待もしていたけど、それもなし。ちなみに、わたしの中学進学のお祝いは図書券で、しかも両親が薦める本を買わされて終わりました。
生きる理由って言ったら変かもしれませんが、人間って楽しいことがあるから生きるんだと思います。それがあっさりと剥ぎ取られるって知ると、なにかこう、人生そのものが疑わしいと思えるようになりました。特に学校。学校のつまらなさって異常だと思います。ゲームと比べるまでもなく。学校っていうか、友だち。みんなバカだと思っていました。
つまり、学校に行かなくなったのは、中2のころからです。最初に学校を休んだ日は、本気で体調が悪くて、朝から吐き気がして休んだんですけど、わたしの登校拒否の1日目は? と問われたら、その日だと思います。一応、病欠になってると思います。そのあとも何度か休んでて、同じように気持ちが悪かったこともあるし、ただ行く気がしなかっただけのこともあるけど、理由はぜんぶ病欠になっていました。しばらくは。
母は「学校でなにかあったの?」と聞いてきましたが、とくになにもありませんでした。いじめ? のようなものも、もしかしたら向こうはそのつもりってひとはいたかもしれませんが、わたしはとくに、なにも。成績のことがプレッシャーになってるとかも、もしかしたら深層心理ではそうなのかもしれませんが、とくに。逆に、理由があればそれを克服すれば学校にも行けるようになるんでしょうけど、ないから困ったものです。ラスボスのいないゲームが永遠に終わらないように、わたしの不登校も終わらないんです。短大生になった姉はもう制服を着ることもなく、朝にバタバタと鞄を用意することもありませんでした。木曜日は授業がないとかで家にいて、その日にわたしも学校を休んでみたんですが、姉は居間のゲーム機に触れることもありませんでした。
これで学校の美術部が少しでも面白ければ張り合いになったのかもしれませんが、たまに顔を出しても話題に入っていけないっていうか。アニメの話、漫画の話なら少しはわかりましたが、アイドルの話、ドラマの話となるととんとついて行けず、ましてやどの男子がかっこいいなど、いったいどんな目で見ればそんなたわけたことを言えるのかとうんざりしたものでした。
不登校が板についてくると何度か家庭訪問されて、先生は「気分が良いときだけでいいから学校に来てみては?」と言ってくれて、その言葉を聞いて、「開放された」と思いましたね。学校って、気分がいいときだけでいいんだ、ずっと気分が悪かったら行かなくてもいいんだ、って。そのころはまだ、不定期に学校に行くことも、たまに2時間目から顔を出したりすることもあったんですけど、もうこうなるとだめですね。教室に入ると、異物が紛れ込んだみたいな空気になって、結局は保健室に行って、午後には家に帰るというパターンに陥っていました。わたしがよく保健室に行くものだから、「学校に行くと気分が悪くなる」という病状が与えられてましたが、気分が悪くなるというより、精神的に堪えられなくなる、が正解でした。そわそわして、落ち着かなくて、大声で叫んでうずくまりそうでした。やればよかったんだと思います。いま思えば。
家族がわたしを無理に学校に通わせなかったのは、いじめを疑っていたのが大きいように思います。母や姉から「学校でなにがあったの?」とよく聞かれましたけど、要は「だれかにいじめられてるの?」ということのようでした。いじめられてたら、そいつを殺しに行くし、ひとつの目標にはなったと思いますけど、それすらもないから行きたくないというのが本音です。まあ、池田のことは殺したかったけど、2年になっても隣のクラスだったし、急に殺されてもわけがわからないだろうし、それに本当に殺してしまったら本当にいじめられてたみたいになって、それも嫌だし、それよりは部屋にこもって池田殺すゲームでも妄想してたほうが楽しかったです。休みの日に姉が勉強を見てくれて、それはまあ、姉の教え方が要領を得ているのもあって楽しかったんですけど、本当はドラクエで遊びたかったです。姉がドラクエで遊んでて、わたしはその後ろで見て、「ブチスライム湧いたよ!」って教えたかったです。そしてそれを学校でだれかに話せたら最高だったんだろうなって思います。
中2でクラス替えしたあと、いちどだけ放課後の美術室に行ったことがあります。中2になってハギとは別のクラスになって、向こうもわたしが不登校になったって聞いていたんだと思います。微妙な空気が流れていました。ぶかぶかだった学生服が、いまではもう少し小さいかもってくらいになって、背の高さも抜かれて、「背、伸びたね」っていうと、照れ笑いしてました。ま、いまだから言いますけど、ハギだけがわたしを学校に引き止められたんだと思います。わたしも少し期待していたっていうか。でも世の中って、そんなにドラマチックに動くわけでもないですね。「じゃあ」ってひとことだけ言って、先に帰って行きました。
姉がブックオフでWiiFitっていうフィットネス用のゲームを買ってきたのは、わたしのひきこもりも堂に入った初夏でした。わたしの不登校は、家族のライングループで対策が練られていたようで、姉がそのゲームを買ってきたときも、ああ、わたしを運動させる計画が始まったんだな、って冷めた目で見ていました。
それでも、ひさしぶりに遊んだゲームは楽しかったです。ゲーム機が来てすぐのころ、家族でコントローラーをまわしてボーリングやテニスを遊んでいたときのことを思い出しました。父と姉がテニスの試合をしてるときに後ろを通って、コントローラーを思いっきり頭にぶつけられたことがありました。「大丈夫?」って、ちらっと見ただけで姉は試合を続けて、そしてあろうことか父を負かしてて、わたしは痛いのそっちのけで盛り上がってました。ひきこもってからはとくに、ゲームはしちゃいけない気がして離れてたんですが、やっと楽しいひと時がもどってきて、大げさかもしれないけど、溺れかけて死にそうになっていたときにやっと息が出来たみたいな喜びがありました。
ただ母はこの、ゲームで運動不足を解消する計画には反対だったみたいです。「ゲームで遊んでもいいの?」と聞くと、「いいけど、WiiFitだけね」って返事が返ってきました。もちろん、嫌な顔をして言ったわけではなく、「不登校でも娯楽は必要よね」とでも言いたげな笑顔を讃えて言ってくれたんですけど、要は、わたしの体力が落ちないように、WiiFitだけはしょうがなく、っていう本音も見えてしまって、これはもうWiiFitも楽しめないなって、そのときに思いました。とは言え、家にいても退屈なだけだし、なんどか立ち上げて遊んではみたんですけど、でもこういうゲームの楽しさって、みんなでやることじゃないかと思うんです。ひきこもって父も母もいない居間にのこのこ降りてきて遊ぶWiiFitって、シュールすぎると思いませんか?
姉が勉強を見てくれるのも、裏で家族でラインして決まったんだろうなと思うと、疎外感が有りました。自分ではじめたひきこもりで言うのはおかしいんですけど、あのころのわたしは、どちらかと言えばそっちをやりたかったんじゃないかと思うほどです。つまり、姉がひきこもって、わたしが両親とラインして対策を練って、実行する。そんなことを考えてるせいか、だんだんゲームもそらぞらしくなっていくのを感じました。姉に見てもらう勉強もそうです。わたしはもうお膳立てされた世界で生きていくだけ。世界からは切り離されたんだなぁって、そんな寂しさを感じました。
こうやって家族がどんな意図で動いていたかなんてことを考えるのは、わたしがカンが良いからなのですが、ずっと昔、少年の失踪事件があったことを皆さん覚えておられるでしょうか? 家族旅行中にふと目を離すとまだ就学前くらいの長男がいなくなっていたと、ニュースになりました。わたしはそのニュースを見てすぐに父親の狂言だとわかりましたが、多くの人は「母親がウソをついている」「少年はもう死んでいる」などという的外れの推理をしていました。だけどわたしは、少年は1週間程度で帰ってくるだろうと予測し、事実その通りになりました。
わたしがこの事件を狂言だと見抜いたのは、わずかにテレビに映った母親の挙動でした。わたしから見たら、常人ではなかったんです。心身症か、あるいは精神遅滞のようにも見えました。この母親の映像が報道されたのは初期の1回だけ、そのあとはころころと供述を変えるさまが報道され、それで世間のニワカ探偵たちはこの母親を真犯人と睨んだのですが、その背景にはもっと深い物語があるのだと思いました。
わたしの推理はこうです。この家庭は、母親と幼い息子を近づけられなくなるような状況に陥っていた。息子を母親から引き離すために、母親を納得させなければいけない。そのために父親は狂言誘拐を計画し、知人を巻き込んで実行に移しました。母親はこれで息子のことは諦め、すぐに忘れるだろうと踏んでいましたが、そううまくことは運ばず、事件は大きく報道されることになります。これがニュースの第一報です。息子は協力者の部屋(おそらく息子もよく知っているひと、母親のことを以前から相談していたひとで、親戚筋の可能性が高いと思います)に保護されていましたが、事件が大きくなると協力者も「こんなはずではなかった」と考えます。そこで警察に相談しますが、他方、母親の問題もあります。事件の全容を表に出すわけにはいきませんから、マスコミ対策としてのシナリオが必要になります。そこで少年はひとりで勝手にどこかに行き、無事に保護される、という筋書きが生まれます。そしてこれを各自治体に根回しし、同時に関係者にも聞き取りをして進めるために3日、事件発生から1週間で少年は意外なところで保護される――。結果は、みごとわたしが予想した通り、ネットではもうみんな少年は死んだと諦めたころに、森のなかの小屋で発見されました。
この予想は当時遠回しにひとにも話しましたが、母親のことだけはどうしてもぼかした言い方になりました。いま思えば、わたしがこう推理できたのも、わたしの環境が大きいのだと思います。ただ、自分のことになるとどうしても靄がかかったように見えなくなってしまうものです。家族はみんな、父も、母も、姉も、ひきこもったわたしのことを気遣って、裏で口裏を合わせて動いているのだと思っていました。
「弓はずっとうちにいてくれるの?」
と、父に聞かれたときは、なにか得体の知れないおぞましさを感じたものです。
「ずっとうちにいるの」ではなく、「いてくれるの?」ですよ?
たぶん、ですけど「うちにいるの?」だと迷惑してる感が出るから「いてくれるの?」と言ったんだと思いますけど、いや、それはちょっと気持ち悪いでしょう、と。あるいはそうやって気持ち悪がらせて家から追い出す作戦なのかもしれません。警戒しながら耳を傾けていると、話題は意外な方向に流れていきました。
お正月前、父が下関のほうまで鯛とハマチを買いに行くというので、わたしから一緒に行きたいと申し出た日でした。不登校も半年くらいになって、その日は、母と家にふたりきりになるか、父と車でふたりきりになるかという選択でした。もちろん、部屋にこもって一歩も外に出ないという選択肢もありましたが、母ははっきりとわかるくらいピリピリしていて、トイレに出た一瞬に顔を合わせるのさえ辛いほどでした。直接話すとどうしてもこじれるので、姉のラインを介してやりとりすることが多かったのですが、母としては3年生からは学校に通ってほしいという思いを持っていたみたいです。3年生になったらクラス替えもあるし、ちょろっと紛れ込めばいいくらいに考えてるのかもしれませんが、まあ、無理ですね。半年不登校やったらもう、復帰なんて3千メートル級のハードルですよ。
そのころの父の役割は、あそこに行こうか、こっちに行ってみようかと、わたしの興味を誘うことだったのだと思います。「北九州空港に写真を撮りに行こうかな」「
黒井というのは、下関の北の方にある黒井漁協養殖場のことです。高速を下関で降りて車で小一時間ほど走ったところにあるのですが、有名な観光スポットではなく、たぶん地元のひとにしか知られていない穴場なのだと思います。まあ、漁協で養殖場ですからね。近くには下関フィッシングパークという施設があって、そちらは観光地としてもそこそこ有名だと思います。ただ、釣れるのがアジやカレイやサバなど、小さい魚がメインになるので、ガッツリと鯛やハマチとなると漁協に一日の長があります。ただしこちらはフィッシングパークと違って、釣りは楽しめません。一応短い竿に紐がついたもの――釣り竿と言うには足りない、バカが作った釣り竿みたいなもの――に餌をつけて魚を上げるのですが、糸を垂らしたら自動的に食いついてくるので、ドラクエの釣りよりも簡単に上げることができました。
わたしの家は
北九州、とくに八幡のあたりは、昔は「煙突の街」だったと聞いています。無数の煙突が立ち、もくもくとあがる煙は空を覆い隠し、祖父の更に祖父の時代くらいになると、それも誇らしかったのだそうです。そのころは苅田の町もいまより寂しく、ただただ地平線まで田畑が広がっていたそうですが、まあ、いまも小倉や門司に比べればのどかな田園風景が広がっていることに違いありません。そんな苅田の景色も、祖父に言わせれば「小倉が染み出してきた」のだそうで、苅田のアイデンティティはやっぱり、北九州の肩に寄りかかってるような気がします。いっそ北九州市になるときに6番目の区になったらよかったのにと思います。
その苅田にもいまは高速のインターチェンジがあるのですが、父は国道を北上し、小倉のインターチェンジから高速に乗ることが多かったようです。黒井の養殖場へは小倉で高速に乗ると、関門海峡を超えて、下関で降りて向かいました。高速は関門橋の利用のために乗っているようなもので、下関からは海沿いの道をひたすら北上しました。黒井の漁協には、お正月用の魚を買いに行くことが多く、わたしが目にする日本海はいつも荒れて、雲も低く垂れ込めていました。その日も例に漏れず、助手席の窓の外に広がる海には風が幾重もの白いレースを編んでいました。広げたレースに花瓶を置いて皺を寄せるように、波は陸へと打ち寄せ、電線が風にたわみ、震えていました。父はわたしの不登校の話には触れずに、祖父のフェリー会社に就職した従兄弟の話、出張先で食べたカニの話、門司港で開かれたイベントで芸能人を見かけた話などをしていたように思います。わたしはいくつか笑って返したり、「そうなんだ」「たいへんだね、大人って」みたいなことを返したりはしましたが、話の中身はあまり聞いていませんでした。
その日はとにかく、風が強かったことを覚えています。駐車場でドアを開くと、風にドアが引かれるような勢いでした。電線は羽虫のような低い音をうならせ、雨粒が不定期に横からバラバラと降ってきました。でも、冬の日本海はこれがふつうなのかもしれません。傘は無理だと察して、父はフード付きのジャケットを羽織り、わたしのぶんもトランクから出して持ってきてくれました。たしか大昔に、家族で釣りにでかけたときのものです。わたしの赤いジャケットはもう小さく、姉の黄色いジャケットを渡してくれました。トランクの匂い、あるいは塩の匂いなのか、それが硬くなったビニールの布地に貼り付いて、ところどころに白い染みを浮かせていました。ゲートの付近に立ったポールには、おそらく風向きを見るためだろう吹き流しがあったのですが、ぱんぱんに卵を讃えたししゃもが断末魔に痙攣するように震えていました。ジャケットも下手すると飛びそうになるなかで、「これ、だいじょうぶなのかな」なんて言ってボタンをとめていると、またこれが不思議なもので、嘘のように雨風は収まっていきました。収まる寸前の風もやっぱり断末魔の魚のようで、不意に吹き荒れては収まり、またちょっと吹いては収まる、という不定期なサイクルで萎んでいくのですけど、風がなくなるとやっと道路に染み付いた魚の臭いが鼻に届きました。これが風の断末魔の匂い。それでもまだ思い出したようにビチビチと暴れる。苅田も海に面していて、海には馴染んできたんですけど、冬の日本海には、たくさんの吹き流しを絞め殺す裏の顔がありました。
信号を待って岸壁のほうに歩くと、雨風に侵食されてところどころ大きくえぐれた足元のコンクリートは高波に濡れて滑りやすくなっていました。たまに吹き付ける風は冷たく、その風がちぎり取った波濤もまだ、時おり頬を濡らしました。だけどもう暴風雨というほどでもなく、レストラン――とカタカナで看板に書かれた食堂――からぞろぞろとひとが出てきたので、雨風は一時的なものだったのかもしれません。
「今日は鯛は1尾も釣れてないよ。ハマチしか上がってない。どうする?」
鯛とハマチを1尾ずつ釣って帰る予定が、腰までの長靴を履いた漁協のひとからそう言われました。魚にもどうやら、釣られたい日と釣られたくない日があるようで、今日は鯛にとっての釣られたくない日だったようです。
養殖場は大きな防波堤に囲まれたなかにありました。岸壁を少し離れるとテトラポットの護岸があり、その先は自然の岩壁が切り立ち、幼いころここで姉と、わたしと、両親とで岩登りをしたことがありました。ここへは何度か来たことがあります。父が「まえに来たときより、海面が高い」というので「きのう雨がふったからじゃない?」というと、「海の水は雨じゃ増えんぞ」と笑われたことが思い出されます。雨では海の水が増えないということを理解できなかったので、幼稚園か、小学校の低学年のころではないでしょうか。頭のなかで雨の水がどこへ行くのか、しばらく考えていました。
この日もたぶん、雨のあとで水面が高かったのだと思います。
「じゃあ、わたしが鯛を釣る」というと、漁協のひとは「そうかい、お嬢ちゃんが挑戦するのか」と、50センチほどの釣り竿を渡してくれました。「お父さんはハマチを釣って」と、ふたりそれぞれに竿を受け取りました。前回訪れたのはもう5年ほど昔になるかもしれません。あの日は姉が釣りに挑戦し、わたしは後ろで見守っていました。いけすには鯛もハマチも一緒に放されていて、餌によってどちらがかかるかが変わりました。大きさは概ねそろっていたのでしょうが、それでもものによって大きかったり、小さかったりがあり、大物を釣り上げるとまわりの人たちも湧いて、びちびち跳ねては〆られる魚を見て姉とふたりでぎゃーぎゃー騒いだものでした。
その思い出がはしゃぎまわる場所で、まずは父から釣り糸を垂らしました。すぐに掛かりがあり、なんなく引き上げて、ハマチをゲット。入れ食いってのはこのことだと思います。養殖の課程で、釣られるときの心得も学んでいるのでしょう。
「目の前にエサが降りてきたらどうする!」
「全力で食いつきます! サー!」
「それに釣り針がついているとわかっていてもか!」
「サー! イエッサー!」
陸に上がったら、釘の飛び出た棒で脳天に一撃を喰らい、彼の人生はそこで終わりました。
次は鯛。わたしの番です。さて、どうなることかと釣り糸を垂らしてみると、なんと、すぐに掛かりが来ました。今日一尾も上がっていいない鯛がついに上がるのか? 漁協のひとが驚いて振り向きました。わたしもなんてゆうかな。釣りは初めてなんだけど、さすがわたし、才能の宝庫、みたいな感情がぱーっと湧いてきて、よっしゃ! 来いや! 鯛っ! とか心のなかで叫んで糸を引いたらハマチでした。
「鯛のエサだったとしてもか!」
「サー! イエッサー!」
彼の人生も脳天一撃で〆られて終了しました。
トランクにクーラーボックスは積んであったのですが、ハマチは入らず、売店? で発泡スチロールのケースを買って、氷をたくさん入れてもらって、頭に穴の空いた2尾の勇敢な兵士をそこに寝かせました。トランクにはずっと昔使った水中メガネ、シュノーケル、足ひれ、グラスロッドの釣り竿があって、それをどかして場所を作りました。どれもたぶん、5年ぶりくらいに目にしました。父はきっと車で釣りに行くたびに目にしているのでしょうけど、わたしが求めているのって、このなくしちゃった5年の時間みたいなものなのだと思います。
自称レストランは、入り口をはいると左手に干物や雲丹の瓶詰め、海藻類のお土産が並び、ひとの常駐していない薄暗いレジとトイレがありました。右手には「本日の煮魚」が書かれたボードがあって、その向こうが「レストラン」です。いけすで釣った魚をその場で料理もしてくれるそうですが、釣り上げた2尾はお正月用ということで、わたしは海鮮丼、父は煮魚定食を食べました。父はわたしのひきこもりの話は避けるほうでした。母がわりとストレートで、ぶつかりやすかったので、それを見て手を考えてたんだと思います。母との話にもだいたいは姉が間に入るのですが、その日はわたしの機嫌が良いと察したのか、父が少し切り込んできました。
「江頭さんとこもずーっとひきこもっとらすやろう?」
いや、もう、切り込むにしても、ですけど。
「息子がゴルフにしか興味んなかけん、やらせとーち。プロになりたかーちゆーとるけん、支援はしてやるつもりち言うとった」
父がどういう意図で言ったのかはわかりませんが、そのひとのことはわかる気がしました。その江頭さんの息子さん――たしかわたしの4つ上だったと思いますが、ゴルフに特別な思い出があるのだと思います。なんかこう、社会に出る過程でなくしちゃったものが、そこにある、みたいな。わたしたちがおとなになる過程でなくしたものって、自分のなかにわだかまるんですよね。
父はこう続けました。
「最初に聞いたときはわからんやったばってん、いまはわからんでもない」
それを聞いて、父にもこの感覚がわかるんだ、と、少し嬉しくなったのを覚えています。でも、よくよく聞いてみるとそれも違っていました。
「俺も、弓がやりたいことがあったら、せいいっぱい支持してやっけん、なんでん好きなこつしたらよか」
――と、わかったのは江頭さんの親の気持ちのようでした。
おかげでわたしも、親の気持ち、みたいなものを少し垣間見てしまいましたが、だけど同時に、こうやってずっとすれ違ったままなんだろうなという寂しさも感じました。プロゴルファーなんて、そんなの急になろうとしてなれるものじゃないって、わたしにもわかります。それを認めて、支援するに至るまでには迷いもあったんだろうなぁ、とも。それに、息子にとっても本当にいまもゴルフは楽しいのだろうかとも。
わたしは「ありがとう」とは言ったけど、やりたいことなんてとくにありませんし、話もそこで途切れました。
帰りの車のなかは静かでした。
カーラジオをかけて、父もわたしも聞いたことのない曲が風のない車内に仄かな温もりになってたまり続けていました。
しばらく走って、いつも立ち寄る店で竹輪と天ぷら――これは関東でいうところのさつま揚げです――を買って、道端に止めた車のなかで竹輪を1本ずつ食べました。海鮮丼を食べてから1時間と経ってはいませんでしたが、まあ、竹輪はカロリーも少ないから。それにしてもわたしの胃袋って元気だな。と、思ってたら、姉からラインが入りました。竹輪を置いて、小指で画面タッチして確かめると、グループへの誘い。家族のグループかと思ったら、父と姉だけ、ふたりのグループでした。
姉からのメッセージには「お父さんと相談して、弓にも共有することになった」とありました。
父もスマホを見ていて、竹輪をかじりながら言いました。
「このままじゃ
恵美子というのは母のことです。
「僕と詩帆じゃ、もう支えきらん。弓にもいろいろと知ってもらおうち思うて」
いったいなんのことか。聞こうと思ったけど、わたしは知っている気がしました。母はおかしかったんです。最初から。ずっと。
第3章 フウラ
14歳でした。いくらカンが良い、大人の考えが見抜けるとは言っても、それでなにができるわけでもないじゃないですか。もちろん大人だってそうなのでしょうけど、14歳なんて、自分の悩みさえ消化できない歳ですよ。母と話していると必ず、だれになにをされているの? という話になりましたが、そんな誤解をどう解けば良いかもわかりませんし、カンの良いわたしの読みでは、母がそうやって学生時代を過ごしてきたのだと思います。母の過去になにがあったかは知りません。父がそれを知っているかどうかも。なにも知りたくなかったので、母との間には壁を作るしかありませんでした。
祖父が会長を務める汽船会社は、以前は門司に本社を置いていたそうですが、いまは大阪に移し、神崎家の本家筋、祖父の兄から続く小倉の神崎家は昭和の時代にみな大阪に引っ越しました。門司港から大阪のなんていったかな。なんとかって埠頭までフェリーを運行しているのですけど、これが本当にたいへんだったみたいで、江戸時代から持っていたという山は売り払い、小倉城のすぐ脇にあった土地もバブルが訪れる少しまえに手放したのだとか。「あと3年待っとったら大金持ちやった」が大伯父の酒席でのネタでした。祖父は跡取りではなかったものの、大伯父が会社を継ぐ気がなかったせいで、赤字続きの汽船会社の会長に取り立てられ、それでいま大阪に住んでいるんですが、まあ、人質か生贄みたいなものですね。
苅田は好きな町です。昭和のはじめに建てられた屋敷は、昔ながらの黒い瓦をいただく二階建てで、通りに面しては柘植の生け垣がありました。わたしの肩の高さまであった柘植には小さな葉がみっしりと生え、それを毎年近所の植木屋さんに頼んで剪定してもらっていたのを覚えています。春になると小さな花をつけ、それは躑躅や百日紅のような華やかさのない、新芽とも大差のないささやかなものでしたが、それでもちゃんとミツバチたちは蜜を集めにやってきました。路肩には幅50センチばかりの小川が流れ、春にはカエル、アメンボの姿が見られ、鮒の鰓をくぐった水の匂い、ヒメジョオンの足元の土の匂い、どくだみの雑じる草の匂いと、いくつかの匂いの層を抜けて、通学路途中には大きな鳥居があり、それがはたしてどこの神社の鳥居かも知らず、歩道の上の側溝の穴ごとにかけられた金属製のカバーをカタカタと踏んで学校に通っていました。花の名前を覚えたのは、苅田を離れてからです。
中3になるまえの春休みのころだと思います。小学校のころからの友だち、
「生存確認!」
「おかげさまで」
「もうずいぶん会ってないけど、いつか話そう。いまじゃなくてよかけん」
「うん」
それだけのやりとりで終わって、少し寂しさを感じました。「うん」じゃなくて、「いまでもいいよ」だったら、もう少し話ができたのかもしれないって。
朝食に起こされることもなくなりました。お昼も近くになって食卓へ行くと、わたしのぶんの冷めた目玉焼きとミニトマト、茹でたブロッコリーが皿に盛られ、ごはんとマヨネーズ、それから、カップスープ。毎朝ちゃんと用意された食事を見て、どんな気持ちになるか、みなさんわかりますか? それは、「不安」です。母は呆れながらこれを用意したのか、怒っていたのか、そしてこれを用意して、どんな気持ちで、どこへ向かったのか、帰ってきて何か言われないか、おそるおそるテーブルに近づいて、冷めた目玉焼きをご飯の上に乗せて食べました。母が気分を害することをいつも恐れていました。ひきこもってからは特にそうです。べつに野生動物のように襲いかかってくるわけでもないのに。母がなにを考えているのか、いつも気になっていました。
二階の部屋に戻りカーテンを開けると、窓の外に中学の制服姿が見えました。時間はたぶんお昼を少しまわったくらい。この時間に帰宅しているということは……と、カレンダーに目をやったのですが、今日が何日で何曜日だったかも怪しいので、あまり意味がありませんでした。巡る月日からこぼれ落ちて生活しているので、カレンダーも古代の石版も変わりはありません。それでもぼんやりとカレンダーをながめていると、「今日は始業式だ」とわかるのだから不思議です。カレンダーからはなんの情報もなく、カレンダーに記すこともなにもなく、部屋にいてもただぼんやりしているだけなんです。学校に行けば落書きもしてたし、ゲームのことを考えたりもしてたけど、部屋にいるとそれもありません。もう死のうかなって何度か考えて、カッターナイフで腕を切ったことがあります。手首は怖かったから、少し上の方。血が流れるのをぼんやり眺めても、自分の痛みと、その傷とがつながらなくて、無性に悲しくなったことを覚えています。痛みよりも、血が肌を這う感覚のほうがリアルでした。すぐに血を拭って絆創膏を貼ったのですけど、母にはバレて泣かれました。泣かれるのは怒られるよりも辛かったです。でもいちばん辛いのは、変化も何もないことでした。だから愛未から「同じクラスになったよ」ってラインが来たときは駆け出したいくらい嬉しかったです。
「矢作くんって知ってる?」
「知ってるけど、どうして?」
「ユミのこと知ってるっていうから」
「彼まだ、美術部続けてるかな?」
「どうだろう。明日聞いておく」
「ありがとう」
「最近どう?」
――手首切った。
言えば良かったんだと思います。どんなリアクションが帰ってこようとも。わたしはただどう返していいかわからなくなって、ボロボロと泣いていました。
「やっほー」
「やっほー」
「昨日はごめんね」
「ごめんって、なにが?」
「いろいろ聞いて」
「だいじょうぶ」
「矢作くん、美術部辞めたって」
「そうなんだ。もったいない」
「だよねー。めちゃくちゃ上手いよね、彼」
「わたしたち、何組になったの?」
「3年2組」
「出席番号は?」
「わたしは28。ユミのは明日調べてきてあげる」
「ありがとう」
家族が出払って、階段を降りるとき、いつも緊張しました。だれかいるんじゃないかって気がして。それでできるだけ、「お母さん」って声をかけるようにしていました。声が返ってきたら、洗濯物、なり、洗い物、なり、ひとこと言えば「ああそう」と言って、部屋にそれを取りに行ってくれました。まあだいたいは返事もなく、椅子に座って、ご飯を食べてまた2階へと戻ったのですけど、その日はなんとなくゲームをしてみたくなって、久しぶりにWiiFitを立ち上げて、しばらくコントローラー持ってぴょんぴょん跳ねてみたんですけど、ちょっとだけマリオカートを遊びました。ハンドルコントローラーなしで遊ぶマリオカートは難しくて、たびたびコースアウトしたけど、少しムキになっていつもより長くリビングのソファにいました。
その日の夜でした。母が部屋に来て、「ひきこもるんだったら、もっと真面目にひきこもりい」って言ったのは。
「わかんない。どういうこと?」
「ゲームで遊ばせるために休ませとーとじゃなかと。ゲームは禁止ち言うたやろう?」
「ばってん、WiiFitはしてよかち」
「今日、なんで遊んだか言うてみなさい」
母はわたしがマリオカートで遊んだことを知っていました。なぜかはわかりません。ゲーム機に履歴が残っていたのか、監視されていたのか。わたしはただごめんなさいごめんなさいと謝るだけで、「謝るくらいなら学校に行きなさい」と言われても言い返せなくて、姉にも目配せを送ったのに助けてもらえませんでした。あとになってラインが来ました。
「ゲームさせると学校に行かなくなるち、お母さん、最初から反対だったんよ」
「ゲームは関係ないと思う」
「わたしもそげん言うたばってん、証明してち言われた」
このころがいちばん辛かったかな。このあと、大阪の祖父の家に移ってからは、ここまで辛いことはなかったと思います。あ、いや、そうでもないな。ただ向こうには話せるひとがいたし、苦しみの種類が苅田とは違ってました。でもいずれにしても、たかが不登校ですよ。たとえば、いじめとか家庭内暴力とかで殴られたりしてたら、もっと辛いと思うし、ひきこもりなんて最悪わたしが学校に行けばいいだけっていうか、学校だってそんなにひどいとこじゃないはずだって思って、「あした学校に行く」って、愛未には決意表明のラインを送りました。姉にも。
朝、ずいぶんと早く目を覚まして、壁に吊られている制服を見てると動悸がしてきました。昨日はお風呂でいつもよりしっかりと体を洗ったけど、もう寝汗をかいてて臭うかもしれない。布団もずっと敷いたままだし、その匂いが染み付いてるかもしれない。従姉妹の家に従姉妹の家の匂いがあったように、わたしからはわたしの部屋の匂いがしてるはずだと思いながら、一応ぜんぶ新しい服に着替えて、いまさらだけど布団を畳んでみて、そこにできた1メートル半の畳のスペースを見ると、なんとなく決心が付きました。制服に着替えて、階下に降りると母は今日は早番だとかで姿がなく、姉が食事の用意をしてくれました。母はたぶん、わたしと顔を合わせたくなかったんだと思います。あるいは、せっかくの決心を邪魔したくないと思ったのかもしれません。わたしもほっとしました。門を出ると、少し離れたところで愛未が待っていて、手を振ってくれました。
坂道から見下ろすと、桜が見えました。きっともう葉桜だと思います。愛未の鞄はもうだいぶ使い込まれていて、わたしの妙に真新しい鞄が少し気恥ずかしく思えました。「大丈夫?」と聞かれ、少し立ち眩んではいましたが、「大丈夫」と応えました。取り壊されて更地になったばかりの茶色い土の上で、サビの浮いた重機が口を開いたまま居眠りし、足元の土の匂いに燻されていました。まだブロック塀のいくらかはそこに残され、苔むした肌をわずかに残す壊れた肩から飛び出した鉄筋は30年ぶり、あるいは40年ぶりの風に晒され、歩道に落ちた粘土質の土の塊のいくつかは靴底の模様を写し、大地への帰還を夢見ていました。わたしも、大丈夫そう。そのときはそう思いました。
洋食屋の、レンガでしつらえられた低い花壇の、花にまだ早い小さな木立のような紫陽花と、寄植えの多肉植物の少し赤らんだ穂先と、電柱へと伸びる斜め45度の黄色い樹脂のひび割れと、2年前にも見た景色がいまもそこでわたしを待っていました。白いモルタルのマンホール。アスファルトとアスファルトの間にはみ出す黒いピッチ。石造りの鳥居。姉が通っていた高校の塀を左手に見ながら歩いて、フェンスの向こうに朝練の野球のユニフォームを見るころ、耐え難い吐き気に襲われました。
「大丈夫?」
愛未の問に答えられませんでした。
金属バットのキーンという高い音が耳に飛び込むと、立っている足元が急にものすごく遠くに思え、見てるはずの景色がもう見えていない、わたしが焦点をあわせるたびに地面はぐるぐると逃げていって、「ユミ!」「大丈夫!?」という愛未の声が遠くに聞こえるなか、わたしの視界は闇に捉えられていきました。
気がつくと、病室のベッドにいました。気がつくと……というのは少し変な言い方で、体が目覚める前に夢のなかで気がついていました。わたしは学校へ行こうとしているのに、道はぐるっと一周してもとの場所に戻って、姉や母、愛未やハギがそれぞれにわたしを責めて、舞台はいつの間にか病院に変わり、みんなパタパタと走り回り、そのときにはもう病室のベッドにいることは気がついていました。廊下にひとの声が聞こえて、目を開けても天井の模様に焦点があわなくて、天井は迫ったり離れたり、しばらくあたりを見渡していると、「がんばったね」って、姉の声が聞こえました。
「もうすぐお父さんが来る」
少しだけわたしのリアクションを待ったあと、姉は言いました。わたしがゆっくりと2回瞬きをするくらいの間がありました。
「外傷はないって。でも念のため1日入院していってもいいって、先生言ってた」
病室で目を覚ましたのは、まだ午前中でした。倒れてから30分も経ってなかったのだと思います。それにしては長い夢を見たし、体にもぎしぎしと疲労が溜まっていましたが、ずっと部屋のなかにいて急に歩いたのも良くなかったのだと思います。父もお昼前には駆けつけてくれて「お母さんは?」って聞くと苦笑いしていました。母は厳しい人でしたから、どうせ仮病だと思われているんだろうなと思い当たりましたが、ふと、姉と父もそう思っているかもしれないと、不安がよぎりました。
「あのね、お父さん」
「うん?」
「仮病じゃないよ」
「わかってるよ」
「お母さんにも……」
「わかってる」
病院を出るときに鞄を返してもらって、スマホを見ると愛未からのラインが7つ溜まっていました。
「ごめんね、無理させて」
「家に電話して、留守電に入れておいた」
「いまお姉さんから電話があった。すぐに向かうって」
「落ち着いてからでいいので、連絡して」
「あ、無理にじゃないよ。その気になったらでOK」
「みんなユミのことが大好きだよ」
「I love you!」
泣いちゃった。なんでこんなに涙出るんだろうってくらい。
夕方、父の車で家に帰ると、リビングで母が泣いていました。姉が寄り添って、わたしたちが帰ると同時に母は寝室へと上がっていったので、はっきりとは言えませんが、たぶん泣いていたんだと思います。姉はわたしに振り返ると、眉を互い違いにした笑顔と困惑を混ぜたような顔を見せました。そういえばずっと昔、同じように母が泣いていたのを見たことがあります。父が博多のビジネスショウに向かう際に、会社の若い女性を車に乗せて行ったときのことでした。母はそれを浮気だ、浮気でなかったとしても許せないと言い、部屋には隣の江崎のおばさんが来ていて、いまの姉と同じように肩に手を置いてなだめていました。まだ小学校に入ったばかりでした。わたしにとって大人が泣くというのはたいへんなことでしたので、父はとんでもないことをしでかしたのだと思いました。車の助手席に若い女性を乗せるということがどれほどのことなのか、わたしには判断できませんでした。わたしは車というものを移動手段以外の特別なものとして見たことはないので、目的地が同じであれば電車代も浮くし、合理的なことのようにも思えました。
まあこれも、車が男女の仲にとって特別なものかどうか、そんなことを考える歳になるまえに母と父の件を目にしたわけですから、父が浮気をするはずないと信じるために、車は移動手段にすぎないってじぶんに言い聞かせてるのかもしれないし、あんな光景を目にしなかったら、どの車に乗る男の子がカッコいいみたいなことを言っていたかもしれません。いまでは、漫画やドラマで「男の車に乗る」というのが特別なこととして語られるのを何度か見て、知っています。
だけど要は、ひとそれぞれなのだと思います。でも、ひとそれぞれということは、父も母の気持ちを理解する必要があったのだと思いますし、きっとそのすれ違いを放置し続けてきたことが問題なのだろうと、あとになって考えました。たとえばそれは、そのビジネスショウ1回の件が仮に浮気でなかったとしても、妻に対する行動としては総合的には浮気と呼べるものではなかったのだろうかと。
そんなことを思い出していると、姉は耳元で小さく、「ユミのせいじゃないから、気にしないで」と言いました。でもそれは、父が浮気したか、していないかと同じようなことで、本当はわたしの罪はもう、決定的ななにかに達しているのではないのかとも思いました。
祖父が訪ねてきたのは、それから一週間ほどしてからでした。祖父はわたしがひきこもって、もう1年ほど学校に行っていないことを知っていました。玄関に入るといきなり階下から「ユミー! じいちゃん来たでー!」と声がして、降りていくべきかどうか迷いました。もう六十過ぎのひとだから、ぜったい古臭いひとじゃないですか。学校に行けってぐちぐち言われるに決まってると思って、部屋から出ないで帰るのを待ってました。でも、あれぇ? と思いました。昼過ぎに来たから、ジジィ、自分の会社のフェリー使わないで飛行機で来たな? って。フェリーを使っているとしたら朝に着いて、夕方くらいにはうちを出るはずだけど、飛行機だったら何時に出るつもりか読めません。まあ、考えてみれば、赤字航路とはいえ、大会社の会長ですし、フェリーで片道12時間かけて来るはずもないんですが、じゃあ、フェリーってなに? みたいな。
「ユミ、部屋片付いてる?」
姉からのラインでした。
「どういう意味?」
「おじいちゃん、会いたいって」
「待って。無理」
「降りてきたほうがいいよ。お土産もあるし」
こういうとき、すごく困るんです。わたしは部屋にこもってるだけで、中身はそんなに変わってないんですよ。病気になったわけでもないし、少し沈んでるとは言え、ひとと話せなくなったわけでもない。なのに相手は、「ユミは不登校でひきこもりだ」って聞いて構えちゃってるわけでしょう? 少しは具合が悪いフリ(なんで?)しなくちゃいけないのかなとか、どんよりとした声出さなきゃいけないのかなとか考えてしまいます。だって、堂々と現れて、こいつ、学校行く気もないくせに偉そうだなぁって思われたら、どんな言葉が飛んでくるかわからないし、だからちょっとだけ沈んだ感じで、「こんにちは」とだけ言いました。リビングには父と姉と祖父。母はいませんでした。
「お母さんは?」
どちらに聞くでもなく尋ねると、口を開いたのは祖父でした。
「あれは、俺に会いたないんちゃうかな」
うわーって感じ。簡単な挨拶を交わした直後がこれでした。その祖父の言葉に父は急いで取り繕っていました。
「いや、そうは言ってないでしょ」
まあ、このあたりのやりとりで、自動的にどんよりした気持ちにはなったのですが。お母さんは美容院の予約があるからと言って出ていったと、父は言いました。テーブルの上には姉が言っていたお土産があって、それが部屋中にホカホカとした甘塩っぱく煮詰められた獣の匂いを充満させていました。姉はわたしの顔を見ると、「明日の準備があるから」と席を外し、目配せされるので仕方なく腰を下ろすと、祖父の口から「恵美子さんがあんな事件を起こすとは」と聞こえました。
あんな事件――それが何を意味するのか、父の顔を覗くと申し訳無さそうに、「弓には言ってないんで」と肩をすくめて見せました。あーもう、なにそれ。そういうところじゃないのかな、わたしが閉じこもるようになっちゃったのは。祖父も少し気まずかったのか、出しかけた言葉を慌てて飲み込んで、お茶で流し込みました。わたしは「事件ってなに?」とは聞けず、ふたりのどちらかが口を開くのを待ちました。
「ちょっと、傷害事件があって。朝方だから、弓はまだ寝てたと思う」
話してくれたのは父でした。わたしは混乱して、母が加害者なのか被害者なのかもまだつかめていなかったと思います。
「でもまあ、相手に後遺症は残っとらんのやろう?」祖父が尋ねました。
「腕を2針塗ったくらいで」父が答えました。
「目や耳じゃのうて良かったわ。向こうの親御さんには?」
「ああ、裁判にはせんと――」
「いや、
宗像は母の実家がある市のなまえで、ここでいう宗像は、母方の親戚のことです。
「いや。なにも。それほどおおごとでは」
ふたりはわたしには直接話してくれませんでしたが、どうやら通学中の生徒に母が怪我を負わせたらしいことがわかりました。立ち止まってわたしの部屋を見上げている生徒がいたから、手に持っていた清掃用のトングで追い払って、そのときに。もう2ヵ月もまえの話だとか。だけど2ヵ月まえだったら、わたしと姉と父のライングループはできたあとです。なのにその話は知らされていませんでした。わたしに気を遣ったのだろうとは思いますが、姉と父とでは抱えきれないからとわたしも加わったのに、結局わたしは信頼されていなかったんだと考えざるをえませんでした。
その話が一巡して、祖父は「学校には行けないんか」とわたしに尋ねました。その意味は、わたしが学校に行けば解決する、ということだとわかりました。わたしが俯いていると父が「行こうとしたけど、無理だったんだよな」と、わたしの目を覗き込んで、口調は優しかったけど、結局はわたしのせいなんだ、わたしが悪いんだという思いが胸の中に吹き上がりました。わたしだけなんか、いつもこんな。
しばらくの沈黙のあと、「急なことでびっくりするかもしれんが、ユミちゃん」祖父が少しおどおどした様子で切り出しました。大丈夫。わたしもう、なに聞いてもびっくりしない。
「しばらく大阪で暮らしてみるのはどないや」
もう、びっくり。
まあ、青天の霹靂ですよね。言葉の意味がどこにもつながってないっていうか、なにを言われてるかもわからない感じです。大阪で暮らすと言っても、その大阪も、祖父の住む家も思い描けないものですから、頭のなかはもうただ真っ白ですよ。真っ白い闇のなかにじわじわと自分の感情だけが浮き上がってきて、それと対峙するしかありませんでした。わたしがいなければこの家族は円満に暮らせるのだという、悔しさや悲しさ、もどかしさ、それに申し訳無さでいっぱいになりました。捨てられるんだ、わたしは。やっかいの種だから、取り除かれるんだ、って。
「無理にっちゅう話やないよ。少しだけ考えてくれれたらええねん」
わたしの挙動がおかしかったのだと思います。祖父は慌てて取り繕いました。父は黙って手に持ったコーヒーカップを眺めてるだけ。
「わたしとお母さんやったら、うまくやっていけるけん」
混乱のなかからなんとか絞り出した言葉がそれでした。本当にそう思っていたかどうかはわかりません。言葉が先に出て、それを追いかけるように気持ちを繕いました。
「お母さんがあげんなったとは、お父さんのせいやけん」
それを父と、その父である祖父のまえで言いました。でもまあ、偽らざる本音です。
「お父さん、博多のビジネスショウに女のひと乗せて行ったやんね。お母さん、泣いとったよね? ずっとお母さんのこと放っといたよね?」
そう訴えると涙がポロポロと溢れてきました。別にこんなこと、話すつもりでもなかったし、考えたこともなありませんでした。ただ、自分がゴミのように捨てられることが耐えられなくて、必死にしがみつこうとしたのだと思います。父の口から、最悪のひとことを聞いたのはその直後でした。
「迷惑かけたとは思っとう。ばってん、浮気はあれ以来しとらんちゃ」
継ぎ足そうとしていた言葉がまたぽろぽろと溢れていきました。浮気じゃない、よくあることだって、何度も自分に言い聞かせてきたのに、浮気だった。本人が言った。じゃあそれをどんな言葉で責めればいいのよ、わたしは。しかもそれでもまだ、浮気は言葉の綾だと信じ込もうとしているわたしもいて、目の前の景色が意味を失って、バラバラに砕け散るようでした。
「もうやだ! こげん話!」
二階の部屋にいるはずの姉に聞こえるように、大声で叫びました。だけど二階からはなんの反応もなし。そこからはもう、泣くしかないというか、あらゆる記憶も感情もすべて混ぜっ返されて、自分が泣いているというほかは何もわからなくなっていました。
「傷害事件のことだまっててごめん」
姉からのラインに気がついたのは翌日でした。
「わたしがいなくなればいいんだ」
返信。
ほかにもっと言葉があったと思います。よりにもよって、どうしてそんな言葉を選んだのか。
「だれも言ってないよ、そんなこと」
そういえば愛未は門から少し離れて立ってたことを思い出して、もしかして母の暴力を知っていたからなのかもしれない、もしかしたら怪我をさせたのは愛未だったのかもしれない。だから、「みんなユミのことが大好きだよ」って言葉をくれたんだ。
「お母さんに相談して決める」
祖父に引き取られる件、姉にはそう伝えました。姉はおそらく、それだけはやめたほうがいいと思ったでしょう。でもわたしはそうするしかありませんでした。だって、母がいないところで、父と祖父の間で決まったことにそのまま乗ってしまったら、母が可愛そうです。そのときはそう思いました。
それからの母はわたしを避けているようでした。朝、少し早く起きて母に話そうとしても、忙しいからあとにしてとあしらわれるばかり、夜もそうです。お風呂には入ったの? 洗濯物溜まってるでしょう? その隙を見つけて言葉を割り込ませようとすると、「なあに? 言いたいことがあるなら言って」と苛立った様子を見せて、そうやってわたしの口を柔らかく塞いでいるようでした。ラインで知らせる手もあったとは思います。だけどあの母がわたしの文字をどう読むか想像ができず、躊躇われました。
「大阪に行く」
姉にラインしました。祖父が来た日から一週間ほど経った日でした。少しやけになったのもあり、姉の反応を知りたかったのもあり、なのにそう伝えた瞬間、それは既定路線になってしまいました。
「ごめんね、相談に乗ってあげられんで」
あのときわたし、大阪になんか行きたくなかったんだと思います。
「お母さんのことをよろしく」
「わかった」
それから父とも話しました。祖父が訪ねてくることはありませんでしたが、ラインで話して、気持ちを伝えました。ラインでのやりとりは、直接話すより落ち着いて話せました。祖父は屋敷の周辺、最寄りの駅、商店街とコンビニとわたしのために用意した部屋の写真を送ってくれました。近くには映画館もあると、わたしがひきこもりだってことをすっかり忘れてしまったかのようでしたが、それを読むとわたしもいまの生活を忘れられるような気がしました。引っ越しの日取りを知らせてくれたら、飛行機のチケットは用意すると祖父が言うので、わたしは「フェリーで行きたい」と返事をしました。母とも話したかったのですが、それはわたしが門司港を発つまで叶いませんでした。
ダンボールに荷物を詰めているとき、押し入れのなかから羊のぬいぐるみをみつけました。小さいころに買ってもらった記憶があります。ビーズが入ったふにゃふにゃしたぬいぐるみで、「めーめー」と呼んでいたのを思い出しました。そういえば、ドラゴンクエストXで、わたしの出身国の姫ポジションのキャラがずっと羊の人形を抱いていたことを思い出しました。そのキャラはフウラという少女なのですが、彼女の人形は頭にケーキを模した帽子をかぶっていて、ケキちゃんと呼ばれていました。わたしが見つけたぬいぐるみは、ケーキの帽子はかぶってませんでしたが、わたしは彼女をケキちゃんと呼ぶことにしました。
ケキちゃん。
あなたはめーめー改め、今日からはケキちゃんです。
苅田から連れていける友だちはあなただけです。
どうかわたしが挫けそうになったとき、勇気づけてください。
わたしがフウラみたいな強い子になれるよう、見守ってください。
旅立ちの日、祖父の家に住んでいる木村さんというひとがわたしを迎えに来てくれました。木村孝江さん。父の従姉妹にあたるらしく、小倉神崎家筋のひとだと聞かされましたが、それ以上のことはわかりませんでした。
門司港までは下道を通り、日豊本線沿いの県道を北上して埠頭へと向かいました。電車に乗ったのはもう遠い記憶で、母と宗像の実家へ行った日の景色が思い出されました。あの日は祖母がいっしょに電車に乗っていました。わたしと姉とでずっと窓の外ばかり見ている姿を、ずいぶんあとになってからも話のネタにされました。いまも会えばその話になると思います。赤い屋根のファミレスを過ぎると、そこが自転車で到達した最北端。愛未とふたりジュースを買って飲んだ百円自販機。タカエさんが「ここを真っ直ぐ行くとわたしの実家です」と、小倉方面を指さした十字路を折れるとあとは車ばかり。お正月に車でよく連れてこられたコメダ、スシロー、ジョイフルと、べつに異世界に行くわけでもないし、いつでもまた帰って来れるのに、ひとつ店が通り過ぎるごとに悲しみがこみ上げてきました。
港に着くと、もう大きな船が停泊していました。父と姉とわたし、それとタカエさん。母は姿を見せませんでした。
「無理せんごつね。いつ帰ってきたっちゃよかけん」姉はそう言ってくれました。
わたしがケキちゃんに手を振らせて「大丈夫。天命の
「なにかあったらわたしが責任持って追い返しますから」と、タカエさんが言うと、父は「よろしくお願いします」と頭を下げました。
船に乗り込んで甲板に出ると、そこは埠頭からずいぶん高く、姉と父の姿を探すのに手間取りました。姉が手を振るとまるで、門司の街、北九州の街、この景色のすべてが手を振っているようでした。わたしが失うものが多すぎる。わずか半月前まで予想だにしなかったのに、すべてがわたしから離れていく。でも、必ず帰るから。船のエンジン音が高鳴ると、船体はゆっくりと埠頭を離れていきました。まっすぐな波のない水面が船と艀の間に広がって、門司のパノラマがゆっくりとわたしの周囲を回りました。そして母にラインを送れなかったこと、いまのいまでさえ躊躇い、何も出来ないことを悔やんで、それが悔しくて、わたしは欄干に手をかけたまま膝を折りました。
第二部 大阪での暮らし
第4章 高石のお屋敷
祖父の家は埠頭から車で20分ほど走ったところにありました。そこからも海はすぐ近くだと教えられましたが、大阪は建物が多く、車から見ていた海はすぐに姿を隠し、少し離れて工場の煙突などがあり、わたしの記憶に照合してみる限りでは若松か八幡に近いような印象を受けました。車は祖父が運転し、わたしが助手席、タカエさんが後ろの席に腰をおろして、埠頭を離れて黄色い橋を渡るとすぐに大きな通りへと出て、その信号のさきを左手に折れたあとは倉庫の向こうにあるはずの海を胸のなかに描くばかりで、祖父のいくつかの問いに都度返事はしていたものの、なにを聞かれ、なにを答えたかもわからないまま、ただタカエさんが合いの手を入れて笑ってくれるので、わたしも少し笑みを返し、テールランプが灯っては消えるトラックの煤煙の後ろを走ると、やがて車は右折し、路地に入り、眼前に迫る民家の壁と、生垣と、塀を降りるサビ猫と、方向指示器のカチカチという音を2度ほど聞けば通りで競り合う大型の車の音も消えて、まわりに立ち並ぶ真新しいおもちゃの家を分け入って、「ついたで、ユミ」と祖父の声を聞いたころにやっと、古い漆喰の壁に囲まれた敷地のなかに、古くて大きな屋敷が時間を止めて佇まう姿が見えました。緩めた手の中をするするとハンドルが戻り、サイドブレーキを引く音を聞いたら、あとはシートベルトをはずして車から降りるだけのことなのに、どうすればよいのか戸惑い、祖父の動きを気に留めながらロックをあげて、ドアのレバーを引くと狭い室内に幾重にも折り返していた吐息の音が日溜まりに零れ、遠くに響く鳥の声になって返ってきました。ドアの外は光の色が変わり、左足を外へだすと、陽の光が揺らめく水面のように体を舐めて、ぷすぷすと鳴る静かなエンジンの他にはなにもない透明に広がった無風の光のドームがそこにありました。通りを行き交う車の音も空に返され、右から左、左から右へと交互に流れ、トランクを開け、タカエさんが荷物をおろして、「ほら、こっちや」と祖父が促したその屋敷の門をくぐるとき、泣いて座り込んだことを覚えています。ちょうど藤の咲くころでした。
祖父の家は大阪市からは南に少しはずれた高石市という小さなまちにありました。北九州と苅田のような関係だとは聞いたものの、道は狭くぎっしりと家が詰まり、苅田のように道の向こうに地平線が見えることはありませんでした。そこからわたしが通うべき中学へは自転車で10分、歩いて20分と教えられ、「転入手続きはすましとるし、明日からでも行けるで」とは言われたものの、はいとも、いいえとも返せなくて、まあ、いつかは学校へ行こうと、思ってはいたんです。具体的な決意はずっと先送りにはなってましたが、母のこともあって、まあ、いつかきっと、必ず、そのうちきっと、と、感じてはいました。言い訳になるかもしれませんが、大阪に来たことでその決意が揺らいだのも事実です。言葉にも戸惑ったし、そりゃそうでしょう、地元の学校でも友だち作れないのに、なんで? って感じです。部屋には制服も教科書も用意されていて、タカエさんから「先生に挨拶だけでも」とか言われて、それもたぶん、挨拶だけならできたと思うんです。でもそうやって1日通ってしまうと、次の日に断れなくなる。その次は? またその次は? って考えると、どんよりと気持ちは沈んでって、「どしたん? 具合、悪いんか?」って聞かれたのですが、具合が悪いんじゃないよね。行きたくないだけで。
具合、悪いんか?
うん。
言えば学校に行かずに済むし、そう考えるとたしかに目眩がしているような気がしてきて、「うん」と答えました。まあ、そういう子なんです、わたしは。それからもずっと、なんとか誤魔化して、学校に行かずに済む方法を考えて、気がつくとまた自分の部屋に閉じこもっていたっていうか。なんどか家庭訪問があって、カウンセラーの先生ってのも来てくれて、そのたびに部屋を覗かれて挨拶はしたんだけど、それがまたわたしをひきこもりという言葉のなかに閉じ込めてったんだと思います。本当はわたしは、ひきこもりでも不登校でもないんです。わたしはふつう。わたしのなかではそうでしたが、世間はどうも違っているようでした。わたしはただ戸惑うばかり。ひきこもりという御札を部屋のまえにぺたぺたと貼られているようでした。
家のなかの静けさというのは不思議なもので、たとえばだれもいない昼に玄関を明けて靴を脱いだときのがらーんとしたあの感覚は、長く暮らした苅田の家にいた頃もそうだったはずです。あの静けさが肩にのしかかって来なかったのは、自分で自由にテレビをつけることができたからだと思います。たとえば宗像の母の実家のお寺にいったときのお堂の静けさも、あれはだれもそこに喧騒を持ち込まないという厳かな決まりのうえで作られてるものでしょう? だけど祖父の家の、あるいはだれかもっと知らないひとの家の静けさってものは、どうやって生まれ、どうやって終わるのか。それがまったく見当もつかず、静けさはただ、わたしの口を塞ぐことだけを使命に、ここに来ているような不安がありました。
祖父は午後から職場へ行くことが多くて、午前中は家にいて、庭木の世話をしたあとは新聞を読んだりしていたようですけど、顔を合わせるのもためらわれ、階下に降りるのはトイレに行くときだけになりました。友だちに聞くと、2階にもトイレがあるという子が沢山いたけど、苅田の家も、大阪の家も、トイレは1階だけ、しかもここは男子便器にならんで個室があって、その個室も和式のしゃがんでするタイプ。このことは、引っ越してきた当日に車のなかでタカエさんが言っていた気がします。古い家だしトイレも洋式じゃないけど、大丈夫? って。別にトイレがどうという理由でひきこもったりひきこもらなかったりしているわけじゃないし、そのときはどうでもいいと思ったんですけど、わずか数日であんまり大丈夫じゃないと思うようになりました。
お風呂もそう。洗い場が狭くて、湯船はタイル貼りで、もちろんきれいに掃除はしてあるんですけど、どうしても古くなった目地、シャンプーのボトルの後ろの汚れに目が留まるっていうか。まあこれにしても、苅田の家だって似たりよったりではあったんですけど、わたしと姉と両親とで使って汚れたものは堪えられても、他人の汚したものはやっぱなんか、嫌でしょう? シャンプーの種類もちがっていて、これもまあ当然なんですが、うちでは姉があれこれとこだわってうるさかったので、そこそこ良いシャンプーがコンディショナーとセットで置かれていたのですが、祖父の家には、なんかすごいテキトウなデザインの消毒液みたいなシャンプーしかありませんでした。そこに住んでいるのは祖父と祖母、あとはおしゃれにももう縁のない父の従姉妹のタカエさんなので、シャンプーだけでなくすべてがこの調子でした。リビングにコンビニで買ったカレ・ド・ショコラがあることも、冷蔵庫にハーゲンダッツがあることもありません。漆塗りのかごに入れられた個装のモナカとか、ゼリー菓子とか、自由に食べていいよとは言われたけど、食べるものはともかく、わたしの使えるカップがどれかもよくわかりませんし、戸棚にはカップがたくさん並んでいましたが、当然のようにだれかが使った形跡が染み付いて、それを使って良いものかどうか、使ったものをどこに戻せばよいのか、冷蔵庫の麦茶は緑と赤の模様の入ったプラスチックの容器に作られて、床に置かれたダンボールを示して、なかの野菜ジュースも飲んでええよって言われたのですが、なんかそういうのぜんぶ、小さなハードルのようでした。
祖父は「これからは家族や思て、欲しいモンあったら遠慮のう言うてくれ」って言ってくれたんですけど、わたし専用のカップが欲しいというのも失礼かもしれないと思って、そのとき手に持っていたカップを指して、「これ、使ってもいいですか」とだけ聞きました。かまへんでそんなん断らんでも、なんや気に入ったんかいな、そりゃあよかった、遠慮せんでええよ、そのカップはだれやったかいな、披露宴のとき、だれそれとだれそれが云々――
わたしのために用意された部屋にもテレビはありましたが、大阪のテレビはあたりまえのように大阪弁ばかりでした。苅田にいたころも九州ローカルのテレビはありましたが、まあたいがいは全国区の東京の放送を見ていたわけで、それが不思議なことに大阪にいるとほとんどすべてが大阪ローカルのように思えました。しかしこれにはトリックがあって、苅田にいたころは、全国放送に関西の芸人が出ていても、それは全国放送だったんですけど、大阪にいて、お昼から夕方の関西ローカルのテレビを見たあとで夜のバラエティを見て、そこにも有名な関西の芸人が出ていたりすると、なんか大阪の番組に東京のひとが出ているという感覚にしかならないんです。大阪弁がカルピスで、東京弁は水。大阪、濃いいんですよ。夜に放送されるのは、単に水で薄めた関西ローカルの番組でした。苅田にいるとときどき、地元がすごく田舎に思えて、その対極が東京で、田舎から抜け出すというのは東京に何メートルか近づくことだと感じていたんですけど、それじゃあここはどこなんでしょうね、っていう。チャンネルを変えてもどこでなにをやっているかわかりませんし、スマホで調べたりもしたのですけど、わたしのスマホは中学生用のフィルタリングと時間制限がされていて、1日に2時間だけ、しかも朝の7時から夜10時の間しか使えなかったんです。これ、父が契約しているスマホだからなんです。そのとき14歳。あと3年ちょっとしたら18歳、成人するわけですよね? そのときもわたし、このスマホを使うの? というか、父はわたしのスマホのこと忘れずに通話料払ってくれるの? みたいな。
幸いなことに、父は養育費として月に3万円を祖父に振り込んでいたようです。それを聞いたときに、スマホの利用料はまたそれと別に父がもつことになっているとも教えてもらいました。更にうれしいことに、なんと! その3万円はわたしが自由に使って良いことになっていました! 大阪に来ていろいろ寂しいことはあったけど、月に3万円ってのはいろんなものを吹き飛ばしてくれましたね。欲しい物があったらタカエさんが買い物のついでに買ってきてくれて、お金はわたしが持っていてもしょうがないのでと、タカエさんが預かってくれて、中学生にとって毎月3万円はとんでもない大金で、夏を過ぎるころには使い切れていないぶんが10万円以上になっていたことを覚えています。そもそもずっとうちにいるし、スマホもキッズ設定で制限も多く、お金を使う手段がありませんでした。でも10万円は魅力です。タカエさんはあれがほしい、こんなものが買いたいと、わたしの購買意欲を刺激するような話をよくしましたけど、買ってきてもらうのは主に漫画でした。デザート、マーガレット、フレンド、花とゆめ、りぼんは押さえで、これは毎号買ってきてもらって、わたしが読み終えるとタカエさんも読んでいました。あとはジャンプとガンガン。ティッシュや歯ブラシのようなものはわたしが買わなくても、タカエさんが買ってきてくれて、部屋着や下着にしても、「こんなん売っとったわ」とタカエさんがお金を出して買ってきてくれたし、マグカップにしても、わたしが「本当はこんなのがほしい」と話したのを聞き漏らさず、何日かして「ちょうどええのが見つかったんよ」と買ってきてくれたりしました。タカエさんが選んだカップは、どこか少しタカエさんの昭和のセンスが紛れ込んでいましたが、真新しい自分のカップができたことで、自分の場所が見つかったような気がして、そのカップが戸棚のどこに収まるか、隣のカップはだれが使ってるカップか、使ったカップをどこに戻せば洗ってもらえるかなどをトレースしては、小さなハードルをいっこずつ踏み潰していきました。
それが大阪にきてどのくらいのことだったか、はっきりとは覚えていませんが、初夏だったと思います。やっと保留していた姉へのラインを返したのがこのころです。最後のやりとりは「またいつか」「うん」、そのあとにお互いにスタンプを送って終えていました。わたしがタカエさんに買ってもらったマグカップの写真を撮って「タカエさんから」とだけ書いて送ると、返事はすぐに来ました。
「メルヘンの世界(大笑いの絵文字)」
それに対して、わたしは――
「なにもかも昭和(泣き笑いの絵文字)」
タカエさんが部屋着にと買ってきてくれたカットソーには、謎の小さなフリルがついていました。それも撮って送ると、「でも可愛いと思う」とまた絵文字つきで返事が来ました。そしてすぐに「着るひと次第かな」と続けて吹き出しが上がりました。
「そっちは大丈夫?」
「うん。なんとか」
「お母さんもだいぶ落ち着いてる」
「うん。よかった」
学校に行っているかどうか、姉は聞きませんでした。そもそも平日の昼間にラインをしているのだから、聞くまでもないのですが。
ここまで祖父とタカエさんの話ばかりで、祖母はどうかと言えば、祖母に会うことはほとんどありませんでした。祖母は部屋で寝たきりで、タカエさんが介護していたのがその理由です。わたしは屋敷へ来た初日に顔を見せただけで、同じ家にいながらそれだけというのはずいぶんと不義理ではないかと思われるかもしれませんが、祖父は「だれに会うても本人にはもうわからへん」と、無理に引き合わせるようなことはしませんでした。祖母の具合が悪いことは2年ほどまえに耳にしていたのですが、その直前には会ったような記憶もあります。まさか寝たきりになっているとも、認知症が進んでいるとも思いませんでした。祖父もタカエさんも、祖母のことがわたしの負担にならないよう気遣っていたのだと思います。いま思えば、タカエさんにとってわたしに服を買ってくること、漫画を買ってきて一緒に読むことは、良い気分転換になっていたんだと思います。もちろん、祖父にとっても。当時は、わたしがいることがふたりの張り合いになっているなどとは考えませんから、こんなたいへんなときにわたしがいてもいいものかと、不安になったものです。祖父はわたしを学校に行かせる使命を帯び、生活も顧みずに尽くしている、わたしもそれに応えるべく努力しなければいけないのだ――と、まあ当然ですよね、そう考えるのも。
とは言え、梅雨の走りのころにはもう、実質的にわたしはひきこもりではなくなっていました。祖母の部屋のとなりのタカエさんの部屋とわたしの部屋とをよく往復していましたし、祖父がいても気にせずに隣を通り抜けてトイレへも行けましたし、その帰りにマグに冷蔵庫のなかのオレンジジュースを注ぎ、居間の大きな一枚板のテーブルの上のカゴに入った岩おこしを取って戻れるようになっていました。ただ、同時に、学校へ行っていないことへの罪悪感はわだかまっていったように思います。タカエさんの話では、中学に通わなかったとしても卒業できないなんてことはほとんどないそうで、高校もその気になればいけるというのですが、姉に勉強を見てもらっていた去年までならともかく、いまは学校でみんななにを習っているかもわからないし、教科書を開いてもわかるわけがないという謎の絶対的な自信がありました。制服はずっと柱に吊ってありましたし、教科書も机の上に置いたままでした。普段は気にせずに暮らしていましたが、学校に行かねばならないと考えた途端、それは腹の底にむかむかと渦巻く熱となり、胸のなかに広がってはただ動悸だけを吸い取る虚ろとなり、喉を上がってはわたしの思考を蝕む闇となりました。まあ、こんな書き方しかできないので、何も伝わらないかもしれませんが、手も足も震えたし、あの日、通学路の歩道で倒れてきたときの感触がたびたび蘇っていたのは事実です。
風のない雨の日は窓を開けて、漫画を読みました。晴れた日よりも小雨の日が好きです。小雨の太陽は無駄なコントラストを作り出すこともなく、静かな窓縁に腰掛けて漫画を読ませてくれました。肘掛窓というらしいのですが床から40センチばかりのところから頭の高さまであり、畳に座って肘を掛けて外が見れるし、広く開ければそこに腰を下ろすこともできました。東に向いたその窓からは、残念ながら海は見えませんでしたが、時折、潮の香りがするのがわかりました。苅田の家はずいぶん陸に入ったところで、潮の香りを感じたことはなかったので、これは真新しい体験でした。タカエさんは、夏も近いからと浴衣を買ってきてくれて、部屋着代わりにして浴衣で窓縁に座って漫画を読むこともありました。漫画を読み終えて、窓の外を眺める時間も増えました。わたしが行くはずの中学校の生徒の姿もよく見かけましたし、向こうからもわたしが見えていたと思います。わたしはなにかきっかけを探していたんだと思います。学校へ行くための。そして本当のことを言うと、少し期待していました。わたしが学校へ行くと、隣の男子が「見てたよ」って声を掛けてくるんです。
「見てたって、なにを?」
「浴衣で窓縁に座って漫画読んどったろ?」
だからちょっと多めに足を出してみたり、髪をアップにしてみたり、いつか行くはずのクラスで少し話題になるようにして漫画を読んでたこともあったのですが、こういうことも、いまになってようやく笑い飛ばせるようになりました。漫画の影響だと思うんです。もちろん14歳ですから、漫画で見た登場人物の色気のようなものはなく、傍から見たらただガサツな女子中学生でしかなかったと思います。ただなんとなく祖父の家は、そういう景色がよく似合う家だと思いましたし、窓の上にはすだれのようなものが巻いてあって、夏になったらこれを半分だけ下ろして、風鈴が揺れる向こうに花火など上がれば最高だと思うようになりました。いまならそこでビールを、と思うところですが、当時はスイカでしたね。窓の外に向かって種を吐いて庭にスイカがなったら、わたしがここに来た甲斐もあるというものです。わたしから「おばあちゃんに会いたい」と告げたのもそのころでした。
祖母のベッドは広い掃出し窓のある明るい部屋にありました。床は板張りになっていましたが急ごしらえの床なのか、緩やかな凹凸があり、一部は足を置くとキィキィと音をたて、戸棚には紙で折られた鶴たちが幾筋にも連なり束となり、見事なグラデーションを描いていました。その部屋の中央、少し窓寄りに介護用のベッドが置かれ、庭に面した広い窓のカーテンは締め切られ、ベッドの足元にある腰窓の光が床と壁と天井に折り返して部屋の明度を作り出していました。掃き出しの外には縁側があり、庭は車が入るように改築され、病院や介護施設へ通うときはその縁側を通っているようでした。部屋に入ると消毒液の匂いがしました。タカエさんにもときどきその匂いがありました。
おずおずと部屋に入ると、すぐに祖母と目が合い、「タカエはん、お客さんきてはるよ」祖母はわたしの顔を見て言いました。
「そうよ、おばさんのお孫さん。ユミちゃん。陽介の下の子ぉよ。中学3年生やて」
父の従姉妹ですからタカエさんから見たら祖母は叔母にあたりました。父方の従姉妹ですので血の繋がりはなく、義理の叔母というのかもしれませんが、義理の叔母という言葉があるのかどうかはわかりません。
「ユミちゃん? すてきなおなまえやねえ」
祖母の言葉は半分ほどは音を鳴らさずに吐息となって抜けているようでした。
「こんにちは。お加減はどうですか?」
「ぼちぼちやな。きょうはひとりできよったんか?」
「ええ。大阪へはひとりで。いまはこの家の2階に住んでいるんです」
「まあ、えらいわねえ。せやろ、孝江はん」
祖母はわたしの方を向いたまま、うしろに立っているタカエさんに確認をとりました。
「ええ、立派ですわ」
「いくつになられたんや?」
「14です。もうすぐ15になります」
「あら。いいわね。きょうはひとりできよったん?」
タカエさんが涙ぐむのでなにかと思いましたが、あとで聞くと普段はこんなには喋らないという話でした。もう長くないのはわかっているので、尽くしてあげたいけど、正直なんの報いもなく折れそうになることがあるとも聞きました。それに――わたしが認知症になったら介護してくれるひとがいない、とも。息子夫婦に迷惑をかけたくない。息子はともかく、お嫁さんに迷惑かけて嫌々お世話をされるくらいなら死んだほうがまし。おばさんは幸せものよ。旦那さんもしっかりしておられるし、わたしもいるし、ユミちゃんも会いに来てくれた。わたしなんか、お給料はもらっているけど、遺産がはいるわけじゃない。ここでのお手伝いを終えたら行くあてもない。でももういい。自分はもう十分な幸せを頂いたから、それをお返しする番。おじさまもね――タカエさんは祖父のことをそう呼んで――ユミちゃんから「おばあちゃんと話したい」って聞いてね、涙ぐんでたのよ――と語ってくれました。
わたしは単純でしたから、この話を聞いて、明日から朝早く起きて、制服に着替えて、祖母に行ってきますと言って中学に行こうと思いました。いまにして思えば、単純なうえに脈絡もありませんが、あのときはたしかに、理路立てて結論したのです。
その日はお風呂で入念に体を洗って、寝る前に部屋中に消臭剤をスプレーして、どれを使うかもわからない教科書はぜんぶ鞄に詰めてふとんに入り、また起き上がり、机の上の目覚ましと、スマホの目覚ましと、指差しセットしてまたふとんに入り、寝付けぬ夜の時計のカチカチカチカチと鳴る音を聞くうちにいつの間にか落ちた眠りから、目覚ましのベルが鳴るとともに早押しクイズのように起き上がり――
「ラッコの味噌汁!」
「正解です! 神崎ユミさん、優勝にリーチがかかりました!」
と、下着までぜんぶ替えて制服の袖に腕を通しました。
このことは祖父にもタカエさんにも言ってませんでしたから、階下へ降りると新聞を読んでいた祖父は二度見して固まり、乾いたタオルを持って奥から現れたタカエさんは、「もうすっかり洗い替えがなくなっちゃって」と言いながら顔を上げて、目を丸くしました。言葉を選んでいた祖父が「サイズぴったりやないか、ええ?」と言うと、タカエさんはタオルを置いて傍まで来て、裾を少しひっぱって、襟を直してくれました。「ほんとぴったりやわー。似合うとるわー」
「車出したるさかい」
「大丈夫。地図を書いてある」
「歩いて行くん? わたしのチャリあるで?」
自転車はおそらく登録したものしか通学に使えないと思うのですが、昭和の時代はそうでもなかったのでしょうか。
「大丈夫。行ってみる。それよりも、おばあちゃんに――」
わたしが祖母の部屋の扉を静かにあけて、「それじゃあ、学校に行ってきます」と声をかけると、その間にタカエさんが靴を用意してくれていました。
表に出ると朝の太陽はそれほど重く肩にのしかかることもなく、むしろ木陰の清しさのなかでキラキラと透けて通る陽の光は笑っているようにも見えました。わたしが大阪を歩くのは、フェリーから車まで、車を降りて屋敷まで、その2回に続いて、これが3回目でした。
「無理せんといてね」
玄関先まで見送りに出たタカエさんと、そのうしろには祖父もいて微笑んでいました。大きな木陰を作っていたのは楠の木だと思います。梢にはきっとわたしが名を知らぬ鳥の巣があるのでしょう。
「行ってくるね」
そう言って日向へと滑り出すと、もう冬の制服には似つかわしくない初夏の暖かい風が追い越しました。わたしは少し、汗のことが気になりました。路地を歩くと、ひとつ角を曲がるたびに道幅は少しずつひろがって、幾人かの制服姿が合流し、いまは冬服から夏服への切り替えの時期だと思います。気温のせいもあってか、夏服が多いように思えました。はじめて歩く町なのに、景色はひとつも頭にはいることなく、地図を見なくてもこの制服の流れに沿って歩けばいい、まずは職員室に行ってクラスと名前を告げればあとはなんとかなると、これからのことで頭がいっぱいになっていました。ひとの目は気になりました。徒歩20分の道のりは意外と遠く、持ち慣れない鞄は重く、右手、左手と持ち替えているうちにふと、両手首の内側にある傷跡のことを思い出しました。両腕に3本ずつ。もうそんなには目立たない、いまは冬服なのでひとに見られることはない、そう思いながらも、だんだんと呼吸が荒くなっていくのが自分でもわかりました。あのころのわたしの最大の弱点は両腕の傷跡でした。手首にカッターの刃をあてて滑らせるときの高揚と冷たい痛みだけがわたしの慰みだったころがありました。べつに死にたくてそれをしたわけではありません。あらゆる感情の起伏をなぎ倒すあの恍惚は、だれにもわからないと思います。腕だけではなく、胸にも大きくバツの字が記されています。もちろんそれをだれに見せるわけでもありませんが、もしかしたら体育の時間に着替えるとしたらひと目に触れるかもしれません。夏にプールがはじまれば、たぶん水着では隠れない場所に、1本ならともかく、左右対称にXの字があるのです。気がつくとわたしの足は止まっていました。鞄をその場に置いて、なにをどうすればよいかもわからなくなり両手で顔を覆っていると、「ユミちゃん、大丈夫?」と、声がかかりました。タカエさんがわたしのあとをつけてきてくれていました。「大丈夫? 横なるんやったら、すぐそこにベンチがあるで」そう言って背中をさすってくれるタカエさんに、わたしは「怖い」としか言えず、ポロポロと涙をこぼしました。
自傷には性欲を解消するときと同じような悦びがありました。そして毎回、激しい後悔がありました。祖父もタカエさんもわたしの自傷のことは聞いていたと思います。そしておそらく、人生が嫌になったか、あるいは無理解な家族への当てこすりでやったのだろうくらいに見られていたのだと思います。もちろん最初はそれに近い感覚でしたが、違うんです。自傷は人生においてこの上ない快楽を与えてくれました。万引きしてる級友から話を聞いたことがありますが、その感覚も同じなのだと思います。死が間近に迫る背徳の興奮。手首の傷は絶望ではなく、命を弄ぶわたしの愚かさを記憶しているのです。
屋敷に戻って、タカエさんにだけは言いました。手首の傷を見られたくない、胸にも傷があるし、腹にも、脚にも。後悔してるし、もう二度としない、だけど二度ともとに戻ることはない、と。泣いて訴えるわたしの肩を抱いてタカエさんは、あなたが思ってるほど目立たないから大丈夫、胸の傷もどこにあるの、見せてみなさいよ、なんてことないわよそのくらい、わたしのお尻なんてセルライトでボッコボコなんだから、見る? と言って、スカートを少しまくって、「ほら、ここも」と内股の皮膚に走る肉割れ線を見せてくれました。スマホには手首を切ったとき、胸に大きなばつ印を刻んだときの写真が残っていました。あえて口元とまだ華奢な胸の先が映るように撮ったあられもない写真です。それはわたしの裏の顔です。わたしには裏の顔があると思うからこそ、姉と、母と、父と、対等に話せていたのだといまも思います。
それからしばらくして、「夜間の高校やったら制服もないし、考えてみたらどない?」と、タカエさんがアドバイスをくれました。
高校に行けば、「わたし、高校生になったよ」って祖母に言える。もちろん、姉にも、それからしばらく音信不通の愛未にも。だったらそれも悪いことじゃない。
「タカエさん、本屋さんとか行きます?」
このころはずいぶんと本屋の数も減ったのだといいます。コンビニで買える本ならともかく、ほかにほしい本があったら梅田なり難波なりに出るしかないのだと。
「ああ、うん。なんか欲しいモンあったら言うて。火ぁ金どっちかに買うてくるわ」
火曜日と金曜日はヘルパーさんがきて、タカエさんはゆっくりと羽根を伸ばしていました。梅田のスカイビルを眺めてきた話、ミナミの道頓堀、日本橋の話をよくしてくれました。
「参考書が欲しい。お金ぜんぶ使ってもいいから」
「ぜんぶ! しゃあないなもう、梅田の蔦屋カラにしてきたるわ」
第5章 ストーカー小峰
中2、中3と、すっかりじぶんが中学生だって認識は抜けていましたから、ずっとあとになってひとと話すときも「初恋は中2のころだった」などと聞いても、どこかピンと来なくなっていました。小6が12だからと、指折り数えて、中2だとつまり「14歳のころ?」と考えれば時制は一致するものの、べつに友だちの誕生日を祝うわけでもなく流れていく時間は、時間としてはもう意味をなしていなくて、わたしとしては「苅田でひきこもっていたころ」「高石に来てすぐのころ」みたいに言うのがしっくり来てたのですが、それで通じるのは家族とカウンセラーの先生くらいでした。
だからたとえば小6のころ、と言えばわたしにも覚えがあったし、その頃の趣味や聞いていた音楽について考えること、話すことはできたけど、中3のころ、高2のころと聞いても、ああ、みなさんそうだったんですね、みたいな感覚しか、ないっていうか。
定時制の高校に通うようになる半年ほどまえ、つまり一般的には中3? のころに、よく手紙を書いていたんですけど、このだれに宛てるでもない手紙もたぶん、「中3のころはこうでした!」と言えば、みんなじぶんの人生に重ね合わせて、「わたしはこうだったけど、このひとはこうだったんだな」と、その差分をわたし、神崎弓の体験として受け取れたんだと思います。
そう考えると、わたしの人生はすべて、だれも受け取り手がいない手紙。「中3のころ」という比較できる時間を失くしたことで、わたしは「差分」ではなく、「すべて」を伝えるしかなくなって、どこか世の中が、わたしからすごく遠くに行ってしまったような感覚というか、逆かな? どこかすごく世の中から遠いとこに来てしまった感覚があります。
それで、その手紙なんですけど、ひとり部屋で寂しいとき男子は詩を書いて、女子は手紙を書くのだと、これも漫画で読んだのだと思います。背景に柔らかな点描の入ったヒロインの横顔の絵とともに覚えています。ガサツな男子が詩を書くというのは不思議なようでいて、そのギャップにはどこかしら萌え要素的なものを感じました。
「男子は詩を書く」というのは、アニメーターになってから隣の席の佐々木さんにも話したのですが、佐々木さんもどこかで聞いたことがあるらしく、その理由について「男子は肉体と精神とが分裂してるから」だと語っていました。女子が体と精神が分裂し得ないことはもう疑いようのないことで、佐々木さんと話して改めて男子には生まれついての肉体的特権が与えられているのだと感じました。「だからロボットアニメが好きなんだよ」と佐々木さんは言いながら、昼間はサッカーなんかで激しく体を動かして、部屋に帰ったら胸のハッチから身長15センチほどのパイロットが出てきて、机に向かって詩を書くのが男子なのだと、サラサラと絵を描いてわたしに見せてくれました。それ以来、男子という謎生物はザクやゲルググみたいなもので、被弾するとなかのパイロットが「お母さん!」なんて叫んでるのだと考えるようになったのですが、わたしは、わたしの体はわたし自身のものですから、ハッチから降りるに降りられずに、手紙を書き連ねていました。だれに? と聞かれると、だれ宛なんでしょうね。キリスト教徒だったら神様に、と言うのかもしれませんし、わたしだったら仏教徒だから、ブッダに? 手紙を?
小学校の卒業式ではボロ泣きしたことを覚えています。卒業式はそれっきりなので、他の卒業式との比較はできませんが、たった12歳のわたしがあれほどの感受性を持っていたというのは、いま考えても驚きます。12歳の3月というのは、おそらくひとの感受性がもっとも高まる時期なのだという思いが、わたしのなかにはあるのですが、でもこの感覚だって、小学校からひきこもりを始めたひとには届きようのない言葉なわけでしょう? 体験ってのは、いっけん共有できるように見えても、じつはすべて幻覚なのだと思います。たまたま共感できるひとがいたら、わたしはそのひとと親しく言葉をかわせるかもしれませんが、わたしが共感できる話題はとても限られたものでしかありません。もし会話の本質が共感であるなら、この世界にはもう、わたしの居場所はないんです。
わたしが通った定時制の高校は17時に始まり、そのころにはまだ昼の生徒たちの姿がありました。定時制とはいえ校舎はふつうの高校ですし、そこに私服で通うことに少し戸惑いはありましたが、17時となるとほとんどが部活の生徒たちで、それぞれのウェアやジャージをまとっていましたので、それほどのプレッシャーを感じることはありませんでした。夜間の高校と聞いて、どんな深夜に通う学校かと思えば、夕方まだ日も沈みきる手前から夜はバラエティだの歌番組だのを見る時間までの営みでした。時間は1時限目から始めればもう少し遅くから通えたのですが、高校を受験したころのわたしはおかしいくらいに前向きでしたので、選択科目の0時限も選んでの登校になりました。
受験のときと、最初の通学、それぞれ祖父、タカエさんに車で送ってもらいましたが、そのあとは定期を買って電車で通いました。なんといってもそのころのわたしは、前向きでしたから。
長く外に出ていないせいで、まわりの目は気になりましたが、大阪という街は不思議なもので、わたしよりもずっとおかしな、しかもさまざまなタイプにアレンジされたひとたちが路上に
高校へは電車を一回乗り換えて20分。まだ日のある夕刻に門へ入り、夜も更けた9時過ぎにまた駅へと向かいました。定時制の高校には働きながら通うひと、二十代になってから学び直す人が多いのかと思っていましたが、実際にはわたしのように中学時代にひきこもっていたひとが半分近いのだと、入学前の面談で聞きました。その言葉の裏には「ひきこもり経験者同士だから心配はない」と言わんとする意図が透けて見えて、いやいや、ひきこもり同士が会うのは「能力者」を引き会わせるのと同じことで、場合によっては大惨事にも繋がりかねないのではないかと、身構えたものですが、実際に教室にいたのは「能力者」というほどの能力もないふつうのひとたちでした。もちろんわたしもそうなのですが、じぶんのなかでは設定があって、なにかトラブルが発生したときにその能力は発揮されることになっていましたし、あるいはまあ、他の人もそうだったのかもしれません。みんな連載がはじまるまえの漫画の主人公のように、己の凡庸さに辟易とした潜在的な能力者でした。全員能力者だった、みたいな。最近はそれもまあ、ありがちな話ではありますけど。
中学校へ行かなかった理由、高校へ行き始めた理由、それぞれなにかあるのかもしれませんが、じぶんのなかではあまり明確ではありませんでした。たしかにひとに説明するときには、生きる理由がないとか、ドラクエXのサービスが終了したからとか言ってましたが、それがじぶんでも腑に落ちていたわけではありません。ただなんとなく、理由は聞かれるだろうし、考えておいたがいいかなとは思いましたけど、そうやって後付で考える理由なんて、意味はありませんよね。
事実としてあるのはただ、半年以上に渡ってタカエさんといっしょに勉強に勤しんだことと、高校に合格が決まったその日に任天堂のゲーム機、スイッチを買ったことでした。タカエさんは「そんなん、入学祝いにわたしが買うたるわ」と言ってくれましたけど、いやいや、まってまって、って。わたしはいつかタカエさんとふたりでドラクエを遊びたいの。遊びたいんです。だからわたしのはわたしで、タカエさんのはタカエさんで買おうと言ってお断りました。お断りました? お断りしました。
タカエさんは「しゃあないな」と言ってくれたので、きっとじぶんのぶんのスイッチもそのうち買うのだろうと思ったのですが、学校へ行き始めて2週間経ってもタカエさんにその気配は見えず、そのころにはわたしの前向きさもまあ、後述するいろんな事情がありまして、少しだけ削がれていましたが、それはともかく、わたしは一刻も早くドラクエを遊びたかったんですけど、まずはタカエさんと遊ぶためにと思って大乱闘スマッシュブラザーズを買いました。もちろん、少し遅れてドラクエも買って、タカエさんも引き込もうと思って、懐かしのエルフのキャラを作ってプレイして見せたのですが、あんまり興味は持ってもらえず、それでタカエさんはじぶん用のスイッチを買うには至らなかったのだと思います。キャラクターのなまえはまたデュエットにしたのですが、なまえとは裏腹、デュエットはずっとソロのままでした。
姉と連絡を取ることはありませんでした。タカエさんから、「お姉ちゃん、小倉のケーキ屋さんに就職しはったそやで」とは聞きましたが、姉は保育科のある短大に通っていましたし、卒業後はすっかりその道へ進むものと思っていて、なにか遠い他人の話を聞かされているような気持ちになりました。幾度か行ったことのある小倉の街並みをこう、脳裏に思い描いて……そこにケーキ屋を思い浮かべて……仕上げに姉の姿を添えてみたのですがありえないありえない。なぜかジャージ姿で思い描いたわたしもわたしですが。あの姉が。ポエみちゃんが。ケーキ屋って。
定時制高校はわたしに向いていると思いました。友だちを作るというプレッシャーがなかったからだと思います。めいめいに私服で通う高校ってなんとなく、それぞれ他人でいられるような気楽さがありました。もちろんそのなかでも気の合うもの同士は言葉を交わし合っていましたが、だれとも話さずにそそくさと帰る二十代の男のひと、ヤンママ風のケバい女のひとがいて、それぞれみんなじぶんの世界を背中に抱え、授業が終わるとみなじぶんの世界へと帰っていくという暗黙のルールが、学校という空間への深入りを禁じているようにも思えました。
のちにストーカーとなる小峰さんが親しげに声をかけてきたのは、二日目か三日目だったと思います。カバンからラムネを取り出して、「どう?」と聞いてきたのですが、どう? と言われても、ですよ。小さく会釈して断ると、次の日はアーモンドチョコの箱を開けて、前後の級友に配り、昨日と同じようにまた「どう?」と声をかけて来ました。いや、だから。その日も断ると、照れ笑いしながら「ラムネもチョコも食わへんねんな」と言う声が聞こえましたが、もちろん、ラムネもチョコも嫌いではないんですけど、鏡見ろとは言わないけれど、まあ、そういうことですよ。
祖父の家近くにある駅は、大阪のはずれとは言えそこそこにぎやかな駅で、それでもそれなりの怪しさは漂っていたのですが、学校のそばの駅に比べればまだずいぶん安全でした。他方、学校は静かな住宅街にあり、駅前には繁華街的な喧騒もなく、一件だけ夜空を照らす24時間営業のスーパーが、誘蛾灯のように佇んでは街並みに独特の匂いを広げ、スプレーの落書きのあるガード下には、弁当の空き箱がひとつ、ふたつと、ひとの汗と混じった異臭の底に転がって、その谷底を抜けると、まばらな街灯は薄いオレンジに空間を染めて、その転がるオレンジと民家の明かりの合間の闇と、学校が終わる9時過ぎにはひとの姿も減り、スーパーのまえに自転車を止める作業着の男がこちらに向ける視線には、真の闇とはまた違った恐怖がありました。その道を歩くときはいつも、後ろを付けられているような変な予感が胸を塞ぎました。おそらく、昼間に通ればなんでもない道なんだと思います。
そのむかし、アニメで見たことがあります。学校の出し物の準備に追われた同級生の男女が、遅い時間に駅のホームのベンチに座って、話しながら電車を待つ場面が、ちょうどこの駅のホームに似ていました。好きな、アニメ、だったんですけど、その駅もひとりで利用すると、ただただ恐怖があるばかりかもしれないと、そのときになって感じたものでした。
わたしがまた学校へ行けなくなるのに、ひと月を要しませんでした。
宿題もないし、授業で指されることもないのに、どこか通うのが憂鬱で、家を出るときにまた目眩に襲われるようになっていました。決定的なのは、小峰さんがストーカーと化してしまったことです。もう、酷い話ですよ。夜道を歩いていると、小峰さんが追いかけてきて、「ここは暗くて危ないから」と手をつないで来て、あー、こういうのあるんだー、って、はじめて遊んだゲームで見知らぬモンスターの不意打ちを食ったときの気持ちになりました。
帰り道はよく偶然を装って隣に並ばれましたし、肩を抱かれ、耳を舐められたこともあります。うわーっ。なにこれー、みたいな。向こうはもう二十代のはずです。わたしの姉よりも年上のように見えました。最初はつないでいただけの手が腰のあたりにまわるようになり、その手はいちいちわたしのお尻を撫でるようにして動きましたし、肩に手を回すときも背中に手を掛けたあとに、いちど脇腹に指を這わせたうえで、二の腕から肩へとたどりました。昼間はじぶんの部屋でスイッチで遊んで、窓から挿す陽が傾き始めると、小さな駅舎を出て学校までの道に伸びる夕方の影を思い出しては、なんかもう、うんざりっていうか、行きたないなー、またあいつ絡んで来るねんなーって。
ただどこかには、べつに小峰さんでもええかーって気持ちはあったんです。馴れ馴れしいとは思いましたが、決定的に嫌なことが起きたわけではなし、学校帰りの駅までの道で小峰さんの話を聞くのは、わたしの退屈をよく紛らわせてくれました。でも、耳舐めんなや、耳。手ぇはもうええわ、尻でも背中でさすったええわ。でも、べろはあかんやろ、べろは。まあ、わたしのほうも優柔不断だったと思います。男子にも興味がないわけではありませんし、正直なとこ「生理的に無理」ゆー水準さえ超えてくれたら、未知との遭遇への薄い期待もそりゃあありますよ。あるいはまあ、わたしも甘い声でも出していたのかもしれません。小峰さんとは同じ電車に乗り、しばらくしたら私は乗り換えて、小峰さんはそのまま先の方へと乗って行ったのですが、ある日彼が、わたしが乗り換える電車に乗って、家までついてきたことがありました。不覚にも――ほんっとこれ、気の迷いなんですけど、家までの道のりを手を繋いで歩いてしまったことをいまでも後悔しています。家のまえに着くと肩を抱いてきて、向こうはさあこれからキスだ、という雰囲気を作ってきて、ようやく焦りました。遅いっすね、ほんと。わたしのダメなところだと思います。
今思い起こしても、小峰さんは良い男ではありません。が、ブ男というほどのものでもありませんでした。少しチャラくて、平均点も取れていないのに満足しているようなやや勘違いしたところのある残念な男です。これがもし一切の勘違いがなく、己の分をわきまえて、真摯に職能を磨くことに精を出し、たまの休日に骨を休めるためにどこか遠くへでも、と言ってくるんやったらギリギリOKレベルなのが小峰さんでした。要は誘い方もあったのだと思います。もうキスくらい当然やゆーように顔を寄せてくる、イケメンと思い違った非モテのブ男ムーブですわ。おのれにその速度感が許されると思うとんのか、と。おのれ原付きやぞ、おまえの法定速度は、ここに書いたる60ちゃうねん、30やねん。みたいな。
「まだそんな仲じゃないよ」と言ったのを覚えています。
顔は平均点でも、心はイケメンでいようよ。そう言ったつもりでした。
仕方なくはじめたつきあいでも、時間をかけていればなにか見えてくるものはあると思います。男女の仲というのは決してすべてが一目惚れの大恋愛ではじまるわけではないはずです。幼なじみの男女なんて、偶然隣り合って生まれただけですし、それでも身近にいるというだけで恋愛に発展していくケースがあるわけですから、そういう意味ではわたしも小峰さんに対して、ゆくゆくはそういう感情を抱いたかもしれないわけですよ。小峰さんは大きな古墳のすぐ近くのアパートに住んでいると言ってましたが、その更に先、どんなところで働いて、休日はどんな過ごし方をしているか知れば、「親しみ」は湧いたと思うんです。最初は親しみで十分で、悩みなど相談されれば必然その悩みはわたしを侵食しますし、わたしからだって家族のことをいつかだれかに打ち明けたいと思っていましたし、いまのだれ宛てでもない手紙にもやがてだれかの名前が書かれるのだろうと、わたしはそうやって恋愛って育っていくと思っていたんですが、小峰さんは体を触ったり、耳を舐めたりするのが先でした。それは恋愛ではなく、単にそういう行為だと思いますし、端的に言えば犬のすることです。
おそらくわたしも思わせぶりな態度を取ったのでしょう。いや、取りましたね。こればかりはもう、ごめんなさい。取りました。ラムネやアーモンドチョコレートを勧められて、もしかしたらこのひとはわたしに気があるのかもしれない、言葉が通じるひとなのかもしれないと感じてしまったことも否定はしません。これは持論ですが、女子が男子を好きになる理由は、話を聞いてくれるかどうかだと思います。だからたとえばわたしが読むのと同じ漫画などを読んで、同じ箇所で笑い、同じ箇所で泣けば、それだけで好きになる可能性だってありますし、じぶんでも見過ごしたようなヒロインの機微を気取って語りでもしたら、それはもう恋に落ちるなというほうが難しいことです。が、ほとんどの男子はそうではなく、だから女子は漫画やアイドルのなかに理想の男子像を探すしかなく、そしてそれを作品に描くのだと思います。わたしもこのころには絵など描いて、キャラクターの設定なども書き添えていたのですが、現実からは遥かに遠い妄想でした。
それでもあの晩、小峰さんが無理にでもキスしてきたら、わたしもふっきれたのだと思います。こいつはこーゆーやっちゃ、しゃーないなもう、ちゅーでもなんでもしたらええわー、って。でもあの人はわたしの口から「まだそんな仲じゃないよ」と聞いて、「そうだね」とはにかんだ笑いを見せて、私の肩に乗せた手を下ろしました。わたしは目を合わせず、ちらりとだけ顔を仰いだのですが、少し目を潤ませていて、そのときに「このひと、本当にわたしのこと好きなんだ」と感じてしまって、トラック2台分ほどのガラクタを一気に胸の中にガラガラと流し込まれるような混乱に陥りました。なんかね、不覚にもね、不覚2回目ですけど、はじめて小峰さんにときめいたんです、そのとき。
その次の日、わたしは学校に行けませんでした。わたしのなかには、小峰さんとなかば無理矢理に初体験するんだろうなってぼんやりとした予感があって、でもまあそれもしょうがないくらいに考えてて、だってそれは恋じゃないから。そうやって否応なく変わっていく世界を受け入れる気でいたのに、その未来は違っていたっていうか。
小峰さんのことはいまもよく思い出すんです。少し時間が経ってからですが、よくわたしの妄想の相手もしてもらっていました。なんで学校に行かなくなったんだろうって、後悔することもありました。
昼間、部屋でゲームをしているとタカエさんがお茶を持ってきてくれて、「どうすんの、あんた」と、呆れて聞いて、隣に腰を下ろしました。
「もう学校行かへんの?」
「もう無理や。一週間なる」
「ギリギリ行けるんちゃうの? なにがあったん?」
「なんもない。いやんなっただけや」
タカエさんの大阪弁は半年ほどで私にも伝染っていました。そのタカエさんにしても小倉で生まれ育ったはずですが、すっかり大阪弁がナチュラルになっていました。高石のお屋敷の前は守口という町に住み、キタの印刷所に通っていたと言い、「どこの大阪弁かようわからへんわ」と言っていたニュージェネレーションな大阪弁が、わたしたちの標準語になっていました。ニュージェネレーション。ちゃうよ、ニュージェネレイションや。ニュージェネ、レイション。だいぶ近なった。ニュージェネ……レイっション。
「あんた学校行かん言うた日、殴ったろか思たわ」
「なんやそれ。殴ったよかったやん。なんでいまいうん」
いまだったらちゃんと順序立てて説明できると思います。クソみたいな男をクソのようにあしらっていたら、本当に好きになられたので戸惑ったのだと。そう言っていれば一週間ものあいだタカエさんと反目することもなく笑い飛ばしてくれたんだと思います。小峰さんとの関係についてもアドバイスをくれたと思いますし、また学校へ行った可能性も捨てきれません。わたしはドラクエを中断して、スマッシュブラザーズに切り替えて、コントローラーをひとつタカエさんに渡しました。タカエさんは座り直してコントローラーを握って、わたしのスタートの合図にタカエさんがあごをしゃくって返すと、すぐにゲームがはじまって、空中に浮かせてコンボを叩き込んでいるうちに、タカエさんもわたしも少し顎のネジが緩んできて、気がつくとふたりともボルネオの猿のように雄弁になっていました。
「ストーカーおんねん、あのがっこ」
「そんなんおるんか」
「後ろから追いかけてきて、手ぇ握ってくるねん」
「きんも。わたしがかけおうたるわ。学校に」
「ええよ、そこまでしてもらわんで」
「あんた、人生かかってんねんで」
「大げさや、そんなん」
そしてゲームが終わるとまた冷静になって、「向こうは本気で好きなんかもしれん」と繕うと、「本気で好きやったら、そんなキショいことせぇへん」とタカエさんは汚物でも思い描いたかのような顔をして見せました。
第6章 淳一爺
苅田の神崎家はもともと小倉神崎家に仕える船頭の家系だったと言われています。江戸の時代までは坂本といったそうですが、坂本というのも苅田ではありふれた名前でした。
その時代から苅田と難波の間とで荷を乗せた船を運行させていたと聞きますので、小倉の神崎本家は地元でもそれなりに名の通った家柄なのだと思います。祖父に紹介された祖父の従兄弟、神崎淳一爺ももとは小倉神崎家のひとでしたが、のちに大阪近郊に在住し、わたしが知り合ったころは神崎グループの会社のひとつを任されていました。「そのむかし、東京でアニメ描いとった」と紹介された淳一爺の言葉の端々には小倉訛りが残っていました。
小倉弁には懐かしさを感じました。小倉弁といってもピンと来ないかと思われますが、要は北九州弁です。語尾に「~ちゃ」とか「~んよ」とついて、わたしの感覚だとどこか土佐弁にも似たように思えました。ただまあ、わたしが知っている土佐弁はアニメやドラマで使われる土佐弁ですから、現実のものとはまた違うのだと思います。
北九州のひとにとって、北九州弁というものはなく、八幡の八幡弁、小倉の小倉弁があるだけで、それぞれ似てはいても違う言葉で、わたしの耳には小倉弁は古く伝統のある音に聞こえましたし、八幡弁からはより新しい、そして少し雑多な印象を受けました。わたしのなかの、八幡、小倉、の印象は、実際に目で見た印象よりも、法事で集まる親戚の言葉遣いから受けた印象のほうが大きかったように思います。
わたしが生まれ育った苅田の言葉は、隣り合う小倉ともまた少し違って、のんびりと牧歌的にすら聞こえていたのですが、これも後に知り合った博多の出身の後輩からしたら北九州弁に聞こえるということでした。不思議な話ですよね。小倉弁、八幡弁を聞き分けて暮らしてきたのに、その隣の苅田の言葉が北九州弁だと言われるのですから。方言というのは、使い手の少ないマイナーな言葉だと思われているのですが、そこそこの話者がいないと、それこそ苅田弁とさえ言ってもらえずに、近隣の都市に吸収されちゃうんです。なんか、本気で北九州空港封鎖してやりたい気持ちです。
淳一爺を紹介されたきっかけは、おそらくタカエさんを介して、わたしが絵をよく描いていることが祖父に伝わり、そこからだと思います。淳一爺が東京でアニメを描いていたころ、タカエさんは中学生で、淳一爺が東京で活躍するさまにはほのかな憧れを抱いていたと聞きました。タカエさんはオタクには見えないし、単に「東京のテレビの仕事!」っていうだけの憧れだったのだと思います。祖父の従兄弟で、祖父はじぶんと同世代だからって理由で「淳一爺」と呼んで彼を紹介してくれましたが、当時淳一爺は五十代の半ばだったと思います。コンピューターを使って船の設計をする会社の社長でジジィだと聞いて、白衣を来たマッドサイエンティスト風の骸骨のような男を想像していたのですが、紹介されたのはふつうに背の高いスラッとしたナイスミドルでした。玄関を入ると祖父に挨拶した後、祖母の部屋に入り、耳も遠くなった彼女に語りかける懐かしい小倉弁の言葉がひとひらふたひらと漏れて聞こえました。
ひきこもりの漫画好きにとってアニメーター経験者というのは、それだけで尊敬に能うひとでした。そのひとがアニメを辞めたあとは巨大企業グループの一角の社長を任されているなんて、人類が手に入れうる究極の成果ですよ。淳一爺が訪ねてくるというその日は米津玄師や大谷翔平や花江夏樹がうちに来たってこれほど緊張しないだろうという高濃度の緊張に侵食されました。普段は客が来ても部屋に閉じこもってさっさと帰れと念を送るばかりでしたが、この日ばかりは部屋にいて、階下から聞こえる他愛も無い話と笑い声を耳にしながら、名前を呼ばれるのを待ちました。
そして聞こえてきたのは――
「ユミちゃん。まえ話した淳一爺来とるでー」
タカエさんが声を放り上げてくれたのですけど、「来とるでー」じゃリアクションできへんやろ。タカエさんはわたしのことをよく知っているはずやのに、距離感が近いせいか、ものごとの運び方が雑。「来とるでー」って。「ほーなん?」でおしまいやん。「話したいらしいでー」とか、「お土産あるでー」とかなら階下へ降りるきっかけにもなるのに、来とるでー。ほーなん? どないせえと。
それでのこのこ下に降りていったら「じぶんから話をしに降りてきたひと」になるわけでしょう? 高いねん、ハードルが。わたし、ひきこもりなんよ? しってる? なんでひきこもってると思う? 人間関係の距離感がようつかめんのよ。……と躊躇っていたら「ユミちゃん、絵ぇ描いてたやろ? 見てもらいい」って、更にハードル上げんなや。ほんまにもう。ひきこもりやっちゅうねん。それでのこのこ描いた絵をもって降りれるんやったら、そのまま学校行って卒業証書もろて帰ってくるわ。
直後、「ユミちゃん、タコ焼き買うて来とるけー」と、階下から通る声が響きました。さっきからわずかに聞こえていた淳一爺の声でした。さすがはわかっていらっしゃる。わたしは食い物にだけは目がないひきこもりなんです。タコ焼き大好き。アイラブ、えー、テンタクルス。テンタクルス焼き、大好き。
淳一爺から、「アニメーターのころの名前は横尾慶一郎やったっちゃ」と懐かしい小倉弁で自己紹介され、ペンネームかと思ったら、母が新興宗教にはまって離婚、名前もそこの偉い人の指導で改名されていたという地獄のような経緯を話してくれました。なんなんだそれは。一時は本人もその宗教に引き込まれながらも、小倉神崎家の働きで取り戻され、名前も父方の神崎に改名したのだそうです。その件以来、その宗教と神崎家とは反目した関係にあるそうですが、淳一爺の母はいまもその教団を信仰しているらしく、話しているとところどころ言葉が途切れることがありました。いやはや、それを笑顔で語られても、ですが、ひとの真剣な悩みも、認識にギャップがあるとギャグになりますね。困ったものです。
アニメーターを続けたのは4年ばかりだそうです。バイトで食いつなぎながら、なんとか食費と家賃とは工面したが、最後は母親を頼って生まれ故郷でもない大阪に帰るしかなかったと淳一爺は語ってくれました。そのなかで母の宗教のひとたちが懇意にしてくれて、じぶんも受け入れるしかなかったのだ、と。
なぜ宗教にはまったのかと問えば、淳一爺がアニメーターをしていたころ、ほとんどの日本人がノストラダムスの予言を信じていたことにも一因はあろうとのことでした。ノストラダムスの予言というのは、1999年の7の月に恐怖の大王が舞い降りて人類を滅ぼすとかうあれですね。16世紀の占星術師が予言した人類滅亡を信じるというのも、いまでこそ笑い話ですが、社会全体が信じているものを疑うのは難しかったと、淳一爺は振り返りました。要はまあ、淳一爺も信じていたんですね。小学生のころから「これが人類の最後だ!」と題されたイラストを見て過ごし、人類滅亡を示す「終末時計」がニュースになるし、人類滅亡は差し迫った現実の問題で、ひとはその救いを宗教に求め、アニメ業界も例に漏れず新興宗教に傾倒するものが多数在籍していたそうです。で、いまもタブーだから、触れないほうがいいって。いまもって。なんかもう、びっくり。
うえのひとが信仰する宗教の信者になることで仕事を回してもらえることもふつうにあったそうです。いまのわたしの耳にはとてつもない不正のように聞こえるのですが、でも当時のひとたちにとってはそれが「生き延びる」という至上の目的のまえに正当化され、不正とかなんとかそんなのは関係なくて、そうすることが人間としてあるべき姿だったのだと淳一爺はクールに熱弁をふるいました。
淳一爺に言わせれば、そもそも日本のアニメーションがノストラダムスの予言への日本人からのアンサーだったのだそうです。宇宙戦艦ヤマトしかり、超時空要塞マクロスしかり、北斗の拳しかり、エヴァンゲリヲンしかり、風の谷のナウシカしかり。かつて魔王とアポカリプスとアニメーションと宗教と哲学とは密接に関係していて、いまでこそ小学生の読むような雑誌で人類滅亡のビジョンが語られることはなくなったけど、他方では地球温暖化はそれ以上の危機をもたらそうとしている――とシリアスな話になり、その間わたしとタカエさんは「ええーっ」「怖いですねー」と真剣な顔を繕って聞いているしかありませんでした。
そしてこのアポカリプスも過ぎ去るころにやっと「どんなアニメを描いていたんですか?」と、大阪と東京のイントネーションが混じったへんな言葉で聞くと、「オリジナル・ビデオ・アニメが多かったかな」と語っては、妖刀伝、バブルガムクライシスというタイトルを挙げてくれましたが、私には馴染みのないものばかりでした。
アニメーターを辞めたあとは、しばらく警備員のアルバイトをしていたそうです。務めていた警備会社は研修が厳しいことで知られ、当時はメンタルタフネス研修と呼ばれるサバイバル訓練もあったと、クッキーの個装をギザギザがあるからそこから裂けばいいものを横に引っ張って剥きながら思い返していました。わたしはこの、話の最中のこのような動きをされるとそちらばかりに目が行ってしまう質で、そこちゃううやろ、縦にこう、あーもうわからんかなと、隊員たちは深夜に山に放たれて、夜明けまえまでに麓のチェックポイントに降りねばならず、その間に先輩に発見されたら熊退治用のスプレーを吹きかけられるという漫画のような研修で、淳一爺は警備員2年目に参加した折に事故に逢い、足首を骨折、補償もないままに放置されて、母親を頼るしかなくなったとのことでした。淳一爺が務めていたその警備会社は、その母君に誘われて踏み込んだ新興宗教と同じように愚かなものに思えましたが、淳一爺は「厳しい訓練を受けたから、じぶんたちはだれよりも優れてると思っていた」と振り返りました。わたしからしたら、とても現実感のない昭和の話でした。
タカエさんはなんどか、「絵は見せんの?」という意味で、わたしを肘でつつきましたが、その日は十分な勇気が湧きませんでした。部屋に戻って、じぶんで描いた絵を見返すと、2~3、ひとに見せるレベルのものはありましたが、ほかは最後まで仕上がってすらおらず、今日見せなかったのは正解だったのだとじぶんに言い聞かせもしましたが、それじゃあ次の機会はあるのだろうか、それまで見せられる絵を用意できるのだろうかと考えると、いっそ今日、「急なことでこれしかありません」と見せたほうが良かった気もしてきました。
それに、そうやって絵を見せたとして、どう言うつもりだったのか。
「アニメーターになりたいです」だなんて、考えてもみなかったことを言うのは変だし、「これでアニメーターになれますか?」と聞くのもねえ。ふつう、聞かないよ。それに、「わたしも絵を描いているんです」って、ひとに見せられる絵はせいぜい3枚。3枚見せられたところで、はあ? って感じでしょ?
それでその日の夜は、淳一爺に見せられる絵を描こうと机に向かってみたのですが、ハードルを上げすぎたせいか下書きの線からどう描いてよいかわからず、ただ顔の輪郭の線を描いては消すを繰り返しました。雑誌の絵を見ながら描くと、それなりのものができたので、まずはそれを何枚か描いて、あとは過去のじぶんの最高傑作を横に置いて、それを書き写して丁寧に仕上げてみたのですが、わたしの絵は丁寧に描けば描くほど歪んでいくのがわかりました。下書きを重ね、ペンでなぞって、下書きの線を消したときに出てくる絵はどうしてもこう貧相で歪んでいるのか。
ドラゴンクエストのフウラの絵は愛らしく描けたと思うのですが、でもそれだって小学生が描くような絵です。タカエさんがいつも可愛いと言ってくれるのもこういう絵で、わたしからしたらプロが求める絵じゃないんです。三頭身で、口をぱかっとあけて、手はうしろに回して見えないようにして、描くとしてもいちばん描きやすいパーの手を顔の横に添えるだけ。――でも、わたしだって、たとえばジャンケンするまえに手を組んでくるってやって片目で覗いてるようなポーズを描きたいんだよう! 鏡のまえで前髪をあげて、枝毛を気にかけてるようなポーズが描きたいんだよう!
ひさしぶりに再開したドラクエで、フウラの大活躍の場面にたどりついたのがちょうどこのころでした。姉とプレイしていたころのフウラは、どこか後ろ向きでいつもトボトボと歩いている印象が強かったのですが、じぶんの手でプレイしながら味わう世界では、まるでヒロイン同然の輝きを見せてくれました。フウラのお話は物語のなかのことながら、わたしに勇気を与えてくれました。前向きにやっていれば、いつかわたしにもエルドナ神が降りてきて、だれかを救うことができるかもしれない。わたしが何かにならなくても、「依代」になればいい。そう思うと、いま遊んでいる物語がじぶんのことなのかフウラのことなのか、頭のなかではごちゃまぜになった状態で涙がポロポロと零れてきました。わたしが何かを頑張るのはわたしのためじゃない。だれか大切なひとを守るためなんだ。だから傷ついても諦めちゃいけないし、嘆く必要もない。へっぽこでいいし、へっぽこだからこそやんなきゃいけないことがあるんだ、と。
わたしはフウラになりたい。彼女が何度も「若葉の試み」に挑んだように、わたしも挑めばいい。わたしが淳一爺に見せる絵はその最初の一回だ。フウラだってそこで失敗したんだし、そこでくじけなかったから世界を救ったんだ。
大阪はどこが中心とは言い難い大きな街ですが、淳一爺の会社はその街の中心の候補の一角にありました。碁盤の目のように道路が行き交い、歩道もない狭い通りの両側に高いビルがきゅうきゅうにひしめくなかに、神崎グループのビルがあり、その4階に淳一爺の会社、神崎船体設計のオフィスがありました。船の設計をする会社だと聞いていたので、コンピューターがたくさん並ぶなかで作業服を着たひとたちが図面を引いている姿を思い描いていましたが、オフィスにはデザイン事務所のような洗練されたインテリアと、雑多に積み上がった雑誌や資料とがありました。あと、サボテン。
聞けば、いまは船の設計をすることはほとんどなく、あったとしてもここではインテリアのデザインや電気配線などを設計し、それも細かい設計図は下請けの会社に頼んでここでは管理するだけなのだという話でした。じゃあ、船体設計ってなまえはなに? みたいな。
神崎グループも以前と比べるとはるかに大きな規模になり、いくつもの子会社に分かれて、統廃合が進み、昔からあった子会社も時代に沿って役割を変えたのだといいます。淳一爺の会社は、たとえば客室のレイアウトを変更する時、たとえば液晶型のテレビを導入する時、あるいはイベントのために船内の什器を変更する際に、電源や配管の設計から発注、施工、監督、役場への届け出などをするのが主な業務なのだそうです。
最近では旅行会社が企画するイベントと連携することも多く、本来なら専門の別の部署があるにもかかわらず、祖父と淳一爺の間からこちらに回されることが多いのだと笑っていました。子会社のなかでは古株で、小倉のなんとかというグループの出資もあって、本社からはいろいろとお目溢しされることが多く、淳一爺いわく、「最後の抜け道」とのことでした。
淳一爺はアニメと警備員とをやってきて、そのまえは大学も出ておらず博多のアニメの専門学校に通っていたと聞きました。そんななかで、東京で知り合ったアニメーターのなかに、やはり大阪に本社を持つ工業部品大手の息子がいて、そのひとと始めた事業の成功などを経て抜擢されたというのですから、才能はあるのだと思います。淳一爺はそれをただ「運がよかった」と振り返るのですが、その運をちゃんと形にできるのは実力なのだと思いました。
わたしとタカエさんとふたり応接室に通され、淳一爺は多くのパンフレットや雑誌の切り抜きのファイルを抱えて現れました。それは淳一爺が社長になってからのこの会社の集大成でした。アニメでは芽が出なかったけど、これらがいまこうして形になった、ビジネスサイトのインタビューにも出たと、照れながらその切り抜きを見せてくれました。
「今日はユミのほうからも見せるモンあるねんな」と、切り出してくれたのはタカエさんでした。この言葉がなかったら、もしかしたらわたしはなにも見せずにすごすごと高石の屋敷に帰ったかもしれません。
かばんをゴソゴソしはじめると、「おっ」と言って、淳一爺は目を輝かせました。
「いやぁ、思い出すわ。おれも三十ウン年前、絵ぇ持って上京したっちゃあ」
淳一爺の言葉は小倉弁と大阪弁のキメラでした。その混じり具合は逆に器用。
「でも、わたしのはそれほどでも」
「かまへんかまへん」
恐る恐る見せた絵は5枚。ここで本当に絵が描けるひとだったらスケッチブックなり、クリアファイルなりをどーんと机に置いたのだと思います。
「これだけなん? ほかのはどうしたん?」タカエさんがわざとらしく声を上げました。
「ひとに見せられるの、これしかない」
「んなことないよー、わたし何枚も見たやん、なんで持って来ぉへんのー」と、わたしの代わりに「本当はもっとたくさん描いていること」をアピールしてくれるタカエさんに、「ええよええよ、多い少ないでもないし」と、淳一爺は笑って応えました。
そこに「デザイナー採用しはるんですか?」と割って入ったのが、この会社のホームページを作っている藤島さんでした。藤島さんとはこのあといろいろあったんですが、最初の印象は「事務のおばちゃん」でした。
「ええやろ? どう思う?」
お茶を持ってきた藤島さんに、淳一爺はわたしの拙い絵を取り上げて見せました。
「可愛えなー。合格や。高校生?」
事情を知らない藤島さんはそう言ってわたしの顔を見て、その瞬間、淳一爺が固まったのがわかりました。わたしはとくに、高校に行ってないことが禁句というわけでもないんですが、まわりが気を遣っているのを見ると、やっぱりその、なんというか、キョドりますよね?
「あ、これ、あかん空気や」
空気を察するのも早いし、それを口にするのも早いという、藤島さんの高速カウンターでした。
「あ、気にせんでください。高校行ってませんけど、本人気にしてませんので」わたしが言うとさすが大阪、お笑いの都です。「あんたは気にせなあかんやろ」とタカエさんがツッこんでくれました。
淳一爺は、さすがにここで更に被せて良いものかと、リアクションに困っているようでした。あるいはまあ、藤島さんの言葉に戸惑ったのか、あるいはやはりわたしの絵が拙く、それもたった5枚しか持ってこなかったのが引っかかっているのか。
笑いというのは出口なんです。他愛のないギャグで笑えるのは、そこから逃げ出せるからなんです。わたしがその場の空気が耐えられず、テーブルの上のスナックを手にとってモノボケ的なことをやって凌ごうかと考えていると、淳一爺が静かに口を開きました。
「アニメーター時代の知り合いがいるんで、ちょっと話してみるわ」
話してみる? って、えっ? なにを? って、なにを言ったのこのひと? と思ってタカエさんを見ると、タカエさんも同じ顔でこちらを見ていました。タカエさんもきっと場の空気を変えるネタを探し、それが喉にでかけた瞬間の淳一爺の言葉だったのだと思います。わたしも大阪には来たばかりですが、ボケとツッコミでかわせるところはそれで行ってまえみたいな感覚が芽生えていて、淳一爺の真面目な言葉には戸惑いました。藤島さんも同じなのだと思います。大げさな二度見をして戸惑っていました。
いやもう、なんかようわからんけど、ここは、ボケるしかない!
「もしかしてわたしも、アニメーターデビューですか?」
「うん、そうなるといいね」
だからツッコむんやて! こういうときは!
第7章 なむりん
藤島さんは、神崎船体設計のホームページを作っているひとだと、タカエさんが教えてくれました。そのときの本職はマネージャーで、権利関係の手続きや、工事やイベントの手配を手掛けているという話でしたが、新人時代に? ホームページを任されて? そのとき始めたハンドパペットを使ったコーナーがいまも人気で? それをいまさらやめたくなくて、ずっと昔のスタイルでやっているのだそうです。
本来ならあの規模の会社のホームページはちゃんと業者に頼むらしいのですが、藤島さんの前職がIT関連のデザイナーだったこともあって、まだどの企業も事務的なサイトしか持ってないような時期にそのページを作ったという話でした。デザイン性に優れ、前述のパペットを主役にしたコーナーを始めたり、ツイッターのサービスが始まるといち早くアカウントを開設したり、小さなデザイン事務所ならではの足回りで運営してきたのだそうです。ただ、開設から20年近く経ち、内部の仕組みは当時の基準からしてみたらボロボロだったそうで、それを改修するためには5百万くらいかかると見積もられて、仕方なく古いままで運用していたとのことでした。当時わたしもそのサイトを見たのですが、デザインにおいては神崎グループのなかでも屈指の出来栄えでしたね。が、しかし。それも内部のコードを見たら(どうすればそんなことができるかはわかりませんが)世代が古いことは明らかで、この実装では世のハッカーたちが喜んでターゲットにするだろうと指摘され、グループの監査でもたびたび問題になっているとのことでした。ただ、藤島さんに言わせれば、この監査も言いがかりに近く、実際にセキュリティーホールが指摘されたというよりは、ホームページ制作費が予算として計上されていないための憶測だったという話です。グループのほかの会社、とくに本社などと比べると、向こうはホームページの制作と運用に億の金をつぎ込んでいるわけですし、そこに社員が手隙の時間に作っているページが並んでいるのが理解できなかったのでしょう。もちろん、監査の言う通りに外部に出すことはできたわけですが、そうなると人気のパペットのコーナーはなくなってしまうわけで、それでのらりくらりと躱しているのだと、社長の淳一爺も笑って言っていました。
このあたりの事情はなにやら非常に込み入った話ではあったのですが、タカエさんはそれら諸々の事情コミコミで受け取りながら、「手に職があるってのは、最高よね」と、気楽に感心していました。わたしこの、タカエさんの、あらゆるディティールをなかったことにできる能力、ちょっとうらやましいと思った。
高石のお屋敷で淳一爺に会い、アニメーター時代の知り合いに云々という話を聞いて、恥ずかしながらわたしの胸のなかに「アニメーターになれるかもしれない」という思いが芽生えていました。
結果だけを見れば、事実そうなってるわけだし、「淳一爺はあなたの才能をちゃんと見て取ったんだよ」、とも言われるかもしれませんが、あのとき見せた絵がそんなに良い出来ではないことはわたしがいちばんわかっています。でもそれだって、いまになってそう思ったって話でしょ? と、聞かれたら、うーん。当時のわたしはたしかに、ほんとはすごい才能があるのかもしれないって妄想がどんどん膨らんで、脳から変な汁出まくってましたね。
わたしはどうしてもほら、たとえばイラストを描いたりしてるときも、雑誌に送ったらものすごく評価されて、すぐに仕事の依頼が来たりするんじゃないかって考える質でしたから、あの数日間は胸のなかのハムスターが妄想のマニ車を回して止まりませんでした。
調子に乗るってのは、人生においてとても大切なことだと思います。しばらくしてまた淳一爺が高石の屋敷を訪れるまでに、わたしはアニメーターになるための絵をたくさん用意してましたから。
――ちなみにわたし、マニ車って、ハムスターが回してるあの車のことだと聞いて信じてた時期があって、あとになって本当はチベット仏教か何かのものだから表で言わないほうがいいよって聞いたんですけど、いちど刷り込まれたらおしまいでしょうよ、そんなもの。
淳一爺の事務所の見学をしてから十日ばかり経ったころでしたか、また淳一爺が訪ねてくるというので、わたしはすっかりアニメーターに採用されるかどうか、その結果を伝えに来るのだと考えて舞い上がっていました。楽観してるわけではありませんが、いや、してたかな? してた? おそらくまあ、前回渡した絵ではまだわからない、可能性は感じたがまだ判断はできない、くらいの返事だろうなぁとは考えていました。
最悪、ぜんぜん駄目だったって答えが返ってきても、まだ本気を出したわけでもない、今日用意した絵のほうが何倍も良くなってるし、二の矢三の矢と放てば必ず道は拓けるという謎の自信がありましたね。
当日は、「あんた、先生じゃないんだから、じぶんから動かなきゃダメよ」って、左後頭部あたりにタカエさんから釘を刺されて、その日はわたしの方から階下に降りて、「新しいのも描いたので見てください」って、淳一爺にスケッチブックを渡しました。
緊張? しますよ、それは。お茶を飲む間もなくスケッチブックを渡された淳一爺は「積極的だねぇ」と笑って受け取って、ページをめくり始めたのですが、その時間はずっと、「わたしはフウラだ。あの子が頑張ったみたいに、わたしも頑張るんだ」というひとことを胸のなかに繰り返していました。
淳一爺はスケッチブックを最後までめくり終えると、「うん。いいと思う」と言って、テーブルの上のお茶に手を伸ばしました。
「いいと思う」
なんかもう、そのひとことはハート型の砂糖を溶かしたように、胸のなかにぱーっと広がっていきましたね。ラブ。これがラブかぁ。あったかい……みたいな。
それで祖父がわたしのとなりに座るまえで、淳一爺はお茶を飲みながら、じぶんが上京してスタジオをまわって、いろんなひとにスケッチブックを見せた日のことを語ってくれました。
当時、アニメの専門学校にいて、仲間たちと4人で上京したんだそうです。いくつかスタジオを回って、話を聞いてもらって、ある程度話をすると「それじゃあ、持ってきた絵を見せてもらおうか」って話になって、そのときはさすがに緊張したと、淳一爺は心臓のあたりに手を置いて振り返りました。
うんうん、緊張、わかる。なんかもう、ひとの恋バナを聞くのってこういう感じなんだろうなっていうドキドキを感じましたね。せんけど。恋バナ。
続けて、そうやって絵を見せたあとは、絵が上手いひととそうでないひととで向こうの態度が変わったと、漏らしたのですが、そのときの声のトーンは唐突に風が凪いだように静かでした。
絵を見せる前は4人均等に視線を移して話していた相手が、見せたあとは一番上手いひとにだけ語りかけているのがはっきりとわかって辛かった、って。向こうははっきりとダメだとは言わない。決してこちらの夢を砕いたりはしない。だけど答えを胸の中に持っているのは見てわかった。それを複数のスタジオで経験して、アニメーターになるまえに勝手に砕けそうになっていた、と。
えーっと、そんな話をするということは、なに? どういうこと? まさかねえ、「わたしの絵じゃ、やっぱりダメですか?」と、上目遣いに聞くと、「あのころのおれよりずっと上手いよ」と、淳一爺は答えてくれました。
いま思えばお世辞ですよ。お世辞にしても微妙であることはさておいても。わたしが母と同じ気質を受け継いでいることは、祖父も淳一爺に伝えていたと思います。すぐ壊れる。すぐ駄目になる。それがあのころのわたしでしたから。
淳一爺は、「それに絵は究極的に言えば上手い下手じゃない」と続けました。
またこれもちょっと
それで、「でもアニメーターになるとしたら、デッサンですよね」って、わたしが聞くと、淳一爺は「あれをデッサンとは言わない」と、世のオタクに聞かれたらと思うとそら恐ろしい言葉を発しました。
絵はすべて文脈で評価されるのだそうです。アニメーションのデッサン重視の絵が重宝されるのもアニメーションという文脈の中にあるからであって、その文脈から外れたらあれらの絵は「デッサンが優れている」とは言わない。ひょえ~~~~! デッサンによってアニメーションが支えられているのではなく、アニメーション文化がアニメ用のデッサンという概念を作り出している。ひょえ~~~~! みたいなことを言っていました。ちなみに、途中のひょえ~~~~! はわたしです。
そしてそのアニメーションの文脈はいまだに魔王であり、アポカリプスであり、宗教であり、生と死の哲学であり、人類の滅亡なのだそうです。そして、そこから考え直して新しいものを作り出すとしたら、いったんデッサンのことは忘れていい――と、やっぱりわたしのデッサン力が足りてないことを暗に示したような言葉を並べられました。
だけど同時に、淳一爺のデザインに対する視点がわかった気がしたっていうか、いや、これはまあ、気がしただけで、デザインがただ表面的なものではなく、もっと時代? とか、世界? とかに通じた大きなもの? だと感じたくらいで、それをどうすればよいかまではわかりませんでしたけど。
思い出語りを終えると淳一爺は、フェイスブックの知り合いから、ゲームの開発チームがひとつ浮いていることを相談されていると、祖父に切り出しました。優秀なチームだけど、製作がうまく機能していなくて、作品は完成させたものの発売には至らなかった。会社側はその作品のプロモーションビデオを作ってディベロッパーに売り込みにかかっている。そのゲームが4億程度、あるいはもっと安く手に入る。が、注目すべきはそこではなく、開発したチームの方に独立の意志があるところだ、と。
唐突に祖父とその話が始まって、少し呆気にとられました。そもそもこの話、ふたりの間ではもう何度か話されていたらしく、祖父も「条件はわかっている」「こちらでもあたってみた」と応じて、ああそうか、今日はこの話をしに来たんだ、わたしの絵を見るためではなく、別の話だったんだ、そういえば、アニメーター時代の知り合いに見せた結果は聞いてないし、わたしの空回りだったんだって、なんかちょっと恥ずかしくなって、肩を落としたときでした。淳一爺はこう切り出しました。
「このチームを使って、ユミちゃんのキャラクターでゲームを作って、会社のプロモーションに使うのはどうかなち、持ちかけとるっちゃ」
まさかの展開でした。冗談かと思ったくらいです。このときの淳一爺の意図はいまならなんとなくわかるのですが、あのときのわたしはただ神か仏が現れたように思いました。ポロポロと涙がこぼれ始めたのを覚えています。
淳一爺はわたしのスケッチブックを祖父に渡し、祖父はそのスケッチブックを1ページずつ丁寧に眺め始めました。人生でいちばん緊張した瞬間だったと思いますが、わたしはいったい何を評価されたのかわかりませんでした。なぜ、どうして、いつのまにわたしの絵でゲームなんて話に? これで祖父が頷いたら、あるいは首を振ったらなにが起きるのか。それが一切想像もできないままに、ときばかりが流れました。
神崎グループは巨大な海運会社で、役員には銀行からの出向もあり、経営は自由ではありませんでした。当時ははっきりとそれがわかるわけもなく、社長や会長なら会社のお金を自由に投資できるものだと思っていたのですが、実際にはかなり難しかったようです。淳一爺の会社が抜け道のように機能しているとはいえ、常に監査の目は光っているのですから、なにをするにしても社内での稟議は必要になるのだと、いまならわかります。「ひきこもりの孫のためにゲームを作る」が、どれほどの覚悟のいる決断か、それが決して簡単ではないことも。
祖父は絵の描かれたページをゆっくりと最後までめくり、白紙のページをパラパラと最後まで送ったあとで、少しうなだれて、間をおいて、ようやく「ユミちゃん。あのな」と、意を決したように口を開きました。
「宗像の、恵美子さんの実家。あっちにはずいぶん世話になった」
祖父の話は意外にも、母の実家の話から始まりました。なんかこれは、ええ? どうして? って、わたしの思考がぐるぐると巡るなか、少し間をおいて、言葉を選びながら祖父の話は続きました。
「正直な。後悔もしたよ。娘を返せって何度か電話も来た」
後悔? 後悔って? わたしのこと? どうやらそうらしい。娘を返せって、お母さんから? もちろんそんな電話のこと、わたしは知りませんでした。
「でもまあ、断った。まだ時期やないゆうて」
祖父の言葉はとぎれ、だけど目線はテーブルのうえに揺れ、次の言葉を探しているようでした。
「向こうには、ユミ、おまえ高校通うとることになっとーねん。それでこっち残るゆーとる伝えてある」
わたしは高校を辞めたことを取り繕うべきか戸惑いながら、言葉を待ちました。
「高校辞めた聞いたときは、失敗した思たけど……でも、彩乃に声かけてくれたやんか」
彩乃というのは祖母のことです。
「学校行こうしたのも、彩乃のためゆーとったやんか」
そこまで来ると、祖父の目からついに涙がこぼれました。祖父はテーブルの端に置かれたティッシュケースからティッシュを一枚取って、涙を拭いて続けました。
「なあ、ユミ。ひとつだけ約束してくれ。彩乃が逝くまで、そばにいてやるて。それだけ聞かせてもろたら、あとはもうええ」
そうやっていきなり凄まじい選択を迫られました。「あとはもうええ」のあとがなんなのか想像もできません。ただただ途方もない選択を迫られていることだけがわかりました。祖父が母の実家にどう世話になったのかもわたしは知りませんし、もちろん母がどんな気持ちで娘を返せと電話してきたかも知りません。父と姉がそれにどう対応したのかも知りません。だからあっさりと高校も辞めたんです。家族が抱えた事情に比べたら、わたしが高校を辞めた理由なんて、小峰さんに会うのが辛かったって、たったそれだけでした。
わたしはなにもわからないまま、「わたしの絵でいいんですか?」と、あらためて淳一爺に聞きました。そう聞けばきっと、淳一爺は優しく答えてくれる。決意の定まらないわたしの背中を押してくれる。そのくらいの気持ちで尋ねましたが、返ってきた声は何かを噛み潰したような苦渋を含んでいました。
「ひとに絵を見せる人間が、わたしの絵でいいかなど問うたらいかん」
それは、実家にいたころのわたしだったら、パニックになって暴れだしたほどに衝撃的な言葉でした。いままでなんどか、泣いて暴れて、母に羽交い締めにされたことがありました。この言葉を聞いたときそうしなかったのは、甘えられる母がいなかったせいなのかもしれません。わたしは覚悟を迫られたのです。その覚悟の中身は見えないままでした。思い返せばわたしがアニメーターになると言い出したのは、タカエさんが勝手にわたしの絵を褒めだしたからです。わたしからアニメーターになりたいなんて言ってないはずです。それなのにその決意を、いま、このとき、わたしの一存でしなければいけないのか。
だけど――
だけどわたしはフウラだから。
ねえフウラ、わたし、あなたになれるのかなフウラ、って、フウラのことばかり胸のなかに繰り返して、フウラだったらきっとこう言うと思って、
「ずっとお祖母さまのそばにいます。約束します」
そう口にしました。
それからすぐ、祖父は屋敷を抵当にいれて2億の資金を調達、浮いているというソフトウェアチームに打診し新しいソフトハウスを興しました。わたしはその2億という金額に衝撃を受けましたが、タカエさんが「神崎家は、ユミちゃんのお母さんの実家から、20億都合してもろたことあんねん」と、目をそらしたまま教えてくれました。そういえばバブルの少しまえに会社が危機に陥った話を聞いたことがありました。
「八幡に製鉄所持ってはったんよ。それ手放して神崎を救ってくれてん」
母の宗像の実家には従兄弟が住んでいました。両親は駅前に洋品店を営み、そのほかに資産があるような話は聞きませんでした。わたしが生まれたのはバブルから20年経ったころです。神崎家と母の実家のエピソードはそこから更に遡ります。わたしにとっては、洋品店の母の実家と、会社勤めの我が家、というのがあたりまえの景色でした。
チームが動き出すとすぐにわたしはキャラクターデザインをすることになりました。これはもう、腕の見せ所と言うか、わたしも責任重大です。
ただ、新参のソフトハウスがゲームを出したところで、それを十分に告知できなければ売上は伸びないということで、そこは淳一爺の会社のホームページとの連携で乗り越えることになりました。
藤島さんがゲームの開発のほうも窓口になってくれるということで、わたしもたびたび打ち合わせに行きました。わたしのアイデンティティ! ひきこもりはどうなった! いやもう、そんなものはどうでもいい! アイデンティティより未来だ! 未来は金だ!
ゲームのシナリオに関して見積もりを取ったら、ゲームの内容が固まっていないため百万から5百万というアバウトな数字しか出てきませんでしたから、それならと、わたしがシナリオライターとして名乗りをあげました。いまにして思うと、痛恨のバカでした。シナリオライターというのはセリフを考えるひとくらいにしか思っていなかったので、百万も5百万も取るのはボッタクリもいいところだと義憤に駆られての行動でしたが、義憤に駆られようがバカはバカでした。
「わたしだったらたぶん3日で書ける」
「いやいや、無理しないで。2週間あげるから、それで書いてみて」
という話をしたくらいですので、藤島さんにもゲームのシナリオは理解できていなかったのだと思います。後に知ったのですが、ゲームのシナリオは、ゲームのどのタイミングで、どんな仕組みで文章を表示するかを制作側と細かく打ち合わせて調整する必要があり、そこが理解できていないとプロジェクト全体が停止してしまう非常に繊細なポジションだという話でした。
何度目かの打ち合わせで、神崎船体設計のホームページでプロモーション用の漫画を掲載するという話が挙がりました。ゲームの発売日まで毎月1回、1年に渡って連載して、そのお話をゲームに続ける、というのが藤島さんからの提案でした。それを聞いてわたしは、漫画だったらだれにも負けないと思いました。なぜならわたしはバカだったからです。漫画を描いたことはありませんでしたが、好きな漫画はたくさんありましたし、じぶんなりのストーリーを考えることもよくありました。ここでも「わたしが描きます!」と手を挙げたのですが、ここは「いや、ユミにはぜんたいのディレクションをしてもらわないといけないから」というふわふわ言葉で却下されました。藤島さんはデザインのセンスもあり、わたしの絵も見ていたので、無理だと察したのだと思います。まあ、いまにして思えば、それでもかなりの譲歩だったと思います。20年手塩にかけたサイトに、どこの馬の骨ともしれぬ素人の漫画が掲載されるわけですから。
それで、わたしが書いたストーリーに沿って漫画を描いてくれるひとを、最初は広告代理店経由で探したんですけど、カラーだとページあたり6万などとふざけた値段を提示されて、藤島さんが「フレッシュジャンプの新人漫画家なんかページ2千円だったんだぞ」と、謎のキレかたをしていました。モノクロで納品してもらって、色は藤島さんとわたしで塗って、という条件で再度代理店をあたって、サンプルの絵をいくつか見せてもらったんですが、昭和かよっていう古臭い絵とか、教育テレビのイラスト風とか、あきらかに漫画描いたことのないひとの絵とかしかあがって来なくて、そちらは最終的には淳一爺のツテを頼って探してもらうことになりました。
ただ、そちらは少し時間がかかりました。藤島さんの話では、代理店はつねに人材に当たりをつけていて、商売としてひとを探してアサインしてくれるけど、ツテで頼むと知り合いが仕事の合間に思い出したら声を掛ける程度のものになり、いつ返事が来るともつかないものになる。それだとプロジェクト全体のスケジュールが組めないので、代理店や人材紹介を通して確実に組み上げるのがビジネスの基本であり、そこがマネージャーの仕事なのだ、とのことでした。だから藤島さんとしてはここで淳一爺を頼ることには少し不満はあったようなのですが、こと漫画やアニメの話では専門のひとに聞くのが間違いないだろうということで渋々譲った形になりました。
このプロ意識の高い藤島さんにとって、会社のホームページは、20年かけてき育てあげた愛着と、専門の業者に任せるべきという思いの間でせめぎあいがあったようです。サーバを設定してくれたエンジニアもいまは退職し、じぶんで保守はしているけれど詳しい仕組みまでとなると手に負えない。社長からたまにああしてくれ、こうしてくれとリクエストは受けるけど、ほかの会社のホームページでできるからといってわたしにできるとは限らない、と愚痴のような言葉も耳にしました。
漫画を描いてくれるひとが見つかるまで3ヵ月ほどかかったと思います。純一爺の古い知り合いだという制作進行のひとから連絡が来ました。制作進行というのは、ひとを探したり仕事を発注したりする、業界のことに詳しく顔の広いひとです。そのひとを経由して紹介されたのは、六十も近い老アニメーター。漫画の経験は学生時代にあるだけ、現在は原画、作監、演出をしていると聞いて、わたしが、また昭和の絵が来るパターンだと警戒したのは書くまでもありません。淳一爺と知り合いなのかどうかは不明でしたが、ウィキペディアに名前はありませんでした。
第一報から数日、淳一爺の会社に呼ばれて、その応接室で件のアニメーターのポートフォリオを見せてもらったのですけど――そのときはほんとにもう、足が震えましたね。そこには彼が手掛けたアニメの原画や背景原図、絵コンテ、作監修正紙まであって、キャラクターも美少女から老人、少年、怪物となんでもあり、しかもわたしが見たことがある作品ですよ。憧れのアニメーターが実際に描いた線があるんですよ。
「どう?」って、淳一爺は聞いてくるけど、どうもこうも。「素晴らしいです」って声を震わせて言うしかありません。
「漫画はもう30年以上描いてないらしい」
「30年前に描いてただけで十分です!」
絵コンテに描かれたストーリーの流れは漫画のコマ割りと共通するものがあると思いました。なんの経験もないわたしがそんなことを考えるのは、じつに尊大な話です。でも、手応えを感じていたのは事実です。その手応えの正体を探るために、背景原図に描かれたパースのライン、絵コンテに書かれたライティングの指示、原画に書かれた中割の指示まで細かく胸に刻みました。
これがわたしとなむりん師匠との出会いです。いや、まだ本人同士は顔を合わせていないのですが、脳天からヒノカミ神楽でも叩き込まれたような衝撃は忘れようがありません。
本当にこんなすごいひとがわたしのキャラで漫画を描いてくれるのかと疑問も湧きましたが、そこは淳一爺のカリスマでしょう。淳一爺がアニメをリタイアしながら、いまこうやって会社を切り盛りしている実力に魅せられて動いてくれるんだと、わたしは思いました。
さあ、次はわたしのターンです。
淳一爺からは、まだ条件の交渉中で契約には至っていないと聞きました。
「キャラクターはこれです。物語はこうです。漫画の雰囲気はこうで、このように展開します」と伝えるのはわたしの役割です。
そのときどれほどの高揚感があったか想像できますか?
当時のわたしの画力については、『アニメーターの老後』に師匠の視点で書かれていると思います。まあ、想像つくので読みたくもありませんが、その程度の絵しか描けないわたしがどれほどに盛り上がったか。その姿は滑稽だったかもしれませんし、藤島さんは内心ドキドキしていたかもしれません。このあとすぐ藤島さんは会社を去ってしまうんですけど、それもいま思えばわたしのせいなんです。社長の道楽で2億という大金が動いて、ひとを巻き込んで火遊びしているような会社、だれだって考えますよね。でも当時は、ものすごいプロジェクト――それこそドラゴンクエストの次を狙えるようなプロジェクトがわたしを中心に動き始めたんだという気持ちがあって、藤島さんの気持ち、もっと言えば淳一爺の気持ちも祖父の気持ちもわかっていませんでした。
そんなプロジェクト成功するはずがない、って言ってくれるひとがいなかったのは、良いことでもあり、悪いことでもありました。これもあとで知ったのですが、制作チームに渡った資金は7千万で、残りの1億3千万は淳一爺の会社の債務の支払いに消えていました。わたしは利用されていたんです。祖父だって気がついていました。知らないのはわたしだけ。でも当時わたしが気がついていたら、じぶんがなにをしでかしていたか想像もできません。だけど、ならばいまのわたしが当時のわたしに声をかけるとしたら、どう言うでしょうか。答えは、「そのまま走れ」です。あなたのまえには信頼できる師、名村英敏がいる。走れ。とにかく、走れ。彼が目の前に現れたのは単なる偶然です。わたしの生まれた家が裕福だったことも、淳一爺の人生と交差したことも、タカエさんも、藤島さんも、すべての出逢いは偶然です。でも、チャンスを得たんです。いままであなたは何度も手首を切ったでしょう? なんの覚悟もなかったの? ただひとの目を引きたかっただけ? あなたがノートに記した、人生に絶望した、世界はわたしを愛さない、は嘘だったの? 走れよ。走るしかないでしょう。駄目だったら腕ごと切り落としなさいよ。そんな腕、ついてるだけ無駄なんだから。
渾身の作をクリアファイルにコレクションして、淳一爺に預けました。
数日経って、藤島さんから「契約完了しました」のライン、先方が詳しい話を聞きたがっているというので、なんどか制作進行のひとを介してやりとりしたのですが、やり取りをするうちに、わたしもそのメールのグループに加えてもらうことになりました。メールというのは低機能のラインのようなもので、いまではほとんど使われることはなくなりましたが、当時は親しい間柄ならライン、ビジネスの話などはメール、という棲み分けがありました。わたしは書き溜めた設定と、キャラクターのイラストをまとめてなむりん師匠に送りました。
それを読んだなむりん師匠の返事に、もちろんお世辞ですが、「可能性を感じました」とあり、わたしはプロジェクトの成功を確信しました。
第8章 門出
わたしが考えたのは、みっつめの目が開くと見たものを石に変えてしまう能力を持つヒロインの物語でした。このヒロインが仲間たちとドラゴンを倒しに行くんです。で、ドラゴンも同じ能力を持っていて、最後になんと! ヒロインは石に変えられてしまいます! うわー! やばい! 人類は滅亡してしまうのかー! と、絶望のヴェールが大陸を覆ったとき、仲間たちの友情でヒロインは息を吹き返し、もういちどドラゴンを討ちに行く……というお話です。
わたしはこのお話を書きながら、ヒロインが石になる場面、仲間たちが力を合わせて石化を解く場面でボロボロと泣いてしまいました。ヒロインはじぶんが死んでしまうことを知りながらドラゴンに挑んだのです。
物語の最初のハードルは書き手自身がその物語に感動することだって、どこかの漫画家が言っていた言葉が思い出されました。わたしはそのハードルを超えたし、あとは形になっていけば自然とひとに伝わるのだと思いました。あ、いや、マジでこれを書いたときは、そう思っていたんです、恥ずかしながら。
いまはその物語の欠点がわかるようになりましたが、当時はそれがなむりん師匠にうまく響いていないことに、ものすごく苛立っていました。わざとわかんないふりしてんのかなぁーとか、物語読む素養ないのかなぁーとか。
いまにして思えば伝わらないのは当然で、欠点は明らかでした。わたしはいくつかの物語をツギハギしてこのお話を書いただけなんです。だから当然わたしは、元の物語の場面を知ってるわけで、ヒロアカのあの場面とか、呪術廻戦のこの場面とかを連想して、それで泣いていたんです。ヒロインも、それを助けてくれる仲間たちも、敵方のライバルも、みんなどこかで見たキャラクターだし、それで感動できるのはわたしだけだってことが、あのころのわたしにはわかっていませんでした。
どうして伝わらないんだろう。
だって、ヒロインの兄は同じ理由で死んでいるんだよ?
などと思っていたわけですが、そんなことどこにも書いていなかったので、伝わるはずがないんです。
なむりんとはしばらくメールでやり取りしていたのですけど、メールはどこか面倒だし、味気ないし、じぶんの言いたいことの半分も伝わっていないような気がして、途中からはラインに変えてもらいました。クリエイター同士、外の意見に惑わされず意見を出し合うことって大事だと思ったんですけど、祖父がふたりだけのやり取りに反対して、仮にふたりでやりとりしたものでも、あとですべて見せるという条件が付けられました。もしかしたらわたしがその、いわゆる援助なんとかみたいなことをすると警戒されたのかもしれませんが、まあ、半分くらい見せれば納得するだろうと思って受け流していたら、なむりんも同じように言われてたみたいで、けっきょくふたりのやりとりはすべてなむりんから祖父に公開されていました。
そうそう、そのなむりん――なむりん師匠なんですが、最初のころはちゃんと名村先生って呼んでいたんです。でもやっぱりそれだと言いたいことが伝わらない気がして、ラインに変えたときに「やっほーなむりん!」ってメッセージしたら、「だれにその呼び方聞きました?」って。もう、ウケたのなんのって。わたしが呼ぶまえからなむりんって呼ばれてたって、それってもう生まれつきなむりんってことでしょう? それまではちょっと、頑固なわからず屋で、ちょっと怖いひとかもしれないって思ってたんです。それが、なむりんですよ? そう呼んだ瞬間からすべて話せる友だちになったように感じました。
ただそれでもねー。立場上なのかもしれませんが、事務的な話が多かったです。
「ヒロインはどうしてその能力が使えるんですか?」
「仲間はどうして彼女を支えるんですか?」
って。
わたしはそういうのはあんまり考えないで、わーっと進めばいいんじゃないかなと考えていましたし、ある意味いまもそれで正解のような気はします。でもそう言うとなむりんは、「表面的にはそれで描くと思いますが、キャラクターの背景を知ることで云々……」って。あーもう、そういうのはぜんぶなむりん考えて! って感じ。原作者としてはそういうのはどうでも良くって、パッションが欲しいの! なむりんが言ってるのは、細かい演出の話でしょう?
なむりんとのやりとりはずっとそんな感じでした。距離感が縮まらないなぁっていうのが、モヤッとした感じで胸の中にあって、学校で友だちと話すときの「うわーそうそう! あるよね!」みたいなノリがまったく感じられなくて、やる気がないのかなぁとか、世代の差なのかなぁって、それなりに悩むようになりました。
藤島さんにも相談しました。なむりんがまたやる気なくしてる、って。でも、藤島さんの答えは、「プロとしてはごくまっとうなやりとりで、むしろ好感度アップ」でした。えーっ、ですよ。えーっ。それにそんなふうに言われたら、逆にわたしがプロでやっていけない――と、当時は考えたものですが、まあ、ある意味たしかにそうなんですね。変わる必要があったのはわたしでした。
それから、ほぼ毎日のようにラインするようになりました。他愛もないこと。ハエトリグモがなにか捕まえて歩いてる写真だとか、深爪した写真だとか、あと、祖父のホクロの毛とかも送りました。そのうち祖父がチェックしているだなんて忘れて、腕の皮膚で作ったエッチなシワとか、やや問題あるラインも送ったりしましたけど、まあ、ギリギリセーフだったんじゃないかなって、じぶんでは思っています。
なむりんも細かく返事は返してくれてたんですけど、でもある日、ぱたっと返事が止まったんです。で、そうなるとやっぱり焦って、なんかまずいライン送ったのかな、嫌になったのかなって、不安になったりするじゃないですか。わたしはしたんです。してたときでした。
――唐津の市営病院にいます
――たったいま、母が他界しました
って、なむりんからラインが入りました。
あわてて履歴を遡ると、わたしからのラインは、親指の皮が剥けた、今朝はコーンフレーク、天気図がエロい。
いや、でもしょうがないでしょう、さすがにわたしでも、知ってたらこんなライン送らないですよ。あわてて、
――わかった
――ご冥福をお祈りします
って送ったんですが、ちゃんとした社会人だったら、もう少し言い方はあったのだと思います。でもそれしか言えなくて、呆れられるのか、失望させるのかと、送信したあとなむりんの入力中のアイコンをながめて、祈るようにして待ちました。
――一週間ほどこちらからの連絡が途切れるかもしれません
1時間ほどして返ってきたのは、いつもの事務的な返事。怒ってるのか、悲しんでるのかもわからず、これをどう受け取ってよいのかわかりませんでした。
なむりんに母君のことを聞いて、じぶんがすっかり母のことを忘れてしまっていること、祖母の部屋にも行かなくなってしまっていることも改めて思い起こしました。師匠からのラインはそんなわたしを諌めているかのようにも思えましたし、あるいはもしかしたら深く傷つけたのかもしれないとも思いました。
わたしはこう見えても冷静なんです。じぶんが滅多に反省しない質だということには気がついています。後悔することはあっても、たいがいはだれかのあら捜しです。わたしが学校に行かなくなったことも、大阪へ来たことも、あるいはアニメーターを目指したことだってだれかがそう仕向けたのだとまずは考えましたし、仮に反省するにしても、次はちゃんと回避できるようにしようというのがわたしの反省でした。この日だって、最初に母君に不幸があったと言ってくれたら、天気図がエロいなんてラインは送らなかったんだと、最初に考えました。でもそれで師匠が腹を立てて、あるいは悲しんで、この仕事を降りるとしたら傷つくのはわたしなんです。それを考えると、ちゃんとしないといけないのは、わたしなんです。
アニメーターなんかゴマンといるのはわかっていますが、こんなにたくさんじぶんのことを話せたひとというのは、師匠が初めてでした。仮に師匠が去って、ほかの絵描きさんが来たとして、また同じように話せる自信はありませんでした。あるいはすべての言葉が、言いっぱなしの、独り言みたいなものだったら、また次のだれかに向かって独り言を漏らせば良いだけなのですけど、はたしてわたしの言葉はすべて独り言だったのでしょうか。
履歴を遡って師匠の言葉を読み返すと、どれもちゃんとわたしの言葉に対して言葉を返してくれているのがわかりました。だからわたしは話したのだと思います。
なむりん師匠のトーンはずっと抑えめで、藤島さんがどう言ってくれたところで、乗り気ではないという思いは拭えませんでした。でも逆に、だれとも話さない少女がヌイグルミにだけは本音を漏らすってことがあるじゃないですか? あれと同じで、顔も見えないぶっきらぼうなオッサンだから話せたって部分はあると思います。あたかも片思いの少女がするように、バカなラインを送って、じぶんのことを伝え続けたのは、ずっとそうやって話せる相手を探してたのだと思います。冷静に考えれば、師匠はわたしと組まなくても、もっとふさわしい仕事があるんです。胸の奥ではずっと、どうすれば認められるのか、どうすれば捨てられずにいられるか、その不安に抗っていました。
師匠の母君が旅立たれた日。その夜はゲームが手につかず、ドラクエのタイトル画面を出したまま、ぼんやりと天井を眺めていました。この天井の模様と、古臭いペンダントライトもいつのまにか目に馴染んで、もう部屋のどこを見ても他人の部屋に来たような感覚は残っていませんでした。壁にかかった酒屋のカレンダー、チェストの上の置き時計も、私の部屋の一部になって、部屋にはいったときに感じた他人の匂いももうありません。安定したこの世界のなかで、ただ師匠のことだけが不安の影を落としました。
切り立った夜に抗いながら電気をつけたまま居眠りをしていると、スマホが震えました。
師匠からのラインでした。
そこにはたったひとこと。
――母に嘘を吐いた
とあり、にわかにその意味はわかりませんでした。でも、たったひとつのラインがこんなにも心を潤したことはありません。もちろん、喜んで良い内容でないことはわかります。でも、嬉しかったんです。
――嘘って?
聞き返すと、
――少年ジャンプに漫画が載るって
すぐに返信。
それを読んで、わたしの頭の上に疑問符が灯りました。
わたしはバカなので、わたしと描く漫画が大ヒットして少年ジャンプに載ったりするんじゃないか? なんて大風呂敷でもひろげたのかと思ってしまいましたが、言葉の途切れたラインの画面を見ていると、いや、そうじゃないんだって、不安が込み上げてきました。師匠は、見栄を張ったんです。母君の最後に。
やっぱりわたしじゃ駄目なんだ。
本当はこんな仕事受けたくなかったんだ。
師匠はわたしにとっては雲の上の存在です。だけどウィキペディアにも乗っていない無名のアニメーターです。わたしは、実力さえあれば名前などは関係のない、師匠はそういう世界にいるんだと思っていましたが、内心そうでもないんだなって、そのときに思い当たりました。戸惑いはありました。軽く見られていたのだという失望も、当然。だけどそれよりも、捨てられる恐怖の方が胸を占めました。捨てられるかもしれない。どんな言葉なら通じるだろう、なにを言えばいいんだろうって。
恥ずかしげもなく言うとしたら、わたしが伝えなければいけないのは、「ずっとそばにいて欲しい」です。でも当時はそんなはっきりとした言葉が浮かんだわけではなく、しかもそんな恋人に言うようなセリフ、ストレートに言えるわけもありません。
描いた絵はぜんぶ送りました。日常のスナップ、ハエトリグモの写真も、深爪の写真も、ケキちゃんの写真も、それから冒険中のデュエットの写真も送りました。あと見せていないのは、手首を切ったときの写真だけでした。
自傷するとき、「思い通りにならないなら、死んでやる!」と思ったことは、いちどもありません。このときだって、「わたし、死ぬかもしれない」って、伝えたかったわけではないと思うんです。
だけどね。もしもね。ハエちゃんが牛くんのことを好きになったら、どうすればいいと思います? ハエちゃんは牛くんのことが大好きなんです。だけどハエちゃんには、ぶんぶん飛び回るくらいしか思いを表現する手段なんてないじゃないですか。たとえ牛くんが反射的に尻尾ではたいて死んでしまうとしても、だからって思いを伝えないなんてこと、ハエちゃんにはできないと思うんです。
わたしもそう。あのときわたしは、わたしのことを伝えるために、最後まで守ってきた秘密を明かすしかないと思ったんです。これでぜんぶだ、って。
手首に残った傷の写真を送ると、なむりん師匠からの返事はじつにそっけないものでした。
――ラインのやり取りはスクショして社長に送らないといけないんだけど、どうすればいい?
なむりん師匠は、わたしが思った以上の牛くんでした。
――ごめん、消す
――スクショは撮った
――だめ! 消してっ!
ネタのような会話。この瞬間、わたしにとって最悪の過去が、ハエトリグモの写真、祖父のホクロの毛の写真と並んだんだと思います。同情されても責められても、わたしはがっかりしたと思います。日常の中で大きく飛び出していた部分が、日常に戻ったんです。
ねえ、タカエさん、わたし見せちゃった。手首の傷の写真。
目が覚めたらタカエさんに真っ先に報告しようと思うと、その日は寝付けませんでした。目を閉じてもタカエさんのリアクションパターンが無数に浮かぶばかり。
「写真送った?」
「てゆーか、撮っとったんか?」
「なんてことすんねや、この子は」
まああと一枚、必殺技の胸のXも残っていますが、もう大丈夫。わたしは、大丈夫。いちおう師匠にも「そっちも見る?」とは聞いてみたんですが、「見ねぇよ」とのことだったので、送ってません。
なむりんの故郷は九州は佐賀の唐津という町なのだそうです。そこはわたしが生まれ育った苅田から、ちょうど博多を挟んで反対側になります。わたしの故郷から遠くないその唐津で、なむりんは母君の葬儀に追われ、合間にいくつか、弱音を吐露するかのラインを送ってきました。
なむりんのツイッターも見つけていて、普段はあまり多くを呟いていないようでしたが、その日はいくつか自分自身や親戚に対して毒づいた書き込みが見られました。そしてそれを読みながら、やっぱりなむりんにとって、わたしの仕事を受けるのは本意ではなかったのだという思いが大きくなりました。わたしも上がったり下がったり。本当になんか、やばい感情に極めて近いなにかがありました。
――求めていたものは失われた
――絵を描いていれば人生は薔薇色だと信じていた
――あのひとにただ謝りたいだけの人生だった
それぞれなにを意図した書き込みかはわかりませんでしたが、大きな悲しみがあるのはわかりました。それをどう慰めてよいかわからず、わたしは「名村英敏」で改めて検索し、同姓同名の幾人もの群像に埋もれたなむりん師匠本人の動画を見つけました。説明を読むと、福岡の専門学校で行われた講演を無断で録画したもののようでした。冒頭、音は拾えず、途中からようやく声と字幕とが現れましたが、そこに語られていたのはなむりん師匠のまわりで起きた3件の自殺の話でした。
ひとり目は失明を苦にして命を断った大先輩、ふたり目はじぶんの才能に限界を感じた後輩、三人目はストーキング行為の果に仕事を降ろされた先輩。静まった会場をまえに、なむりんはこう続けました――
ごめんね、こんな話で。
この講演の話受けたとき、「アニメ界に残したいものはなに?」って聞かれて、それでいろいろ考えたんだけど、命よりも残すべきものってないんじゃないかと思って。
みんなうまいんですよ。僕より。なのに、なんで死ぬのかなって。
アニメ残したって、死んじゃしょうがないじゃん。
逆になんで僕は生き残ってんだと思います?
魂なんかなかったからですよ。半年あとにスタジオに入った一条一って後輩がいるんだけどさ。僕と違ってウィキペディアにも名前が出てるし、知ってるひと多いと思うんだけど。半年くらいで追い越されたよ。でも別に悔しくもなんともなくて。まあ僕の実力じゃしょうがないよねって思った。
死なないよ、そんなやつは。
何があっても。
最初から死んでるようなもんだからさ。
死ぬのは魂があるやつだよ。
ただ、五十になってさ。死んでりゃ良かったって思うんだよ。たまに。
死ぬくらいだったら命賭けでなんかやればいいじゃん、とも思うけど、でも命賭けて絵がうまくなるかっていうと、そんなわけないじゃん。
ていうか、命賭けてまでやり遂げたいこともない。
いままでも命なんか賭けてこなかったし、これからも賭けないし。
じゃあなんなんだ、僕の人生は。
ただやっぱり最初に言った通り、二種類の人間がいるのは確かで、僕には魂がないから、ひとの魂を支えて生きるのが使命だと思ってる。だから、なにやってもダメだなって感じたときは、せめてだれかを支えようって考えることにしてる。
演出がいない、コンテ描きがいないなら僕がやるし、そのシナリオの意図を形にすること、原画や声優の魅力を引き出すことが僕の使命だと思ってる。そう考えてやっと、じぶんにも価値があるんだと思えます。
そんな僕から、みんなに言えることはただひとつ。
死ぬな。
何があっても。
――なむりん師匠はそういって、最後は泣き崩れていました。
なんかこういうの、臭いって思ってたことはあるけど、でもなんか、カッコつけて言ってるわけでもないし、感動させようとしてるわけでもなくって、それを教室の群衆をまえに、涙して語ったんです。ふつうは言える言葉じゃないと思うんです。でもそれを語らせた、なむりんの内なるパッションこそ、わたしが求めてきたものだと思いました。
そのときふと気がついたんです。それまでわたしは、どうすれば師匠が振り向いてくれるか、そればかり考えていたなって。だけどこの講演を聞いて、救いを求めているのは師匠のほうも同じなんだって。いや、師匠だけじゃないですね。おそらく、みんな。だれもが救いを求めてる。ほんの小さな救いを。
いや、ほんっとごめん。わたしこういうカッコいいこと言える立場じゃないんだけど、でもやっぱ、名村英敏というひとの傍にいるからには、言わなきゃいけないことがある気がするの。
それで、会場からも少し啜り泣く声が聞こえて、わたしも涙を堪えることができませんでした。
――死んじゃだめですよ、先生
なんかもう、堪えきれずにラインした感じでした。
――死なないよ。なんで?
――動画見ました
疑問を浮かべた絵文字だけ返ってきたので、ビデオのURLを送ると、
――なぜwww
と、続きが返ってきました。
――私も何度か死のうと思った。いろんなひとに勇気づけられたけど、いままでで一番勇気づけられました。だから先生も死なないでください
翌日、目を覚ますと藤島さんからラインが入っていました。
師匠とのやりとりで少し前向きになっていたわたしは、ゲームの方にもなにか進展があるのだろうと思ったら、退職の案内でした。
内容はただ、一身上の理由で退職しますとあっただけでしたが、詳しく理由を尋ねると、淳一爺の火遊びにはこれ以上付き合えないといった言葉が返ってきました。この時点ではわたしはまだ、淳一爺が資金の半分以上をネコババしたとは知りませんから、火遊びが具体的になにを指すのかはわかりませんでしたが、「これ以上続けたら、わたしの責任になる」と言い出すくらいに藤島さんは追い詰められていました。
それでも一縷の望みはあると思ったのですが、「サイトのドキュメントは残していくけど、20年前のコードを保守するのたぶん無理」とか「ゲームは1ミリも進んでない」とか「ゲームが完成したら、その時点で神崎船体設計は不渡り出して倒産する」とか不穏な言葉ばかり聞かされました。
その会話は「要はマネロンや。判断遅すぎた。臭いメシ食わなかんかもしれん」と結ばれ、わたしはただ途方に暮れるしかなくて、悲しみはあとからじわじわと湧き上がって来ました。
いったいだれに相談してよいかわからず、ひとまずはタカエさんにラインのやりとりを見せました。タカエさんも「これ、だれが悪役かわからへんな」と首をひねり、タカエさんにわからないことを、わたしがわかるはずもありません。
タカエさんから船体設計に電話をしてもらって、人事に確認してもらうとたしかに藤島さんは退職するし、おそらくホームページもなくなるとの話でした。ゲームの話を尋ねてみると、とてもややこしい話が交わされて、わたしはただ話が終わるのを待つしかなくて、受話器を置いたあとでタカエさんに聞いてみると、「あれ、藤島さんの独断で進めてたことになってる」との言葉が返ってきました。
そのあとタカエさんは藤島さんの携帯に電話して、しばらく話し込んでいるようでしたが、「泣かんでええ」「うちが証言したるから」「だいじょうぶやから」と聞こえてきて、なにか想像以上の事が起きていることはわかったのですが、わたしは放心してなにも考えられなくなっていました。
――なむりん、クビだよ。
師匠にラインしたのはお昼を過ぎてからでした。
――どういうこと?
正直、こっちが聞きたいくらい。淳一爺が悪党だとは思いたくなかったし、祖父がそれを見抜けないはずがない、藤島さんの勘違いの可能性があると、それでもじぶんに言い聞かせていましたが、なにを信じたところで、藤島さんの退職とホームページの閉鎖が変わるわけではありません。
――ホームページ担当のひとが退職するって。
――ホームページはどうなるの?
――もうメンテできるひとがいないって。
そのやり取りの後、なむりんからの返事は途切れました。
あとはもう、悲しいよう、悲しいようとしか文字を打てず、そればかり繰り返し打ち込みました。わたしが悲しかったのは、ゲームが駄目になったことでも、ホームページがなくなることでも、藤島さんが去ったことでもなく、なむりん師匠との仕事がこれで終わることだったのだと思います。
悲しいよう、悲しいよう、悲しいよう、悲しいよう。
まさかこんなことで終わるなんて。人生で初めて掴んだ「実感」だったのに。打ち込むたびに涙があふれ、視界は歪んで、もう画面なんか見えなくなったころに、着信の音が鳴りました。なむりんからです。この溺れかけた波の遠くに、なむりんの言葉が投げ込まれました。わたしが涙をぬぐって、画面のなかの小さな滲んだ文字に焦点を合わせるとそこには、
――おれが社長にかけあう
の文字がありました。
いままでいくつの物語を読んだかわかりません。そのなかに何人のヒーローが登場したかも数えられません。その無数に見てきたヒーローのなかで、もっともクールなヒーローの登場でした。
――マジで!?
――マジだ。おれの人生を賭ける
第三部 栄華之夢
第9章 折り鶴
「あんたそれ、本気で言うとんのか?」
わたしがなむりん師匠と梅田で待ち合わせると聞いて、タカエさんは本気で驚いているようでした。
「梅田は地図見ても迷う大阪のサルガッソーやで?」
サルガッソーがなんのことなのかはわかりませんでしたが、大阪のひとはネタで驚くときと、本気で驚くときの驚き方が一緒で、本当に驚いたときもわざとらしく声を作って驚きますので、はたしてこの驚きがネタか本気かというのは、文脈やそのひとの性格から推し量るしかありませんでした。「あそこは、縦横高さに加えて、もう一次元あんねん」と、両手の指で複雑な形を作って示してみせるタカエさんもそうでした。
なむりん師匠からは東京から夜行バスに乗り、朝の7時に梅田に到着するとの連絡を受けていました。
「プラザモータープールってとこに着くて書いてあった」
「どこそれ」
「なんかしらん。バス停ちゃうの?」
タカエさんはなんで新幹線で来ないのか、あるいは飛行機だったら迷いようもないのにと首をかしげましたが、「倹約家ちゃうん?」と言うと、「まあ、そうかもしれんけど」と、怪訝な目を投げたあとにスマホでバス代を調べ始め、「うっわ」と3度発したあとに、「名村先生、賢いで。これ、バス一択や」と、手のひらを返しました。まあこの、なにかにつけて本気なのか冗談なのかわかりにくいところも、しばらく大阪にいるとそのノリで暮らすしかないということが身に染みてくるのですが。
「せやかて、梅田で待ち合わせて、どないして行くん」
「どないて、電車」
「できんの? あんた、ひきこもりやで?」
「それ、はっきり言う?」
たしかにわたしは、学校に行こうとして倒れたり、うずくまったりしたことはありますが、それは学校へ行くというプレッシャーがあったからだと思います。いまはタカエさんといっしょにではありますが、淳一爺のオフィスへも行けましたし、通りを渡ってコンビニくらいまではたまに行くようになりました。そう伝えるとタカエさんは、「梅田は次元がちゃうゆーてんねん」と返し、その次元というのも比喩的な表現なのか、さきほどのネタの続きなのかわかりませんでしたが、おそらく両方なのでしょう。そういう意味では大阪はそもそも、次元が違うのです。
「火ぁ金どっちかやったら、わたしもついてったるんやけど、なんとかならへんの?」
「だいじょうぶよ。ケキちゃんついとるし」
最寄りの駅から梅田へ出るのに40分から50分、徒歩の時間まで考えると1時間ほどはかかり、当日は6時には家を出る必要がありました。
わたしは5時半に起きて急いで身支度をして階下へと降りたのですが、その時間にはもう祖母は起きていて、タカエさんが盆に急須を乗せて部屋に入るところでした。
「そやね、今日やったね。いってらっしゃい」というタカエさんに、祖母に会えるか確認をとり、柔らかく朝日の射す部屋に入ると、祖母は介護ベッドの起こされた背もたれに体を預けて、一枚の折り紙を手にしていました。小さなテーブルには三角に折られた色とりどりの折り紙がならび、わたしの姿に気がつくと、折りしわのない綺麗な金の折り紙を取ってわたしにくれました。
祖母にとって、テーブルの上の三角の紙は鶴でした。
もともとはボケ防止のためにと鶴を折り始めたのだと言います。それがある時期からもう鶴は折れなくなり、そのあとも折り紙を折ることだけは忘れずに、ひたすら四角い紙を三角に折り続け、たまに交じる金や銀の紙は孫にでも渡すかのように渡してくるのだと、タカエさんは話してくれました。わたしは受け取った金色の折り紙を三角に折って、それを祖母に渡そうとしたのですが、祖母が少し戸惑うような表情を見せたので、続きを折って、鶴の形になるまで仕上げると、祖母が静かな声で「お上手ね」と言った声が聞こえた気がしました。
「今日は梅田に行ってきます。先生に会うんです。お祖母様にも紹介しますね」
そう伝えると、「あらよかったわね、先生に」と紡いだような笑顔を返してくれました。祖母が本当はなにを言ったのかは、みんなもう心に思い描くしかありませんでした。
早朝の駅はひともまばらに、まだ太陽は静かに地面に這うばかりで、素知らぬ顔で吹く風には夜の星の静寂がありました。朝、ちゃんとブラシした髪は足取りに合わせてふわふわと揺れて、その影を見ているだけで、いくらでもときめきが湧き上がって来るのがわかりました。伸ばしっぱなしの髪はわたしが意識することもなくワンレンのスタイルに仕上がってはいたものの、自然にまかせた髪は決してナチュラルとは言い難く、たまにすれ違うひとの仄かに明るい茶色くなった髪に比べると少し重く、野暮ったいようにも思えましたが、それでも毎日ブラッシングして、自分にあったシャンプー・リンスを使って、ワンレンとは言いながらも前髪の長さ、肩に触れて内外に跳ねる毛先を整えでもしたら、あたかもテレビから這い出してきそうな伝統ある妖艶な姿にはなったのかもしれません。服もそうです。小花柄のワンピースなのですが、タカエさんが選んでくれたものですから、少しタカエさんの雰囲気がありました。わたしの持つ服の中では少し大人びた印象はあるものの、布地にははりがなく、漫画で描くときに足すような硬質なスッとした皺はなく、ちょっと良いボタンを付けてあるだけの部屋着のようでもありました。でも、ワンピースは楽です。女性らしい服と思われていますが、中東の男性はみな似たものを着ていますし、ウエストのくびれから腰のラインまでを隠してくれましたし、それに上下を合わせる必要もないのですから、そこでセンスがバレることもありません。それに、スカートの裾が揺れるんです。わたしの足取りに合わせて。
なんば駅で乗り換えて、梅田駅について、そこから目的のプラザモータープールへは少し距離がありましたが、早朝の梅田はまだ四次元の背を伸ばし始めるまえでした。
なむりん師匠はGパン、トレーナーにハンチング帽だというので、わたしも薄いクリーム色のワンピースだと伝えて、バスが止まるとその出口のまえに立って、ケキちゃんの手を振らせて待ちました。はたから見たら春先にありがちなじぶんの世界に浸りすぎたひとですが、わたしは裁定者オーディン、胸元で手を振っているのは天命の戦乙女です。天の
ケキちゃんとふたり、何人か降車するひとを見送ると、わたしと目を合わせたまま見据えてくるひとがいました。ほとんどのひとはわたしと目が合わないようにしていましたから、すぐにピンと来ました。Gパン、トレーナーにハンチング帽をかぶっています。向こうから不意に掛けられた「神崎さんですか?」の声にもう、心臓がバックバクですよ。わたしは笑顔らしきものを顔に作って、大きく頭を下げました。
「はじめまして。いろいろとご迷惑おかけしてます」
ひさしぶりの標準語――苅田のひとが考える標準語ですので、すこしイントネーションは違うかもしれませんが――で言葉を紡ぐと、「いえ、こちらこそいままであまりお力になれなくて」と、バスの排気音と混じったなむりん師匠の声が耳に返りました。まず、どうしよう。高石に帰って、祖父に会ってもらうのが先か、それとも淳一爺のオフィスに案内すべきか、迷っていると、「朝食は食べました?」となむりん師匠。わたしはいっこだけおにぎりを食べて家を出てきたのですが、とっさに「いえ、まだです」と答えていました。
「じゃあ、いっしょにメシでも。ハンバーガーでいい?」
「はい! よろこんで!」
わたしは、尊敬するひとと早朝のバス停で待ち合わせた経験がありませんでしたので、このようなときどうすればよいかもわからず、へんなテンションのへんな声を出すしかありませんでした。
最近のマクドナルドは、並ばなくとも席に貼ってあるステッカーの番号をスマホに入れてオーダーすれば、座ってるだけで料理は運ばれてくるのだとタカエさんは言っていましたが、なむりん師匠とわたしはきっちりと5人ほどならんだ列の後尾に並びました。その後ろ姿は、これから大仕事に臨むギャングのバディのようにも、戦場を潜り抜けて再会した古い寄宿学校の師弟のようにも見えていました。わたしはチキンクリスプマフィンコンビ、師匠はソーセージマフィンコンビを頼んで、席に戻って作戦を練りました。作戦を練りながら、まだ作戦を練るほどの情報が揃っていないという課題も明らかになり、その日はまず祖父に会い、事情を聞いて、次に淳一爺の会社に行き、現在の契約について確認する、という計画が立ちました。なむりん師匠は淳一社長と祖父とを混同していたようで、話の途中で「そのふたりって別人なの?」と聞かれて少々不安にはなりましたが、なむりん師匠が完璧だったらわたしなんかいなくても良いわけですから、そこはむしろ、活躍の場が与えられたのだと考えることにして、わたしはおにぎりはともかく、胸がいっぱいで、ハンバーガーなんて食べられるのかなとも思いましたが、なむりん師匠がハンバーガーにかぶりつく姿を見ると、わたしのなかの本能も目を覚ましたかのように空腹を訴え始め、やはりギャングのバディがするように、あるいは古い寄宿学校の師弟がするように、向かい合ってハンバーガーを大口で頬張りました。
梅田から大阪メトロに乗り、なんばで南海線に乗り換え、大和川を超えるあたりの開けた空の開放感が好きで、本当はそのことをなむりん師匠にも伝えたかったのだと思います。わたしからは、どんな作品に携わったか、どんなキャラを描いたかなど聞くばかりで、退屈させまいとするばかりのその話は、とても退屈なものだったに違いありません。難波から15分ほどでいつもの駅につき、ここへ来たときは、苅田と比べてずいぶんとぎっしりと家が詰まっているものだと思ったものですが、梅田、難波と見て帰ると家と家の間に曲がりくねる路地は人の往来も緩やかで、どっと緊張が抜けるのがわかりました。駅の西口へ出て、民家へ分け入るような細い裏道に入るといつか見たサビ猫が振り返り、両手に迫る軒下と鼻先を道路に突き出して駐車した車とをかすめて、ほんの数分も歩くと祖父の家の土塀が見えました。歩きながらなむりん師匠から、どんなアニメを観ているかと問われて、呪術廻戦、鬼滅の刃、ゾンビランドサガなどのタイトルを挙げて、どのキャラ、どの場面、どのセリフがお気に入りかをまくしたてるように語ったものですが、ほんの世間話として聞いた話題の返事にしては、力が入りすぎていたようにも思い出されます。
「ただいま」
と、玄関の戸を引くと、タカエさんが「まあまあ、いらっしゃい。よう来てくれはったな」と、エプロンで手を拭いて、髪を少し整えました。
「はじめまして、名村です」
「こちらこそはじめまして、住み込みでお世話させてもらっている木村です」
「お祖父ちゃんは?」
「いてはるよ。それよりも居間に通したげて。すぐお茶淹れるから」
タカエさんのことはここに来るまでに説明していましたし、祖母が寝たきりだということもまた、それからもし祖母の具合が良ければ紹介したい旨も伝えていました。
「先にお祖母ちゃんに。いま会える?」タカエさんに尋ねると、「どやろね。ちょっと覗いてみて」と、台所のほうへ小走りで消えていきました。
祖母の部屋を覗くと、ちょうどうとうとと居眠りをしているところでした。
「寝てはる」
小さな声でなむりん師匠に伝えて、居間へと向かいました。
なむりん師匠が下座に座ろうとするのを制して、いつも祖父が座っている場所に座らせると、すぐにお茶が来て、わたしはどこへ座るべきか悩み、正面は祖父が座るからとなむりん師匠の隣に腰を下ろすと、祖父も木のビーズの暖簾を分けて居間へ入り、なむりん師匠が慌てて立とうとするのを「いえいえ、どうぞどうぞ」と制しながら、祖父はいつもわたしが座っている席に腰を下ろしました。
「はじめまして。神崎龍次です。孫が世話になっています」と、祖父は頭を下げて、「名村です、はじめまして、こちらこそ急に面会のお願いなどして、恐縮です」と、師匠もまた頭を下げて、こうして最初の挨拶が済むと、お茶菓子が運ばれました。祖父はそれをなむりん師匠に促すとタカエさんに耳打ちし、財布から紙幣を渡し、なむりん師匠は「いや、そんなに気を遣わんでください」と急いで挟んだのですが、「いやいや、大切な孫の世話をしてもらってるんですから」と、祖父はタカエさんになにか買ってくるようにと促しました。わたしはおそらく、駅の方まで出て和菓子かケーキを買ってくるよう頼んだのだろうと察しました。
東京からは新幹線で?
いや、夜行バスで。貧乏なので。
言うてくださったら、旅費は出せましたのに。
でも夜行バスだと、時間を有効に使えるし、旅を実感できます。
そうですか。わたしは最近飛行機ばっかりで。
という世間話が一段落するころに、タカエさんが家に戻り、わたしたちのまえに練切と水羊羹とが並べられました。
本題らしきものにはいると、「今回は本当に、淳一の会社の不手際でご迷惑をおかけして、面目ない」と、祖父は頭を下げました。なむりん師匠は、いえいえ、めっそうもないと、頭を上げるよう手のひらを差し出して、祖父と目があったところで改めて、「それなんですが、本当にもうどうしようもないんですか?」と尋ねました。
「淳一にまかせとるよって、こちらではなんとも。ほんま今回は縁がなかったものとして、また次の機会に」
祖父は恐縮しながら言いました。
「いえ、僕は縁がなかったとは考えません。むしろここへ来たのは縁があったからじゃないでしょうか」
なむりん師匠は腰を浮かせて座り直し、少し前のめりに祖父に向かいました。
「それはもう、こちらも十分存じ上げておりますが」
祖父はずっと低頭に言葉を重ね、なむりん師匠も負けじと下へ下へと頭を潜らせるようで、そのさまは押し問答ならぬ引き問答のようでした。
「神崎会長、お願いです、少しだけ聞いてください」
ただただ頭を下げるばかりの祖父に、なむりん師匠は改めて言葉を区切って、そして続けました。
「ビジネスの話だけならおしまいでかまいません。だけど僕は大人として、ひとはどうあるべきかをユミさんに示すべきだと考えてるんです。それは、縁あって知り合った人間同士だったら、あたりまえのことだと思うんです」
なむりん師匠の言葉は、こうやって書き起こすほどには雄弁ではなく、とぎれとぎれでした。考え考えであった部分もあると思います。祖父はその言葉を最初のうちは受け流そうとしているようでした。祖父もビジネスマンですから、なむりん師匠がビジネスの話をしに来たのだと考えていたのでしょう。だけど、「僕にできる限りのことをやらせてください」というなむりん師匠の言葉は、ビジネスの話として受け流すにはあまりに重い質量を持っていました。
「いま、可能性はゼロかもしれません。だけどそれが1%になる瞬間を、ユミさんに見せたいんです。そしてその1%の可能性に賭けるのが人間なんだって、僕に示させてください」
最初はなむりん師匠の会話を受け流そうと必死だった祖父も、途中からただ黙って聞くだけとなり、最後には――これも少し芝居がかった大阪のひとのありがちな口調で――「なしてそこまでのことをしてくれるんや」と、絞り出すようにして言いました。
「僕は、僕が描いてきたヒーローをウソにしたくないんですよ」と、なむりん師匠は言いました。「困ってるひとをたくさん助けてきて、そこにどんな理由も、計算もなくて、これがヒーローだ、かっこいいだろ、こうやって生きるんだ、って、描きながらずっと子どもたちに語りかけてきました。それが僕の30年でした。それをウソにしたくないんです」
祖父は、なむりんの熱弁を煙たがるような素振りを見せて「そんなん、お話のなかだけちゃいまんの?」と言いました。
「事情は聞いています。これ以上会長にご負担いただこうとは思っていません。ただ、もう少しだけユミさんのために動こうと思っています。それまでの間、ラインを続けることをお許しいただけたら、それで結構です」
そんなものは綺麗事だ、と言いたい祖父の気持ちはわかりましたが、なむりん師匠の言葉に動かされているのも明らかでした。
「名村くん」
関西のイントネーションで、祖父はなむりん師匠を呼びました。
「わしかてね、ヒーローになりたいよ。それは同じや。なるつもりやった。それを名村くん。君に奪われるのは慚愧の極みだよ。しかし、ラインするだけいうのを咎めるわけにもいかん。正直ね、淳一の会社――神崎船体設計が失敗したら、わしの責任も軽ぅない。そうなんのかならんのか、1%の可能性しかないのは、むしろわしや。その1%を名村くん、君に託せんのかどうか……」
祖父は本気でそれを迷っているようでした。いくつかの言葉を胸の中に書いて、また消して、少し時間を置いて、ようやく言葉となって祖父の喉を通りました。
「その返事、もう少し待ってもらえへんやろうか」
祖父が涙をこらえながらそう言うのを聞いて、わたしは確かな手応えを感じる一方で、強い責任を感じました。そしてわたしのまえに現れた名村英敏という人物が途方もないひとであることも実感しました。
帰りはまたバスかいな、チケット代は請求してくれてかまへんで、と、話題がまた世間話に戻るころ、祖母が目を覚ましたというので、わたしはなむりん師匠とともに祖母の部屋に向かいました。
床板が軋むので、静かに足を擦ってベッドのまえに進んで、なむりん師匠が「お孫さんをお預かりしてます、名村です」と自己紹介すると、「あら先生」と、祖母の口から漏れ、その先はよく聞きとれない風となってわたしの耳元を抜けました。なむりん師匠がテーブルの上の三角に折られた色紙を見ていると、祖母は「鶴を折っているの」と口に漏らし、それに続く言葉はまた聞き取れない風になりました。祖母が群青の色紙を三角に折って、師匠に手渡すと、わたしが折った金の鶴が師匠の目に留まったのだと思います、師匠は祖母の手から三角の色紙を受け取り、それを鶴に折りあげて祖母の手に渡しました。祖母はただ、柔らかい風を纏っていました。それ以来です。わたしが祖母の折った三角を鶴に折り上げるようになったのは。
第10章 バナナトラップ
祖母の部屋を出ると、目を真っ赤にして濡れたタオルを頬に当てたタカエさんが、涙声で「これ、会長から」と茶封筒を渡してくれました。なかに一万円札が4、5枚入っているのはわかったのですが、いったいどういう意味か戸惑っていると、「駅前のお寿司屋さんあるでしょう? しらんか。あるねん、そこ予約したんで、名村先生と食べて来なさいて」と、唐突に言われて、そんな店、行ったこともないのにどうすれば良いのか再び戸惑っていると、「ハイヤー呼んであって、場所は伝えてあるさかい」と、声を詰まらせながら言葉にしました。不審がるなむりん師匠に、「なんでもないねん。ドラマ見てたら、涙止まらんようになって」と、タカエさんは言って、なむりん師匠も「僕もあります、それ」と笑いながら、うっすらともらい涙を浮かべたように言うと、タカエさんはわたしに「ほんまええ先生に会うたな」と言って、そそくさと祖母の部屋に去りました。
お金が入った茶封筒持ってぽかーんですよ。
あとから聞いたのですが、このとき祖父は完落ちしていたそうです。なむりん師匠が祖母に語りかけるのを祖父も後ろで見ており、鶴を折って祖母に返したところで祖父は涙腺崩壊、書斎へと戻り、心配したタカエさんがあとを追うと、号泣していたとのことでした。
しばらく待っていると「ハイヤー」というものが来て、わたしはてっきりタクシーのことかと思っていましたが、そこにあったのは黒塗りの高級車で、屋根の上にあるはずの箱型のランプもなく、その後ろのドアの前では、白い手袋をしたスーツ姿の運転手が静かに佇まっていました。突っ立つと佇まうの違い。それがハイヤーでした。
なむりん師匠は「えっ?」と言ってわたしの顔を見たのですが、わたしもハイヤーは初めてだし、えっ? って言われても、こっちもえっ? ですよ。実家にいたころはタクシーさえ乗ったことないし。車のことは詳しくないので、車種などはわからなかったのですが、高級車なのだと思います。なんか、ペガサスなんとかとか、スーパーストライクなんとかとか。そういう系?
運転手さんがドアを開けてくれて、なかにはいって、寿司屋まではわずか数百メートルかな? その距離をハイヤーで移動、のれんが出ているだけでメニューも何もわからない寿司屋の戸を引くと「神崎さんの?」と、向こうから声がかかりました。神崎さんの、なに? はい、ああ、ええっと、孫ですけど。みたいな。
高級な寿司屋は緊張しました。カウンターに座ると、テーブルのうえのガラスのケースにたくさんの魚が並び、そのなかには伊勢海老や鮑、殻ごとの雲丹まであって、こう見えても海のそばで育ったから魚の良し悪しはわかるつもり。だてに漁協で釣った活け〆のハマチを食べて来たわけじゃあないよ? でー、そのわたしからしたら、そこに並んだ魚はもう、見ただけで美味しい! 目がヨダレを垂らすという言葉がありますが……いや、これはいま考えた言葉なんだけど、あまりにも美味しそうなものをまえにして涙が溢れてくる、いまのこれ、この状態を指す言葉だと思います。
「会長からは、おまかせならおまかせで、注文があったら注文聞いてやってくれ言われとるけど、どないします?」と板前さんに聞かれて、「これっ!」って、わたしもなむりん師匠も迷わず殻ごとの雲丹を指さしました。
黄色くてプリプリの雲丹に感激して、なむりん師匠は「いっそ殻ごと食いてぇ」と言っていましたが、わたしも同意見。ラッコになって腹の上で割って食いてぇ。
ふたりで食べた寿司はあわせて2万円になりましたが、それでももらったお金の半分。1万円ぶんの寿司というのは、ゲームでいうとなにかのトロフィーを得たような気持ちでした。
ハイヤーは高級車ながらも国産車で、運転席が右にあることにやや違和感ってゆーか、そもそもうちにあった車が左ハンドルだったから、運転手さんが座っているのは、父とドライブをするときにわたしがよく座る席でした。そんな話をすると、なむりん師匠は、「お父さん、外車乗ってたんだ」と感心したように漏らしましたが、ちょっとだけ事情は違っていました。
「外車っていうか、日産のローグって知ってる?」
知ってる? って、まあ、その聞き方が違和感なかったわけじゃないんです。
日本語には敬語というものがあって、目上の人にはそれを使うって話はよく聞いてたんですけど、このころのわたしは、はたしてじぶんの語彙のどれが敬語か、どんな相手に使うべきかとかよくわかんなくて、むしろその敬語というものを使うと冷たく聞こえるのではないかとさえ思っていました。漫画を読むと、敬語を使う相手ってだいたい敵だし、やっぱそういうものだって刷り込みはありました。敬語を使うのは概ね敵。あと、タメ口で近づいてくるのも概ね敵ですね。
だからこのときも、「日産のローグは知っていますか?」と言えば、そこにはあたかもクールキャラが主人公を見下して言うような「あなたはわたしと対等に話せる存在ではない」という気持ちが包含されるような不安があり、こんな口ぶりになってはいましたが、敬愛の念はむしろあったのです。
「いや、日産だとスカイラインとかブルーバードしかわかんない」
「なんか、いかつい顔した車。アメリカから並行輸入したって」
父は妙なところで妙な見栄を張る人だったから、日本車でも外車でもない、左ハンドルの日本車というものにステータスを感じたんだと思います。
寿司をたいらげて、ハイヤーでそのまま神崎船体設計のある心斎橋へ移動するあいだ、なむりん師匠とは故郷の話などをしていました。なむりん師匠も唐津ですから、海のそばで育ち、家系には水産関係のひとが多かったと聞いて親近感が湧きました。わたしの家系は神崎家の傍流みたいなとこがあって、巨大海運グループになった神崎家とは、遠からず近からずみたいな関係? 感覚的にはたまたま名字が同じ? くらいな感じでした。それってつまり、豊田って名字で名古屋に住んでるようなもので、まわりは「もしかしてあのトヨタのひと?」と思うかもしれないけど、じつはまあ、ふつうのひと、みたいな。でもそれが最近、祖父の家に来てから少し変わったというか、もしわたしが神崎家のひとでなかったら、こんなに美味しい寿司は食べられなかったわけだし、いや、寿司なんてまだまだ生ぬるい話、わたしがもし神崎家の一員でなかったら、わたしの絵でゲームとか漫画とかの計画が進むなんてことはありえませんもの。
ハイヤーだって、本当は予約が必要なんだってあとで知って、それを祖父は電話一本で即日手配したんですから、まあ、事情さえ知ってればびっくりな話ですよ。赤字路線で補助金頼みでヒーヒー言っていると聞いてたけど、祖父の家に来てそんな気配がどこかにあるようには見えなかったし。以前からも少しあったのですが、「神崎家の一員」というのは、わたしにとってプライドであり、責任であり、同時にコンプレックスでもありました。コンプレックスっていうのは、あれ。エリートばっかりの家系で、わたしだけなんでこんなダメ子ちゃんなの、って。
で、その話の中でなむりん師匠は、父君との折り合いが悪かったことを教えてくれたのですが、ミートゥです。ミートゥ。わたしは母との関係がよくなかったことを話しました。同性の親というのは、やはり自分の嫌な部分と共通するものがあって、それで嫌悪感を持つのかもしれません。
いま向かっている心斎橋という地名なんかも、ずいぶんと古風な響きを感じて、神崎船体設計を訪れるまえは宗像の母の実家の東郷の駅前のような印象を抱いたものですけど、わたしが母の実家に感じていたのは郷愁であり、憐憫でした。田舎に暮らしながら、なんとなく田舎への偏見があったんです。田舎に暮らす残念なひとたち。その家に育った、残念な母。それが幼いころの、わたしの母への印象でした。
心斎橋の駅に降りると、そういった印象とはまったく違った活気ある街が広がり、碁盤の目の路地はそこが古い伝統のある街であることを示し、わたしのなかの辞書は連鎖的にいくつも書き換えられていきました。さっきの寿司のこともあり、ハイヤーを止めて、神崎グループのビルを見上げると、誇らしい気持ちさえ湧きました。いやあ、1万円分の寿司を食べると、人間、変わりますね。わたしの勘違いが始まったのは、はっきりとこの日なのだと思います。
神崎船体設計の事務所に入ると、知らない事務の人が迎えてくれました。向こうには少し緊張があるようにも見えましたが、グループの会長の孫が、契約を有耶無耶にされそうな取引先を引き連れて乗り込んできたのですから、まあ、それはそうでしょうね。わたしもこのときは気が大きくなっているので、態度は少し高圧的だったと思います。2ヵ月後に18になる、世間一般でいう高校3年生のころでした。
「契約のわかるひととお話をしたいのですが」
と、なむりん師匠は切り出し、メガネにストレート長髪の女性が応対してくれました。名前までは覚えていません。田中ヒロミさんみたいなひとです。その田中ヒロミさんとなむりん師匠とで名刺を交換し、わたしはただ名刺をもらって話し合いがはじまりました。
なむりん師匠からの質問はまず、契約は破棄になるのか、継続しているのか。これについて先方……神崎グループのひとをわたしが「先方」と呼ぶのも変な話ではありますが、相手のひとは、契約は継続しているはずです、との返答をくれました。
では、データはどのような形でどこに納品するかと問うと、それは契約書にある通り、との答えでしたが、契約書には甲、すなわち神崎船体設計が指定するとしかありませんので、さらにそれを問うと、いまは回答できるものがいない、という話になりました。おそらく藤島さんがすべて取り仕切ることになっていたのでしょう。
そして納品したものをだれがチェックし、内容に関するフィードバックはどのようになされ、どこで公開されるかについても尋ねましたが、それもわからないとのことでした。そしてそこに「おそらく、公開はされないだろう」という言葉も加えられました。
「残念です」と、師匠。残念です。
質問はさらに続きます。
納品する漫画はゲームとの連携を行うと契約書にありますが、はたして連携とは何を指すか、連携すべきゲームはいまどのような状態か。これに関しても担当者――すなわち藤島さんが退職したのでわからないとの回答でしたが、「いちどバナナトラップさんに直接問い合わせていただけますか?」と、謎のひとことももらいました。
「バナナトラップというのは?」
「プロジェクトアローのプログラムを請け負っている会社です」
プロジェクトアローというのは、今回のわたしの絵をゲーム化するプロジェクトのコードネームのようでした。だとしたらたぶん、わたしの名前の「弓」から取ったのだと思いますが、アローは「矢」です。「プロジェクトボウ」が本来あるべきプロジェクト名です。とりあえず、船体設計の方ではもう埒が明かないということがわかりました。
スマホでハイヤーに連絡して事務所を出ると、すぐに車が来て、運転手がドアを開けてくれました。タクシーは自動ドアだと聞いていたのですが、ハイヤーは運転手がいちいち車を降りてドアを開け閉めしてくれました。「おもてなし」というのはたぶん、ひとを使役する喜びを与えることなのだと思いました。
バナナトラップは心斎橋の駅を挟んで反対側の、アメリカ村近くにあるという話でしたが、大阪暮らしも短く、その間滅多に外に出なかったわたしにはなんのことやら見当もつきませんでした。
混み合った道を抜けて、目的のビルは1階にカフェが入る真新しいオフィスビルでした。2階にデザイン事務所、3階にバーチャルゴルフスタジオが入り、株式会社バナナトラップはその上の階にありました。小さなエレベーターで4階に上がり、呼び鈴を鳴らすとタイガースの法被を羽織ったファンキーな男の人が顔を出し、一瞬、部屋を間違えたかと思ってドアに掛けられた表札を確認していると「心配いらんで、バナナトラップやろ、ここや」と、明るい声が肩越しにかかりました。そのひとは、社長でした。
広めのワンルームのような事務所の奥に応接ソファがありましたが、テーブルにはコンピューター関係の雑誌やゲームの箱が積み上がり、雑多でした。そばに大きなモニターとゲーム機があり、ソファの上にはコントローラーも転がっていたのですが、社長がそれを片付け、座る場所を確保し、ほかのスタッフの姿も見えましたが、とくに来客を気にかける様子はありませんでした。社長は冷蔵庫からペットボトルのお茶を出して、わたしたちのまえに置いて、「あれやろ? 原作者のひとと、絵描きさん」と、わたしたちの顔を覗きました。
「松山貞俊です。バナナトラップの社長やってます。ゲームはできてません。ごめんなさい。じゃあ、乾杯しますか」と、社長はお茶を掲げ、なむりん師匠も応じるものですから、わたしもペットボトルを掲げて乾杯しました。
「でも、あれやで。おれら資本金はもろたけど、開発費とか、一切もろてへんで。完成したら金もらう契約なっとるけど、仕様書とかいっさいなしやで。なに作ったらええかさっぱりわからん。教えてほしいわ」
早口でまくしたてられましたが、わたしは会社のことには詳しくありませんでしたので、社長が言っていることが正当なものかどうか見当がつきませんでした。
「でも、ゲームは作る契約になってるんですよね?」
「せやけど、いつまでて書いてへん。できたら金出す書いてあんねん。ほかは『別途協議する』ばかり書いたるねんけど、協議なんか1回もあらへん。1回もやで」
あとで詳しく聞いたのですが、当初は制作期間1年でゲームを完成させるという契約で進みそうになっていたものを、バナナトラップ側が「仕様書の合意から」という文言を足してもらったとのことでした。おかげで仕様書がないので締切も定まることもないが、進みもしない。しかしこのひとことがなかったら、首を括るしかなかったので、ギリギリで助かったとも社長は語っていました。
「じゃあ、いま、どうしてるんですか?」
「しゃあないから、絵描きは知り合いのアニメの下請けやって、プログラマは出向に出しとるわ。原作はどない? 進んどるん?」
「ええ。それなりに」
「それなりて、進捗でいうと何パー?」
「はんぶんくらい?」
「半分て。あかんわ。やっぱあかんねん、このプロジェクトは。数字書いて管理する人間もおらんし、まともに発注も来ぉへん。だいたいなんで会社の人間よこさんと、孫と外の人間よこすねん。なんの話せぇっちゅうねん」
はりのある明るい声で言っていましたが、激しい憤りを感じているのがわかりました。無神経を装えば、冗談で言っているものとして受け流すことができるのでしょうが、ここまでの憤りとなると、カピバラ並みの無神経でなければ無理な話です。
「本人まえにして言いたないけど、ペラ何枚か絵ぇと文言はもろたけどそれっきりや。ゲームにするんなら三面図は必要です、テキストもこのままじゃ使えません、どないしますか、ゆーても、すぐ用意します言うだけで音沙汰無し。このままじゃ資本金食いつぶす思うてつついてたら、なんて言われたと思う? 担当者辞めましたやで? 引き継ぎは? あんたら、おれらのことちゃんと考えて動いとん?」
そんなことを言われても、わたしは神崎家の人間ではありますが、神崎グループのひとではありません。もちろん、そんな事情がわかってもらえるはずもなく、「それは船体設計のほうに相談してください」と言うと、「これや」と、松山と名乗った男は鼻で抜いたような笑いを返しました。
「申し訳ありません、社長」
と、口を開いたのはなむりん師匠でした。わたしを見かねたのだと思います。
「社長がこのプロジェクトに尽力していただいていることはよくわかりました。あとはこちらの責任だと思います。こちらで持ち帰って、もろもろ対策を練って、もう一度相談させてください」
そう言ってなむりん師匠は頭を下げたのですが、わたしの胸の中には妙な悔しさがありました。悪いのはわたしたちなの? そう問い返したい気持ちでいっぱいでした。でもそれもいま考えると、わたしを救うためにみんな動いてて、はじめてのことで勝手がわからずに失敗して、疑心暗鬼になり、すれ違っていたんです。だれが悪いという話ではありませんが、その起点にいたのはわたしでした。
なむりんのおかげで、社長の気持ちも少し落ち着きを見せて、そろそろ会合もお開きの予感が漂うころ、「カブトムシ、お好きなんですか?」と師匠が尋ねました。「ああ、まあ、ガキのころな。いまも好きは好っきゃけど、獲ったりはようせんわ」と、社長が顔を綻ばせ、わたしがなぜその話になったのやらわけがわからず戸惑っていると「僕もバナナトラップ作ってカブトムシ獲ったことあります」と、なむりん師匠がカブトムシを捕まえる仕草を見せました。
「おっ! どのくらい獲れました?」
「いやぁ、獲れないっすねぇ。最高で3匹だったと思いますが、オスは1匹だけで」
「じゃあ、俺の勝ちっすわ。最高5匹、オス、オス、メス、クワ、クワ」
「あれ、場所によるらしいっすね」
「あと、バナナの熟し具合」
「シュガースポット出てる的な」
「腐りかけがええ言われてましたね、高槻界隈では」
聞けば、バナナトラップというのはカブトムシを捕まえるためにバナナで作る罠なのだそうです。いまはネットで見れば作り方が乗っていますが、師匠やこの社長の時代は手探りで、学校ごと、クラスごとにさまざまなノウハウが語り継がれていたという話でした。
バナナトラップの事務所を出たのが、まだ3時すぎ。なむりん師匠の帰りのバスは、夜の9時半出発でした。それまでの時間をどう過ごすか尋ねると、映画を見て時間を潰すというので、だったら祖父からもらったお金があるからと、それでふたりで公開されたばかりのガンダムの映画を観ました。そのあとまたマクドナルドを探して、ハンバーガーにかぶりつくと、なむりん師匠は映画を振り返り、「無駄に作画が上手い」と言うので、わたしはその「無駄に」という修飾語を拾いあげ、埃を払って、「無駄な上手さってなに?」と聞き返しました。師匠はハンバーガーをコーラで流し込んで、「絵が上手すぎて、それを見せたくてしょうがない感じ。ただアムロ――これが主人公のなまえです――が走るだけの場面なんかがある。安彦好き――安彦というのはこのアニメの作画監督のことです――にはご馳走だけど、あれってどうなの」と笑いながら言いました。たしかに思い出してみると、ただアムロが動いているだけの場面は多かったのですが、それでも退屈したわけではないので、無駄とまで言うのは大げさな表現だと思いました。
ハンバーガーを食べ終えると充足感の向こうに、ほんの少し寂しさがありました。たぶん、別れの寂しさなのだと思います。
「わたしたちのゲーム、どうなるん?」
寂しいときにあえて寂しいことを口に出すこともないとも思ったんだけど、寂しさって、そういうものよね。よね? よねっていう口調もわたしらしくないけど、
「マネージャーが入れば動く気配がある」
と、なむりん師匠は可能性を口にしてみせましたが、それをやっているのが藤島さんで、それが畑違いでうまくいかなかったのだと思います。それにわたしには、そこまで単純な話にも思えませんでした。
「ゲームの資金は淳一爺が使い込んでるて聞いた」
「ありがち。でもこっちには契約書もあるし、ちゃんと完成させたら神崎グループ全体でフォローしてくれるんじゃないの?」
つまり、たとえその支払で船体設計が不渡りを出しても、グループが救済するという意味だったのだと思います。ただ、それはそれでわたしは祖父と顔を合わせにくくなるのですが、筋として正しいのはなむりん師匠のように思えました。
「とりあえず、ひとに相談してみる」と、なむりん師匠は言いました。
「ひとって?」
「青木真理子っていう、おれの師匠。良い山師」
良い山師?
「あのひと、『わたしのことはまりりんって呼んで』ってじぶんで言ってたから、まりりんでいいよ」
まりりん?
「そのひと、タダで動いてくれるん?」
「あー。わからんけど、まあ、相談はしてみる」
そのとき、わたしの貯金は50万を超えていました。だから、「もしお金かかったら、わたしが出せるかもしれん」というと、それはやめたほうがいい、となむりん師匠は言いました。
「金を取るのは、ビジネスだから取るんであって、ユミさんがお金を出したら、このプロジェクトをビジネスとしてどう成立させる気か、焦点がわからなくなる。青木真理子が乗り込んでくるときは、そういう半端なことはしないほうがいい」
そこにはなむりん師匠から青木真理子……すなわちまりりん師匠に対する絶対的な信頼があるように思えて、正直、少し不満を感じました。神崎グループの件を無関係なひとに相談するのが、やはりどこかじぶんの役割を奪われたようで、スッキリとしませんでした。この日、船体設計でプロジェクトの経緯を聞き、バナナトラップへ乗り付けて実情をリサーチしたわたしのなかには、わたしは神崎家に生まれた神崎弓なのだという変なプライドが生まれていました。だけど、わたしにできることは、父から振り込まれた50万をいかに使うかというだけで、どうすればプロジェクトが軌道に乗るか、そのために何をすればよいかなどはまったくわかっていませんでした。
夜の8時。バスまではまだ時間がありましたが、遅くなると家族が心配するからと、わたしは先に帰されました。ステーションシティシネマから地下鉄改札へ向かう途中、祖父が苅田に来たときに買ってきた豚まんの店を見つけ、なむりんのお土産と高石の家用にそれぞれ6個入りの箱を買いました。お金を持っていたせいか、気持ちが大きくなって、それでなむりん師匠になにかしてあげたいと思っていましたし、それだけで場を支配しているような気持ちになっていました。お金ってやっぱり、怖いです。
ステーションのまえで、「ありがとう」を言いました。
「いえいえ、こちらこそいろいろと気を遣わせてしまって」
そういって恐縮するなむりん師匠が、高石の屋敷で祖父に言ったことを思い出しながら、「かっこよかったです。わたしもあんなふうに言えるようにがんばります」と言ったのですが、肝心のなむりん師匠はじぶんが何を言ったか覚えていませんでした。
「ずっと子どもたちに語りかけながら書いてきた。その気持をウソにしたくないゆうて」
「そんな事言いました? 苦し紛れだったんじゃないっすかね」
なむりん師匠が言ったその言葉は、照れ隠しのようにも聞こえましたし、あるいは本当にわたしが受け取ったような深い意味はなかったのかもしれません。ひとの本音とごまかしの間には、鉛筆の線1本分に満たない表情の差しかないのだと思います。漫然と描けば、それは同じになります。だけどわたしは、このときのなむりん師匠の表情にこそ、それこそわたしの命をかけてでも選り分けなければいけない1本の線があるのだと思いました。
「それ、決してバスのなかで開けないでくださいね」
「開けるとどうなるんですか?」
「とんでもないことになります」
第11章 まりりんリサーチ
「まだフラッシュアイデアですが、本編とは少しはずれたところで、こんなエピソードを考えてみました。ユミさんの意見を聞かせてください」
と、なむりん師匠からラインが来たのは、師匠と顔合わせした直後、体感では翌日だったと思います。いよいよなむりんが本気を出してきたと思って、送られてきたプロットを読むと、新キャラのマリリンが登場していました。マリリンと言えば、先日聞いた青木真理子というひとの愛称です。本気を出したというよりは、ついにブチ切れて内輪ネタに走り出したか? とも思ったのですが、ひとまずは読んでみると、プロットはヒロインが悪党にさらわれたところから始まっていました。
どん!
と、テーブルを叩く拳のアップからはじまり、苛立った主人公が仲間に訴えます。ヒロインが魔の山に幽閉されているのはわかっているのですが、主人公たちにそこに近づく手段がありません。このまま手をこまねいているしかないのか。主人公が肩を震わせていると、そこに主人公の師、マリリンが登場します。マリリンは本来なら主人公たちよりも数世代は年上のはずですが、とても若く、瑞々しく、美しい容姿で描かれていました。これはわたしの大好きなドラゴンクエストでもそうでしたが、男の賢者はヨボヨボの老人で描かれ、女の賢者は齢をとっても美しく描かれるというありがちなパターンを踏襲したものです。王道だと思いました。
マリリンはすぐに活動を開始しますが、その動きを元老院が察知し、妨害してきます。元老院は本来ならば味方のはずです。しかし、急に現れて現場を仕切り始めるマリリンに不信感を抱き、妨害してきたのです。これでは主人公もマリリンもヒロインに近づくことができません。
――一方その頃、ヒロインは魔の山で殻ごとの雲丹を貪り食っていたりするわけですが――このあたりでカンの良い私は、このプロットがなむりん師匠からの暗号だと気が付きました。ヒロインはわたし、マリリンが青木真理子師匠、そして主人公がなむりんでしょうか。だとするとなむりんは実物よりもかなり美化されていました。
目立った動きをすると味方から撃たれると察したマリリンは、主人公のアシスタントを装って、小間使いとして敵地に潜入します。そこから情報を得て主人公たちに伝えるのですが、ヒロインに連絡を取る手段がありません。八方塞がりに思えた状況のなか、主人公はヒロインに「想念」を送ると言い出します。いつの間にそんな設定ができたのかツッコミどころではありますが、主人公とヒロインの間には、かすかながらも脳内に描いたイメージを伝え合う能力が備わっていました。
「決行は満月の翌日、太陽が正中する時間。そう伝えてくれ」
マリリンが告げると主人公はヒロインにその想念を送り始めます。主人公の送る想念はか細く、それが届くかどうかはわかりません。
「本当にそれで届くのか?」と問うマリリンに、主人公が「あの子なら、必ず」と、ふたりでハンバーガーにかぶりつく場面でそのプロットは終わっていました。
つまりこの漫画は、今度の満月の次の日、お昼の12時に梅田のマクドナルドで待ち合わせることを意味する暗号だったのです。
痺れましたね、これは。
青木真理子というひとのこと、ほんの少し聞いただけでしたが、あまり良くは思っていなかったんです。もともとそんなに人付き合いが得意なほうではないし、だからこそオタクでひきこもりなんかやっていたりするんですけど、このプロットを読んで、「このひとに会いたい!」って思ってしまいましたから。本当にオタクの心をつかむのがうまいというか、あるいはなむりん自身オタクなので、こういう言葉でしか物事を伝えられないのかもしれません。オタクじゃなかったらたぶん、あのプロットを読んでも、なにやってんだろうこのひと、くらいの感覚だろうと思います。
そしてこの潜入捜査官みたいな暗号でのやりとり、これもまあ、なむりん師匠が本気でそうやって祖父の目から隠れたかったわけではなく、ノリみたいなものだとは思うんです。漫画というのはある意味「オタク弁」であって、その親しみのある言葉によってわたしたちの見る世界は構成されていましたし、制限もされていました。これをオタクでないひとに語るときには、あたかも大阪弁にものすごい圧迫感を感じるように、たくさんの誤解が混じりますが、オタク同士で交わすときは、ものごとのディティールを本当によく伝える言葉なのです。
あと気がついたんですけど、わたし、どんな危機に陥っててもとにかく食うやつだって思われてるのがわかりました。
満月の翌日は、月の半ばの水曜日でした。梅田のマクドナルドでわたしがチキンクリスプマフィンコンビを食べていると、「よう。邪魔するぜ」と、となりの席にソーセージマフィンコンビを持ったまりりんが腰を下ろしました。はじめて見たまりりんはとても背が高くて、かっこよくて、背景に描かれた精緻な点描と前景に流れるキラキラとが見えました。なむりん師匠、てっきりマリリンのこと美化して描いているものだとばかり思ったんですけど、実物は更に超えてきました。これはちょっと意外でした。女性の賢者を美化して描くのは、女の価値を美と比例させる男の作家のエゴだと思っていましたし、なむりん師匠もその点では俗物だと感じてしまったものですが、現実はその上をいきました。
世間話をして、ラインを交換して、あのときなむりん師匠といっしょにハンバーガーを食べたように、ふたりで大きなくちを開けてハンバーガーにかぶりつきました。
まりりん師匠は大阪の街にも慣れているらしく、メトロの改札を探すわたしに「こっち」と指さして、カートを引いて先に行って、わたしはなんというか、これからなにか大きなことが起きる予感に胸をときめかせたものですが、人混みを避けるだけでせいいっぱい、ふたりで天王寺行の地下鉄のドアに駆け込むと、「あとはまかせて。なんとかするから」と、まりりん師匠はほっと息を吐いて、船体設計とバナナトラップはひとりで当たってみるので、報告はなむりん師匠から聞いて欲しいと言い残して、列車が心斎橋のホームに入ると、「じゃあ」とだけ言い残してひとりで降りていきました。
なむりん師匠
新キャラ、めちゃくちゃいいです!
カッコいいです!
こういうキャラ、めっちゃくちゃ好きです!
次の展開が楽しみでしょうがないのですが、続きはいつごろわかりそうですか?
ユミ様
いまはまだ思いついたばかりでなんとも言えません。
一晩ゆっくりすればアイデアが降りてくると思うので、また簡単なラフでも添えてお送りします。
この青木真理子というひともウィキペディアに名前がないひとでした。
アニメーターのデータベースというサイトを見つけたので調べてみたら、そちらには名前は出てくるのですが、そこにもなむりん師匠と出会ったころの情報はなく、おそらく昔は、名前を出すこともなく活躍する天才アニメーターたちが無数にいたのだと思いました。あるいは、いまもそうなのかもしれません。アニメーターの名前で知っているのは、有名作品の作監やキャラクターデザインを手掛けたひと数人くらいで、それすらもフルネームで言えるかと問われると、すんなりとは出てきません。アニメのエンディングでたくさんのなまえが並んでいるのを見ていますが、それをひとりひとり読むこともなく、またそのなまえがすべてウィキペディアにあるわけではないのだと思います。クラスでいちばん絵が描けたひとが、アニメスタジオに入り、その天才が巨大なアニメーション作品の数分、あるいは数秒を担当し、そのなまえや、作品中のどこを描いたかなどはひとに知られることなく、やがて引退していく。世のアニメーターは、そういうサイクルのなかで生きているのだと思います。
匿名の掲示板で、「アニメーター格付け」というリストを見たのも、まりりん師匠のことを調べているときでした。数百人の巨大なリストがいくつかに分割してアップされ、それぞれ「アクション得意」「性格に難あり」「スケジュール守らない」などのひとことコメントが添えられて、当時のわたしはマニアックなアニメファンが己の偏見を書き散らかして公開したものだろうと思いましたが、いま思うと演出か制作進行が持っているリストが漏洩したものでした。いちばん上はSランク、ここには3人か4人のなまえがあり、Aランク、Bランクと下がり、Eランク、その下はランク不能までありました。なむりん師匠のなまえはギリギリEランクにありましたが、✕のマークが付いていました。これはたぶん、元になったリストに演出家が記していたのだと思います。「もう仕事は出せない」という意味です。わたしはもう、カッとなって、なむりん師匠がそんな評価な訳がない、見る目がない奴がまとめた資料だと思って見るのをやめました。
わたしはそのころまだ、「原作者」であり、じぶんで絵を描く覚悟も、アニメーターになるというのも些細な憧れでしかありませんでしたが、アニメーターになろうと決意したとき脳裏に浮かんだのはこのリストでした。じぶんが知らないところでランク付けされる恐怖、Dランク、Eランクと言われても、それでもわたしはアニメを続けられるのか。いや、それはもうアニメだけの話ではなく、「ランク不能」と言われたときにわたしは正気でいられるのか。
長い夜が開けると、また例の暗号文が送られてきました。
マリリンは港湾管理局へ行き、主人公の使いであることを告げ、情報を集めます。ここはおそらく、神崎船体設計を表しています。そこでわかったことは、行方をくらました港の管理官(すなわち、淳一爺?)が、どうやら主人公(こちらがなむりん師匠?)を知っているらしいこと? そしてその、行方をくらましている理由が、海外の提携先(なにそれ)との調整? であること? って、えっ? って感じでした。わたしがその、「えっ?」って感じたコマの次のコマで、ヒロインが「えっ?」とか言ってるコマが挿し込まれてましたから、わたしのリアクションはほぼ把握されていたのだと思います。手には雲丹の殻を持っていましたし、なむりん師匠のなかでは、すっかりそういうキャラとして定着していました。いまもわたしの自画像が雲丹を持っているのも、ここに由来します。
港湾管理局に乗り込んだマリリンは、「……あの男、生粋の詐欺師じゃないようだ」とつぶやいて、次の目的地、ビートルハンターと名乗る傭兵団に乗り込みます。つまりこれがバナナトラップです。そこで縦縞の法被を着た、いかにも甲子園でメガホンを振っていそうなリーダーと話し合い、うっすらと解散を考えている彼らに、「アニメイテッド・マテリアル」と呼ばれる技を用いる部隊で一時的に雇用する話を切り出します。これは少しわたしも戸惑いましたが、おそらく巨大なアニメスタジオで彼らを雇用し、会社を畳まずに済むように救済するということではないでしょうか。
なむりん師匠
マリリンの活躍、読んでいて胸が踊りました。
港湾管理官の正体はわたしにもアイデアがあります。
ファミリーネームはサイドテイルというのはどうでしょう。
――これはつまり「横尾」のことです。たしか淳一爺のアニメーター時代の名前は横尾だったはず。これを聞けばなむりん師匠もピンとくるのでは?――
彼はいまはその名前を捨てて暮らしています。
それから、ビートルハンターを別部隊で雇用する話、ヒロインは賛成すると思います。そうやってビートルハンターたちの立場も守りながら時間を稼ぐようなアイデアは、わたしには思いつけませんし、とても勉強になります。
だけど、読んでいてひとつ納得がいかないところがあります。
マリリンは主人公の師とは言え、無報酬で手助けするのはあまりにもご都合主義です。本当にマリリンは義憤だけで主人公を助けてくれているんですか?
ユミ様
港湾管理官の正体に関するアイデア、ありがとうございます。
サイドテイル、いいですね。なんとなく顔が浮かびました。
これでプロットの完成度をより高めることができます。
懸案のマリリンの動機ですが、あのひとはAB型なのです。
僕にもその行動原理ははっきりと読めません。
それはなむりんの本音だったのだと思います。AB型なので、行動が読めない――この説明はとても腑に落ちました。いえ、腑に落ちている場合ではないのですが、まあ、不思議な説得力がありました。
わたしは血液型占いを信じるたちではありませんでしたが、AB型の二重人格、行動原理が不明、みたいなところだけは当てはまると思っていました。神崎家はほとんどがA型で、わたしの家族も全員がA型でした。B型やAB型の友達はいましたが、やはりどこかじぶんとは違うセンスを感じましたし、逆にA型の友人とは妙にウマが合うと感じていました。これを一般的には「血液型占いを信じている」というのでしょうが、それはたとえばお地蔵様に手を合わせることが、ストレートに「信仰」とは結びつかないように、雑誌の占いコーナーで一喜一憂することもまた「信じている」とは言わないのだとわたしは思っています。仮に、雑誌の血液型や星座占いをついつい読んでしまい、今日なにが起きるのかと想像をふくらませることがあったとしても、これも「信じる」とは違うと思います。たとえば「星占いを信じる」というのは、1年のサイクルに合わせてそれぞれの星座から特殊な放射線が降り注ぎ、それによって人類の遺伝子が改変され、蟹座は蟹座の、獅子座は獅子座の性格が現れる、というようなことを言い出すのが「信じる」ということです。雑誌に書いてある文字を見て、「今日は嬉しい出会いがある」と書いてあって喜ぶのは、「お姉ちゃんに褒められて嬉しい」というのと同じくらい、人間としてふつうの反応であって、信じるということではありません。だれだって良いことが書いてあれば嬉しいし、嫌なことが書いてあれば辛いのです。たとえばわたしから「てめぇはバカなんだよ」と言われたひとはきっと悲しいし、「ステキな方ですね」と言われたら嬉しいと思いますが、じゃあそれで「わたしを信じている」ことになるかと言えばならないと思います。それと同じです。逆にそれを「わたしを信じている状態」と言えるのであれば、わたしは世界中のありとあらゆるひとにバカだのウンコだの言って、わたしを信じている状態にさせることができます。
なむりんはA型だと思いました。ウマが合ったので絶対にそうだ、と。あとで聞いたらB型で、すこしがっかりもしたのですが、総合的に考えると、やはりわたしは血液型占いを信じていたのだと思います。いまもそうです。当時を振り返って、血を信じ、それによってひとを分類しようとしていたじぶんを愚かだったと断じるいまも、いや、あるいはあのころ以上にいまのほうが信じているのかもしれません。その話からはもう脱却したつもりなのに、ずっと抜け出せずに、いまでも血液型と聞くとこのころのことを思い出し、胸が締め付けられるのは、きっとそういうことなのだと思います。
マリリンが港湾管理者を追い詰めるまでに二週間を要しました。
港湾管理者、これは淳一爺のことですが、ゲームを実際に制作する気でいたことはたしかなようでした。地元の有力者――これは祖父の事ですが――から得た2千枚のゴールドのうち7百で傭兵所を建て、残りは港湾管理局にプールし、傭兵を動かす資金――すなわち、実際のゲームの制作費――にするつもりでしたが、ちょうど海外に発注していた案件で資金の焦げ付きが起きて、それを乗り切るために現金が必要になった。傭兵を扱うのは初めてで、もっとじぶんから動いてくれるものだと思っていた――と彼は述懐しました。
実際に傭兵を動かしてみると、港湾管理局側の手も取られ、ノウハウもなく、作戦はひとつとして進むことがありませんでした。やがて港のなかにも管理者の計画的な詐欺ではないかとの声があがりはじめ、担当者が不安を感じ、逃げ出した……。
いまからでも担当を呼び戻せないのかと詰めると、もう港湾にも地元有力者の私兵による査察が及んでいる、かれらが決めたルールのうえで動くしかないとの答えでした。
ゲーム完成までの道のりがほぼ断たれていることは、そこに書かれた文字よりも、キャラクターの表情、背景、フキダシの形で伝わり、それはわたしにとって、どんな説得よりも雄弁なものでした。
なむりん師匠
納得できません。
せっかく始めたエピソードがこれでは尻切れトンボです。
このあとに大逆転があるとわたしは信じています。
マリリンと主人公はヒロインを助けるんですよね?
ヒロインに、自力で抜け出してひとりで山を降りろとは言いませんよね?
ユミ様
僕のいたらなさで、このような展開しか描けなかったことをお詫びします。
ビートルハンターの持っている金貨千枚の契約書を担保に、マフィアから金貨9百ほどの活動資金を引き出すという展開も考えたのですが、僕のなかのマリリンがそれを認めませんでした。差額でたかが金貨百枚の儲けを欲しがるマフィアはいません。マフィアは金貨1万を出し、2万にして返せというのです。
漫画というのは不思議なもので、リアルに話を聞くよりもありありと状況が伝わって来ました。ただ、なむりん師匠の漫画はあまりにリアルで、奇跡が起きない漫画でした。わたしに、もうヒロインが助かる目はないのだと、この上ないほどの説得力をもって伝えてくれました。
なむりん師匠
そうですか。残念です。
でも、ヒロインはみんなに会えてうれしかったと思います。
主人公とハンバーガーを食べたこと、同じ場所でマリリンとハンバーガーを食べたこと、このふたつは一生の思い出になると思います。
わたしがもっともっと強いヒロインを描けたら良かったのかもしれません。
でも、わたしなりにこれからも頑張って生きていきますので、どうか主人公とマリリンには、あたらしい活躍の場を与えてあげてください。
このじぶんのことかヒロインのことかわからない文章を打ちながら、ボロボロと泣いていました。祖父にこの秘密のやりとりがバレないように、顔文字も使わず、なむりん師匠から来るような事務的な口調で書き記しましたが、本当はいくら泣き顔の顔文字を打っても満たせないほどの悲しみがありました。祖父に聞かれてもいけないと思って、ただただ声を殺して泣きました。
それからまたしばらくしてプロットが送られてきました。急いで描き上げたもので、キャラはただ丸い顔に目がちょんちょんとついたものが多かったのですが、主人公のもとに地元のマフィアから連絡が来る場面から始まっていました。
「国から大口の金を引き出した。新規事業名目の金で自由には使えない。この金を洗いたい」
「洗うというのは?」
「なんでもいい。まっとうな理由のある金にしたい」
なむりん師匠
その展開はあまりにも危険です。
しかもそれでは主人公が悪に染まります。
他に手はないのでしょうか。
ユミ様
田舎へ行けばマフィアと実業家は同じです。
主人公もそこで生まれ育ちました。
マリリンもまだ活躍の場がありますので、お楽しみに。
人生経験の長いなむりん師匠が言うのでそれはそうなのでしょう。京都にある任天堂という有名なゲームの会社も、あまり知られてはいませんが、もとは花札を作っていた会社だと言います。花札と言えば時代劇で賭博に使われ、主人公のイカサマがばれてヤクザものに縛り上げられる場面が浮かびます。花札を作っていた会社だと聞いて以来、わたしが任天堂という言葉から思い浮かべるのは、表面的に英雄を装っているキャラクターたちが、賭場の裏手の倉庫で縛られた主人公たちを足蹴にする場面です。
それともうひとつ疑問があります。
マリリン――青木真理子師匠がそこまでしてくれる理由が思い当たりません。なむりん師匠とは契約がありますし、ここまで説明は略してきましたが、どこに発表されるでもない漫画は着々と進行し、もう半分ほどは納品を済ませたところです。だけどまりりん師匠は1円のギャラすら出ないのに、自腹で大阪まで来て、船体設計のひとやバナナトラップのひとに会ってくれました。AB型というだけでこんなことをしてくれるというのは、どの雑誌の占いコーナーを見ても書かれていないはずです。むしろそれはO型の特徴ではないでしょうか。
なむりん師匠
わかりました。だけどまだ解けない疑問があります。
マリリンの動機です。
AB型であるというのは納得のいく理由ですが、ファンタジー世界において血液型を理由に動機を説明するわけにはいきません。
なにか合理的な理由がなければいけないと思います。
しばらくして、またプロットの形でその返事が来ました。
鉛筆の線に、マーカーで陰影を入れた、それだけで痺れそうになる絵を5~6枚、これをわたしにはとても信じられないペースで描いて送ってくるのです。
冒頭、ビートルハンターが屯する隠れ家へのハイコントラストな路地を歩くマリリン、突き当りの階段を降り、扉を開け、振り返るハンターたち。
「仕事を持ってきた。これでしばらく安泰のはずよ」
「ありがてぇ、これで傭兵団の旗を降ろさずに済む」
「いざってときは、あの子たちに協力してあげて。それが条件」
あの子たちというのは、なむりん師匠とわたしのことですね。
わたしたちへの協力と引き換えに、まりりんはバナナトラップに仕事を回している、と。
「ああ、わかってる。だがいまは動く余裕がない」
「だから協力してるの」
「違いねぇ。ところで、これが成功したら、あんた、誰からいくら貰うんだい?」
そう、そこが気になるところ!
契約書もないし、プロジェクトの未来もわからないのに、どうして? って。
「成功したら? 成功したら、わたしのギャラはゼロ」
「どういう意味だ?」
「この計画が失敗したら、あなたたちを買いたいって組織があるの。金はそこから貰うわ。あなたたちにも悪い話じゃないはずよ」
「ハッ! 俺たちを売ろうって腹か! とんでもねえ女に目ぇつけられたもんだ」
「どう? 嬉しい?」
「ああ、わくわくする」
「戦ってるのはあの子たちだけじゃない。駒はいくらあっても足りないの。わたしが使えそうな駒を見過ごすはずがないでしょう?」
つまりは、青木真理子師匠が手にするのは成功報酬ではなく、失敗したときにバナナトラップのメンバーを別プロジェクトに口利きをする際の紹介料だったのです。さすが師匠が言った通りの山師でした。こんな汚いやり方、ストレートに耳にしていたらとても納得できなかったと思います。それが漫画にして見せられたらストンと胸に落ちて、「わたしも負けない、これはわたしとあなたの勝負よ、フッフッフ……」となるのですから、わたしもチョロいものです。
そしてこれもまた、あのころは気が付かなかったことなのですけど、まりりん師匠がそんな態度を取っていたのも実はポーズに過ぎなくて、本当は愛おしい弟子、なむりんのためを思って動いていたのだと、いまになってわかるようになりました。人間って本当にもう、複雑で、複雑で、複雑で、わたしがこうだと思った裏には必ず別の意味がありました。
第12章 決意
前回父に電話したのは、16になったときでした。「誕生日おめでとう」と言ってくれた父の言葉が、本当はどんな意味なのかはかりかねて、「うん、ありがとう」とだけ言って流して、キッズ携帯の設定の変更を頼みました。高校に行けなくなって、ずっと部屋でゲームをしていたころでしたので、いまどうしているか聞かれるのが怖かったのだと思います。父も母も姉も、わたしがいなくなった苅田の家で、ごくふつうに暮らしているのだろうと考えていました。わたしは早く幸せになりたかったし、父や母に、ほら、こんなに幸せだよ、お祖父ちゃんもタカエさんもとてもよくしてくれるし、どうしたの? なんで泣いてるの? 元気だしなよ――って言いたかった。
8月に18になって、2年ぶりに父に電話をしました。知り合いとはラインで連絡を取ることが多かったのですが、父にラインをするのはプライベートな空間に踏み込まれるような違和感があり、リストにならんだ日産ローグのアイコンには触れずに、居間の据え置きの電話のほうに掛けました。
「誕生日おめでとう」
の声が聞こえました。
「スマホ、新しいの買うから、手続きに承諾が必要になるんだって」
「ああ、そうだね、どうしたらいいの?」
「日曜日にショップに行く。そのときに確認の電話が行くと思う」
「わかった」
5年ほど使ったスマホは型落ちも激しく、ネットを見ていてもよく固まりました。もともとキッズ用ということで、性能も控えめのものを使っていましたし、携帯の設定を変えるにも、ファミリープランの契約ではいちいち父の同意を得るしかなく、かといってどこそこのサイトが見たいという理由で電話をするのも躊躇われ、わたしの世界はずっと狭いままでした。だけど実感はないけど、この日わたしは、成人していました。
「お母さんとお姉ちゃんは元気?」
「うん。変わろうか?」
「いい。話すことないし」
「わかった。弓はどう? 元気にしてる?」
「わかんない。考えたことない。元気って、どういうことなんだろう」
母や姉のことは元気かと尋ねながら、じぶんが元気かと問われたら元気というのが何を指すのかわからなくなるのも不思議なものです。あのころのわたしは、精力的ではあったと思います。だけど希望があるかと言えば、ない。ただ悔しくてじたばたと喘いでいただけで、たとえば海でビーチボールを追いかけてはしゃいでいるひとより、サメに追われてじたばた逃げ回っているひとの方が元気だと言うなら、わたしは元気でした。
8月の2日に18になると、もう成人したわけですから、なむりん師匠とのラインのやりとりをいちいち祖父に報告する必要もないとは思ったのですが、わたしがそう思ったところで、なむりんは丁寧に報告するだろうし、そう考えるとわたしのプライベートは半分は開け放たれたままでした。だけど、父親に隠すべきプライバシーと祖父に隠すべきプライバシーはどこか違っていました。父親に着替えるところを見られても、そう大慌てで取り繕うほどではありませんでしたが、男女関係の話をするのは嫌で仕方がありませんでした。これが祖父に対しては反対で、着替えは見られたくないどころか、洗濯を終えた下着でさえ目に触れさせるのが躊躇われたのですが、男女の話は特に気にもならず、なんなら性に関することでも祖父のいるまえでタカエさんと交わしていました。あるいはこれは、年齢のちがいでもあるかもしれません。苅田にいたときのわたしは13、4でしたから。
じぶんで選んだスマホをじぶんで契約すると、わたしはとても大きくなったような気持ちになりました。お金は父から振り込まれていたものから出しているわけですから、決してわたしの成果と言えるわけではありませんが、武器があるというのは強みになりました。
それで、なむりん師匠があげてくれた漫画がもう第6回まで進んでいましたから、わたしはなんとかこれを公表したいと思うようになり、まずはじぶんでホームページを作れないかと模索するようになり、ひとまずはSNSで尋ねてみようと思い立ちました。
フォロワーは多い方ではありませんでしたが、よく絡んでくるひとは少なくはなく、ホームページについて尋ねると、「フェイスブックで作れるよ」だの、「PIXIVでよくない?」だのという返事は来るのですが、いわゆる、クソリプ? じゃないのかこれ? そこで示されるものはわたしが作りたいホームページとは違っていました。
「ふつうの企業が作ってるようなホームページはどうすればいい?」
「ふつうの企業とは」
「資生堂とか、トヨタとか」
「まず5億円用意します」
「いや、そこまでの規模じゃないんだけど」
フォロワーのなかに、ホームページ作成の見積もりサイトを紹介してくれるひともいましたが、そこに書かれたサンプルページの参考価格は眩暈を催すほどのものでした。それに、あくまでも自分で作りたいんです。
ネットには基礎からわかるホームページ講座のようなものもあり、そこを読んでサーバーというものが必要らしいことはわかったのですが、これをどうすれば良いのか、わたしのスマホからそのサーバーへはどう繋がっているのか、まったく理解できませんでした。
悩みながら呟き散らかしていたら、そのうち業者のひとに捕捉されて、「どの規模のものをお考えですか?」と聞かれたので、身バレするのは嫌だったので、神崎船体設計と同じくらいの規模のページを探して、「これにプラスして漫画の連載が載ります」と説明すると、返ってきた返事は、制作費で1千万、サーバの維持費で最低でも月に十万、個人には負担が大きいので弊社ではこちらの商品を云々と、ビジネスの話になりかけて、あわててそのひとはブロックしました。
それで仕方なく、船体設計のひとにもらった名刺の電話番号に連絡して、藤島さんの転職先を聞いたのですが、さすがに会長のお孫さんでもお教えできないという、まるでわたしがずっと祖父の威光をかさに着てきたような言い方に、釈然としない気持ちを抱いたのですが、考えてもみれば、向こうからすれば常にわたしはそんな存在だったんです。ひとに不幸を撒き散らす、引きこもりの会長の孫。そいつのせいで何人のスタッフが職を奪われ、いくつ会社が潰れたか。まあ、このころは気がついてなかったわけですが、ハッと気がついたときの衝撃たるや、ですよ。そしてその衝撃を紛らわすために、じぶんについたたくさんの嘘たるや。
ネットの匿名掲示板に「藤島さんにハァハァするスレ」というものがあって、覗いてみると藤島さん退職からこちらお通夜のような雰囲気で、大手に引き抜かれただの、寿退社しただのと書かれていましたが、みんな藤島さんを二十代の妙齢の女性だと勘違いしているようでした。たしかに藤島さんの齢での寿退社もあるのでしょうし、それを揶揄するわけではありませんが、変態だらけの「藤島さんにハァハァするスレ」でそれを読んだわたしの感想ですから、それはもう無理からぬものです。
しかしそう思う一方で、藤島さんはパペットのブログで知られていたわけですから、ネットの上のこの幻想こそがむしろ本当の藤島さんで、子育てに追われながら船体設計のマネージャーを勤めていた藤島さんの方がバーチャルだと考えるのが自然なのかもしれません。
藤島さんの連絡先は、意外なことにバナナトラップの社長が知っていました。退職するときに、「どうせ仕事はまともに引き継がれないから」と言っては、なにかあったら聞いてほしいとのことで連絡先を交換していたのだそうです。周到です。さすがです。
わたしから頼んで会わせてもらったのはお盆明け、場所はバナナトラップの事務所でした。
まずは淳一爺が詐欺を企んでいるわけじゃなかったことを伝え、もういちどサイトを再開できないか確認してみたのですが、藤島さんは「潮時だった」と言うばかりでした。
20年まえは、少しIT知識があるとホームページは作れたし、それぞれのプロバイダー(これはインターネットに接続してくれる?業者のことだそうです)はユーザーがホームページを作るためのサーバーを提供していたのだそうです。藤島さんもそれでホームページの作り方を覚え、文字が流れたり点滅したりという当時では珍しい技工を仕込んで、ユーザーが書き込める掲示板も設置していたと教えてくれました。
「漫画、掲載したいです」
しばらく話したあと、じぶんの気持ちを抑えきれず、そう伝えていました。
「船体設計のいまの担当者に掛け合うしかないな」
「まりりんが何度か掛け合うたけど、無駄やてん」
「まあ、せやろな」
それでもわたしは、なんとかホームページだけは続ける方法がないかと、切り出す言葉を探していると、藤島さんが呆れたようなため息を挟んで言いました。
「うちが今日、なんでここに来たかわかる?」って。
はあ? って感じでした。
なんでもなにも、わたしに会うためで、ホームページのことで聞きたいことがあると伝えていたはずです。藤島さんに別の理由があったとしてもわかるはずがありません。
「なんかあるんですか?」
「あんたに説教せなあかん思うて」
「わたしに?」
「あのな。厳しいこと言うかもしれへんけど、あんたのお話で漫画も、あんたの絵でゲームも、どっちもありえへんの。会長があんたのこと可愛いのはわかるけど、それで振り回して会社ぐちゃぐちゃにしとんのは、あんたなんよ。わかる?」
いきなりまくしたてられて、混乱と怒りと悲しみとが同時に大動脈を駆け上がりました。
「でも、お話はなむりん師匠が漫画にしてくれたし、絵も……」
「じゃあその漫画持ってジャンプでもりぼんでも行ったらええやんか。なんて言われると思う? 面白いですねーヒット間違いなしですわーって? アホくさ。読者おんの? その漫画に」
意味がわかりませんでした。たったいままで味方だと思っていたのに。いろんな思考、感情が発散し、最後に残ったのは悔しさを押しのけて理不尽さでした。このひとが淳一爺を悪者にして逃げ出さなかったら、プロジェクトはうまくまわってたのに。その責任をわたしに押し付けようとしている。淳一爺を悪者に仕立てたときのように、わたしを陥れようとしている、と。
「ねえ、社長、ゲームもそうでしょう?」藤島さんは大声で松山社長を呼び止めて、続けました。「この子の絵じゃなかったら、もっとちゃんと進んでたって、社長からも言うたらどうですか。この子、わたしたちのこと、悪党思てますよ」
「思ってません! そんなこと!」
わたしが思わず立ち上がると、藤島さんも声を荒らげました。
「わたしもこんなこと言いたないわ! 会社も辞めたなかったし、ホームページも続けたかったわ!」
藤島さんは味方だと思っていました。わたしのキャラを漫画やゲームにしてくれるために、いっしょに戦ってくれているのだとばかり思っていました。それをなんなの。じぶんの思い込みで勝手にぎゃーぎゃーわめいて辞めていったあとも、こうして話を聞いてあげてるのに、なんなんだ……なんなんだほんとにこのババァは! って、わたしの気持ちがついに噴き出しかけたとき、遠巻きに見守っていた社長が間に入ってくれました。
「まあ、契約やからしゃあないやんか。それで金もろてんねやろ?」と、社長はなだめましたが、藤島さんは「このひとなんもわかってへん」という目で社長を見返しただけでした。
このところずっとホームページのことを調べていました。藤島さんが片手間に作っていたサイトは業者に頼めば5百万、それも写真やブログの文章は含まない値段です。そのお金を藤島さんはもらっていないのだから、お金の話ではないのだというのはわたしにもわかりました。
「あのな、この絵やけどな」
社長は藤島さんの隣に座り、わたしが描いたキャラのスケッチをテーブルに置いて話し始めました。
「この絵を3Dで動かすには、立体のデータ作らなあかんねん。それには三面図が必要になる。前から、横から、上から見た絵ぇな。それをうちで起こしてもええけど、元絵がこれやと、どう描けばええかわからん。この髪のうしろのこのへん。どこから髪がつながっとんのかようわからへんやろ? それをうちでやるとして、じゃあ監修はしてくれはるんですか、デザインでひと増やさなあかんけど、再委託で稟議通りますか、いうて確認しても、わかるひとおらへん。なんべん聞いても、会長の孫娘が描いた絵やから、これでお願いしますの一点張りや。正直、後悔したわ」
逃げ出すか、泣き出すか、暴れるか、わたしの選択肢はそのくらいしかなかったと思います。それでもそこにとどまったのは、神崎の名を背負っていたからです。使用人のまえで弱みを晒すのは神崎家の名折れだと、じぶんに言い聞かせました。それももちろん本音ではありません。ただ、そうすることでしかじぶんを保てなかったんです。
「わたしが悪いんですか?」
「悪いもなにも子どもやんか。おれらの責任や。藤島さんも」
「そんなん、わかってます」
お互いに言いたいことを言うと、社長も藤島さんもトーンダウンしました。わたしはひとり、そのまえの白熱した議論のなかに取り残されたように、胸のなかのざわめきを均していましたが、均しても均してもどこかが盛り上がる砂の山のように気持ちの波が収まりませんでした。
「わたしが三面図を描きます」
たいした考えもなくそう言うと、すぐに「いや、ちゃうねん。そういう話やないねん。そこをちゃんと金払ってプロをアサインせぇっちゅう話やねん」と社長が笑いながら否定してきましたが、わたしにもどこか引くに引けない気持ちがありました。
「でもそのプロがアサインできないんだったら、やるしかないですよね?」
わたしのこのセリフも漫画です。漫画やアニメではいくらでも見てきたシチュエーションです。
家に帰ってからもずっとむしゃくしゃした気持ちが収まらず、「絵がうまくなりたい」とだけ師匠にラインしました。返ってきたのは、「僕も絵がうまくなりたいです」でした。師匠はもうじゅうぶんうまいです。わたしからしたら神の領域です。
「師匠くらいうまくなりたい」
「描いていればなれるよ」
「絵の上達法を教えてください」
「描きたい絵があれば上手くなるよ」
そのときわたしが描きたかったのは、ヒロインの三面図でした。それは、うまくなったものが結果としてその仕事を与えられて描くものではないでしょうか。
そのあとすぐに、「サイコロ描いてみて」と来たので、これは相当バカにされているなと思って、すぐにサイコロを描いて写真に撮って送ると、直後に師匠からもサイコロの絵が送られてきました。わたしの絵は四角を張り合わせたもの。師匠の絵は角が面取りされて、赤い点にはツヤまで入った立体感のあるものでした。これはもう、絵の上手い下手以前に、描こうとしたもの、頭に思い浮かべたサイコロがそもそも違っていたというレベルでした。
「じゃあ、魚描いてみて」
今度はわたしからリクエストしました。魚なら得意です。小学校の頃、図工の時間に描いて褒められたくらいです。意気揚々と描いて送ると、師匠からサバの絵が送られてきました。しかも切り身でした。モノクロの鉛筆画で切り身なのにサバとわかりました。わたしが描いた魚は、よくよく見るとサバかアジかわからない謎の魚でした。
そしてすぐに、「絵がへたなひとの特徴は」と送られてきました。
どうやら書いている途中で間違って送信したものらしく、入力中のアイコンが揺れていました。わたしはてっきり、つらいことを言われるのだと思って、胸の中を暴れまわる獣を抑え込んでじっと待っていると、続いた言葉は「じぶんは絵が描けないと思い込んでる」でした。
「絵が下手なひとは、じぶんは描けないと思い込んでる。絵が描けるひとは、じぶんが描けるとか描けないとか考えない。まずは描く。描いてみて考える。考えるのはあとでいい」
「なるほど」
「絵について質問するときは、まず一枚描いて、それからにするだけでいい」
それから何枚か絵を描いて、師匠に見せるまえにSNSの反響を見てみようとネットにアップすると、イイネが3つ付きました。そしてそれはすぐに4つになりました。
「いいねありがとうございます! ちゃんとサバに見えましたでしょうか?」
「ばっちりです! 新鮮で美味しそうな切り身です!」
いまでもたまに、どのくらい上手くなったかな、と思ってサバの切り身を描くことがあります。何年かまえまでは、サバの模様を精緻に入れることでサバらしさを出していたものですが、いまは簡素化した線でいかにサバとわからせるか、みたいな描き方をするようになりました。5年後も、10年後も、わたしはサバを描くと思います。
その日描いたサバの絵はなむりん師匠とまりりん師匠と三人のチャットにもあげました。
「なむりん師匠のマネして描いてみた」
ふたりの返事は、
「おいしそうにゃー」
「いただくにゃー」
でした。
その後すぐに、なむりん師匠は実家の唐津へと旅立ち、おそらくは暗号で語っていた地元のヤクザに会いに行ったのでしょう、大金を任されるかもしれないというのは話の骨子から理解していましたが、詳細はわかりませんでした。
まりりん師匠に、「マリリンの漫画、読みました?」と尋ねると、「あれは、フィクションだから、真に受けないでね」との返事が返ってきて、そう言われるとまあたしかに、あんなにドラマチックなことがそうそう起きるわけでもないと思い、「じゃあ、地元のマフィアの件もフィクションなんですかね」と聞き返すと、「それ、知らなかったことにした方がいいよ」というシリアスな返答が返ってきました。まあ、なんていうか。
「いざってときは、なむりんだけ放り出して逃げる」
「ひでぇw」
「あ、師匠いた」
「いるよw ずっと見てたよw」
「草生やしてる場合じゃねぇだろ」
まりりん師匠のなむりん師匠の扱いはひどいものでしたが、これもまた、漫画でした。
ビートルハンター……じゃなくて、バナナトラップの方は、仕事は途切れることなく入って経営的には安定しているものの、仕事があるというのはほかのことをやっている余裕もないという意味で、ゲーム制作の方は止まったままでした。神崎船体設計から制作費が出れば動けるものの、具体的な指示が出る前に資本金を食いつぶして動けなくなったとのことでした。
まりりんの話では、アニメーションでは成果物の納品から60日以内に対価を支払うことになっており、船体設計はそれと同じ調子で契約したのでしょうが、ゲームの製作はそれでは回らないとのことでした。3ヵ月おき、あるいは2ヵ月おきにアルファ版、ベータ版などの細かいステップで成果物を検収し、それに対して報酬を払いラインを維持する必要があり、その納品・検収まで含めて工程の一部としてワークフローを設計する必要がある――と、まりりん師匠は語ってくれたのですが、わたしの頭ではちんぷんかんぷんでした。加えて、「たとえばアニメーションだと、原画は下請法の規制を受けるけど、作画監督は下請法の範囲外という扱いになる。なんでだかわかる?」と、マリリン師匠は追い打ちをかけるように質問を投げてきました。
もちろん、わたしは首を振るしかありません。首を振ると言っても、ラッコが首を振ってるスタンプを送るだけですが。
「原画は成果物があるので、『情報成果物作成委託』になって、再委託などに制限がかかる。作画監督は役務を提供する仕事だから、制作会社が作監を雇っても再委託にはならない。アニメーション製作だったらわたしもだいたいのことは頭に入ってて、なにをどう契約すればよいかはわかるけど、ゲームはわからない。ゲームとアニメは比較的近いと思うんだけど、わたしですらそう。それを完全に未経験の船体設計が、しかも本社の法務部と連携もせずに進めたら、こうなるのは必然。しかもバナナトラップは資本金が神崎グループではなく、神崎龍次単独で議決権もぜんぶ持ってる。このケースでどう動けるかなんて、ちゃんと専門家に聞かないと、どこで地雷を踏むかわかったもんじゃない。わたしにできるのは、アニメーションの仕事を委託するのがせいぜいだね」
バナナトラップのモチベーションはずいぶん落ちていたそうでした。このところ海外の資本で動いている会社も多く、そこがよく引き抜きを仕掛けており、油断しているとチームごとズルズル持っていかれることがある、アニメよりもゲーム業界で顕著で、プロジェクトが終了したタイミングがいちばん気が抜けない、スタッフのモチベーション管理は常に目を配っていないと会社など維持できない――と、まりりん師匠は小分けにしてチャットに流しました。
「わたしなんかでごめんなさい」
なにかずっとわたしには理解できない話ばかり出ていて、本当に自信をなくしてしまって、つい送ってしまっていました。その言葉をとらえて、マリリン師匠は書きました。
「ごめんなさいなんて言葉は要らないんだよ、この世界は」
ごめんなさいはいらない? なぜ?
わたしは疑問符を浮かべたラッコを返しました。
「ごめんなさいは、過去へ向けた言葉。何を言っても変わりはしない。これから何をするかだけ聞かせてくれたらいいし、それがないなら黙ってればいい」
この言葉もきつかったです。これからと言っても、いまここで語られたことの2割も頭に入ってないのに何が言えるのよもう……と、思っていたら――
「あなたは絵のスキルを磨きなさい」
と、まりりん師匠の言葉がチャットに上がりました。
その意図はわかりません。可能性を感じてもらえたのか、それともわたしが考えすぎないよう助け舟を出したのか。そのときの気持ちはいろいろで、いろんなことを思い出しました。たとえば、淳一爺が言った言葉、たとえば、なむりんが描いたサイコロ、たとえば、ネットで見たアニメーター格付け。巨人ばかりを目にして、しかもそのひとたちですら無名なのです。その世界に一歩を踏み出す勇気なんてとてもありません。あるはずないんです。でもわたしは、「わたしなんかでごめんなさい」という思いがウソでないことを示すために、まえに進むしかありませんでした。
第13章 第十五曳山
「金、出してもらった」
と、なむりん師匠がラインに流したとき、まりりん師匠は、
「わたしは関知しない」
と、切って捨てました。
「つれねぇな」
「スタッフは手配する。果実にはあやかる。しかし、そこまでだ。金の話はわたしの耳に入れないでもらおうか」
とのやりとりも、どこかのアニメからのパロディなのか、普段からこういう話をしているのか、あるいはもうこういう話をするひとがアニメのライターにも中核をなしていてオタク弁として定着してしまっているのか、あるいはわたしの言葉もすでに同じようになっているのか。詳しい話をしたのは梅田のマクドナルドでした。船体設計は港湾管理局、バナナトラップはビートルハンターなどと言い換えて、あたかもアニメの話でもするかのように話しましたが、中身はリアルなヤクザの話でした。
このときなむりん師匠が地元のヤクザから引き出したお金は4億円でした。国のなにかの事業の補助金を不正に回して儲けたお金で、そのままでは使えないからIT事業への投資を経てキレイなお金にするのが目的だと、あとでまりりん師匠が教えてくれました。まりりん師匠がこのお金についてなむりん師匠に直接聞くことはなかったと言います。あくまでもなむりんに尻を拭かせる、でなければ被害がどこまで拡大するかわからない、とまりりん師匠は警告をくれましたが、その警告はなむりんにではなく、わたしに向けたものでした。
もともとヤクザと実業家とは区別がつかないというのは確かなことで、神崎グループにしても小倉の有力者だった時代には、乱暴な側面がありました。大伯父が会社を継がなかったのも、そのころの逮捕歴や、ヤクザとのつながりが関係しているとも言われ、昭和の時代には企業と役場との癒着は常識で、知り合いに議員がいるかどうかで事業の成功失敗が別れましたし、議員のほうにしてもお抱えの事業が大きければ大きいほど立場が安定しました。それが犯罪だと認識されるようになったのはごく最近のことです。わたしの地元の炭鉱もまたひどいもので、巨大な企業グループが世襲の政治家を擁立し、いまでは福岡にアニメーションのスタジオまで持っており、その設立にもまりりん師匠が一枚噛んだとか、噛んでいないとか。彼らとわたしたちがやっていることの間には、時代と規模の違いがあるだけで、本質は同じなのです。
その神崎グループの会長の孫娘がやっている火遊び(これはまりりんの表現です)に、唐津のヤクザが4億出して乗ってくるというのは、尋常なことではないというのです。わたしは当初、4億なんてお金がどうして動くのか見当もつかなかったのですが、そこに神崎グループが噛んでいるとしたら、4億でもはした金だとまりりん師匠は言いました。
「成功報酬ばかりが報酬じゃない。なむりんが失敗すれば神崎グループにリーチがかかる。わたしが言ってる意味、わかる?」
アニメや漫画なら、この4億の投資で神崎グループを乗っ取るみたいなお話です。引きこもりのバカな令嬢を利用して。でもそれも、わたしたちがオタクだからそういう発想になるだけで、現実なのかどうか。
「どうすればいいんでしょう?」
「わかんない。わかんないけど、わたしは乗る」
「乗る?」
「その金でアニメなりゲームなり作れるんだったら、作るよ。たとえなむりんやあなたを犠牲にしてでも。サガだよ、これは」
2022年10月、株式会社カンズ・シャール・バレーヌ発足。なむりん師匠が社長を務める会社で、社名は「第十五曳山・クジラ」のフランス語、すなわち、第十四までしかない唐津くんちの曳山の第十五番目を神崎グループの支配してきた海に放ったのです。わたしは当時その社名の真意を汲み取れませんでしたが、なむりん師匠の地元の支援者の盛り上がりようがいまは手に取るようにわかります。ある意味、わたしは、あるいはなむりん師匠も含めてかもしれません、利用されていたのです。
カンズ・シャール・バレーヌはバナナトラップを支援し、プロジェクトアローを推進するほかに、更にもう一本、アニメーションの企画を始めました。それはもちろん、わたしが書いた原作のアニメ化でしたし、わたしもなぜか、その会社の役員に名を連ねました。
――あのね、お姉ちゃん
――ひさしぶり! 元気してる?
――わたし、役員になった
――おめでとう! って、なんの?
――アニメスタジオ
――!?!?!?!?!?!?
――わたしの絵でアニメ作るの
――!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
いやあ、こないだまで引きこもっていたのに、いきなり取締役ですよ。しかも18歳。お金は制作費にまわしたいから、役員報酬はナシでって言われましたが、いやもうなんか、お金じゃないし。って、バカだからもう、はしゃぐはしゃぐ。
カンズ・シャール・バレーヌの母体となったのは、東南アジアに拠点を置くレーザーコルベットっていう水産流通企業。いちおうその日本法人。なむりんの地元の企業――要はヤクザが出資して作った会社。4億出資の条件が、わたしが役員になることだったから、まあ、役員というよりは人質。いざってときは、わたしを足がかりに神崎グループにまで手を伸ばすつもりだろうってのは、当時でもなんとなくわかりました。
でも、どうやって?
わたしはお金持ってるわけでもないし、戸籍上は苅田の両親の子だし、なむりんの考えすぎかもしれないじゃない? それに、わたしにできるのは人質になるくらいだったから。考えてみれば命を売るのと同じだったけど、これでしか役に立てなきゃもう、やらせてもらうしかないって感じで、きっと大丈夫、アニメみたいなすごい事件は起きないよって、じぶんに言い聞かせて、とにかく、まえに進むことにしました。
スタジオの発足にあたり、まりりんはアニメはやめたほうがいいと進言しましたが、バナナトラップから回収できるのは1億、あと3億をどこかに投資して綺麗にする必要がありました。
「いま、映画1本分のスタッフ探そうとしてもそうそういないよ? グロスで出すにしても実力のあるとこは押さえられてるし、どうやって作る気?」
と、まりりん師匠はなむりん師匠に問いましたが、なむりん師匠には他に選択肢はありません。セオリー通りにするならば、売れそうな原作を探し、金を出してくれそうなスポンサーを探し、製作委員会を作り、その製作委員会の力をバネにして配給先を当たり……とまりりん師匠は説明してくれましたが、そのすべてを無視してなむりんは進撃を開始しました。商売として考えればでたらめな話です。まりりん師匠にも「絶対に売れない」という感触はあったのだそうです。
だけど、それでもまりりん師匠は乗ったのです。
「オネアミスの翼ってアニメ知ってる? ついにわたしたちであれを作るときが来たんだよ。尻込みなんかしてる場合じゃないっしょ」というまりりんの言葉に、オネアミスの翼というアニメを知らないわたしも、なぜか上気していました。
このときの素直な気持ちを吐露しますと、「見返したい」でした。バナナトラップで藤島さんと社長に詰められて、わたしのキャラクターでは漫画にもゲームにもならない、神崎会長の孫だから使ってやっているのだといわんばかりの物言いに、一矢でも報いることが出来たらと、それだけでした。
まりりんがヤクザの金だと知りながらもプロジェクトを離れないことにも違和は覚えたのですが、実はヤクザの金でゲームが作られることは0年代には珍しいことではなかったと言います。その末路も事務所のドアに銃弾を撃ち込まれる程度で、東京湾に浮いたものはまりりんの知る限りではひとりもいない、だから安心していいということでしたが、安心の基準が東京湾というのはいささかレベルが低いのではないかと思いました。
で、ゲームの例はわかりました。では、ヤクザが作ったアニメは? となると、アニメは広告としては機能するものの収益性は低く、また、大企業と巨大な代理店による製作委員会が壁となって、ヤクザが狩り場にするのは難しく、ヤクザ資金でアニメが作られるのはまりりんが知る限りは今回が初めてのケースで、なむりんも業界初の東京湾になるかもしれないと笑いながら教えてくれました。
「わたしは?」
「神崎グループを唐津のヤクザに売った女豹」
うわ、やだ、それちょっとかっこいいかもしれない、と、当時は思ってしまったことを告白します。
2022年の末だったと思います。まだ事務所もないうちからなむりん師匠は動き始めて、バナナトラップとの条件面での交渉に入ったと、梅田マクドナルドの役員会議で教えてくれました。
カンズ・シャール・バレーヌにゲームの制作を管理できるノウハウがないのはあきらかだったので、仕様書は完全にバナナトラップにおまかせ。とにかくPS5でもスイッチでもなんでもいいので、動くものを納品すれば、それで船体設計から綺麗なお金1億円を引き出せる。
これをカンズ・シャール・バレーヌは9千万でバナナトラップに依頼して1億得るから、1千万のプラス、バナナトラップは8千万で作ればいいから、こっちも1千万のプラス、それにバナナトラップにだってプライドはあるし、つまらないゲームは作らない。船体設計がちゃんとそのゲームを宣伝できたら、何億にも化ける。これは、負けるひとがいない新しいスタイルの詐欺でした。
しかし、カンズ・シャール・バレーヌの1つ目の問題点がここでした。予算9千万、期間1年ではバナナトラップが得意とする3Dのアクションゲームを作れず、リズムゲーとパーティゲーが合わさったような畑違いのゲームで勝負せざるを得なかったことで、実はこれがあとあと響くことになりますが、その話は追々。
「事務所はどうなってる?」
「いま、練馬で探してる」
「スタッフは?」
「演出家・平野豹馬、テクニカルディレクター・一条一がほぼ決定」
それはなむりん師匠の古い友人で、ウィキペディアになまえもある、実力もカリスマも備えたスーパースターでした。その後も制作、シナリオ、キャラクターデザインと、なむりんとまりりんの声かけでタレントが集結し、業界でもこのスーパープロジェクトのことは囁かれるようになっていたそうです。
そして、問題点の2つ目がここ。実力のあるひとは、業界でのつながりも多く、平野豹馬という演出家はネット配信大手との提携案を持ってきてくれました。アニメの資金の流れは製作委員会方式を取ることが多く、その場合、いろんな協賛企業が集まって資金を出し合うのですが、著作権をそちらで管理されてしまい、制作会社はリスクを負わない代わりに儲けも取れませんでした。これに対してネット配信の企業は放送権を欲しがるだけですから、制作会社にも著作権料収入が期待できるというメリットがありました。
だからこれはもう、渡りに船の話で、なむりんのみならず、あの慎重なまりりん師匠も飛びついたわけですが、これがまた後々やっかいな問題を引き起こしました。あの百戦錬磨のまりりんさえ見誤るトラップが仕掛けられていたのです。
でもまあ、最大の問題点はわたしだから。他はなんてことなかったかな、とも。
明けて2023年1月、事務所は東京、練馬に置かれ、バナナトラップとは専用回線で結ばれ、ささやかながらオープニングパーティが開かれました。わたしはその1週間前、アメリカ村の美容院で髪の毛を萌黄色に染めました。萌黄色というのは緑がかった金髪で、ドラゴンクエストのフウラの髪色でした。これにさらに和装して袴など履けば完全にフウラの完成なのですが、大阪で着付けして、飛行機に乗って? 練馬? それどこ? と考えると少し冷静になり、和装は無理無理、和装モドキで、とタカエさんを誘い出してまたまたこんどはふたりでアメリカ村へと出向き、和装風のワンピースと底の厚いスニーカーを買いました。アメリカ村大好き。もっと早くここにたどり着けばよかった。
伊丹から羽田へはじめての飛行機。タカエさんに車で送ってもらって、はじめての搭乗手続き。プスゴン、アマカムシカ、天命の戦乙女たちがフウラの旅立ちを見守っていました。行ってくるよ、みんな。
飛行機はまんなかの列の通路側。窓際が良かったけど取れなくて、座席のモニターで映画をやってて、ピクサーのアニメもやっていたので観始めたら、半分も行かないうちにポーンと音が鳴って着陸案内。シートベルトを着用してくださいってアナウンスが流れるけど、大丈夫。わたしはずっとベルトは締めたまま。羽田の滑走路が見えるとエンジン音が高鳴り、機体が震えた。
飛行機を降りるとなむりん師匠が待っていてくれて、そのままカートを引いてモノレールへ。窓際の席で、ビル影に見え隠れする海を眺めながら浜松町、「大江戸線なんで、ちょっと歩きます」と、改札を出て通りに出ると、そこには大阪の街とはまた違った都会の風景が広がっていました。
「この先が芝大門」
「なにそれ」
「ようわからんけど、江戸城のそういう門があったとこ? あれが東京タワー」
なむりんが指さした先に、赤白の鉄塔の先端が見えました。
東京。生まれて初めての。
練馬で地上に出て5分ほど歩いたスーパーの2階に、カンズ・シャール・バレーヌの事務所がありました。まだ会議室のパーテーションがあるほかはなにもないオフィスの一角に、今夜の設立パーティ用のテーブルがならび、あとはなむりんが持ち込んだ私物の机や荷物類、これから組み立てられるであろうパーテーションの資材などが雑多に置かれ、ブラインド越しの柔らかい日に影を落としていました。
奥の会議室には四角い長テーブル4つとキャスター付きの折りたたみ椅子があって、わたしとなむりんが下のスーパーで買った弁当を持って入ると、すぐにまりりん師匠も姿を見せました。
「あれだね。三鷹にあったころの東京ムービーみたい」
「トムスでしょ、そのころはもう」
「いや、確か三鷹時代にトムスに変わったんだよ」
「そうだっけ?」
というなむりんとまりりんの雑談に入っていけず、でもついにわたしも、アニメーターの仲間入りしたのだと思いました。もちろん、絵は描けません。どんなアニメーターよりも、いや、どんなアニメーター志望のアマチュアよりも描けなかったと思います。ただ運が良いというだけで、そこにいました。
バナナトラップの仕様書のドラフトは上がっていて、その件もそこで話しました。
まりりん師匠は今回の仕事は実入りが悪いので、素材は次回作にも使えるように作っておいたほうが良いと言いましたが、なむりんは次回作のことを考えているひますらないと応じました。
「ヴォイスは入れるの?」
「一応入れるつもりです」
「じゃあもうシナリオはフィックスしてないと間に合わないよ。スタジオとかだれが押さえるの?」
「そのへんは松山社長が。あと、最悪、シナリオには音声なし」
「シナリオに音入れずにどこに声当てんだよ」
まりりんはスタバのコーヒーをすすりながらなむりんを睨みました。まりりんはこの暴力的な眼差しが本当にステキな女性です。
「攻撃とダメージと必殺技」
「あとあれだ。攻撃で服がぱーっとはだけて、いやぁ~~~~んって」
「そういうのはない」
「それじゃあ声優さんも張り合いがない」
「んなこたーない」
「ま、いいか。要はこの仕様書で1年で上がるかどうかでしょ?」
「松山社長の見積もりだし、行けるっしょ」
その仕様書はわたしも見せてもらいました。わたしのキャラが丁寧にクリンナップされた2Dの絵になっていて、それだけで感動モノで、わたしはその攻撃とダメージと必殺技の声の「ああっ!」とか「ぐふっ!」とか書いてあるものを監修することになっていたのですが、「ああっ!」はどう監修しても「ああっ!」だし、「ぐふっ!」はどう監修しても「ぐふっ!」でした。
「これ、声優さんに『役になりきって叫んでください』って伝えるだけじゃダメなんですか?」
「そういうのもある。『これはこういう場面での叫びでーす』って伝えて、それだけじゃイメージできないだろうから、たとえばこんなでーす、みたいな感じで『ああっ!』とか『ぐふっ!』とか書いてある」
なるほど。
「だから、『こう叫んでください』よりも、『このキャラは熱血で、どんなときでも仲間を守る使命感を持ってます』とか、『冷静沈着でじぶんを見失わないキャラです』とかそういうのを伝えたほうがいい。で、それに合わせて『ぐふっ!』じゃないな、もっと堪えて『うっ!』って感じだなぁとかあったら、これこれこういうキャラなのでこうです、って伝える」
なるほど!
恥ずかしながらわたくし、原作者でありながら、字面の「ああっ!」だの「ぐふっ!」だのしか見ていませんでした。そうでした、声優さんは演技をするんです。
「じゃあたとえば、ヒロインは支配的な母のもとで育ってきて、ずっと抑圧されたコンプレックスがある、とか、そういうのも伝えたほうがいいんですか?」
と、思わず無意識に敬語が出るくらい素直でしたね、このときのわたしは。
「ていうか、それよ。伝えなきゃいけないのは」
「そーゆーのネットに書いてると設定厨言われる」
「勲章だよ、そういうのは」
すげぇ! まりりんすげぇ! もうわたし、一生このひとについていく!
って思いましたね、このときのわたしは。
まりりんは夕方の設立パーティまでいったん席を外し、なむりんはケータリングの受け取りや業者との打ち合わせがあるのでと事務所に残り、わたしはなんとなく、外へ散歩に出ることにしました。
もうお正月の飾り付けも消えた1月の終盤、わたしは萌黄色の髪に和装風ワンピースというバカが熟したような出で立ちでしたが、コートを羽織るとふつうの大阪のひとになりました。苅田で暮らしたのが14年、高石が5年。わたしのアイデンティティが大阪にあったのは、大阪でわたしがわたしになったからだと思います。その後7年の東京生活を経て、東京に出てまでエセ大阪弁を話すこともないかと、標準語のイントネーションを意識してはいるんですが、たとえば「トマト」も「コーヒー」も東京のイントネーションには程遠いまま今に至っています。
練馬は懐かしい匂いがしました。苅田と高石をちょうど混ぜたようなほどよい喧騒と抜けた空がありました。近くに豊島園といういろんな漫画でおなじみの遊園地があり、10分も歩けばそこにたどり着きましたし、その近くにはシネコンもありました。このあたりにはアニメスタジオも多く、アニメーターや漫画家もたくさん住んでいると聞きます。それを思うと、すれ違うひとがもしかしたらそうなのかもしれないと目を凝らすのですが、まあ、ただの怪しい人ですね。
豊島園前はがらーんと人影も少なく、そこで寂しく営業する喫茶店に入ってコーヒーを頼みました。
夕方の設立パーティで、わたしは初めて名刺というものをひとに渡しました。
演出家の平野豹馬、テクニカルディレクターの一条一と紹介され、ほかにもシナリオライター、キャラクターデザイナー、制作、経理、音響技師などなど、いったいどんな仕事をするのか検討もつかないひとたちと名刺を交換しました。パーティには淳一爺も招いたらしいのですが、そちらは多忙のため欠席、バナナトラップの松山社長が打ち合わせのついでに参加して、最終の新幹線の時間を気にしながらスパークリングワインを飲んでいました。
わたしは「まだ18ですので」とお酒を断るときの向こうのリアクション、「若いと思ったら10代!?」「その齢で取締役!?」という言葉に少し優越感を感じたり。
10代の取締役なんてのは、親族の威光を借りて金を握ってるものと相場も決まっていますし、カンズ・シャール・バレーヌがそういう会社だって知らなかったひとも、わたしを見てきな臭いと感じたのではないでしょうか。でも、まりりんが言ってたみたいに、金は金。金がなきゃなにも始まらないじゃない。それにわたしがたとえば、祖父の威光を借りてすみませんって言って引っ込んだって、それで変わるものはなにもないんだし。
配信会社からの資金援助が期待できるという話を聞いたのも、その席でしたね。
なむりん師匠はアニメの資金だけで3億ある――これは映画1本を作るには十分な資金です――だから、じぶんたちだけでやりたいと言ったのですが、慎重なまりりん師匠は「3億で映画作れるのは確定したラインを押さえられる安定した会社の話でしょう? しかも平均だよ? たとえば動画の蒔き直しとかになったら、ポーンと跳ね上がるよ?」と、ある程度のバッファを見込んだほうが良いとの見解を示しました。一理ある。
「神崎取締役の意見は?」と、なむりんが振るので、わたしはつい、「唐揚げうまー」とボケをかまし、「あーこの唐揚げ最高やー……って、唐揚げ食うとる場合ちゃうて。ゼニの話や、ゼニ」と、演出の平野さんがツッコんでくれました。
まあ、結末を先にばらしてしまうと、結果としてこのプロジェクトは失敗するんですけど、なむりんもまりりんもそれは覚悟の上で動いていて、わたしだけでしたね。無邪気に大ヒット間違いなしって信じていたのは。結果はさんざんですよ。完成すらしませんでした。でもここで多くの天才を間近に見たことは、わたしの力になったと思います。トップのアニメーターの手による原画と、そこに至るまえのコンテ、シナリオ、あるいは作打ちも目にしましたし、色彩や背景とどう打ち合わせ、なにを考えて絵を描くかというのを肌で感じました。
なむりんから以前、「描きたいものを描けばいい」って言われましたが、それは「描きたいものがなければ始まらない」という意味でしたし、「描きたいものがあるなら、そのディティールをとことん詰めろ」という意味でしたし、「ものを描くっていうのは、最後のひと押しに過ぎないんだ」という意味でした。その言葉を、はっきりとして形をもって示してくれたのが、カンズ・シャール・バレーヌという空間でした。
後にわたしは、まりりんとなむりんが言う「伝説」、すなわち「
だからわたしの「伝説」はただの役割。わたしは、サイボーグなんだと思います。
大阪へ戻って、日本橋でパソコンを買いました。性能に関しては「店の人間に相談するな、クソを掴まされる」というテクニカルディレクター一条一の言葉を信じて、店員の言葉には一切耳を貸さず、一条ディレクターが薦めるモデルを数件回って確認して、「いちばん変なものを進めてこない店」で買いました。これでいいんですよね?
ウェブカメラ:どれでもいい
ヘッドセット:どれでもいい
とメモにあって、この「どれでもいい」っちゅうのが、わからんっちゅうねん。この象さんの形したウェブカメラでもええのん、ヘッドセットはキティちゃんでもかまへんのか、っちゅう話やねん。でもまあ、どれでもええ言うたからには買うぞ、買うたるかんな、みたいな。うひょ、とか言ってカゴに入れて、ウッキウキしながらレジに並んだった。
ウェブ会議は緊張しました。ZOOMというアプリを使うというのですが、「まずはスラックを入れろと言われて混乱しました。スラックにもウェブ会議システムはあるがそっちじゃない、ZOOMだ、いや、MEETだ、MEETで頼む、は? ここをクリックしろ、さいでっかって、結局わたしはじぶんがなにを操作しているかもわからないままウェブ会議に参加しました。
とりあえず最初の会議は顔合わせと、定例会議の時間を決めて、それと現在の進捗状況の報告を聞いて終わりました。わたしは会議と聞いてすっかり、わたしのキャラクターをモニターに大写しにされて、このキャラクターのここがデッサンが崩れているから修正しよう、このストーリー展開は矛盾があるがいったいどうすればいいんだ、みたいな吊し上げ? のようなものがあるのではないかと思ったんですが、そういうのはありませんでした。会議を開いて、会議の時間を決めて終わった感じで、それはいったいなにを生み出すのでしょう? みたいな。
でもその定例会議の何回目かに、バナナトラップが作ったキャラクターを見たんですけど、もう、泣きそうなくらい感動したっていうか、じぶんのキャラ……わたしこんなに上手かったんだって感じの絵に仕上がってて、3Dで、しかも踊ってるんですよ。
ゲーム部分の基本も、もとから社長が温めてきたものらしくて、音楽に合わせて踊って、音楽が止まったらジャンケンして、勝ったら攻撃タイムっていうクレイジーなゲームでしたが、それ見てもう、やりたくてしょうがないって思ったし、ぜったいヒットすると思いました。だって、音楽止まったらジャンケンですよ? 勝ったらタッチで連打して、負けたら身体クネクネして避けるんですよ? で、音楽が再開したらまた踊るんですよ? なにこのバカゲー、天才か、って思いましたね。
それがたしか、3月。もう、すぐにでも発売できるんじゃないかと思ったんですが、デモ用にPCででっちあげたものだから、いちから組み直さなきゃいけないって聞いて、ゲームってたいへんだなぁと思いました。
で、その直後、4月。シナリオの第一稿が上がって来ました。プロのライターさんに発注した、プロのシナリオです。
第14章 南海の大海戦
新規タイトルの立ち上げには本当はもっと時間がかかるとのことでした。とくに週刊誌で連載してるような大きなタイトル――まあ今回のタイトルとは正反対ですが――は、いろんなひと、権利者やスポンサーが絡んでいて企画の調整だけで時間が取られるのだそうです。
シナリオにしても、作品の全容を把握して、そこからアニメ用にどこを見せるか再構成しなければいけないし、そうやって構成したものを製作委員会のさまざまな企業が参加する会議で発表して、読み合わせて、再調整。シナリオを書く以上にその会議が地獄だとしか思えないんですけど、それはシナリオライターの仕事じゃなくて、文芸の仕事だとか……
「だから、企画の立ち上げは、シリーズ構成や文芸担当のひとがやるんで……」
「つまり、シナリオライターとは違うんですね?」
「いや、シナリオライターが文芸もシリーズ構成もやるんだけど」
「じゃあ、シナリオライターがやるんですね?」
「だから、そこは文芸担当やシリーズ構成が……」
「は?」
みたいな。
今回のプロジェクトは、元になるのがわたしの原作と、なむりんが描いた漫画だけ、バナナトラップのスピンアウトはあるものの、まあ別物として扱えるでしょうということで、シナリオまではとんとん拍子でいけたとまりりんは余裕で足を高く上げて組み変えて、スタバのコーヒーを飲んでいました。
でもわたしは正直、上がってきたシナリオには疑問を持ちました。
それまでの打ち合わせでも、ヒロインの母親に二面性があることは話されていました。なむりんの漫画でも豹変する場面が描かれていましたし、でもそれはギャグ調の一コマとして納得しています。だけど、上がってきたシナリオでは明確に(明)(暗)と書かれ、「(ここで急に暗になる)」と記された部分もあり、まるで変身するかのように変わる点は納得できませんでした。ヒロインの母は二面性どころか、どんな側面ももち、それがひとつの人格のなかでころころ変わるのです。でも、まりりんから、「それがアニメだから」と言われて、まあ確かにそうかもしれないと、その場はわたしも尻を収めました。ただ、問題はこのときのまりりんの言い方でした。「パイロットフィルムができるから、それ見て確認しなよ」と言われたら、それはつまりパイロットフィルム後でも修正ができるという意味じゃないですか。まりりんとしたら「パイロットフィルム見たら納得するよー」くらいのノリだったんだとは思いますが、まあ、実際に納得はできなかったわけで。
そしてこの、パイロットフィルムというのがまた曲者で、当初の予定にはなかったのですが、ウェブ配信会社の稟議を通すために急いで仕上げたものでした。ゼロからスタートするスタジオでしたし、名刺代わりのハッタリ的なものは必要だったのだと思います。
たしかにそれで認められれば追加の予算だって取れるかもしれませんが、そのためにスケジュールも予算も必要になるはずです。
しかしこれもまりりんの判断でゴーになりました。いきなり映画にかかるよりも、一本仕上げまで経験してシステムの不備を洗いたいというのがまりりんの腹積もりだったそうですが、システムの不備ってなに? みたいな。アニメってなんかこう、制作の仕組みは決まってて、工場みたいにシナリオからコンテ、コンテから原画、ってふうに作るんだと思ってましたから、まりりんがたまに言う「やってみないとわかんない」が意味不明でした。
「万全なつもりでも、たいがいは抜けがある。アニメの制作方法って、マニュアルがあるわけじゃなくって、プロデューサーや制作進行がノウハウとして持ってるだけでしょ? だからたとえば、集めたひとが3Dやったことないひとばっかりだったら、そこは手探りでやるしかない」
って。
それにしてもあれですね。まりりんはカンズ・シャール・バレーヌの委託社員で、取締役でもなんでもなかったんですが、制作の方針はすべて決めていました。なむりんはもっぱら描くばかり、経営と制作はまりりんまかせという実態で、カンズ・シャール・バレーヌの社長は実質まりりんでしたね。
『神崎ユミにハァハァするスレ』を見つけたのがそのころでした。
だって、みんなが必死こいてアニメ作ってるとき、わたしは高石のお屋敷にいて、パソコン覗いてるくらいしかやることないんですもん。それならよーっし、情報収集だー、で見つけたのがそれですよ。
カンズ・シャール・バレーヌの発足の会見は、テレビにこそ流れませんでしたが、アニメ雑誌とウェブメディアには小さな記事になって、会見の様子はネットに上がっていました。わたしはフウラのような萌黄色の長い髪、和装風のワンピースで挨拶していたので、そこから存在を知られたようです。
「妙に若いけど何者?」「カッコが痛いwwww」ほっとけ。「名村の愛人に10万ペリカ」「登記簿確認。神崎グループの孫娘らしい」と、すぐに正体を割られ、18であることもすぐに晒されました。18であることがわかってからのスレは酷かったです。エロネタはまぁ、しょうがないとして、わたしのPIXIVもすぐにバレて、リンクが貼られて、身元も一瞬で割られて、カンズ・シャール・バレーヌは神崎の会長の道楽だのなんだのと言われるようになりました。
焦りましたね。このままでは神崎グループにわたしが怒られると思って、「神崎グループとは資本関係ないみたいだよ」とか「神崎グループから訴えられたらどうするつもり?」とか、こっそりと匿名で書き込んでみたんですが、すぐに「本人降臨?」みたいなこと書かれて、それからはそのスレッドは見なくなりました。
わたしのSNSアカウントもみつかって、直接アニメの内容を質問されたこともあったし、「本気でこの絵でアニメになると思ってるの?」「あなたが何をしようが構いませんが、声優の◯◯さんと◯◯さんは使われたくないです」と書かれたこともありました。まあ、そうなるだろうってのはまりりんから聞いてたので、ああ、来ましたかって感じではあったんですけど、いざそういう文字を見ると辛いですね。言い返したくてしょうがなかったけど、ぜったいに反応しちゃダメってのはきつく言われてたし。
ネットにあれこれ書くひとは、議論や説明を求めてるひとじゃないから、何を言い返しても無駄なんですって。「おまえは◯◯したのか!」に対して、「しました」も「してません」も、更に叩かれる理由にしかならないってまりりんに聞いて、わたしも反応はしなかったけど、そういう雰囲気は感じました。中学の時の池田といっしょで、池田が大量に出てきたんだなぁ、じつはわたしの生活圏の外側って池田だったんだなぁと思うしかなかったっていうか。こんなところで伏線回収って、なんなのわたしの人生。
あと、ひとりだけかな。フウラちゃんみたいですね、って気がついてくれたのは。
外部からだけでなく、内部からも不満は上がっていましたね。
わたしがパイロットフィルムを見てあれこれ注文をつけ始めてからは顕著で、「フウラがうぜぇ」とネットにも書かれるようになりました。たぶん、スタッフのだれかが漏らしていたんだと思います。「フウラ」はまだいいほうで、「腐裏」とか「ブウラ」とか書かれるのはなんか、こっちが恥ずかしいのでやめてほしいと思った。
で、こういうのが外部に漏れ始めると、投資する側が疑問視するようになるし、ユーザーも作品の品質を疑うようにもなるからって、なむりんとまりりん連名で、ネットへの同様の書き込みは訴訟の対象になるって、スタジオ内で通達を出したんですが、収まりませんでした。
さすがに辛かったです。じぶんが絵が描けないのはもうわかりすぎるくらいわかってたし。だから絵に関してはなにも口出ししてないのに、どうしてPIXIVの絵や会見でちらっと写っただけの絵を並べて貶されなきゃいけないんだろうって。カンズ・シャール・バレーヌだって、わたしが役員になるのが条件だっていうから役員になってるだけで、べつにわたし、高石の二階の部屋でアニメができるのをワクワクして待ってるだけでも良かったんです。
それまではPIXIVの評価も悪くなかったのに、とたんに地に落ちました。丁寧にぜんぶの絵に低評価つけていくひともいたし、いちいち「これは◯◯のパクリですね」って言ってくるひともいたし。PIXIVの絵と、発表された絵を並べて、「これ、キャラデザの意味あるの?」とか、一条さんの昔の絵といまの絵を並べて「フウラ前・フウラ後」って。そーゆうさあ、ひとを愚弄するためだけのスキルってどこで磨くの? わたしがあなたになにか迷惑かけた? あなた、わたしのせいで1円でも損した?
あと、なんかもう、本当にひどくて、会見のときの映像大写しにされて「キスマークがある」だの「やっぱりそういうことか」だの、学校に行ってなかったこともバレるし、なんなのこれ、って。
それで、なんだったかな。パイロットフィルムのキャラについて、一条さんとMEETで話したときだと思う。ヒロインの母のことだけは納得してなかったから、直してって言ったら、なんか、「だからネットでもクビにしろって書かれるんじゃないっすか?」って言われてもう、カーっとなって、なむりんとまりりんに、ネットに漏らしてるのあいつだからクビにしてってラインしたの。
実際に、一条さんと平野さんは、わたしをクビにするようになむりんに進言してたらしいです。まあ、当然なんですよ。だって、もう原画まで入った段階でシナリオを修正するとか言い出したんだから。演出はそりゃ反対するだろうけど、でもまりりんはパイロットフィルム見てから決めていいって言ったっていうと、まりりんはそんなこと言ってないって言い出すし、でも、わたしがいるからお金が出てるわけでしょう、このプロジェクトは。無理ならわたしを役員から下ろして、って言うと、まあそれも無理な話で、まあ、最終的にはかなりのカットを再発注することになりました。
でももうそのころは、わたしの作品が云々とかじゃなくって、ネットに晒した一条さんへの恨みのほうが大きかったです。
――またあのクソ女に引っ掻き回された
って、これたぶん一条さんが書いてたんだと、いまでも思ってます。
――引っ掻き回されたっていうと?
こっちがわたし。匿名だけど。
――40カット以上撒き直し
――言い返せなかったんだ
――上がバカだから
――でも、負けたんでしょう?
と、このログをなむりんに送って、「わたしを取るか、一条を取るかはっきりして」と迫ったことを覚えています。漫画ですね。こういうのも。
――クソ女、人事にまで口出しはじめた
――フウラちゃん強w
――うっせボケ
――もしかして、一条一本人wwww? ウケるんですけどwwwww
もちろん、いまは反省してますよ。でも、わたしに直接言わないで影で言ってるわけだし、わたしはそれに応じてるだけでしょう? 身から出た錆でしょ、そういうのは。
とはいえ、それでスケジュールは遅れ、そのぶん予算も食いつぶしていったので、わたしも責められて当然なんですけど、で、これもまだ序の口。もう、びっくりですね、これでまだ序の口なんですから。決定的な事件が起きたのは8月でした。
配信会社のひととはスタジオ発足の頃からこまかく打ち合わせをしていて、アニメのタイトル、『トロワシムウィユ・ペトリ』が決まったのも、その打ち合わせのなかででした。読みにくいのは、あえて読みにくくしようってことで、フランス語のスタジオ名と合わせてタイトルもフランス語にしました。意味は、石化させる3つの目だそうです。「ほんとにフランス語でそう読むんですか?」ってまりりんが確認してましたけど、「そういうのは雰囲気で」みたいな話でした。
ロゴもそうですね。いくつか候補の上がるなかから、社内プレゼンを通しやすい、ほかタイトルと競合しないものを絞ってくれました。パイロット版ができるころから動きは加速して、少々早めではあるけど、周知期間を取りたいということで、8月に速報を打つことになりました。パイロット版はわたしのわがままで作り直していましたから、それを大急ぎで準備して、そこからプロモーション用のビデオを作成、編集は前日の深夜までかかって、ぎりぎり間に合わせて第一報を打ったのですが、その翌日に事件は起きました。
もともと、カンズ・シャール・バレーヌは制作集団であって、経理は親会社に頼っていたんです。なむりんの地元のレーザーコルベット・ジャパンから、ほぼべったりひとりつくような形で経理スタッフが派遣されていて、まあ経理という性格上、いつどのタイミングでなにをするかというのは親会社には筒抜けだったのですが、それもまた問題でしたね。
朝方とつぜん、スラック――ウェブ会議システムのことです――に一報が入りました。年寄は起きてるけど、わたしみたいな若者はまだ寝てる時間です。わたしとなむりんで描いた――というか、ほぼなむりんが描いた原作漫画が、無断で親会社のホームページに掲載されたんです。
「今朝、レーザーコルベット・ジャパンのホームページに、神崎ユミ原作、名村英敏画のトロワシムウィユ・ペトリが公開されましたが、こちらはカンズ・シャール・バレーヌでは関知していないものです。ただいま弁護士を通してレーザーコルベット・ジャパンに確認中です。この件に関して外部には一切のコメントを控え、またSNSなどにリンクを貼るなどの行為は絶対にしないでください」
前代未聞のアクシデントが発生したわけですが、提携していた配信会社はたまったもんじゃないですよね。向こうには向こうの販促計画がありますし、そもそもこのタイトルだってもともとは配信会社側の案なのですが、それを親会社が横取りですよ。
で、ここでまりりんは、「まあ田舎の水産業がなんの考えもなくやらかしたんだろう」くらいに考えたそうなのですが、これがまた甘かった。レーザーコルベットは東南アジアを中心とした水産加工ネットワークが母体でしたが、その通信インフラを活かしてIT進出を目論んでいることがすぐにわかり、日本ではまだ経営実態は把握されていなかったものの、タイ、シンガポール、マレーシアではガチで配信事業にまで手を出していることが判明、事態は急転しましたね。
配信会社のほうでも、カンズ・シャール・バレーヌの資本は調査されてはいましたが、海外のIT企業からの投資なんてのはありふれた話で、それがまさかこんな形で乗っかってくるとは思わないでしょ。ありえないもん。
すぐに弁護士を通して、レーザーコルベットのホームページから漫画を取り下げるように連絡を入れるも、向こうからの来たのは「おまえが手を引け」。つまり、配信事業者を追い出せ、資金が必要ならこちらから出す、との返事でした。
いやぁ、そんなん乗り換えればいいんじゃなーい? お金を出してくれるって言うんだったら渡りに舟じゃなーい? って思うじゃない? わたしなんか、よくわかんないから、なにを悩んでんのかなーくらいな感じで。でも、この配信との提携話を持ってきた平野さんは反対するわけで、いわく、配信事業者との連携はこれからのアニメーション制作の軸になる。これを足がかりに、次、またその次がある。レーザーコルベットがどういうビジネスモデルを考えているのかもわからないのに、委ねるわけにはいかない、と。
ごもっとも。
しかも今回の件に関しては、タイだかマレーシアだかにある本社の意向なのか、唐津に事務所を置く現地法人――これは実質、なむりんの地元のヤクザが興した会社です――の独断なのかもわからない。そもそもなむりんがこのことを把握してない。それに、なむりんが勝手に漫画のデータを渡してる。なんで、って感じ。だいたい、船体設計に納品されたデータでしょう? 親会社とは言え別の会社なのに、どうして? と思ったら、
「契約書には、船体設計は利用権だけとあるので、大丈夫だって言ってました」って、なむりん。
「言ってました? だれが?」って、聞いたら
レーザーコルベットのだれそれが云々。
いやいや、そういうのちゃんと役員会で決めようよ。
そのころ、わたし抜きでよく練馬の事務所で打ち合わせが行われているようでした。わたしは高石の屋敷にいて、MEETで定例会議には出ていましたが、現場の細かい様子までは伝えてもらえず、このままなむりんとまりりんが一条さんと平野さんに説得されたら、わたし、クビになるのかなって不安もありました。
まあ、レーザーコルベットとの契約で、わたしを役員からは下ろせないはずだとは思いましたけど、わたしの側で安心できる根拠ってそれだけでしょう? そこを省いたら、わたしなんか、お荷物なんです。ネットで何度も読みました。あいつさえいなけりゃ最高のチームだって。
で、そのレーザーコルベットがチームを引っ掻き回し始めて、いまわたし抜きで話されてることって、このままレーザーコルベット資金で行くのか、いっそ平野さんの配信会社資金に乗り換えるか、みたいな大きな話だと思ったんです。だとしたら、そのときはわたしが……わたしひとりだけが切り捨てられて、みんなは配信会社のほうとくっついて、スッキリ仲良くアニメ作りに集中しちゃうのかもしれない、って。
考えたって悲しくなるだけなのに、だって高石の屋敷でぼんやりしてるだけが仕事だったんだもん。役員なのに。ネットを見て情報収集するくらいしかすることがなくて、横になって天井見てぼんやりしていても、やっぱ気になるでしょう? 気になるの、どうしても。
そして9月、一条一と平野豹馬がプロジェクト離脱。なむりんは配信会社よりも、地元のヤクザを選びました。
ホッとしたけど、ホッとしていいのかな、って。
その時点で配信会社から入ってた資金は引き上げられて、場合によっては訴訟って可能性もあったけど、そこはなんとか回避、でもタイトルは変えなきゃいけなかったし、あとはパイロットフィルム用に――これは締め切りすぎてわたしが掻き回したのが悪いんですけど――平野さんが口頭で発注してた原画があったり、それがろくに引き継がれもしないまま、これもおそらくレーザーコルベットの強権でスタッフが排除されたのが原因で、もう、しっちゃかめっちゃかだったそうです。
という事情を、わたしは役員なのに、業務委託のまりりんから聞いて、へぇーとか言ってるんだから、推して知るべしですよ。
聞けばこの地元のヤクザ、なむりんの弟さんの事業資金を支援した会社なんだそうです。
それと、なむりんの同級生にも構成員がいて、何年か前に自殺か他殺かわからないけど死んだ、って。なむりん、そういうところから4億引っ張って来てたって、このずっとあとに知りました。
ほんと、わたしってバカ。
最初に言ってくれたらいいのに、ってまた考えちゃったけど、そういうの言ってもらう前提で動くのがダメなんだよ。だれがどんな苦労してるか、こっちが考えて動かないからいつも後悔するんじゃん。
平野さん、一条さん、ふたりが去ったニュースは、カンズ・シャール・バレーヌのページに小さく掲載されただけだったけど、その瞬間から『神崎ユミにハァハァするスレ』は荒れましたね。当然のようにわたしがふたりをクビにしたことになったし、その判断をした名村英敏はわたしと愛人関係にあるとか書かれて、「平野豹馬の最新作だから楽しみにしていたのに」「一条一のポストプロセスは常識を塗り替えると思ってた」ともあって、それは確かにわたしが望んだ未来ではあったんだけど、でも違う、こんなんじゃないって、一晩かけて反論のレスを書いて、フォームにコピペして、エンターキーさえ押せば公開されるってとこまで行って、ぎりぎり押しとどまりました。
死にたかった、わたし。
死んじゃえばいいと思った。
第15章 約束の日
大阪の風は、春は西南西、秋は北東から吹くと聞きました。言われてみればたしかに春に潮の匂いを感じたものです。片側二車線の府道を超えて吹く風は少しホコリにまみれていましたが、目を閉じるとかすかに海が見えました。
秋の風はただ山から、京都、あるいは奈良のあたりから、東に向いたわたしの部屋の風鈴を揺らして、少しずつ去りゆく夏を追い越して、部屋の空気をひとつ、またひとつと入れ替えました。
祖母の部屋に降りて鶴を折っている時間は、毛羽立った胸を落ち着かせ、わたしに鼻歌などを歌わせては、小学生のころ学校であったことの記憶を探り、祖母への言葉を紡がせました。姉のこと、両親のこと、それに、家族で行った旅行のことも。不思議なことに、祖母のそばで鶴を折っていると、穏やかにそれを思い出せました。
祖母が亡くなったとき、わたしは鶴を折っていました。
「おばあちゃん。今日はここまで。明日、またね」
わたしは祖母が寝ているものだと思い、静かに部屋を出ようとしたのですが、その目はうっすらと開いているようにも見えました。
「おばあちゃん? 起きてるの?」
そう聞いたときはもう、そのときが来たことはわかっていました。涙がこぼれはじめ、
「あのね……」
声をかけようとしたけど、じぶんがなにを言いたいのかもわからず、
「おばあちゃん」
手を握ると冷たくて、そこからは言葉にもならない音が喉を鳴らすばかりで、次第に大きくなっていく悲しみを吐き出すように声をあげました。
おばあちゃん。
おばあちゃん。
わたしから聞いた、最後の歌は、なんでしたか。
わたしから聞いた、最後の話は、なんでしたか。
祖母の葬儀までに、髪を黒く染めなおすことは叶いませんでした。
葬儀は駅の向こう、海にほど近い斎場で開かれ、その日は父と姉とが訪れましたが、母の姿を見ることはありませんでした。わたしは萌黄色に染めた髪を隠すように、黒い帽子を被りましたが、モノトーンの静かな斎場でわたしだけ浮き上がっていたことは否めませんでした。
父と姉の姿を見たのは5年ぶりです。わたしはただ泣き崩れました。タカエさんが来て、「ずっと側におって、最後も看取ってくれはったんよね」とわたしの代わりに言葉を紡いでくれましたが、タカエさん自身堪えきれずに、あとは姉も含めて、三人でただ泣くばかりでした。
わたしと祖母が折った鶴を、祖父は棺に入れたいと言ってくれましたが、祖母がじぶんで折った鶴ですから、祖母が一番愛したひとに捧げるべきだと、わたしはこれを拒みました。それがなんなのかは、祖父が知っていました。いつかこの鶴をすべて千羽鶴の束にして、そのひと、その場所に捧げるのが、きっとわたしたちの使命なのだと伝えました。
「お母さんは?」
「里帰りしてる」
「ずっと?」
「うん。ずっと」
わたしがアニメーターになったら伝えたいひと。その筆頭は母なのだと思います。笑顔で歓迎してくれるとは限りませんが、「ユミは頑張ったよ」って、遠くから伝えられたらそれでいいし、今日会えなくても、そしてこのあと何年も会えなくても、いつかアニメーターになったら、それはわたしのなかで母に会うことと同じだと思いました。
葬儀にはなむりん、名村英敏師匠と、まりりん、青木真理子師匠も足を運んでくれました。ふたりとも仕事が忙しいだろうにと、そんなことが気になって、ごめんなさいって何度か謝りました。それと淳一爺ともひさしぶりに顔を合わせました。なむりんまりりんとは時間が合わなくて顔は合わせず仕舞い。そう言えば、なむりん師匠を紹介されたのは、制作進行を通してでした。こんなときに「名村英敏ってひとを知っていますか?」と聞くのも変だと思って、ただ棺の前でうなだれて、祖母のことを話しました。そして、「よろしかったら鶴を折ってください」と、折り紙を一枚渡しました。
姉とは少し話したかったのですが、いまの仕事のことをうまく伝えられず、「アニメーションのキャラクターデザインするの? すごいやん」と言われても口ごもるばかりで、せっかくの機会なのになにも喋ることができませんでした。
「髪の色、フウラみたい」
「うん。アメリカ村で染めたんよ」
「アメリカ村?」
「にやかしいとこ。心斎橋にあるっちゃ」
「心斎橋は聞いたこつある気のする」
「うん、難波と梅田の間」
「あとね」
と、姉は照れた笑いを見せると、「こんなときにあれだけど」と、左手薬指にさしたリングを見せてくれました。
結婚したの? ううん、まだ婚約。いつ結婚するの? 予定は6月だったけど、喪があけるまで待ってもらう。そっか。うん。
それからの一週間はバタバタとして、祖父ともタカエさんともゆっくり話す時間がなく、混沌としたカンズ・シャール・バレーヌのほうにも気持ちが向かいませんでした。作業服を来た運送業者が来て、祖母の寝ていたベッドを運び出し、また別の業者が消毒と、少し傷ついた壁の修理をして、祖母は一枚の遺影になって仏間に寝屋を移しました。
タカエさんは、「さて」と手を叩いて、「貯金食いつぶすまえに次の仕事も探さなあかんし、アパートも借りなあかん。次はうちの番やし、悲しんでるひまないで」と、エプロンをはずして洗濯かごにまるめて入れました。
祖父と話したのは、祖母の逝去から1週間ほど経ったころでした。
まず、ごめんなさいと謝りました。
バナナトラップで資金を溶かしたこと、カンズ・シャール・バレーヌで神崎家を巻き込んでしまってること。
祖父の話では、船体設計に預けた金は全額返ってきた、そちらの経理もいまは正常化しているとのことで、残りの7千万もゆくゆくは回収するとのことでした。どういう意味かはわかりませんでしたが、きっとわたしの知らない魔法のような方法があるのだろうと思いました。
そのあとで祖父は、「これからどうする?」と聞いてきました。
高石にこのまま住むなら、タカエさんに代わって家事をしてもらうことが条件。もし家を出るなら引越代は世話する。陽介――わたしの父です――とも話したが、弓が望むなら苅田の家に帰ってもいい。母、恵美子はもう1年ほど実家に帰って戻ってこないので、ぶつかることもないだろう、と。
わたしが漫画やアニメでどたばたしてる間に、家族のあいだでいろんなことがあったんだって、改めて思い知らされました。いつもそうでした。わたしから聞くこともないし、わたしがこんなだから、気を遣ってだれも教えてくれない。
「わたしがここに残ったら、タカエさんはどうなるん?」
「あれはもう家族と同じや。放り出したりはせんよ。仕事は探すかもしれんけど、あっちはあっちで話すし、心配はいらん」
それを聞いて少し安心はしたけど、すぐには返事できませんでした。
正直もう、わたしはひきこもりじゃなかったんです。むしろ独立したかったし、東京に引っ越してアニメの仕事に携わりたかった。だけど、役員はしてるけど給料はなし。「お給料をください」って言ったところで、じぶんになにかできるような気もしませんでした。
無謀にも、アニメーターになりたいって思いは消えてなかったけど、もうネットに絵を上げる気なんかさらさらしなかったし、じぶんの絵が下手だってのは筆先を紙に置いた瞬間にはわかるようになっていました。高校も出ていません。
しばらくここで暮らしながら、また定時制の高校に行って、4年で卒業するとしたら19歳春から、23の春まで。どこに行っても失敗してきたわたしが4年間も? ありえないよ、そんなのはもう。
そしてまたわたしの悪い癖で、明日答えを出そう、今日まで来れたんだから、明日もまだ大丈夫と、結論をずっと先送りにして、その間にタカエさんはクリーニング屋のアルバイトを見つけて、水曜日と木曜日以外は家にいることもなくなりました。
カンズ・シャール・バレーヌの混乱は、10月になっても11月になっても収まる様子はなく、平野さんが口頭の指示で進めていたぶんの把握もままならず、新しい演出は来たものの、一条さんが計画していたアフター処理による画面効果を出せるスタジオが限られ、絵コンテレベルでの抜本的な見直しが必要になっていました。作画打ち合わせで出た指示なども、制作進行が把握はしていたものの、それでなくともヘビーワークだったところに見舞われた混乱で、ミスが増え、それがまた新たな工数を生むという悪循環に陥っていました。
他方、バナナトラップは不慣れなテーブルゲームの制作でスタッフのモチベーションが下がり、中心人物1名が離脱、それを追うようにふたり、3人と抜けていったが、松山社長の話では引き抜き攻勢がかかっているとの話でした。必要な人材の確保に追われ、船体設計に再委託の許可を打診するものの、船体設計の体質は変わることなく梨の礫、余裕だと思われた制作もろくに進まず、ただ無機質に制作期間が削られていきました。
まりりんからウェブ会議の連絡が来て、応じてみると、「このままだとカンズ・シャール・バレーヌは崩壊するので、ユミだけは逃したい。神崎グループを巻き込むわけにいかない。レーザーコルベットが株を全部持ってるから解任はできない。辞表を出して欲しい」との依頼でした。
「辞職したあとはどうなるの?」
「名村にまかせる」
「まかせるって?」
「敗戦処理」
「待って。でも急に言われてもわかんない」
「神崎龍次と話す。いまアポ取れる?」
「いまは無理」
神崎龍次はわたしの祖父です。いまも書斎にいて、アポを取るくらいは簡単にできました。でも、わたしの決断がつきません。断ると青木師匠は苛立ったように息を吐いて続けました。
「わたしは構わないんだよ、なにが起きても。でも、あなたと名村は最悪なにがおきるかわかんない。名村はしょうがないよもう、覚悟してやってんだから。でもあなたは違う。だから……」そこで青木師匠は天を仰ぐようにして、言葉を飲んで、「決心が固まったら連絡して」と結んで会議を終えました。
なんだろう。
なんだろうなあ。
辞表を書けば、いままでのこと、なにもなかったことにはできたんだよ、あのとき。
なむりんともまりりんとも知り合わなかったし、バナナトラップにも行かなかった、カンズ・シャール・バレーヌにも携わらなかった世界に戻れる。PIXIVもまた名前変えてはじめればいいし、髪も染めればいい。
でもそれってさあ、この5年を失うってことでしょう?
苅田から来て、玄関でうずくまって泣いた日に戻るんだよ。
姉はケーキ屋さんになって、母は実家に帰って、祖母はいなくなったのに、わたしだけ昔に帰るって、それって、死ぬのとどう違うの? って。
でも一族に迷惑はかけられない。
まりりん師匠はその直後、なむりん師匠経由で祖父にアポをとって、事の経緯はすべて話したらしかったけど、三人ともわたしにはなにも言いません。そのことをわたしが知るのはそれからしばらくしたあとでした。
ちょうど実家の父から電話が来て、わたしも気が回らなくなり、それで話す機会がなかったのが理由かもしれません。
父からの電話は単純でした。
「恵美子と離婚が成立した」
そのひとことでした。
苅田の家は売り払って、半分を慰謝料にあてる。弓の荷物はお父さん、すなわち祖父宛に送ることはもう連絡してある。電話はこれからは実家ではなく、携帯に頼む。
「わかった」
わたしはそのひとことしか言えず、電話を切りました。
あの母が勝手に家を出ていったのに、どうして慰謝料を払うのだろうと、いぜんのわたしだったら考えたと思います。だけど、神崎家は母の実家には頭が上がらないのだと知ったいまは、不思議とすんなりと受け止めていました。
母の実家が祖父の会社を救ったのなんて、もう大昔の話だし、そもそも祖父の兄の話で、そもそも父は神崎グループとは違う道を歩んでるのに、それでも血に縛られるのが不思議に思える一方で、わたしがこうして大阪でチャンスを得た理由も血にあると考えると、そこに異を唱えるのもおかしいのだと思いました。
――電話では話せなかったこと
父はラインで、そう切り出しました。
――アニメーターを目指しているという話、聞きました。
――黒井にいったときに約束した通り、弓が夢を叶えるまで支援は続けるつもりです。
――だから、月3万円の仕送りはそれまでは続けます。
――孝江さんの話では、弓はよく食べるという話だったので、3万円では足りないかもしれませんが、それ以上は父が受け取りません。
――だからもし、高石の家を出てアパートを借りたいというなら、もう少し多めに支援することもできます。
――遠慮はしないように。家族なんだから。
正直、揺れました。
じゃあ8万円にして、と言えば、練馬でアパートを借りて一人暮らしできたかもしれません。だけど一方では、お金なんかいらない、とも思いました。お母さんがゲームすると学校に行かなくなるって言ったのが本当だった。わたし、甘やかされるとなにもできなくなるから、なにもいらない。って言いたい気持ちもありました。
――夢なんかないよ。いまの生活がずっと続いたらごめん。
そう返すと、
――いいよ、それでも。
と、ひとことだけ返ってきました。
その日はわたしが晩ごはんの用意をして、祖父が書斎にこもったあと、リビングでテレビを見ながら「わたし、結婚したい」と、タカエさんに話しました。
「おっ! 相手だれや? 彼氏おったんかいな」
「相手おらんけど」
「なんや。しょうもな」
「わたしもう、無理やねん」
「なにが」
「生きるの」
「しょうもな」
「人生ってあるやんか」
「ああ、うん。あるな。あるある」
「可能性ってあるやんか」
「あるある。めっちゃあるよ、あんた」
「でも、どこ引っ張ってっても、ぜんぶ無理やねん」
「引っ張りようやろ、あんた。いま3べんぐらいしかひっぱらへんかったわ。もっと百ぺんも千ぺんもひっぱったらええがな」
「千ぺんてなにー?」
「百ぺんの上は千ぺんやろ」
「よー聞かんわ。やっぱタカエさんエセや」
「あんたに言われたないわ」
「でもな。金のため働くんと、金のため結婚すんの同じ思うねん」
「それ、ちゃうよ。ぜんっぜんちゃう」
「そうかなあ」
「旦那が稼いできた金もろうて、生活費のなかから1万円っぽっちしか自由に使えへねんで?」
「でも、働かんでええし」
「働いて10万でももろたら、なんべんライブ行けるか考えてみ?」
「行かんし」
「ドラゴンクエスト何本買えるか考えてみ?」
「買わんし」
「うちは無理やったなー。服も欲しかったし、ライブにも行きたかったわー」
「そーゆーもんかなぁー」
「そー ゆー もん や」
「うちな」
「どしたん」
「アニメの会社、もう辞めよ思てん」
「なしてよ」
「会社潰れかけとん。このままやと爺にも迷惑かかる」
「それで結婚したいってか?」
「うん」
「しょうもな。親父さんはなんて言うてんの?」
「爺にはなんも言うてへん」
「それや」
「それって?」
「あんたいつもそうや。だれにも相談せんと。悪いクセや」
「でも」
「家族やんか。あんたもうちも親父さんも、みんな。なんで相談せんのよ。相談してええのよ」
「会社潰すかもしれんて?」
「ええよ。あんた、親父さんより会社の経営うまいんか? ああ?」
「せやけど」
「相談されんの、嬉しいもんやで」
「じゃあタカエさんもいま嬉しいんだ」
「ああ、嬉しいわ。嬉しーって、見てみいこの笑顔。嬉しー」
「しょうもな」
ネットで調べて、辞表は書いて、印鑑も押していました。あとはひとこと、いままでのことを祖父に話して、謝って、カンズ・シャール・バレーヌに届ければいいと思ってました。タカエさんと話した日の翌々日か、その次かのお昼すぎでした。「話があります」って、書斎の外から声をかけて、その日は祖父の書斎で話しました。
わたしはわたしの言葉で、いままでのことを話したのですけど、祖父はすでに「青木っちゅう女のひと」から事情を聞いて、すべて把握していました。
祖父は言いました。
「名村くんは戦っとるんやろ?」
わたしはどう答えればよいかわからず、「ええ、まあ」と、そんな返事をしたと思います。
「名村くんが戦っとるんやったら、わしは全面的に支援する」
わたしは書斎の外で固めてきた辞職の決意がガラガラと壊れていくのを、どう繕えばよいのかと、身を震わせて聞くしかありませんでした。
「わしはな、名村くんが彩乃に折り鶴わたしたときな、彩乃がありがとう言うのが聞こえたんや。聞こえたやろ、ユミちゃんも。あいつはな。ああゆー男なんや。せやからユミちゃんも尊敬しとんのやろ。それはわしも一緒や。あの男が戦う限り、わしも戦う」
と、弁を振るう祖父の口調はだんだんと芝居がかってきて、本気なのかなんなのかよくわからなくなってきましたが、それは大阪ではふつうのことでした。
「レーザーコルベットか変態カバトットかしらんが、なんぼのもんや。神崎の法務舐めてもろたら困るで。戦う気ぃなら受けて立ったる。せやろ」
浪花節ってさぁ、そーゆー芝居があるんやて思てたけど、ちゃうねん。ぜんぶやねん。もう、この空間ぜんぶ。関西一円、ぜんぶ浪花節やねん。
「せやからな。辞表は出したらあかん。あの男を支えてやりなさい。それで失敗しても、一切責めはせん。青木さんにも伝えてあるねん。神崎はあの男に賭ける。それが浪速の男の生き様やゆうて」
って、なんかもう涙出る。止まらへん。
「なんやそれ。爺、小倉生まれ小倉育ちちゃうん?」
ボロボロボロボロ。爺も泣いてるやんか。なんやそれ。おかしいやろ。
「そこは、ハイブリッドや」
ハイブリッド、意味ちゃうわ。
「おかしいわそれ。ぜったいおかしいて」
第四部 絆
第16章 身の振り方
明けて1月。元旦の街の静けさは例年ならどこか心を浮き立たせるものがありましたが、喪中の年明けにはそれをどこか遠くに聞くばかりで、真新しい下着とシャツとに着替えたほかは普段通りに、タカエさんと交わす言葉もおめでとうとは言わず、ただ、今年もよろしくお願いしますとだけ言って深々と頭を下げました。
喪中の案内は送っていたものの、それでもそそっかしいひとはあるもので、バナナトラップの松山さんもそのひとりでした。まあ、てんてこまいの年末でしたし、致し方あるまいて。
そのバナナトラップ。悲劇のバナナトラップ。1月半ばに松山社長が自ら設定した締切の日が訪れるも、ゲームは完成していませんでした。仕様書から比べるとキャラ数8人の予定が6に、6ステージの予定が4になっており、それはそれでじゅうぶんにプレイはできたものの、船体設計からは未完と評価され、受け取りを拒否されました。そしてこれも本来なら、両者協議しながら規模をコントロールし、完成を目指すのだそうです。おそらく船体設計にも支払いの余裕はなかったのでしょう。バナナトラップはカンズ・シャール・バレーヌに9千万の負債を負い、どこぞのソフトハウスに派遣していたプログラマー2名が離脱、松山社長は名村社長に吸収合併を打診してきました。なむりんが都合した4億のうち、これで約1億が消滅。ここまで、わずか1年でした。
カンズ・シャール・バレーヌは昨年末に制作進行のリードのひとが過労で倒れ、入院。実質的にすべての機能が停止しました。アニメは演出家が倒れても、原画マンが倒れても、代役はどこかから探し出して来ますが、制作進行が倒れたらおしまいです。それにしては容赦のない使われ方をするのが制作進行でしたが、だれもがそういうものとして見ていたと言うか、いえ、その存在は目にも留まっていなかったのだと思います。遠隔のスタジオでカットが上がればいつの間にかそれが手元にある、アフレコの直前になればいつの間にかアフレコ台本とボールド付きのラッシュが手元にある、それはあたりまえのことになっていたのです。
アニメ用の資金3億も、そのうち2億がすでに溶けていました。上がったのはパイロットフィルムのおよそ4分。だけどもう、残り1億ではこのクオリティの作画・演出は無理。オーディエンスの期待は大きく裏切らざるを得ず、作り手としてもそれに納得できるものはだれもいませんでした。
なむりんはそれでもレーザーコルベットに頭を下げ、追加の融資を受けると言い、まりりん師匠に見積もりを依頼しましたが、まりりん師匠がもう首を縦には振りませんでした。練馬のスタジオにはそれなりの設備が整っていましたから、そこにひとを囲って動画の下請けをするのなら大口で仕事が取れる、うまくいけば2年で体制を整えられる、このままスタジオを開けておいても資本金を食いつぶすだけだと訴えましたが、なむりんは拒否。なむりんが拒否ならわたしも拒否です。結果、青木真理子、まりりん師匠はプロジェクトから外れることになりました。それは、実質的な社長を失ったのと同義でした。
2月、青山でイルミネーションジャケットの発表会がありました。レーザーコルベットの関連企業が開発中のLED入りのジャケットで、スマホとつないでいろんな画像を映し出すことができました。クラブ風の重低音のリズムが波打つカクテルライトに彩られたステージの奥のスクリーンに、トロワシムウィユ・ペトリのパイロットフィルムが流れ、DJの紹介でイルミネーションジャケットを羽織った名村英敏がステージに上がります。なむりん師匠は観客にアピールして、スマホを取り出し、ジャケットの配色を変化させて見せました。
わたしも用意されたイブニングを着て、ヘッドセットをつけてステージに上って、アシスタント役としてマイクを渡したりなどしたのですが、ヘッドセットつけてるのにマイクって。なにこのギャグレベルの茶番。
ドレスを着るときブラははずせって言われて、なんかもう、うわーって。なにされるのわたしー、って。まあドレス用のブラってのをちゃんと用意してくれてんけど、先言えや、あるならあるて。焦るわ。鏡見たら、エッロ。なにこれ、うっわ。にく。にく。揺れる揺れる。で、リハーサルんとき「ダンスはできますか?」とも聞かれてんけど、そんなん無理て。ひきこもりやぞ、こっち。調べとけ。神崎ユミにハァハァするスレにぜんぶ書いたるわ――
トロワシムウィユ・ペトリは伝説のメンバーが集結し、じぶんたちのやりたいことに100%全力投球したエッジの効いた作品という扱いになっていました。しかし、エッジの効いた演出部分は、わたしがクビにした平野豹馬と一条一とが実現した部分で、残念ながら青木真理子さえ抜けたカンズ・シャール・バレーヌには実現不能なものでした。むしろ平野さんが配信企業のスポンサードで始めた新スタジオにそのカラーはあり、このころはじわじわと注目を集めるようになっていました。
ミラーボールの回るステージから見ると、何人かのサクラが奇声を上げるほかは投資家の年寄の顔しか見えない、残念な発表会で、このひとたちはいったいいくら騙されているんだろう――なんて考えながら、いちおうは音楽にあわせてリズムを取ったりはしてみました。
発表会が終わって、レーザーコルベットが用意したホテルのラウンジで、わたしはまだ19歳。なむりんもアルコールは苦手で、ふたりでコーヒーを頼んで飲みました。せっかくだからあのエロエロのイブニングのまま来たかったけど、でも、外は寒いし、イブニングのうえにダッフルコートってのもアホの見本だろうし。毛皮とかなら良かった。真っ白い。イタチかウサギか知らんけど。
「なむりん、エロいドレス好きやろ」
「ユミさん、性格も昔の青木真理子まんまですよ、それ」
「ほーなん?」
いやあ、それにしてもね、って苦笑いするから、わたしも、いやぁ、たまらんっすわ、って。
「やりたないなら、断ってもええんちゃう?」と、わたしが聞くと、「ギャラは出てるから」ってなむりんは笑うけど、でもそんなん、4億にくらべたらスズメの涙やんか。
いつのまにかわたしの貯金も数万円台に減っていて、その日は深夜バスで東京へ向かいました。バス一択やな、タカエさん。夜の梅田は遠くで不意のシャウトを叫ぶ男の声と、せわしなく行き交う車の音と、喧騒を抜けて高速道路のゆっくりと回るカーブに身を預けているうちに眠りに落ちて、目を覚ますともう新宿の雑踏の信号のまえでした。
大江戸線の新宿の改札はずいぶん地下深くにあり、まるで二百年前の江戸が地下深くに息づいているかの錯覚を覚えました。大江戸線にはワイパーがありました。きっと地下の江戸には雨が降るのです。
練馬のなんとかというスーパーを目指して、その2階へ上がるとたくさんの机とパソコンが並べられたカンズ・シャール・バレーヌのオフィスがありました。人気は少なく、再売り込み用のプロモーションビデオを作るひとたちと、制作進行と経理のひとは敗戦処理に追われていました。いまもまだポロポロとカットが上がり、それを検収するほかに、契約書もなく振り出した仕事の上がってきた請求書を、倉庫に積み上げた成果物と突き合わせて支払いをするのだそうです。家賃と光熱費と、機材のリース代、人件費と、いまもそれなりの経費がかかっていました。
「バスで!?」
なむりん師匠は驚いていましたが、師匠だってそうですよ。
「新幹線でいいよ。精算するから」
「でも、お金ないし」
「あるある。出張旅費くらい出せるって」
「売り込み先は決まりました?」
「目処だけ。あ、そうだ。来月からユミさんにも役員報酬出すから、あとで口座番号とか教えて」
「役員報酬!?」
「まあ、ちょっとだよ、ほんのちょっと」
それって、練馬にアパート借りれるくらい?
なむりんは首を捻りながら、両手の指で7の数字を示して見せました。
「ほんとにいいんですか? 貧乏なのに」
「このまえみたいなプロモーションとかあるし、タダ働きってわけにはいかない」
あれはプロモーションじゃなくて、投資詐欺の片棒担ぎ。
「あとでメシ食いに行く?」
と、なむりんは誘ってくれましたが、その日はアパートを探すつもりでした。だから、
「ちょっと見たいところがあるので、ひとりで食べます」
「あ、そう。領収書取っといてくれたら、会議代で出せるよ」
「会議代?」
「中華でも牛丼でも会議代で出る」
どんな会議だ。
不動産屋のまえに貼られた物件をながめて、写真も間取りもあったけど、それでわかるのは家賃と間取りと新しさ。こうやって選ぶ限り、安いもの=正義にしかなんなくて、わたしはたとえば、高石のお屋敷みたいなところだったらサッシ窓でなくてクルクル鍵でも別にいいんだけど、住心地はあたまのなかで思い浮かべるしかありませんでした。
至近にコンビニあり、って読むと、コンビニとアパートの部屋を行ったり来たりして生活してるじぶんしか思い描けなくなるので、むしろその中途半端な情報は出さないで欲しかった。東京なんだから、コンビニくらいどこにでもあるよ。と、一件の不動産屋に勇気振り絞って入って、「表にあった月4万5千円の……」というと、「あれは古い情報だから」と言って、まったく違った物件を紹介されたり。それは要するに、詐欺とは違うの?
「学生さん? この春から?」と聞かれて、「いいえ、アニメスタジオの取締役をやっています」と答えたいのはやまやま、まだお給料だってももらってないし、しかももらえるのは月に7万円だっていうし、ええ、まあ、なんか、そういう感じです、というと、「大阪から?」と尋ねられました。「ええ、まあ、なんか、そういう感じです」って、東京だとイントネーション違うの? って。
わたし、不動産屋って、車に乗って、「こちらの物件になります」って案内されるものだと思っていたのに、地図渡されただけ。練馬は3万円から部屋はあったけど、不動産屋さんいわく、女性にはオススメできない、って。うん。言いたいことはわかるけど、じゃあオートロックの部屋となると5万からでしょう? その差額の2万円ってなに? みたいな。それって、不動産屋と痴漢がグルになったら、いくらでも高い物件売れるってことじゃない?
それで、オートロック、4万円台、拝島駅15分、行ってみる! って電車に乗ると、拝島、遠い遠い。あと似たような値段で福生駅8分。行ってみる! 遠いわ! まあ、5箇所くらい見たけど、そのうち一箇所は「違法建築です、撤去してください」って役場が立てた看板があって、大阪もたいがいだけど、東京もたいがいだなと思った。
オートロックで、家賃は5万円。給料と仕送りあわせて10万円。残り5万。電話代1万円。あとはわかんない。なんとかなるかな。
で、その日はなむりんの家に無理やり泊めてもらうことになって、手ぶらじゃ悪いので、パスタの材料買ってって、パスタ作った。六畳と台所の狭い部屋。動画机があって、押し入れは開けっ放しで、カラーボックスに服と雑誌とが折り重なって入ってて、テレビ台の上にはフィギュアがびっしり並んでました。
「ベッド……」と言って、なむりんはベッドの匂いを嗅いで、「ちょっと臭いけど、眠くなったら使って」と言って、動画机の椅子に座りました。
「ほんとだ。ちょっと臭い」
「あえて嗅がなくていいから」
本当は帰りのバスのチケットも取っていたんですが、なむりんが新幹線代を精算してくれるって言うので、まあ、今日は夜通し話でもして、睡眠はあした、新幹線で取ればいいかなと思ってたんだけど、不動産めぐりで疲れてたのか、あっさり寝ちゃった。
でも、寝る前にいろいろ話せた。
「アニメーターは無理だけど、制作進行ならできると思うよ」
「車の免許あるの?」
「えっ? いるの?」
「いや、あったほうがいい。いろんなスタジオ回るから」
「じゃあ、ハイヤーで」
「一瞬で飛ぶわ」
「なむりん、お嫁さんもらわないんだ」
「ほしいけど、無理っしょ」
風呂はあるけど、汚れてるからといって使わせてもらえませんでした。じゃあ、シャワーだけ、というとなむりんは風呂場の確認に行き、「やっぱダメ」って。
「風呂場になにおんねん」
「切り身になったトトロ」
「見たいわ、それ」
いちいちセンスおかしい。
「なんかさあ、子どものころって、みんな結婚する思てなかった?」
「ああ、わかる。クラスで男子のほうが人数多かったから、あぶれたくねぇーって思ってた」
「やっぱり結婚したかったんだ」
「ガキのころだよ」
なんか、眠くて眠くて。
「こたつ好き」
「こたつで寝ちゃいかんぞ」
「どうして?」
「こたつに失礼」
「なにそれ」
「だから寝るなって」
「昼間ね。アパート探してたんだ」
「へえ。どうだった?」
「オートロック高い」
「そりゃそうだ」
こたつの魔力でもう、ほとんど寝ていたんだと思います。なむりんの声もぼんやりしていたし、目の前の景色も蕩けるようでした。
「ほんとうは、アニメーターになりたい」
朝起きると寝汗びっしょりで、なむりんは動画机に突っ伏して寝ていました。この隙に下着だけ替えようと思って、荷物を取って、ふとんを被ったままごそごそ着替えて、「コンビニ行ってくる」ってひと声かけると、「ん、ああ……」ってモゴモゴしはじめるなむりんを置いて、手ぐしで髪を整えながら外に出ました。
朝、朝、朝、ぜんぶ朝。朝らしい朝。スズメがチュンチュン鳴いてて、通勤通学のひとが道路の脇を歩く朝。くつしたもなしに履いたスニーカーのつま先を蹴って、スチールの階段をリズムよく降りては、昨日の夜見かけたコンビニ、たしかこっちだと頭のなかで組み立てて通りに出ると、そこも朝。コンビニの看板。トラックの煙。歯ブラシと、化粧水を買って、あとはオレンジジュース。おにぎりも食べたい。ツナマヨ、焼きおにぎり、なむりんのはようわからん。テキトウ。目ぇ瞑って2個手にとって、千円ちょっと。あ、それとレジ袋お願いします。
女が男の部屋に入り込みひと晩を過ごすことが、世間でどう言われているかを知らないわけではありません。でもそれはお互いに恋というアンテナをもったひと同士の話です。
恋人がほしいと思ったことは、あまりありません。結婚は――すれば楽になるとは思いますが、だれかと寄り添って暮らすことの困難さは両親を見てよくわかっています。わたしも母と同じですから、ときどきじぶんを抑えきれなくなって、暴れたり、ものを壊したりしていました。いつまたそれが出るかもわからないのに、だれかとちゃんと暮らしていけるとは思えませんし。
だけどこうやってなむりんとの関係のように、恋でもなんでもなく、ふつうにひととひと同士で付き合えるとしたら最高だと思います。
以前にも言いましたとおり、女子のハートを掴むのは理解だと思います。男子はわかりません。男子はメカですから、カブトムシでも与えるのがベストなのかもしれません。女子にとっては理解し合うことが恋であって、その先にあるお互いに隠してる凸凹を突き合わせて気持ちよくなるのはオマケです。ただこのところはそのオマケばかりを目当てにするひともいるようですが、それもまたわからなくはないんです。だって、理解されるのは、怖いです。理解し合って恋なんかするより、ただ気持ちよくなりたいって、そう思うこともあります。
この日だって、もしなむりんがそういうタイプのひとだったら、わたしはただ、「あーもーしょうもな」とか言って、それを明け渡すことに躊躇いはなかったと思います。逆に気分次第ではわたしから、どうだわたしを気持ちよくしてみろと馬乗りになることだって考えられるわけですが、でもそれは、どうでもよいことです。しょせんは肉体のこと。それで満たせない飢えがあるから、生きているのです。
理解されるのは怖いです。恋に落ちるのは、怖いです。わたしはそうやって、お互いの心を開きあって、理解し合って、蕩けたチョコレートのようなカップルになるよりは、お互いにわかりあえないものを目の前に積んで、後手7三金、胸のばってん、いやこりゃまたわかりませんな、いやはや若気の至りでござると、友だち同士のように笑いあって、「あのときはどうかしてた」「あんたほんとおかしいわ」と言えるひとがそばにいたらと思います。なむりんはそれにとても近い存在です。
だからわたしは、なむりんに恋をしません。向こうもそうです。その間に、仮に間違いがあって、仮にわたしが子を宿し、捨てられて、私生児をもうけたとしても、それはふつうのことです。
ただこれも、漫画やアニメで世界を覚えたわたしの所感ですから、肉体的な実感はないものだと思います。
おにぎりを食べながら、これからどうするつもりなのか話しました。
レーザーコルベットのことを詳しく聞いたのもこのときです。レーザーコルベットの相談役をしているひとが、師匠の弟さんのお店を支援してくれたこと、その弟さんが家を失くしたあとも、マンションを安く世話してもらっていること、ヤクザの構成員だった同級生が、おそらく自殺しただろうこと。それに、会社名の由来。それは唐津で十四を数える曳山の架空の第十五番手であること。
捨てたはずの地元の縁を頼ることに抵抗はあったそうです。わたしのためにそこまでしてもらわなくてもと言うと、それは違うと師匠は言いました。アニメーターではもう首が回らなかったのだそうです。
「いつもあと何日か、何週間か生き延びるための金を探してた。アニメーターになってから、ずっと」と、なむりんは述懐しました。
それはどんなに絵が描けようが訪れるのだそうです。この仕事はトーナメントのようなもので、負けたものは脱落していく。最後まで残るのは運。その勝った人間ですら、一般のサラリーマンの半分しか稼げていない。
わたしは正直、レーザーコルベットからはもう離れようと、まりりん師匠と同じことを言うつもりでした。だってこんな出鱈目なやりかた。イルミネーションジャケットだってただの投資詐欺だし、きっとそういうことをたくさん仕掛けてきた会社です。でも、言えませんでした。
午後の新幹線を取って、事務所へと顔を出すと、デザイナーの高橋くん(年上ですが)がホームページを作っていました。カンズ・シャール・バレーヌのホームページは、藤島さんがやっていたように社内で用意していました。まあ、それを言うと高橋くんは「それよりはぜんっぜん新しいと思います」と言っていたのですが、まあわたしもたいがい暇だったので、後ろで操作を眺めていました。
「見られてると緊張しますね」
「そんなんすぐ慣れるわ。慣れるまで続けて」
「むちゃくちゃ言いますね」
「エグザイルのぐるぐるまわるやつ」
「やめてください」
というとまあ、高橋くんは緊張をごまかすためか、いろいろと説明しながら操作してくれて、わたしからも、このアイコンはなに? こっちはどうなってるのん? と聞くようになって、話を聞くうちに、これ、じぶんでもできるんじゃないかなって思えてきました。理解が早いのはアホの特権ですわ。
「高橋くん、ウェブよりやる仕事あるよね?」
「ああ、はい。ありますけど」
これや。
「これ、うち引き継ぐんで、もうちょっと教えてもろていい?」
「はあ?」
「なむりん! 今日も泊めて!」事務所の奥のなむりんに言うと、「大声で言うな!」って、秒で返ってきました。
「風呂も入るんで、洗っといて!」
「来るなよ! 大阪帰れよ!」
「いや、ええわ、うち洗うわ! 切り身のトトロ片したるわ!」
どんな会話だ。
と、その日のことでした。
なむりんが電話を受けて、とつぜん家に帰ったので、わたしはてっきり風呂の掃除でもするのだろうと思い、夜の8時すぎにアパートを訪ねると、部屋はがらーんとして、机と衣料品の山を残してなにもなくなっていました。
「はりきりすぎやろ、これ」
こんなときでも冗談めかした言葉が出るのは、これはもう染み付いた性なのですが、なむりんは口の曲がった悲痛な笑顔から「やられた」という声を漏らしました。
「どないしてん? 空き巣?」
「もっとひでえ」
「もっとって?」
「レーザーコルベットの連中がぜんぶ持っていった」
第17章 腐ったバナナ
2024年の2月に、初めての役員報酬が振り込まれました。具体的になにをして稼いだお金かと言われると、イルミネーションジャケットの発表会でエロいドレスを来て見世物になったくらいですので、きっとあのステージの、あのわたしに、その価値があったのでしょう。
そしてそれをどこから嗅ぎつけたのか、しっかりと『神崎ユミにハァハァするスレ』に掲載するものがいて、まあ、なんというか、死ねよって感じですよね。
はじめてのお給料をもらって浮かれた神崎弓、つまりわたしは、タカエさんとたこ焼きを食べに行きました。「大阪じゅうのたこ焼き制覇してみーひんか」ってタカエさんがいうので、まずは1件目、アメリカ村の甲賀流本店に朝から並んで、すぐ脇の広場で食べて、「スカジャン欲しいな」「おそろいで買う?」「タコの柄がええな」「じゃ、次の給料日で買おか」みたいなことを、たこ焼きをほふほふと口に運びながら話しました。
わたしが給料をもらうようになって、タカエさんはよく「これからどうすんの」って聞いてきたんですが、どうするって、いつまでも高石の屋敷にいるのか、独立するのか。みたいな? あるいは、ひとりで生きるのか、結婚するのか。みたいな。
「女ひとりで生きるんは厳しいけど、クソみたいな男に捕まるよりはずっとマシや」って、その日も楊枝に刺したたこやきを持ったまま、「ま、息子夫婦は幸せそうにしとるし、やっぱ、男運なんやろな」って。
「ヤドカリみたいやな」
「なんやそれ」
「勝手にカラダ大きゅうなって、勝手に出てかなあかんくなる」
「ああ、せやな」
で、平野豹馬と一条一の共同プロジェクトの全容が出たのもこのころですね。ちらちらとリークはされて噂にはなっていたんですが、彼らが作った5分半の映像はほんっとに凄まじかったです。トロワシムウィユ・ペトリも凄まじかったんですが、それを凌駕して、ネットの反応は「こっちが本物だった」みたいな流れになって、またわたしが叩かれてました。
クビにしろって言ったのは事実だけど、実際にはレーザーコルベットの都合で追い出されたようなものでしょう? それをなんでわたしが責められなきゃいけないのかな、って。
で、これでまたしばらく叩かれるんだろうなって思ってたら、叩かれたのってほんの一時期だけで、向こうのプロジェクトが波に乗るとすっかりこっちは言及されなくなって、なにそれって感じ。神崎ユミにハァハァするスレでは、わたしが書いた物語ってのが勝手に始まってて大喜利みたいなことになってるし、なんかこう考えていくと、いちばんクリエイティビティのないことやってんの、わたしなんじゃないかな、とも思ったり。
月に2回くらい、東京に出ていました。新幹線で往復して、すっかりものが片付いたなむりんちに泊めてもらってたんだけど、経理のほうから、交通費だけ計上して宿泊費が上がってないと不自然だってわけのわかんない難癖をつけられて、ほんと、なにそれもうって感じで、ここの社長、大阪から愛人呼び寄せてはるわーっ、そんなん経費で落とせませんわーって、アホちゃうかって、それでまあ、光が丘ってとこにホテル用意されるようになって、そっち泊まることになりました。光が丘って。少女漫画の主人公住んでそう。
で、このホテルってのも、微妙に懐かしいもので、使い捨ての歯ブラシとか、ティーバッグのお茶と紙のフタがついた湯呑とか、ああこれこれ、あったあった、みたいな変な感動も覚えたんですけど、そんな感動で心躍ったのもせいぜい2回でしたね。あとはまあ、よう! また会ったな! 歯ブラシ! またあんたかいな。ああ、わしや、使わせてもらうで。みたいなツーカーの仲でしたよ。
でも敗戦処理中の職場って、行ってもやることなくて、なむりんのほうはいろいろ忙しそうに飛び回ってたけど、わたしは藤島さんのマネしてパペットでブログ書くくらいしかありませんでした。とりあえず、ホームページの更新の仕方は基本的なことだけは教えてもらって、よっぽど特殊なことでない限りわたしでできるようになってましたから、次のお給料からは「ホームページを作ったぶんのお金です!」って言えるようにはなったわけです。
サイトに乗せるニュースなんかも、わたしが記事を書いて更新する手はずになっていたんですが、飛べない鳥にニュースなどあるはずもなく……と思っていた矢先、そのニュースは飛び込んできました。
まあ、そのまえから、なむりんがよく大阪に来ていたのは知っていましたし、祖父に会ってバナナトラップ関連の話が進んでいるのもまあ、把握はしていたんですが――だって、一応は役員ですもの、議事録にもすべて目を通していますわ――でも、実際に弁護士さんからプレスリリース用の資料もらったら、やっぱ驚きますよ。ついに来たかー。みたいな。
――カンズ・シャール・バレーヌ、バナナトラップの株式の51%を取得。バナナトラップ新社長には、カンズ・シャール・バレーヌ社長名村英敏が就任、現社長松山貞俊は副社長として同社に留任する。
これはまあ、わたしからしたら、カンズ・シャール・バレーヌのお金をバナナトラップが溶かしたんだから当然の話だったんですけど、でもあとから聞いたんだけど、まりりんからしたら痛恨の大誤算。ここから不可逆に流れが変わったのだそうです。
なんでも、それまではカンズ・シャール・バレーヌにわたし、神崎弓が絡んでいるといっても神崎との資本関係はなかったし、どんな失敗をしても簡単に切り捨てられた。それがバナナトラップを介して資本の接点ができてしまった。
その危惧を現実にしたのが、バナナトラップから松山貞俊がかつて在籍した老舗のソフトハウス、クールエーに出された訴状でした。
バナナトラップからってことはなむりんからってことになるんですけど、なむりんだって会社の経営なんかわかってないし、レーザーコルベットの言いなりですよ。松山の古巣のクールエーは小さいソフトハウスだったんですけど、そこそこ当たったIP……知的財産を持ってて、その権利の割譲を求める訴訟でした。
どういうことかって言うと、クールエーで開発したゲーム、仮にタイトルを『尻出しクマの子かくれんぼ大会』としましょう。これはもちろん開発元のクールエーが版権を持っています。もちろん社員は開発したゲームの版権を主張しないという書類にサインしてます。
だがしかし!
ばばーん!
これをレーザーコルベットは「時間外労働ぶんはチームリーダーである松山貞俊が保有する」って主張したんですねぇ。つまり、無報酬のぶんまで会社のもんちゃうやろ、ちゃんと社員に払ったらんかい、と。
ふつうは認められないと思うんですよ。いや、知らんけど。でも、仮にこれで裁判になったら、労働基準法が守られていたかどうか、契約書に不備はなかったか、すべて調べられて、関係者もみんな裁判所で証言しないといけなくなる。そして万が一にもレーザーコルベットの主張が認められて、おおそうだ、版権は松山貞俊にもあるはずだ、なんてことが判例になった日にゃあですよ? ほかの版権もそうやって手放さざるを得なくなる可能性が出てくるわけですよ。
まりりんが言うには、大手だったらぜったいに和解しない、蹴散らしてるって言うんですけど、クールエーは小さいソフトハウスで、ビジネスソフトとかいろいろ手掛けていたんで、裁判のリスクを考えたうえでの決断だったんだと思います。彼らはゲームを捨てました。
『尻出しクマの子かくれんぼ大会』の版権なんか取ったところで、ほとんど儲けはないですよ。クールエーもそんなもんにこだわってもしゃーないし。でも、クールエーのその行動が、レーザーコルベットの成功体験を作ってしまったんですねぇ。いやですねぇ。
そしてもうひとつ。
世間が注目したのは……
それを仕掛けたバナナトラップの資本金が神崎グループの会長の懐から出ていた!
……という点で、クールエーが手を引いたのも神崎グループが後ろに見えたからだとも言われています。
バナナトラップの資本が神崎からといっても49%なので、カンズ・シャール・バレーヌの51%と対比すると0に等しいんですよ。そんなん、多数決で勝ちか負かですから、51の勝ちですよ。でも、世間はそうは見ない。むしろカンズ・シャール・バレーヌという謎の会社も神崎グループのトンネル会社だという見方が支配的になる。音もなんか、ほら、カンズ・シャール・バレーヌ、かんず・ぁーき・ぐるーぷ、と、似てなくもない。まあこれは無理やりだと思うけど、ネットには書いてありました。いや、似てるかぁ?
いまにして思えば、まりりん師匠がカンズ・シャール・バレーヌを離れていたのが痛恨のミスですよ。だけどこの当時、このニュースリリース、わたしがホームページの記事を上げたんですが、「おっ、やっと少し回収できた」くらいにしか思いませんし、まりりん師匠いなくてもできるじゃん、むしろせいせいしたわーくらいの感覚ですよ。
この翌日くらいに、なむりん、相当まりりんから罵倒されたらしく、落ち込んでました。そしてわたしは、そのときですら、出ていったまりりんがやっかんでる程度にしか思っていませんでした。
それにわたしのなかにも、資本をちゃんと回収すれば、またわたしのアニメの制作に戻れるんじゃないかっていう期待がありました。このときはもう「わたしの」じゃなくてもいい、カンズ・シャール・バレーヌでアニメを作りたいってのが最優先で、いや、あるいはもう青木真理子にいいとこ見せたい、平野一条を蹴落としたいって気持ちのほうが強かったかもしれません。それに、会社が安定したらわたしのお給料だって15万とか20万とかになるわけでしょう? ひとなみに練馬にオートロックの部屋を借りて暮らせるわけでしょう? と、いま思うとその金額もささやかなものなんですが、当時のわたしには、それが絶対的な正義でした。
で、こうしてバナナトラップ問題にケリをつけました。
じゃあ、次は?
もちろん、平野一条プロジェクトです。
わたしはなんども彼らのパイロットフィルムを見て、トロワシムウィユ・ペトリとの共通点をたくさん見つけていたので、動画を一時停止して、該当箇所に◯を付けたものを大量に用意して、パペットのブログに投下しました。それはすぐに、神崎ユミにハァハァするスレから拡散し、「神崎グループが動き始めた」という噂になってアニメ業界を駆け抜けました。
そのブログはすぐにレーザーコルベット・ジャパンにも見つかって、なむりん経由でクレームをもらって取り下げましたが、ハァハァするスレはもう、ハァハァハァハァのオンパレードで、やったった、ついにわたしはやったったっていう謎の高揚感が全身を駆け巡っていたんですけど、でもやっぱ。じぶんのなまえがネットで連呼されるってのは、コワイ、ちょっとコワイ。
それで、高石の自分の部屋にいるとき、まりりんからMEETの連絡が入ったんですけど、うわーっ、きたかーって感じ。
無視しても良かったんですけど、このときはわたしのほうも少し気が大きくなってますし、なにしろお給料をもらうカンズ・シャール・バレーヌの役員でしたから、ちゃんと会談に応じました。
「余計なことしないんで欲しいんだけど」
と、いきなり喧嘩腰のまりりん。
「いまなにがおきてるか知ってる? ちゃんと名村から聞いてる?」
「知っています。それがなにか」
わたしのこの口調もうわーって感じですけど。
「だったらなんであんなことしたの。説明して」
「わたしにあなたに説明するメリットありますか?」
まりりんは大きなため息をついて続けました。
「あのねえ、名村、とんでもないことしでかしたんだよ? それが神崎グループが糸を引いてることになってんの。あんたらこのままカンズ・シャール・バレーヌ続けても利用されるだけだよ?」
「それは青木さんも同じだったはずです。わたしや名村さんを売ってでもアニメを作りたい。それが性だって言いました。わたしが同じじゃおかしいですか?」
「だから、このまま続けてたらあなたたちふたりとも干されて、アニメ界に居場所がなくなるの。作れなくなるの」
「やっかみですよね」
「はあ?」
「あなたがいなくなって、わたしが仕切るようになってお金を回収できたから、それで言ってきてるんですよね。わかります」
「あんたバカなの?」
「そうやって感情的になる。もう少し冷静に話せませんか?」
そう話しながら、これは母の話し方だと、わたしは気が付きました。母は怒るとき、いつも敬語でした。ちょうど、漫画やアニメの悪役のように。それを思い出すと急に動悸がしてきました。
「あのね、ユミ」
わたしはもう、言葉を返せません。
「名村から聞いてるかもしれないけど、わたし、5年動画やってたの。名村の先生やってた時期も含めると6年。なんでか聞いた? 3年間引きこもってたの。だからユミ、あんたのことはわかるよ」
そこで少しまりりん師匠は言葉を選びあぐねているようでした。
「名村から写真見せてもらった」
写真?
「手首の」
ああ……。あれ……見せたんだ……。
「名村に聞いたの。なんでそこまで入れ込んでんの? って。そしたら、ユミはまりりんに似てるから、まりりんへの恩返しだって。わたし、へーって言ったの。似てるって? どこが? って。そのときだよ。写真見せてくれたの。わかる?」
「わかんない」
「わたしににも同じ傷があるんだよ。見せようか? いや、見せるよ。ほら。よく見て。同じでしょ? 両方の手首にあるよ」
「……」
「わかるよ。名村の裏切りだって思ってるよね? でもね、あなたを助けたいんだよ。わたしの過去をぜんぶ晒してでもあなたを助けたい」
「うるせぇよ……」
「なんども死のうと思った。どうしてこんなにわたしだけ描けないんだろうって。拒食症になって体重30キロまで落ちたこともあるよ」
「だったら死ねよ! ババァ!」
「ユミ!」
「60過ぎて若作りして出てくんな! 勝手に手首でもなんでも切って死ねよ!」
叩きつけるようにノートPCを閉じて、これも母から受け継いだ気質でした。
わたしはこういう気質は血液型のように親から子に受け継がれていくのだと思っていました。だけどそれも調べてみると、50%なのだそうです。わたしは、わたしのこの気質が母から受け継いだものなのか、家庭環境から身につけたものなのかわかりません。
祖父が心配して二階まで来てくれました。
「だいじょうぶか、ユミ。なにがあったんや。開けるで。ええか」
わたしはそのとき、床に座り込んで顔を覆って泣いていました。
この日ずっと、あたまのなかに、カイガラムシがびっしりと着いた枝の絵が浮かんで離れませんでした。庭にあった木だと思います。その木だけ真っ白く枝を覆われて、そのまま弱って枯れていったと記憶しています。
その日は、わたしが夕食の当番でしたが、タカエさんが代わってくれました。
「急に言われても、冷蔵のなか把握してへんし、ようわからんわ」
と、言う割には豪華な食事が出てきて、わたしの当番のときより、ずっと美味しくて、品数も多いのに、わたしは、なんなんだろうって。
翌日、昨日叩きつけて閉じたPCは壊れてはいなかったようで、すぐに画面は出てきたのですが、MEETの画面はまりりん師匠がまだいるような気がして、怖くて恐る恐るウインドウを閉じました。
本当は謝らなければいけないことはわかっていましたが、もう無理な話でした。
連絡用に使っているスラックを開くと、なむりん師匠から「大逆転の手を見つけたかもしれない」との連絡が入っているのを見つけました。だけどそれをどう受け止めて良いかもわからず、なにも考えることなくただぼんやりと画面を眺めていました。
わたしはなんで生まれてきたんだろう。だれかの役に立つためか、それとも幸せになるためか。もし生まれた理由がそのふたつなら、わたしにはもう、そのどちらも手に入らない。
しばらくぼんやりしていると、スタジオの高橋くんからスラックがはいりました。
――社長が怪我して入院しました。詳細は追って連絡します。
って。
社長が……?
それはつまり……なむりんが?
第18章 ユミ改造計画
新幹線のなかでもPCを開いて続報が入るのを待ちました。まさかとは思いましたが、自殺未遂かもしれません。あるいは他殺、殺人未遂の可能性もあります。だけどそこに入ってくるのは社長の話ではなく、レーザーコルベットの話ばかり。
曰く――バナナトラップが聖蹟桜ヶ丘の老舗スタジオに内容証明を送ったらしいと、まりりんから照会があった――
バナナトラップにはレーザーコルベットからの役員が3人入っています。社長が事故の隙に独断で動いたのでしょう。だとしたら、その事故は本当に事故なのでしょうか。バナナトラップ副社長松山貞俊に問い合わせるも、事態は把握しておらず、唐津のレーザーコルベット日本法人に問い合わせているが、芳しい返事はなしと、スラックに上がりました。
――もし、レーザーコルベットが本当に動いているとすれば、クールエーのIPを奪ったときのように聖蹟桜ヶ丘からも同様にIPを奪おうとしている可能性が高い。もちろん相手は弱小ソフトハウスではない、日本を代表するアニメーションスタジオがクールエーのように簡単に屈するとは思えない。
――しかしたとえば、聖蹟桜ヶ丘のIPを巡って裁判にでもなれば、多くのスタッフが証言台に立たされる。そこで暴かれるのは大量の時間外労働と、大量に結ばれた杜撰な契約。それが聖蹟桜ヶ丘だけでなく、関係するスタジオ全体への絨毯爆撃となる。これは、まりりんが言っていた通り、名村英敏の命脈を止める。
なむりん師匠が聖蹟桜ヶ丘に企画書を出した話を聞いたことがあります。魔法学校を舞台にした物語で、その案は却下されたが、似たような別案がすぐに採用されたと愚痴っていました。数日まえ、なむりんの部屋に荷物がごっそりと運び出されたことを思い出しましました。レーザーコルベットはあのなかから、自分たちが奪えそうなIPを探していたのです。
羽田、浜松町から大門へ、地下鉄大江戸線で練馬、タクシーを拾って、順天堂大学附属病院へ。
エレベーターで3階へ、病室へと急ぐ廊下、病院に似つかわしくないスーツ姿の3人とすれ違いました。ヤクザだ。地元でも何度も見てきた。こちらの姿を舐めるように見てすれ違う。わたしが神崎弓であることを確かめるように。
病室の扉をノックすると高橋くんの「どうぞ」の声。
「神崎です」発声と同時にドアを開くと、足を吊ったなむりんと、そのベッドを囲んで高橋くん、経理の井澤さんがいました。
「容態はどうなんですか?」
「左足骨折。全治3ヵ月だって」と、高橋くんが答えると、「若者なら1ヵ月って言われた」となむりんが笑いながら付け足し、さっきヤクザものとすれ違ったことを伝えると、レーザーコルベット・ジャパンのひとたちだと教えてくれました。
「なにをしに?」
「見舞いと、少し仕事の話」
「仕事というのは?」
「聖蹟桜ヶ丘の件。訴訟を起こす気でいるけど、待って欲しいって頼んだ」
「なにが目的なんですか?」
「なんか、本気でIP奪えると思ってるらしい」
「それで、ラオスのアニメスタジオ押さえてるから、そこで作らせるって。あたまおかしいですよ、あいつら」
思わず高橋くんが割り込んだのを、なむりんは口に人差し指をあてて「声が大きい」と制しました。
神崎船体設計がなにも知らずにゲームを作ろうとしたように、彼らはなにも知らずにアニメを作ろうとしている。日本のスタジオにはもう入り込む余地はないが、東南アジアに興っているアニメスタジオは簡単に買収できた。規模もかなりのものになるというが、アニメは製作管理のノウハウがあってこそ形になることを彼らは知らない。じぶんたちでも、君の名は、鬼滅の刃に並ぶものを作れると信じている。
「純粋だよね」と、なむりんは笑いました。
「いや、笑ってる場合じゃなくて、訴訟はどうなるんですか? 実際に裁判になったら……」
「まあ、めんどくさいことになるよね」
いや、だから、もっと真剣に考えて欲しいのに。
「うちの会社、だいたい3億のマイナスなんです。それを埋めるあてがあれば、考えてもいいって話でしたね」と、高橋くん。
「3億を?」
「青木真理子にも散々言われたよ。なんで相談しなかったんだって」
「でもそれは、まりりん師匠が金のことは言うな、って」
「真に受けるなっちゅう話しよ」
ちょっとそれ、ハイコンテクストすぎる。
そう言えば、と、わたしは思い出しました。
「昨日スラックでもろてた件は?」
「ああ、あれ? いま、青木真理子に相談中」
「どういう話?」
「学校の先生やらないかって話が来てる。東南アジアの、アニメの学校の」
なんだ……せいぜい数百万の話……。しかも東南アジアとなれば、もっと単価は下がる。その時は正直、そう思いました。
「カリスマが欲しいんだって。宮崎駿とか、庵野秀明に直接授業してもらうみたいな」
それなら確かにもう少しましな値段になる。それでも3億に届くはずがない。
「ツテはあるんですか?」
「ユミを……」
「わたし?」
「1年で総作監レベルに育てる。そのドキュメントを売る」
「ちょっと待って! わたし!? 1年で!? 作監レベル!?」
「違う。総作監レベル」
「できるわけあらへん、そんなの……しかも、1年!?」
「3億で売るんだから、インパクトないと話にならん」
「インパクトって!」
「めちゃくちゃありますよね、インパクト」
「高橋くん!」
「救世主登場ですね」
「井澤さん!」
そのとき2月の末でしたから、4月の頭から翌年2月の末までに完成させる。言われたときは驚きと同時に、ぱーっと目の前に光が挿したように感じました。でも、プレッシャーが大きすぎます。プレッシャーに弱い質なんです。いや、プレッシャーに強かろうが弱かろうが、そんなの、夢物語じゃないですか。
「わたしの1年前の絵といまの絵、並べて見せましょうか? 成長なんてしてないですよ、わたし」
「だからいいんだよ」
いや、それ、師匠さりげなくわたしが成長してないこと肯定したよね?
「幸いなことにPIXIVにいままでのポートフォリオが残ってる。これを1年後と比べて、ばーんと載せて、『最強のアニメーション学習法! 神崎メソッド!』として売り出す」
「せめて名村メソッドにできませんか? わたし、叩き込まれるだけなんで」
「たしかに」
「神崎さん、いま叩き込まれるの認めましたよね?」
「高橋くん!」
わたしの声は、病院に響かせるには少し大きすぎました。なむりんはたぶん1週間もすれば退院できるだろうということで、本格始動はそこから、まあ、そのまえにまりりんの確認も取るんですが、昨日の今日だけに少し気まずい感じでした。
なむりん師匠からは、とりあえずいまのいちばんうまく描ける絵をPIXIVに載せておくよう言われて、病院をあとにしました。
「あとで青木真理子からも連絡が行くと思う」
と、なむりんは言うけど、ええーって感じ。
要はこの作戦、仮にわたしが上達しなかったとしても、レーザーコルベットを足止めできればよかったのだと思います。時間さえあれば神崎グループも動けますし、聖蹟桜ヶ丘のスタジオも訴訟に対して準備ができます。わたしは、囮のようなものです。そう考えると、気持ちは少し楽になりました。
「わたし、風俗に売られるのかと思った」
高石に帰って、夕食後の片付けをしながらタカエさんと話しました。
「なんなん、その話」
「カンズ・シャール・バレーヌ、3億の借金あんねん。わたし、役員やんか」
「3億なら逆に心配あらへん。さすが風俗でもそない稼げへんし」
「ああ、せやな」
「で、どうすんの、その3億」
「わたしを改造するんやて」
「改造て。それ風俗よりキッツいんやないか?」
「ああ、まあな、そうかもしれんな」
「でもまあ、よかったわ」
「よかったって、なにが?」
「こないだ、キレ散らかしとったやん」
「あれな」
まあ、それに関しては後悔してばっかり。
「タカエさん、ゲームせえへん?」
「おっ、ええな。相手したるで」
「改造計画はじまったら、ゲーム封印するんで、最後のゲームや」
タカエさんに話すといろんなことがすーっと楽になりました。つかなかった踏ん切りもこれでつくのですから不思議です。その日は遅くまでスマッシュブラザーズとマリオカートとをはしごして、翌日からはわたしのチャレンジがはじまりました。
まだ初日は改造前、ミッションはいまのわたしの実力を記録に残すこと。
机の上にはスタジオで使っている原画用紙がありましたし、鉛筆も消しゴムも原画のひとたちが使うものと同じものを揃えていました。ライトボックスもタップも羽箒も、スタンドライトまで揃えて買いました。
そのプロ仕様の机で描いてみる絵はまあまあうまく描けて、1年前のじぶんの絵とくらべるとずいぶんと進化が見られるように思えました。もちろんそれでもプロの絵には遥かに及ばないのですが、1年の差分を見せるというコンセプトに従えば、もう少し手を抜いたほうが良いのかもしれません。が、これがまた不思議なもので、本気で手を抜くとわざとらしいものにしかならないのでと、さらさらと肩の力を抜いて描くと、むしろさっきよりうまく描けたような気もしてくるのです。
それで調子に乗って5枚、6枚と描いて、PIXIVにあげて反応を見たのですが、まあ、散々でした。おそらく神崎ユミにハァハァするスレから来るのでしょう、「ハァハァ」とだけ書かれた荒らしのようなコメントと、相変わらず「よくこれでトップのアニメーターをクビにできましたね」という例のやつ。こういうのは気にしなくてもいいって、みんなから言われるけど、気にするよ、それは。わたしのことだけなら、まだいいんです。「クソ神崎グループの姫」とか、「日本のアニメを滅ぼす神崎グループの方ですか? お上手な絵ですね」とか、「こんどは何ジャケット詐欺?」とか、PIXIVに書き込まれたものでそれです。ハァハァするスレでなにを書かれてるかなんて想像もできませんでした。
そりゃあ、折れるでしょ。だれだって。
それにさあ。バナナトラップの松山社長に与えられたのも1年。わたしに与えられるのも1年。松山社長がハードルをクリアできなくて苦しんだように。わたしも苦しむんです。それでも、上達すればまだいいです。でも、何も変わらなかったら? 名村メソッド! と称して中途半端なもの、あるいはぜんぜんダメダメなものが公開されたら、批判はいまの比じゃない。
「4年とかになんないかな」
そこいらじゅう天才だらけの世界にいて、じぶんの絵がダメだってことは、嫌でもわかりますよ。まりりんから意思確認のMEETが来たとき、思わず弱音を吐いてしまいました。
まりりんの返事は、「名村英敏、作画崩壊でぐぐってみ」でした。「みんなどんなこと言われてこの世界でやってんのか、見てみるといいよ」って。そんなの、わたしが一番見たくないものが並んでるに決まってるし、それにこれからわたしに超絶技巧を叩き込む先生だよ? 失望したくないよ、こんなタイミングで。
「しょうがないよ。溶かした3億埋め合わせなきゃいけないんだから」
「でも、3億って、そっちの都合でしょう? なんでわたしが?」
これは言った瞬間、こちらのミスだってわかりました。そっちってどっちだっつー話で。でもなんか、わたしはそういう子なんです。
「はあ? 役員あんたでしょ? 受けたんでしょ、それを」
「受けざるを得なかったんです」
じぶんのミスがわかっていてもすぐに訂正できないのも、わたしの悪い癖でした。まりりんは、まあわかるよと理解を示してくれながら、今の状況を丁寧に教えてくれました。
レーザーコルベットが各国で作ろうとしてるアニメの学校は、把握しているだけで6カ国、その学校が力をつけると、やがてそこが輩出した人材が業界を席巻する。その源流にリーチをかけると考えれば、悪い話じゃない。学校は毎年確実な収益をあげるし、補助金もある、税制でも優遇される。それこそヤクザの大好物。大手スタジオと喧嘩するなど、変なリスクを取るよりずっといい。
「わたしじゃなくても、適任がいるんじゃないですか?」
わたしは、計画が現実味を帯びれば帯びるほど弱気になりました。
「そんなの探してるひまないよ」
「いるよ、そのへんに」
わたしなんか、だって。ぱーの手しか描けない。
「色がついてないひとが欲しいの。なまじ描けると手癖で描くから。あんたの絵はこう言っちゃわるいけど、どうにでもなる」
それもちょっと……。
「あんた、パイロットフィルム作り直させたでしょ? あの意地をじぶんに向けるだけだよ。ひとには言えても、自分には言えないの?」
パイロットフィルムの件は、わたしの弱点でもありました。結果として平野・一条を追い出したことにもなったわけですし、それを自分に向けろと言われると、本当にもうごもっともな話で。
「あのときはなにも知らなかったし、いまはあんなこと言わない」
そうやってだらだらと逃げ回っていると、まりりん師匠は深くため息を吐きました。
「あーそう。ダメか。神崎ユミはダメか」
「やっとわかっていただけましたか」
この言い方もひどかったと思います。少し冗談に出来ないかとも思ったんですが、まりりんはカチンと来たみたいでした。
「あんた、何人の人生めちゃくちゃにしたと思ってんの」
まりりんの言葉のなかに何%か含まれていた冗談の色が消えました。
「わたしは……でも……」
「まず藤島さん。いまどこでなにしてる? 知らないでしょ。松山さん。あんたが横尾に泣きついてなかったらああはなってない。バナナトラップの谷崎、小林、山下、このへんはなまえも知らないよね? 町田くん。過労で入院。いまはうつ病。家族もいるんだよ? どうやって暮らしてると思う?」
「そういうのぜんぶわたしのせいなん!?」
またわたしは、声を荒らげていました。だって、ぜんぶわたしのせいだって言われたのその時が初めてで、考えたこともなかったし、考えたくもなかったから。
「そうだよ。神崎弓がやったの。神崎グループの、会長の、孫の、ひきこもりのあんたが。ぜんぶやったって言ってんの」
まりりんは低い声で、脅すように言いました。それを聞くとわたしは堪えきれず――
「だいたいわたしがアニメーターになりたい言うたことあった!? おだてられて利用されただけやん! いまもそう! なんでそんな偉そうなん! あんた、神様なん!?」
じぶんが何を言っているかもわからないまま捲し立てました。
「ああ、はいはい。もういいです。3億は神崎龍次に支払わせます。それでおしまい」
弱音を吐きたいだけの話でした。そこに藤島さん、松山さん、そして祖父……。わたしのことを嫌ってるひと、恨んでるひとがいると示されるのは、辛かったです。
「なんでそんなこというの……おじいちゃん関係ないじゃん!」
「関係ない人間なんかいないよ」
いまだとわかるんです。松山さんがどんな苦労をしてきたか。彼の元を去ったスタッフが、どんな思いだったか。町田さん……当時子どもが生まれたばっかりだったと思います。その彼がうつ病で仕事に復帰できず、家族はどんな思いだったか。おそらく当時も、それを見ないようにしていただけで、わかっていたのだと思います。
「いいよもう。わたしが死ねばいいんだ。大阪来ないで、死んでたらよかったんだ」
なだめてほしかったんだと思います。あるいは切れて怒鳴られたかったのかもしれません。しょうがないよ。みんないろいろあるけど、がんばろう。きっとうまくいくよ。そんな言葉が返ってくるはずだって、ぼんやりと考えていました。でも――
「そうだね。死ねばいいよ。勝手に」
まりりんは純粋に呆れたんだと思います。その会談は突然終わり、ただわたしのなかに虚無だけが残りました。わたしがみんなの人生を壊した? わたしのせい? 胸の中にそればかり繰り返されて、目の前からさーっと色が消えて、体温が消えて、からだが重力を感じなくなって、わたしは絶叫しながら立ち上がり――ノートPCを床に叩きつけたことは覚えています。トレス台を持って、そのままコードを引き抜いたことも覚えています。でも明らかな記憶はそこまでです。いつもそうでした。母に羽交い締めにされてるとき、何をしていたか、どのくらいの時間が経ったかなんて、覚えていないんです。
気がつくとトレス台の割れたガラスでざっくりと内股を切って、血が流れ出していました。
鼓動に合わせて吹き出す血が、だらりと足を這って、畳に落ちて、服もPCも真っ赤に染まっていました。
「タカエさん……」
怖くなってタカエさんを呼びました。
「タカエさん! 血が止まらない! タカエさん!」
気がつくと、病室のベッドにいました。気がつくと……というのは少し変な言い方で、体が目覚める前に夢のなかではもう気がついていて、まぶたを開くと輸血の赤いバッグが揺れているのが目に止まりました。足は麻酔がかけられているのか、感触もなく、動かすこともできません。
輸血のバッグには「B」と書いてありました。
わたしは血液型占いを信じるタイプではありませんでしたが、ずっと同じA型の子とはウマがあうし、B型、AB型の子は少し読めないところがあると思っていました。神崎の家系はみなA型、もちろん父も母もA型でしたから、みな几帳面で、神経質で、その性格だからいまの神崎グループはあるのだろうと、大伯父が笑って話していたのを覚えています。
ドアを開ける音がして、ポットを抱えたタカエさんの姿が見えて、タカエさんはわたしの視線に気がついて、輸血のバッグを少し横に向けました。
「なんで隠すん?」
いろんな景色が思い出されました。
「隠すて、なにを?」
「とぼけんでええよ」
筆頭は黒井の漁協に行ったときの釣りの思い出です。
「うん、まあ、あんた、やんちゃやからな」
姉はハマチのなかでも特大のものを釣り上げて、腰を抜かしそうなくらい驚いて、母も側にいて、姉が引く竿に手を添えていました。
「おとうさんも知ってるの?」
「知ってるて、なにを?」
関門海峡の向こう、壇ノ浦には、同じように公園があるのが見えて、次はあそこに行こうと姉とふたり、父の手を両側から引いたのを覚えています。
「わたしの血液型」
別府のケーブルラクテンチ。あひるの競走を家族四人で応援しました。
「わたしが知ってるくらいやからな。まあ、知ってはるよ」
白石海岸の潮干狩り。アサリとマテ貝、それとカニ。
「みんな知ってたんだ」
父は姉のことも、わたしのことも、同じように愛していました。
「関係ないよ、そんなん。たかが血ぃやんか」
わたしがボロボロと泣き始めると、タカエさんも顔をしわくちゃにして泣き始めました。
第19章 ロールモデル
地元の苅田から、母の実家の宗像までは、日豊本線から鹿児島本線へ西小倉で乗り換えて東郷駅まで、徒歩の時間まで含めるとおおよそ1時間半がかかりました。3月なかば、何度か染め直した萌黄色の髪も、本来春の新緑の季節には似つかう色だとは思いましたが、このところの無精がたたって、頭頂の方はずいぶんと黒い髪が目立ち、土手の菜の花もようやくほころび始めるこの時期に、釣り川の支流の小さな流れにはまだいくつかの黄色い色が見え隠れするだけで、季節が追いつくころにはわたしの髪もずいぶんと黒くなっているのだろうと思い描きながら、その川に沿う県道を歩きました。
大阪へは行ったきりの旅でした。もういちどフェリーでこの地に戻れば、あらためてここがスタートになると、泉大津の埠頭からフェリーに乗っては瀬戸内の波の上で一晩を過ごし、門司の埠頭からいちど苅田へと出て、実家のあった土地へと戻りましたが、そこにはただ思い出が屯するほかは、柘植の生け垣も黒い瓦屋根も、敷地の脇に流れた小さな小川も埋められて、19になって見る苅田のまちは、とても小さく、ただ空ばかりが広がっていました。
父は職場にほど近い戸畑区に小さなマンションを買って、犬とふたりで暮らしていました。母の連絡先を聞くと、会いに行くのかと問われましたが、おそらく会ったとして、言葉をかわすことはないでしょう。ただ、宗像の町並みをもう一度胸に刻もうと、足の傷が治るのを待ってここに来て、父には、あと1年だけ仕送りをくださいと頼みました。その1年で、わたしはアニメーターになるのだと。
「遠慮せんでよかち」と、父は言いましたが、それは遠慮ではなく、また、1年で答えを出すという自信でもなく、じぶんに課した枷でした。
「お父さん」
そう呼ぶと涙がこぼれ始めましたが、父はその理由など知りません。
「どうした、どうした。なにがあった、急に」
わたしはただ、いままでの人生を、いままでの思い出を確かめるように、
「お父さん」
もう一度呼んで、何度かうなずいて涙を堪えました。
姉はもう婚約者と同棲をはじめていて、いまは福岡の天神のあたりに住んでいるのだと聞きました。そこに押しかけるほど野暮ではなく、ただ電話をかけて、「いま戸畑。これから宗像に行くんよ」と伝えました。
「ああ、うん。なんで泣いとーと?」
「なんでもない」
なんでもないんよ、お姉ちゃん。
東郷の駅前の小さな洋品店は、どこにあったかすらもう記憶も朧で、わたしは北口のロータリーの更に少し向こう、見知った小川を見つけては、思い出をひとつひとつ拾い集めて流れに沿って歩きました。母が勤めるスーパーには、ずっと昔、祖母と姉と、それと母の四人で行ったような記憶があります。
食品と日用雑貨と文具、惣菜とが雑多に売られる店の、いくつか並ぶひとの列のひとつで、母はレジを打っていました。家を出る前のいくつかの顔を思い出して、そのなかのどれが最後の母の姿だったかと、並べ替えてみましたが、記憶ももう定かには浮かばず、顔を上げて、気さくに客の声に応えて、主任を呼ぶ母の懐かしい声がわたしの耳にも届きました。
わたしはいちばん端のセルフレジに並んで、母の姿を見ながらヨーグルトのパックをひとつと、おにぎりをひとつ買いました。いまはどうですか、お母さん。あなたの娘ももう、昔ほどは手がかからないはずです。
大阪へは飛行機で戻りました。フェリーは旅になりますが、飛行機はその距離をゼロにします。そこからはもう、苅田と、大阪と、東京と、そのすべてがわたしの故郷になります。
心斎橋にあったバナナトラップの事務所は、少し東の玉出に場所を移し、少し古びた雑居ビルの三階で、隣のビルに向かい合う細い路地に窓を開けていました。動き出すときと止まるときとに少し揺れるエレベーターは、定員の5人で乗ると、停止するときにその衝撃でブザーが鳴るのだそうです。「ようあれ使うたな」といまは副社長になった松山さんは笑いましたが、わたしはそんな事情など知りませんし「そんなん、知らへんし」と笑って返しました。
わたしのせいで迷惑をかけましたと頭を下げると、「社長がおのれの判断で決めたことやし、おれの責任や。謝らんでええよ」と言ってくれました。
「金は怖いな。死ぬか思たわ」
ソファとテレビは以前のオフィスにあったものでしたが、ずいぶん狭く、部屋の雑多さは倍に濃縮されていました。
「じぶんらのゲーム作ることに、ずっと憧れとってん。金さえあったら無敵や思たら、ぜんっぜん。チームもバラバラなってもうたけど、幸いなのは喧嘩別れやないちゅうとこやな。谷崎くんも、山下さんも、小林くんも、また一緒にやろうゆうて出てったよって、またいつか、いつになるかわからんけどな、そんときは今度こそじぶんらのゲーム作る思うわ。まあ。まだ負けたとは思うてへん。世の中にゲームは何千もあるけど、じぶんのゲーム作りたい人間はその百倍おんねん。アニメもせやろ。せやから、お互い頑張らなあかんな」
例のごたごたの渦中、淳一爺は新しい会社を起こし、船体設計には代表権のない役員として名を残し、活動の場を東京新宿に構えた小さなオフィスに移しましたが、それは一般的な庶民の言葉で言えば「左遷」でした。暮らしぶりは相変わらずで、大川沿いのホテルのラウンジにケースいっぱいの書類を抱えて現れては、いまはいろんなIT企業と顔をつないで、そのIP、知的財産のマネージメントをしているのだと語ってくれました。その日も児童向けの絵本と、京都の小さな劇団の資料とを開いて、それぞれゲーム化の話と、地域活性化の映画祭の話と。
「淳一爺」
と、わたしはいまもその愛称をそのまま使っていました。
「名村英敏ってひと、知っとった?」
「ああ、知ってたよ。タツノコでおれの一年先輩で、おれは一条一と同期」
「なんで言うてくれへんの」
「ごめんごめん。向こうから聞くと思ってた」
淳一爺は目を細めて言いましたが、名前が変わっているのに、聞くもなにも。
「なまえ、高校のころ、知らん間に変わっとったっちゃ。弟も」
「はあ?」
まあ、相変わらずでした。
「なんでわたしの絵でいこうと思ったん?」と、聞くと、「風向きを変えたかった」と。
「デザインは文脈やきい、たとえば『老人ホームでアニメを作りました』って言った場合、老人たちが作ったことに意味があるんじゃないんよ。老人ホームでアニメを作るには、社会構造や、社会の理解そのものを変える必要があって、アニメは結果でしかないちや。そこに新進気鋭の作家が参加する――作家はどんどんそこに入ってかんといかん――世界を変えてかんといかん。だから、なんていうの? 決してそれは、奇をてらったものじゃないっちゃ。むしろそれをあたりまえにしていくことなんよ。それは、あたりまえに見える、そうじゃない何かを、いまの世のなかが抱えた……?」
そこまで話すと、不意に淳一爺は笑みをこぼし、
「まあ、そういうことちや」
と、締めました。
「名村さんはどんなひとでした?」と聞くと、
「映画好きの男。よくビデオ借りて一条の部屋に押しかけて観てて、『あいつは、なんでおれの部屋で観ていくんだ』って、一条はピキピキしながら笑ってた」
4月、いよいよわたしの改造計画がはじまるのですが、わたしには「最初の3ヵ月はじぶんの絵を描かない」という制限が科されました。それを聞いて、こりゃあわたしでないと無理だと思いましたね。だって、ふつうのひとだったらじぶんの絵があるし、メキメキ上達してるのに自分の絵を描かないなんてのはありませんもの。
わたしのPIXIVのコメント欄は相変わらず荒んでましたが、3月31日、ひとまずはそのときに描けるわたしの最高傑作を投稿、更新を停止しました。
で、まず何をやるかと言えばクリンナップ。なむりんから送られてくる絵を、とにかくクリンナップ。線を拾うだけ。アニメの動画にも線のクリンナップって作業はあるのですが、そこまでの精度は求めないので、「とにかく鉛筆に慣れろ」「指先をコントロールしろ」と言われました。そこから? って感じですよね。こないだわたし、得意げにPIXIVにアップしたし、その直後に「これは好き」ってコメントがついたの見たし、なのに「鉛筆に慣れろ」ですよ。わたしいままで、鉛筆にも慣れてない状態で描いてたんだ。そう見られてたんだって。でもこれが1ヵ月もすると、はい、いままでのわたしは鉛筆に慣れてませんでしたw って感じで、なんかすごいことが始まったって予感が湧いてきましたね。
そしてそのクリンナップ作業から段階的に、模写のステップに移って、これも模写っていうかトレース台を使ってのそのまんまの書き写し。よくネットですごく叩かれてる奴。
これが本当に、1日100枚とかいう勢いで送られてくる。3ヵ月はじぶんの絵を描くなって言われたけど、正直、描いてるひまない。ありとあらゆる角度の絵が送られてくる。それも、なむりんがさらさらって描いたもの。まりりんの絵も混じってたけど、まりりんの方がやや線が柔らかい感じでした。ひとが走ってるポーズの、横から前から下からって、なんでこんな角度で描けんの? ってのが死ぬほど送られてきました。
正直この、書き写してるだけってのに疑問もあったんですけど、3ヵ月目に入ると、絵はどんどんラフになっていって、頭と手と足の位置にだけアタリがあって「走ってる」って書いてあって、「はあ?」って思いましたけど、ふつうに描けるの、わたしw なんだこれw って感じ。いつのまに描けるようになったんだw って。
こうなってくると楽しい楽しい。下から見たキックポーズ、あたりしか入ってなくて、「マント着用」って書いてあって、これも描けるのw いつの間にw リクエストはどんどん高度になってって「服の皺だけで描いて」とか「筋肉の筋だけで腕描いて」とか来るんだけど、ちゃんとわたしの手がそれをどう描けばいいか知ってて、たとえばもうこのころには、ベルトの先から描き始めて全身を描けるみたいな曲芸もできるようになってましたね。
そして3ヵ月目、じゃあ、じぶんの絵を描いてPIXIVに載せてみようかって言われて、でもそこまでトレースばっかりだったから、やっぱり戸惑うじゃない? 「なにを描くのがいいんだろう」ってスラックで聞いたら、なむりんが「例の漫画のヒロインとヒーロー」って、おう、それなら描ける気がする、と思ってたら、まりりんが「ベッドに横たわるヒロインの手を取って、背中に手を回して起こしてあげるヒーロー」ってw んなもん描けるかーい! と思ってたら、描けるのw なにこれって感じw
クリンナップまでしなくていいってなむりんが言うので、さらさらっと描いてPIXIVにあげたら、「本人じゃないっしょ」「ついにトレースアップしてきたw」ってコメントついてもう、ざわざわって鳥肌立ちましたね。
改造人間がまだテスト段階で「これを割ってみろ」って、博士からブロック塀を指さされて、「そんなもの、割れるわけが……」とか言って殴ったら粉々にくだけたときのような、じぶんでも戸惑うほどの変わりよう。
「どうやら最初のテストはクリアしたようだな」
「これが……本当にわたし……」
「そう、それがあなたの力よ」
って。
「でもまだ原画レベル。これからだよ」
って、ちょっと待って! わたし、原画レベル!? 3ヵ月で原画レベルってなに!?
そのあとの3ヵ月は主にレイアウトの訓練だったんだと思います。キャラだけにとどまらず、背景の線がはいり、たとえば下から煽ったような室内のレイアウトに、3人のキャラが配置されて、「ひとり足して」とか、ふたりで会話しているキャラがいて、「背景足して」とか。会話してるキャラはぱっと見で、少しカメラは俯瞰してて、体の傾きから、まあ、こんな感じかなってのが、それもいつの間にかわかるようになっていました。
次の3ヵ月はディティール、そして、動物。
次の3ヵ月は表情、ドラマ、感情。そして、ツールもデジタルに切り替えました。
3ヵ月ごとにPIXIVに絵をアップしたんですが、『神崎ユミにハァハァするスレ』も「マジで?」「何が起きてんの?」という反応が増えて、スレッドタイトルも『神崎ユミにマジでハァハァするスレ』に変わっていました。
そして1年。
じぶんで言うのもなんですが――じぶんでも実感なかったので言いますけど、いつの間にかわたしは、どんな角度から、どんなポーズでも、どんな感情でも描き分けられるスーパー絵師になっていました。
1年前は前髪の線から描き始めて、顔の輪郭を描いて、目と鼻のあたりを取って、それを消しゴムで何度も書き直しながら、という描き方でしたが、このときは爪先から描き始めて服の皺だけを描いて動きを表現することも、鉛筆を寝かしてシルエットから描き始めることもできるようになっていました。
そうやって描いた絵をPIXIVにあげると、もはやトレースだと言うものもなく、「ぼくのユミたんじゃない」と泣き出すわけのわからないものまで出てきて、ようやく、改造は終わったんだと実感しました。
ただ、鉛筆画を大急ぎで習得したため色塗りは苦手です。それを言うとなむりんもまりりんも、わたしたちも苦手だ! と、胸を張っていました。
「でも、有名になりすぎて、これからの生活が不安です」と漏らすと、「有名になったって思ってんの、じぶんだけだよ?」と、まりりん師匠。
「輪るピングドラムの監督のなまえ知ってる?」
「いや、タイトルはわかるけど……」
「幾原邦彦監督だけど、業界でもパッと名前出てこないひとばっかだと思うんだよ」
「まあ、そうですね」
「なのに、神崎弓の名前はパッと出てくると思う?」
まあ、そりゃそうか。
第20章 デュエット
祖母は1950年、戦後間もない小倉の町に生まれました。
北九州は九州随一の工業地帯で、終戦間際になると米軍から度重なる空爆を受け、門司、八幡、若松、戸畑と、壊滅的な打撃を受けましたが、不思議なことに小倉だけは空襲の被害もなく、古い町並みが残されていました。
なぜか。
それは、米軍が小倉に原爆の投下を予定し、その威力を明確にするために、小倉だけはもとの町並みを残すよう、空爆を避けていたからです。
1945年、昭和二十年八月九日、ファットマンと称される原爆を宿したB29爆撃機は第1目標を小倉に定め、テニアン島ノースフィールド飛行場を飛び立ちました。爆撃機は9時44分、小倉の攻撃始点に到達、ところが前日の八幡空襲の影響もあり、小倉上空は雲が多く、小倉上空で雲の切れ間を探して45分を費やしたのち、目標を長崎に変更、10時58分、原子爆弾、ファットマンを長崎の市街地に投下しました。
小倉ではよく知られた話です。祖母も戦後間もない小学生のころに学び、観光バス会社に勤めた20代のころになると、仕事でもプライベートでもよく長崎の町を訪れたのだそうです。
わたしと祖父と、それとタカエさんとで長崎を訪れたのは、祖母の他界から1年半、わたしの改造計画が終わった直後でした。机の引き出しには折りかけの鶴が大量に残されており、わたしと、祖父と、タカエさんとでそれを仕上げて、千羽鶴にして資料館を訪れました。
「いろいろ黙ってて、すまなんだな」
祖父が献花台ならぬ献鶴台のようなものに向かって、千羽鶴を手にして言うものですから、わたしはてっきり祖母へ向けた言葉だと思って聞いていたのですが、どうやらそれはわたしへと向けられた言葉でした。
「タカエはんは甥の連れ合いやから、わしとは血はつながっとらん。彩乃とわしも。夫婦やからな。当然や。そしてユミちゃん。ユミちゃんとわしも、ユミちゃんとタカエはんも、だーれも血はつながっとらんかった。それが高石の神崎家や。でもな。わしら4人、家族やったやんか。いまもそや。家族や」
祖父は涙をいっぱいにたたえて、その顔を見せたくなかったのでしょう。手にした千羽鶴に顔を向けたまま続けました。
「4人だけやない。名村くんもや。せやろ、彩乃。ちがうか」
祖父はなむりん師匠が鶴を折ったとき、この資料館のことを思い出したのだそうです。バスガイドだった祖母はよく小倉と長崎の話を聞かせ、新婚旅行もこの町をめぐり、そのときにもここを訪れて、小さな千羽鶴を捧げたのだと言います。
「家族っちゅうのはな、心の繋がりや。貧乏しても、怪我しても、ボケてなんもわからんようになっても、心だけは繋いでいく。せやから、ユミちゃんも、彩乃の気持ちをな、繋いでやってほしいねん」
ハンカチを取り出して、目に当てる祖父の背中をタカエさんがさすりました。
「見てみい、この鶴を。一羽一羽はちっぽけな鶴や。それをみんなで折ると、こないな大きなうねりになる。アニメもそうなんやろ? ひとりでそないぎょーさん描けへんよ。それをつないでいって、やっと形になる。ちがうか?」
「ええ、ええ、そうです。そうやろ、ユミちゃん」
タカエさんも泣いていました。
「わしは信じとるんや。彩乃が折った鶴が、ユミちゃんの絵ぇに繋がって、そうして世に出るんやと。そのためにはなんでもするで。それが家族や。せやろ、ユミちゃん、タカエはん」
「せやな。家族はそういうもんやな」
タカエさんの声ももう涙声で、何を言っているのか聞き取るのがせいいっぱいで、わたしの視界もすぐに涙に溺れ始め、そこに祖母が佇む姿も見えた気がしました。その祖母の姿に、
「せやろ、彩乃」
ぐちゃぐちゃの顔を上げて、祖父が声をかけました。
戦没者の名簿のなかにはきっと、祖母の両親、祖父の両親のかわりに命を落としたひとがいるのだと思います。そしてそのひとたちもきっと、家族なのだと思います。
天神のカフェで姉と待ち合わせたのは、武蔵野のスタジオの面接のあと、面接当日に内定は出ていましたが、まだアニメーターとして描いた絵は1枚もない微妙な時期でした。これからの仕事に不安がないわけではありません。わたしだったら余裕だろうみたいな気持ちもなく、でももしだめでも、わたしはいくらでも成長するし、いくらでも変わる。そんな確信があって、気持ちは穏やかでした。
姉の去年10月、博多のホテルでの結婚式は、飛行機でとんぼ返りで出ただけで、ろくに話もできませんでしたが、改造を終えたわたしには幾分時間の余裕もできて、少し早く待ち合わせのカフェに訪れたわたしのまえに、少し遅れて来た姉のお腹は、見てわかるくらいに大きくなっていました。
「あかんぼおるん?」
「うん。もう5ヵ月」
いまは3月。わたしが指折り数え始めると、「数えないの」と姉は顔を赤くしました。
「はしゃぎすぎやで、それ」
「そーゆーこと言わない」
そのときわたしはもう、往年の原田知世に似せて髪は短く、色も黒く戻し、姉はフウラだったころのわたしをあまり知りませんでしたから、スマホに残ったわたしの写真を見せました。
「なにこれ、コスプレ?」と、人差し指の曲げた関節で鼻のあたまを押さえて笑う姉の仕草をスケッチし、「これが、このころの普段着」と、和装風のワンピースも見せました。
「このへんに住んどるん?」
「ううん、もうちょっと西のほう。大濠公園の向こう」
「なまえ知ってるわ。大濠公園」
「お父さんお母さんには会った?」
「お父さんには会ったよ。もう来月から仕送りいらん言うた。お母さんにはこれから」
「もうアニメーターだっけ?」
「肩書は。でも、これからや」
「へぇ~、ユミの絵、見たいなぁ」
「ああ、うん。じゃあ、面接のとき見せたスケッチブックあるから」
「見たい!」
「厳密には、面接のときのとは別やな。あれはもう落書きで埋まったし、でも同じもの」
「いまあるの?」
「あるよ」
わたしは、かばんのなかからスケッチブックを取り出して、3日前に福田さん、杉山さんに見せたときのセリフを繰り返しました。
「これは、師匠がこれだけで勝負しろっていうんで、今回はこれだけ持ってきましたー。じゃじゃーん」
関西人にありがちな、芝居がかったセリフです。
「おお~。向こうはなんて言ったの?」
「おお。師匠、厳しいねぇ、って。いや~、ほんと、マジ。マジで緊張した~」
「まあ、うん。わかる」
「でー、おもむろにー、スケッチブックをー、開くとー、じゃじゃーん」
と、わたしが姉の目の前でスケッチブックを開くと、そこに現れたのは、真っ白で何もないページです。姉はきょとんとして言いました。
「実際に見せたのには何が描いてあったの?」
まあ、そういう反応になるよね。杉山さん福田さんもそんな感じ。わたしは真っ白いスケッチブックを指して答えました。
「これ。これがそう」
「これ?」
「なんでもリクエストしてください! いまここで描きます!」
姉は2秒ほど固まって、頭のなかで情報を整理している様子でした。直後。
「あんたそんなことしたの!?」
まわりの目も忘れて姉が立ち上がって、ちょっと引いたかな。小さくコクコクとうなずいてみせて、姉の興奮気味のセリフの続きを待ちました。
「すごいじゃん! 目の前で描いたの!?」
「うん。ブランコ漕いでる少女と、くつにゴミ入ってけんけんしてるOL? あと、ボール投げてるひと、足元からのショット」
「マジで!? いま描ける? 描けるの!?」
「うん。描けるよ。そのくらいなら」
「そのくらいって!」
「プロレス技とかリクエストされてたら爆死してた」
そう言いながら鉛筆を走らせるスケッチブックに、姉は釘付けになっていました。
「すごいわあなた、なにものなの? ポエみちゃんびっくり」
と、姉はじぶんのことをポエみちゃんと呼ぶ謎キャラだったのですが、二十代半ばにしてもそれは健在でした。
その日も宗像の、東郷駅近くのスーパーに行って、レジを打つ母の姿を眺めました。もうフウラのような髪でもないし、もしかしたら気づかれるかもしれないと、黒いマスクと淡いサングラスをかけて、母がレジを打つ列に並びました。
わたしの番が来ると、「スタンプカードはお持ちですか?」と、懐かしい声に尋ねられて、わたしが「いいえ、ありません」と答えたとき、母の動きが一瞬止まったように見えました。
本当は「ユミだよ。大きくなったでしょ」って伝えたかったけど、そんなことを言えば、母があのときのわたしのようにパニックになり、叫びだす可能性もないとは言えません。
だから胸のなかで、アニメーターになったよ。ユミは頑張ったよって、伝えました。
わたしの改造計画の1年を終えると、その資料をもとにして、なむりんとまりりん、レーザーコルベットが中心となった環太平洋アニメ学校ネットワーク化計画が進み、そのなかで『名村メソッド』も本になり、いくつかの国で出版されたとは聞きましたが、とくにセンセーションを起こすことはありませんでした。
聖蹟桜ヶ丘のスタジオを訴えるかの動きのあったレーザーコルベットも、まりりんの潜入捜査官のような働きで、内部からアニメーションの制作事情を吹き込まれ、いまはラオスとタイのアニメスタジオに資本参加し、地道にアニメの制作システムの一角を営むに至っています。
つまり、カンズ・シャール・バレーヌの3億の損失は補填されぬままでしたが、なむりんはレーザーコルベットの輸出関連企業のひとつの社長におさまり、年金に毛が生えた程度の報酬を得るようになりました。
まりりんによると、かなり危険な橋を渡っている会社だという話で、「不正が発覚したときに『すべてわたしの判断でやりました』と腹を切る仕事」なのだそうです。それが比喩なのか実際の話なのかはわかりません。5億10億の不正も、石を投げる相手を立たせておけばチャラにできる。人間とはそういう生き物なのだと言っていました。
そしてそれもまた、ヤクザなりのいたわりでした。
第21章 ゆみりんの成功
2032年6月。わたしの作監作品の試写会は、池袋のシネマコンプレックスで開かれました。なむりん、まりりん、それにアリア―わたしの姉と待ち合わせて会場に入りました。
舞台挨拶に立つのは監督と声優陣で、わたしは難を逃れた形にはなりましたが、せっかくなので黒くて深いスリットなど入ったイブニングドレスをレンタルして会場に入りました。いろんなものに慣れてしまったせいか、あるいは選んだドレスがまだ生温かったのか、それほどのエロさも感じなくなっていましたし、夜の賑やかな映画館のロビーにあっては、その出で立ちはふつうだったのかもしれません。
神崎ユミにハァハァするスレが残っていれば、またそこに動画など晒されたのでしょうが、わたしのやんちゃだった過去のことはすっかりネットの話題からは消えていました。
その後、一条一、平野豹馬両氏と顔を合わせることもあり、そのときは平謝りに頭を下げたのですが、ふたりとも「おれも同じだった」「それがアニメーターの登竜門」と謎の寛大さで許してくれました。わたしもまた、わたしのような新人を何人か目にしていましたし、この業界というのはそういう「能力者」を呼び込むものだと考えるようになりました。
姉はもうすぐ7歳になる息子を連れて、傍らには背広姿の夫がいました。全員分招待券は出せましたが、長い映画だと息子がまだグズるのでと、試写の間は夫とともに下のゲームセンターで過ごすのだと言っていました。
父親に手を引かれて、少年は姉に尋ねました。
「ポエみは?」
「ポエみはみんなと映画観るんだよ」
姉はじぶんの息子に、じぶんのことをポエみと呼ばせてました。姉にはどこか、ナチュラルでかなわないところがあったのですが、この日は格別に深い敗北感を味わいました。
姉の夫をなんと呼ぶのか知りませんが、その姉婿のひとは、「作品はいつか必ず見せてもらいます」と、息子の手を取って、エレベーターに乗って、わたしの甥に当たる小さな少年は視界にあるあいだずっと小さな手を振ってくれました。
まりりんもまた相変わらずでしたが、たださすがにもう年相応のところは見えるようになり、髪も随分白くなっていました。
「髪、ピンクにしてこようかと思ったけど、若作りのババァとか言われるんでやめた」
と、まりりんは笑って言いましたが、このころにはもう、わたしもあの日の出来事を笑って受け流せるようになっていました。じつをいうと、あのあともまりりんとは仕事のこと、プライベートのことで何度か会って、何度か切れてなじったこともあったんですけど、そのたびに「あんたにはそーゆー捌け口が必要なんだよ」と言って許してもらっていました。
そしてなむりん。ジーンズにトレーナー、ハンチング帽の出で立ちで現れた様子は、あの日梅田のプラザモータープールで初めて目にしたときのままでした。
「少し痩せましたね」と水を向けると、「こないだまで入院してたんで」と照れた笑いを見せました。
「入院!?」
「そう。こないだは十二指腸」
「こないだはというと?」
「あと、腎臓も悪い。なんかもう、ボロボロで。ぜんぶダメ」
「今日はだいじょうぶなん?」と、わたしが聞くと、「フラグ立てたね?」と、まりりん。
「燃え尽きたぜ……真っ白にな……」となむりん。
「地球か…何もかも、みな懐かしい……」とまりりん。
「元ネタわかんない、それいつの時代の、なに?」
ドリンクを買って席に座ると、やがて照明が落ちて、予告編もなく、配給、製作のロゴから上映が始まりました。原画で、ラッシュで、何度も見たカットでしたがなむりんが見ていると思うと緊張しました。でもほら、たとえばこのカット、その次のここだって、改造計画のなかで出されたポーズそのままなんです。あの1年で学んだものが、いまのわたしを支えているんです。あの1年で描いた絵は、何千枚というレベルではなかったと思います。
上映後、となりのなむりんの顔を伺うと、ぐったりと座席に体を沈め、
「感謝している さらばだ息子達……!!」
ワンピース、エドワード・ニューゲート、通称白ひげのセリフでした。
反対側のマリリンに目をやると、同様にぐったりと目を閉じて、
「止まるんじゃねぇぞ」
鉄血のオルフェンズ、オルガ・イツカのセリフでした。
わたしがふたりに手を合わせて拝むと、ポエみちゃんがめちゃくちゃ受けてました。
人生には成功があるのではなく、ただ、成功という幻想があるだけなのだと思います。
王様のように金銀財宝を溜め込むことが成功だと思ったことはありましたし、そこを目指してきたことがあったのも事実です。集めたのものが金銀財宝ではないにせよ、わたしがそのすぐそばにまで上り詰めているのも事実だと思います。いまさらそれを謙遜するつもりもありません。
だけどわたしがここに来るまでに、多くの犠牲を払ってきました。母の人生、父の人生、タカエさんもそうでしょうし、名村英敏師匠にもほかの輝かしい老後があったかもしれません。わたしの手に金銀財宝があるとすれば、彼らから集めたものです。
かつて名村師匠は言いました。
僕にはもう成功はない。多くのものを犠牲にしすぎた。そのなかで唯一成功があるとすればゆみりん――つまりわたしが――アニメーターとして成功することだけだ。
だとしたらわたしのこの成功はわたしのものではありません。
名村先生のものです。
わたしにはもう成功はありません。
わたしが真に成功したと言えるのは、わたしの手にあるこのバトンを、この物語を読んでいる、あなたが受け取ったときです。
あとがき
今回は『ひきこもりのユミがアニメーターになるまで』ご清覧いただきありがとうございました。
今作は『アニメーターの老後』の続編となるわけですが、『アニメーターの老後』は、冒頭でユミが言っている通り地味で、重くて、買うひとがいてもラストまで読むはずもないし、その続編が売れるはずもないという代物で、さすがにこれではと思い、別タイトルにしました。ユミは前作のラストで登場して、さあ、これからどうなる? という感じで終わったのですけど、書き終えたあとでどうしても救ってあげたくなってこの作品を書き始めました。そのため設定は前作からすべて引き継ぎ、ユミの自傷癖も、それを師である名村に送ったエピソードも前作から引き継いでおります。青木真理子が病んでいた時期があるというのもそうですね。これは現実でも……おおっと、この作品はフィクションでした。現実は関係ありませんね。
それで『アニメーターの老後』の反省を活かして(?)、今作は少しポップな雰囲気でと思って明るい表紙を用意したのですけど、中身はまた地味で文体も古く、内容も辛いものとなってしまいました。表紙だけ見るとラノベなのですが、詐欺のようにして売りたいわけではないので、長編である旨は表紙に記しました(※)。そして更に今回特別に、読者様が途中で挫けたりせぬよう、最初にハッピーエンドであることを示すくだりを持ってきました。アニメーション用語で言えば「アバン」にあたりますね。
ポップなわりに語り口は古風という、なぜこんな文体になったかと言えば、この作品のまえに書いたのが『第七文学』という作品で、これがタイトルの通り文学小説なのですが、その主人公が傾倒していたのがカズオ・イシグロ、ヒロインが好きだったのがクロード・シモン、ということになっておりまして、ではこのふたつを合わせたらどうなるだろう、みたいなことを考えながら書いているうちにここに落ち着いた感じです。
最近の文学作品では1行の文字数が短いのが基本で、重文複文が複雑にならないように配慮し、それを重ねてテンポよく書くのがセオリーのような部分がありますが、「詩」というものへのぼんやりとした憧れが、僕をそれに抗わせました。
ラノベの切れの良いテンポある文章は好きなのですが、いざ書いてみるとじぶんの狙いや目標は違うところにあるという意識が芽生え、いつもそのあらぬ方向へと猛進してしまいます。その、あらぬ方向、今回見据えていたテーマ、が、「重文複文を恐れない」でした。
僕の作品は人類が滅亡しがちで、そのなかで「はたして人生とは?」「人類とは?」「意識とは?」みたいなことを問うのが通常運転で、僕自身そういう大きなテーマこそ物語に必要なものだと考えてしまっている部分があって、この作品も(前作同様に)書き始めた当初は少し不安なところがありました。
しかしペンが進んでくると、この女子一人称、ユミの目から見た世界をユミの言葉で書く、というスタイルはことのほか楽しめました。女子一人称はこの作品に限らず、『浮遊大陸でもういちど』や『憧れの秋山さんに捧げる冒険』などほかにもあるのですが、だれかに語りかけるスタイルは今回が初でした。
『第七文学』で主人公に語らせた、ひとつの視点から見た世界の、限定的な体験が重なって初めて生み出される立体感――のようなものに気を配りながら書くことで、SF大作にはない、身の回りにありながら奥の深いテーマというものを表現できたように、こっそりと自負しています。
作品のテーマとは別に、表現のテーマをもって書いているときは楽しいもので、今回であれば前述の重文複文を恐れない女子一人称の長尺セリフだったのですが、それが作品のカラー、あるいは長所、あるいは短所にもなり、楽しい半面、不安もまた大きく胸の内を占めました。
後半はもう複数文体が入り乱れるのも気にせず、ねじれ文もものともせず、はたしてだれ視点のどの時制なのかも突破して、心の赴くままに書きました。
おかげで今作も例に漏れず、本人は楽しんで書いてはみたものの、また異形のものが出来てしまったという、勝手に書いては勝手に不安になるといういつもの道を通っているのですが、まあでもそれが文学というものでしょう、いろんなスタイルがあって然るべきなのだと、寛大な心を持って読んでいただけたらと思っています。
最後になりましたが、このたびはこうしてご縁がありましたこと、本当に感謝しております。願わくばこのご縁が長く続きますようにと、心よりお祈りいたしております。
※表紙は改定しました。この記述は以前の表紙のときのものです。